|
名前
|
国 |
生年月
|
役職
|
維新思想
|
最 期
|
明治維新後の職業
|
|
長州藩
|
|
| 村田 清風 |
長州 |
天明3年 |
家老 |
|
|
|
| 周布政之助 |
長州 |
文政6年 |
家老 |
|
切腹 |
|
| 福原 元僴 |
長州 |
文化12年 |
国家老 |
尊王攘夷派 |
自害 |
|
| 宍戸 真澂 |
長州 |
文化元年 |
重臣 |
勤皇思想 |
自決 |
|
| 長井 雅楽 |
長州 |
文政2年 |
家老 |
反尊攘夷派 |
切腹 |
|
| 吉田 松陰 |
長州 |
文政13年 |
|
松下村塾 |
斬首刑 |
|
| 福永 喜助 |
長州 |
生不詳 |
|
討幕派 |
|
|
| 椋梨 藤太 |
長州 |
文化2年 |
重臣 |
反尊攘夷派 |
処刑 |
|
| 益田 親施 |
長州 |
天保4年 |
家老 |
尊皇攘夷 |
切腹 |
|
| 国司 親相 |
長州 |
天保13年 |
家老 |
尊皇攘夷 |
切腹 |
|
| 杉山松助 |
長州 |
天保9年 |
|
尊皇攘夷 |
討ち死 |
|
| 入江 九一 |
長州 |
天保8年 |
|
尊皇攘夷 |
戦死 |
|
| 吉田 稔麿 |
長州 |
天保12年 |
|
尊皇攘夷 |
討ち死 |
|
| 久坂 玄瑞 |
長州 |
天保11年 |
|
尊王攘夷 |
討死自刀 |
|
| 高杉 晋作 |
長州 |
天保10年 |
|
尊王攘夷 |
病死 |
|
| 桂 小五郎 |
長州 |
天保4年 |
|
尊王攘夷 |
|
参与・参議 |
| 広沢 真臣 |
長州 |
天保4年 |
|
倒幕派 |
|
東征大総督府参謀・参議 |
| 伊藤 博文 |
長州 |
天保12年 |
|
尊王攘夷 |
|
初代総理大臣 |
| 山縣 有朋 |
長州 |
天保9年 |
|
尊皇攘夷派 |
|
第3・9代 総理大臣 |
| 井上 馨 |
長州 |
天保6年 |
|
討幕派 |
|
外務大臣・総理臨時代理、 |
| 大村益次郎 |
長州 |
文政8年 |
|
討幕派 |
|
陸軍兵省大輔(次官) |
| 三吉 慎蔵 |
長州 |
天保2年 |
|
討幕派 |
|
宮内省御用掛 |
| 来島又兵衛 |
長州 |
文化14年 |
駕籠奉行 討幕派 |
戦死 |
|
| 品川弥二郎 |
長州 |
天保14年 |
|
尊王攘夷 |
|
松方内閣の内務大臣 |
| 前原 一誠 |
長州 |
天保5年 |
|
尊王攘夷 |
|
萩の乱を起こし |
| 野村 靖 |
長州 |
天保13年 |
|
尊王攘夷 |
|
内務大臣・逓信大臣 |
| 乃美 織江 |
長州 |
文政5年 |
京都留守居役 |
|
山口藩大属・萩部支庁 |
| 根来 上総 |
長州 |
文化13年 |
家老 |
倒幕派 |
|
山口藩大参事 |
| 山田 顕義 |
長州 |
天保15年 |
|
倒幕派 |
|
陸軍中将・司法大臣 |
| 赤禰 武人 |
長州 |
天保9年 |
|
尊王攘夷 |
処刑 |
|
| 三好 重臣 |
長州 |
天保11年 |
|
倒幕派 |
|
陸軍中将・東京鎮台司令官 |
| 坪井九右衛門 |
長州 |
寛政12年 |
重臣 |
佐幕派 |
処刑 |
|
| 寺島忠三郎 |
長州 |
天保14年 |
|
尊王攘夷 |
討死自刀 |
|
| 益田 親施 |
長州 |
天保4年 |
家老 |
攘夷派 |
切腹 |
|
| 佐々木男也 |
長州 |
天保7年 |
|
尊王攘夷 |
|
山口藩国政方 |
| 来原 良蔵 |
長州 |
文政12年 |
|
攘夷派 |
自害 |
|
| 浦 元襄 |
長州 |
|
家老 |
尊皇攘夷 |
|
革新派を支援 |
| 吉川 経幹 |
長州 |
文政12年 |
|
倒幕派 |
|
|
| 乃木 希典 |
長州 |
嘉永2年 |
|
倒幕派 |
|
陸軍元帥大将 |
| 阿部宗兵衛 |
長州 |
天保2年 |
|
倒幕派 |
戦病死 |
|
| 松島 剛蔵 |
長州 |
文政8年 |
|
尊皇攘夷 |
処刑 |
|
| 有吉熊次郎 |
長州 |
天保13年 |
|
尊皇攘夷 |
討死自刀 |
|
| 飯田 俊徳 |
長州 |
弘化4年 |
|
倒幕派 |
|
鉄道庁部長 |
| 飯田 正伯 |
長州 |
文政8年 |
|
尊皇攘夷 |
牢中病死 |
|
| 生田 良佐 |
長州 |
天保8年 |
|
尊皇攘夷 |
病死 |
|
| 河瀬 真孝 |
長州 |
天保11年 |
|
倒幕派 |
|
司法大輔・枢密顧問官 |
| 井上 勝 |
長州 |
天保14年 |
|
倒幕派 |
|
鉄道庁長官 |
| 御堀 耕助 |
長州 |
天保12年 |
|
尊皇攘夷 |
病死 |
|
| 岡部富太郎 |
長州 |
天保11年 |
|
倒幕派 |
|
山口・大阪の各県に出仕 |
| 楫取 素彦 |
長州 |
文政12年 |
重臣 |
尊皇攘夷 |
|
貴族院議員・宮中顧問官 |
| 金子重之輔 |
長州 |
天保2年 |
|
尊皇攘夷 |
牢中病死 |
|
| 久保清太郎 |
長州 |
天保3年 |
|
尊皇攘夷 |
|
三重県)権令 |
| 駒井政五郎 |
長州 |
天保12年 |
|
松下村塾 |
戦死 |
|
| 白石正一郎 |
長州 |
文化9年 |
|
尊皇攘夷 |
|
赤間神宮の2代宮司 |
| 杉 民治 |
長州 |
|
|
松下村塾 |
|
松下村塾を再興 |
| 杉 孫七郎 |
長州 |
天保6年 |
|
倒幕派 |
|
宮内大輔 |
| 杉 常道 |
長州 |
文化元年 |
次番役 |
|
|
|
| 世良 修蔵 |
長州 |
|
|
奇兵隊 |
斬首 |
|
| 大楽源太郎 |
長州 |
天保3年 |
|
忠憤隊 |
斬首 |
|
| 高杉小忠太 |
長州 |
文化11年 |
直目付 |
|
|
権大参事 |
| 玉木文之進 |
長州 |
文化7年 |
証人役 |
松下村塾 |
|
萩の乱 |
| 時山 直八 |
長州 |
天保9年 |
|
松下村塾 |
戦死 |
|
| 所 郁太郎 |
長州 |
天保9年 |
|
倒幕派 |
病死 |
|
| 富永 有隣 |
長州 |
文政4年 |
|
松下村塾 |
|
国事犯石川島監獄 |
| 鳥尾小弥太 |
長州 |
弘化4年 |
|
奇兵隊 |
|
陸軍中将・貴族院議員 |
| 福田 侠平 |
長州 |
文政12年 |
|
奇兵隊 |
突然死 |
|
| 福原 信冬 |
長州 |
天保8年 |
|
倒幕派 |
討死自刀 |
|
| 堀 真五郎 |
長州 |
天保9年 |
|
尊皇攘夷 |
|
東京始審裁判所長 |
| 前田孫右衛門 |
長州 |
文政元年 |
直目付 |
尊皇攘夷 |
処刑 |
|
| 松浦 松洞 |
長州 |
天保8年 |
|
尊皇攘夷 |
切腹 |
|
| 三浦 梧楼 |
長州 |
弘化3年 |
|
奇兵隊 |
|
陸軍中将・熊本鎮台司令長官 |
| 毛利 登人 |
長州 |
文政4年 |
|
|
処刑 |
|
| 山尾 庸三 |
長州 |
天保8年 |
|
|
|
法制局の初代長官 |
| 宍戸 ? |
長州 |
文政12年 |
|
松下村塾 |
|
司法大輔・文部大輔 |
| 山田宇右衛門 |
長州 |
文化10年 |
郡奉行 |
尊皇攘夷 |
病死 |
|
| 山田 亦介 |
長州 |
文化5年 |
|
|
牢中病死 |
|
| 大和弥八郎 |
長州 |
天保6年 |
|
倒幕派 |
斬罪 |
|
| 渡辺内蔵太 |
長州 |
天保7年 |
|
倒幕派 |
斬罪 |
|
| 児玉源太郎 |
長州 |
嘉永5年 |
|
|
|
陸軍参謀総長 |
| 神代 直人 |
長州 |
生年不詳 |
|
大村益次郎を暗殺 |
|
| 寺内 正毅 |
長州 |
嘉永5年 |
|
御楯隊隊士 |
|
陸軍大臣・第18代内閣総理大臣 |
| 西野文太郎 |
長州 |
慶応元年 |
|
文部大臣森有礼殺害 |
|
| 玉井 喜作 |
長州 |
慶応2年 |
|
|
|
ジャーナリスト |
長州藩の幕末期の動向と事件
|
天保8年4月27日には、後に「そうせい侯」と呼ばれた毛利敬親が藩主に就くと、村田清風を登用した天保の
改革を行う。改革では相次ぐ外国船の来航や中国でのアヘン戦争などの情報で海防強化も行う一方、
藩庁公認の密貿易で巨万の富を得た。
村田の失脚後は坪井九右衛門、椋梨藤太、周布政之助などが改革を引き継ぐが、
坪井、椋梨と周布は対立し、藩内の特に下級士層に支持された周布政之助が安政の改革を主導する。
幕末になると長州藩は公武合体論や尊皇攘夷を拠り所にして、おもに京都で政局をリードする存在になる。
また藩士吉田松陰の私塾松下村塾で学んだ多くの藩士がさまざまな分野で活躍、これが倒幕運動に
つながってゆく。長州藩は攘夷も決行した。下関海峡と通る外国船を次々と砲撃した。
1863年(文久三年)5月と1864年(元治元年)7月に、英 仏 蘭 米の列強四国と下関戦争が起こった。
元治元年)の池田屋事件、禁門の変で打撃を受けた長州(山口)藩に対し、幕府は徳川慶勝を総督とした
第一次長州征伐軍を送った。長州(山口)藩では椋梨ら幕府恭順派が実権を握り、周布や
家老・益田親施ら主戦派は失脚して粛清され、藩主敬親父子は謹慎し、幕府へ降伏した。
恭順派の追手から逃れていた主戦派の藩士高杉晋作は、伊藤俊輔(博文)らと共に、民兵組織である力士隊と
遊撃隊を率いてクーデター(元治の内戦)を決行した。民兵組織最強の奇兵隊が呼応するなど、各所で勢力を
増やして萩城へ攻め上り、恭順派を倒した。再び主戦派が実権を握った長州藩は、
長州藩は、奇兵隊を中心とした諸隊を正規軍に抜擢し、幕府の第二次長州征伐軍と戦った。
第二次幕長戦争(四境戦争)に勝利する。長州藩に敗北した幕府の威信は急速に弱まった。
1866年(慶応2年)には、主戦派の長州藩重臣である福永喜助宅において土佐藩の坂本龍馬を仲介として
薩摩藩との政治的・軍事的な同盟である薩長同盟を結んだ。
薩長による討幕運動の推進によって、15代将軍徳川慶喜が大政奉還を行い、江戸幕府は崩壊した。
そして、王政復古が行われると、薩摩藩と共に長州藩は明治政府の中核となっていく。
甲子殉難十一烈士江戸幕府による第一次長州征伐に際し長州藩内の主導権を握った俗論党によって、
萩の野山獄で処刑された長州藩士11人を総称した名称。
宍戸真澂・山田亦介・前田孫右衛門・竹内正兵衛・毛利登人・松島剛蔵・中村九郎・佐久間左兵衛・大和弥八郎
・渡辺内蔵太・楢崎弥八郎
長州五傑
井上聞多(馨)、遠藤謹助、山尾庸三、伊藤俊輔(博文)、野村弥吉(井上勝)の5名の長州藩士を指す。
文久3年(1863年)には井上馨の薦めで海外渡航を決意、5月12日に井上馨・遠藤謹助・山尾庸三・
野村弥吉(後の井上勝)らと共に長州五傑の1人としてイギリスに渡航する。
松門四天王
久坂玄瑞、高杉晋作、吉田稔麿、入江 九一
下関戦争
幕末に長州藩と、イギリス・フランス・オランダ・アメリカの列強四国との間に起きた、文久3年(1863年)と同4年
(1864年)の前後二回にわたる攘夷思想に基づく武力衝突事件。歴史的には、1864年の戦闘を馬関戦争と呼ぶ
攘夷運動の中心となっていた長州藩は日本海と瀬戸内海を結ぶ海運の要衝である馬関海峡
(下関海峡)に砲台を整備し、藩兵および浪士隊からなる兵1000程、帆走軍艦2隻(丙辰丸、庚申丸)、
蒸気軍艦2隻(壬戌丸、癸亥丸に砲を搭載)を配備して海峡封鎖の態勢を取った
5月10日:アメリカ商船ペンブローク号を海岸砲台と庚申丸、癸亥丸が砲撃 ペンブローク号は周防灘へ逃走
5月23日:フランスの通報艦キャンシャン号を各砲台から砲撃するが応戦後損、傷しつつも翌日長崎に到着
5月26日:オランダ東洋艦隊所属のメデューサ号を砲台は構わず攻撃を開始し、癸亥丸が接近して砲戦となった
米仏軍艦による報復
6月1日:アメリカ軍艦ワイオミング号が庚申丸を撃沈し、癸亥丸を大破させた、米側の死者は6人、負傷者4人、
長州藩は死者8人・負傷者7人であった。
6月5日:フランス東洋艦隊のバンジャマン・ジョレス准将率いるセミラミス号とタンクレード号が報復攻撃の
ため海峡に入った。セミラミス号は砲35門の大型艦で前田、壇ノ浦の砲台に猛砲撃を加えて沈黙させ
陸戦隊を降ろして砲台を占拠した。フランス兵は民家を焼き払い、砲を破壊した。
イギリスに留学していた長州藩士伊藤俊輔と井上聞多は四国連合による下関攻撃が近いことを
知らされ、戦争を止めさせるべく急ぎ帰国の途についた。
イギリスの国力と機械技術が日本より遙かに優れた事を現地で知った二人は戦争をしても
絶対に勝てないことを実感していた。伊藤と井上は三カ月かかって6月10日に横浜に到着。
四国連合艦隊の攻撃
7月27日、28日にキューパー中将(英)を総司令官とする四国連合艦隊は横浜を出港した。艦隊は17隻で、
イギリス軍艦9隻、フランス軍艦3隻、オランダ軍艦4隻、アメリカ仮装軍艦1隻からなり、総員約5000の兵力であった。
下関を守る長州藩の兵力は奇兵隊(高杉は前年に解任されており総管は赤根武人)など2000人
砲約120門であり、禁門の変のため主力部隊を京都へ派遣していたこともあって弱体であった。
5日:艦隊は前田浜で砲撃支援の下で陸戦隊を降ろし、砲台を占拠して砲を破壊した。
6日:砲撃をしかけ陸戦隊を降ろし、砲台を占拠して砲を破壊するとともに、一部は下関市街を目指して
内陸部へ進軍して長州藩兵と交戦した。
7日:艦隊は彦島の砲台群を集中攻撃し、陸戦隊を上陸させ砲60門を鹵獲した。8日までに下関の長州藩の砲台は
ことごとく破壊された。陸戦でも長州藩兵は旧式銃や槍弓矢しか持たず、新式のライフル銃を持つ連合軍を
相手に敗退した。長州藩死者18人・負傷者29人、連合軍は死者12人・負傷者50人だった。
8月8日:戦闘で惨敗を喫した長州藩は講和使節の使者に高杉晋作を任じた。四国連合艦隊旗艦の
ユーライアラス号に乗り込んでキューパー司令官との談判に臨んだ。18日に下関海峡の外国船の通航の
自由、石炭・食物・水など外国船の必要品の売り渡し、賠償金300万ドルの支払いの5条件を受け入れて
講和が成立した。ただし、賠償金については長州藩ではなく幕府に請求することになった。
 |
| 薩摩藩 |
|
| 名 前 |
国 |
生年月
|
役職
|
維新思想
|
最期
|
明治維新後の職業
|
| 島津 斉彬 |
薩摩 |
文化6年 |
藩主 |
|
病死 |
|
| 島津 久光 |
薩摩 |
文化14年 |
|
公武合体 |
|
左大臣 |
| 島津 忠義 |
薩摩 |
天保11年 |
12代藩主 |
版籍奉還 |
|
|
| 島津 久治 |
薩摩 |
天保12年 |
家老 |
|
|
自殺 |
| 調所 広郷 |
薩摩 |
安永5年 |
家老格 |
|
服毒自殺 |
|
| 小松 清廉 |
薩摩 |
天保6年 |
家老 |
倒幕派 |
|
|
| 西郷 隆盛 |
薩摩 |
文政10年 |
|
倒幕派 |
|
陸軍大将・参事・ 西南戦争首謀者 |
| 大久保利通 |
薩摩 |
文政13年 |
|
倒幕派 |
|
参議・初代内務卿 |
| 伊地知貞馨 |
薩摩 |
文政9年 |
|
誠忠組 |
|
内務省に出仕 |
| 吉井 友実 |
薩摩 |
文政11年 |
大目付役 |
尊皇討幕 |
|
宮内大丞・宮内次官 |
| 伊地知正治 |
薩摩 |
文政11年 |
|
精忠組 |
|
参議を兼任し、修史館総裁 |
| 黒田 清隆 |
薩摩 |
天保11年 |
|
倒幕派 |
|
第2代内閣総理大臣 |
| 五代 友厚 |
薩摩 |
天保6年 |
|
倒幕派 |
|
大阪商船、阪堺鉄道 |
| 篠原 国幹 |
薩摩 |
天保7年 |
|
倒幕派 |
|
近衛長官・西南戦争 |
| 桐野 利秋 |
薩摩 |
天保9年 |
|
倒幕派 |
|
陸軍少将・西南戦争 |
| 村田 新八 |
薩摩 |
天保7年 |
|
倒幕派 |
|
宮内大丞・西南戦争 |
| 海江田信義 |
薩摩 |
天保3年 |
|
精忠組 |
|
元老院議官・貴族院議員 |
| 有村 雄助 |
薩摩 |
天保6年 |
|
倒幕派 |
藩命自刀 |
|
| 有村次左衛門 |
薩摩 |
天保9年 |
|
尊皇討幕 |
自決 |
|
| 高崎 正風 |
薩摩 |
天保7年 |
留守居役 |
武力討幕反対 |
|
枢密顧問官 |
| 奈良原 繁 |
薩摩 |
天保5年 |
|
討幕反対 |
|
沖縄県知事 |
| 森 有礼 |
薩摩 |
弘化4年 |
|
|
|
初代文部大臣 |
| 西郷 従道 |
薩摩 |
天保14年 |
|
精忠組 |
|
海軍元帥大将 |
| 大山 巌 |
薩摩 |
天保13年 |
|
倒幕参加 |
|
陸軍元帥大将 |
| 川村 純義 |
薩摩 |
天保7年 |
|
倒幕参加 |
|
死後海軍大将 |
| 野津 道貫 |
薩摩 |
天保12年 |
|
倒幕参加 |
|
陸軍元帥大将 |
| 野津 鎮雄 |
薩摩 |
天保9年 |
|
倒幕参加 |
|
陸軍中将 |
| 有馬 藤太 |
薩摩 |
天保8年 |
|
倒幕参加 |
|
西南戦争に参戦予定が捕まる |
| 川路 利良 |
薩摩 |
天保5年 |
|
倒幕参加 |
|
初代大警視 |
| 大山 綱良 |
薩摩 |
文政8年 |
|
倒幕参加 |
|
西南戦争 |
| 益満休之助 |
薩摩 |
天保12年 |
|
尊王攘夷派 |
戦死 |
|
| 大迫 貞清 |
薩摩 |
文政8年 |
|
倒幕参加 |
|
警視総監・鹿児島県知事 |
| 種田 政明 |
薩摩 |
天保8年 |
|
倒幕参加 |
|
熊本鎮台司令長官 |
| 池上四郎 |
薩摩 |
天保13年 |
|
倒幕参加 |
|
西南戦争 |
| 永山弥一郎 |
薩摩 |
天保9年 |
|
倒幕参加 |
|
西南戦争 |
| 伊東 祐亨 |
薩摩 |
天保14年 |
|
倒幕参加 |
|
海軍元帥大将 |
| 伊牟田尚平 |
薩摩 |
天保3年 |
|
尊王攘夷派 |
切腹 |
|
| 有馬新七 |
薩摩 |
文政8年 |
|
尊皇攘夷 |
藩士殺害 |
|
| 田中新兵衛 |
薩摩 |
天保3年 |
|
尊皇攘夷 |
自刀死 |
|
| 税所 篤 |
薩摩 |
文政10年 |
|
倒幕参加 |
|
初代奈良県知事 |
| 樺山三円 |
薩摩 |
|
|
精忠組 |
|
|
| 中井 弘 |
薩摩 |
天保9年 |
|
|
|
京都府知事 |
| 赤塚 源六 |
薩摩 |
天保5年 |
|
精忠組 |
|
海軍大佐 |
| 三島 通庸 |
薩摩 |
天保6年 |
人馬奉行 |
倒幕参加 |
|
警視総監 |
| 橋口 伝蔵 |
薩摩 |
天保2年 |
|
寺田屋事件 |
斬殺 |
|
| 奈良原 繁 |
薩摩 |
天保5年 |
|
倒幕参加 |
|
沖縄県知事 |
| 柴山愛次郎 |
薩摩 |
天保7年 |
|
寺田屋事件 |
斬殺 |
|
| 森岡 昌純 |
薩摩 |
天保4年 |
|
|
|
日本郵船会社 |
| 松方 正義 |
薩摩 |
天保6年 |
|
|
|
第4・6代総理大臣 |
| 高島鞆之助 |
薩摩 |
天保15年 |
|
倒幕参加 |
|
陸軍大臣 |
| 仁礼 景範 |
薩摩 |
天保2年 |
|
|
|
第2次伊藤内閣の海軍大臣 |
| 薩摩藩の幕末期の動向と事件 |
嘉永4年)に第11代藩主となった島津斉彬の下で、洋式軍備や藩営工場の設立を推進し,(集成館事業)、養女の
篤姫を第13代将軍・徳川家定の正継室にするなど、幕末の雄として抬頭した。斉彬は松平慶永・伊達宗城・
山内豊信・徳川斉昭・徳川慶勝らと藩主就任以前から交流をもっていた。斉彬は彼らとともに幕政にも積極的に
口を挟み、老中・阿部正弘に幕政改革(安政の幕政改革)を訴えた。安政5年(1858年)に大老に就いた井伊直弼と
将軍継嗣問題で真っ向から対立した。斉彬の死後、藩主・島津忠義の実父にして斉彬の異母弟にあたる久光が
実権を握り、「国父」・「副城公」と呼ばれた。
公武合体派として雄藩連合構想の実現に向かって活動するが、薩英戦争を経て西郷隆盛ら倒幕派の下級武士へ
藩の主導権が移る。幕末には公武合体論や尊王攘夷を主張、その後長州藩と薩長同盟を結んで明治維新の
原動力となり、明治以降の長きにわたって日本政治を支配する薩摩閥を形成することとなる。
薩英戦争
文久3年7月2日(1863年8月15日) - 7月4日(8月17日))は、生麦事件の解決を迫るイギリス(グレートブリテン
及びアイルランド連合王国)と薩摩藩の間で戦われた鹿児島湾における戦闘である。
生麦事件
幕末の文久2年8月21日(1862年9月14日)に、武蔵国橘樹郡生麦村(現・神奈川県横浜市鶴見区生麦)
付近において、薩摩藩主島津茂久(忠義)の父・島津久光の行列に乱入した騎馬のイギリス人を、
供回りの藩士が殺傷(1名死亡、2名重傷)した事件である。
6月22日:ジョン・ニールは薩摩藩との直接交渉のため、7隻の艦隊と共に横浜を出港
6月27日:イギリス艦隊は鹿児島湾に到着し鹿児島城下の南約7kmの谷山郷沖に投錨した。
6月28日:イギリス艦隊はさらに前進し、鹿児島城下前之浜約1km沖に投錨した。
7月1日: ニール代理公使は薩摩藩の使者に対し、要求が受け入れられない場合は武力行使に出ることを通告
イギリス艦隊の盗賊行為と受け取った薩摩藩は7箇所の砲台(台場)に追討の令を出す
イギリス艦隊の艦砲射撃は敵対した台場だけでなく鹿児島城や城下町の民家などに対しても
7月4日:砲撃やロケット弾(火箭)で攻撃を加え、城下ではおりからの強風のため大規模な火災が発生した。
戦闘の結果
薩摩藩の砲台によるイギリス艦隊の損害は、大破1隻・中破2隻の他、死傷者は63人に及んだ。
一方、薩摩藩側の人的損害は什長の税所清太郎、他に7人が死亡、老臣の川上龍衛が負傷した
戦争の処理
10月5日 - 幕府と薩摩藩支藩佐土原藩の仲介により代理公使ニールと薩摩藩の重野安繹らが
横浜のイギリス大使館で講和。薩摩藩は2万5000ポンドに相当する6万300両を幕府から借用して
支払ったが、これを幕府に返さなかった。
幕末の四大人斬り
田中新兵衛/河上彦斎/岡田以蔵/中村半次郎(桐野利秋)
月照事件
月照は文化10年(1813年)- 安政5年11月16日(1858年12月20日)幕末期の尊皇攘夷派の僧侶。大坂の町医者の
長男として生まれた。京都の清水寺成就院に入る。そして天保6年(1835年)、成就院の住職になった。しかし
尊皇攘夷に傾倒して京都の公家と関係を持ち、徳川家定の将軍継嗣問題では一橋派に与したため、大老の
井伊直弼から危険人物と見なされた。西郷隆盛と親交があり、西郷が尊敬する
島津斉彬が急死したとき、殉死しようとする西郷に対し止めるように諭している。
安政5年(1858年)8月から始まった安政の大獄で追われる身となり、西郷と共に京都を脱出して西郷の故郷である
薩摩藩に逃れたが、藩では厄介者である月照の保護を拒否し、日向国送りを命じる。
これは、薩摩国と日向国の国境で月照を斬り捨てるというものであった。このため、月照も死を覚悟し、
西郷と共に錦江湾に入水した。月照はこれで亡くなったが、西郷は奇跡的に一命を取り留めている。享年46
辞世の歌 大君の ためにはなにか 惜しからむ 薩摩の瀬戸に 身は沈むとも

|
| 土佐藩 |
|
| 名 前 |
国 |
生年月
|
役 職
|
維新思想
|
最 期
|
明治維新後の職業
|
| 山内 容堂 |
土佐 |
文政10年 |
15代藩主 |
|
|
|
| 山内 豊範 |
土佐 |
|
16代藩主 |
|
|
|
| 池 内蔵太 |
土佐 |
天保12年 |
|
土佐勤王党 |
遭難死 |
|
| 石川潤次郎 |
土佐 |
天保7年 |
|
池田屋事件 |
殺害 |
|
| 石田 英吉 |
土佐 |
天保10年 |
|
奇兵隊 |
|
千葉県知事 |
| 乾 正厚 |
土佐 |
|
|
尊皇攘夷 |
倒幕参加 |
|
| 板垣 退助 |
土佐 |
天保8年 |
|
倒幕参加 |
|
内務大臣・自由党総理 |
| 岩崎弥太郎 |
土佐 |
天保5年 |
|
|
|
三菱商会設立 |
| 岡田 以蔵 |
土佐 |
天保9年 |
|
土佐勤王党 |
打ち首 |
|
| 岡本健三郎 |
土佐 |
天保13年 |
|
|
|
実業家 |
| 片岡 源馬 |
土佐 |
天保7年 |
|
土佐勤王党 |
|
貴族院勅選議員 |
| 神山 郡廉 |
土佐 |
文政12年 |
大目付 |
|
|
高等法院陪席裁判官 |
| 北添 佶摩 |
土佐 |
天保6年 |
|
池田屋事件 |
殺害 |
|
| 後藤象二郎 |
土佐 |
天保9年 |
幡多郡奉行 |
|
|
逓信大臣・農商務大臣 |
| 小南 五郎 |
土佐 |
文化9年 |
|
戊辰戦争参戦 |
|
高知藩権大参事 |
| 近藤長次郎 |
土佐 |
天保9年 |
|
亀山社中違反で切腹 |
|
| 斎藤 利行 |
土佐 |
文政5年 |
近習目付 |
|
|
元老院議官 |
| 坂本 権平 |
土佐 |
文化11年 |
|
|
|
|
| 坂本 龍馬 |
土佐 |
天保6年 |
|
討幕派 |
暗殺 |
|
| 佐佐木高行 |
土佐 |
文政13年 |
|
|
|
参議・工部卿 |
| 沢村惣之丞 |
土佐 |
天保14年 |
|
海援隊 |
割腹 |
|
| ジョン万次郎 |
土佐 |
文政10年 |
|
|
開成学校(現・東京大学)の英語教授 |
| 新宮馬之助 |
土佐 |
天保7年 |
|
|
|
|
| 菅野覚兵衛 |
土佐 |
天保13年 |
|
|
|
海軍少佐 |
| 武市 瑞山 |
土佐 |
文政12年 |
|
尊王攘夷 |
割腹 |
|
| 田中 光顕 |
土佐 |
天保14年 |
|
倒幕参加 |
|
陸軍少将・警視総監 |
| 谷 干城 |
土佐 |
天保8年 |
|
倒幕参加 |
|
初代農商務大臣 |
| 寺村 道成 |
土佐 |
天保5年 |
側用人 |
|
|
|
| 中岡慎太郎 |
土佐 |
天保9年 |
|
土佐勤皇党 |
暗殺 |
|
| 長岡 謙吉 |
土佐 |
天保5年 |
|
倒幕参加 |
|
三河県知事 |
| 中島 信行 |
土佐 |
弘化3年 |
|
土佐勤王党 |
|
初代衆議院議長 |
| 那須 信吾 |
土佐 |
文政12年 |
|
土佐勤王党 |
戦死 |
|
| 間崎哲馬 |
土佐 |
天保5年 |
|
土佐勤王党 |
切腹 |
|
| 平井収二郎 |
土佐 |
天保6年 |
|
土佐勤王党 |
切腹 |
|
| 土方 久元 |
土佐 |
天保4年 |
|
土佐勤王党 |
|
農商務大臣・宮内大臣 |
| 福岡 孝茂 |
土佐 |
文政10年 |
奉行 |
|
|
元老院議官、文部卿、参議、 |
| 福岡 孝弟 |
土佐 |
天保6年 |
|
|
|
|
| 本山 茂任 |
土佐 |
文政9年 |
大目付 |
倒幕参加 |
|
|
| 望月亀弥太 |
土佐 |
天保9年 |
|
池田屋事件 |
自死 |
|
| 安岡 直行 |
土佐 |
天保10年 |
|
天誅組 |
斬首 |
|
| 吉田 東洋 |
土佐 |
文化13年 |
大目付 |
反尊皇攘夷 |
暗殺 |
|
| 高見 弥市 |
土佐 |
天保2年 |
|
土佐勤王党 |
|
|
| 安岡 嘉助 |
土佐 |
天保7年 |
|
天誅組乱で |
処刑 |
|
| 吉村虎太郎 |
土佐 |
天保8年 |
|
土佐勤王党 |
戦死 |
|
 |
|
水戸藩
|
| 名 前 |
国 |
生年月
|
役 職
|
維新思想
|
最期
|
明治維新後の職業
|
| 徳川 斉昭 |
水戸 |
寛政12年 |
第9代藩主 |
攘夷論 |
享年61 |
|
| 徳川 慶篤 |
水戸 |
天保3年 |
第10代藩主 |
|
享年37 |
|
| 戸田忠太夫 |
水戸 |
文化元年 |
家老 |
安政江戸地震にて死 |
|
| 安島 信立 |
水戸 |
文化8年 |
家老 |
安政の大獄 |
切腹 |
|
| 藤田 東湖 |
水戸 |
文化3年 |
水戸学 |
|
享年50 |
|
| 会沢正志斎 |
水戸 |
天明2年 |
思想家 |
|
|
|
| 武田耕雲斎 |
水戸 |
元治2年 |
執政 |
天狗党 |
斬首 64 |
|
| 武田金次郎 |
水戸 |
嘉永元年 |
|
天狗党 |
|
|
| 藤田小四郎 |
水戸 |
天保13年 |
|
尊皇攘夷 |
処刑 24 |
|
| 里見四郎左衛門 |
水戸 |
文化12年 |
歩行頭 |
尊皇攘夷派 |
切腹 51 |
|
| 里見四郎左衛門 |
水戸 |
寛政6年 |
旗奉行 |
尊王の志士 |
切腹 71 |
|
| 市川 弘美 |
水戸 |
文化13年 |
重臣 |
門閥派 |
極刑 |
|
| 結城 朝道 |
水戸 |
文政元年 |
執政 |
|
死罪 39 |
|
| 田丸稲之衛門 |
水戸 |
文化2年 |
|
尊皇攘夷 |
斬刑 61 |
|
| 原 市之進 |
水戸 |
天保元年 |
慶喜の側用人 |
暗殺 |
|
| 大場一真斎 |
水戸 |
享和3年 |
家老 |
|
|
|
| 加倉井砂山 |
水戸 |
文化2年 |
教育者 |
|
|
|
| 香川 敬三 |
水戸 |
天保12年 |
|
勤皇志士 |
|
宮内少丞、宮内大丞 |
| 住谷 寅之介 |
水戸 |
文政元年 |
警衛指揮役 尊王攘夷志 |
斬殺 50 |
|
| 鵜飼吉左衛門 |
水戸 |
寛政10年 |
京都留守居役 尊王攘夷 |
死罪 62 |
|
| 高橋多一郎 |
水戸 |
文化11年 |
|
尊王攘夷 |
自刃 47 |
|
| 海後磋磯之介 |
水戸 |
文政11年 |
|
勤王志士 |
|
警視庁 |
| 関 鉄之介 |
水戸 |
文政7年 |
|
勤王志士 |
斬首 39 |
|
| 青山 延光 |
水戸 |
文化4年 |
教授頭取 |
|
|
|
| 豊田 天功 |
水戸 |
文化2年 |
彰考館総裁 攘夷 |
病没 60 |
|
| 豊田 香窓 |
水戸 |
天保4年 |
総裁代 |
|
暗殺 33 |
|
| 金子孫二郎 |
水戸 |
文化元年 |
郡奉行 |
尊王攘夷派 |
斬罪 58 |
|
| 本間 玄調 |
水戸 |
文化元年 |
水戸藩医 |
|
|
|
| 榊原新左衛門 |
水戸 |
天保5年 |
家老 |
尊皇派 |
切腹 32 |
|
|
福井藩
|
|
| 松平 春嶽 |
福井 |
文政11年 |
第16代藩主 |
|
|
| 松平 茂昭 |
福井 |
天保7年 |
第17代藩主攘夷(倒幕反対 |
|
| 由利 公正 |
福井 |
文政12年 |
側用人 |
新政府へ |
|
|
| 橋本 左内 |
福井 |
天保5年 |
藩医 |
安政の大獄で斬首26 |
|
| 中根 雪江 |
福井 |
文化4年 |
御用掛 |
|
|
明治新政府の参与 |
| 本多 釣月 |
福井 |
文化12年 |
家老 |
直廉の軍事総奉行 |
|
| 村田 氏寿 |
福井 |
文政4年 |
|
|
|
岐阜県令や内務大丞兼警保 |
|
大垣藩
|
|
| 戸田 氏正 |
大垣藩 |
文化10年 |
第9代藩主 |
尊皇攘夷 |
|
|
| 戸田 氏彬 |
大垣藩 |
天保2年 |
第10代藩主 |
|
病死 35 |
|
| 戸田 氏共 |
大垣藩 |
嘉永7年 |
第11代藩主 |
幕府側 |
|
|
| 小原 鉄心 |
大垣藩 |
文化14年 |
藩老 |
|
|
|
| 小原 適 |
大垣藩 |
天保13年 |
|
|
|
|
第11代藩主・戸田氏共は第2次長州征伐に参加し、慶応2年から藩政改革を断行している。
慶応4年(1868年)1月の鳥羽・伏見の戦いでは大垣軍と新政府軍が戦い、朝敵に指定される
しかし新政府に召されていた家臣の小原鉄心は直ちに大垣に帰国して先々代藩主である氏正とともに
氏共や、佐幕派を説得して尊王派に藩論を統一して謝罪、戊辰戦争では新政府軍に与して東山道軍の
先鋒を務めている。 |
|
熊本藩
|
|
| 細川 斉護 |
熊本藩 |
文化元年 |
第10代藩主 |
|
|
|
| 細川 韶邦 |
熊本藩 |
天保6年 |
第11代藩主 |
尊皇攘夷 |
|
熊本藩知事 |
| 長岡 是容 |
熊本藩 |
文化10年 |
家老 |
攘夷論 |
安政6年 |
|
| 細川 行真 |
熊本藩 |
天保13年 |
宇土藩の第11代 |
|
|
| 細川 護久 |
熊本藩 |
天保10年 |
|
新政府 |
|
|
| 長岡 護美 |
熊本藩 |
天保13年 |
|
|
|
参与、貴族院議員 |
| 細川 利永 |
熊本藩 |
文政12年 |
高瀬藩10代 |
|
|
| 元田 永孚 |
熊本藩 |
文政元年 |
高瀬町奉行 |
|
宮中顧問官 |
| 横井 小楠 |
熊本藩 |
文化6年 |
儒学者 |
|
|
参与 |
| 横井 太平 |
熊本藩 |
嘉永3年 |
|
|
|
|
| 岩男 三郎 |
熊本藩 |
嘉永4年 |
航海術 |
|
|
司法省、6県の知事 |
| 徳富 一敬 |
熊本藩 |
文政5年 |
儒学者 |
|
|
|
| 井上 平太 |
熊本藩 |
嘉永元年 |
|
武術家 |
|
熊本県警察 |
| 林 桜園 |
熊本藩 |
寛政10年 |
教育者 |
|
|
|
| 宮部 鼎蔵 |
熊本藩 |
文政3年 |
|
尊皇攘夷池田屋にて自刀 45 |
|
| 宮部 春蔵 |
熊本藩 |
天保10年 |
|
尊皇攘夷禁門の変にて長州藩として自害 26 |
| 河上 彦斎 |
熊本藩 |
天保5年 |
|
尊皇攘夷 |
|
大村益次郎暗殺事件にて |
| 松田重助 |
熊本藩 |
天保元年 |
|
尊皇攘夷池田屋にて殺害 35 |
|
| 高木元右衛門 |
熊本藩 |
天保4年 |
|
尊王攘夷禁門の変にて長州藩として戦死 32 |
| 轟 武兵衛 |
熊本藩 |
文化15年 |
|
尊皇攘夷 |
|
弾正大忠(権弁事) |
| 太田黒伴雄 |
熊本藩 |
天保5年 |
|
尊王攘夷 |
|
神風連の乱を起こし自刀 |
| 加屋 霽堅 |
熊本藩 |
天保7年 |
|
尊王攘夷 |
|
神風連の乱を起こし戦死 |
| 尾形俊太郎 |
熊本藩 |
天保10年 |
|
新撰組会津戦争で消息不明 |
| 岡田 摂蔵 |
熊本藩 |
生年不明 |
幕府海軍 |
|
|
海軍省の権秘書官 |
幕末には藩論が勤王党、時習館党、実学党の3派に分かれた。実学党の中心は横井小楠である。
彼は藩政改革に携わったが失脚。安政5年(1858年)福井藩主松平慶永の誘いにより政治顧問として
福井藩に移った。また、勤王党の中心人物宮部鼎蔵も元治元年(1864年)池田屋事件により死去。
これにより時習館党が主流となったが藩論は不統一のままだった。12代藩主細川 護久は鳥羽伏見の
戦いで砲火を掻い潜って旅装のまま御所へ参内しこれを護衛したというエピソードも伝わっている |
|
佐賀藩
|
肥前国 |
| 鍋島 直正 |
佐賀藩 |
文化11年 |
10代藩主 |
攘夷 |
|
|
| 大隈 重信 |
佐賀藩 |
天保9年 |
|
尊王派 |
|
参議兼大蔵卿、内閣総理大臣 |
| 江藤 新平 |
佐賀藩 |
天保5年 |
|
尊王派 |
|
参議、佐賀の乱で梟首の刑 |
| 副島 種臣 |
佐賀藩 |
文政11年 |
|
尊皇攘夷 |
|
枢密顧問官、内務大臣 |
| 大木 喬任 |
佐賀藩 |
天保3年 |
|
尊皇攘夷 |
|
民部卿、文部卿 |
| 佐野 常民 |
佐賀藩 |
文政5年 |
海軍予備伝習 |
|
農商務大臣 |
| 島 義勇 |
佐賀藩 |
文政5年 |
海軍軍監 |
|
佐賀の乱を起こす 斬罪梟首 |
| 鍋島 直大 |
佐賀藩 |
弘化3年 |
下総野鎮撫府 |
|
宮中顧問官、貴族院議員 |
第二次長州戦争では筑前まで出陣したが、実戦を体験しなかった。大政奉還、王政復古まで静観を続けた。
1867年には藩主直大が新政府から北陸道先鋒に任命されて、佐賀藩兵も戊辰戦争に参加するために東上、
江戸における上野戦争などで戦い、その結果、明治政府に多数の人物が登用された。
明治維新を推進させた人物を輩出した藩を指す薩長土肥に数えられ、副島種臣、江藤新平、大隈重信、
大木喬任、佐野常民らが活躍した。 |
|
紀州藩
|
和歌山国 |
| 徳川 茂承 |
和歌山 |
天保15年 |
第14代藩主 |
|
和歌山藩知事、貴族院議員 |
| 水野 忠央 |
和歌山 |
文化11年 |
付家老 |
|
52
|
|
| 水野 忠幹 |
和歌山 |
天保9年 |
付家老 |
|
|
|
| 三浦 安 |
和歌山 |
文政12年 |
|
尊皇攘夷 |
大蔵省官吏、元老院議官、貴族院議員 |
| 安藤 直裕 |
和歌山 |
文政4年 |
付家老 |
|
|
|
| 陸奥 宗光 |
和歌山 |
天保15年 |
海援隊 |
尊王攘夷 |
|
農商務大臣、外務大臣 |
長州戦争では第二次征長軍の先鋒総督に任命され、附家老の安藤直裕を先鋒総督名代とし、
内政においては御用取次に登用した津田出に藩政改革を行わせた。慶応4年、戊辰戦争が勃発した際、
茂承は病に倒れていたが、徳川御三家の一つである上、羽・伏見の戦いで敗走した幕府将兵の多くが
藩内に逃げ込んだため、新政府軍の討伐を受けかけた。しかし、茂承は病を押して釈明し、新政府に
叛く意志はないということを証明するため、藩兵1,500人を新政府軍に提供すると共に、軍資金15万両を
献上した上、勅命により京都警備の一翼を担った。このため、新政府は紀州藩の討伐を取りやめたという。 |
|
津和野藩
|
国 |
| 亀井 茲監 |
津和野 |
文政8年 |
第11代藩主 |
|
参与 |
| 岡 熊臣 |
津和野 |
天明3年 |
|
国学者 |
|
|
| 大国 隆正 |
津和野 |
寛政4年 |
|
国学者・神道家 |
|
| 福羽 美静 |
津和野 |
天保2年 |
|
国学者 |
|
元老院議官、貴族院議員 |
第2次長州征伐には消極的な立場をとり、幕府軍が撤退すると、幕府が目付として残していた
その後は次第に長州藩寄りとなる。 |
|
桑名藩
|
国 |
| 松平定敬 |
桑名藩 |
弘化3年 |
藩主 |
京都所司代 |
|
日光東照宮宮司 |
| 松平 定教 |
桑名藩 |
安政4年 |
|
|
|
外務省の書記官 |
| 酒井孫八郎 |
桑名藩 |
弘化2年 |
家老 |
|
|
|
| 山脇正勝 |
桑名藩 |
嘉永2年 |
|
新選組隊士 |
|
三菱に入社長崎造船所所長 |
| 立見 尚文 |
桑名藩 |
弘化2年 |
周旋役 |
|
日露戦争では陸軍中将として第8師団
旧幕府軍出身者ながら陸軍大将に昇進 |
| 森 常吉 |
桑名藩 |
文政9年 |
|
新選組隊士 |
切腹 44 |
|
| 高木 貞作 |
桑名藩 |
|
|
新選組隊士 |
|
第十五国立銀行 |
慶応4年の鳥羽・伏見の戦いで定敬が前将軍・徳川慶喜に従ったため、桑名藩は新政府と
敵対することとなるが、在国していた定教は家老ら家臣の擁立もあり定敬に従わず、1月23日には
新政府に降伏して蟄居を命じられた。1月28日には桑名城を無血開城し、、尾張藩の管轄下に
置かれることとなった。蝦夷地まで転戦した定敬を説得するために箱館まで赴き、東京(江戸)の
新政府に出頭させている。 |
|
彦根藩
|
国 |
| 井伊直弼 |
彦根藩 |
文化12年 |
第15代藩主 開国派 |
暗殺 44 |
|
| 井伊 直憲 |
彦根藩 |
嘉永元年 |
第16代藩主 |
|
アメリカおよびイギリスに遊学 |
| 長野 主膳 |
彦根藩 |
文化12年 |
家老 |
|
斬首 48 |
|
| 岡本 半介 |
彦根藩 |
文化8年 |
家老 |
尊皇攘夷 |
|
|
| 西川 吉輔 |
彦根藩 |
文化13年 |
国学者 |
尊王 |
|
生國魂神社宮司 |
| 三須宗太郎 |
彦根藩 |
安政2年 |
江戸湾防衛 |
|
|
海軍軍令部次長、海軍大将 |
慶応2年、第二次長州征討では高田藩兵とともに彦根藩兵が芸州口の先鋒となった慶応4年戊辰戦争では
前哨戦となる鳥羽・伏見の戦いで、谷鉄臣らの藩兵が最初から新政府軍に属して東寺や大津を固めた。
その後、東山道鎮撫総督に属し、近藤勇の捕縛に加わったが、小山の戦闘で大鳥圭介らの旧幕府軍に
撃破される。彦根藩兵はその後、白河口から会津に転戦する。
|
|
津 藩
|
国 |
| 藤堂 高猷 |
津 藩 |
文化10年 |
11代藩主 佐幕派 |
|
|
| 藤堂 高克 |
津 藩 |
文化13年 |
家老 |
|
|
|
| 藤堂 元施 |
津 藩 |
天保7年 |
家老 |
|
|
敢國神社の神官 |
| 藤堂 監物 |
津 藩 |
天保13年 |
|
|
自殺 29 |
|
慶応2年の第2次長州征伐では津藩軍3000人、幕末期、高猷は佐幕派で公武合体を推進していたが、
あまり幕政には関わらなかった。(1868年)の戊辰戦争の緒戦である鳥羽・伏見の戦いでは、当初は幕府軍に
与していたが、後に新政府軍に転じて新政府軍勝利の一因となった。さらに戊辰戦争、箱館戦争にも派兵した。 |
|
宇和島藩
|
国 |
| 伊達 宗紀 |
宇和島 |
寛政4年 |
7代藩主 |
開国 |
|
|
| 伊達 宗城 |
宇和島 |
文政元年 |
8代藩主 |
公武合体 |
|
民部卿兼大蔵卿 |
| 伊達 宗徳 |
宇和島 |
文政13年 |
9代藩主 |
|
|
|
| 吉見 左膳 |
宇和島 |
文化14年 |
家老 |
|
|
|
伊達 宗城は福井藩主・松平春嶽、土佐藩主・山内容堂、薩摩藩主・島津斉彬とも交流を持ち「四賢侯」と謳われた。
彼らは幕政積極的に口を挟み、老中首座・阿部正弘に幕政改革を訴えた。井伊直弼と将軍継嗣問題で
真っ向から対立した。安政の大獄で宗城は春嶽・斉昭らとともに隠居謹慎を命じられた。
王政復古の後は新政府の議定(閣僚)に名を連ねた。しかし明治元年(1868年)に戊辰戦争が始まると、
心情的に徳川氏・奥羽列藩同盟寄りであったので薩長の行動に抗議して、新政府参謀を辞任した。
9代藩主宗徳は新政府から罪を問われかけたが、兄(宗城)の仲裁により家督を甥で婿養子の宗敬に譲ることを
条件にして許された。
|
|
岡山藩
|
国 |
| 池田 慶政 |
岡山藩 |
文政6年 |
8代藩主 |
|
|
|
| 池田 茂政 |
岡山藩 |
天保10年 |
9代藩主 |
|
|
弾正大弼 |
| 伊木 忠澄 |
岡山藩 |
文政元年 |
家老 |
|
|
|
| 土倉 一善 |
岡山藩 |
文政2年 |
家老 |
|
|
|
| 牧野権六郎 |
岡山藩 |
文政2年 |
軍事御用掛 尊王攘夷 |
|
|
| 森下 景端 |
岡山藩 |
文政7年 |
郡奉行 |
尊攘派 |
|
大分県令 |
| 藤本鉄石 |
岡山藩 |
文化13年 |
脱藩 |
天誅組 |
戦死 48 |
|
幕末に9代藩主となった茂政は、水戸藩主徳川斉昭の九男で、鳥取藩池田慶徳や最後の将軍徳川慶喜の
弟であった。このためか勤皇佐幕折衷案の「尊王翼覇」の姿勢をとり続けた。しかし戊辰戦争にいたって
茂政は隠居し、代わって支藩鴨方藩主の池田政詮(岡山藩主となり章政と改める)が藩主となり、岡山藩は倒幕の
旗幟を鮮明にした。そうした神戸事件が起こり、その対応に苦慮した。
神戸事件
慶応4年1月3日(1868年1月27日)、戊辰戦争が開戦、間も無く、徳川方の尼崎藩(現・兵庫県)を牽制するため、
明治新政府は備前藩に摂津西宮(現・西宮市)の警備を命じた。
2,000人の兵を出立させ、このうち家老・日置帯刀率いる500人は大砲を伴って陸路を進んだ。
その時に神戸,]三宮神社前において備前藩兵が隊列を横切ったフランス人水兵らを負傷させ、銃撃戦に発展し、
居留地(現・旧居留地)予定地を検分中の欧米諸国公使らに水平射撃を加えた事件である。
これを見た第3砲兵隊長・滝善三郎正信が槍を持って制止に入った。しかし、言葉が通じず、
結局、2月2日(2月24日)、備前藩は諸外国側の要求を受け入れ、2月9日(3月2日)、永福寺において
列強外交官列席のもとで滝を切腹させるのと同時に備前藩部隊を率いた日置について謹慎を課すと
いうことで、一応の決着を見たのである。
|
|
広島藩
|
国 |
| 浅野 斉粛 |
広島藩 |
文化14年 |
9代藩主 |
|
52
|
|
| 浅野 長訓 |
広島藩 |
文化9年 |
11代藩主 |
|
|
|
| 浅野 長勲 |
広島藩 |
天保13年 |
12代藩主 |
王政復古 |
|
貴族院議員 |
| 浅野 忠敬 |
広島藩 |
享和元年 |
家老 |
|
61
|
|
| 辻 維岳 |
広島藩 |
文政6年 |
家老 |
王政復古 |
|
参与、麝香間祗候 |
| 熊谷 直彦 |
広島藩 |
文政11年 |
京都留守居役 |
|
日本画家 |
第2次長征が事実上幕府軍の敗退に終わると、広島藩は次第に長州藩の影響を受けるようになり、
慶応3年(1867年)には長州藩・薩摩藩と同盟を結ぶに至った。
第15代将軍・徳川慶喜に大政奉還を推進するなどしている。このため、広島藩は後の明治政府の
中枢から排除されることにはなったが、官軍に加わって戊辰戦争を戦った。
|
|
小倉藩
|
|
| 小笠原忠徴 |
小倉藩 |
文化5年 |
7代藩主 |
|
49
|
|
| 小笠原忠幹 |
小倉藩 |
文政10年 |
9代藩主 |
|
39
|
|
| 小笠原忠忱 |
小倉藩 |
文久2年 |
10代藩主 |
|
|
貴族院議員 |
| 小宮 民部 |
小倉藩 |
文政6年 |
家老 |
|
自刃 |
|
長州征討では、小倉藩は幕府側の九州側最先鋒として第一次、第二次ともに参加した。
慶応元年の第二次長州征討(四境戦争)では、小倉藩は総督・小笠原長行(同じ小笠原氏だが、忠真の兄忠脩の
子孫で唐津藩藩主・老中)の指揮下で小倉口の先鋒として参戦した。この戦闘は幕府・小倉藩に不利に展開し、
長州軍の領内侵攻により門司が制圧され、小笠原総督は事態を収拾することなく戦線を離脱し、
他の九州諸藩も撤兵。孤立した小倉藩は慶応2年8月1日(1866年9月9日)小倉城に火を放ち田川郡香春
(現・香春町)に撤退した。田川郡香春に政庁を設置した。慶応3年1月、長州藩と講和する。
|
|
福岡藩
|
|
| 黒田 長溥 |
福岡藩 |
文化8年 |
11代藩主 |
開国論 |
|
麝香間祗候 |
| 加藤 司書 |
福岡藩 |
文政13年 |
家老 |
勤皇派 |
切腹 36 |
|
| 月形 洗蔵 |
福岡藩 |
文政11年 |
|
尊王論 |
斬首 |
|
| 平野 国臣 |
福岡藩 |
文政11年 |
|
攘夷派 |
斬首 37 |
|
| 早川 養敬 |
福岡藩 |
天保3年 |
藩医 |
尊王攘夷 |
幽閉 |
奈良府判事、元老院大書記官 |
慶応元年(1865年)当初、一次長州征伐解兵に奔走した筑前勤王党を主とする勤王派が主力を占めるが、
勤王派は同時に三条実美ら五卿を太宰府に移しており、その事を藩主である黒田長溥が幕府に責められていた。
藩論が佐幕に傾き、勤王派の多くが逮捕され家老・加藤司書をはじめ7名が切腹、月形洗蔵ら14名が斬首、
野村望東尼ら15名が流刑となった乙丑の獄が起こり筑前勤王党は壊滅した。
慶応4年(1868年)勤王派の巻き返しがあり藩論は勤王に転向と目まぐるしく変転した。 |
|
宇都宮藩
|
|
| 戸田 忠恕 |
宇都宮 |
弘化4年 |
第6代藩主 新政府軍 |
22歳の若さで病死 |
| 戸田 忠至 |
宇都宮 |
文化6年 |
家老 |
|
京都裁判所副総督 |
| 県 勇記 |
宇都宮 |
文政6年 |
家老 |
戊辰戦争では新政府に味方する |
慶応4年(1868年)1月、戊辰戦争の折は新政府軍につくも、幕府軍により攻められ落城したが
宇都宮藩は宇都宮城を再び奪回。 |
|
佐倉藩
|
|
| 堀田 正睦 |
佐倉藩 |
文化7年 |
5代藩主 |
開国派 老中首座 その後桜田門外の変後蟄居 |
| 堀田 正倫 |
佐倉藩 |
嘉永4年 |
6代藩主 |
京都に軟禁状態 |
| 平野 縫殿 |
佐倉藩 |
文化11年 |
家老 |
新政府が大多喜藩に対して応じ、藩の危機を救っている 70 |
堀田 正睦は老中時に日米修好通商条約が調印された後、将軍継嗣問題や条約勅許問題などで正睦が失脚し
堀田正倫が藩主になると、慶応4年(1868年)1月の鳥羽・伏見の戦い後、正倫は上洛して新政府に対し、
徳川氏の存続と徳川慶喜追討令の取消を嘆願するが、かえって新政府に捕らえられて京都に拘禁されてしまった。
このため、佐倉藩は藩主不在という危機を迎えたが、縫殿は家老として冷静に対処し、新政府が大多喜藩に対して
出兵するように命令が下ると、佐幕派などの過激な意見を抑えた上で大多喜出兵に応じ、藩の危機を救っている。 |
|
忍 藩
|
|
| 松平 忠国 |
忍 藩 |
天保12年 |
3代藩主 |
幕府から安房・上総の沿岸警備を命じられ 54才 |
| 松平 忠誠 |
忍 藩 |
天保11年 |
4代藩主 |
京都警備 |
|
新政府に恭順 |
慶応4年(1868年)の鳥羽・伏見の戦い後、親藩だったということもあり藩内では旧幕府方に与して抗戦するか、
新政府軍に恭順するかで二分に分裂したが、忠国は病身を押して藩論を一つにまとめた上で、
新政府軍に恭順を誓った。
|
|
加賀藩
|
|
| 前田 斉泰 |
加賀藩 |
文化8年 |
11代藩主 |
尊皇派の弾圧 |
|
|
| 前田 慶寧 |
加賀藩 |
|
13代藩主 |
御所の警備を放棄、戊辰戦争では新政府軍側 |
| 本多 政均 |
加賀藩 |
天保9年 |
家老 |
尊攘派、金沢城中で暗殺される 32才 |
| 岡田 棣 |
加賀藩 |
天保6年 |
大参事 |
|
|
海外視察 |
| 高橋荘兵衛 |
加賀藩 |
文政9年 |
年寄席執事役・海防方兼帯 |
|
金沢第十二国立銀行の副頭取 |
| 島田 一郎 |
加賀藩 |
嘉永元年 |
御歩並 |
|
大久保利通を東京紀尾井坂で暗殺 斬首刑 |
禁門の変では嫡男の慶寧に兵を預けて御所を守らせていたが、敗れて退京してきたので、怒った斉泰は慶寧を
謹慎させ、家老の松平康正(大弐)と藩士の大野木仲三郎に切腹を命じている。
慶寧と親密な関係にあった尊皇攘夷派の武士たちを、城代家老の本多政均と協力して徹底的に弾圧した。
慶応2年4月4日、斉泰から家督を譲られたが、実権は依然として斉泰が握っていた。同年5月10日に参議に
任官する。戊辰戦争では新政府軍に味方している。
|
|
尾張藩
|
|
| 徳川 慶勝 |
尾張藩 |
文政7年 |
14代藩主 |
尊皇攘夷 |
隠居謹慎 |
|
| 徳川 義宜 |
尾張藩 |
安政5年 |
16代藩主 |
新政府軍に帰属 |
|
| 成瀬 正肥 |
尾張藩 |
天保6年 |
家老 |
参与会計事務局権判事 信濃鎮定へ |
| 田宮如雲 |
尾張藩 |
文化5年 |
家老 |
|
|
|
幕閣において老中・阿部正弘の死後に大老となり幕政を指揮していた井伊直弼が安政5年にアメリカ合衆国と
日米修好通商条約を調印したため、慶勝は水戸徳川家の徳川斉昭らとともに江戸城へ不時登城するなどして
直弼に抗議した。これが災いし、井伊が反対派に対する弾圧である安政の大獄を始めると隠居謹慎を
命じられる。幕府が第一次長州征討を行うこととなる。征討軍総督には初め紀州藩主・徳川茂承が
任じられたが慶勝に変更され、 慶勝は薩摩藩士・西郷吉之助を大参謀として出征した。この長州征伐では
長州藩が恭順したため、慶勝は寛大な 措置を取って京へ凱旋した。しかしその後、長州藩は再び勤王派が
主導権を握ったため、第二次長州征討が決定する。
慶勝は再征に反対し、茂徳の征長総督就任を拒否させ、上洛して御所警衛の任に就いた。
慶喜は軍艦で大坂から江戸へ逃亡した後、謹慎する。慶勝は新政府を代表して大坂城を受け取る。
そのうち尾張藩内で朝廷派と佐幕派の対立が激化したとの知らせを受け、1月20日(2月13日)に尾張へ戻って
佐幕派を弾圧する(青松葉事件)。
|
|
大村藩
|
肥前国 |
| 大村 純熈 |
大村藩 |
文政13年 |
12代藩主 |
長崎総奉行
尊王倒幕
|
|
| 渡辺 昇 |
大村藩 |
天保9年 |
藩士 |
大村勤皇党 |
元老院議官、会計検査院長 |
| 渡辺 清 |
大村藩
|
天保6年 |
藩士 |
東征軍監
奥羽追討
総督参謀
|
元老院議官、徴士民部官権判事、同権大丞
民部大丞、厳原県権知事、大蔵大丞などを
|
| 楠本 正隆 |
大村藩 |
天保9年 |
中老 |
尊攘倒幕運動 |
外務大丞、新潟県令、内務大丞
衆議院議員、衆議院議長
大久保利通の腹心
|
| 松林 飯山 |
大村藩 |
天保10年 |
藩士 |
勤王派 |
佐幕派による暗殺される |
幕末期は藩内で佐幕派と尊王派が対立し、文久3年に純熈が長崎総奉行に任じられると佐幕派が台頭した。
しかし尊王派はこれに対して改革派同盟を結成し、元治元年、純熈の長崎総奉行辞任により逆に
尊王派が台頭した。藩論が一気に尊王倒幕へと統一され、在郷家臣団を含む倒幕軍が結成された。
以後、薩摩藩・長州藩などと共に倒幕の中枢藩の一つとして活躍し、戊辰戦争では東北地方にまで出兵した。 |
|
津山藩
|
美作国 |
| 松平斉民 |
津山藩 |
文化14年 |
8代藩主 |
勤皇に統一 |
|
麝香間祗候 |
| 松平 慶倫 |
津山藩 |
文政10年 |
9代藩主 |
尊皇攘夷派の排斥 |
|
| 安藤 要人 |
津山藩 |
不詳 |
家老 |
征長に幕府側 |
|
恭順 |
| 箕作 秋坪 |
津山藩 |
文政8年 |
|
文久遣欧使節 |
|
三叉学舎の開設 |
| 箕作 麟祥 |
津山藩 |
弘化3年 |
|
|
|
|
| |
ジョン万次郎(中浜万次郎)について英学を学んだ。元治元年)には
外国奉行支配翻訳御用頭取となり、福澤諭吉・福地源一郎らとともに、
英文外交文書の翻訳に従事したフランスに留学司法大書記官、太政官大書記官、
元老院議官、司法次官、貴族院勅選議員、行政裁判所長官等を歴任。
和仏法律学校(現・法政大学)初代校長 |
| 箕作 阮甫 |
津山藩 |
寛政11年 |
|
幕府天文台翻訳員 |
|
| 箕作 佳吉 |
津山藩 |
安政4年 |
|
英国に留学。東京帝国大学理科大学で日本人として
最初の動物学の教授 |
|
|
|
|
| 津田 真道 |
津山藩 |
文政12年 |
|
オランダに留学 |
裁判官、元老院議官
初代衆議院副議長 |
| |
|
福山藩
|
備後国 |
| 阿部 正弘 |
福山 |
文政2年 |
7代藩主 |
江戸幕府の老中首座 |
|
| |
嘉永7年3月3日、日米和親条約を締結させることになり、約200年間続いた鎖国政策は終わりを告げる。 |
| 阿部 正方 |
福山 |
嘉永元年 |
9代藩主 |
|
|
|
| |
長州征伐(第一次)の先鋒を命じられ、藩兵約6,000人を率いて安芸国広島(広島市)に出征する。
福山藩は再び長州征伐(第二次)を命じられ、正方は藩兵を率いて出陣する。
石見国を進む途中に正方は病(脚気と思われる)を悪化させ、指揮を家老内藤角右衛門に委ねて
長州藩と交戦して敗北した。
戊辰戦争の前哨戦として長州藩軍(新政府軍)が領内に迫ろうとするとき、正方は病を悪化させ、
福山城内にて20歳で死去した。
|
| 阿部 正桓 |
福山 |
嘉永4年 |
10代藩主 |
|
|
|
| |
年明け早々から新政府(長州軍)への恭順と新政府軍(芸州軍)の福山入城に始まり、、伊予国松山への
出兵、播磨国西宮の警護、大阪府天保山砲台の警護など新政府軍への対応に追われたが、
正桓も藩主就任直後の明治元年(1868年)9月に箱館戦争への出兵を命じられた。 |
 |
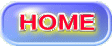 |
|