| 長州藩 |
|
毛利 敬親
慶親
 |
長州藩の第13代藩主
(安芸毛利家25代当主)
幕末の混乱期にあって、有能な家臣を登用
し、幕末の雄藩に引き揚げ、結果として
明治維新を作った人物として有名である。
|
明治2年(1869年)1月、敬親は薩摩藩・土佐藩・
肥前藩と連署して版籍奉還を奉請した。
6月には権大納言の位を得て、養嗣子の
毛利元徳と共に10万石を下賜されている。
明治4年3月、山口藩庁内殿で死去。享年53
|
村田 清風
むらたせいふう
長州藩家老 |
1783年5月26日(天明3年4月26日) - 1855年7月9日(安政2年5月26日)
長州藩士村田光賢(91石)の長男、長州藩 家老藩主毛利敬親のもとで天保の改革に
取り組んだ。1855年(安政2年)、清風を尊敬する家老・周布政之助の要請で再び藩政に
携わったが、清風の改革に対して反対派である椋梨藤太の台頭などもあって再びの改革に
は失敗。73歳で死去した。
|
周布 政之助
すふ まさのすけ
長州藩家老
|
文政6年3月23日(1823年5月3日) - 元治元年9月26日(1864年10月26日))
周布氏は益田氏の支流にあたり、長州藩士(大組219石)・周布吉左衛門の五男として生まれる。
政之助は天保の藩政改革を行った家老の村田清風の影響を受けており、
村田の政敵である坪井九右衛門派の椋梨との連立政権を意味していた。
元治元年(1864年)、高杉晋作とともに長州藩士の暴発を抑えようとしたが失敗、
その結果起こった禁門の変や第一次長州征伐に際しても事態の収拾に奔走したが、
次第に椋梨ら反対派に実権を奪われることとなった。同年9月、責任を感じて切腹した。享年42
|
福原元僴
ふくはらもとたけ
長州藩家老
|
文化12年8月28日(1815年9月30日) - 元治元年11月12日(1864年12月10日)
長州藩の永代家老。福原越後の名で知らる。長州藩支藩である周防徳山藩主・毛利広鎮の
六男。国家老として藩主・毛利慶親(斉元の子、のちの敬親)を補佐し、尊王攘夷運動を
推進する。禁門の変、並びに長州征伐の責任を取る形で、元治元年、岩国の龍護寺で
自害した。享年50。寡黙で果断、温厚でもあり、幕末初期の長州藩政を見事に運営した
名臣として、高く評価されている |
宍戸真澂
ししどますみ |
文化元年8月13日(1804年9月16日) - 元治元年11月12日(1864年12月10日))
長門萩生まれ。贈正四位。父は林隆州。養父は宍戸知之。子に宍戸小弥太。
萩藩の重臣として活躍し、萩藩大坂屋敷の留守居役を務めた
若き頃に伴信友や近藤芳樹に師事して、国学を熱心に学び、勤皇思想に感化され、
勤皇の志士として活動した。(利一門宍戸氏の一族)
来島又兵衛、久坂玄瑞らとも気脈を通じて活動したが、1864年の禁門の変に
連座して自害した。
|
長井雅楽
ながい うた
直目付 |
文政2年5月1日(1819年6月22日) - 文久3年2月6日(1863年3月24日)
主家毛利家と同じく大江広元の子孫であり、毛利家家臣団の中でも名門中の名門であった。
萩藩士大組士中老・長井次郎右衛門泰憲の長男として生まれた。
藩内の吉田松陰とその門下生が主流の尊皇攘夷派とは対立関係にあり、安政の大獄で松陰が
捕縛され、後の江戸護送に対しても強硬な対抗策を取らなかった。このため、後に松陰の弟子で
ある久坂玄瑞や前原一誠らによる暗殺を計画された。
文久2年(1862年)、幕府で公武合体を進めていた安藤や久世らが坂下門外の変で失脚すると
藩内で攘夷派が勢力を盛り返し、敬親により帰国謹慎を命じられた。同年6月に免職され、帰国。
翌、文久3年(1863年)、雅楽は長州藩の責任を全て取る形で切腹を命じられた。長井本人も
この措置には納得しておらず、また長井を支持する藩士はいまだ多くいたが、藩論が二分され、
内乱が起きることを憂い切腹を受け入れた。享年45
|
吉田 松陰
よしだしょういん
 |
文政13年8月4日(1830年9月20日) - 安政6年10月27日(1859年11月21日)
思想家、教育者、兵学者、地域研究家。明治維新の精神的指導者・理論者として知られる。
文政13年(1830年)8月4日、萩城下松本村で長州藩士・杉百合之助の次男として生まれる。
天保5年(1834年)、叔父で山鹿流兵学師範である吉田大助の養子となるが、天保6年に大助が
死亡したため、同じく叔父の玉木文之進が開いた松下村塾で指導を受けた。
西洋兵学を学ぶために1850年)に九州に遊学する。ついで、江戸に出て佐久間象山に師事する。
この松下村塾において松陰は久坂玄瑞、高杉晋作、伊藤博文、山縣有朋、吉田稔麿、入江九一、
前原一誠、品川弥二郎、山田顕義などの面々を教育していった
安政6年(1859年)10月27日、安政の大獄に連座し、江戸に檻送され、評定所で取り調べの結果、
斬首刑に処された。享年30
|
福永 喜助
ふくなが きすけ |
生没年不詳)は、幕末の長州藩重臣。通称は喜助。諱は喬久
福永氏は出雲国の戦国大名・尼子氏の末裔とされ、後に毛利氏に仕えて長州藩士となっていた
喜助は幕末長州藩の討幕派として活動していた。薩摩藩と長州藩との対立においては、
脱藩浪人の坂本龍馬や中岡慎太郎の斡旋もあり、自宅を会談場所として提供するなど、
薩長同盟の下地を作り上げた。
|
椋梨 藤太
むくなし とうた
反尊皇攘夷派 |
文化2年(1805年) - 慶応元年閏5月28日(1865年7月20日)
小早川氏庶流で、小早川隆景死後に毛利氏家臣となった椋梨氏の分家出身。
嘉永3年(1851年)に密用方から政務座役に抜擢され、長州藩の重臣になる。
幕末の長州藩において、中川宇右衛門とともに保守佐幕派(俗論派)の代表的人物であった。
長州藩の改革派(のち、正義派)の村田清風・周布政之助・桂小五郎らの陣営と藩内の
主導権争いを繰り広げた。嘉永6年(1853年)に政務座役を辞任させられ、周布政之助に実権を
奪われるが、安政2年に再び実権を掌握した。安政5年、熊毛郡代官に転じ、
万延元年までつとめた。元治元年7月(1864年禁門の変で暴走した正義派の壊滅後、
同月から始まる第一征長後では幕府への恭順を訴え、周布政之助を失脚させ、奇兵隊はじめ
諸隊へ解散令を出し、益田親施・福原元僴・国司親相三家老を切腹させて、幕府へ謝罪。そして
政敵である周布を自害へと追い込み、正義派の面々を大量に処刑していった。
この粛清に危機感を募らせた高杉晋作・伊藤俊輔らが元治元年12月に功山寺で決起
(功山寺挙兵)、潜伏していた桂小五郎が帰国して、長州の藩論を再び、武備恭順・尊王・
破約攘夷・倒幕路線に統一するに及び椋梨藤太は失脚、同年2月に岩国藩主・吉川経健を
頼って逃亡した。最終的には津和野藩領内で捕らえられた。そして5月、息子の中井栄次郎らと
ともに萩の野山獄において処刑された。
|
益田 親施
ますだ ちかのぶ
|
天保4年9月2日(1833年10月14日)- 元治元年11月11日(1864年12月9日)
長州藩士。益田家第33代当主。長州藩永代家老・須佐領主益田家14代。右衛門介の名で
知られる。1863年には上洛して孝明天皇に謁見し、真木保臣らと共に過激な尊皇攘夷に
走ろうとした。禁門の変に出陣して長州軍の指揮を執るが、薩摩藩・会津藩連合軍の前に
敗れ、長州に帰国した。第一次長州征伐で、幕府軍より益田に責任が問われて、切腹を
命じられ、死去した。
|
国司 親相
くにし ちかすけ
長州藩の家老
|
天保13年6月15日(1842年7月22日)- 元治元年11月12日(1864年12月10日))
寄組藩士・高洲元忠(たかす もとただ)の次男として生まれる。
6歳の頃、同じく寄組藩士5600石の国司迪徳(みちのり、通称は亀之助、将監)の養嗣子となり、
1847年(弘化4年)に家督を継いで大組頭となった。
文久3年5月、親相は久坂玄瑞らと共にアメリカ船ペングローブ号を砲撃し、下関海峡を封鎖、
禁門の変を引き起こした。しかし薩摩藩・会津藩連合軍の前に大敗、やがて第一次長州征伐が
始まると、大軍が長州に押し寄せてくる。そして西郷が長州藩に対して、責任を取る形で親相ら
三家老の切腹を要求したため、親相は徳山澄泉寺にて切腹して果てた。
享年23。 親相の家老職は、益田や福原の永代家老とは違い、実力で昇進した家老職であった。
|
杉山松助
すぎやま
まつすけ
|
天保9年(1838年) - 元治元年6月6日(1864年7月9日))
安政5年(1858年)の吉田松陰による間部詮勝天誅計画をはじめとした過激な尊皇攘夷運動に
参加。文久2年(1862年)には京都に赴き、久坂玄瑞らと共に活動を続ける。藩主より功績が
認められて藩士の身分を許された。元治元年6月5日、池田屋事件に遭遇。脱出して深手を
負いながらも長州藩邸に辿り着いて危険を知らせたが、重傷だったため助からず、
翌日死亡した。享年27。明治24年、従四位を贈られる。
|
入江 九一
いちえくいち |
天保8年4月5日(1837年5月9日) - 元治元年7月19日(1864年8月20日))
天保8年(1837年)、長州藩の足軽・入江嘉伝次・満智夫妻の長男として生まれた。
弟に野村靖(和作)、妹にすみ子(伊藤博文の最初の妻)がいる。
安政5年(1858年)になって入門した。松陰から高く評価され久坂玄瑞、高杉晋作、吉田稔麿と
並んで松門四天王の一人に数えられた。京都で尊皇攘夷のための活動を行なう一方で
高杉の奇兵隊創設にも協力し、奇兵隊の参謀となった。
元治元年(1864年)、禁門の変では久坂の率いる浪人隊の一員として天王山に布陣し、
敵の槍を受けて傷を負い、鷹司邸敷地内で自刃した。享年28。
|
吉田 稔麿
よしだ としまろ |
天保12年閏1月24日(1841年3月16日) - 元治元年6月5日(1864年7月8日))
萩藩松本村新道に軽卒といわれる十三組中間(大組中間)の吉田清内の
嫡子として生まれる。
久坂玄瑞、高杉晋作とともに松陰門下の三秀と称される
文久3年(1863年)6月、高杉晋作の創設した奇兵隊に参加
元治元年(1864年)6月5日の池田屋事件では、吉田も出席していたが、
新撰組が池田屋の周辺を取り囲んでいたため、奮闘の末に討ち死した。享年24
|
久坂 玄瑞
くさかげんない

|
天保11年(1840年)長門国萩平安古(ひやこ)本町(現・山口県萩市)に萩藩医・久坂良迪、富子の
三男・秀三郎として生まれる。松下村塾では高杉晋作と共に「村塾の双璧」、高杉・吉田稔麿・
入江九一と共に「松門四天王」と言う
安政6年(1859年)に安政の大獄によって松陰が刑死した後、文久元年(1861年)12月、玄瑞は、
松下村塾生を中心とした長州志士の結束を深めるため、一灯銭申合を創った
(参加者は桂小五郎、高杉晋作、伊藤俊輔、山縣有朋ら24名)。
この頃から玄瑞は、頻繁に各藩の志士たちと交流し始め、特に長州、水戸、薩摩、土佐の四藩に
よる尊攘派同盟の結成に向けて尽力し、尊王攘夷運動、反幕運動の中心人物となりつつあった
禁門の変(蛤御門の変)
蛤御門を攻めた来島又兵衛は会津藩隊と交戦したが、薩摩藩の援軍が加わると劣勢となり、
指揮官の来島が狙撃され負傷すると長州軍は総崩れとなった。
来島は自害。この時、狙撃を指揮していたのが西郷隆盛だった。来島隊の開戦に遅れて到着した
玄瑞・真木らの隊は、既に来島が戦死し、玄瑞は鷹司輔煕に朝廷への嘆願を要請するため、
鷹司邸に近い堺町御門を攻めた。
鷹司邸に入った玄瑞は鷹司輔煕に朝廷への参内に付随し、嘆願をさせて欲しいと要請したが、
輔煕はこれを拒絶、玄瑞を振り切り邸から脱出した。
最後に残った玄瑞は寺島忠三郎と共に鷹司邸内で自刃した。享年25
|
高杉 晋作
たかすぎ しんさく

|
天保10年8月20日(1839年9月27日)- 慶應3年4月14日(1867年5月17日))
江戸時代後期の長州藩士。幕末に長州藩の尊王攘夷の志士として活躍した。奇兵隊など
諸隊を創設し、長州藩を倒幕に方向付けた。安政4年(1857年)には吉田松陰が主宰して
いた松下村塾に入り、久坂玄瑞、吉田稔麿、入江九一とともに松下村塾四天王と呼ばれた
元治2年(1865年)1月11日付で晋作は高杉家を廃嫡されて「育(はぐくみ)」扱いとされ、
そして同年9月29日、藩命により谷潜蔵と改名する。
晋作は再度の長州征討に備えて、防衛態勢の強化を進める。慶応2年1月21日、
土佐藩の坂本龍馬・中岡慎太郎・土方久元を仲介として、晋作も桂小五郎・井上聞多・
伊藤俊輔たちと共に進めていた薩長盟約が京都薩摩藩邸で結ばれる。
晋作自身は、肺結核のため桜山で療養生活を余儀なくされ、慶応3年4月14日、
江戸幕府の終了を確信しながらも大政奉還を見ずしてこの世を去った(享年27)。
|
|
|
天保4年6月26日(1833年8月11日) - 明治10年(1877年)5月26日)
維新の十傑長門国萩城下呉服町に藩医・和田昌景の長男として生まれる。
和田家は毛利元就の七男・天野元政の血を引くという。弘化3年、長州藩の師範代で
ある内藤作兵衛(柳生新陰流)の道場に入門している。江戸三大道場の一つ、
練兵館(斎藤弥九郎)に入門し、新太郎の指南を受ける。免許皆伝を得て、入門1年で
塾頭となった。吉田松陰の教えを受け、藩内の尊王攘夷派(長州正義派)の中心
人物となり、留学希望・開国・・破約攘夷の勤皇志士、長州藩の外交担当者、
藩庁政務座の最高責任者として活躍する。明治期以後は別記参照
|
|
| |
広沢 真臣
ひろさわ
さねおみ 
|
維新の十傑
の一人 |
天保4年12月29日(1834年2月7日) - 明治4年1月9日(1871年2月27日))
維新の十傑長州藩士・柏村安利の四男として誕生する(幼名は季之進)。
藩校・明倫館に学び、嘉永6年(1853年)の黒船来航時には大森台場警衛のために出張。
安政6年(1859年)には藩の軍政改革に参画するなど、尊攘派として活躍した。
元治元年(1864年)、長州藩は禁門の変、下関戦争、第一次征長と厄続きであったため、
藩内の政権闘争で主戦派(主に正義派)が恭順派(主に俗論派)に敗れた結果、
波多野も投獄された正義派でなかったために処刑を免れた。慶応元年、高杉晋作や
伊藤春輔、山縣狂介ら正義派がクーデターによって藩の実権を掌握すると、中間派で
あった波多野が政務役として藩政に参加する藩命によって広沢藤右衛門と改名し、
更に翌月の5月6日には広沢兵助と改名した。慶応3年10月には大久保利通らと共に
討幕の密勅の降下にも尽力する
など倒幕活動を推進した。明治期以後
|
参与や海陸軍務掛、東征大総督府参謀を務め、民部大輔や参議の要職を務めた。
明治4年(1871年)1月9日、東京府麹町富士見町私邸での宴会後の深夜、刺客の
襲撃によって暗殺された。享年39。死後、正三位を贈位される。
|
伊藤博文
いとうひろふみ |
天保12年9月2日(1841年10月16日) - 明治42年(1909年)10月26日)
周防国熊毛郡束荷村(現 山口県光市束荷字野尻)の百姓・林十蔵(後に重蔵)の
長男として生まれる。父が長州藩の蔵元付中間・水井武兵衛の養子となり、武兵衛が
安政元年に周防佐波郡相畑村の足軽・伊藤弥右衛門の養子となって伊藤直右衛門と
改名したため、十蔵・博文父子も足軽となった。安政4年2月、江戸湾警備のため相模に
派遣されていた時、上司として赴任してきた来原良蔵と出会い、その紹介で吉田松陰の
松下村塾に入門する。幕末期の尊王攘夷・倒幕運動に参加。松蔭が安政の大獄で
斬首された際江戸詰めしていた伊藤は、師の遺骸を引き取ることなる。文久3年には馨の薦めで
海外渡航を決意、5月12日に馨・遠藤謹助・山尾庸三・野村弥吉(後の井上勝)らと共に
長州五傑の1人としてイギリスに渡航する。元治元年3月、米英仏蘭4国連合艦隊による
長州藩攻撃が近いことを知ると、馨と共に急ぎ帰国し6月10日に横浜上陸後長州藩へ戻り
戦争回避に奔走する。その後戦いでは活躍してない
明治期以後は別記参照 |
|
山縣 有朋
やまがtあととも
|
天保9年閏4月22日(1838年6月14日) - 大正11年(1922年)2月1日)
萩城下近郊の阿武郡川島村(現在の山口県萩市川島)に、長州藩の中間・山縣有稔(ありとし)の
長男として生まれる。足軽以下の中間身分ながら将来は槍術で身を立てようとして少年時代
から槍の稽古に励んでいた。
安政5年(1858年)7月、長州藩が京都へ諜報活動要員として派遣した6人のうちの1人として、
杉山松助・伊藤俊輔らとともに上京し、尊皇攘夷派の大物であった久坂玄瑞・梁川星巌
・梅田雲浜らに感化を受け9月に帰藩後に久坂の紹介で吉田松陰の松下村塾に
入塾したとされる。文久3年、高杉晋作の奇兵隊創設とともにこれに参加し、武芸や兵法の
素養を活かして頭角を現す。
戊辰戦争では北陸道鎮撫総督・会津征討総督の参謀となった。
明治期以後は別記参照
|
井上 馨
(多聞)
いのうえたもん
|
天保6年11月28日(1836年1月16日) - 大正4年(1915年)9月1日)
藩士、井上光亨(五郎三郎、大組・100石)の次男として、周防国湯田村(現山口市湯田温泉)に
生まれる。安政2年(1855年)に長州藩士志道氏(大組・250石)の養嗣子となるが、後に
密航を機に井上家に復籍藩主毛利敬親の江戸参勤に従い下向、江戸で伊藤博文と出会い、
岩屋玄蔵や江川英龍、斎藤弥九郎に師事して蘭学を学んだ。
文久3年、執政・周布政之助を通じて洋行を藩に嘆願、伊藤・山尾庸三・井上勝・遠藤謹助と共に
長州五傑の1人としてイギリスへ密航するが、留学中に国力の違いを目の当たりにして
開国論に転じ、翌元治元年(1864年)の下関戦争では伊藤と共に急遽帰国して
和平交渉に尽力した。
第一次長州征伐では武備恭順を主張したために9月に俗論党(椋梨藤太を参照)に襲われ
(袖解橋の変)、瀕死の重傷を負った。
慶応3年の王政復古後は新政府から参与兼外国事務掛に任じられ九州鎮撫総督沢宣嘉の
参謀となり、長崎へ赴任。浦上四番崩れに関わった後、翌明治元年(1868年)6月に長崎府判事に
就任し長崎製鉄所御用掛となり、銃の製作事業や鉄橋建設事業に従事した。
明治2年から3年(1869年 - 1870年)にかけて発生した長州の奇兵隊脱隊騒動を鎮圧した。
明治期以後は別記参照
|
大村 益次郎
村田蔵六
 |
文政8年5月3日(1824年5月30日) - 明治2年11月5日(1869年12月7日) 維新の十傑の一人
周防国吉敷郡鋳銭司(すぜんじ)村字大村(現・山口県山口市鋳銭司)に村医の村田孝益と
妻うめの長男として生まれる。天保13年(1842年)、防府で、シーボルトの弟子の梅田幽斎に
医学や蘭学を学び、翌年4月梅田の勧めで豊後国日田に向かい、4月7日広瀬淡窓の
私塾咸宜園に入る。
文久3年(1863年)10月、萩へ帰国する。24日、手当防御事務用掛に任命。
長州藩ではその風貌から「火吹き達磨」のあだ名を付けられた。このあだ名は周布政之助が
付けたとも、高杉晋作が付けたとも言われている。
明治2年(1869年)6月2日、戊辰戦争での功績により永世禄1500石を賜り、木戸孝允(桂小五郎)、
大久保利通と並び、新政府の幹部となった。
大村は諸藩の廃止、廃刀令の実施、徴兵令の制定、鎮台の設置、兵学校設置による職業軍人の
育成など、後に実施される日本軍建設の青写真を描いていた。
明治2年9月3日、京へ帰る。翌4日夕刻、大村は京都三条木屋町上ルの旅館で、
元長州藩士の団伸二郎、同じく神代直人ら8人の刺客に襲われる。静間と安達は死亡、
大村は重傷を負った。11月1日に敗血症による高熱を発して容態が悪化し、5日の夜に死去した。
享年46。
|
三吉 慎蔵
みよししんぞう
 |
天保2年10月11日(1831年11月14日) - 明治34年(1901年)2月16日)
長府藩の今枝流剣術師範・小坂土佐九郎の次男として生まれる。
田辺惣左衛門の養子となり、藩校敬業館に入学。天保10年(1839年)、諸武芸師範に入門。
嘉永2年(1849年)、長州藩校明倫館に入学。宝蔵院流槍術に長じ、安政2年(1855年)には
長州藩師範・小幡源右衛門より免許皆伝を受ける。
安政4年、長府藩士・三吉十蔵の養子となり、藩主・毛利元周の近習扈従役として江戸に
随従している。文久3年(1863年)、下関の外国船砲撃事件により大砲鋳造掛締方・
精兵隊諸事肝煎に就任。
慶応2年、長府藩士・印藤肇の仲介で坂本龍馬の知遇を得る。長府藩より京都の情勢を探るよう
命じられ、薩長同盟を取り纏めつつあった龍馬と共に下関を出発。伏見・寺田屋に入った。
伏見奉行配下の捕り方に踏み込まれる。慎蔵は槍で応戦し、包囲された寺田屋を奇跡的に脱出
傷を負った龍馬を材木小屋に隠すと単身薩摩藩邸に走り、救援を要請して龍馬の命を助けた
第二次長州征討(四境戦争)が始まると慎蔵は長府藩の報國隊軍監に就任。
高杉晋作の指揮のもと長州藩の奇兵隊と共に幕府軍と交戦し、これを破った。
明治維新政府
豊浦藩(長府藩)権大参事。廃藩置県後は宮内省御用掛として北白川宮家の家扶となり
のち家令を務めた。明治23年に辞任。晩年は故郷の長府で暮らし、
明治34年、71歳で没した。従六位 |
来島又兵衛
きじままたべい
|
文化14年1月8日(1817年2月23日) - 元治元年7月19日(1864年8月20日))
長門国厚狭郡西高泊村、無給通組の下士・喜多村政倫の次男として生まれたが、
天保7年(1836年)、大津郡俵山村の大組(八組)の上士・来島又兵衛政常の婿養子となった。
天保12年(1841年)、柳川藩の大石神影流の創始者大石進に剣術を学んだ。
嘉永元年(1848年)に帰国。家督を継ぐ。同年10月に手廻組に入隊。
その後、藩世子の駕籠奉行など藩の要職を歴任した。
文久3年(1863年)、藩命により猟師を集めた狙撃隊を率いて上洛。
自ら遊撃隊600名の兵を率いて、激戦を繰り広げた。しかしこの禁裏内の蛤御門の戦いで、
当時薩摩藩兵の銃撃隊として活躍した川路利良の狙撃で胸を撃ちぬかれた。
甥の喜多村武七に介錯を命じ、自ら槍で喉を突いた後、首を刎ねられて死亡した。
|
|
品川弥二郎
しながわ
やじろう
|
天保14年閏9月29日(1843年11月20日)- 明治33年(1900年)2月26日)
長州藩の足軽・品川弥市右衛門の長男として生まれた。安政5年(1858年)、松下村塾に
入門して吉田松陰から教えを受ける。高杉晋作らと行動を共にして尊王攘夷運動に奔走し、
英国公使館焼き討ちなどを実行している。
禁門の変では八幡隊長として参戦し、のちに太田市之進、山田顕義らと御楯隊を組織した。
薩長同盟の成立に尽力した。戊辰戦争では奥羽鎮撫総督参謀、整武隊参謀として活躍する。
明治期以後は別記参照
|
前原 一誠
まえばらいっせい
 |
天保5年3月20日(1834年4月28日) - 1876年12月3日 維新の十傑の1人
土原村(現・山口県萩市)にて、長州藩士・佐世彦七(大組47石)の長男 生まれ、
前原氏を相続する。
安政4年(1857年)、久坂玄瑞や高杉晋作らと共に吉田松陰の松下村塾に入門する。
松陰の処刑後は長崎で洋学を修め、のちに藩の西洋学問所・博習堂に学ぶ。
明治元年の戊辰戦争では北越戦争に出兵し、参謀として長岡城攻略戦など
会津戦線で活躍する。維新後は越後府判事や参議を勤める。大村益次郎の死後は兵部大輔を
兼ねたが、出仕することが少なかったため、船越衛は省務停滞を嘆いている。
徴兵制を支持する山縣有朋に追われるように下野し、萩へ帰郷する。
新政府の方針に不満をもった前原は明治9年(1876年)、奥平謙輔とともに不平士族を集めて
萩の乱を引き起こしたが、即座に鎮圧されて捕らえられ、萩にて処刑された。享年43。
|
野村 靖
のむらやすし
|
天保13年8月6日(1842年9月10日) - 明治42年(1909年)1月24日)
長州藩の下級武士(足軽)入江嘉伝次の次男として生まれる。兄に入江九一
吉田松陰の松下村塾に入門して尊王攘夷に傾倒、老中・間部詮勝の暗殺計画が露見して
兄と共に投獄されるが、イギリス公使館の焼き討ちに参加。第二次長州征討でも活躍している
明治期以後は別記参照
|
乃美 織江
のみおりえ |
文政5年1月28日(1822年2月19日)- 明治39年(1906年)7月24日
長州藩士乃美八郎右衛門の子として生まれる。天保13年、記録所出頭役見習として江戸に赴く。
文久2年(1862年)に上京して目付役、京都留守居役となる
元治元年6月5日の池田屋事件の際に、織江は河原町の長州藩邸の邸門を閉ざした
責任者であった。翌日、長州藩邸のすぐ近くで死亡していた吉田稔麿を自ら発見し、
長州藩に報告した。同時に、「桂小五郎が殺された」と時期尚早に長州藩に誤報を知らせ
長州藩内を過剰に激昂させてしまう失態を犯した。
禁門の変勃発後は長州藩邸に火を放って西本願寺に逃走してしまった。
西本願寺では会津藩兵士に取り囲まれて自害しようとしたが僧侶に制止されたため
更に大阪方面に逃走して帰藩した。山口藩大属・萩部支庁・兵庫伊弉諾神社宮司などを務めた
|
山田 顕義
やまだあきよし |
天保15年10月9日(1844年11月18日) - 明治25年(1892年)11月11日)
山口県萩市で、藩士である山田七兵衛顕行(禄高102石、藩海軍頭)の長男として生まれる。
一門に村田清風・山田亦介・河上弥市らがいる。藩校明倫館に入って師範の馬来勝平から
剣術(柳生新陰流)を学び、安政4年(1857年)6月、松下村塾に入門した。
高杉晋作・久坂玄瑞・志道聞多(のちの井上馨)・伊藤俊輔(のちの伊藤博文)・品川弥二郎ら
とともに攘夷の血判書(御楯組血判書)に名を連ねた。元治元年(1864年)、禁門の変では
山崎に布陣する久坂玄瑞・真木保臣らの陣に加わったものの長州勢は敗北し、山田も長州へ
落ち延びている。慶応2年(1866年)、第二次長州征伐では藩海軍総督の高杉晋作から
丙寅丸の砲隊長に任命され慶応4年1月、鳥羽・伏見の戦いにおいて、
新政府征討総督・仁和寺宮嘉彰親王の副参謀に任命される。
明治期以後は別記参照
|
根来 上総
ねごろ
かずさきよし
長州藩の家老
|
文化13年7月2日(1816年7月26日) - 明治25年(1892年)2月7日)
寄組(上士)の1,036石取りの根来煕行(ひろゆき)の長男として生まれる。
文久2年(1862年)からは江戸留守居役に任じられて長井雅楽の公武合体運動を手助けした。
しかし長井が失脚したことが影響し、8月には藩主の世子である毛利元徳の近侍にされた。
文久3年(1863年)には帰国を命じられてしばらくは逼塞した状況にあったが、まもなく復帰して
5月に家老に任じられた。7月には上京し、京都留守居役の宍戸真澂と共に
朝廷工作などを行なった。
第1次長州征伐後、高杉晋作らが功山寺で挙兵した際に根来はこれに降伏し、以降は
高杉らに協調して藩政を主導、明治3年には山口藩大参事に任じられた。明治17年(1884年)、
家督を子の親保に譲って隠居し、明治25年(1892年)2月7日に死去した。享年77。
|
赤禰 武人
あかねたけと
|
天保9年1月13日(1838年2月7日) − 慶応2年1月25日(1866年3月11日))
周防国玖珂郡柱島(現・山口県岩国市柱島)の島医師・松崎三宅の次男に生まれた
15歳の時に妙円寺の僧侶・月性に学び、月性の紹介で浦靱負の克己堂で学ぶ。
安政3年(1856年)、短期間ではあるが吉田松陰の松下村塾に学ぶ。
文久2年(1862年)4月、謹慎が解かれると江戸に赴いて尊王攘夷活動を行い、御楯組に加盟。
同年12月には 高杉晋作・伊藤俊輔・久坂玄瑞・井上聞多らと共に英国公使館焼き討ちに加わり
文久3年(1863年)5月の下関戦争に参加、同年10月には奇兵隊の第三代総管に就任した。
元治元年8月の第一次長州征伐後、赤禰は藩内の融和を図るが、当時の藩政を主導していた
俗論派と正義派諸隊の調停を行った事が同志に二重スパイとして疑われる契機となる。
幕府の攻囲を前に内戦を行うことを危ぶむ赤禰はこれに反対し高杉と対立する。
元治元年12月、高杉による功山寺挙兵が成功すると藩内での立場を失い、出奔して上方へ赴く。
その後、幕府に捕縛されたが、幕府大目付・永井尚志や新撰組参謀・伊東甲子太郎らは長州藩
の鎮撫工作に赤禰を利用することを画策,12月に長州藩士・槇村半九郎に捕縛される。
赤禰は弁明を望むが、取調べは一切行われず、翌年1月、山口の鍔石で処刑された。享年29。
|
三好 重臣
みよししおみ |
1840年11月14日(天保11年10月21日)- 1900年(明治33年)11月28日)
長州藩士、三好五右衛門の五男として生まれた。1863年、奇兵隊に入隊して参謀職を務めた。
(1867年)振武隊総監に就任 1868年の戊辰戦争では越後方面に進出して武功を挙げている。
明治期以後は別記参照
|
坪井
九右衛門
つぼいくえもん |
寛政12年(1800年)- 文久3年10月28日(1863年12月8日))
長州藩士。名は正裕。子寛。号は顔山。佐藤家(内閣総理大臣・岸信介、佐藤栄作兄弟の実家)に
生まれ、幼少時に坪井家の養子になった。村田清風の藩政改革に
村田清風の藩政改革に協力して功を挙げた。清風と共に藩政改革の建白書を
毛利敬親に提出している。
しかし清風の2回目の藩政改革は、清風の政敵である椋梨藤太の台頭で失敗し、しかも
清風は安政2年(1855年)に中風が原因で他界した。このため、坪井は椋梨により
失脚を余儀なくされる。
後に椋梨の失脚により、再び藩政に参与したが、坪井は尊王攘夷よりも佐幕派を支持したため、
過激な尊王攘夷派が多い長州藩内部で孤立してしまい、文久3年(1863年)にその過激な一部の
尊王攘夷派によって萩城下の野山獄で処刑された。享年64。
|
寺島忠三郎
てらしま
ちゅうさぶろう |
天保14年(1843年) - 元治元年7月19日(1864年8月20日)
日本の武士・長州藩士、尊皇攘夷派の志士である。父は寺島直一。
藩校明倫館、私塾松下村塾で吉田松陰に師事した。文久2年(1862年)、高杉晋作、久坂玄瑞、
大和弥八郎、長嶺内蔵太、志道聞多、松島剛蔵、有吉熊次郎、赤禰幹之丞、山尾庸三、
品川弥二郎ららのメンバーと御楯組結成に参加、長州藩家老の長井雅楽暗殺計画にも
参加する。
元治元年、八月十八日の政変で長州藩が失脚した後に、久坂らとともに
禁門の変で自刃する、享年21
|
益田 親施
ますだちかのぶ
長州藩の家老
|
天保4年9月2日(1833年10月14日)- 元治元年11月11日(1864年12月9日)
益田家第33代当主。長州藩永代家老・須佐領主益田家14代。右衛門介の名で知られる。
吉田松陰の山鹿流兵学に入門。嘉永6年(1853年)、アメリカ合衆国のマシュー・ペリーが浦賀に
来航すると、浦賀総奉行として着任する。
1856年には長州藩の国家老となった。1858年、通商条約問題が起こると、周布政之助らと
共に朝廷の意思に従って攘夷を決行すべきと江戸幕府に提言し、
「朝廷に対しては忠節、幕府に対しては信義、祖先には孝道」という藩の三大原則を打ち出した。
禁門の変に出陣して長州軍の指揮を執るが、薩摩藩・会津藩連合軍の前に敗れ、
長州に帰国した。幕府軍より益田に責任が問われて、徳山藩に身柄を預けられた後、
惣持院にて切腹を命じられ、死去した。
|
佐々木男也
ささきなおり
|
天保7年5月26日(1836年7月9日) - 明治26年(1893年)11月25日)
長州藩遠近附士・佐々木五郎兵衛の子として、長門国萩で生まれる。
元治元年(1864年)禁門の変では福原元僴の隊に所属して戦うが、敗戦とともに再び潜伏。
同年の内に八重垣隊を結成し、間もなく南園隊と改称して自身はその総督となる。
慶応2年(1866年)第二次長州征伐の際には石州口の主軍としって幕府軍と交戦しこれを破った。
明治期以後は別記参照
|
来原 良蔵
くるはらりょうぞう |
文政12年12月2日(1829年12月27日) - 文久2年8月29日(1862年9月22日)
長門国阿武郡で、福原光茂の子として生まれる。福原冬嶺に学び、その後天保12年に
藩校である明倫館に入った。翌年末に母方の伯父である大組来原良左衛門盛郷の
養子となった。嘉永4年(1851年)2月、江戸に登って朱子学者安積艮斎に師事。
安政元年(1854年)正月、来島又兵衛らと忠義会を結成。その後、相模国警備にあたった。
久坂玄瑞らと長井雅楽を除くため奔走した。この長井雅楽暗殺未遂事件の際に、責任を取って
死地を求めた良蔵は文久2年8月に江戸へ登り、横浜の外国公使館襲撃を企てるも失敗。
毛利定弘に諌められ、長州藩江戸藩邸にて自害した。 |
浦 元襄
裏もととし
長州藩の家老
|
寛政7年1月11日(1795年3月1日) - 明治3年6月1日(1870年6月29日)
長州藩寄組・国司氏の当主で長州藩家老の一人として重用されていた国司就孝
(通称:国司信濃)の次男として生まれる。元襄は有能であったため、長州藩内でも重臣と
して頭角を表し、加判役等要職を歴任した。家老職に任ぜられ江戸当役となって上京。
嘉永6年(1853年)、アメリカ合衆国のマシュー・ペリー来航時には長州藩兵を率いて江戸湾口の
大森、羽田の警備にあたった。文久2年(1862年)にも、幕命で兵庫周辺の警備の任についた
元襄は文久2年4月(1862年5月)、藩主の意を受けて京都に登り、朝廷に謝罪した。
京都の長州藩邸には、久坂玄瑞、福原乙之進、寺島忠三郎、入江九一、前原一誠ら、
尊皇攘夷派の急進派が集結しており、その説得を行った。
帰国後、文久3年(1863年)6月には尊皇攘夷を実行すべく、関門海峡を挟んで下関の
向かいにある門司周辺の要地を借用することを小倉藩に申し入れるために宍戸真澂(ますみ)、
福原元僴とともに小倉城に向かったが、交渉は不調に終わった。
同年、高齢ということもあって一切の職を辞して阿月に戻ったが、その後も影から革新派を支援し、
新しい日本の姿を見た元襄は、明治3年(1870年)6月1日に没した。
|
吉川 経幹
きっかわつねまさ |
文政12年9月3日(1829年9月30日) - 慶応3年3月20日(1867年4月24日)
周防岩国領の第12代領主、のち岩国藩初代藩主。
第11代領主・吉川経章の長男。母は長井元幹の娘・梅(清操院)。
本家の長州藩毛利家との融和に努めた。幕末の動乱の中では懸命に本家を輔け、
元治元年(1864年)の第一次長州征伐では幕府との間で仲介役として奔走する。
慶応2年の第二次長州征伐でも芸州口の戦いで功績を挙げ幕府軍を撃退することに
貢献している。慶応3年(1867年)3月20日に死去、享年39。
新政府も慶応4年3月13日にこの経幹が生存しているものとしてこれを城主格の諸侯と認めた。
悲願だった岩国藩6万石の藩主となる。
|
乃木 希典
のぎまれすけ |
嘉永2年11月11日(1849年12月25日) - 大正元年(1912年)9月13日)
長州藩の支藩である長府藩の藩士(馬廻、80石)・乃木希次と乃木壽子(ひさこ)との三男として
長府藩上屋敷(毛利甲斐守邸跡)に生まれ幼名は無人(なきと)で
その後、源三と名を改め、頼時とも称した。さらに後、文蔵、次いで希典と名を改めた。
元治元年(1864年)9月から、源三は明倫館文学寮に通学することとなったが、一方で、
同年11月から一刀流剣術も学び始めた
元治2年(1864年)、源三は集童場時代の友人らと盟約状を交わして、長府藩報国隊を組織した
慶応元年(1865年)、第二次長州征討が開始されると、長府藩報国隊に属し、山砲一門を有する
部隊を率いて小倉口での戦闘、この際、奇兵隊の山縣有朋指揮下において戦って、
小倉城一番乗りの武功を挙げた
明治期以後は別記参照
|
阿部 宗兵衛
あべ そうべえ |
天保2年(1831年) - 慶応2年(1866年)6月)
周防国山口に生まれる。1863年、奇兵隊に入隊し、司令官の一人として1864年12月の高杉晋作に
よる長州藩の俗論党に対するクーデターで活躍した。
1866年、第二次長州征伐が起こると、阿部は豊前国小倉において高杉や山縣有朋らと共に
小笠原長行が指揮する幕府の大軍と戦って奮戦したが、大谷越の戦いで重傷を負った。
治療のために下関に戻されたが間もなく死去した。享年36。
|
松島 剛蔵
まつしまごうぞう |
文政8年3月6日(1825年4月23日) - 元治元年12月19日(1865年1月16日))
長州藩の藩医である松島瑞蟠の長男として萩中ノ倉に生まれた
弟に吉田松陰の妹婿である小田村伊之助(楫取素彦)と小倉健作(松田謙三)がいる。
江戸遊学し、坪井信道に4年間従学のち、世子である毛利元徳の侍医となった。
長崎に赴き勝海舟らと共に長崎海軍伝習所でオランダ人に航海術を3年間学び
帰藩して洋学所・軍艦教授所を創立する。軍艦教授所の門下生には高杉晋作らがいた。
桂小五郎、吉田松陰とは友人であり、特に松下村塾の門下生らと提携して様々な活動を行った。
文久2年(1862年)、高杉晋作、久坂玄瑞らと共に御楯組を結成する。12月12日、江戸品川の
御殿山に建設中だったイギリス公使館を襲撃した(英国公使館焼き討ち事件)。
元治元年(1864年)、禁門の変が起こり、久坂玄瑞らが戦死する。幕府による第一次長州征伐で
俗論派が藩政権を握ったため、松島は萩野山獄に投ぜられる。同年12月16日、「高杉晋作が
功山寺で挙兵」との報が萩に伝わるや、12月19日に処刑された。享年40
|
有吉 熊次郎
ありよしくまじろう |
天保13年(1842年) - 元治元年7月19日(1864年8月20日)
長州藩士有吉忠助の次男(近習有吉傳十郎の弟)として生まれる。
16歳の時に土屋蕭海の紹介により吉田松陰の松下村塾に入塾する。
安政5年(1858年)、松陰の老中間部詮勝暗殺計画に血盟をしたことから、外叔の白根多助により
家に幽閉される。急進派の藩士らと上京、禁門の変(蛤御門の変)において重傷を負い、
久坂、寺島らとともに鷹司邸内で自刃する。享年23。
|
飯田 俊徳
いいだとしのり |
1847年8月5日(弘化4年6月25日) - 1923年(大正12年)8月27日)
萩藩大組飯田家の子として生まれた。はじめは吉次郎といった。藩校明倫館に学んだ後、
吉田松陰・大村益次郎らに師事する。高杉晋作率いる奇兵隊にも所属していた。
明治期以後は別記参照
|
飯田正伯
いいだしょうはく |
文政8年(1825年) - 文久2年6月1日文政8年、50石の長州藩医の子として生まれる。
安政5年(1858年)に吉田松陰の松下村塾に入り、主に兵学を学んだ。安政の大獄で松陰が
刑死すると、桂小五郎や伊藤博文らと共に松陰の遺骸を引き取ることに尽力している。
万延元年(1860年)7月、軍用金調達を名目にして浦賀の富豪を襲って金品を強奪したため、
罪人として幕府に捕縛され、獄中において文久2年(1862年)6月1日に病死した。享年38。
|
河瀬 真孝
石川 小五郎
かわせまさたか |
天保11年2月9日(1840年3月12日) - 大正8年(1919年)9月29日)
はじめ石川新五郎、石川 小五郎(いしかわ こごろう)と称したが、のちに河瀬真孝、
河瀬安四郎と改名周防国吉敷郡佐山に、長州藩士の子弟として生まれる。萩の明倫館に学ぶ。
文久2年、先鋒隊に入隊文久3年の朝陽丸事件での幕府使節団暗殺の首魁とされる。
元治元年、御楯隊に入隊。禁門の変では、戦死した来島又兵衛の指揮権を引き継いで
遊撃隊の指揮を執り、のちに遊撃隊総督となる。
(1865年)、高杉晋作による功山寺挙兵では、遊撃隊を率いて参加した。
慶応3年、トーマス・ブレーク・グラバーの協力の下イギリスに渡り、明治4年(1871年)まで滞在する。
明治期以後は別記参照
|
野村弥吉
井上 勝 |
天保14年8月1日(1843年8月25日) - 明治43年(1910年)8月2日)
長州藩士・井上勝行の三男として萩城下に生まれる。野村家の養嗣子となる野村弥吉と改名が、
のちに復籍する。文久3年(1863年)に脱藩。同年5月12日、英国総領事による斡旋の下、
長州五傑(長州ファイブ)と呼ばれることとなる伊藤博文らとジャーディン・マセソン商会の船
(チェルスウィック号)に密航し渡英、明治元年までユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン
(UCL)にて鉱山技術・鉄道技術などを学ぶ。途中、元治元年(1864年)に井上と伊藤が帰国
翌慶応元年(1865年)に薩摩藩第一次英国留学生と出会い日本人同士の交流を喜んだのも
つかの間、藩からの費用が少なくなり困窮、慶応2年(1866年)に遠藤も病気の悪化で
帰国するなど苦境が続く中で明治元年9月に無事卒業を果たした。
同年、木戸孝允の「母国で技術を役立てるように」との再三の要請により11月に山尾と共に帰国。
長州藩へ戻り実家と復縁し、父の名前から1字取り井上勝と改名、
長州藩から鉱山管理の仕事を任されていたが、明治2年(1869年)に木戸の呼びかけに
応じ新政府に出仕、10月に大蔵省造幣頭兼民部省鉱山正となる
明治期以後は別記参照
|
御堀 耕助
みほり こうすけ |
天保12年7月7日(1841年8月23日) - 明治4年5月13日 前名:太田市之進
長州藩士・太田要蔵の長男として萩に生まれる。18歳で江戸の斎藤弥九郎道場に入門、
塾頭を務める。文久3年(1863年)5月、長州藩による馬関海峡(関門海峡)での
米仏商船砲撃に参加。
元治元年7月の禁門の変に参加、破れて帰藩。四国連合艦隊との戦闘に参加後、山田顕義・
品川弥二郎らと御楯隊を結成し総督となる。慶応元年(1865年)、太田市之進から
御堀耕助に改名。慶応3年(1867年)、参政となる。同年8月、柏村数馬と共に京都に赴き、
薩摩藩の小松清廉・西郷隆盛・大久保利通らと倒幕の実施計画について会談。
明治4年(1871年)、三田尻において病死。享年31。
|
岡部 富太郎
おかべ とみたろう |
天保11年7月30日(1840年8月27日) - 明治28年(1895年)10月28日)
長州藩士岡部藤吾の長男として生まれる。藩校の明倫館に学び、安政4年(1857年)に
吉田松陰の松下村塾に入塾する。湯浅丑兵衛と友に衛撃隊を組織馬関戦争、
四境戦争、戊辰戦争に出征し、維新後は山口・大阪・兵庫の各県に出仕する。
明治28年(1895年)没、享年56。
|
楫取 素彦
かとりもとひこ
(小田村
伊之助)
|
文政12年3月15日(1829年4月18日) - 大正元年(1912年)8月14日)
長門国萩魚棚沖町(現・山口県萩市)に藩医・松島瑞蟠の次男として生まれる。
兄に松島剛蔵、弟に小倉健作(松田謙三)がいる。小田村家の養子となるのは
天保11年(1840年)で同家は代々儒官であった。弘化元年明倫館に入り、同4年(1847年)19歳で
司典助役兼助講となる。
吉田松陰とは関係が深く、また松陰の次妹の寿と結婚し、寿に先立たれた後の明治16年
久坂玄瑞の未亡人であった末妹の美和子(文)と再婚している。
文久元年(1861年)以後はもっぱら藩主に従って江戸・京都・防長の間を東奔西走する。
慶応3年(1867年)9月に藩命により、楫取素彦と改名した。
慶応3年(1867年)冬、長州藩兵上京の命を受け、諸隊参謀として出征する。
鳥羽・伏見の戦いにおいて、江戸幕府の死命を制するに至った。
明治期以後は別記参照
|
金子 重之輔
かねこしげのすけ |
天保2年2月13日(1831年3月26日) - 安政2年1月11日
長門国阿武郡紫福村商人・茂左衛門とつるの長男として生まれる。
幼時より白井小助、次いで土屋蕭海に学び嘉永6年、家業を嫌って江戸に出て長州藩邸の
雑役となる。同年、熊本藩士・永島三平を伝にして吉田松陰と出会いその弟子となる。
嘉永7年、アメリカ合衆国の東インド艦隊再来に際して松陰と共に渡米を計画して藩邸を脱走。
日米和親条約が締結されると松陰と共に下田へ赴いて米艦に乗り込もうとするがアメリカ側に
拒否されたためにやむなく計画を中止、自首した。その後、幕吏によって萩へ送還され
安政2年(1855年)、士分以下の者が入る岩倉獄で病没した。 |
久保 清太郎
くぼせいたろう |
1832年12月29日(天保3年閏11月8日)- 1878年(明治11年)10月2日)
長州藩士・久保五郎左衛門の長男として、萩城下松本村(現:山口県萩市)で生まれる。
松下村塾で玉木文之進、吉田松陰に学ぶ。安政4年4月帰藩し、富永有隣の出獄に尽力して、
彼と松陰の三人で協力して松下村塾を独立させる。安政5年7月(1858年8-9月)に藩務に復帰し、
舟木代官、上関代官、筑前伊崎代官、山口藩会計主事などを歴任。
明治期以後は別記参照
|
駒井政五郎
こまいまさごろう |
天保12年(1841年)-明治2年4月23日、江戸時代の長州藩士・吉田松陰の松下村塾に学ぶ。
文久3年(1863年)に海防大砲掛、慶応3年(1867年)、鋭武隊総督に就任。戊辰戦争には征討軍の
軍監を務める。奥羽、函館方面を転戦し、二股口の戦いで土方歳三率いる衝鋒隊・伝習歩兵隊
約300人と戦ったが、乱戦の末、胸に銃弾を受け戦死した。
|
白石 正一郎
しらいししょういち
|
文化9年3月7日(1812年4月18日)- 明治13年(1880年)8月31日)長門国赤間関竹崎に萬問屋
(荷受問屋)小倉屋を営んでいた白石卯兵衛の長男(8代目)として生まれた。
米、たばこ、反物、酒、茶、塩、木材等を扱い、ほかに質屋を営み酒もつくった。
鈴木重胤から国学を学び、重胤の門下生を通じ西郷隆盛が正一郎を訪ね親しくなり、
文久元年にはには薩摩藩の御用達となった。月照上人、平野国臣、真木保臣らと親しかった
経緯から尊皇攘夷の志に強い影響を受けて、長州藩の高杉晋作、久坂玄瑞らを資金面で
援助した。土佐藩を脱藩した。坂本龍馬なども一時、白石邸に身を寄せていた。
文久3年(1863年)6月7日、高杉晋作の奇兵隊結成にも援助し、自身も次弟の白石廉作と
ともに入隊。正一郎は奇兵隊の会計方を務め、7月には士分に取り立てられた。
明治維新後は、赤間神宮の2代宮司となった。明治13年(1880年)、69歳で死去。
|
杉 民治
すぎ みんじ |
長州藩士・杉常道(百合之助)の長男として、長門国萩の松本村に生まれる。 吉田松陰の兄
幼少期は弟・寅次郎(松陰)とともに父や叔父・玉木文之進に師事し、のち玉木の松下村塾や
藩校・明倫館で学んだ。嘉永6年(1853年)江戸湾警備のために相模国へ出張するが、
翌安政元年(1854年)松陰の黒船密航未遂事件に関連して帰国し、郡奉行所勤務となった。
しかし安政6年(1859年)安政の大獄で捕縛された松陰に連座して免職となった。
慶応元年(1865年)東光寺組を結成し、手廻組として藩の革新派に加わった。同年、民政方御用掛、
明治期以後は別記参照
|
杉 孫七郎
すぎ まごしちろ |
天保6年1月16日)- 大正9年5月3日)植木五郎右衛門の次男として周防国吉敷郡御堀村
(現在の山口県山口市)で生まれる。母は周布政之助の姉である。杉考之進盛倫の養子となり、
藩校明倫館で学んだ、吉田松陰にも師事、文久元年、藩命により江戸幕府の遣欧使節である
竹内保徳・松平康英らに従って欧米諸国を視察する。
帰国後、下関戦争では井上馨とともに和議に尽くし、元治の内乱では高杉晋作を支持しつつも、
保守派との軍事衝突には最後まで反対した。四境戦争では長州軍の参謀として活躍した。
明治期以後は別記参照
|
杉 常道
すぎ つねみち
吉田松陰の父 |
文化元年2月23日(1804年4月3日) - 慶応元年8月29日 民治・松陰の父
無給通組士の杉常徳(七兵衛)の子として生まれる。文政7年(1824年)に家督を相続
家格は無給通組(下級武士上等)、石高26石という極貧の武士であったため、農業もしながら
生計を立て、7人の子供を育てていた。おまけに三男は発声が不自由であった。
天保3年(1830年)に記録御次番役となり、翌年に呉服方になる。
弟吉田大助が死去したため、吉田家(家禄57石)の家督を次男の寅之助(松陰)に相続させた。
安政2年、松陰の処分が解け、松下村塾の主宰者となると、長男修道と共に最初の生徒となる。
安政6年5月(1859年)に松陰が江戸護送となると、藩職を罷免され万延元年(1860年)に家督を
修道に譲るが、文久3年(1863年)に当職(国相府)内用方になり、盗賊改方を兼務する。
慶応元年3月に辞職しほどなくして死去した。
|
世良 修蔵
せら しゅうぞう |
天保6年7月14日(1835年8月8日) - 慶応4年閏4月20日
周防国大島郡椋野村の庄屋・中司家の子として誕生、17歳の時、萩藩の藩校である明倫館に
学び、後に大畠村で月性の時習館(清狂草堂)に学ぶ。文久3年頃に奇兵隊に入隊し、
奇兵隊書記となる。
江戸幕府による第二次長州征伐が行われると第二奇兵隊を率いて抗戦し、同年6月の大島口
において松山藩を中心とした幕府軍相手に勝利を収めた。
慶応4年(1868年)1月、幕府方との鳥羽・伏見の戦いに際し前線に復帰し、長州庶民軍である
第二中隊(第二奇兵隊)や第六中隊(遊撃隊)を指揮して戦い、新政府軍の勝利に貢献している。
その後は薩摩の黒田清隆、長州の品川弥二郎に代わり、薩摩の大山格之助と共に新政府の
奥羽鎮撫総督府下参謀となり、戊辰戦争においては、同年3月、会津藩征伐のために総督・
九条道孝以下五百余名と共に派遣され、3月23日、仙台藩の藩校養賢堂に本陣を置いた。
仙台藩士を嘲り、傍若無人な振る舞いもあるなど、次第に周囲からの反感を高めていく
仙台藩士・瀬上主膳、姉歯武之進はその内容に激昂し、世良の暗殺実行を決意する
瀬上主膳、姉歯武之進、鈴木六太郎、目明かし・浅草屋宇一郎ら十余名に襲われる。
瀕死の重傷を負った上で捕縛された世良は、同日、阿武隈川河原で斬首された
|
大楽 源太郎
だいらくげんたろう |
天保3年(1832年)(1834年の説もある) - 明治4年3月16日(1871年5月5日))
萩城下に萩藩重臣で寄組児玉若狭の家臣である山県信七郎の子として誕生。
天保14年(1843年)12歳にして、主命により同地の大楽助兵衛の養嗣子となる。
青年期に太田稲香、僧月性、広瀬淡窓らの門下に学び、勤皇思想を身に付け、
また久坂玄瑞らと知己となる。久坂、高杉晋作らと協力して積極的に尊王攘夷運動を推進。
禁門の変においては書記として参陣。長州藩の敗戦を受けて再度山口へと逃れ、
慶応元年(1865年)高杉の下関挙兵に呼応して宮市に忠憤隊を組織した。
同2年(1866年)には、故郷台道に私塾敬神堂(別称西山書屋)を開設、明治2年までに多くの
門人を育てた(後の内閣総理大臣寺内正毅もここに学んだ一人である)。しかし同年、
大村益次郎暗殺事件が勃発。犯人の神代直人、団紳二郎らが門下生であったことから
首謀者の嫌疑を受け、幽閉を命ぜられる。
翌3年(1870年)、多くの門下生が山口脱隊騒動を起こすと、再び首謀者の嫌疑を受け藩庁から
出頭を命ぜられる。ここに至りついに山口より脱走し、豊後姫島に潜伏した後、豊後鶴崎において
河上彦斎と語らって二卿事件を企てるも失敗。さらに久留米に走って応変隊を頼るが、
新政府からの追求を受けた。
同隊隊士の川島澄之助、来島三治郎らの手によって、翌4年(1871年)に斬殺された。
|
高杉 小忠太
たかすぎこちゅうたう
高杉晋作の父 |
文化11年10月13日(1814年11月24日)-明治24年(1891年)1月13日
長州藩士で200石取りの高杉春豊の次男として萩で生まれる。次男だったため、はじめ長州藩士・
武藤又左衛門(大組・280石)の養子となり弥四郎正方と名乗るが、兄が死去し、実家の継嗣が
絶えたために旧姓に復して家督を継いだ。文久2年には上洛し、直目付・学習館御用掛に
任じられて長州藩と朝廷・幕府の交渉役を務めた。元治元年(1864年)8月に第1次長州征伐が
始まると、その余波を受けて失脚を余儀なくされた。慶応2年(1866年)に直目付として復帰し、
明治2年6月には大監察となって藩政を掌握した。明治3年(1870年)には権大参事となり、
諸隊の脱退騒動を木戸孝允らとともに鎮圧する。明治4年7月の廃藩置県で政界から退隠し、
以後は主家である毛利氏の歴史編纂事業に務めた。
明治24年(1891年)1月13日、東京で死去。享年78
|
玉木 文之進
たまき ぶんのしん |
文化7年9月24日-明治9年(1876年)11月6日 長州藩士で無給通組・杉常徳(七兵衛)の3男と
して萩で生まれる。40石取りの玉木正路(十右衛門)の養子となって家督を継いだ。
天保13年(1842年)に松下村塾を開いて、幼少期の松陰を厳しく教育した。また親戚の
乃木希典も玉木の教育を受けている。天保14年(1843年)に大組証人役として出仕。
慶応2年(1866年)の第2次長州征伐では萩の守備に務めた。その後、奥番頭にすすむが
明治2年(1869年)には政界から退隠し、再び松下村塾を開いて子弟の教育に務めている。
明治9年(1876年)、前原一誠による萩の乱に養子の玉木正誼や門弟の多くが参加したため、
その責任を取る形で11月6日に先祖の墓の前で自害した。
享年67。その後は正誼の子、正之が相続。
|
時山 直八
ときやまなおはち |
天保9年1月1日(1838年1月26日) - 慶応4年5月13日(1868年7月2日))
萩城外の奥玉江にて士雇・時山茂作の子として生まれた、同藩の槍術師範・岡部半蔵に
宝蔵院流を習う。また、嘉永3年頃、吉田松陰の松下村塾にて学んだ。
高杉晋作らとともに尊王攘夷運動に参加するが、攘夷の不可能を悟ると討幕運動に邁進した。
また、8月18日の政変や禁門の変、長州征伐などの数々の戦争において、奇兵隊参謀として
活躍した。慶応4年(1868年)、北越戦争における越後長岡藩との朝日山攻防戦において、
陣頭に立って指揮し立見尚文率いる桑名藩兵と戦ったが、顔面を狙撃されて即死した。享年31。
|
所 郁太郎
ところ いくたろう |
天保9年2月16日(1838年3月11日) - 慶応元年3月12日(1865年4月7日))
美濃国赤坂の醸造家・矢橋亦一の子として生まれ、同国大野郡の医者所伊織の養子となった
初め、加納藩医・青木松軒、次いで京の安藤桂洲に学ぶ、万延元年(1860年)には大坂の
適塾に入り、緒方洪庵に学んだ後、京にて医者として開業、近傍に長州藩邸があったことから
、郁太郎の治療を請う長州藩士が多くこの頃から長州藩士と交わり、尊王思想の
大義を説いている。
文久3年(1863年)には長州藩邸内の医院総督となり、八月十八日の政変では
長州に下向している。井上聞多(後の井上馨)の治療にあたり、井上の一命を救うのに
成功している。遊撃隊参謀として高杉晋作を助けて転戦したが、陣中で腸チフスにかかり、
吉敷村の陣営で没した、享年28
|
富永 有隣
とみながゆうりん |
文政4年5月14日(1821年6月13日) - 明治33年(1900年)12月20日)
幼少の頃に天然痘にかかり右目を失明する。9歳で長州藩藩校・明倫館に入り、13歳で藩世子
成人後、小姓を務めるが、他人と打ち解けなかったために、同僚・親族らに憎まれ、
嘉永5年(1852年)に冤罪で見島に流され、嘉永6年(1853年)には萩野山獄に移された。
そこで同じく幽閉中であった吉田松陰と意気投合し、安政4年の出獄後は松陰の松下村塾で
講師を務めた。
慶応2年(1866年)の四境戦争では、鋭武隊を率いて石州・芸州口で幕府軍と交戦した。
明治維新後の開国政策への不満から、大楽源太郎とともに脱隊騒動を起こして敗北、
各地を逃亡した。明治10年に逮捕されて、2年後大審院において有罪判決を受けて
国事犯として石川島監獄に収容される。明治17年(1884年)に特赦により釈放
|
鳥尾 小弥太
とりおこやた |
弘化4年12月5日(1848年1月10日) - 明治38年(1905年)4月13日)
萩城下川島村に長州藩士(御蔵元付中間)・中村宇右衛門敬義の長男として生まれる。
文久3年(1863年)に奇兵隊に入隊。乱暴者なので、親から勘当され、自ら鳥尾と名を定めた。
長州征伐や薩摩藩との折衝などの倒幕活動に従事した。戊辰戦争では建武隊参謀や
鳥尾隊を組織し、鳥羽・伏見の戦いをはじめ、奥州各地を転戦。戦後は和歌山藩に招聘され、
同藩の軍制改革に参与。
明治期以後は別記参照
|
福田 侠平
ふくだ きょうへい |
文政12年(1829年) - 明治元年11月14日(1868年12月27日)
長州藩士、十川権右衛門の次男として生まれた。のちに大津郡伊上村(現長門市)の
福田貞八の養子となり、福田姓を名乗る。文久3年、侠平35歳のとき、下関で奇兵隊が
結成されると志願して入隊
元治元年(1864年)には書記役として英仏蘭米四カ国連合艦隊との戦闘(下関戦争)に従軍
第二次長州征討では小倉口の戦いを歴戦し、戊辰戦争においては北越戦線から
陸奥へと転戦する。明治元年11月14日、戊辰戦争に勝利して凱旋、下関に滞在していたところ
突然卒倒して死亡した。大の酒豪であり、戦闘中も酒を常に携えていた。
|
福原 信冬
福原乙之進
ふくはらのぶふゆ |
天保8年9月26日(1837年10月25日) - 文久3年11月25日(1864年1月4日)
過激な攘夷論者で、文久2年に、久坂玄瑞、中谷正亮とともに長州藩を脱藩。航海遠略策を唱え、
藩内で勢威を増していた長井雅楽の暗殺をたくらむが、未遂に終わった。
同年には、高杉晋作らとともに御楯組を組織して、英国公使館焼き討ち事件に加わる。
江戸で討幕を画策するも、赤坂の刈谷藩邸内の倉田珪太郎宅で一橋家家臣・脇坂又三郎、
刈谷藩士遠藤木工、浜田篤蔵、村上其太郎らと密議中に、古河藩主・土井利則の捕吏の
襲撃を受け、戦うも負傷して自害した。
|
堀 真五郎
ほりしんごろう |
1838年5月4日(天保9年4月11日) - 1913年(大正2年)10月25日)
萩の堀文左衛門松園の子として生まれたが、脱藩して各国の志士達、特に久坂玄瑞・
高杉晋作らと交友を深めて尊皇攘夷活動に加わる。戊辰戦争時には徴士内国事務局判事、
次いで箱館府兵事取扱役に就任した。榎本武揚率いる旧幕府軍が蝦夷地へ
上陸を開始すると侵攻を阻止するため防戦したが敵わず、箱館府知事清水谷公考と共に
25日五稜郭を脱して青森へ逃れる。維新後は東京始審裁判所長や大審院判事などを務める。
1913年(大正2年)、死去。享年76。
|
前田
孫右衛門
まえだまごうえもん |
文政元年7月28日 - 元治元年12月19日、長州藩士。諱は利済、字は致遠、通称は岩助、
号は陸山。甲子殉難十一烈士の一人。萩藩出身。藩校の明倫館で学び、長州藩の代官や奉行を
歴任後、1862年に上京して直目付に就任して軍備の整備に当たるが、奉勅攘夷の為出奔、
1863年の8月の政変により直目付を罷免されるが、政変により直目付を罷免されるが、
9月に表番頭格用談役に登用され、後に直目付に復職。禁門の変の後、直目付を再び罷免され、
謹慎処分に処される。その後野山獄に入れられ、楢崎弥八郎・松島剛蔵・毛利登人・山田亦介・
大和弥八郎・渡辺内蔵太ら6人と共に処刑される。 |
松浦 松洞
まつうらしょどう |
天保8年-文久2年4月13日 亀太郎、魚商人の子として生まれる。長州藩士・根来主馬の
家臣として仕える。安政3年(1856年)吉田松陰の松下村塾に入り、尊王攘夷運動に参加。
文久2年久坂玄瑞らと上洛し、公武合体・開国派であった長州藩士・長井雅楽暗殺計画を
計画したが、翻意を促されて断念し、京都粟田山にて切腹した。幼少より絵画を志し、
画家としては四条派の羽様西崕に師事しており、安政6年安政の大獄によって江戸護送が
決定した吉田松陰の肖像画を残している。
|
三浦 梧楼
(梧樓)
みうら ごろう |
弘化3年11月15日(1847年1月1日) - 大正15年(1926年)1月28日)
現在の山口県萩市に萩藩士の陪臣五十部吉平の五男として生まれる。
明倫館で学んだ後、奇兵隊に入隊して第二次長州征伐や戊辰戦争に従軍する。
明治期以後は別記参照
|
毛利 登人
もうりのぼる |
文政4年7月6日(1821年8月3日) - 元治元年12月19日(1865年1月16日))
吉敷毛利家の末家、毛利虎十郎(大組600石)の嫡男として誕生。
第1次長州征伐の後に俗論派が藩論を主導するようになると、前田孫右衛門、
大和弥八郎らと共に謹慎処分を受け、蟄居した。12月には野山獄に投じられ、山田亦介、
松島剛蔵、前田孫右衛門、大和国之助、楢崎弥八郎、渡辺内蔵太らと処刑された。
|
山尾 庸三
やまおようぞう |
天保8年10月8日(1837年11月5日) - 大正6年(1917年)12月21日)
長州藩重臣繁沢氏の給領地庄屋であった山尾忠治郎の二男、萩藩寄組である繁沢石見に
経理の才を認められ奉公(陪臣)に上がる。江戸で航海術を学ぶ。文久2年(1862年)、塙忠宝を、
伊藤博文とふたりで暗殺した。文久3年(1863年)、藩命により陪臣から藩の士籍に列し、密航で
ロンドン・グラスゴーに、伊藤博文・井上馨・井上勝・遠藤謹助と共に留学し、長州五傑と
呼ばれさまざまな工学を学ぶ。
明治期以後は別記参照
|
宍戸璣
ししどたまき |
文政12年3月15日(1829年4月18日) - 明治34年(1901年)10月1日)
前名の山県半蔵でも知られる.。長州藩士・安田直温の三男として生まれる。名は子誠、のち敬宇
吉田松陰らと共に玉木文之進の塾(松下村塾)に学び、また藩校明倫館に学ぶ。
嘉永元年(1848年)、藩儒・山県太華の養子となり、半蔵と称する。文久2年(1862年)には同藩の
久坂玄瑞、土佐藩の中岡慎太郎らとともに松代藩で謹慎中の学者佐久間象山を訪問。
高杉晋作・伊藤博文らの挙兵によって藩論が再転換し、赦免される。しかし幕府は長州藩へ
問罪使の派遣を決定。藩は半蔵を家老宍戸家の養子として宍戸備後助と改名させ、広島の
国泰寺で幕府問罪使・永井尚志に応接させた。
明治期以後は別記参照
|
山田
宇右衛門
やまだううえもん |
文化10年9月9日-慶応3年11月11日、生家は増野氏。大組・山田氏(禄高100石)の養子になって
家督を継ぐ。安政元年(1854年)相州警衛総奉行手先役、安政3年(1856年)徳地代官、万延元年
遠方方、文久3年(1863年)奥阿武代官、元治元年(1864年)郡奉行を歴任。
文久2年(1862年)政務座・学習院用掛のとき京都にあり、尊王攘夷運動に参加した。
慶応元年(1865年)番頭格・政務座役に就任。参政首座となって、木戸孝允とともに藩内における
指導的立場となり、兵学教授として軍備拡張を推進するなど藩政刷新に尽力した。
しかし、慶応3年(1867年)に明治維新を前に病没。
|
山田 亦介
やまだまたすけ |
1809年2月2日(文化5年12月18日) - 1865年1月16日(元治元年12月19日))
大組頭山田家の嫡男。村田清風の甥にあたる。甥に初代司法大臣、陸軍中将の山田顕義がいる。
長沼流兵学を学び、弘化2年(1845年)には吉田松陰(寅次郎、当時15歳)に教授している。
嘉永5年(1852年)、古賀侗庵の『海防憶測』を出版した罪で隠居となり、知行も削減される。
安政5年(1858年)には隠居雇として海防や軍艦「庚申丸」製造に関わり、銃士隊の編成を進言する。
しかし、長州藩内の主導権を握った俗論党によって、萩の野山獄にて57歳で処刑された。
|
大和 弥八郎
やまとやはちろう |
天保6年11月3日(1835年12月22日) - 元治元年12月19日(1865年1月16日)
江戸時代末期(幕末期)の長州藩士。大和国之助とも。甲子殉難十一烈士の一人。
1862年、久坂玄瑞、寺島忠三郎らと横浜居留地焼討ちを計ったが、藩主・毛利定広に伝わり実行には
到らなかった。その後、御楯組結成に参加。1865年、山田亦介・前田孫右衛門・毛利登人・
松島剛蔵・渡辺内蔵太・楢崎弥八郎らと共に斬罪に処された。
|
渡辺 内蔵太
わたなべくらた |
天保7年2月3日(1836年3月19日) - 元治元年12月19日(1865年1月16日)
萩藩士。長嶺内蔵太(ながみね くらた)とも。甲子殉難十一烈士の一人。
1862年、御楯組結成に参加。その後、山田亦介・前田孫右衛門・毛利登人・松島剛蔵
松島剛蔵・大和弥八郎・楢崎弥八郎らと共に斬罪に処される。
|
児玉 源太郎
こだまげんたろう |
嘉永5年閏2月25日(1852年4月14日) - 明治39年(1906年)7月23日)
長州藩の支藩徳山藩の中級武士(百石)児玉半九郎の長男として生まれる。
父とは5歳で死別し、姉である久子の婿で家督を継いだ児玉次郎彦に養育された。
しかし、源太郎が13歳のときこの義兄は佐幕派のテロにより惨殺され、家禄を失った一家は困窮した。
明治元年(1868年)に初陣。下士官として箱館戦争に参加した後、陸軍に入隊する。
以下明治期に記載
|
神代 直人
きうじろなおと
|
生年不詳 - 明治2年(1869年))剣の流派は不詳である。大楽源太郎の西山塾で学び、狂信的な
攘夷論者となる。初めは高杉晋作の暗殺を計画したが、高杉が彼を避けたこともあり、果たせなかった。
慶応元年(1865年)1月の御楯隊名簿に相図方として名が見えるが、その後脱走している。
その後、明治政府が洋式軍政改革を行うとこれに反発し、明治2年(1869年)に改革を指導していた
大村益次郎を暗殺。の後はしばらく豊後姫島に潜伏していたが、師である大楽源太郎が政府から
嫌疑をかけられている事を知ると山口へ戻り、捕吏が来る前に自害したとも捕縛されて
斬首されたともされる。
|
寺内 正毅
てらうちまさたけ |
嘉永5年2月5日(1852年2月24日) - 大正8年(1919年)11月3日)
嘉永5年、周防国山口(のちの山口県山口市)に長州藩士・宇多田正輔の三男として生まれる。
後に母方である寺内勘右衛門の養嗣子となる。
明治元年(1868年)、御楯隊隊士として戊辰戦争に従軍し、箱館五稜郭まで転戦した。
明治期以後は別記参照 |
| 薩摩藩 |
|
島津 斉彬
しまづなりあきら

第11代薩摩藩主 |
文化6年3月14日(1809年4月28日)-安政5年7月16日(1858年8月24日)
第10代藩主・島津斉興の長男として江戸薩摩藩邸で生まれる。斉興は斉彬が40歳を過ぎても
まだ家督を譲らなかった。そして、家老・調所広郷(笑左衛門)や斉興の側室・お由羅の方らは、
お由羅の子で斉彬の異母弟に当たる久光の擁立を画策した。
斉彬派側近は久光やお由羅を暗殺しようと計画したが、情報が事前に漏れて首謀者13名は
切腹また連座した約50名が遠島・謹慎に処せられた。斉彬と近しい幕府老中・阿部正弘、
伊予宇和島藩主・伊達宗城、越前福井藩主・松平慶永らが事態収拾に努めた。こうして
嘉永4年(1851年)2月に斉興が隠居し、斉彬が第11代藩主に就任した。
この一連のお家騒動はお由羅騒動(あるいは高崎崩れ)と呼ばれている。
藩主に就任するや、藩の富国強兵に努め、洋式造船、反射炉・溶鉱炉の建設、地雷・水雷・ガラス・
ガス灯の製造などの集成館事業を興した。
下士階級出身の西郷隆盛や大久保利通を登用して朝廷での政局に関わる。
斉彬は松平慶永・伊達宗城・山内豊信・徳川斉昭・徳川慶勝らと藩主就任以前から
交流をもっていた。安政4年(1857年)の阿部正弘の死後、安政5年(1858年)に大老に就いた
井伊直弼と将軍継嗣問題で真っ向から対立した。
安政4年の阿部正弘の死後、安政5年に大老に就いた井伊直弼と将軍継嗣問題で
真っ向から対立した。
井伊は大老の地位を利用して強権を発動し、反対派を弾圧する安政の大獄を開始する。
結果、慶福が第14代将軍・徳川家茂となり、斉彬らは将軍継嗣問題で敗れた。
斉彬はこれに対し、藩兵5,000人を率いて抗議のため上洛することを計画した。
しかし、その年の7月8日、鹿児島城下で出兵のための練兵を観覧の最中に発病し、
7月16日に死去した。享年50、斉彬の日本船章にすべきだと幕府に献策により日の丸は
太政官布告によって日本の国旗となってゆく。
|
島津久光

|
文化14年10月24日(1817年12月2日)-明治20年(1887年)12月6日
薩摩藩10代藩主)島津斉興の五男、11代藩主:島津斉彬は異母兄、12代藩主:島津忠義は長男。
安政5年(1858年)7月16日に斉彬が死去すると、遺言により忠教(久光の実子・忠徳(忠義)が
12代藩主に就任する。久光は藩主の実父として忠教の藩内における政治的影響力が増大する。
藩内における権力拡大の過程では、小松清廉(帯刀)や中山中左衛門等とあわせて、
大久保利通・税所篤・伊地知貞馨(堀仲左衛門)・岩下方平・海江田信義・吉井友実等、
中下級藩士で構成される有志グループ「精忠組」の中核メンバーを登用する
ただし、精忠組の中心であった西郷隆盛とは終生反りが合わず、文久2年の率兵上京(後述)
時には、西郷が無断で上坂したのを責めて遠島処分(徳之島、のち沖永良部島に配流)にし、
藩内有志の元治元年(1864年)に西郷を赦免する。文久2年(1862年)、公武合体運動推進の
ため兵を率いて上京するが東海道を帰京の途上、生麦村(現神奈川県横浜市鶴見区)で
イギリスの民間人4名と遭遇し、殺傷する生麦事件が起こる
翌文久3年(1863年)7月の薩英戦争へと発展する。薩摩藩の推進した公武合体運動は頓挫する。
久光は3月14日に参預を辞任、小松帯刀や西郷隆盛らに後事を託す。
久光が在藩を続けた約3年間に中央政局は禁門の変・長州征討・薩長盟約の
締結・徳川家茂の薨去徳川慶喜の将軍就職・孝明天皇の崩御・明治天皇の践祚
等々と推移する政治的妥協の可能性を最終的に断念した久光の決断により、薩摩藩指導部は
武力倒幕路線を確定明治維新後明治2年従三位・参議兼左近衛権中将に叙任される、
明治6年 左大臣となり明治20年(1887年)12月6日に死去、享年71
|
島津 忠義
 |
天保11年4月21日(1840年5月22日)-明治30年(1897年)12月26日
島津氏分家の重富家当主・島津忠教の長男として生まれる。伯父・斉彬の養嗣子となり12代藩主
藩政の実権は当初祖父の斉興、次いで後見人となった父・久光(忠教)や西郷隆盛、
大久保利通らに掌握され、忠徳自身は若年ということもあり、主体性を発揮することはなかった
明治維新後は長州・土佐・肥前の3藩と協力して版籍奉還を進んで行なう。
名を「忠義」と改め薩摩藩知事となるが、実質的な藩政は西郷に任せていたと言われている。
明治30年(1897年)12月、58歳で鹿児島市にて薨去した。 |
島津 久治
しまづひさはる |
天保12年4月25日(1841年6月14日) - 明治5年1月4日(1872年2月12日)
島津久光の次男として重富館(現鹿児島県姶良市)に誕生する。島津久宝の養嗣子
文政2年(1855年)に海防総頭取に任命され、鹿児島藩の沿岸防衛の要を務める。
薩英戦争勃発に際して実兄の茂久(のちの忠義)の代理として鹿児島藩海軍の指揮を執る。
元治元年、禁門の変でも茂久の代理として皇居警衛総督、慶応2年に家老に任ぜられる
慶応3年には小松帯刀、桂久武らの強硬論に対して、重職では慎重論を唱えただ一人反論した。
明治5年(1872年)正月に急死した。享年32。
西郷隆盛から大久保利通に宛てた当時の書簡では「ピストル自殺」と明言されている。
|
調所 広郷
ずしょひろさと
|
安永5年2月5日(1776年3月24日) - 嘉永元年12月19日(1849年1月13日)
城下士・川崎主右衛門基明(兼高)の息子として生まれ、天明8年に城下士・調所清悦の
養子となる。隠居していた10代藩主・島津重豪にその才能を見出されて、登用される。
後に藩主・島津斉興に仕え、使番・町奉行などを歴任し、小林郷地頭や鹿屋郷地頭、
佐多郷地頭を兼務天保3年には家老格に、天保9年(1838年)には家老に出世し、藩の財政・
農政・軍制改革に取り組んだ。
やがて斉興の後継を巡る島津斉彬と島津久光による争いがお家騒動(後のお由羅騒動)に
発展すると、広郷は斉興・久光派に与する。これは、聡明だがかつての重豪に似て西洋かぶれ
である斉彬が藩主になる事で再び財政が悪化する事を懸念しての事であると言われている。
斉彬は幕府老中・阿部正弘らと協力し、薩摩藩の密貿易に関する情報を幕府に流し、斉興、
調所らの失脚を図る。嘉永元年(1848年)、調所が江戸に出仕した際、阿部に密貿易の件を糾問される。
薩摩藩上屋敷芝藩邸にて急死、享年73。死因は責任追及が斉興にまで及ぶのを防ごうとした
服毒自殺とも言われる。広郷の財政改革が後の斉彬や西郷らの幕末における行動の基礎を
作り出し、現在の日本の近代化が実現されたと評価されるようになったのは戦後のことである
|
小松 清廉
帯刀
こまつきょかど

薩摩藩家老
維新十傑
|
天保6年10月14日(1835年12月3日) - 明治3年7月20日(1870年8月16日)
鹿児島城下山下町の喜入屋敷にて喜入領主・肝付兼善(5,500石)の四男として生まれた
安政2年正月に21歳で奥小姓・近習番勤めに任じられ、同年5月には江戸詰めを命じられた
安政5年(1858年)、24歳となった尚五郎は帯刀清廉と改名した
島津忠義が藩主になると清廉は当番頭兼奏者番に任命され、集成館の管理や貨幣鋳造を
職務とした。文久2年には久光による上洛に随行し、帰国後は家老職に就任した。
禁門の変では、幕府の出兵要請に対して消極的な態度を示したが、勅命が下されるや
薩摩藩兵を率いて幕府側の勝利に貢献した。
戦後、長州藩から奪取した兵糧米を戦災で苦しんだ京都の人々に配った。
第一次長州征討では長州藩の謝罪降伏に尽力している。
土佐藩脱藩浪士の坂本龍馬と昵懇となった。亀山社中(のちの海援隊)設立を援助したり、
龍馬の妻・お龍の世話をしている。長州の井上馨と伊藤博文を長崎の薩摩藩邸に
かくまってグラバーと引き合わせ、その後、鹿児島へ井上を伴って薩長同盟の交渉を行った。
慶応3年(1867年)の薩土盟約や四侯会議など、諸藩との交渉に関与した。討幕の密勅では
請書に、西郷隆盛・大久保利通とともに署名している。大政奉還発表の際は藩代表として
徳川慶喜に将軍辞職を献策し、摂政・二条斉敬に大政奉還の上奏を受理するよう迫った。
下腹部の腫瘍が悪化し、明治3年(1870年)1月には大久保や木戸らが小松を見舞うが、
7月18日に数え年36歳で大阪にて病死
|
西郷 隆盛

維新の十傑 |
文政10年12月7日(1828年1月23日) - 明治10年(1877年)9月24日)
薩摩藩の下級藩士・西郷吉兵衛隆盛の長男 通称は吉之介、善兵衛、吉兵衛、
吉之助と順次変えた。薩摩藩の下級武士であったが、藩主の島津斉彬の目にとまり抜擢され、
当代一の開明派大名であった
斉彬の身近にあって、強い影響を受けた。斉彬の急死で失脚し、月照和尚をかくまい二人で
自殺をするが奄美大島に流される。その後復帰するが、新藩主島津忠義の実父で事実上の
最高権力者の島津久光と折り合わず、久光が無官で、斉彬ほどの人望が無いことを理由に
上京すべきでないと主張
ところが久光上洛時、激派志士たちの京都焼き討ち・挙兵の企てを止めようと大阪に向かう
しかし4月6日、姫路に着いた久光は、西郷が待機命令を破ったことで再び沖永良部島に流罪に
遭う。その間に生麦事件で薩英戦争が起り、江戸幕府では徳川慶喜が将軍後見職、長州藩で
の事件等が多く発生、大久保利通(一蔵)や小松帯刀らの勧めもあって、
西郷を赦免召還することにした。
元治元年(1864年)2月28日に鹿児島に帰った西郷は足が立たなかった。29日、這いずりながら
斉彬の墓参をしたという。元治元年(1864年)の禁門の変以降に活躍し、第一次長州征伐の
征長軍参謀に任命された。第二次長州征伐と薩長同盟は坂本龍馬の仲介により成し遂げて
打倒幕府として薩長と土佐を含め各藩を引き込んで慶応4年1月3日、大坂の旧幕軍が
上京を開始し、幕府の先鋒隊と薩長の守備隊が衝突し、鳥羽・伏見の戦いが始まった
西郷は2月12日に東海道先鋒軍の薩摩諸隊差引(司令官)、14日に東征大総督府下参謀
江戸総攻撃を前に勝海舟らとの降伏交渉に当たり、幕府側の降伏条件を受け入れて、
総攻撃を中止した。その後、薩摩へ帰郷したが、明治4年(1871年)に参議として新政府に復職。
明治10年に私学校生徒の暴動から起こった西南戦争の指導者となるが、
敗れて城山で自刃した。
明治期以後は別記参照
|
大久保 利通

維新の十傑 |
文政13年8月10日(1830年9月26日) - 明治11年(1878年)5月14日) 維新の十傑の一人
琉球館附役の薩摩藩士・大久保利世と皆吉鳳徳の次女・福の長男として生まれる。
幼少期に加治屋町(下加治屋町方限)に移住し、下加治屋町の郷中や藩校造士館で、
西郷隆盛や税所篤、吉井友実、海江田信義らと共に学問を学び親友・同志となった。
嘉永3年(1850年)のお由羅騒動では父・利世とともに連座して罷免され謹慎処分となる。
安政4年(1857年)10月1日、西郷とともに徒目付となる。精忠組の領袖として活動し、
万延元年(1860年)3月11日、重富邸にて忠教と初めて面会し、閏3月、勘定方小頭格となる。
久元年12月から同2年1月中旬までの間に久光から一蔵(いちぞう)の名を賜り通称を改める。
御小納戸頭取に昇進となる。この昇進により、小松清廉、中山中左衛門と並んで久光側近となる
薩摩藩の大久保・西郷と長州藩の広沢真臣・品川弥二郎、広島藩の辻維岳が
会し出兵協定である三藩盟約を結んだ。 明治期以後は別記参照
|
伊地知 貞馨
いじちさだか |
文政9年(1826年)9月27日) - 明治20年(1887年)4月15日)
薩摩藩の少壮藩士による誠忠組の旗揚げに加わる。藩主の父として実権を握る島津久光は
別名:堀又十郎、堀仲左衛門、堀次郎、堀小太郎、伊地知壮之丞。当初は大久保利通と並ぶ
久光側近として、京都・江戸などで他藩との交渉などに活躍した。藩主・島津忠義の参勤を
遅らせるための奇策として、国元からの指示で江戸藩邸を自焼させた。
この「火災被害」により、忠義は江戸出府の遅延を差し許されたが、翌文久2年(1862年)8月3日、
幕府によって薩摩藩の自作自演であることが発覚(この際に藩命により伊地知壮之丞に改名)。
主犯格とされた伊地知は10日、藩の船天祐丸により江戸から鹿児島に檻送され以後は薩摩藩の
政治活動の第一線からは退いた。明治維新後は内務省に出仕するが、長年の盟友だった
内務卿・大久保利通に、琉球から賄賂を受取った事を咎められ免職となる。
明治期以後は別記参照
|
吉井 友実
よしいともざね

|
文政11年2月26日(1828年4月10日) - 明治24年(1891年)4月22日)
薩摩藩士・吉井友昌の長男として鹿児島城下加治屋町に生まれる。藩主・島津斉彬の
藩政改革の下、大坂藩邸留守居役などを務めて諸藩の志士との交流を重ね、若手改革派の
一人として活躍する。
斉彬の死後、大久保利通や税所篤ら同志40名と共に脱藩を企てたものの、藩主・島津忠義の
慰留をうけて大目付役に就任。
西郷隆盛・大久保らと始めとする精忠組の中心人物として藩政をリードし、
尊皇討幕運動を推進した。
第一次長州征伐で西郷隆盛が征長総督徳川慶勝に長州処分を委任された際、
税所篤と2人で西郷と共に長州に乗り込み、その戦後処理に努めた。
鳥羽・伏見の戦いでは、自ら兵を率いて旧幕府軍を撃退するなど多大な功績をあげる
明治期以後は別記参照
|
伊地知 正治
いじち まさはる
 |
文政11年6月10日(1828年7月21日) - 明治19年(1886年)5月23日)
薩摩藩士伊地知季平の次男として鹿児島城下千石馬場町に生まれる(幼名は竜駒)。
剣術を薬丸自顕流の薬丸兼義に、合伝流兵学を初め伊敷村の石沢六郎、後に荒田村の
法亢宇左衛門に学んで奥義を極めた。合伝流の弟子に西郷従道、高崎五六、淵辺群平、
三島通庸がいる。池上四郎、有馬藤太も薫陶を受けている。のち藩校・造士館の教授となる。
安政6年には精忠組に参加。文久2年、島津久光の上洛に従って京都に上った功績により軍奉行
禁門の変や戊辰戦争で大きな功績を挙げた。白河口の戦いではわずか700の兵で
白河城に拠る、旧幕府軍2,500に圧勝し、また土佐藩の板垣退助と共に母成峠の戦いで
旧幕府軍を大破して会津若松城開城に大きく貢献した。明治期以後は別記参照
征韓論争では征韓側につく。対立していた左院議長の後藤象二郎が下野したことで、
同副議長の伊地知が代わって議長に就任したためである。のちに参議を兼任し、修史館総裁
、一等侍講宮中顧問官などを歴任。西南戦争終戦後鹿児島に帰国し、
明治19年(1886年)に58歳で死去。
|
黒田 清隆
 |
天保11年10月16日(1840年11月9日) - 明治33年(1900年)8月23日)
薩摩藩士・黒田仲佐衛門清行の長男として生まれた。黒田家は家禄わずか4石の
下級武士だった。文久2年(1862年) 6月の生麦事件には、随行の一人としていあわせたが、
自らは武器を振るわず、抜刀しようとした人を止めたという。なお、黒田自身は示現流門下でも
有数の使い手
慶応4年(1868年)の鳥羽・伏見の戦いでは薩摩藩の小銃第一隊長として戦った。
同年3月、北陸道鎮撫総督・高倉永祜の参謀に、山縣有朋とともに任命され、
鯨波戦争に勝利した。
明治2年(1869年)1月に軍務官出仕に任命された。箱館戦争がはじまると、黒田は2月に
清水谷公考中将の参謀を命じられ、途中、宮古湾停泊中に宮古湾海戦に際会した
明治期以後は別記参照
|
五代 友厚
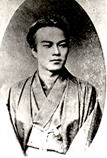 |
天保6年12月26日-明治18年(1885年)9月25日五代直左衛門秀尭の次男として
鹿児島城下で生まれる。質実剛健を尊ぶ薩摩の気風の下に育てられ、8歳になると児童院の
学塾に通い、12歳で聖堂に進学して文武両道を学ぶ。安政2年(1855年)、藩の郡方書役助
(当時の農政を司る役所の書記官の補助)となる。その翌年、長崎海軍伝習所へ藩伝習生として
派遣され、オランダ士官から航海術を学ぶ。文久3年7月、生麦事件によって発生した
薩英戦争では、3隻の藩船ごと松木洪庵(寺島宗則)と共にイギリス海軍の捕虜となるが、通弁の
清水卯三郎のはからいにより、横浜において、小舟にてイギリス艦を脱出、江戸に入る、慶応元年、
寺島宗則・森有礼らとともに薩摩藩遣英使節団として英国に出発、欧州各地を巡歴
慶応2年、御小納戸奉公格に昇進し薩摩藩の商事を一気に握る会計係に就任。
慶応4年(1868年)、戊辰戦争が勃発し五代は西郷隆盛や大久保利通らとともに
倒幕に活躍した。その結果、明治元年(1868年)に明治新政府の参与職外国事務掛となる。
外国官権判事、大阪府権判事兼任として大阪に赴任し、堺事件、
イギリス公使パークス襲撃事件などの外交処理にあたった。 明治期以後は別記参照
|
篠原 国幹
しのはらくにもと |
天保7年12月5日(1837年1月11日) - 明治10年(1877年)3月4日)
平之馬場町中小路で篠原善兵衛の子として生まれる。
諱(名)は国幹、通称は藤十郎、冬一郎という。
剣術ははじめ薬丸兼義に薬丸自顕流を、次いで和田源太兵衛に常陸流を学ぶ。
文久2年、有馬新七らと挙兵討幕を企てたが、島津久光の鎮圧にあって失敗した(寺田屋騒動)
戊辰戦争のとき、薩摩藩の城下三番小隊の隊長となって鳥羽・伏見の戦いに参戦し、その後、
東征軍に従って江戸に上った。 明治期以後は別記参照
|
桐野 利秋
中村 半次郎 |
天保9年(1838年)12月 - 明治10年(1877年)9月24日)
吉野村実方(現在の鹿児島市吉野町)で城下士の中村与右衛門(桐野兼秋)の
第三子として生まれる。
文久2年(1862年)3月、島津久光に随って上京、尹宮(朝彦親王)附きの守衛となった。
人切り半次郎と有名、戊辰戦争(明治元年、1868年)では、城下一番小隊に属して伏見の戦いで
御香宮に戦い、功をもって小隊の小頭見習いを務めた。
会津藩降伏後の開城の式では、官軍を代表して城の受け取り役を務めた。
明治期以後は別記参照
|
村田 新八
|
天保7年11月3日(1836年12月10日) - 明治10年(1877年)9月24日)
加治屋町山之口馬場(高見馬場方限)で高橋八郎の第三子として生まれ、幼にして
村田十蔵(経典)の養子となった。村田は年少のときから西郷隆盛に兄事し、尊王の志を抱いた。
京都挙兵(寺田屋騒動)を煽動したと久光から疑われ、呼び戻されて西郷は徳之島へ、
村田は喜界島(薩摩硫黄島(鬼界ヶ島)ではない)へ遠島された。
元治元年(1864年)、赦免された西郷は途中、喜界島へ寄って村田を鹿児島へ連れ帰った。
東征大総督府の下参謀となった西郷は、中村半次郎(一番小隊長)・村田新八(二番小隊長)・
篠原国幹(三番小隊長)らで構成される先鋒隊を指揮して2月25日に駿府、27日に
小田原へ進んだ。上野戦争の後は二番小隊を率いて東山道軍の応援に赴き、
5月26日の白河奪還戦(棚倉口を担当)、二本松戦を経て、会津若松城攻囲戦に参加した。
明治期以後は別記参照
|
海江田 信義
かいえだのぶよし
有村俊斎 |
天保3年2月11日(1832年3月13日) - 明治39年(1906年)10月27日)
薩摩藩士・有村仁左衛門兼善の次男として生まれた(幼名は太郎熊)。
11歳の時、島津斉興の茶頭に出仕して茶坊主となり、俊斎と称した。はじめ東郷実明に
示現流剣術を学び、次いで薬丸兼義に薬丸自顕流剣術を学んだ。嘉永2年、薩摩藩の内紛
(お由羅騒動)に巻き込まれた有村父子は一時藩を追われ家は貧困の極みに陥るが、
嘉永4年(1851年)、新藩主・島津斉彬によって藩に復帰、このとき
俊斉は西郷吉之介、大久保利通、伊地知正治、税所篤、吉井友実らと「精忠組」を結成
文久元年(1861年)12月、日下部伊三治(安政の大獄で捕縛され獄死)の次女・まつを娶り、
同時に婿養子となって海江田武次信義と改名(海江田は日下部の旧姓)。
生麦事件において久光の行列を遮って斬られ瀕死となっていた
イギリス人・チャールス・リチャードソンに止めを刺した。戊辰戦争では、
東海道先鋒総督参謀となる。江戸城明け渡しには新政府軍代表として西郷を補佐
明治期以後は別記参照 |
有村 雄助
ありむらゆうすけ |
天保6年(1835年) - 万延元年3月24日、薩摩藩士・有村兼善の三男として生まれる。兄に
海江田信義(有村俊斎)、弟に・有村次左衛門がいる。安政5年次左衛門とともに脱藩して江戸
で尊攘活動を行い、水戸藩士高橋多一郎らの志士と交流を深める。安政6年安政の大獄が
起きるとそれに憤慨し、その実行者である大老井伊直弼の暗殺と京都・大坂での
挙兵を計画する。幕府によって藩士が捕らえられることを恐れた薩摩藩では、道中の
伊勢四日市で有村らを捕縛し、すぐに薩摩に護送した。万延元年3月24日、幕府の探索が
鹿児島に迫ると、藩命によって自刃させられた。享年26。
|
有村
次左衛門
ありむら
じざえもん |
天保9年12月28日(1839年2月11日) - 安政7年3月3日(1860年3月24日))
薩摩藩士・有村兼善の四男。兄に有村俊斎(後の海江田信義)、有村雄助がいる。
剣術は薬丸兼義に薬丸自顕流を学び、後に江戸で北辰一刀流を修めた。
安政5年、兄・雄助とともに江戸で尊攘活動を行い、水戸藩士らの志士と交流を深める。
安政7年3月3日の朝、桃の節句祝いに登城する井伊を狙って江戸城桜田門外で行列を襲撃
(桜田門外の変)した。自身は行列中央の井伊を襲い、篭より引きずり出して断首殺害した。
井伊の首級を持ち去ろうとしたが、彦根藩士・小河原秀之丞に斬り付けられて重傷を負い、
小河原を斬り伏せるも若年寄・遠藤胤統の辻番所付近で力尽きて自害。
|
高崎 正風
たかさきまさかぜ |
天保7年7月28日(1836年9月8日) - 明治45年(1912年2月28日)
薩摩藩士高崎五郎右衛門温恭の長男。1849年嘉永2年、お由羅騒動によって父五郎右衛門が
切腹し、翌嘉永3年)正風も連座して奄美大島に流刑となった。1852年(嘉永5年)赦免され
幕末の京都で活動し、薩会同盟の立役者となる。その功により京都留守居役に任命されるが、
武力討幕に反対して西郷隆盛らと対立し、維新後は不遇をかこった。
明治2年(1869年)から明治4年で、薩摩藩の垂水(現 鹿児島県垂水市)の行政管理をし、
明治4年に新政府に出仕。岩倉使節団の一員に任じられ、2年近く欧米諸国を視察。
明治維新後
明治8年(1875年)宮中の侍従番長 、 明治23年(1890年)初代國學院院長
明治28年(1895年)、枢密顧問官を兼ねた。、 明治45年(1912年)2月28日死去
|
奈良原 繁
ならはらしげる |
天保5年5月23日(1834年6月29日) - 大正7年(1918年)8月13日)
薩摩藩出身。諱は混。幼名は三次。通称喜八郎。名乗りは幸五郎 兄・喜左衛門
生麦事件では、リチャードソンに斬りつけたのは、兄の喜左衛門ではなく、弟の繁であると
子孫から異議が申したてられている。薩英戦争には、兄の喜左衛門が加わっているが、
弟の繁は加わっていない。西郷隆盛らの討幕路線に反対していたため、藩政改革のため、
側役まで出世した藩政から退けられる。
明治期以後は別記参照
|
森 有礼
もり ありのり |
弘化4年7月13日(1847年8月23日) - 明治22年(1889年)2月12日)
薩摩藩士・森喜右衛門有恕の五男として生まれた。兄に横山安武がいる。
安政7年頃より造士館で漢学を学び、元治元年頃より藩の洋学校である開成所に入学し
慶応元年、五代友厚らとともにイギリスに密航、留学し、ロンドンで長州五傑と会う。
明治期以後は別記参照
|
西郷 従道
さいごうじゅうどう |
天保14年5月4日(1843年6月1日) - 明治35年(1902年)7月18日)
加治屋町山之口馬場(下加治屋町方限)に生まれる。兄は西郷吉之助剣術は薬丸兼義に
薬丸自顕流を、兵学は伊地知正治に合伝流を学んだ。有村俊斎の推薦で
薩摩藩主・島津斉彬に出仕し、茶坊主となって竜庵と号する。文久元年(1861年)9月30日に
還俗し、本名を隆興、通称を信吾(慎吾)と改名。斉彬を信奉する精忠組に加入し、
尊王攘夷運動に身を投じる。
文久2年(1862年)、勤王倒幕のため京に集結した精忠組内の有馬新七らの一党に参加するも
寺田屋事件で藩から弾圧を受け、従道は年少のため帰藩謹慎処分となる。
文久3年(1863年)、薩英戦争が起こると謹慎も解け、西瓜売りを装った決死隊に志願。
戊辰戦争では、鳥羽・伏見の戦いで貫通銃創の重傷を負うも、各地を転戦した。
明治2年(1869年)、山縣有朋と共に渡欧し軍制を調査。明治3年(1870年)7月晦日、横浜に帰着。
同年8月22日に兵部権大丞に任じられ、正六位に叙せられる。明治4年(1871年)7月、陸軍少将
明治期以後は別記参照
|
大山 巌
おおやまいわお |
天保13年10月10日(1842年11月12日) - 大正5年(1916年)12月10日)
加治屋町柿本寺通(下加治屋町方限)に薩摩藩士・大山綱昌(彦八)の次男として生まれた。
幼名は岩次郎。通称は弥助 西郷隆盛・従道の従弟
同藩の有馬新七等に影響されて過激派に属したが、文久2年(1862年)の寺田屋事件では
公武合体派によって鎮圧され、大山は帰国謹慎処分となる。薩英戦争に際して謹慎を解かれ、
砲台に配属された。戊辰戦争では新式銃隊を率いて、鳥羽・伏見の戦いや会津戦争などの
各地を転戦。12ドイム臼砲や四斤山砲の改良も行い、これら大山の設計した砲は「弥助砲」と
称された。会津戦争では薩摩藩二番砲兵隊長として従軍していたが、負傷する。狙撃は
山本八重とも言われる
維新後の明治2年、渡欧して普仏戦争などを視察。明治3年から6年の間はジュネーヴに留学
明治期以後は別記参照
|
川村 純義
かわむらすみよし |
天保7年11月11日(1836年12月18日) - 明治37年(1904年)8月12日)
安政2年(1855年)に江戸幕府が新設した長崎海軍伝習所へ、薩摩藩より選抜されて入所。
慶応4年1月にはじまった戊辰戦争では薩摩藩4番隊長として各地、特に会津戦争に奮戦した。
明治期以後は別記参照
|
野津 鎮雄
のづしずお |
天保6年9月5日 - 明治13年7月22日)下級藩士野津七郎鎮圭(4石)の長男として生まれる。
早くして両親を亡くし、弟とともに叔父折田氏に育てられた。
青山愚痴に天山流砲術を、薬丸兼義に薬丸自顕流を学ぶ。文久3年(1863年)、薩英戦争に参加。
青山愚痴配下として沖小島を守る。慶応4年、戊辰戦争では五番隊長となり鳥羽・伏見の戦い、
奥羽・箱館に転戦した。
明治期以後は別記参照
|
野津 道貫
のづみちつら |
天保12年11月5日-明治41年)10月18日) 兄は陸軍中将の野津鎮雄
鹿児島城下高麗町の下級藩士・野津鎮圭の二男として生まれる。幼くして両親を亡くした。
薬丸兼義に薬丸自顕流を学ぶ。戊辰戦争に6番小隊長として参加。
その活躍がめざましく、鳥羽・伏見の戦いから会津戦争、次いで箱館戦争に参戦。
明治期以後は別記参照
|
有馬 藤太
ありま とうた |
天保8年(1837年) - 大正13年(1924年))薩摩藩砲術師範有馬藤太(同名)の長男に生まれる。
小野郷右衛門に飛太刀流を学び、十九歳で師範代になるほどの腕前だった。特に抜刀術を
得意としたという。伊地知正治に引き立てられた。 慶応4年(1868年)1月に戊辰戦争が
勃発すると、東山道総督府の斥候を命じられ、香川敬三率いる一隊に従軍して
宇都宮へ向かった。
明治期以後は別記参照
|
川路 利良
|
天保5年5月11日(1834年6月17日) - 明治12年(1879年)10月13日)
薩摩藩与力(準士分)・川路利愛の長男として比志島村(現在の皆与志町比志島地区)に生ま
薩摩藩の家臣は上士、郷士などに分かれ、川路家は身分の低い準士分であった。
元治元年(1864年)、禁門の変で長州藩遊撃隊総督の来島又兵衛を狙撃して倒すという
戦功を挙げ、西郷隆盛や大久保利通から高く評価された。慶応3年、藩の御兵具一番小隊長に
任命され、西洋兵学を学んだ。慶応4年、戊辰戦争の鳥羽・伏見の戦いに薩摩官軍大隊長として
出征し、
上野戦争では彰義隊潰走の糸口をつくる。東北に転戦し、磐城浅川の戦いで敵弾により
負傷したが、傷が癒えると会津戦争に参加。戦功により明治2年、藩の兵器奉行に昇進した。
明治期以後は別記参照
|
大山 綱良
|
文政8年11月6日(1825年12月15日) - 明治10年(1877年)9月30日)
嘉永2年(1849年)12月26日に大山四郎助の婿養子となる。
西郷隆盛、大久保利通らとともに精忠組に所属。島津久光の上洛に随行し、文久2年の
寺田屋事件では、奈良原喜八郎らとともに過激派藩士の粛清に加わり、事件の中心的役割を
果たした。特に寺田屋2階には大山巌・西郷従道・三島通庸らがいたが、皆で説得を行った結果、
投降させることに成功した。明治元年の戊辰戦争では、奥羽鎮撫総督府の下参謀になった
明治期以後は別記参照
|
益満 休之助
ますみつ
きゅうのすけ |
天保12年(1841年) - 慶応4年5月2日高麗町生まれ。薩摩藩の尊王攘夷派として、
江戸で活動する。万延元年(1860年)には清河八郎が結成した虎尾の会に名を連ねる。
鳥羽・伏見の戦いが勃発した。のち、幕府方により逮捕され処刑される直前に勝海舟によって
身請け・幽閉された。慶応4年(1868年)3月、新政府軍の江戸総攻撃に際し、勝海舟の命を受け、
幕府の使者・山岡鉄舟を駿府総督府へ送る大役を務め、西郷隆盛との会見を成功させた
同年5月の上野戦争で、流れ弾にあたって横浜の野戦病院で最期を遂げたと伝わる。享年28。
|
大迫 貞清
|
1825年6月22日(文政8年5月7日) - 1896年4月27日)
城下平之町に薩摩藩士・山之内立幹の四男として生まれ、大迫貞邦の養子となる
万延元年(1860年)から京都警備に従事。戊辰戦争では、二番遊撃隊隊長、そして
東山道先鋒総督本営付として従軍した。
明治期以後は別記参照
|
種田 政明
たねだまさあき |
天保8年8月(1837年) - 1876年(明治9年)10月24日)
鹿児島城下の高麗町で生まれる。文久2年、島津久光の上洛に従い、中川宮朝彦親王付の
護衛となった、戊辰戦争にも参加した。
明治期以後は別記参照
|
池上四郎
|
天保13年(1842年) - 明治10年9月24日)薩摩藩侍医・池上貞斎の第一子として生まれる。
医術を好まず、西郷隆盛(吉之助)・伊地知正治の教導を受け、勤王の志を抱いた。
安政の大獄の前頃、藩主・島津斉彬の命によって江戸に遊学し、時々天下の情勢を
藩主に報告した。
薩英戦争(1863年)のときはスイカ売り決死隊に志願して英艦に切り込もうとしたが失敗、
戊辰戦争(1868年)では鳥羽・伏見の戦いに城下十番小隊の監軍として参戦したが、東山道軍が
結成されて以後は参謀・伊地知正治の下で軍議に参画し、白河城攻防戦、棚倉・二本松攻城戦、
会津若松攻城戦では直接戦闘に参加した。
明治期以後は別記参照
|
永山弥一郎
|
天保9年(1838年) - 明治10年(1877年)4月13日)
永山休悦の第1子として薩摩国鹿児島郡荒田村(現在の鹿児島市上荒田町など)に生まれる。
弥一郎は若くして勤王の志を抱き、これに奔走した。文久2年有馬新七らに従って京都に上り、
挙兵に荷担して失敗(寺田屋騒動)したが、年少であるという理由で処罰を免れた。
戊辰戦争のときは、城下四番小隊(隊長は川村純義)の監軍として鳥羽・伏見の戦いに参戦した。
白河城陥落後は棚倉に転戦した。この棚倉戦で重傷を負い、横浜病院に送られたが、
療養途中に全治と称して無理矢理に隊に帰った。
明治期以後は別記参照
|
伊東 祐亨
いとうすけゆき |
天保14年5月12日(1843年6月9日) - 大正3年(1914年)1月16日)
薩摩藩士・伊東祐典の四男として鹿児島城下清水馬場町に生まれる。飫肥藩主伊東氏に
連なる名門の出身である。開成所にてイギリスの学問を学んだ。
勝海舟の神戸海軍操練所では塾頭の坂本龍馬、陸奥宗光らと共に航海術を学ぶ。
薩英戦争にも従軍。鳥羽・伏見の戦い前の薩摩藩邸焼き討ち事件で江戸から脱出し、
戊辰戦争では旧幕府海軍との戦いで活躍した。明治期以後は別記参照
|
伊牟田 尚平
いむたしょうへい |
天保3年5月25日(1832年6月23日) - 慶応4年(1868年)2月)
天保3年(1832年)、喜入郷の領主・肝付氏の家臣の息子として生まれた。
万延元年(1860年)、脱藩して江戸に出る。そしてアメリカ公使館員のヘンリー・ヒュースケン
暗殺など、各地で外国人を殺傷した。このため、薩摩藩の追捕を受けて捕らえられ、
鬼界ヶ島に流罪に処された。
後に罪を許され、益満休之助と共に江戸市中で江戸城二の丸に放火するなどの
破壊工作を行い、江戸幕府を挑発するのに一役買った。これは幕府が大政奉還したために
武力討伐の理由がなくなったため、薩摩藩などが大義名分を求めて幕府を挑発し、
挙兵させようとしたためである。
その後上洛したが、部下の辻斬りなど様々な罪を着せられて、詰め腹を切らされる形で
慶応4年(1868年)に切腹させられた。享年37才
生誕地である鹿児島市喜入に、「伊牟田尚平の誕生地記念碑」が、
1923年(大正12年)に建てられた。
|
有馬新七
ありましんしち |
文政8年11月4日(1825年12月13日) - 文久2年4月23日(1862年5月21日))
真影流(直心影流)と崎門学派を学び文武両道の俊傑とうたわれた。薩摩藩伊集院郷の
郷士・坂木四郎兵衛の子として薩摩国日置郡伊集院郷古城村で生まれるが、
父が城下士の有馬家の養子となったため、新七もそのまま城下士となり、城下の
加治屋町に移住した
尊皇攘夷派の志士達と多く交流して水戸藩とともに井伊直弼暗殺(桜田門外の変)を謀ったが、
自藩の同意を得られなかったため手を退き、結果的に水戸藩を裏切る形となった。
その後も過激な尊皇攘夷活動を続け、同志達と共に寺田屋に集っていたところを、
同じ薩摩藩士らによって粛清された(寺田屋事件)。この際、小刀が折れて相手の
道島五郎兵衛の懐に入り壁に押し付けた状態で橋口吉之丞に「オイゴト刺セ、オイゴト刺セ」
(俺ごと刺せ)として最期を遂げた。享年38。
|
田中 新兵衛
|
天保3年(1832年) - 文久3年5月26日(1863年7月11日)) 幕末の四大人斬りの一人。
元々は武士の生まれではなく、鹿児島の伝承では薩摩前の浜の船頭の子
(又、薬種商の子)と言われる
文久2年(1862年)5~6月に上京。海江田信義や藤井良節(藤井良蔵)の元に身を寄せた。
土佐勤王党の武市瑞山と引き合わされ、武市と義兄弟の契りを結んだ。以後、新兵衛は
岡田以蔵などと徒党を組み、暗殺を示唆された相手を次々と手にかけるようになった。
本間精一郎、渡辺金三郎、大河原重蔵、森孫六、上田助之丞などを暗殺したと言われるが、
真意不明、文久3年(1863年)8月21日、朔平門外の変で姉小路公知が複数名に襲撃されて
暗殺された。この事件の現場で投げつけられ、残されていた刀が新兵衛の愛刀であり、
薩摩下駄も残されていたことによって、新兵衛が犯人と断定されて捕縛された。通説では
刀は数日前に盗まれたものというが信憑性は不明。町奉行の永井主水正は、新兵衛を
尋問しようとしたが、新兵衛は一言も発せず隙をついて突然自刃し、頸動脈を突いて
即死したため供述は得られなかった。
|
税所 篤
ざいしょあつし |
文政10年11月5日(1827年12月22日)- 明治43年(1910年)6月21日)
薩摩藩士・税所篤倫の次男として生まれる。幼少期の生活は貧しいものであったが、
実兄の篤清が吉祥院住職として島津久光の寵遇を受けるに従い、
税所家の暮らしぶりは好転した
精忠組の中心メンバーとして、幼少期からの親友で郷中仲間であった西郷隆盛や大久保利通、
吉井友実らと行動を共にする。禁門の変では小松帯刀率いる薩摩軍の参謀として一隊を率いて
参戦、3発の銃弾を浴びる重傷を負いながらも、長州藩の敵将国司親相の部隊を
退却させるなど武功を上げた
明治期以後は別記参照
|
樺山三円
かばやまさんえん |
藩主島津斉彬の茶坊主として機密の用を務める傍ら、同時期に江戸に出た有村俊斎、
大山格之助、税所篤ら藩内の改革派と親交を深める。水戸藩の藤田東湖、戸田蓬軒らの
影響を受け、安政元年には出府した西郷吉之助を藤田に引き合わせた。
1859年には薩摩精忠組に加入、桜田門外の変の計画にも当初関与するが、決行には
加わらず帰国し、以後は主に在国にて他藩との連絡活動に従事した。
文久元年(1861年)江戸において、武市瑞山、久坂玄瑞らと会見したのもその一端であり、
薩摩、長州、水戸、土佐各藩の藩士間の相互提携に貢献した。
|
中井 弘
|
天保9年11月29日(1839年1月14日) - 明治27年(1894年)10月10日)
薩摩藩鹿児島城下に藩士・横山休左衛門(詠介)の長子として生まれる
藩校の造士館に学ぶ。祖父の代までは藩の重職にあったが、父の代には没落し経済的に
困窮していた、その後、脱藩して京都に行き浪人となるが、後藤象二郎や坂本龍馬らに
その剛毅な性格を愛され、彼らが工面した資金で、1866年11月に土佐の結城幸安とともに、
イギリスへ密航留学する。1867年春に帰国。その後、宇和島藩周旋方として京都で活躍。
中井弘三と改名し、1868年1月、外国事務各国公使応接掛となる
同年3月のイギリス公使・パークス襲撃事件では、パークス一行の護衛として襲撃犯の一人
朱雀操と斬り合い、自身も頭部に傷を負いながらも朱雀の胸部を刺し、後から駆けつけた後藤に
朱雀が斬られて倒れたところを首を刎ねた。
パークスらを救った功績により、後藤と共にイギリス・ビクトリア女王から宝刀を贈られた。
明治期以後は別記参照
|
赤塚 源六
あかつかげんろく |
天保5年(1834年)10月 - 明治6年(1873年)6月12日)
薩摩藩士、赤塚真矩の四男として生れる。安政6年(1859年)、精忠組結成に参加。
過激な尊皇思想のもと活動を続け、慶応3年(1867年)の王政復古を前にして長崎に赴き
軍艦「春日丸」を購入。前艦長松方正義の後任となって艦長に就任した。
明治2年に箱館戦争が勃発すると海戦にほぼ参戦し、特殊任務として弁天台場・七重浜に
かけて仕掛けてあった旧幕府軍の水雷を除去した。
維新後は海軍大佐までに昇進する。明治6年、死去。享年40
|
三島 通庸
みしま みちつね |
天保6年6月1日) - 明治21年10月23日)薩摩藩士・三島通純の長男として生まれる。
三島家は藩の鼓指南役の家柄であったが、示現流剣術を学ぶとともに伊地知正治から
兵学を学んだ。寺田屋事件に関与して謹慎を命じられるが、のちに藩主島津忠義によって
人馬奉行に抜擢され、鳥羽・伏見の戦いでは小荷駄隊を率いるなど活躍した。
戊辰戦争後は藩政改革に参加する
明治期以後は別記参照
|
橋口 伝蔵
はしぐち でんぞう |
天保2年(1831年) - 文久2年4月23日(1862年5月21日))
幕末の薩摩藩士。同藩士橋口兼器の次男、天保2年(1831年)鹿児島城下で誕生。江戸で
安井息軒に学び、後に江戸藩邸の記録書記となった。
文久2年(1862年)橋口壮介らと江戸を脱して上洛し、有馬新七らと佐幕派の九条尚忠や
酒井忠義襲撃を画策する。しかし京都寺田屋で集合中に島津久光に派遣された鎮撫使側の
奈良原繁らによって斬殺された。(寺田屋事件)
|
柴山 愛次郎
しばやま あいじろう |
天保7年(1836年) - 文久2年4月23日(1862年5月21日))
幕末の薩摩藩士。同藩医柴山良庵の次男。名は道隆、鹿児島城下高見馬場で誕生。
兄に尊王志士柴山良助、弟に海軍大将柴山矢八がいる
幼少より文武を修め、藩政では記録書書記、造士館訓導を歴任する。その後、尊王攘夷を
志して諸国を遊学して見聞を広める。文久2年(1862年)橋口壮介らと鹿児島を脱し、大坂で
有馬新七らと九条尚忠・酒井忠義襲撃を謀議する。しかし島津久光の派遣した鎮撫使の
襲撃に遭い、山口金之進に斬殺された。寺田屋事件の悲報を聞いた西郷隆盛は橋口や
柴山の死を悲しんだと言われている。
|
森岡 昌純
もりおか まさずみ |
1834年1月10日(天保4年12月1日) - 1898年(明治31年)3月27日
城下樋ノ口通で薩摩藩士の家に生まれる
文久2年4月23日寺田屋事件において島津久光の命を受け薩摩藩尊皇派を鎮撫した
明治期以後は別記参照
|
松方 正義
まつかた まさよし |
天保6年2月25日(1835年3月23日) - 大正13年(1924年)7月2日)
松方正恭、袈裟子の四男として生まれる。わずか13歳にして両親を亡くす
島津久光の側近として生麦事件、寺田屋事件等に関係した。
慶応2年(1866年)、軍務局海軍方が設置され御船奉行添役と御軍艦掛に任命される。
明治期以後は別記参照
|
高島 鞆之助
たかしま とものすけ |
天保15年11月9日(1844年12月18日) - 大正5年(1916年)1月11日)薩摩藩士・高島喜兵衛の
四男 明治元年(1868年):戊辰戦争に従軍する。
明治期以後は別記参照
|
仁礼 景範
にれ かげのり |
天保2年2月24日(1831年4月6日) - 明治33年(1900年)11月22日)
薩摩藩士の子弟として生まれる。
慶応3年(1867年)に藩命によりアメリカに留学、
明治期以後は別記参照
|
伊集院 兼寛
いじゅういん
かねひろ |
天保9年1月2日(1838年1月27日) - 明治31年(1898年)4月20日)
薩摩藩士伊集院直五郎兼善の嫡男として生まれる。
兼寛は西郷隆盛・西郷従道兄弟や大久保利通らとの関係が深く薩摩藩きっての
行動派の一人として活躍する。 文久2年(1862年)の寺田屋騒動に有馬新七の同志として
討幕計画に参加するも藩主命令により帰順する。謹慎処分を受ける。 文久3年(1863年)の
禁門の変では斥候として参加。戊辰戦争では東山道総督府参謀に任ぜられ各地を転戦する。
明治期以後は別記参照
|
寺島 宗則
てらしま むねのり |
天保3年5月23日)- 1893年(明治26年)郷士・長野成宗の次男として生まれる。
弘化2年(1845年)、江戸に赴き伊東玄朴、川本幸民より蘭学を学び、安政2年(1855年)より
中津藩江戸藩邸の蘭学塾(慶應義塾の前身)に出講する
文久元年(1861年)には、英語力が買われて幕府の遣欧使節団の西洋事情探索要員として、
福澤諭吉、箕作秋坪とともに抜擢された。文久3年(1863年)の薩英戦争においては
五代友厚とともにイギリス軍の捕虜となる。
慶応元年(1865年)、薩摩藩遣英使節団に参加し、再び欧州を訪れる。
明治期以後は別記参照
|
| 土佐藩 |
|
山内 容堂 /
豊信 |
文政10年10月9日(1827年11月27日)-明治5年6月21日(1872年7月26日)
土佐藩連枝の山内南家当主・山内豊著(12代藩主・山内豊資の弟)の長男。土佐藩15代藩主
豊信は門閥・旧臣による藩政を嫌い、革新派グループ「新おこぜ組」の中心人物・吉田東洋を
起用した。老中・阿部正弘に幕政改革を訴えた。阿部正弘死去後、大老に就いた井伊直弼と
将軍継嗣問題で真っ向から対立した。容堂ほか四賢侯、水戸藩主・徳川斉昭らは次期将軍に
一橋慶喜を推していた。
井伊は紀州藩主・徳川慶福を推した。井伊は大老の地位を利用し政敵を排除した。
いわゆる安政の大獄である。結局、慶福が14代将軍・家茂となることに決まった。
容堂はこれに憤慨し、安政6年(1859年)2月、隠居願いを幕府に提出した。
この年の10月には斉昭・春嶽・宗城らと共に幕府より謹慎の命が下った。
明治5年(1872年)、積年の飲酒が元で脳溢血に倒れ、46歳(数え年)の生涯を閉じた。
|
幕末の四賢侯
ばくまつの
しけんこう |
幕末に活躍した次の4人の大名をいう。
福井藩第14代藩主 松平慶永(春嶽)・宇和島藩第8代藩主 伊達宗城
土佐藩第14代藩主 山内豊信(容堂)・薩摩藩第11代藩主 島津斉彬
|
山内 豊範
やまうち とよのり |
弘化3年4月17日(1846年5月12日)-明治19年(1886年)7月13日
第12代藩主・山内豊資の十一男として生まれる。
文久2に豊信の隠居が解かれると、実権は豊信に握られることとなり、豊範の主体性は薄かった。
明治4年(1871年)の廃藩置県後は、鉄道事業や銀行事業などの成立に寄与している。
明治19年(1886年)7月13日、41歳で死去した。
|
|
池 内蔵太
いけ くらた |
天保12年(1841年) - 慶応2年5月2日(1866年6月14日)
土佐藩士の中でも身分の低い微禄の家柄の息子として生まれた。1861年、江戸に出て
安井息軒に師事し、様々な藩の志士と交流した。武市半平太と共に土佐勤王党の
結成に尽力する。土佐藩から脱藩して長州藩に逃げ込み、長州の尊皇攘夷運動に
参加することにしたのである。
そして長州軍の遊撃隊参謀となり、1863年5月10日のアメリカ船砲撃を指揮した。
1864年に長州藩が軍を率いて禁門の変を起こすと、長州軍の忠勇隊を指揮するなどして
活躍している。1866年、長崎から薩摩藩へ小型帆船・ワイルウェフ号を回航する途中で
台風のため難破し、死亡する。享年26。
|
石川 潤次郎
いしかわ
じゅんじろう |
天保7年(1836年) - 元治元年6月5日(1864年7月8日))
幕末期に土佐藩に仕えていた足軽。諱は直義、元治元年、土佐藩の命を受けて
京都黒谷三条家別宅の警備を勤めていた。
同年6月5日、土佐脱藩望月亀弥太を池田屋に訪ねたところ、池田屋事件に巻き込まれて死亡。
享年28才
|
石田 英吉
いしだ えいきち |
天保10年11月8日(1839年12月13日) - 明治34年(1901年)4月8日
土佐藩の医師の家に生まれる。家業を継ぐため大坂の適塾で緒方洪庵に師事し、医術を学んだ。
しかし、志士・吉村寅太郎に心酔し、天誅組に加わって大和挙兵に参陣した。
禁門の変で負傷、三条実美ら有力公卿が都を落ち延びた、いわゆる「七卿落ち」で三条とともに
都を離れた。その後、再び長州に逃れた英吉は、そこで高杉晋作と合流し、
奇兵隊創設に貢献する
明治期以後は別記参照
|
乾 正厚
いぬい まさひろ |
生年未詳 - 明治3年5月22日(1870年6月20日))
ゆえあって片坂限西へ追放処分とされた、本山茂良(彦弥)の嫡男として生まれ、
初名を「本山楠弥太」
1839年(同10年)6月18日、当分敏衛様、郁松様(山内豊矩)附きを仰せ付けられる。
長州兵の入京を阻止せんと薩摩藩士吉井幸輔、久留米藩士大塚敬介らと議して連署の
意見書を朝廷に建白し、その決意を求める(禁門の変)。
1866年(慶応2年)6月に長防探索用を命ぜられ探索方として活躍する
正厚は無嗣子ゆえ板垣退助の次男乾正士を後嗣として家を継がしめた。
|
板垣 退助
乾退助
いたがき たいすけ |
天保8年4月17日(1837年5月21日) - 大正8年(1919年)7月16日)
土佐藩上士(馬廻格・300石)乾正成の嫡男として、高知城下中島町に生まれた。
乾家は武田信玄の重臣であった板垣信方を祖とした家柄である
後藤象二郎とは竹馬の友である。同じ土佐藩の中岡慎太郎とは交誼があったが、
坂本龍馬とは生前に一度も出会ったことは無い、土佐藩の谷干城・毛利恭助らと共に
薩摩藩の西郷吉之助(のちの隆盛)らと武力討幕を議し、薩土密約を結ぶ。戊辰戦争では
土佐勤王党の流れをくむ隊士を集めた迅衝隊総督として土佐藩兵を率い、
東山道先鋒総督府の参謀として従軍した。東北戦争では、三春藩を無血開城させ、
二本松藩・仙台藩・会津藩などを攻略するなどの軍功によって、賞典禄1,000石を賜っている。
(1868年)12月には藩陸軍総督となり、家老格に進んで家禄600石に加増される。
明治期以後は別記参照
|
岩崎 弥太郎
いわさき やたろう |
天保5年12月11日(1835年1月9日) - 明治18年(1885年)2月7日)
地下浪人・岩崎弥次郎と美和の長男として生まれる。幼い頃から文才を発揮し、
村を追放されるが、当時蟄居中であった吉田東洋が開いていた少林塾に入塾。
土佐勤王党の監視や脱藩士の探索などにも従事していた弥太郎は、吉田東洋が
暗殺されるとその犯人の探索を命じられ、同僚の井上佐市郎と共に藩主の江戸参勤に同行
する形で大坂へ赴く。
慶応3年(1867年)、後藤象二郎に藩の商務組織・土佐商会主任・長崎留守居役に抜擢され、
藩の貿易に従事する。明治元年(1868年)、長崎の土佐商会が閉鎖されると
開成館大阪出張所(大阪商会)に移る。
明治期以後は別記参照
|
岡田 以蔵
おかだ いぞう |
天保9年1月20日(1838年2月14日) - 慶応元年閏5月11日(1865年7月3日))
土佐国香美郡岩村に二十石六斗四升五合の郷士・岡田義平の長男として生まれる。
弟に同じく勤王党に加わった岡田啓吉がいる。人切り以蔵
外国船に対する海岸防備のために父・義平が藩の足軽として徴募され、以蔵自身はこの
足軽の身分、武市瑞山(半平太)に師事し、はじめ小野派一刀流(中西派)の麻田直養(勘七)に
剣術を学ぶ。以蔵は瑞山在京時の文久3年1月に脱藩、その後八月十八日の政変で
土佐勤王党は衰勢となる。同志と疎遠になった後は一時期坂本龍馬の紹介で勝海舟の元に
行っていたという逸話が残っている
土佐藩では吉田東洋暗殺・京洛における一連の暗殺に関して首領・武市瑞山を含む
土佐勤王党の同志がことごとく捕らえられていた。以蔵は女も耐えたような拷問に泣き喚き、
間もなく拷問に屈して自分の罪状及び天誅に関与した同志の名を白状し、土佐勤王党の
獄崩壊のきっかけとなる。慶応元年(1865年)閏5月11日に打ち首、獄門となった。享年28。
|
岡本 健三郎
おかもと
けんざぶろう |
天保13年10月13日(1842年11月15日) - 明治18年(1885年)12月26日)
土佐藩士・岡本亀七と寅の間に土佐郡一宮で生まれる。土佐藩下横目を務め、
また坂本龍馬らと交流を持って国事にも奔走する。
慶応3年(1867年)、龍馬とともに由利公正を訪ねて維新後の経済政策を聞き出している。
明治期以後は別記参照
|
片岡 源馬
こうやま くにきよ |
天保7年10月9日(1836年11月7日) - 明治41年(1908年)11月2日)
土佐藩士・永野源三郎の次男として生まれたが、家老深尾氏の家臣・那須橘蔵の養子となって
那須盛馬と称した。文久元年(1861年)、武市瑞山が結成した土佐勤王党に参加するが、
前藩主山内豊信が勤王党弾圧を開始したことから、謹慎に処されている。
元治元年長州藩を頼って脱藩し、後に京都や大坂、十津川などに潜伏して
尊王攘夷活動を推進した。戊辰戦争では嘉彰親王を擁して越後にて柏崎軍監をつとめ、
戦後は慰労金として2万匹を下賜される。
明治期以後は別記参照
|
神山 郡廉
こうやま くにきよ |
1829年2月16日(文政12年1月13日) - 1909年(明治42年)8月20日
土佐藩士・神山久左衛の五男として生まれ、神山左平の養子となる。
吉田東洋により藩の要職に抜擢された。慶応元年(1865年)、大目付に就任。
慶応2年(1866年)、第二次長州征討に当たって、家老・福岡宮内と共に広島に赴き、
幕府からの出兵督促を拒否した。慶応3年10月 (1867年)の大政奉還において、
建白書に連署した王政復古後、慶応3年12月12日(1868年1月3日)、参与に就任。
明治期以後は別記参照
|
北添 佶摩
|
天保6年(1835年)-元治元年6月5日(1864年7月8日))
土佐藩高岡郡岩目地(いわめじ)村の庄屋北添与五郎の五男。16歳で庄屋職をつぎ、
19歳のとき高北九ヶ村の大庄屋となる。
開国に反対して攘夷を唱え、文久3年(1863年)、本山七郎を名乗って江戸へ出て、
大橋正寿の門人となり同志と共に学ぶ。元治元年の池田屋事件に遭遇し死亡した。
この際、新選組によって殺害されたと思われていたが、近年の研究によって自害して
果てたことが判明している。享年30。
|
後藤 象二郎
ごとう しょうじろう |
天保9年3月19日(1838年4月13日) - 明治30年(1897年)8月4日)
土佐藩士・後藤正晴(馬廻格・150石)の長男として高知城下片町に生まれる。
少年期に父を失い義理の叔父・吉田東洋に預けられて育ち、吉田が開いた少林塾に学ぶ。
安政5年(1858年)、吉田東洋の推挙によって幡多郡奉行となる。
文久元年、御近習目付となるが、翌文久2年(1862年)に東洋が暗殺されると任を解かれた。
文久3年勉学のため江戸に出て、開成所で大鳥圭介に英語を学び、会津藩士・高橋金兵衛に
を学んだ。元治元年に藩政に復帰した。前藩主で事実上藩政を執っていた山内容堂の
信頼を得て大監察や参政に就き、公武合体派の急先鋒として活躍した。
次いで慶応2年、藩命を奉じて薩摩、長崎に出張し、上海を視察して海外貿易を研究した。
坂本龍馬と深く交わるようになったのはこの頃である。
薩摩藩の西郷隆盛、大久保利通、小松帯刀らと会談し薩土盟約を締結した。
明治期以後は別記参照
|
小南 五郎
こみなみ ごろう |
文化9年(1812年)10月 - 明治15年(1882年)2月22日)
土佐郡大川筋(現高知市大川筋2丁目)に生まれる。大目付をつとめ、1853年に山内容堂より
側用役として抜擢される。安政の大獄時には、井伊直弼の容堂に対する追及をかわす為に、
小南などの重臣が身代わりとなって幽閉処分を受ける。のちに復帰し大目付に就任するが、
尊皇攘夷主義の土佐勤皇党に協力的だった。だったため、勤皇等弾圧時には任を解かれ、失脚。
勤皇党盟主武市瑞山をはじめ、平井収二郎、間崎哲馬ら同志が相次いで切腹に追い込まれる
中、小南も武士の位を剥奪され、町人と同じ位に落とされるという屈辱的な処罰を受ける。
慶応2年(1867年)に復職し、戊辰戦争に際しては、板垣退助率いる土佐迅衝隊に従軍した。
維新後は土佐に戻り、高知藩権大参事などを務めつつ余生を過ごした。
|
近藤 長次郎
|
天保9年3月7日(1838年4月1日) - 慶応2年1月14日(1866年2月28日))
別名は上杉宋次郎、近藤昶次郎、梅花道人。高知城下の饅頭商人の息子として生まれ、
長次郎自身も饅頭を売り歩いていたため、はじめは苗字がなく饅頭屋長次郎と呼ばれた。
幼少期から聡明で土佐では河田小龍、江戸では安積艮斎らに学んだ。その才能を山内容堂に
も認められて文久3年(1863年)に名字帯刀を許された上で、神戸海軍操練所に入った。
同じく土佐藩出身である坂本龍馬とは仲が良く、龍馬と共に海援隊の前身である亀山社中を
設立した。亀山社中の社中盟約書に違反したとして仲間たちより追及を受けたのち責任をとって
小曽根乾堂邸で切腹した。享年29
|
斎藤 利行
|
1822年2月2日(文政5年1月11日)- 1881年(明治14年)5月26日)
旧名は渡辺 弥久馬(わたなべ やくま)。同藩士・斎藤利成の子
若くして藩主山内豊煕の御側物頭として仕えるが、おこぜ組に加わったことから(天保14年)に
反対派によって失脚させられる。後に吉田東洋の命によって復職し、近習目付、上士銃隊
総練教授などを歴任後、慶応年間には仕置役・家老となる。明治期以後は別記参照
|
坂本 権平
|
文化11年(1814年) - 明治4年7月8日(1871年8月23日)坂本直足の長男として生まれる。
坂本龍馬の兄。龍馬とは21歳の年齢差がある。安政2年(1856年)12月4日に父の直足が死去し
当主となり、幼き頃の龍馬の父代わりとなった。龍馬の土佐藩脱藩には断固反対の立場を
取っていたが、のちに理解を示し、資金援助という形で龍馬の志士活動を陰で支えた。
|
坂本 龍馬
 |
天保6年11月15日(新暦・1836年1月3日) - 慶応3年11月15日(新暦・1867年12月10日))
土佐郷士株を持つ裕福な商家に生まれ、脱藩した後は志士として活動し、貿易会社と
政治組織を兼ねた亀山社中(後の海援隊)を結成した。薩長同盟の斡旋、大政奉還の成立に
尽力するなど倒幕および明治維新に影響を与えた。大政奉還成立の1ヶ月後に
近江屋事件で暗殺された。
嘉永元年に日根野弁治の道場に入門して小栗流を学び、嘉永6年、龍馬は剣術修行の
ための1年間の江戸自費遊学を藩に願い出て許された。
北辰一刀流の桶町千葉道場(現: 東京都中央区)の門人となる。
剣術修行の傍ら龍馬は当代の軍学家・思想家である佐久間象山の私塾に入学した
そこでは砲術、漢学、蘭学などの学問が教授されていた。
龍馬の脱藩は文久2年(1862年)3月24日のことで、当時既に脱藩していた沢村惣之丞や、
那須信吾(後に吉田東洋を暗殺して脱藩し天誅組の変に参加)の助けを受けて
土佐を抜け出した。
文久2年12月9日、春嶽から幕府軍艦奉行並・勝海舟への紹介状を受けた龍馬と門田為之助・
近藤長次郎は海舟の屋敷を訪問して門人となった。
薩長同盟成立慶応2年1月8日、小松帯刀の京都屋敷において、桂と西郷の会談が開かれた。
船中八策に基づいた王政復古を目標となす薩土盟約が成立した。
慶応3年(11月15日)京都の近江屋で中岡慎太郎と共に刺客に襲撃され暗殺される。 |
佐佐木 高行
|
文政13年10月12日(1830年11月26日) - 明治43年(1910年)3月2日)
土佐藩士・佐々木高順(100石)の二男として生れる。剣術を麻田直養(勘七)に学び、
山鹿流兵学を窪田清音の門下生である若山勿堂から習得、国学を鹿持雅澄に学んだ。
鹿持の同門であった尊皇攘夷派・武市半平太などとも交流。藩主・山内豊信(容堂)の側近と
して藩政をリードし、慶応3年(1867年)には上洛して後藤象二郎・坂本龍馬と薩土盟約の
吟味および大政奉還の建白について協議している。
明治期以後は別記参照
|
沢村 惣之丞
さわむら
そうのじょう |
天保14年(1843年) - 慶応4年1月25日(1868年2月18日))
別名に沢村延世・前河内愛之助・関雄之助などがある。
土佐国土佐郡潮江村の子として生まれる。
間崎哲馬に師事し、学問を学ぶ。その後土佐勤王党に加入した。
文久2年(1862年)に吉村虎太郎と共に土佐藩を脱藩する。
慶応3年には坂本龍馬暗殺(近江屋事件)の容疑者であった三浦休太郎の暗殺計画に
参加するが、失敗に終わった(天満屋事件)翌年には維新の混乱から無人状態となった
長崎奉行所に、沢村ら海援隊の人間が中心となって入居、長崎の町を警備した。しかし1月14日の
警備中、薩摩藩士・川端平助を誤殺してしまう。沢村は薩摩藩との軋轢を恐れ、海援隊本部で、
薩摩藩関係者の制止にもかかわらず割腹した享年26。
|
ジョン万次郎
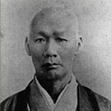 |
文政10年1月1日(1827年1月27日) - 明治31年(1898年)11月12日)
土佐国中濱村(現在の高知県土佐清水市中浜)の半農半漁の家の次男に生まれた。
天保12年、手伝いで漁に出て嵐に遭い、漁師仲間4人と共に遭難、5日半の漂流後奇跡的に
伊豆諸島の無人島鳥島に漂着し143日間生活した。そこでアメリカの捕鯨船ジョン・ハウランド号に
仲間と共に救助される。ホイットフィールド船長の養子となって一緒に暮らし、(天保15年には
オックスフォード学校、1844年(弘化元年)にはバーレット・アカデミーで英語・数学・測量・航海術・
造船技術などを学ぶ。1850年12月17日、上海行きの商船に漁師仲間と共に乗り込み、購入した
小舟「アドベンチャー号」も載せて日本へ向け出航した。嘉永4年(1851年)2月2日、薩摩藩に
服属していた琉球にアドベンチャー号で上陸を図り、番所で尋問を受けた後に薩摩本土に
送られた。海外から鎖国の日本へ帰国した万次郎達は、薩摩藩の取調べを受ける。薩摩藩では
万次郎一行を厚遇し、開明家で西洋文物に興味のあった。藩主・島津斉彬は自ら万次郎に
海外の情勢や文化等について質問した。嘉永5年(1852年)、漂流から11年目にして故郷に
帰る事が出来た。帰郷後すぐに、万次郎は土佐藩の士分に取り立てられ、藩校「教授館」の
教授に任命された。
万延元年(1860年)、日米修好通商条約の批准書を交換するための遣米使節団の1人として
咸臨丸に乗りアメリカに渡る。
慶応2年、土佐藩の開成館設立にあたり、教授となって英語、航海術、測量術などを教える。
明治維新後の明治2年、明治政府により開成学校(現・東京大学)の英語教授に任命される。
明治31年(1898年)、72歳で死去。 |
新宮 馬之助
しんぐう うまのすけ |
天保7年(1836年) - 明治19年(1886年)
高知で河田小龍に師事し、学問や絵を学ぶ(この頃の塾生に近藤長次郎がいる)。
その後「焼継業修業」のため江戸へ遊学する。
遊学中に坂本龍馬の誘いで勝海舟に師事し、その後は龍馬と行動を共にする。
神戸海軍操練所で航海術を学んだ後、長崎で結成された亀山社中(のちの海援隊)に参加した。
薩長同盟を締結した際には、龍馬らとともに調停役として同席する。
その後、海援隊の中心メンバーとして活躍する。維新後は浦賀にあった海兵団に所属、
海軍大尉まで出世する。長崎市で死去。享年51。
|
菅野 覚兵衛
すがの かくべい |
天保13年旧10月21日(1842年11月23日) - 明治26年(1893年)5月30日
土佐藩の庄屋・千屋民五郎の三男として和食(わじき、現安芸郡芸西村和食)に生まれる。
土佐勤王党に加盟し勤王活動を始める。文久2年、山内容堂を警護する五十人組に参加し
上京する。その時坂本龍馬らともに勝海舟の弟子となる。勝の進言によって幕府が神戸に
設置した神戸海軍操練所にも参加した。慶応4年(1868年)3月、生前の龍馬の希望もあり
長崎でお龍の妹・起美と結婚。その後戊辰戦争に従軍し奥羽地方を転戦。
終結後の明治元年から小松清廉の取計いで元海援隊隊士・白峰駿馬とともに
アメリカ合衆国に渡りニュージャージー州のラトガース大学に留学。
横須賀鎮守府建築部長などを歴任して海軍少佐となる。
明治26年(1893年)に死去。享年52
|
武市 瑞山
たけち ずいざん
武市 半平太 |
文政12年9月27日(1829年10月24日)-慶応元年閏5月11日(1865年7月3日)
土佐国吹井村(現在の高知市仁井田)に生まれる。武市家は元々土地の豪農であったが、
半平太より5代前の半右衛門が享保11年に郷士に取り立てられ、文政5年には白札格に昇格。
天保12年(1841年)、一刀流・千頭伝四郎に入門して剣術を学ぶ,優れた剣術家であったが、
黒船来航以降の時勢の動揺を受けて攘夷と挙藩勤王を掲げる土佐勤王党を結成。
参政・吉田東洋を暗殺して藩論を尊王攘夷に転換させることに成功した。
京都と江戸での国事周旋によって一時は藩論を主導し、京洛における尊皇攘夷運動の
中心的役割を担ったが、八月十八日の政変により政局が一変すると前藩主・山内容堂によって
投獄される。1年8ヶ月20日の獄中闘争を経て切腹を命じられ、土佐勤王党は壊滅した。
即日刑が執行され、以蔵ら4名は獄舎で斬首。切腹を命じられた半平太は体を清めて
正装した後、同日20時頃に南会所大広庭にて、未だ誰も為しえなかったとも言われてきた
三文字割腹の法を用いて法式通り腹を三度かっさばき、前のめりになったところを両脇から
二名の介錯人に心臓を突かせて絶命した。享年37。
|
田中 光顕
たなか みつあき |
天保14年閏9月25日(1843年11月16日) - 1939年(昭和14年)3月28日)
土佐藩の家老深尾家々臣である浜田金治の長男として、(現・高岡郡佐川町)に生まれた。
土佐藩士武市半平太の尊王攘夷運動に傾倒してその道場に通い、土佐勤王党に参加した。
叔父の那須信吾は吉田東洋暗殺の実行犯だが、光顕も関与した疑いもある。
翌元治元年(1864年)には同志を集めて脱藩。のち高杉晋作の弟子となって長州藩を頼る。
薩長同盟の成立に貢献して、薩摩藩の黒田清隆が長州を訪ねた際に同行した。
慶応3年(1867年)、中岡が坂本龍馬と共に暗殺(近江屋事件)されると、その現場に駆けつけて
重傷の中岡から経緯を聞く。中岡の死後は副隊長として同隊を率い、鳥羽・伏見の戦い時では
高野山を占領して紀州藩を威嚇、戊辰戦争で活躍した。
明治期は別記参照
|
谷 干城
たに たてき |
天保8年2月12日(1837年3月18日) - 明治44年(1911年)5月13日)
儒学者・谷景井(萬七)の四男として土佐国高岡郡窪川に生まれた。
安政6年、江戸へ出て安井息軒、安積艮斎の弟子となり、帰国した後は藩校致道館で
史学助教授となる。
文久元年、武市半平太と知り合って尊王攘夷に傾倒する。慶応2年(1866年)の長崎視察の際
藤象二郎や坂本龍馬と交わる。明治元年の戊辰戦争では、板垣退助の率いる迅衝隊の
大軍監として北関東・会津戦線で活躍する。明治3年(1870年)に仕置役(参政)や
少参事として藩政改革に尽力した。
明治期は別記参照
|
寺村 道成
てらむら みちなり |
天保5年6月24日(1834年7月30日) - 明治29年(1896年)7月27日)
土佐藩士・寺村主殿成相(中老・700石)の三男として生まれる。ははじめ麟三郎、のち左膳。
文久2年(1862年)2月5日、安政の大獄以来隠居していた前藩主・山内容堂から召され、
側用人となる。山内容堂の前において、武闘派の乾退助と時勢について対論をすることになり、
寺村は穏健な公武合体論を述べ、乾退助は尊皇攘夷論を唱えた。
村は、当時藩政を主導した改革派の吉田東洋によって起用されたが、吉田に敵対する
土佐勤王党の武市瑞山らの過激尊王攘夷派からも、無難な穏健派と見られていた。
吉田東洋を暗殺後、元治元年(1864年)6月には側用役を罷免となり、容堂から遠ざけられた
慶応3年(1867年)4月、再び容堂の側用役に任ぜられ、側近として復帰。
土佐藩の討幕派が中心勢力に転じたことで左膳は立場を悪化させ、明治元年)6月27日には
士族の身分を剥奪されて、安芸郡野根村(現東洋町。土佐藩領の東端)へ追放処分となる
明治3年(1870年)2月に処罰が解除され、高知帰参を許された
|
中岡 慎太郎
なかおか しんたろう |
天保9年4月13日(新暦・1838年5月6日) - 慶応3年11月17日(新暦・1867年12月12日))
北川郷の大庄屋・中岡小傳次と後妻ウシの長男として生まれる。
安政元年、間崎哲馬に従い経史を学び、翌年には武市瑞山(半平太)の道場に入門して
剣術を学ぶ。文久元年には武市が結成した土佐勤皇党に加盟して、本格的に志士活動を
展開し始める。文久2年、長州藩の久坂玄瑞・山県半蔵とともに、松代に佐久間象山を訪ね、
国防・政治改革について議論し、大いに意識を高める。
元治元年(1864年)、石川誠之助を名乗り上洛。薩摩藩の島津久光暗殺を画策したが果たせず
また脱藩志士たちを率いて禁門の変、下関戦争を長州側で戦い、負傷する。
慶応3年11月15日、京都四条の近江屋に坂本龍馬を訪問中、何者かに襲撃され、
瀕死の重傷を負う、龍馬は即死ないし翌日未明に息絶えたが、慎太郎は二日間生き延び、
暗殺犯の襲撃の様子について谷干城などに詳細に語ったという。11月17日に死去。享年30。
|
長岡 謙吉
ながおか けんきち |
天保5年(1834年)- 明治5年6月11日(1872年7月16日))
高知城下の浦戸町の医師・今井孝順(孝純、玄泉)の息子として生まれる。
幼少期は河田小龍の下で蘭学に励んだ。その後は江戸や大坂に遊学して、医学や文学を
学んだ、脱藩して長崎に赴き、坂本龍馬の下で海援隊に参加した。龍馬は長岡の才能を
高く評価し、海援隊の通信文書の作成など、事務処理のほとんどを長岡に一任していたという
慶応3年、夕顔丸に坂本龍馬や後藤象二郎らと同船し、大政奉還後の龍馬の構想をまとめた
船中八策」を成文化したとされる。
龍馬が暗殺されると、海援隊の2代目隊長に選ばれた。戊辰戦争では、海援隊を率いて、
瀬戸内海の小豆島や塩飽諸島などを占領した。
明治期は別記参照
|
中島 信行
なかじま のぶゆき |
弘化3年8月15日(1846年10月5日) - 明治32年(1899年)3月26日
(現・高知県土佐市塚地)の郷士・中島猪三の長男。武市半平太の土佐勤王党に加盟、のちに脱藩して
長州藩の遊撃隊に加わり、その後坂本龍馬の海援隊で活躍した。龍馬の死後は陸援隊に参加する。
明治期は別記参照
|
那須 信吾
なす しんご |
文政12年11月11日(1829年12月6日)- 文久3年9月24日(1863年11月5日))
土佐藩の家老を務める浜田光章の三男として生まれる。
田中光顕の叔父にあたる。坂本龍馬に深く傾倒し、文久元年(1861年)に土佐勤王党に加わった。
文久2年(1862年)には安岡嘉助や大石団蔵らと共に尊王を無視して藩政改革、佐幕を唱える
吉田東洋を暗殺した上で脱藩し、長州藩に逃亡する。
文久3年、天誅組の変に参加し、軍監を務めるが、鷲家村にて狙撃されて戦死した。享年35。
|
間崎哲馬
まさきてつま |
天保5年(1834年) - 文久3年6月8日(1863年7月23日))
江戸で安積艮斎の私塾に学び、清河八郎などとも親交があった。
土佐勤王党に参加。中核人物として暗躍し、武市瑞山から最も重用された存在の一人で、
勤王運動を行う藩政改革を計画したが、それが佐幕派や山内容堂に疎まれ、切腹させられた。
享年30
|
平井 収二郎
ひらい しゅうじろう |
天保6年7月14日(1835年8月8日) - 文久3年6月8日(1863年7月23日))
土佐藩士(新留守居組格、三人扶持10石)平井伝八直証の嫡子として
土佐郡久万村に生まれる
1861年、武市半平太を中心とする土佐勤王党に参加し、尊王攘夷運動に奔走する。
1862年、藩主山内豊範による上洛時、小南五郎右衛門や武市らと共に他藩応接役として、
公卿や薩摩藩、長州藩の尊王攘夷運動家と交わりを深める。また、安政の大獄で処罰された
水戸藩士鵜飼吉左衛門の子息2名の宥免を図り、彼の名声を上げる。
薩長両藩の調停を謀る尊王攘夷運動に奔走した。
土佐勤王党が構想する運営方針を藩が容れないのを憂慮し、青蓮院宮に令旨を請いて
藩政改革を迫る。しかし、前藩主山内容堂が青蓮院宮を問い詰めて実情を聞き出したことに
よって計画は失敗し、間崎哲馬、弘瀬健太と共に切腹を命ぜられる。享年29
|
土方 久元
ひじかた ひさもと |
天保4年10月12日(1833年11月23日) - 大正7年(1918年)11月4日))
土佐藩上士・土方久用(200石)の長男として生まれる。
安政4年(1857年)、江戸へ遊学して儒者・大橋訥庵の門に学び、尊王攘夷思想に傾倒する。
帰国後、武市瑞山らが結成した土佐勤王党に参加。
文久3年(1863年)以後は藩命により京都へ上り、尊攘派の牙城であった長州藩はじめ諸藩の
勤王の志士と交流する。
長州藩と三条らは失脚し京から追放される。久元は「七卿落ち」に従い、三条や沢宣嘉らとともに
長州へ下った。幕府による第一次長州征伐の際には、三条らとともに九州(福岡藩)へ渡海し、
大宰府に逃れる。中岡慎太郎・田中光顕や坂本龍馬らとも連係し、薩長同盟の仲介に尽力。
明治期は別記参照
|
福岡 孝茂
ふくおか たかしげ |
1827年(文政10年) - 1906年(明治39年)12月25日)
福岡家は代々土佐藩家老職を務める家で、孝茂は10代目、3000石を領した。
13代藩主山内豊熈を助け、新政輔弼の功を挙げる。14代藩主豊惇が幼少で死去し、
豊信が藩主となるや、奉行として藩政を総轄する。部下に吉田東洋がいて
十分手腕をふるわせた。文久2年の東洋の横死後、藩人事に更迭があり、孝茂も一時免職と
なったが、重大政局に際し再び登用され、旧職に復帰した。元治から慶応年間は藩兵を
統轄して上京、清和院門を警護、維新後に引退する。1906年(明治39年)12月25日死去。80歳。
|
福岡 孝弟
たかちか |
天保6年2月5日(1835年3月3日) - 大正8年(1919年)3月7日)
土佐藩士・福岡孝順(180石)の次男として生まれる。
安政元年(1854年)、吉田東洋の門下生として後藤象二郎や板垣退助らと共に師事し、
その薫陶をうけた。安政5年(1858年)、吉田の藩政復帰に伴って大監察に登用され、後藤らと
若手革新グループ「新おこぜ組」を結成して藩政改革に取り組む。反主流派の土佐勤皇党を
弾圧するなどしたが、文久2年(1862年)の吉田暗殺によって失脚する。
文久3年(1863年)、藩主・山内豊範の側役に就任して公武合体運動に尽力する。他方で
坂本龍馬や海援隊、陸援隊と提携するなど、前藩主・山内容堂を中心に藩営商社・開成館を
通じて殖産興業政策を推進した
慶応3年、参政に就任。幕府を中心とする公議政体論を藩論とし、大政奉還の実現に向けて
薩摩藩との間に薩土盟約を締結する。同年、後藤とともに将軍・徳川慶喜に大政奉還を勧告し、
武力討幕派の薩摩藩や長州藩に対抗した。
明治期は別記参照
|
本山 茂任
もとやま しげとう |
1826年(文政9年) - 1887年(明治20年)8月28日)
土佐藩士(馬廻格)本山茂養(伊平)の嫡男として高知城下に生まれる
1830年(同13年)5月1日、江戸代勤を以って惣領御目見を仰せ付けられる。
1853年(嘉永6年)、土佐藩主山内豊信の側小姓となる。
土佐藩上士の中でも尊皇攘夷派の人物として知られており、乾退助、谷守部、佐々木高行らと
独自の勤皇派閥を形成していた。1856年(安政3年)に、幡多奉行に任ぜられる
1866年(慶応2年)、大目付(大監察)に任ぜられる。
1868年1月、鳥羽・伏見の戦いで、土佐藩は、薩土討幕の密約に基づき乾退助を大司令として
東征の為の藩兵迅衝隊を編成した。
維新後は新政府に仕え、松山県参事を勤め、春日大社、京都の下賀茂神社、奈良の大神神社
などの宮司を勤め、1887年(明治20年)8月28日、帰幽した。享年62
|
望月 亀弥太
もちづき かめやた |
天保9年10月7日(1838年11月23日) - 元治元年6月5日(1864年7月8日))
文久元年(1861年)、兄・望月清平と共に武市半平太の尊皇攘夷思想に賛同して土佐勤王党に
加盟し、文久2年10月、尊攘派組織五十人組の一人として、江戸へ向かう旧藩主山内容堂に
従って上洛する。
文久3年(1863年)、藩命を受けて幕臣・勝海舟の下で航海術を学び、
元治元年(1864年)、藩より帰国命令が出されたため脱藩して長州藩邸に潜伏。
池田屋事件に遭遇した。池田屋を脱出した望月は幕府方諸藩兵によって取り囲まれて深手を
負い、かろうじて長州藩邸に辿り着いたものの中へ入る事を許されずに門前で自刃した。享年27。
|
安岡 直行
やすおかなおゆき |
天保10年(1839年) - 文久4年2月16日(1864年3月23日))
安芸郡安田村の庄屋の息子として生まれる。1861年、土佐勤王党に参加する。
翌年、50人組の一人として江戸に赴き、山内容堂の護衛を務めた。
1863年には容堂の命により、勝海舟の海軍塾に入って様々なことを学んだ。そして北方警備や
蝦夷地開拓などに大きな興味を持ち、北添源五郎と共に蝦夷地の調査を行なっている。
1864年、天誅組の反乱に砲隊伍長として参加したが、鷲家村の戦いで負傷して捕らえられ、
京都六角の獄中において斬首に処せられた。享年26才
|
吉田 東洋
よしだ とうよう |
1816年(文化13年) - 1862年5月6日(文久2年4月8日)
土佐藩上士・吉田正清(馬廻格・200石)の四男として高知城下帯屋町に生まれる。
1842年(天保13年)9月に船奉行として出仕し、同年11月には郡奉行に転じて民政に携わる。
1848年8月23日(嘉永元年7月25日)、妻の兄弟後藤正晴が病死すると、その遺児
後藤保弥太(のちの後藤象二郎)を父親代わりになって養育する。
1853年(嘉永6年)7月、藩主山内容堂によって大目付に抜擢され、12月には参政として強力に
藩政改革を主導した。革新的な改革は、保守的な門閥勢力や尊皇攘夷を唱える
土佐勤王党との政治的対立を生じさせる結果となり、久2年4月8日)、帰邸途次の帯屋町にて
武市半平太の指令を受けた土佐勤王党の那須信吾・大石団蔵・安岡嘉助によって
暗殺された。享年47才
|
高見 弥市
たかみ やいち |
天保2年(1831年)1月 - 明治29年(1896年)2月28日)
大石団蔵、後に松元誠一・安藤勇之助と変名した。土佐藩郷士・大石磯平の長男として生まれる。
文久元年(1861年)土佐勤王党に加盟し、長州に使者として出ている他、薩摩へも視察へ向かった。
文久2年(1862年)那須信吾・安岡嘉助と計って、高知城下で土佐藩参政の吉田東洋を暗殺し、
首級を鏡川河原に晒す。そのまま脱藩し、京都で久坂玄瑞に保護され、後に薩摩藩士・奈良原繁の
養子として薩摩藩に所属するようになる。慶応元年(1865年)五代友厚らとともにイギリスへ密留学する
イギリスでは森有礼と下宿を共にしながら測量や機関学、数学を学び、慶応3年(1867年)帰国。
維新後は鹿児島県立中学造士館で数学教師となり、明治25年(1892年)沖縄県庁に勤めるも、
やがて辞職して鹿児島へ帰った。
|
安岡 嘉助
やすおか かすけ |
天保7年11月22日(1836年12月29日) - 文久4年2月16日(1864年3月23日)
土佐藩郷士・安岡正理(文助)の二男として生まれる。土佐勤王党に所属し、
文久2年那須信吾・大石団蔵とともに政敵であった吉田東洋を暗殺して脱藩、京都で
久坂玄瑞の保護を受け、一時薩摩藩邸に居留した。文久3年(1863年)いわゆる
天誅組の変に参加して敗北。戦闘で負傷して捕えられて京都六角獄舎に入り、
翌年に処刑された。
|
吉村 虎太郎
よしむら とらたろう |
天保8年4月18日(1837年5月22日) - 文久3年9月27日(1863年11月8日)
里正(庄屋)吉村太平の長男として生まれる。武市半平太に剣術を学び尊攘思想に
傾倒するようになった。文久元年(1861年)武市半平太が土佐勤王党を結成するとこれに加盟。
平野国臣らが画策する浪士蜂起計画(伏見義挙)に参加すべく脱藩するが、
寺田屋事件で捕縛されて土佐に送還され投獄される。釈放後、再び京都へ上り孝明天皇の
大和行幸の先駆けとなるべく中山忠光を擁立して天誅組を組織して大和国で挙兵するが、
八月十八日の政変で情勢が一変して幕府軍の攻撃を受け敗れて戦死した、享年27
|
山本 旗郎
やまもと はたろう |
京都鴨川松原河原にて、水戸藩京師警衛指揮役住谷寅之介を暗殺するが、
870年(明治3年)、住谷の長男・次男らによって東京神田筋違見附で仇討ちされた。
1873年(明治6年)2月7月に仇討ちが禁止される前の、合法的な仇討ちである。
|
| 佐賀藩 |
|
鍋島 直正
なべしま なおまさ
第10代佐賀藩主

|
文化11年12月7日-明治4年1月18日、第10代肥前国佐賀藩主。9代藩主・鍋島斉直の十七男。
斉正はアメリカの武力外交に対して強く攘夷論を唱え、品川台場建設に佐賀藩の技術を
提供し、正弘より信頼を得た。文久元年(1861年)、48歳で隠居。家督を次男・直大に譲って
閑叟と号した。文久2年12月25日、上京した閑叟は関白近衛忠煕に面会し、京都守護職への
任命を要請している。鳥羽・伏見の戦いの時に上京中で藩主も家老も京都に不在だったため、
薩摩藩からは佐賀征伐を主張する声が挙がったが、薩長(薩摩藩・長州藩)側が勝利に
終わって以降は上京した佐賀藩も新政府軍に加わり、戊辰戦争における上野彰義隊との戦い
から五稜郭の戦いまで、最新式の兵器を装備した佐賀藩の活躍は大きかった。
直正が育てた人材の活躍は大きく、直正自身も議定に就任する。
これらにより、討幕運動には不熱心であった佐賀藩であったが、薩長土肥の一角を
担う事となった。明治元年(1868年)に直正と改名。
明治4年(1871年)1月18日、藩邸にて病没。享年58
|
大隈 重信
おおくま しげのぶ |
天保9年2月16日(1838年3月11日) - 大正11年(1922年)1月10日)
佐賀藩士の大隈信保・三井子夫妻の長男として生まれる。
王派として活動した。慶応3年(1867年)、副島と共に将軍・徳川慶喜に大政奉還を勧めることを
計画し、脱藩して京都へ赴いたが捕縛の上、佐賀に送還され、1か月の謹慎処分を受けた。
明治期は別記参照
|
江藤 新平
維新の十傑 |
天保5年2月9日(1834年3月18日) - 明治7年(1874年)4月13日)
佐賀藩士の江藤胤光と妻・浅子の間に長男として生まれる。
江藤家は肥前小城郡晴気保の地頭・千葉常胤の末裔を称する。
嘉永3年に枝吉神陽が義祭同盟を結成すると、大隈重信・副島種臣・大木喬任・島義勇ら
とともに参加、文久2年に脱藩し京都で活動し、長州藩士の桂小五郎(木戸孝允)や公家の
姉小路公知らと接触する。
鍋島直正の直截裁断により永蟄居(無期謹慎)に罪を軽減されたとされる。
薩摩藩と長州藩は公家の岩倉具視と結び、慶応3年12月9日王政復古の大号令を行い、
新政府が誕生すると佐賀藩も参加し新平は副島種臣とともに京都に派遣される。
戊辰戦争で江藤は東征大総督府軍監に任命され、土佐藩士の小笠原唯八とともに江戸へ
偵察に向う。大木喬任と連名で岩倉具視に対して江戸を東京と改称すべきこと
(東京奠都)を献言する。
明治期は別記参照
|
副島 種臣
そえじま たねおみ |
文政11年9月9日(1828年10月17日) - 明治38年(1905年)1月31日)
佐賀藩士・枝吉南濠(忠左衛門、種彰、30石)の二男に生まれる。
父は藩校である弘道館の教授を努める国学者で、兄は同じく国学者の枝吉神陽。
父と兄の影響により、早くから尊皇攘夷思想に目覚める。弘道館で学び、この間に江藤新平や
大木喬任と交わる。
嘉永3年、兄・神陽が中心に結成した楠公義祭同盟に加わる。
安政6年(1859年)、父の南濠が死去し、同年3月には同藩士の副島利忠の養子となる
慶応3年(1867年)、大隈重信と脱藩するが、捕らえられて謹慎処分を受ける。
慶応4年(1868年)、新政府の参与・制度取調局判事となり明治期と入る
明治期は別記参照
|
大木 喬任
おおき たかとう |
天保3年3月23日)– 明治32年6月26日)、肥前国佐賀藩の45石の藩士大木知喬の長男
藩校の弘道館で学び、1850年(嘉永3年)副島種臣らと共に枝吉神陽の義祭同盟結成に参加。
後に江藤新平や大隈重信らも加わり藩論を尊皇攘夷へと導くことを図るが果たせなかった。
明治期は別記参照
|
佐野 常民
さの つねたみ |
1823年2月8日(文政5年12月28日) - 1902年(明治35年)12月7日)
佐賀藩士下村三郎左衛門(充贇)の5男として佐賀市)に生まれる。幼名は鱗三郎。
天保2年)に佐賀藩医佐野常徴の養子、佐賀藩の前藩主・鍋島斉直から栄寿の名を授かった。
安政2年)6月に長崎の海軍予備伝習に参加する。同年8月に幕府が長崎海軍伝習所を開設し、
佐賀藩から常民ら四十八名が第一期生として参加する。
明治期は別記参照
|
島 義勇
しま よしたけ |
文政5年9月12日(1822年10月26日) - 明治7年(1874年)4月13日)
佐賀藩士・島市郎右衛門の長男として生まれる。
文政13年(1830年)より藩校・弘道館で学ぶ。、佐藤一斎・藤田東湖・林桜園らに学ぶ。
慶応4年(1868年)3月、佐賀藩の海軍軍監、ついで東上し下野鎮圧軍大総督軍監となり、
新政府の東北征討に従う。
明治7年に郷里・佐賀において憂国党の党首に担がれ、江藤新平と共に佐賀の乱を
起こすが敗れ、鹿児島まで逃亡。島津久光を頼り、大久保利通に助命の旨を取り次いで
もらうが受け入れられず、同年3月7日捕らえられ、4月13日に斬罪梟首となった。
|
鍋島 直大
なべしま なおひろ |
弘化3年8月27日(1846年10月17日)-大正10年(1921年)6月19日
佐賀藩10代藩主・鍋島斉正(直正)の次男
戊辰戦争では佐賀藩兵を率いて指揮を執り、各地を転戦した。
とくに関東に移ってからは下総野鎮撫府に任命され、下総の防衛に当たった。
明治期は別記参照
|
鍋島 茂昌
なべしま しげはる |
天保3年11月28日(1832年12月9日) - 明治43年(1910年)3月15日)
江戸時代末期の第29代佐賀藩自治領武雄領主。
天保3年(1832年)、第28代武雄領主鍋島茂義の子として生まれる。
元治元年(1864年)、禁門の変に際し、佐賀藩兵100人を率いて上洛する。
安政6年、佐賀藩の請役(藩務を総理する執政職)に就任し、戊辰戦争に際しては、
近代化された。武雄領兵を率いて渡海し、窮地に陥っていた新政府側の秋田藩を救援し、
奥羽越列藩同盟の精鋭庄内藩に勝利するなど、勲功を挙げる。
明治期
兵部省で陸軍兵部大輔(陸軍少将)に就くことを勧められたが、、「西郷隆盛が陸軍大将で、
自分が陸軍少将では嫌だ」という理由で辞退し、武雄に戻る。
|
鍋島 茂彬
なべしま しげよし |
天保14年12月11日(1844年1月30日)-大正4年(1915年)6月13日
第8代藩主・鍋島直永の三男として生まれる。第10代藩主の鍋島直賢が本家の
鍋島直正によって強制的に隠居させられたため、その養子として家督を継いで
第13代藩主となった。慶応4年(1868年)の戊辰戦争では新政府に恭順した。
明治期
明治2年(1869年)6月の版籍奉還で鹿島藩知事に任じられる
明治9年(1876年)には侍従に任じられ、明治天皇の側近として仕えた。
明治12年(1879年)4月に初代の沖縄県令に任じられた。
|
鍋島 直虎
なべしま なおとら |
安政3年2月9日(1856年3月15日)- 大正14年(1925年)10月30日)
肥前小城藩の第11代(最後の)藩主。肥前佐賀藩主・鍋島直正の七男。
戊辰戦争では新政府軍に与して秋田の戦いなどで武功を挙げる
明治期は別記参照
|
石井 忠躬
いしい ただみ |
天保8年(1837年) - 明治16年(1883年)
蓮池藩第八代藩主鍋島直与の四男として生まれる。蓮池藩家老
戊辰戦争では、蓮池藩は朝廷の命により、545名の兵力で奥羽地方に出兵
|
石井 忠亮
いしい ただあきら |
天保11年7月7日(1840年8月4日) - 1901年(明治34年)1月1日)
元佐賀藩士で、中牟田倉之助らとともに藩営三重津海軍所の教官として勤務した。
戊辰戦争では、政府軍に属して佐賀藩海軍の陽春丸船将として箱館に出征。
明治期は別記参照
|
石井 松堂
いしい しょうどう |
文政8年(1825年) - 明治15年(1882年))
佐賀では「龍よんさん」と呼ばれて慕われており、「石井松堂」の名よりも「石井龍右衛門」の名の
ほうが有名である。佐賀藩士北島武兵衛政長の次男として生まれ、後に佐賀藩主鍋島家の
外戚家門石井三男家(三河守家)の石井林太夫広氏の婿養子となった。
養家は、藩祖鍋島直茂の家老石井生札(義元)の子孫でありる
|
石井 貞興
いしい さだおき |
天保13年(1842年)3月 - 明治10年(1877年)10月26日)
佐賀藩士櫛山弥左衛門の長男として生まれ、伯父石井忠克の養子となる。
戊辰戦争に従軍後、明治2年、東京に上り昌平坂学問所に学び、
さらに薩摩藩の造士館にも学んだ。その後、佐賀藩に帰国し、江藤新平の知遇を得て
少参事に任ぜられ、藩の重職として活躍する。
明治期は別記参照
|
石井 富之助
いしい とみのすけ |
1835年6月30日(天保6年7月25日) - 1897年(明治30年)10月25日)
佐賀藩士石井英勝の子として生まれる。幼少より秀才で、国学から蘭学まで通じていた。
長じて佐賀藩の三重津海軍所に入る。戊辰戦争の勃発により新政府の
軍務局判事試補に抜擢され、箱館戦争では海軍参謀補助(副参謀)として活躍する。
明治期
長州藩出身の大村益次郎や山縣有朋の副官として近代軍制の確立に貢献した。
その後、海軍大丞、兵部少丞を歴任し,
1897年(明治30年)10月25日に死去。享年62。
|
伊東 玄朴
いとう げんぼく |
寛政12年12月28日(1801年2月11日) - 明治4年1月2日(1871年2月20日))
佐賀県神埼市神埼町的仁比山)にて仁比山神社に仕える武士・執行重助の子として誕生する。
長崎の鳴滝塾で、フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトよりオランダ医学を学ぶ。
佐賀藩にて牛痘種痘法を実践し、安政5年(1858年)には大槻俊斎・戸塚静海らと図り江戸に
お玉が池種痘所を開設
|
枝吉 神陽
えだよし しんよう |
文政5年5月24日(1822年7月12日) - 文久2年8月14日
佐賀藩の藩校・弘道館の教授であった枝吉南濠の長男として生まれる。
父南濠の唱えた「日本一君論」を受け継ぎ勤王運動を行った。
藩論を尊王倒幕に向かわせようとしたが藩主鍋島直正を動かすことは出来ず失敗している。
1863年、コレラに罹った妻を看病するうち自身も罹患し、死去
|
朝倉 尚武
あさくら なおたけ |
天保13年(1842年) - 明治7年(1874年)4月13日)
佐賀城下に佐賀藩士の家に生まれる。幼少より藩校弘道館に学び特に兵学に優れた。
戊辰戦争では佐賀藩隊の軍監付属や、小隊長として奥羽戦線で活躍している。また戦後は
東京遊学を命じられ、また戦後は東京遊学を命じられ昌平坂学問所に入った。
江戸幕府直轄の教学機関・施設。正式の名称は「学問所」であり
「昌平黌」(しょうへいこう)とも称される
明治期
佐賀の乱で、薩摩の西郷隆盛に助力を請うため佐賀を脱出したため、朝倉も部隊を
六角耕雲に託して江藤の後を追い薩摩へ向かうが市来にて捕えられる
。乱後の裁判にて斬首。享年33。
|
山口 尚芳
やまぐち ますか |
天保10年5月11日(1839年6月21日) - 明治27年(1894年)6月12日)
幼少のころから佐賀藩武雄領主・鍋島茂義に将来性を見込まれ、佐賀藩主・鍋島直正の
命により、薩摩藩や長州藩の武士と交流し、薩長連合にも尽力したという。また岩倉具視ら
公家にも接近し、王政復古後は東征軍に従軍。江戸開城に伴い薩摩藩の小松帯刀らと
ともに江戸へ赴いた。
明治期は別記参照
|
中牟田 倉之助
なかむた くらのすけ |
天保8年2月24日(1837年3月30日) - 大正5年(1916年)3月30日)
金丸孫七郎の次男だったが、中牟田家の養子となる。
長崎海軍伝習所へ入所し、三重津海軍所で佐賀藩海軍方助役を務めて海軍力の発展を促す。
慶応4年(1868年)に戊辰戦争が勃発すると奥州方面へ出陣し、北越戦争に参戦して
旧幕府軍を追討。
明治2年3月に新政府軍艦「朝陽丸」の艦長に任命されると、4月には品川沖を出航して
蝦夷地での箱館戦争に参戦した。
明治期は別記参照
|
| 水戸藩 |
|
徳川 斉昭
とくがわ なりあき
 |
寛政12年3月11日(1800年4月4日)-万延元年8月15日(1860年9月29日)
第7代藩主・徳川治紀の三男として生まれる。長兄の斉脩は次代藩主であり、次兄の松平頼恕は
文化12年(1815年)に高松藩松平家に養子に、弟・松平頼筠は文化4年に宍戸藩松平家に
養子に、文政12年(1829年)、第8代藩主・斉脩が継嗣を決めないまま病となった。
斉脩の死後ほどなく遺書が見つかり、斉昭が家督を継いだ。常陸水戸藩の第9代藩主となる
比較的軽輩の藩士を用い藩政改革を実施した。
嘉永6年(1853年)6月、ペリーの浦賀来航に際して、老中首座・阿部正弘の要請により
海防参与として幕政に関わったが、水戸学の立場から斉昭は強硬な攘夷論を主張した。
安政2年に軍制改革参与に任じられるが、同年の安政の大地震で藤田東湖や戸田忠太夫らの
ブレーンが死去してしまうなどの不幸もあった。
安政4年に阿部正弘が死去して堀田正睦が名実共に老中首座になると、さらに開国論に
対して猛反対し、開国を推進する井伊直弼と対立する。
安政6年(1859年)には、孝明天皇による戊午の密勅が水戸藩に下されたことに井伊直弼が
激怒、水戸での永蟄居を命じられることになり、事実上は政治生命を絶たれる形となった
(安政の大獄)。万延元年(1860年)8月15日、蟄居処分が解けぬまま
心筋梗塞により水戸で急逝した。満60歳没
|
徳川 慶篤
とくがわ よしあつ |
天保3年5月3日(1832年6月1日) - 慶応4年4月5日(1868年4月27日))
常陸水戸藩の第10代藩主水戸藩主徳川斉昭の長男(嫡男)として水戸藩上屋敷に生まれる。
安政の大獄の際には、父の斉昭や尾張藩主徳川慶恕と共に不時登城した責任を問われ、
慶篤は登城停止に処される。父の死後、文久2年の坂下門外の変では、武田耕雲斎らを
登用して尊皇攘夷派の懐柔を図る。元治元年(1864年)の天狗党の乱では、当初は天狗党を
支持したものの、幕府が天狗党の討伐を決定するや、耕雲斎らを罷免して支藩の
宍戸藩主松平頼徳を将とする。討伐軍を派遣するなど、藩政を混乱させた。この乱により、
以後3年間は保守門閥派・諸生党が水戸藩の実権を握った。
慶篤は水戸城にて死去した。享年37。
|
戸田 忠太夫篤
とだ ちゅうだゆう
家老 |
文化元年(1804年) - 安政2年10月2日(1855年11月11日))
幕末の水戸藩の家老。尊王志士として活躍した。文化10年(1813年)、家督を継いで
200石小普請組となる。文政3年(1820年)には大番組頭、文成11年(1828年)には目付となる。
その頃、水戸藩に継嗣争いが起こり、将軍家より養子を擁立しようとする一派に対抗
斉昭が水戸藩主となると藤田東湖とともに斉昭を支え、世に水戸の両田といわれ、尊王の志と
と学識を備えた優れた指導者として知られるようになった。また、この両人と武田耕雲斎を
合わせ水戸の三田ともいう。天保10年(1839年)11月、水戸藩若年寄#藩の若年寄となり
天保11年(1840年)2月には学校造営懸となって弘道館を造営に参与する。
弘化元年に斉昭が幕疑を受け致仕すると藤田東湖同様に同年5月に免職、
蟄居謹慎を命ぜられる。安政元年正月、大寄合頭上座用達となり、再び安政の改革を
執行するなど藩政の枢機に携わる。
安政2年(1855年)に起きた安政の大地震によって、小石川の水戸藩邸で卒去する。
|
安島 信立
あじま のぶたつ
家老
|
文化8年(1811年) - 安政6年8月27日(1859年9月23日))
幕末に活躍した水戸藩の家老。安政の大獄で切腹を命じられた。
戸田三右衛門忠之の次男に生まれ、母方の叔父・安島彦之允信順の養子となった。
三河譜代の名門戸田氏の嫡流・戸田松平家の分家の出、文政12年(1829年)、
水戸藩主継嗣問題が起こると兄・戸田忠太夫とともに徳川斉昭擁立に奔走する。
安政3年(1856年)、再び登用されて御側用人となり、藩政改革や斉昭の幕政を
補佐し功績を残す。安政5年(1858年)7月、斉昭の命により水戸藩家老に任ぜられる
帯刀は水戸藩内に留まらず、幕府の守旧派からも憎まれる存在となっていった。
その様な折に朝廷が水戸藩に幕府への尊皇攘夷を促す様に命じた戊午の密勅に
関与したと疑われ、幕府評定所より召還され軟禁されることとなった。
帯刀は無罪とされたものの、大老・井伊直弼より再審議を命じられ、さらに無罪とされると
井伊自ら帯刀に切腹を命ずることとなった。
安政6年(1859年)8月27日、駒込の三田藩邸において切腹
|
藤田 東湖
ふじた とうこ
側用人 |
文化3年3月16日(1806年5月4日)-安政2年10月2日(1855年11月11日)
藤田氏の遠祖は小野篁に遡るというが不明。のちに常陸国へ移り、
那珂郡飯田村中島で百姓となった。という。曽祖父・与左衛門の代に水戸城下に移り、商家に
奉公してのれん分けを許され店を開いた。
水戸城下の藤田家屋敷に生まれる。父は水戸学者・藤田幽谷、文政10年に家督を相続し、
進物番200石となった後は、水戸学藤田派の後継として才を発揮し、
天保11年には側用人として藩政改革にあたるなど、藩主・斉昭の絶大な信用を得るに至った。
弘化元年5月に斉昭が隠居謹慎処分を受けると共に失脚し、小石川藩邸(上屋敷)に
幽閉され、安政元年(1854年)には側用人に復帰している。
安政2年10月2日(1855年)に発生した安政の大地震に遭い死去。享年50
|
会沢正志斎
あいざわせいしさい |
天明2年5月25日(1782年7月5日) - 文久3年7月14日(1863年8月27日))
水戸藩士・会沢恭敬の長男として、水戸城下の下谷で生まれる。
寛政3年(1791年)、10歳にて藤田幽谷の私塾(のちの青藍舎)へ入門する。
江戸時代後期から末期(幕末)の水戸藩士、水戸学藤田派の学者・思想家。
安政5年、幕府の日米修好通商条約締結に関して、朝廷から水戸藩に戊午の密勅が下る。
会沢は密勅返納を主張し、藩内の尊王攘夷鎮派の領袖として尊皇攘夷激派と対立する。
文久3年(1863年)、水戸の自邸にて死去。82歳
|
武田 耕雲斎
たけだ こううんさい |
享和3年(1803年)- 元治2年2月4日(1865年3月1日))
水戸藩士・跡部正続の子として生まれ、跡部正房(跡部家の宗家・300石)の養嗣子となった。
文化14年(1817年)、家督を継ぐと同時に武田氏に改姓。
戸田忠太夫、藤田東湖と並び水戸の三田と称される。徳川斉昭の藩主擁立に尽力した
功績などから、天保11年(1840年)には参政に任じられ水戸藩の藩政に参与した。
しかし弘化元年(1844年)、斉昭が幕府から隠居謹慎処分を命じられると、これに
猛反対したため、耕雲斎も連座で謹慎となった。嘉永2年、斉昭の復帰に伴って再び
藩政に参与安政3年には執政に任じられた。そして、斉昭の尊皇攘夷運動を支持し、斉昭の
藩政を支えた。万延元年(1860年)、斉昭が病死すると水戸藩内は混乱を極め、
慶応元年(1864年)には藤田小四郎(藤田東湖の四男)が天狗党を率いて挙兵してしまう。
天狗党は、斉昭の子で当時は京都にいた徳川慶喜を新たな水戸藩主に据えることを
目的としていた。
そして、800名の将兵を率いて中山道を進軍したが、敦賀で幕府軍の追討を受けて降伏した。
簡単な取調べを受けた後、小四郎と共に斬首された。享年63。 |
武田 金次郎
たけだ きんじろう |
嘉永元年8月10日(1848年9月7日) - 明治28年(1895年)3月28日)
1848年、水戸藩士・武田彦衛門の子息として生まれる。水戸藩藩士・武田耕雲斎の孫。
母は藤田東湖の妹。
1864年の天狗党の乱には、祖父や父と共に参加する。のちに乱が鎮圧されて祖父など376人が
死罪に処せられたが、若年を理由に遠島処分となる。
1866年、金次郎ら110名は小浜藩に預けられ、佐柿(福井県美浜町)の屋敷に収容されて
謹慎したものの、准藩士格として厚遇される。1868年、王政復古によって朝廷から罪を許され、
水戸への帰藩を命ぜられた。帰藩した金次郎らは、朝廷の威光により藩の実権を掌握。
通称「さいみ党」と呼ばれた金次郎らは、仇敵であった諸生党残党に復讐をすべく、白昼堂々に
襲撃・暗殺し、藩内を極度の混乱状態に陥れた。
版籍奉還後は藩の権大参事を務めたものの、廃藩置県後は経済的に窮迫し、
やがて病に倒れる。1895年、病死。享年48。
|
藤田 小四郎
ふじた こしろう |
天保13年(1842年) - 元治2年2月23日(1865年3月20日))
当時水戸藩主・徳川斉昭の側用人であった藤田東湖の四男として生まれる。
父東湖の影響を受け、尊皇攘夷思想を掲げて活動するようになる。
安政2年、安政の大地震により父を失う。この頃から弘道館館長の原市之進に師事する。
文久3年(1863年)、藩主・徳川慶篤の上洛に随従し、長州藩士の桂小五郎、久坂玄瑞をはじめ
京都に集う志士と交流する。これにより更に尊皇攘夷の思想を深くし、水戸藩過激派の
首領格として台頭する。
元治元年3月27日、朝廷より攘夷の勅が出されながら無策を続ける幕府に憤り、
同志など60人余りが集結して筑波山にて挙兵するが失敗し、越前国新保
(現在の福井県敦賀市)にて加賀藩に捕縛される。加賀藩から幕府へ出された処分寛大の
嘆願も空しく元治2年2月23日敦賀の来迎寺にて処刑された。享年24。
|
里見
四郎左衛門
親長
さとみ
しろうざえもん
ちかなが |
寛政6年(1794年) - 元治元年(1864年)。
水戸藩士。かつての最上氏旧臣だった系統であり、代々「四郎左衛門」を襲名する。
禄高は二百石。文政8年(1825年)、家督を継いで大番組となった。
その後中槍奉行、旗奉行と職責を果たし安政4年に致仕する。元治の役で一族を
率いて参軍し、を引き払って水戸城の東にある栗崎村の民家に隠れていたが、諸生党の
追手に探知され、妻多免子を手にかけ切腹して果てた。享年71 |
里見
四郎左衛門
親賢 |
文化12年(1815年) - 慶應元年4月5日(1865年4月29日)。父は里見四郎左衛門親長
母方の叔父には戸田忠太夫、安島帯刀、従弟には戸田銀次郎がいる。
天保9年、藩主・徳川斉昭により新設された床机廻に任ぜられ、同12年5月、大番組となる
嘉永3年(1850年)武芸指南の功で白銀を賜る。
安政元年(1854年)、家督を継いで四郎左衛門を襲名し、町奉行を拝命し尊皇攘夷派に
与する様になる。藩主徳川慶篤が水戸藩の鎮定のため、支藩である宍戸藩主・松平頼徳を
目代として派遣したが、これに尊王派が従軍したため、水戸城に拠る諸生党が頼徳の
入城を拒否する。
親賢は天狗党の総督であった榊原新左衛門の幕下として頼徳一行に従軍していた。
天狗党と諸生党との間で神勢館の乱が起きるが、幕府軍が諸生党に加担したため、頼徳は
幕府に降伏してしまう。天狗党の大将 榊原新左衛門も幕府軍と戦うのは本意ではないと
降伏、里見親賢もこれに従った。親賢は古河藩に預けられ、
慶應元年(1865年)4月に切腹となる。享年51
|
| 里見家の家系 |
本姓は源氏。家系は清和源氏の一流・河内源氏の末裔。八幡太郎義家の三男義国の子孫で、
新田氏の傍流・里見氏が出羽国に下り、天童氏次いで最上氏に臣従した。里見義親は
山形藩主・最上家親に仕えた。その子、里見四郎左衛門親宗の代になって
最上家が改易となると、松平筑前守(前田利常)を経て旧主・最上家親の実弟にあたる
山野辺義忠が水戸藩の家老として召抱えられると、これを慕って水戸藩に仕官したのが始まり。
里見掃部義親-里見四郎左衛門親宗-里見四郎左衛門親広-里見四郎左衛門親信-
里見八左衛門親善-里見四郎左衛門親和-里見四郎左衛門親候-里見四郎左衛門親長
-里見四郎左衛門親賢-里見勘之介親儀-里見長四郎
|
市川 弘美
いちかわ ひろとみ |
文化13年(1816年)- 明治2年4月3日(1869年5月14日)
水戸藩士・市川弘教(1000石)の二男として生まれる。納戸頭や小姓頭、馬廻頭、大寄合頭等の
要職を歴任し、門閥派(諸生党)の重鎮として改革派(天狗党)と対立した
。1860年、尊皇攘夷的な改革路線を推進した藩主徳川斉昭が死去すると、若年の
藩主徳川慶篤のもと藩論は幾つにも分断され、藩内抗争は激しさを増した。
その中で市川ら保守派は、尊攘派の武田耕雲斎らの率いる天狗党と鋭く対立した。
1868年、幕府が江戸城を明け渡して徳川慶喜も水戸に謹慎することになると、京都における
天狗党派)が藩の実権を握ることが必至となった。
情勢の不利を察した市川は、4月、諸生党約500名を率いて水戸を脱出し、戊辰戦争においては
奥羽・越後各地を転戦して官軍と戦う。しかし、9月に会津が落城すると行き場を失って
再度水戸へ戻り、藩校弘道館に拠って水戸城に拠る本圀寺勢と戦闘に及んだ(弘道館戦争)。
市川自身も二人の子息を失うなど多数の死傷者をだして下総方面へ敗走し、銚子や匝瑳にて
追討される(松山戦争)。これによって諸生党残党は壊滅したが、市川は脱して江戸に潜伏した。
市川は江戸市中の寺院や旧友宅に潜伏したが、1869年2月に藩の捕吏に縛されて
水戸へ移送された。水戸郊外の長岡原で逆さ磔の極刑に処された。
|
結城 朝道
ゆうき ともみち
|
文政元年(1818年)-安政3年4月25日(1856年5月28日)水戸藩士・結城晴徳の
長男として生まれた。天保4年(1833年)からは水戸藩江戸藩邸にて藩主・徳川斉昭の
小姓を務めた。斉昭からは若年寄、御勝手改正掛に任じられ、天保13年からは執政となる。
当初は人物聡明にして主君の斉昭や天狗党からも好感を受けていた。
革新的な政策をとる斉昭や、その腹心たる藤田東湖、戸田忠太夫らをはじめとした尊皇派と
次第に対立を深めることとなった。結城は中士、下士層を中心に形成された尊皇派の
台頭を防ぎ、斉昭の跡を継いだ徳川慶篤のもとでは専横の限りを尽くした。
しかし弘化4年(1847年)9月、老中・阿部正弘の命で結城も失脚となり、同年10月24日に
隠居処分に処せられた。かつて結城によって失脚させられた斉昭や改革派の恨みは凄まじく、
彼らがやがて復権を遂げると、嘉永6年(1853年)10月16日に結城は拘禁されることとなった。
やがて結城は、水戸藩の支藩の筆頭・高松藩の藩主で、幕府内においては譜代大名の
井伊直弼ら保守派との関係が深い松平頼胤が宗家の家督を欲しているのを知り、
慶篤を暗殺して頼胤を藩主に迎えようと画策した。しかし計画は露見し、結城はその3年後に
死罪に処せられた。享年39才。
|
田丸
稲之衛門
たまるいなのえもん |
文化2年(1805年) - 慶應元年2月4日(1865年3月1日))
田丸氏は村上源氏の名門北畠氏の庶流である。嘉永2年(1849年)11月に書院番組頭となり、
安政6年(1859年)に水戸藩目付となる。兄・山国共昌の影響もあり、尊皇攘夷派に組するように
なっていった。幕府軍が尊皇攘夷派を賊軍とみなし、水戸藩諸生党と連合して天狗党鎮圧に
乗り出すと、上野国から美濃国にかけて、高崎藩、諏訪藩、松本藩、大垣藩ら譜代大名の兵力と
戦火を交え、やがて天狗党は北上し、北陸道から京都に向かうこととなった。
加賀藩が天狗党に同情的であったこともあり、武田、稲之衛門ら一党は加賀藩に
降伏することとなった。慶應元年(1865年)2月4日、幕命により稲之衛門は賊将として敦賀の地で
斬刑となる。享年61
|
原 市之進
はら いちのしん |
天保元年1月6日(1830年1月31日) - 慶応3年8月14日(1867年9月11日))
水戸藩藩士・原雅言の次男として生まれる。藤田東湖の従弟に当たる。
文久3年(1863年)- 徳川慶喜の側近となり慶喜の補佐を務める
元治元年- 慶喜の側用人(一橋家家老)であった平岡円四郎が暗殺されると、
慶喜の側用人となる。
慶応2年- 慶喜より幕臣として取り立てられ、後に目付に就任。原自身は聡明で慶喜に
忠義を尽くしていたが、その功績を妬む者も多く、平岡同様に奸臣と見なされていた。
慶応3年8月14日- 同僚の鈴木豊次郎・依田雄太郎によって暗殺された。
|
大場 一真斎
いっしんさい
家老 |
享和3年(1803年) - 明治4年1月15日(1871年3月5日))
天保2年(1831年)に家督を継いで徳川斉昭に仕え、その藩政改革に協力した。
弘化元年(1844年)に斉昭が幕命により隠居させられるに伴って失脚した。しかし斉昭が
復帰すると同時に家老として復帰を許される。斉昭の没後は徳川慶篤に仕え、斉昭没後に
政争が激化した水戸藩の混乱収拾に尽力したが、水戸藩浪士が引き起こした
東禅寺襲撃事件の責任を問われて家老職を解任させられ、謹慎に処された、しかしやがて
復帰を許され、慶篤に従って上洛する。慶篤の実弟・徳川慶喜が第15代将軍になると慶喜から
直臣として迎えられ、二条城留守居役を任された。そのまま明治4年に亡くなるまで
京都で余生を送ったといわれる。享年69。
|
加倉井 砂山
かくらい さざん |
文化2年(1805年) - 安政2年(1855年))
砂山は一党一派に思想が偏ることを好まず、各方面に国家有用の人物をつくるという
方針のもと個性尊重教育、女子教育をしたことは水戸学が主流であった水戸藩では珍しく、
日新塾で学んだ,塾生は三十年間で三千人にも及び、門人の中には藤田小四郎・飯田軍蔵
(天狗党の乱)、斉藤監物・鯉淵要人(桜田門外の変)、河野顕三(坂下門外の変)、香川敬三
(枢密顧問官)川崎八右衛門(東京川崎財閥創始者、砂山の娘と結婚)など
多彩な人物を輩出した。 |
香川 敬三
かがわ けいぞう |
天保12年11月15日(1841年12月27日) - 大正4年(1915年)3月18日)
下伊勢畑(現在の常陸大宮市)の水戸藩郷士蓮田重右衛門孝定・袖の3男に生まれる。
次兄には、蓮田東三(安政3年(1856年)にハリス要撃を計画するも発覚し入獄死)がいる。
水戸の野口郷校(時雍館)や藤田東湖の私塾で学び、
万延元年(1860年)には同志とともに攘夷を訴えるため、薩摩藩に駆け込み、
これがもとで、水戸藩江戸屋敷において謹慎処分を受ける。
慶応3年(1867年)、中岡慎太郎率いる陸援隊の副隊長格となる。
戊辰戦争が勃発すると、岩倉具視の子である具定を総督とする東山道軍総督府大軍監として
進軍。流山で甲陽鎮撫隊(新選組)陣屋を襲って、局長近藤勇を出頭させたと言われている。
明治期
宮内省に移り、宮内権大丞、宮内少丞等を歴任。
明治になると、ともに活動して落命した同志のための名誉回復や、遺族へ訪問するなど、
謝罪のため各地を歴訪したという。浪士組に参加した
|
住谷 寅之介
すみやとらのすけ |
文政元年(1818年) - 慶応3年6月13日(1867年7月14日)
水戸藩士住谷長太夫の長男として生まれる。弘化3年(1846年)藩主徳川斉昭の雪冤運動に
加わり処罰された。安政4年(1857年)、格式馬廻組列・軍用掛見習となる。
安政5年(1858年)10月、強圧的に幕府の実権を握る大老井伊直弼に対する諸藩の決起を
促すため、住谷は大胡聿蔵らと共に土佐藩・宇和島藩・薩摩藩へ遊説に向った。
安政6年(1859年)11月、安政の大獄に伴い住谷も職を免ぜられ蟄居処分を受けた。
同志が井伊暗殺を実行し(桜田門外の変)、この変の後、幕府は水戸藩に対する弾圧を弱め、
10月に住谷は罰を解かれている。水戸藩・長州藩・土佐藩などの尊攘派志士による将軍上洛に
関する会合に参加している。この頃、藤田東湖ら亡き後の水戸藩の尊王攘夷思想の
中心的人物と見られていた住谷は、公卿らとも交際し、住谷は公武合体を容認していたことから
、勤王派志士から敵視されるようになり、慶応3年6月13日宵、鴨川東岸松原河原において
土佐藩足軽武士山本旗郎らによって斬殺された。享年50才
なお、1870年(明治3年)、東京神田において住谷の息子らが山本を殺害、日本で最後に
認められたという仇討ちを遂げている
|
鵜飼
吉左衛門
うがい
きちざえもん |
寛政10年2月12日(1798年3月28日-安政6年8月27日(1859年9月23日)
遠祖は甲賀流忍者といわれ、室町幕府9代将軍・足利義尚を斃した
尾張国中島郡中島村(現,一宮市)頓聴寺住職・鵜飼真教の次男として生まれ、
後に水戸藩士で叔父の鵜飼知盛の養子になった。尊王攘夷運動に励む。
将軍継嗣問題では一橋派につき、徳川慶喜の擁立を図る。
勤皇派弾圧を目論む老中・間部詮勝の上京後、事前の長野主膳からの入れ知恵もあり、
即日捕縛。安政6年(1859年)に水戸藩家老・安島帯刀や子の幸吉と共に
死罪に処された。享年62
|
海後
磋磯之介
かいごさきのすけ
|
文化11年(1814年)- 万延元年3月23日
水戸藩士・高橋諸往の長男として生まれる。藤田幽谷の門弟・国友善菴や藤田東湖に学び、
尊王攘夷論に傾倒、天保12年(1841年)、藩主の側近である奥右筆に任命される。
嘉永2年(1849年)3月に斉昭が許されると高橋も復職。安政2年(1855年)、北郡奉行となり、
安政7年(1860年)3月3日、関鉄之介らが江戸城桜田門外で井伊大老暗殺に成功
桜田門外の変の首謀者の一人として大坂に潜伏した高橋は井伊暗殺成功を知り、
潜伏地を幕吏に探知され、四天王寺境内の寺役人小川欣司兵衛宅にて息子・庄左衛門と
共に自刃した。享年47才
|
関 鉄之介
せき てつのすけ |
文政7年10月17日(1824年12月7日) - 文久2年5月11日(1862年6月8日))
水戸藩士・関新兵衛昌克の子として、水戸上町馬喰町片町に生まれた。
弘道館で学び、水戸学の影響を受けて尊王攘夷運動に乗り出した。
安政7年3月3日(1860年3月24日)、桜田門外の変で実行隊長として襲撃を指揮し、
直弼を暗殺した。その後、薩摩藩などを頼って近畿・四国方面の各地を逃げ回ったが
水戸藩領内を転々と潜伏した後、越後へと逃れたが、湯沢温泉で捕らえられた
水戸で投獄された後、江戸送りとなって、文久2年5月11日(1862年6月8日)に
日本橋小伝馬町の牢ににおいて斬首された。享年39(満37歳没
|
青山 延光
あおやまのぶみつ |
文化4年10月23日(1807年11月22日) - 明治4年9月29日(1871年11月11日)
青山延于の長男として、水戸城下の田見小路(現在の茨城県水戸市北見町)に生まれた。
青山延寿は末弟。江戸の彰考館雇から水戸の彰考館総裁代役、小姓頭、弘道館教授頭取と
出世し、最後は大学中博士となった。弘化3年(1846年)からは水戸の彰考館に勤務したが、
この時、国史編修頭取として『大日本史』校訂作業に尽力した。
藩政末期、天狗党・諸生党の抗争の激化に際しては、人心を鎮めなだめることに
奔走したとされる。
|
豊田 天功
とよだ てんこう |
文化2年(1805年) - 文久4年1月21日(1864年2月28日))
庄屋豊田信卿の次男として、久慈郡坂之上村(現在の茨城県常陸太田市)に生まれる。
幕末の水戸学者である。水戸藩彰考館総裁。『大日本史』の完成に大きく貢献した。
斉昭の攘夷論・海防論に学者としての知的裏付けをした。
安政3年(1856年)、彰考館総裁に就任
|
豊田 香窓
とよだ こうそう |
天保4年(1833年) - 慶応2年9月2日
水戸藩士豊田天功の長男として生まれた。幼い頃から父・天功に学び勤勉であったため、
水戸藩によって選抜され蘭学を修め、洋学世話掛に任ぜられて「航海要録」を訳述した。
脱藩して京都に入り、本圀寺警衛に身を投じたが、水戸藩尊王攘夷の過激派によって
暗殺された。享年33
|
金子 孫二郎
かねこ まごじろう |
文化元年(1804年) - 文久元年7月26日
水戸藩士・川瀬教徳の第2子として生まれ、水戸藩士・金子孫三郎能久の養子となった。
文政12年(1829年)、水戸藩主継嗣問題が起こると、父・教徳らとともに徳川斉昭を擁立した。
安政7年3月3日(1860年3月24日)、桜田門外の変を起こすに至った。
孫二郎自身は、直接参加しなかったが、成功の知らせを受けて薩摩藩士・有村雄助とともに
大坂で後挙を謀ろうとしたが、伏見で捕らえられ、江戸に送られて斬罪に処せられた。 |
本間 玄調
ほんま げんちょう |
文化元年(1804年) - 明治5年2月8日(1872年3月16日))
常陸国小川村(小美玉市)に生まれた。父本間玄有と祖父本間玄琢は稽医館の創始者で、
養父道偉も医者であり、名医一族の中で育った。17歳のとき、原南陽に入門し、
その後、杉田立卿、華岡青洲、シーボルトなどに師事した。
|
榊原新左衛門
かきばら
しんざえもん
家老
|
天保5年(1834年) - 慶應元年4月5日嘉永2年、養父照融の後を継ぎ、800石となる。
中ノ寄合に出仕し、翌5年(1852年)、小姓となり、その翌年には使番と昇任を重ねる。
安政6年(1859年)には大寄合頭に就任した。桜田門外の変とも藩内の尊皇攘夷派を統べ、
文久3年(1863年)には藩主・徳川慶篤に随行し上洛、攘夷実行の機を得られたとの感触を得て、
同年6月には異国からの来襲に備える御備調練司となった。
元治元年3月、筑波山には藩内尊皇攘夷派が挙兵し、水戸天狗党の乱が起こる際に
執政に就任した。頼徳が罪を得たことで、自らも抗争の名目を失った新左衛門ら1000の将兵も
幕府に降伏した。新左衛門は古河藩に預けられ、翌慶應元年4月、古河藩内にて
切腹した。享年32。
|
| 熊本藩 |
|
細川 斉護
ほそかわ なりもり |
文化元年9月16日(1804年10月19日) - 万延元年4月17日
肥後宇土藩の第8代藩主、のち肥後熊本藩の第10代藩主。熊本藩細川家11代
アメリカやイギリスなどの日本接近もあって、幕府から天草地方や相模湾警備を命じられ、
その出費で財政はさらに悪化した。このため、斉護は財政再建のために藩政改革に
取りかかるが、その方針をめぐって横井小楠・長岡是容ら改革派と松井佐渡ら保守派が対立し、
かえって藩内が二分された。このような混乱と苦悩の中で
万延元年(1860年)、斉護は57歳で死去した。
|
細川 韶邦
ほそかわ よしくに |
天保6年6月28日(1835年7月23日)- 明治9年(1876年)10月23日)
肥後国熊本藩の第11代藩主。熊本藩細川家12代。第10代藩主・細川斉護の次男。
母は比企氏。兄に細川慶前、弟に細川護久、津軽承昭、長岡護美。
尊皇攘夷には消極的な人物で、文久2年(1862年)に肥後勤王党が分裂したのを契機として、
藩論を尊王論に統一した。
慶応2年(1866年)、長州藩の高杉晋作が小倉藩を攻撃したとき、小倉藩側に与して戦ったが、
隣国の薩摩藩などの動向が気にかかることもあって、わずかに戦って敗れた後、
即座に撤退している。明治2年6月17日、版籍奉還にともない熊本藩知事となった。
明治9年(1876年)10月23日、42歳で死去した
|
長岡 是容
もりひさ
家老 |
文化10年2月11日(1813年3月13日)- 安政6年8月10日(1859年9月6日)
熊本藩家老・米田是睦の長子として誕生
通称の監物(けんもつ)の名で知られる。本姓は米田氏。幼名は与七郎。別称は源三郎、壱岐。
天保3年(1833年)に父が死去すると1万5,000石の所領を襲封し、藩家老となって江戸藩邸で
藩主細川斉護に仕えた。横井小楠や下津久馬と共に協力して藩政改革に取り組み、
文武芸倡方として藩校の時習館改革などに尽力し、荻昌国・元田永孚らを加えて会読会を
開き、実学党と呼ばれる一派を形成した。しかし改革に反対する保守派である学校派の
家老・松井佐渡の反対を受け挫折。
弘化4年(1847年)、親しくしていた水戸藩主・徳川斉昭が隠居させられると、それによって是容も
家老職を辞職させられた。
嘉永6年、アメリカ合衆国のマシュー・ペリーが再来航したのを契機として家老職に復帰を許され、
浦賀の守備隊長として江戸詰を任じられた。江戸において徳川斉昭、藤田東湖、吉田松陰、
西郷隆盛らと盛んに交流した。しかし攘夷論者であったため、安政2年(1855年)に開国論を唱えて
沼山津派(新民派)を形成した友人の小楠と対立し、自らは坪井派(明徳派)を形成して対抗し、
かえって熊本藩にさらなる混乱の種を生むこととなった。
|
細川 護久
もりひさ |
天保10年(1839年)3月1日、第10代藩主・細川斉護の三男として生まれる。
幕府の首脳である松平慶永(春嶽)や松平容保らと共に公武合体に尽力したほか、
藩主・慶順に代わって、細川内膳家の長岡忠顕(ただあき)らとともに朝廷との
交渉役も務めたという。慶応4年(1868年)1月3日の鳥羽・伏見の戦いでは砲火を掻い潜って
旅装のまま御所へ参内しこれを護衛したというエピソードも伝わっている、新政府より
同月12日には議定、17日には刑法事務総督に任命され、同年4月23日、新政府側に与する
確固たる意思を示す。
明治4年(1871年)7月14日の廃藩置県で免官、同年に白川県(現在の熊本県)知事となる。
明治26年(1893年)9月1日に死去した。享年55。
|
細川 行真
ゆきざね |
天保13年9月2日-明治35年1902年4月9日 肥後宇土藩の第11代(最後の)藩主
第9代藩主・細川行芬の五男として生まれる。文久元年5月、兄で第10代藩主の立則の
養子となり、兄が隠居したため、跡を継いだ。
慶応元年(1865年)、学問所である樹徳斎を創立して、学問を奨励した。
慶安4年(1868年)の戊辰戦争では、高瀬藩と共に新政府に与して大原口警備を務めた。
明治35年(1902年)4月9日に死去した。享年61
|
長岡 護美
もりよし |
天保13年9月19日-明治39年(1906年)4月8日 肥後熊本藩主・細川斉護の六男
嘉永3年(1850年)5月、喜連川藩主・喜連川煕氏の養子となり金王丸と称した。
明治元年(1868年)3月、明治新政府の参与に就任する。
明治維新後
1872年(明治5年)から1879年(明治12年)まで、アメリカを経てケンブリッジ大学に留学する。
1880年(明治13年)、外務省に入省してベルギーやオランダの公使
1882年(明治15年)、元老院議官に就任する。
|
細川 利永
としなが |
文政12年1月24日-明治34年(1901年)4月19日
第8代藩主・細川利愛の三男として生まれる。肥後熊本新田藩(高瀬藩)の第10代(最後)の藩主
元治元年(1864年)4月、神田橋御門番、慶応元年(1865年)7月、佃島砲台警備などを務めた。
慶応4年(1868年)7月25日、藩名を高瀬と改名する。明治2年、同族の宇土藩と共に
大原口警護を務めた。明治34年(1901年)4月19日に死去した
|
元田 永孚
もとだ ながさね |
文政元年10月1日(1818年10月30日) - 明治24年(1891年)1月22日)
熊本藩士・元田三左衛門(700石(本知550石))の子として生まれる。
実学党(横井中心の藩政改革派)の一人として活動した。しかし横井の失脚もあって
一旦実学派から距離を置く。安政5年、家督を継ぎ元田家8代目となり、京都留守居・
高瀬町奉行などを歴任した。
明治期は別記参照
|
横井 小楠
よこい しょうなん |
文化6年8月13日(1809年9月22日) - 明治2年1月5日(1869年2月15日)) 維新の十傑の1人
熊本藩士・横井時直の次男として生まれる。
天保10年(1839年)、藩命により江戸に遊学、林檉宇の門下生となり、佐藤一誠、
松崎慊堂らに会う。また、江戸滞在中に幕臣の川路聖謨や水戸藩士の藤田東湖など、全国の
有為の士と親交を結ぶ。安政2年、農村の沼山津(現・熊本市東区沼山津)に転居し、
自宅を「四時軒」(しじけん)と名づけ、自身の号も地名にちなんで「沼山」とする。坂本龍馬、
井上毅、由利公正など、明治維新の立役者や後の明治新政府の中枢の多くが
ここを訪問している。明治元年(1868年)、新政府に参与として出仕するが、翌2年(1869年)に
参内の帰途、十津川郷士らにより、京都寺町通丸太町下ル東側(現在の京都市中京区)で
暗殺された。享年61。殺害の理由は「横井が開国を進めて日本をキリスト教化しようとしている」
といった事実無根なもので実行者であった十津川郷士ら4名が
明治3年(1870年)に処刑されることとなった。
|
横井 太平
よこい だいへい |
1850年 - 1871年 江戸時代末期(幕末)の熊本藩士。横井小楠の甥にあたり、
兄佐平太と共に米国に密航。日本初の官費留学生となる。
横井太平は1850年(嘉永3年)、熊本城下の相撲町(現在の水道町)に生まれた
兄弟は22歳、17歳のときに密航を企て、その費用は小楠門下が集めた。渡航費用は主として
水俣の徳富家から出た。1866年、兄弟は渡米。ニューヨークに着くと、航海術を学ぶことを志すが、
米国は航海学校への外国人の入学は認めなかった。小楠の働き掛けで日本政府を動かし、
兄弟は日本政府最初の官費留学生となる。兄と共にラトガース大学(Rutgers University)
に留学年後の夏、無理な生活がたたり、太平は結核を発病し、帰国する
1869年、長崎で療養生活に入る。日本の現状をみるにつけ、郷土熊本に洋学校を作ろうと志す
一方兄の方は、無事に留学を終わり1875年に帰朝、同年6月元老院権少書記官になったが、
同年10月結核で死亡した。 |
岩男 三郎
いわお さぶろう |
1851年6月8日(嘉永4年5月9日) - 1909年(明治42年)7月15日)
熊本城下坪井で、熊本藩士・岩男伝之允の三男として生まれる。藩校時習館で学ぶ。
横井小楠の高弟で、幕末期には野々口為志、鵜殿豊之進、横井左平太、横井忠平らと交わり、
勝海舟の神戸海軍操練所で航海術を学び、長崎に遊学、熊本藩の洋学所管術となる。
明治期は別記参照
|
徳富 一敬
とくとみ かずたか |
文政5年9月24日(1822年11月7日)- 大正3年(1914年)5月26日)
幕末から明治にかけての日本の儒学者(朱子学者)、官僚、教育者。徳富蘇峰、徳富蘆花の父。
淇水(きすい)と号した。水俣郷(後の熊本県水俣市)に、惣庄屋の長男として生まれ、
幼児には万熊、後には太多助、太多七などと称した。一敬の父は辛島塩井の高弟で
津奈木手永惣庄屋の徳富美信。
842年に父の死去により惣庄屋の務めのため帰郷。1845年に横井小楠の門下となった。
1845年に横井小楠の門下となった。一敬は、小楠の第一の門弟とされる
1854年に帰郷し、1855年に葦北郡宰属監察に任官した。
1864年に勝海舟の遣いで坂本龍馬が横井小楠を訪ねた時には一敬も同席し、
その様子を書き留めている。
廃藩置県を経て、1871年に熊本県典事、1872年に白川県七等出仕となった後、
病を理由に1873年に官職を辞した。1879年に改進党系の立場から県会議員に当選したが、
翌1880年には病のために県会議員を辞職した
|
井上 平太
いのうえ へいた |
1848年(嘉永元年)9月17日 - 1933年(昭和8年)2月)
高橋の郡奉行(350石)の子として、熊本城下の上林町に生まれる。藩校時習館で学問、
武芸を学ぶ。
1864年(元治元年)、長州征討に野砲隊隊長の父とともに野砲隊副隊長として出征。
1868年(慶応4年)、藩主細川護久に従い上洛。戊辰戦争鳥羽・伏見の戦い勃発に伴い、
京都御所の警備に出動し、新選組の隊員数人を斬り倒した。
その後、家老の長岡是容の次男米田虎之助が率いる熊本藩兵の一員として東北戦争に転戦。
明治期
熊本県警察部の巡査に任官。1885年(明治18年)には陸軍少将乃木希典と親交を結ぶ。
乃木から馬上杯を贈られ、平太は乃木に村正を贈った。
警察には30年間勤務し、警部まで昇進した。
|
林 桜園
はやし おうえん |
寛政10年(1798年) - 明治3年10月12日(1870年11月5日))
肥後国熊本城下の山崎町(現・熊本市)に林又右衛門英通の第三子として生まれる。
天保8年、千葉城高屋敷(現千葉城公園)に原道館(げんどうかん)を開く。
多くの師弟が学び、その数は1400人以上に及んだと言われる。横井小楠、佐々友房、宮部鼎蔵、
吉田松陰、松田重助、河上彦斎、轟武兵衛、太田黒伴雄、加屋霽堅、上野堅五、斎藤求三郎
大村益次郎、島義勇、真木保臣らが学んだ
1870年(明治3年)、新開大神宮の近くにある太田黒伴雄の家にて没。
|
宮部 鼎蔵
みやべ ていぞう |
文政3年(1820年)4月 - 元治元年6月5日(1864年7月8日))
益城郡田代村(熊本県上益城郡御船町)に生まれる。医者の家庭で、
叔父の宮部増美の養子となる。
山鹿流軍学を学び、30歳の頃には熊本藩に召し出され、林桜園に国学などを学ぶ。
長州藩の吉田松陰と知り合い、嘉永3年(1850年)、東北旅行に同行する。
文久元年(1861年)には肥後勤皇党に参加する。
元治元年6月5日 池田屋で会合中に新選組に襲撃され、
奮戦するが自刃する(池田屋事件)。享年45。
|
宮部 春蔵
|
天保10年(1839年) - 元治元年(1864年))
日本の武士・熊本藩士、尊皇攘夷派の活動家。宮部鼎蔵の弟。名は増正、通称大助。
文久2年(1862年)、脱藩して長州へ行く。三条実美に仕える。
文久4年(1864年)、禁門の変に参加し、真木和泉らと共に天王山にこもり自害した。享年26
|
河上 彦斎
かわかみ げんさい
 |
天保5年11月25日〈1834年12月25日〉 - 明治4年12月4日〈1872年/明治5年1月13日〉)
下級藩士小森貞助とその妻和歌の次男として生まれた。 幕末の四大人斬りの一人
兵法を宮部鼎蔵に学んで、尊皇攘夷の思想を固めた、彦斎は特に強硬な攘夷論者であった。
彦斎が斬った人物で確実なのは佐久間象山だけで、後にも先にも、いつどこで誰を
何人斬ったったのかなど明確な記録は存在しない。
元治元年6月の池田屋事件で新選組に討たれた宮部鼎蔵の仇を討つべ
く再び京へ向かったが、7月11日、西洋の馬の鞍を使って神聖な京都の街を闊歩していたという
理由で、武合体派で開国論者の重鎮、佐久間象山を衝動的に斬った。
7月19日には禁門の変に長州側で参加した。第二次長州征伐の時も、
長州軍の一員として参戦、勝利をあげた。
慶応3年に説得のために帰藩するが、熊本藩は佐幕派が実権を握っていたために
逆に投獄された。参議・広沢真臣暗殺事件の疑いもかけられて、藩獄に繋がれ、
次いで江戸送りとなった。
明治4年12月4日(1872年1月13日)、日本橋小伝馬町にて斬首された。
|
松田重助
まつだ じゅうすけ |
天保元年(1830年)-元治元年6月6日(1864年7月9日))
熊本藩士・林桜園に国学を学び、宮部鼎蔵に兵学を学ぶ。
嘉永6年(1853年)に江戸へ出ると過激な尊皇攘夷活動に参加。幕府によって指名手配され
文久3年(1863年)の八月十八日の政変で、公卿達と共に京都を去る(七卿落ち)。
元治元年(1864年)6月5日、池田屋事件に遭遇し、新選組に捕縛される。その翌朝、脱走して
河原町まで逃げたが見廻りの会津藩士らによって殺害された。享年35
|
高木
元右衛門
たかぎ もとえもん |
天保4年(1833年) - 元治元年7月19日(1864年8月20日)深川村の郷士・高木甚之助の次男
武芸に優れ、成童の頃に父・甚之介の剣術仲間であった荒尾村の郷士・宮崎政賢の養子となる。
武者修行の旅へ出る。尊王攘夷派と親交を深め、肥後勤王党に加わる。
文久3年(1863年)、八月十八日の政変による七卿落ちの際には、七卿を護衛して長州に赴いた。
元治元年(1864年)6月の池田屋事件で新選組の襲撃を受け、近藤勇と応戦して包囲網を突破し、
長州藩邸に逃げ込んだ。翌月の禁門の変で長州方として戦い、
幕府軍の銃弾を受けて戦死した。享年32。
|
轟 武兵衛
とどろき ぶへい |
文化15年1月25日(1818年3月1日) - 明治6年(1873年)5月4日)
強硬な尊皇攘夷派として知られる肥後勤王党の中心人物の1人で、宮部鼎蔵、永鳥三平らは同志。
河上彦斎などは教え子。文久2年(1862年)、熊本藩親兵選抜となり藩主細川護久の護衛で
上洛すると、京都での政治活動を活発に行った。
文久3年8月18日(1863年9月30日)の八月十八日の政変により、尊皇攘夷派が追放され、
武兵衛にも帰藩が命じられたが、脱藩。長州に下ったが、捕らえられて3年幽閉された。
しかし情勢が変化して尊皇派が主流になると、帰参を許された。
明治維新の後、照幡烈之助と改名。明治2年、この名前で弾正大忠(権弁事)となって公議所に
務めたが、開国派に転じた明治政府とは意見が合わずに、
官職を辞して帰郷して後に没した。享年56
|
太田黒 伴雄
おおたぐろ ともお |
天保5年(1834年) - 明治9年(1876年)10月25日)
肥後国飯田熊助の三男として熊本被分町(現・熊本市)に生まれる
大野家に養子に入り大野鉄兵衛と称した。その後、江戸にて朱子学・陽明学を学ぶ。
帰藩後、林桜園より国学と神道の手ほどきを受け、尊王攘夷の思想を深めた。
新開大神宮の太田黒伊勢守に入婿し、姓名を太田黒伴雄と改め、神官となる
立派で大柄な太田黒は、宮部鼎蔵、轟武兵衛ら勤王党先輩たちからも
信頼され対等に扱われていた。
明治維新後
1876年(明治9年)、明治政府の出した廃刀令に激怒して加屋霽堅、斎藤求三郎ら、
約170名とともに神風連の乱を起こすが銃弾を受けて重傷を負い、法華坂で義弟の
大野昇雄の介錯により果てる。享年43。
|
加屋 霽堅
かや はるかた |
天保7年1月13日(1836年2月29日)-明治9年(1876年)10月24日)
熊本藩士である加屋熊助の長男として熊本城下高田原(現・熊本市下通)に生まれる
嘉永4年、熊助はある事件に巻き込まれ、自刃。霽堅が長男であったため、家を守らねばならず、
また、加屋家は父が事件に巻き込まれた為にお家断絶の危機に陥るが、加屋家は藩の要職に
ある者に助けられる。1858年(安政5年)、林桜園の原動館に入門。そこで、
神道の教えなどを学ぶ。
そこで後にともに行動する、太田黒伴雄や河上彦斎などの同志の仲間に会う。
文久2年)、朝廷から熊本藩へ御所警備の要請がくると、加屋や河上などがいる肥後勤王党にも、
藩からの出動命令があり、御所に向けて出発する。だが、その職に就いたつかの間、
1863年(文久3年)に御所で8月18日の政変が起こり、尊王攘夷論者は尊王攘夷を昔から
言論していた。長州藩の世話になる者が多く出始め、御所警備隊は解散する。
元治2年)、熊本に帰った途端に牢獄に入れられる。大政奉還が成った慶応3年)に
牢獄から出される。1871年(明治4年)、二卿事件に連座して投獄。1874年(明治7年)に
熊本錦山神社神官となるが、明治9年)に武士の象徴であった刀を捨てろという廃刀令が
出され、新開大神宮の神官・太田黒伴雄が主であった敬神党の志士はこれに反発して
神風連の乱を起こし、霽堅はそのさなかに戦死する。享年41。
|
尾形 俊太郎
おがた
しゅんたろう
新撰組 |
天保10年(1839年) - 大正2年(1913年))熊本藩生まれ。
新撰組の中では永倉新八と同年齢。新選組入隊は文久3年5月25日以降とされる。
同年6月の編成では、副長助勤を務めている。
元治元年月の池田屋事件には不参加。同年12月に長州征討を考えた行軍録では、
五番組組頭に就任、慶応3年(1867年)6月の幕臣取立では、副長助勤として
見廻組格となっている。
慶応4年(1868年)1月に勃発した鳥羽・伏見の戦いでは目付を務め、大阪に敗走後、
江戸に帰還。その後も在隊し、甲州勝沼の戦いを通して会津にへ向かい、同年8月21日の
母成峠の戦いで敗走。22日に斎藤一こと山口次郎ら38名と共に会津若松城下外堀外の
斉藤屋に宿泊した記録を最後に消息を絶った。なお、会津まで新選組に同行した副長助勤は
、尾形と斎藤のみであった。
|
岡田 摂蔵
おかだ せつぞう |
生年不明 - 明治9年(1876年)1月17日)
熊本藩に藩士として生まれ、安政6年(1859年)緒方洪庵の適々斉塾(適塾)に入門。
のち文久3年(1863年)12月、江戸に出て当時鉄砲洲にあった福澤諭吉の慶應義塾に入り、
元治元年頃、幕府海軍に出仕した岡本周吉(古川正雄)の後を引き継いで塾長となる。
慶応元年、外国奉行柴田日向守(貞太郎)が特命理事官としてフランス・イギリスに
派遣された際に随行。この一行には、水品楽太郎・冨田達三・塩田三郎・福地源一郎・
小花作助などが加わる。帰国後は各地で教育者として活動。明治2年4月から2ヶ月岡山藩に
滞在し、その子弟の一人であった高山紀斎の慶應義塾入門を斡旋した。また、長崎や熊本藩の
洋学所で教官を務めた。
明治3年(1870年)7月名村泰蔵などの協力を得て創立した熊本藩の洋学所が廃止されると、
京して海軍省の権秘書官となる。のちに病で帰郷し、明治9年1月17日没。
女優の岡田嘉子は孫に当たる。
|
木下 助之
きのした すけゆき |
1825年(文政8年) 木下右衛門の四男として肥後国菊池郡に生まれる
1848年玉名郡南関手永(手永:近世に細川氏が豊前、肥後で設けた地方行政単位)惣庄屋の
下初太郎の養子となり、補佐役を務める
1868年(慶応4年) 時習館(肥後藩の藩校)訓導助勤・学校方奉行触
明治維新後
1872年(明治5年) 上京し、東京府八等出仕、その後、太政官、左院で勤務
1879年(明治12年) 初代熊本県議会議長
1890年(明治23年)7月1日 第1回衆議院議員総選挙熊本2区に出馬し、初当選
1899年(明治32年) 死去
|
西山 大衛
にしやま だいえい |
生没年不詳)は、幕末の肥後国熊本藩の藩士
通称は大衛。家格比着座同列定席。石高は1100石。藩内派閥は保守派である学校党に所属。
明治2年8月(1869年)まで奉行を務める。父は西山氏侯。子は西山直太郎。「大衛」は西山氏が
がしばしば称した通称であるが、一般的に「西山大衛」というと幕末に奉行を務めた当人を指す。
|
林 正明
はやし まさあき |
弘化4年(1847年)5月 - 明治18年(1885年)3月21日)
熊本藩士の子として託摩郡八代附近に生まれる
文久2年(1862年)6月、小楠の第4回目の越前福井藩行きには、侍者として随行する。
やがて藩主細川韶邦から江戸就学を命ぜられ、藩命により江戸に出る。
文久3年から明治2年までの約6年間、慶應義塾に学び、福澤諭吉や中津藩士に師事して学ぶ。
同年10月に、熊本藩士・津田亀太郎と共にチャイナ号にて横浜を出港し、
藩費にて米国留学の途につく。
アナポリス海軍兵学校にて横井左平太と面会した。帰国後に司法省法官となるが、
明治3年に再び欧米に留学し、高木三郎、勝小鹿(勝海舟の子)、児玉淳一郎、橋口宗儀と共に
ラトガース・カレッジにてロンドンで就学する。
明治期は別記参照
|
宮崎 八郎
|
1851年(嘉永4年)- 1877年(明治10年)4月6日)
郷士・宮崎政賢(宮崎長兵衛/長蔵)・佐喜夫妻の次男として生まれる。
弟に宮崎民蔵、宮崎彌蔵、宮崎滔天がいた。
父には山東家伝二天一流を弟たちとともに習っている。元治元年元服し長州征伐に
父とともに従軍する。
明治維新後
明治8年)4月26日、熊本県植木町に植木学校(校長は平川唯一、学八郎は学務委員)を設立。
明治10年)、鹿児島県で西郷隆盛の私学校が西南戦争をおこすと、民権家同士と
熊本協同隊を結成し、2月21日に川尻で薩摩軍に合流、桐野利秋のもと共に
政府軍を相手に戦う。4月6日、熊本県八代市萩原堤で戦死。
|
安場 保和
家老 |
天保6年4月17日(1835年5月14日) - 明治32年(1899年)5月23日
8歳で熊本・細川藩の藩校時習館に入り、選ばれて居寮生となった。横井小楠門下として、
嘉悦氏房・山田武甫・宮川房之らと並ぶ四天王と称される。
細川藩家老の家柄で、先祖である安場一平は、藩内でも影響力のある家柄であった。
明治元年(1868年)の戊辰戦争に参加。
明治期は別記参照
|
| 津和野藩 |
|
亀井 茲監
かめい これみ |
文政8年10月5日(1825年11月14日)-明治18年(1885年)3月18日
筑後久留米藩の第9代藩主有馬頼徳の六男として江戸で生まれる。
天保10年(1839年)に津和野藩の第10代藩主亀井茲方の養子となり、
石見津和野藩の第11代(最後)の藩主となる
幕末期は長州藩の隣藩だったことから、佐幕派と尊王派の間を苦慮した形となり、
慶応2年(1866年)の第2次長州征伐には消極的な立場をとり、幕府軍が撤退すると、
幕府が目付として残していた長谷川久三郎を長州藩に引き渡して和睦している。
その後は次第に長州藩寄りとなり、慶応4年(1868年)1月には新政府の参与に任じられる
明治2年(1869年)6月、版籍奉還により津和野藩知事に任じられ、従四位上に昇叙する。
|
岡 熊臣
おか くまおみ |
天明3年3月9日(1783年4月10日) - 嘉永4年8月6日(1851年9月1日)
富長山八幡宮の神官・岡忠英の子として生まれる。本居宣長の影響を受け国学に傾倒。
1811年から神職自祭葬運動を展開した。1816年には家塾の桜蔭館を開いた。
1849年、津和野藩校・養老館初代国学教師に就任。津和野国学隆盛の礎を築いた。
|
大国 隆正
|
寛政4年11月29日(1793年1月11日) - 明治4年8月17日(1871年10月1日))
平田篤胤の門下となり国学を学ぶ。さらに昌平黌で古賀精里に儒学を、増山正賢に絵画を、
菊池五山に詩を学ぶ。
本居宣長が音韻学に精通すると聞き、本居の門人である村田春門に国学・音韻学を学ぶ。
文政11年、津和野藩の大納戸武具役となったものの、同僚の誹謗に憤り脱藩、天保2年に父が
死去すると家が没落するばかりか、火災で著書や蔵書・家財を悉く失うという悲運にも遭った。
以降、国学を京都・摂津で講じ、「古事記」奏上序の本教神理に因んで本教本学と称した。
天保7年に播磨小野藩主・一柳末延の招請を受け、藩校・帰正館を開校し藩の子弟を教育。
明治元年に大国は徴士となり、明治維新を経て神祇事務局権判事になるも老齢故に職を辞し、
神祇局の諮問役になった。
|
福羽 美静
ふくば びせい
 |
天保2年7月17日(1831年8月24日) - 明治40年(1907年)8月14日)
日本の武士・津和野藩士、国学者、歌人
津和野藩士福羽美質の長男として生まれる。嘉永2年(1849年)、19歳で藩校・養老館に入学して
学や山鹿流兵学を学ぶ。津和野藩主亀井茲監の命を受け、嘉永6年(1853年)京都に上り、
大国隆正の門に入る。
文久3年(1863年)、御所に召され孝明天皇に近侍する。八月十八日の政変に際しては、
七卿と共に西下し帰藩、藩主亀井に認められ、藩政刷新に尽くすところがあった。
慶応2年(1866年)の第二次長州征伐時には、藩の方針を長州藩寄りにまとめた。
|
| 大垣藩 |
|
戸田 氏正
とだ うじまさ |
文化10年閏11月18日(1814年1月9日) - 明治9年(1876年)6月28日)
江戸時代後期の大名。美濃国大垣藩の第9代藩主。大垣藩戸田家10代。
開明的な藩主で洋学に興味を示し、佐久間象山や勝海舟の門下生として藩士を多数送り込み、
洋式学を学ばせた。城代の小原鉄心と協力して藩政改革に努め、大砲鋳造などの洋式軍制導入
を行なった。また、徳川斉昭と親しかった関係から、尊皇攘夷論に次第に傾倒していったという。
安政3年(1856年)10月25日、長男の氏彬に家督を譲って隠居した。戊辰戦争で朝敵になった際には
小原鉄心を助けて尊王への藩論統一に務めた。
|
戸田 氏彬
とだ うじあきら |
天保2年5月11日(1831年6月20日) - 慶応元年8月8日(1865年9月27日))
美濃国大垣藩の第10代藩主。大垣藩戸田家11代 第9代藩主・戸田氏正の長男
幕府に忠実な人物で、禁門の変では長州藩の家老・福原元僴が率いる軍勢を伏見街道で
破るという功績を挙げている。さらに水戸藩の天狗党・武田耕雲斎が中山道を上洛しようと
したときは、これを妨害した。第2次長州征伐にも幕府方として与し、第14代将軍・徳川家茂の
警護役を務めたが、その途中で病に倒れ、慶応元年(1865年)8月8日に35歳で死去した。
|
戸田 氏共
とだ うじたか |
嘉永7年6月29日(1854年7月23日) - 昭和11年(1936年)2月17日)
美濃国大垣藩第11代藩主、第9代藩主戸田氏正の五男で、第10代藩主戸田氏彬の弟。
慶応元年(1865年)10月3日、兄・氏彬の病死により、末期養子として家督を継いだ。
慶応4年1月10日、鳥羽・伏見の戦いの敗戦により、新政府から朝敵として入京禁止を命じられる。
そうした状況のなかで、家老の小原鉄心は藩論を勤王・恭順にまとめる。
明治2年(1869年)6月18日、大垣藩知事に就任する。明治4年2月、米国留学のために藩知事を
辞任、帰国後の明治12年(1879年)10月に文部省御用掛を命じられた。
明治19年(1886年)3月に公使館参事官、明治20年(1887年)5月に弁理公使と累進し、
同年6月にオーストリア全権公使となった。
明治41年(1908年)1月に式部長官となった。大正10年(1921年)10月、式部長官を退任する。
|
小原 鉄心
おはら てっしん |
文化14年(1817年)11月3日-明治5年(1872年)4月15日死去。享年56
代々城代を務めた小原家に生まれる。天保3年11月6日に家督を相続し、
藩主・戸田氏正に仕えた。
嘉永6年(1853年)6月にペリーが浦賀に来航すると、浦賀奉行戸田氏栄は本家である
大垣藩戸田家に支援を要請した。鉄心は藩兵とともに浦賀警備のために派遣され、
氏栄を助けた。元治元年(1864年)の禁門の変では福原元僴率いる長州藩の軍勢と戦い、
伏見まで追いつめるという武功を挙げている。
慶応元年(1865年)8月に氏彬が没し、弟の戸田氏共が12歳で藩主となると、
氏共に引き続き仕えた。慶応4年(1868年)1月3日、参与(三職参照)に任じられて
新政府に出仕。しかし、この日に始まった鳥羽・伏見の戦いでは、大垣藩は幕府軍に従って
出陣しており、養子の小原兵部(忠迪)率いる
藩兵が淀への先鋒を務めている。鉄心は新政府の許可を得て10日に大垣に帰り、
佐幕派と論争を行う。隠居していた氏正の支持を受けた鉄心は氏共を説得して
藩論を尊王派で統一、恭順を誓う
氏共の請書を京都に持ち帰った。新政府に恭順した大垣藩は、以後の戊辰戦争で
新政府軍に加わり、鉄心は兵部を東山道先鋒として従軍させている。
|
小原 適
おはら ただし |
天保13年(1842年)2月26日-1910年(明治43年)4月9日
大垣藩執政上田能重の長男として生まれ、父の実兄の藩老小原鉄心の婿養子となる。
慶応3年(1867年)幕命により藩兵を率いて大坂に上り、翌慶応4年(1868年)鳥羽・伏見の戦いで
新政府軍と戦う。戦後、官軍に抗した罪により禁固されるも、新政府軍に参加した大垣藩の
戊辰戦争の功績によりその罪を許された。明治2年(1869年)公議人に選ばれる。
明治3年和歌山県権参事。明治4年欧州に留学。明治25年)岐阜県選出の衆議院議員となる。
1908年(明治41年)貴族院議員となる。
明治43年4月急性肺炎により京都で死去。享年69
|
| 宇和島藩 |
|
伊達 宗紀
だて むねただ
宇和島藩
第7代藩主 |
寛政4年9月16日(1792年10月31日)?-明治22年(1889年11月25日))、
伊予国宇和島藩第7代藩主第6代藩主・伊達村寿の長男。正室は鍋島治茂の娘
天保15年(1844年)7月16日、家督を養嗣子の宗城に譲って江戸の藩邸に隠居した。
1853年(嘉永6年)のペリー提督率いるアメリカ東インド艦隊来航の際には、
幕府に開国を献策した。明治22年11月25日、98歳という長寿をもって死去した。 |
伊達 宗城
だて むねなり
宇和島藩
第8代藩主 |
文政元年8月1日1818年9月1日)-明治25年1892年12月20日 宇和島藩第8代藩主
大身旗本・山口直勝の次男、正室は佐賀藩主・鍋島斉直の娘・益子。祖父・山口直清は
宇和島藩5代藩主・伊達村候の次男で山口家の養嗣子となった人物である。
幕府から追われ江戸で潜伏していた高野長英を招き、更に長州より村田蔵六を招き、
軍制の近代化にも着手した。
福井藩主・松平春嶽、土佐藩主・山内容堂、薩摩藩主・島津斉彬とも交流を持ち
「四賢侯」と謳われた。彼らは幕政にも積極的に口を挟み、老中首座・阿部正弘に
幕政改革を訴えた。一橋派は排除された。いわゆる安政の大獄である。これにより宗城は
春嶽・斉昭らとともに隠居謹慎を命じられた。
慶応3年(1867年)12月、王政復古の後は新政府の議定(閣僚)に名を連ねた。
しかし明治元年(1868年)に戊辰戦争が始まると、心情的に徳川氏・奥羽列藩同盟寄りで
あったので薩長の行動に抗議して、新政府参謀を辞任した。
明治2年、民部卿兼大蔵卿となって、鉄道敷設のためイギリスからの借款を取り付けた。
明治4年(1871年)には欽差全権大臣として清の全権李鴻章との間で日清修好条規に調印し、
その後は主に外国貴賓の接待役に任ぜられた。しかし、その年に中央政界より引退している。
|
伊達 宗徳
だて むねなり
宇和島藩
第9代藩主 |
文政13年閏3月27日(1830年5月19日) - 明治39年(1906年)11月29日)。宇和島藩第9代藩主
第7代藩主・伊達宗紀の三男、天保8年(1837年)、従兄の第8代藩主・宗城の
養嗣子となり、安政5年(1858年)11月23日に宗城が井伊直弼の安政の大獄で
隠居処分となったため、家督を継承した。
明治39年(1906年)11月29日、77歳で死去した。 |
吉見 左膳
よしみ さぜん
家老 |
文化14年11月17日(1817年12月24日) - 明治8年(1875年)4月30日) 家老
宇和島藩の参政を務める中井筑後守の実弟であったが、吉見家に養子入りしている。
宗紀が隠居して伊達宗城が藩主になった後も信任は変わらず、むしろ宗城から家老にまで
取り立てられ、宇和島藩のナンバー2として宗城の藩政改革や幕政参与に協力した。
明治8年(1875年)に死去。享年59 |
| 岡山藩 |
幕末に9代藩主となった茂政は、水戸藩主徳川斉昭の九男で、鳥取藩池田慶徳や最後の
将軍徳川慶喜の弟であった。このためか勤皇佐幕折衷案の「尊王翼覇」の姿勢をとり続けた。
しかし戊辰戦争にいたって茂政は隠居し、代わって支藩鴨方藩主の池田政詮(岡山藩主となり
章政と改める)が藩主となり、岡山藩は倒幕の旗幟を鮮明にした。
そうした神戸事件が起こり、その対応に苦慮した。
神戸事件
慶応4年1月3日(1868年1月27日)、戊辰戦争が開戦、間も無く、徳川方の尼崎藩(現・兵庫県)を
牽制するため、明治新政府は備前藩に摂津西宮(現・西宮市)の警備を命じた。
2,000人の兵を出立させ、このうち家老・日置帯刀率いる500人は大砲を伴って陸路を進んだ。
その時に神戸,]三宮神社前において備前藩兵が隊列を横切ったフランス人水兵らを負傷させ、
銃撃戦に発展し、居留地(現・旧居留地)予定地を検分中の欧米諸国公使らに水平射撃を
加えた事件である。これを見た第3砲兵隊長・滝善三郎正信が槍を持って制止に入った。しかし、
言葉が通じず、結局、2月2日(2月24日)、備前藩は諸外国側の要求を受け入れ、2月9日、
永福寺において列強外交官列席のもとで滝を切腹させるのと同時に備前藩部隊を率いた
日置について謹慎を課すということで、一応の決着を見たのである。
|
池田 慶政
いけだ よしまさ
岡山藩第8代藩主 |
文政6年7月5日(1823年8月10日) - 明治26年(1893年)3月4日)備前国岡山藩の第8代藩主
豊前国中津藩主奥平昌高の十男。正室は第7代藩主池田斉敏の養女
文政6年(1823年)、中津藩江戸藩邸で誕生した。天保13年(1842年)、岡山藩主池田斉敏の
養嗣子となった。斉敏は、慶政の実父の奥平昌高と同じく薩摩藩島津家の出身で、血縁上は
斉敏が慶政の従甥にあたるが、慶政よりは12歳年上である。その1ヵ月後に斉敏が
急死したため、斉敏の養女(支藩鴨方藩主池田政善の娘)宇多子と結婚した上で
家督を相続した。質素倹約令などによる財政政策、洋式軍制の導入などを行なったが、
あまりに厳しすぎる改革を行なった上、改革で部落差別などが起こったため、
安政3年(1856年)に藩内で渋染一揆が発生し、加えて強い締め付けの影響で同年中に
銀札(藩札)が札潰れ(発行停止)となり、改革は失敗に終わった。
文久3年(1863年)、病気を理由に家督を水戸藩主徳川斉昭の九男であり養嗣子としていた
茂政に譲って隠居した。
|
池田 茂政
いけだ もちまさ
岡山藩第9代藩主 |
徳川斉昭の九男として天保10年(1839年)、水戸藩江戸藩邸で生まれた
嘉永元年(1849年)8月2日、忍藩主松平忠国の養子となり、忠矩(ただのり)に改名する。
安政の大獄によって水戸徳川家と父・斉昭が処罰を受けると、幕府の顔色を窺った忠国により
廃嫡され、水戸徳川家に復籍する。
文久3年(1863年)2月6日、岡山藩主池田慶政の婿養子となり、池田 修政と名乗る。
慶応3年(1867年)10月15日、大政奉還にともない、朝廷から元尾張藩主の徳川慶勝らとともに
上洛することを命令される。王政復古の大号令後の慶応4年(1868年)、兄で15代将軍だった
徳川慶喜の追討の勅命が出され、岡山藩も東征軍に参加するように命じられる。しかし、
慶喜の弟である茂政は兄を討つための討伐軍に加われるはずもなく、3月15日に朝廷に対して
隠退・養子届けを出し、家督を章政に譲って隠居する。
明治32年(1899年)、61歳で死去した
|
伊木 忠澄
いぎ ただずみ
家老 |
文政元年8月23日(1818年9月23日)-明治19年(1886年)3月24日
岡山藩家老である土倉一静の三男として側室との間に生まれる。
忠澄は隠密裏に鴨方藩主池田政善の娘を斉敏の養女とした。豊前国中津藩主奥平昌高の
二男との婚姻を取り付け、池田慶政として藩主に迎えた。
元治元年(1864年)の第一次長州征討に際し、茂政は征討に批判的であったため、岡山藩の
藩論もこれに同調した。忠澄は藩を代表して姫路に赴き、征長総督徳川慶勝に面会し、
進軍の中止を求めた。しかし要求は却下され、翌元治2年(1865年)正月に帰国した。
この年の4月、忠澄は家督を嫡子の忠恭に譲り隠居したが、引き続き藩政には関わった。
大政奉還の翌年、慶応4年より始まった戊辰戦争では、岡山藩は官軍側として参戦した。
忠澄は木戸準一郎(孝允)と面談し、備中国諸藩の鎮撫を約束した。これに伴い、
忠恭が備中国諸藩の恭順書を取り付けた。
|
土倉 一善
とくら かずよし
家老 |
文政2年(1819年)-慶応4年2月21日(1868年3月14日)岡山藩の家老
文政2年(1819年)、岡山藩家老土倉一静の四男として岡山に生まれる。
父一静の婿養子となった一昌の養子となる。弘化元年12月(1844年)養父一昌の隠居に
より家督相続し岡山藩家老、佐伯1万石の領主となる。
|
牧野 権六郎
まきの ごんろくろう
|
文政2年8月2日(1819年9月20日) - 明治2年6月28日(1869年8月5日))
幕末の備前国・岡山藩士で尊王攘夷の志士である。
嘉永6年(1853年)11月14日、幕府より黒船来航のため岡山藩に房総警備の命令が下ったので
参謀長格で岡山から現地に赴いた
慶応2年3月、岡山藩軍事御用掛となる。
慶応3年(1867年)10月初旬、京都で小松清廉・福岡孝弟・後藤象二郎・辻将曹・都筑荘蔵らと
会合し、権六郎が「慶喜に将軍職を朝廷に奉還せしむるのみ」と発言し大政奉還に
意思統一させたという。10月13日、二条城で徳川慶喜に謁見して、大政奉還を建言した。
明治2年(1869年)、同藩刑法主事上席・参政となる。同年に死去。享年51
|
森下 景端
もりした かげなお |
文政7年(1824年) - 明治24年(1891年)1月1日)
森下重兵衛の子として岡山藩の七番町に生まれる。先祖は百姓であり、宝暦年間に武士に
取り立てられたという。元治元年(1864年)権六郎の命で吉田屋十郎右衛門とともに長州藩に
赴き山縣半蔵らと面会し、さらに益田親施(家老)と折衝することに成功している。
慶応元年(1865年)2月、牧野権六郎の推挙により郡奉行(備中国)になる。
明治元年(1868年)2月6日、太政官より岡山藩が江戸東征軍(新政府軍)先鋒を命じられたため、
耕戦隊と勇戦隊を率いて2月9日江戸へ向い出陣。途中京都今熊野(京都市東山区)の藩邸の
兵を加え350人編成とした。同年4月11日、江戸城明け渡しのため江戸城西の丸に入り
接収役を勤めた。明治元年(1868年)6月6日、新政府より命じられた奥州出兵(戊辰戦争)の
ため傷が癒えぬまま耕戦隊(7月15日遊奇隊と改称)を率いて出陣。6月22日より
関田(福島県いわき市)、矢板坂(福島県いわき市)、湯長谷(福島県いわき市)、
磐城平城攻城戦、三春(福島県三春町)出兵、二本松城攻城戦、同年8月組外格軍事方となり
若松城総攻撃と転戦した。
明治維新後
明治2年(1869年)1月、近習物頭末席・切米取りから知行150石となり、同月中に参政に出世し
役料30石加増となった。同年8月版籍奉還により権大参事に就任。
明治4年(1871年)11月、廃藩置県により大分県参事に登用。明治5年(1872年)大分県権令、
明治7年(1874年)大分県令となる。
|
藤本鉄石
ふじもとてっせき |
文化13年3月17日(1816年4月14日) - 文久3年9月25日(1863年11月6日))幕末の志士・書画家
岡山藩を脱藩し、諸国を遊歴して書画や軍学を学ぶ。京都で絵師として名をなし、
尊攘派浪人と交わり志士活動を行った。大和行幸の先駆けとなるべく大和国で挙兵して
天誅組を結成し、吉村虎太郎、松本奎堂とともに天誅組三総裁の一人となる。
その後、幕府軍の討伐を受けて天誅組は壊滅し、藤本も戦死した。
|
| 広島藩 |
第2次長征が事実上幕府軍の敗退に終わると、広島藩は次第に長州藩の影響を
受けるようになり、慶応3年(1867年)には長州藩・薩摩藩と同盟を結ぶに至った。
第15代将軍・徳川慶喜に大政奉還を推進するなどしている。このため、広島藩は後の
明治政府の中枢から排除されることにはなったが、官軍に加わって戊辰戦争を戦った。 |
浅野 斉粛
あさの なりたか
第9代藩主 |
文化14年9月28日(1817年11月7日) - 慶応4年1月12日(1868年2月5日))
安芸広島藩の第9代藩主。浅野家宗家10代、第8代藩主・浅野斉賢の長男
文政6年(1823年)6月18日、将軍徳川家斉の娘末姫と縁組する。
天災や事業、行事などが重なって、藩政は多難を極め、財政は火の車となった。このため、
斉粛は野村帯刀を登用して藩政改革に取り組んだが、あまり効果は得られなかった。
安政5年(1858年)4月12日、長男・慶熾に家督を譲って隠居した。隠居により、
通称を備後守に改める。
慶応4年(1868年)正月12日、52歳で死去した。
|
浅野 長訓
あさの ながみち
第10代藩主 |
文化9年7月29日(1812年9月4日) - 明治5年7月26日(1872年8月29日))第10代藩主
安芸国広島新田藩第5代藩主、のち広島藩第11代藩主
浅野長懋(ながとし、第7代藩主・浅野重晟の四男)の五男
長訓は野村帯刀・辻将曹の両名を家老(執政)として登用し、藩政改革を断行する。そして、
政治刷新や有能な人材登用、洋式軍制の導入などで藩政を立て直している。
慶応2年(1866年)、第二次長州征伐が起こったとき、停戦を主張し、7月には
岡山・徳島両藩主との連署により幕府・朝廷に征長の非と解兵を請願した。
明治元年(1868年)、明治新政府に恭順の意を示すため、徳川将軍からの偏諱を棄てて諱を
長訓に戻し、翌明治2年(1869年)正月24日には、広島新田藩主の浅野長勲に今度は
宗藩の家督を譲って隠居した。
|
浅野 長勲
あさの ながこと
第11代藩主 |
天保13年7月23日(1842年8月28日)-昭和12年(1937年)2月1日 第10代藩主
浅野懋昭(としてる。第7代広島藩主・浅野重晟の四男・浅野長懋(ながとし)の八男)の長男。
安政3年(1856年)2月、伯父・浅野長訓の養嗣子となる。
幕末期の動乱の中で養父の補佐を務め、江戸幕府と朝廷間の折衝に尽力した。
慶応3年(1867年)には大政奉還の建白書を土佐藩、長州藩と共に幕府に提出した。
その後の王政復古の大号令で議定となり、小御所会議では御所の封鎖に兵を出して協力し、
出席している。同会議では対立する薩摩藩・岩倉具視と土佐藩を仲介した。慶応4年1月17日、
会計事務総督兼任となる。同年2月20日、会計事務局補兼任となる。5月20日、免職となる。
明治2年2月4日、参与に就任した。同年3月6日、議定に就任する。同年5月17日、免職となる。
明治期は別記参照
|
浅野 忠敬
あさの ただひろ
家老 |
享和元年12月8日(1802年1月11日) - 安政7年1月1日(1860年1月23日))
広島藩の家老。安芸国広島藩筆頭家老で三原領3万石10代当主。浅野忠順の養子。
藤堂監物信任の次男として伊勢国津に生まれた。
文化11年(1814年)、14歳の時に家督を継ぎ三原領主、広島藩家老となった。
|
辻 維岳
つじ いがく |
文政6年(1823年)7月 - 明治27年(1894年)1月4日)
広島藩士・辻維祺(豊前)の三男として広島に生まれる。辻家は家祖・重勝が田中吉政に
仕えたが、田中氏断絶ののち浅野長晟に召し抱えられて以後、代々広島藩士となり、
維岳に至った
安政5年(1858年)藩主・浅野慶熾死去により浅野長訓が分家(広島新田藩主家)から藩主を
襲封すると、維岳ら改革派が実権を掌握するようになり、
文久2年(1862年)10月、騎馬弓筒頭から抜擢され野村帯刀らとともに年寄(執政)に任命され
国事掛を兼任した。元治元年(1864年)、年寄上座に昇進した維岳は、同年第1次征長の役が
起こると、幕府と長州藩との間の和平交渉を周旋した。
慶応3年(1867年)6月に上洛した維岳は、在京の薩摩・長州両藩士の間で高まりつつあった
倒幕の気運に同調し、小松帯刀・西郷隆盛らと謀り同年9月には広島藩代表として
薩長芸倒幕三藩同盟の成立に参加した。
維新後
維新後は慶応4年(1868年)2月に徴士として参与内国事務局判事となり、同年閏4月には
大津県知事に転じたが、早くも11月には罷免されている。
翌明治2年(1869年)9月、復古功臣34人の一人として永世禄400石を下付され、
明治3年(1870年)8月に待詔下院に出仕し同閏10月には辞任した後は、もはや新政府の中枢に
据えられることはなかった。
|
| 小倉藩 |
長州征討では、小倉藩は幕府側の九州側最先鋒として第一次、第二次ともに参加した。
慶応元年の第二次長州征討(四境戦争)では、小倉藩は総督・小笠原長行(同じ小笠原氏だが、
忠真の兄忠脩の子孫で唐津藩藩主・老中)の指揮下で小倉口の先鋒として参戦した。
この戦闘は幕府・小倉藩に不利に展開し、長州軍の領内侵攻により門司が制圧され、
小笠原総督は事態を収拾することなく戦線を離脱し、他の九州諸藩も撤兵。
孤立した小倉藩は慶応2年8月1日(1866年9月9日)小倉城に火を放ち田川郡香春に撤退した。
田川郡香春に政庁を設置した。慶応3年1月、長州藩と講和する。
|
小笠原 忠徴
ただあきら
第7代藩主 |
文化5年10月12日(1808年11月29日)- 安政3年5月12日(1856年6月14日) 第7代藩主
第6代藩主・小笠原忠固の次男
父の時代から小倉藩は財政難に悩まされた上、複雑な政争もあって家老や藩士など
300人以上が筑前国黒崎に出奔するなどの事件もあって、忠徴が継いだ頃の小倉藩は混迷を
極めていた。忠徴はこのような藩を立て直すため、積極的な藩政改革に取りかかる。
|
小笠原 忠幹
ただよし
第8代藩主 |
文政10年9月14日(1827年11月3日) - 慶応元年9月6日(1865年10月25日))
播磨安志藩第6代藩主、のち豊前小倉藩第9代藩主
播磨安志藩第5代藩主・小笠原長武の次男。
万延元年(1860年)11月6日、本家の豊前小倉藩主・小笠原忠嘉の死去により、末期養子として
家督を相続し、小倉藩主となった。文久3年、第14代将軍・徳川家茂が上洛したときは、
その警護を務めている。元治元年(1864年)5月5日、侍従に任官し、左京大夫に改める。
慶応元年(1865年)、39歳で死去した。小倉藩は次男の忠忱が継いだが、忠忱が幼少のため、
忠幹の喪は秘された。死去が公にされたのは、第2次長州征伐で小倉城を自焼し、
藩庁を田川郡香春に移した後の慶応3年(1867年)だった。 |
小笠原 忠忱
おがさわら ただのぶ
第9代藩主 |
文久2年2月8日(1862年3月8日)- 明治30年(1897年)2月6日)第9代藩主・小笠原忠幹の次男
嫡子忠忱はわずか4歳という幼年であったうえ、翌年には第二次長州征伐も控えていたため、
重臣たちは忠幹の喪を秘した。以後、家老の小宮民部、島村志津摩らにより藩政は動かされた。
第二次長州征伐では、長州藩の攻撃を受け、慶応2年8月には小倉城に火を放って退却した。
同年9月、田川郡香春に政庁を設置した。慶応3年1月、長州藩と講和する。
小宮民部は藩祖の小笠原忠真以来はじめて居城を離れたという恥辱の責任を
取って自刃している
慶応3年(1867年)6月25日、父忠幹の死亡を幕府に届け、家督を継いだ
慶応4年3月、幼少の忠忱に代わり、重臣を上洛させて、新政府に従う姿勢を示した
同年4月7日、新政府に対し、避難していた熊本藩領から本領に戻ることを申請する。
明治6年(1873年)1月、明治政府からヨーロッパ留学の許可を得る。
明治17年には伯爵を授爵された。明治30年(1897年)、36歳で死去した。
|
小宮 民部
こみや みんぶ
家老 |
文政6年(1823年)- 明治2年(1869年)秋山家に生まれ天保11年、中老の小宮家を継ぐ。
嘉永6年、家老となり、財政改革に尽力し、農兵隊を設立した。
藩主小笠原忠幹の信任厚く民部の名を賜る。慶応元年九月、忠幹が没するや、
その喪を秘し、幼君豊千代丸を護り難局に当たった。慶応2年の第二次征長の際は、
征長軍総督小笠原長行が去った為8月1日、小倉城を自焼させ香春に退却、
その責を負い、のち自刃した。 |
| 福岡藩 |
慶応元年(1865年)当初、一次長州征伐解兵に奔走した筑前勤王党を主とする勤王派が主力を
占めるが、勤王派は同時に三条実美ら五卿を太宰府に移しており、その事を藩主である
黒田長溥が幕府に責められていた。
藩論が佐幕に傾き、勤王派の多くが逮捕され家老・加藤司書をはじめ7名が切腹、月形洗蔵ら
14名が斬首、野村望東尼ら15名が流刑となった乙丑の獄が起こり筑前勤王党は壊滅した。
慶応4年(1868年)勤王派の巻き返しがあり藩論は勤王に転向と目まぐるしく変転した。
|
黒田 長溥
ながひろ
第11代藩主 |
文化8年3月1日(1811年4月23日)-1887年(明治20年)3月7日 福岡藩の第11代藩主
文化8年3月1日、薩摩藩主・島津重豪と側室・牧野千佐との間に重豪の十三男として生まれる。
文政5年(1822年)、第10代福岡藩主・黒田斉清の娘、純姫と婚姻。婿嗣子となり、養父同様、
将軍徳川家斉の偏諱を賜って黒田斉溥と称した
嘉永元年(1848年)11月、伊勢津藩主・藤堂高猷の三男・健若(のち慶賛、長知)を養嗣子とする。
嘉永3年(1850年)、実家島津家の相続争い(お由羅騒動)に際し、斉彬派の要請に応じて、
老中・阿部正弘、宇和島藩主・伊達宗城、福井藩主・松平慶永らに事態の収拾を求め、
翌嘉永4年(1851年)、その仲介につとめ、斉彬の藩主相続を決着させた。
斉溥は斉彬と同様、幕府に対しては積極的な開国論を述べている。
慶応元年(1865年)、藩内における過激な勤王志士を弾圧した(乙丑の変)。
しかしその後は薩摩藩と長州藩、そして幕府の間に立って仲介を務めるなど、
幕末の藩主の中で大きな役割を果たしている。
|
黒田 長知
くろだ ながとも
第11代藩主 |
天保9年12月19日(1839年2月2日)-明治35年(1902年)1月7日 第12代藩主
伊勢津藩主・藤堂高猷の三男として、江戸柳原藤堂藩邸にて生まれる。
嘉永元年(1848年)11月、11歳で福岡藩主・斉溥の養嗣子となり、黒田慶賛(よしすけ、
「慶」は将軍徳川家慶からの偏諱)と名乗った。
幕末期の動乱の中では、親長州藩的な人物で、禁門の変などにおける長州藩の苦境に際し、
朝廷や幕府に対して長州藩の赦免を求めている。
|
黒田 一葦
いちい
筆頭家老
|
文政元年(1818年)11月5日、三奈木黒田家9代当主黒田清定の子として生まれる。
翌年の文政2年(1819年)12月、福岡藩中老の加藤内匠徳裕の養子となり
加藤半之丞徳蔵と称し、天保8年(1837年)9月に養父から家督を継ぎ加藤家10代当主となる。
福岡藩主黒田長溥の偏諱を受けて黒田溥整と名乗り、弘化元年(1844年)8月以降からは
父と同じく播磨と称した。溥整は家老中で尊皇攘夷派に近い立場にあり、自らを「正義派」と
称する政治勢力に属し司書や実妹の田鶴子が嫁いでいた建部武彦らの尊皇攘夷派を
様々な役職に推挙し、藩政に参画させようと画策した。
元治2年(1865年)2月、加藤司書の征長軍解兵の功績が評価され、藩主達の反対を押し切って
司書の家老に昇進を実現させたが、これにより浦上信濃・小川讃岐・野村東馬などの
佐幕派家老が一斉辞任して勤王派が暴走することが多くなり、犬鳴御別館事件や
第二次長州征討決定により征長軍解兵の功績を否定されたことにより、司書は家老を
罷免され、藩論は一転し、佐幕派が復権することとなった。その結果、「乙丑の獄」が起こり、
勤王派はことごとく弾圧され、溥整も蟄居を命じられた。
慶応4年(1868年)2月、藩論が再び勤王に変わったことにより赦されて藩政に復帰した。
明治2年(1869年)2月、老いを理由に隠居し、名を一葦と改めた。
|
加藤 司書
ししょ
家老 |
文政13年3月5日(1830年3月28日)-慶応元年10月25日(1865年12月12日)
福岡藩家老。筑前勤王党首領格。月形洗蔵らとともに勤皇派の中心人物として活躍した。
福岡藩中老職の加藤家9代当主加藤徳裕と側室の尾形友花との間に生まれる。
天保11年(1840年)に遠縁である大老職の三奈木黒田家からの養子だった加藤家10代当主の
義兄加藤徳蔵(黒田溥整)が実家に復籍して三奈木黒田家の家督を継いだことで当時11歳の
司書が加藤家11代目2800石の家を継ぎ、福岡藩の中老の位列に加えられる。
安政3年、司書は藩の執政に就任し、義兄の後押しもあり尊皇攘夷派の中心人物となる。
慶応元年(1865年)2月11日、司書は征長軍解兵の功績を賞じられ、家老に昇進した。
藩内には賛否両論あったが、義兄の播磨の後押しで実現したが、佐幕派の3家老が
一斉辞任して対抗するなど対立が強まった。
これまでの勤王党の活躍を面白く思ってなかった佐幕派はこの事を聞き、加藤司書を非難し
黒田長溥に報告した。これに対して、加藤司書も黒田溥整と連名で「上下一致、人心一和して
過激を抑え因循を奮発することが肝要である。」という内容の建白書を提出したが、
これに黒田長溥はこれに激怒して司書は家老の職を三ヶ月で罷免される。
さらに幕府が長州再征討を決めた為に勤王派の周旋活動の功績が否定された結果、
佐幕派が復権し、形勢が逆転となって勤王派弾圧の動きが強くなった。
これにより勤王派140人余りが逮捕・監禁され、その中でも加藤司書以下7名が切腹、
月形洗蔵以下14名が桝木屋で斬首、野村望東尼以下15名が流罪の大粛清に至る(乙丑の獄)
慶応元年(1865年)10月25日、天福寺にて切腹。享年36。「君かため盡す赤心(まごころ)今よりは、
尚いやまさる武士の一念」と辞世の句を残した。
|
平野 国臣
くにおみ |
文政11年3月29日(1828年5月12日)-元治元年7月20日(1864年8月21日)
福岡藩足軽・平野吉郎右衛門の二男に生まれる。父・吉郎右衛門は千人もの門人を抱える
神道夢想流杖術の遣い手で役務に精勤して士分に取り立てられている。
天保12年(1841年)、国臣は足軽鉄砲頭・小金丸彦六の養子になった。
攘夷派志士として奔走し、西郷隆盛ら薩摩藩士や真木和泉、清河八郎ら志士と親交をもち、
討幕論を広めた。文久2年(1862年)、島津久光の上洛にあわせて挙兵をはかるが
寺田屋事件で失敗し投獄される。出獄後の文久3年(1863年)に三条実美ら攘夷派公卿や
真木和泉と大和行幸を画策するが八月十八日の政変で挫折。大和国での天誅組の挙兵に
呼応する形で但馬国生野で挙兵するがまたも失敗に終わり捕えられた。
身柄は京都所司代が管理する六角獄舎に預けられていたが、
禁門の変の際に生じた火災を口実に殺害された。 |
月形 洗蔵
せんぞう |
文政11年5月5日(1828年6月16日) - 慶応元年10月23日(1865年12月10日))
福岡藩の藩儒・朱子学者月形深蔵(漪嵐)の長男として誕生
嘉永3年(1850年)に父・深蔵の家督を継ぎ、馬廻役から大島(福岡県宗像市大島)の
定番となるも辞職し、尊皇攘夷運動に身を投じる。 万延元年(1860年)5月、藩主・黒田長溥が
参勤交代を行うに際し、尊王論の立場から述べた建白書を提出、さらに8月には藩の汚職を
批判する建言を行った。
このことから11月に捕縛され、翌年の文久元年(1861年)に家禄没収の上、
御笠郡古賀村(現・筑紫野市古賀、上古賀)に幽閉される(辛酉の獄)。
元治元年(1864年)5月、罪を許されて職に復し、町方詮議掛のち吟味役を命じられ、
薩長2藩の融和および薩長同盟の起草に勤めた。
幕府が再度の長州征討を決定すると、反対勢力の佐幕派が復権して藩論が一変し、
罪を問われ身柄を親類に預けられた後、同年10月23日に桝木屋(福岡県福岡市)に
おいて海津幸一ら13名とともに斬首された(乙丑の獄)。
月形半平太 - 戯曲の主人公。月形洗蔵と武市半平太をモデルにしたといわれる。
|
早川 養敬
わようけい |
天保3年7月23日(1832年8月18日) - 明治32年(1899年)2月11日)
筑前国遠賀郡虫生津村(現福岡県遠賀郡遠賀町)の農家の嶺直平の三男として生まれる。
宗像郡吉留村(現宗像市)の医師の早川元瑞の後を継いで医師となったが、
医業は門人に任せて福岡藩や諸藩の士と交流を続け、尊皇攘夷運動に活発に参加した。
第一次長州征討が迫る中、早川の仲介で元治元年12月4日(1865年1月1日)に西郷隆盛、
中岡の会談へと結びつく。さらに、同年12月12日(1月8日。12日(9日)という記録もある)に
早川、月形の斡旋で西郷、高杉晋作の会談が実現する。
福岡藩はこの時、長州周旋活動に取り組み、養敬は加藤司書・建部武彦・喜多岡勇平など
福岡藩士と西郷隆盛などのもとで、月形洗蔵と共に奔走した。
しかしその後、幕府が再び長州征討を決定したことで福岡藩は分裂し、早川・加藤・月形ら
筑前勤皇党は藩政を乱したとして加藤は切腹、月形は斬首、早川は幽閉となった(乙丑の獄
|
| |
 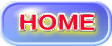 |