| 1前田氏 |
2島津氏 |
3伊達氏 |
4細川氏 |
5黒田氏 |
6浅野氏 |
7毛利氏 |
8吉川 |
| 9鍋島氏 |
10池田氏 |
11蜂須賀氏 |
12山内氏 |
13有馬氏 |
14佐竹氏 |
15南部氏 |
16生駒氏 |
| 17真田氏 |
18上杉氏 |
19津軽氏 |
20森 氏 |
21京極氏 |
22田中氏 |
23立花氏 |
24宗 氏 |
| 25小出氏 |
26加藤氏 |
27加藤氏 |
28加藤氏 |
29福島氏 |
30松浦氏 |
31伊東 |
32伊東 |
| 33戸沢氏 |
34最上氏 |
35蒲生氏 |
36織田氏 |
37織田氏 |
|
|
外様大名は、いわゆる譜代大名に対して、関ヶ原の戦い前後に新しく徳川氏の支配体系に組み込まれた大名を指す。
外様大名には大領を治める大名も多い。譜代大名は元は豊臣政権下のいち大名に過ぎなかった徳川家康のさらに
家臣という立場だったのに対し、外様大名は元は豊臣政権下において家康と肩を並べる大名家だったからである。
松平の名字を授与されることもあった。
松平加賀守家 - 前田家。加賀藩主 松平陸奥守家 - 伊達家。陸奥仙台藩主
松平薩摩守家 - 島津家。薩摩藩主 松平長門守家 - 毛利家。長州藩主
松平筑前守家 - 黒田家。筑前福岡藩主 松平安芸守家 - 浅野家。安芸広島藩主
松平肥前守家 - 鍋島家。肥前佐賀藩主 松平阿波守家 - 蜂須賀家。阿波徳島藩主
松平土佐守家 - 山内家。土佐藩主 松平因幡守家、松平備前守家 - 池田家。鳥取藩主、岡山藩主
|
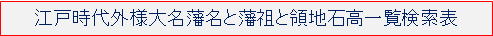 |
| |
藩 銘 |
支藩名 |
藩祖名 |
国名 |
石高 |
|
| |
加賀藩 |
宗家 |
前田利長 |
加賀 |
102万石 |
|
| 富山藩 |
前田利次 |
越中富山 |
10万石 |
|
| 大聖寺藩 |
前田利治 |
加賀大聖寺 |
7万石→10万石 |
|
| 七日市藩 |
前田利孝 |
上野国 |
1万石 |
|
| |
薩摩藩 |
宗家 |
島津家久 |
鹿児島 |
77万石 |
|
| 佐土原藩 |
島津以久 |
日向佐土原 |
3万石→2.7万石 |
|
| |
仙台藩 |
|
伊達政宗 |
陸奧仙台 |
62万石→28万石 |
|
| 一関藩 |
田村宗良 |
陸奧一関 |
3万石 |
|
| 中津山藩 |
伊達村和 |
陸奥国 |
3万石 |
改易 |
| 岩沼藩 |
田村宗良 |
陸前国 |
3万石 |
改易 |
| |
宇和島藩 |
|
伊達秀宗 |
伊予 |
10万石→7万石 |
|
| 伊予吉田藩 |
伊達宗純 |
伊予 |
3万石 |
陣屋 |
| |
熊本藩 |
|
加藤 清正 |
肥後 |
52万石 |
改易 |
| |
熊本藩 |
宗家 |
細川忠興 |
肥後熊本 |
54万石 |
|
| |
|
宇土藩 |
細川行孝 |
肥後宇土 |
3万石 |
|
| |
|
肥後新田藩 |
細川利重 |
肥後 |
3.5万石 |
|
| |
谷田部藩 |
|
細川興元 |
下野国 |
1万石 |
|
| |
福岡藩 |
|
黒田長政 |
筑前国 |
52.3万石 |
|
| 秋月藩 |
黒田長興 |
筑前国 |
5万石 |
秋月陣屋 |
| 東蓮寺藩 |
黒田高政 |
|
4万石 |
陣屋 廃藩 |
| |
広島藩 |
|
浅野幸長 |
安芸 |
42.6万石 |
|
| 三次藩 |
浅野長治 |
備後 |
5万石 |
廃藩 |
| 広島新田藩 |
浅野長賢 |
安芸 |
3万石 |
|
| |
赤穂藩 |
|
浅野長直 |
播磨 |
5.3万石 |
改易 |
| |
長州藩 |
|
毛利輝元 |
長門 |
36.9万石 |
|
| |
|
長府藩 |
毛利秀元 |
長門 |
6万石→5万石 |
櫛崎城 |
| |
|
清末藩 |
毛利元知 |
長門国 |
1万石 |
|
| |
岩国藩 |
岩国藩 |
吉川広家 |
周防岩国 |
3万石→6万石 |
岩国城 |
| |
|
徳山藩 |
毛利就隆 |
周防徳山 |
4.5万石 |
徳山城 |
| |
佐伯藩 |
|
毛利高政 |
豊後 |
2万石 |
佐伯城 |
| |
佐賀藩(鍋島藩) |
|
鍋島勝茂 |
肥前 |
35.7万石 |
佐賀城 |
| |
|
蓮池藩 |
鍋島直澄 |
肥前国 |
5.2万石 |
陣屋 |
| |
|
小城藩 |
鍋島元茂 |
肥前国 |
7.5万石 |
|
| |
|
鹿島藩 |
鍋島忠茂 |
肥前国 |
2.5万石 |
|
| |
岡山藩 |
|
池田輝政 |
備前国 |
31.5万石 |
岡山城 |
| |
|
鴨方藩 |
池田政言 |
備中国 |
2.5万石 |
鴨方陣屋 |
| |
|
生坂藩 |
池田輝録 |
備中国 |
1.5万石 |
|
| |
天城池田家 |
|
池田元助 |
備前国 |
3.2万石→3万石 |
陣屋 |
| |
鳥取藩 |
|
池田忠継 |
因幡国 |
32.5万石 |
鳥取城 |
| |
|
鹿奴藩 |
池田仲澄 |
因幡国 |
2.5万石→3万石 |
|
| |
|
若桜藩 |
池田清定 |
因幡国 |
2万石 |
|
| |
山崎藩 |
|
池田 恒元 |
播磨国 |
3万石 |
山崎陣屋 断絶 |
| |
備中松山藩 |
|
池田 長吉 |
備中 |
6.5万石 |
断絶 |
| |
徳島藩 |
|
蜂須賀至鎮 |
阿波国 |
17.5万石→25万石 |
徳島城 |
| |
|
富田藩 |
蜂須賀隆重 |
阿波国 |
5万石 |
廃藩 |
| |
土佐藩 |
|
山内 一豊 |
土佐国 |
22.2万石 |
高知城 |
| |
|
土佐新田藩 |
山内豊産 |
土佐国 |
1.3万石 |
|
| |
|
中村藩 |
山内康豊 |
土佐国 |
2万石 |
|
| |
久留米藩 |
|
有馬 豊氏 |
筑後国 |
21万石 |
久留米城 |
| |
久保田藩 |
|
佐竹義宣 |
出羽国 |
20万石 |
久保田城 |
| |
|
岩崎藩(新田藩 |
佐竹義長 |
出羽国 |
|
陣屋 |
| |
南部藩(盛岡藩) |
|
南部 利直 |
陸奥国 |
10万石 |
盛岡城 |
| |
|
八戸藩 |
南部直房 |
陸奥国 |
2万石 |
八戸城 |
| |
|
七戸藩(新田) |
南部信鄰 |
陸奥国 |
1.1万石 |
|
| |
矢島藩 |
|
生駒高俊 |
羽後国 |
1万石→1.5万石 |
|
| |
松代藩 |
|
真田信之 |
信濃国 |
10万石 |
松代城 |
| |
|
沼田藩 |
真田信之 |
上野国 |
3万石 |
沼田城 改易 |
| |
米沢藩 |
|
上杉景勝 |
出羽国 |
30万石→15万石 |
米沢城 |
| |
|
米沢新田藩 |
上杉勝周 |
出羽国 |
|
廃藩 |
| |
弘前藩 |
|
津軽 為信 |
陸奧国 |
4.7万石→10万石 |
弘前城 |
| |
|
黒石藩 |
津軽信英 |
陸奧国 |
1万石 |
|
| |
赤穂藩 |
|
森 忠政 |
播磨国 |
2万石 |
赤穂城 |
| |
三日月藩 |
|
森 長俊 |
播磨国 |
1.5万石 |
陣屋 |
| |
丸亀藩 |
宗家 |
京極 高次 |
讃岐国 |
6万石→5.1万石 |
丸亀城 |
| |
|
多度津藩 |
京極高通 |
讃岐国 |
1万石 |
|
| |
豊岡藩 |
|
京極高三 |
但馬国 |
3.5万石→1.5万石 |
豊岡陣屋 |
| |
峰山藩 |
|
京極高通 |
丹後国 |
1.3万石 |
|
| |
柳河藩 |
|
田中吉政 |
筑後国 |
32.5万石 |
改易 |
| |
柳河藩 |
|
立花 宗茂 |
筑後国 |
10.9万石 |
|
| |
三池藩 |
|
|
筑後国 |
1万石 |
|
| |
下手渡藩 |
|
|
陸奥国 |
1万石 |
|
| |
対馬府中藩 |
|
宗 義智 |
対馬国 |
2万石→10万石 |
桟原城 |
| |
出石藩 |
|
小出秀政 |
但馬国 |
5万石→6万石 |
|
| |
園部藩 |
|
小出 吉親 |
丹波国 |
2.9万石→2.4万石 |
|
| |
水口藩 |
|
加藤 嘉明 |
近江国 |
2.5万石 |
|
| |
大洲藩 |
宗家 |
加藤貞泰 |
伊予国 |
6万石 |
|
| |
|
新谷藩 |
加藤直泰 |
伊予国 |
1万石 |
陣屋 |
| |
高井野藩 |
|
福島 正則 |
信濃国 |
4.5万石→2万石 |
陣屋 断絶 |
| |
平戸藩 |
宗家 |
松浦 鎮信 |
肥前国 |
6.3万石 |
平戸城 |
| |
|
平戸新田藩 |
松浦 昌 |
肥前国 |
1万石 |
|
| |
飫肥藩 |
|
伊東 祐兵 |
日向国 |
5.7万石 |
飫肥城 |
| |
岡田藩 |
|
伊東長次 |
備中国 |
1.1万石 |
|
| |
新庄藩 |
|
戸沢 政盛 |
羽前国 |
6.8万石 |
新庄城 |
| |
山形藩 |
|
最上 義光 |
羽前国 |
57万石 |
山形城 改易 |
| |
伊予松山藩 |
|
蒲生 氏郷 |
陸奥 |
91万 |
断絶 |
| |
天童藩 |
|
織田信良 |
羽前国 |
2万石 |
|
| |
丹波柏原藩 |
|
織田 信雄 |
丹波国 |
2万石 |
|
| |
芝村藩 |
|
織田長政 |
大和国 |
1万石 |
|
| |
柳本藩 |
|
織田尚長 |
|
1万石 |
|
| |
相馬中村藩 |
|
相馬 利胤 |
磐城国 |
6万石 |
中村城 |
| |
三春藩 |
|
秋田 実季 |
磐城国 |
5万石 |
三春城 |
| |
臼杵藩 |
|
稲葉貞通 |
豊後国 |
5万石 |
臼杵城 |
| |
喜連川藩 |
|
喜連川 頼氏 |
下野国 |
5千石 |
|
| |
足守藩 |
|
木下 家定 |
備中国 |
2.5万石 |
|
| |
日出藩 |
|
木下 延俊 |
豊後国 |
3万石→2.5万石 |
|
| |
岡 藩 |
|
中川 清秀 |
豊後国 |
7万石 |
|
| |
二本松藩 |
|
丹羽長重 |
陸奥国 |
10万石→5万石 |
|
| |
新発田藩 |
|
溝口 秀勝 |
越後国 |
6万石 |
新発田城 |
| |
沢海藩 |
|
.溝口善勝 |
越後国 |
1.4万石→1万石 |
改易 |
| |
龍野藩 |
|
脇坂 安治 |
播磨国 |
5.3万石 |
|
| |
大溝藩 |
|
分部 光信 |
近江国 |
2万石 |
|
| |
村上藩 |
|
村上 頼勝 |
越後国 |
9万石 |
改易 |
| |
井伊谷藩 |
|
近藤 秀用 |
遠江国 |
1.5万石 |
廃藩 |
| |
郡上藩 |
|
金森長近 |
美濃国 |
3.8万石 |
改易 |
| |
徳野藩 |
|
平岡 頼勝 |
美濃国 |
1万石 |
改易 |
| |
高須藩 |
|
徳永 寿昌 |
美濃国 |
5万石 |
改易 |
| |
黒坂藩 |
|
関 一政 |
伯耆国 |
5万石 |
改易 |
| |
新見藩 |
|
関長政 |
備中国 |
1.8万石 |
|
| |
松前藩 |
|
松前 慶広 |
渡島国 |
1万石 |
|
| |
大村藩 |
|
大村 喜前 |
肥前国 |
2.8万石 |
|
| |
津和野藩 |
|
亀井茲矩 |
石見国 |
4.3万石 |
|
| |
狭山藩 |
|
北条氏盛 |
河内国 |
1万石 |
|
| |
掛川藩 |
|
北条 氏勝 |
遠江国 |
3万石 |
改易 |
| |
亀田藩 |
|
岩城 貞隆 |
羽後国 |
2万石 |
|
| |
窪田藩 |
|
土方 雄久 |
陸奥国 |
2万石 |
改易 |
| |
菰野藩 |
|
土方 雄氏 |
伊勢国 |
1.2万石 |
|
| |
麻田藩 |
|
青木 一重 |
摂津国 |
1.2万石 |
|
| |
高鍋藩 |
|
秋月 種長 |
日向国 |
3万石→2.7万石 |
|
| |
仁正寺藩 |
|
市橋 長勝 |
近江国 |
2万石→1.7万石 |
|
| |
黒羽藩 |
|
大関 資増 |
下野国 |
2万石→1.8万石 |
|
| |
大田原藩 |
|
大田原 晴清 |
下野国 |
1.2万石→1.1万石 |
|
| |
竜田藩 |
|
片桐 且元 |
大和国 |
1万石→4万石→1万 |
無嗣改易 |
| |
小泉藩 |
|
片桐 貞隆 |
大和国 |
1.6万石→1.1万石 |
|
| |
三田藩 |
|
九鬼 守隆 |
摂津国 |
3.6万石 |
|
| |
綾部藩 |
|
九鬼隆季 |
丹波国 |
2万石 |
|
| |
森 藩 |
|
来島 通親 |
豊後国 |
1.4万石 |
|
| |
福江藩 |
|
五島 玄雅 |
肥前国 |
1.5万石 |
|
| |
人吉藩 |
|
相良頼房 |
肥後国 |
2.2万石 |
|
| |
麻生藩 |
|
新庄 直頼 |
常陸国 |
3万石→1万石 |
|
| |
出石藩 |
|
仙石 秀久 |
但馬国 |
5.8万石→3万石 |
|
| |
林田藩 |
|
建部 政長 |
播磨国 |
1万石 |
|
| |
山家藩 |
|
谷 衛友 |
丹波国 |
1.6万石→1万石 |
|
| |
苗木藩 |
|
遠山友政 |
美濃国 |
1万石 |
|
| |
本荘藩 |
|
六郷 政乗 |
羽後国 |
2万石 |
|
| |
西条藩 |
|
一柳 直重 |
伊予国 |
3万石 |
改易 |
| |
小野藩 |
|
一柳 直家 |
播磨国 |
2.8万石→1万石 |
|
| |
小松藩 |
|
一柳 直頼 |
伊予国 |
1万石 |
|
| |
福嶋藩 |
|
堀 秀治 |
越後国 |
45万石 |
改易 |
| |
三条藩 |
|
堀 直政 |
越後国 |
5万石 |
改易 |
| |
村上藩 |
|
堀 直寄 |
越後国 |
10万石 |
改易 |
| |
村松藩 |
|
堀 直時 |
越後国 |
3万石 |
|
| |
蔵王堂藩 |
|
堀 親良 |
越後国 |
4万石 |
断絶 |
| |
椎谷藩 |
|
堀 直之 |
越後国 |
1万石 |
|
| |
須坂藩 |
|
堀 直重 |
信濃国 |
1万石 |
|
| |
烏山藩 |
|
成田 氏長 |
下野国 |
2万石→3.7万石 |
改易 |
| |
佐野藩 |
|
佐野 信吉 |
下野国 |
3.9万石 |
改易 |
| |
那須藩 |
|
那須 資景 |
下野国 |
1.4万石 |
無嗣断絶 |
| |
西方藩 |
|
藤田 信吉 |
下野国 |
1.5万石 |
改易 |
| |
片野藩 |
|
滝川雄利 |
常陸国 |
2万石 |
返還 |
| |
飯山藩 |
|
佐久間安政 |
信濃国 |
3万石 |
改易 |
| |
長沼藩 |
|
佐久間勝之 |
信濃国 |
1.8万石→1万石 |
改易 |
|
|
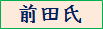

加賀前田氏は
菅原氏の末裔を
名乗ったために
梅を家紋にした。 |
美濃前田家
利仁流の系統で、叙用(利仁の七男、斎藤氏の祖)の子・吉信の三男・為時(伊博)を祖とする。
美濃国守護代斉藤氏庶家として、同国前田村に居住し前田氏を名乗ったとされる。
その子孫には前田玄以がいる。玄以は豊臣秀吉に仕え五奉行の一人となり、丹波において
大名となったが、子茂勝の代に江戸幕府により改易された。
尾張前田家 (与十郎家)
尾張の一族であり、代々の当主は与十郎を称した。上記の美濃の前田家との関係については系図上は
同族とされるが確証はない。戦国期には織田氏に仕えていたが、安土桃山時代以降に加賀藩に仕えた
加賀八家のうちのひとつ前田対馬守家として存続
尾張荒子前田家
代々の当主は蔵人を称したことから前田蔵人家ともいわれる。
前田利昌以前の系譜ははっきりしない。利昌の跡は嫡男の前田利久が継承したが、主君の織田信長の
命令で利久は隠居し、信長の寵臣で弟の前田利家が家督を継いだ。
利久の養子である前田利益は利家に仕えたがのち出奔し上杉氏に仕えた。利益の嫡男正虎を含む
家族は前田家に残留し、以降も加賀藩主家に仕えた。
加賀前田家
尾張国愛知郡(現名古屋市中川区)の土豪だった前田利昌の四男・利家が、織田信長に仕えて
功績を挙げ、能登国を領する大名となる。利家については下記記載 |
前田 利家(まえだ としいえ)
| 戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、戦国大名。加賀藩主前田氏の祖。豊臣政権の五大老の一人。 |
| 尾張国海東郡荒子村の荒子城主前田利春の四男。はじめ小姓として織田信長に仕え、 |
| 柴田勝家の与力として、北陸方面部隊の一員として各地を転戦し、能登一国23万石を拝領し大名となる。 |
| 利家は賤ヶ岳の戦いでは一時は秀吉と対立したものの、豊臣政権においては五大老の一人として |
| 徳川家康に次ぐ地位を得、さらに新たに加賀国と越中国を領した。 |
| 慶長4年(1599年) 閏3月3日 - 死去 |
豊臣政権崩壊後の江戸期前田家の存続
| 二代利長は秀吉没後に家康暗殺を企んでいるとの疑いをかけられるが、利長の母で利家の妻である芳春院が人質になることで |
| 疑いは晴れ、1600年(慶長5年)関ヶ原の戦いでは徳川方についてさらに領地を加増され、江戸時代初期には加賀・能登・越中3国で |
| 119万石を領する大大名になった。利長の跡を継いだ弟の三代利常は徳川秀忠の娘珠姫を正室に迎え、以後の当主も |
| 御三家・御家門との姻戚関係を繰り返したことから、加賀藩主は徳川将軍家から特に「松平」の苗字と葵紋を許されて御家門に |
| 準じる家格を与えられた。利常は次男の利次に富山藩10万石を、三男の利治に大聖寺藩7万石を分与した |
| ほかに利家の五男・利孝を祖とする上野国七日市藩がある。 |
本家
| |
加賀藩 |
外様。102万石 加賀国
| 1.前田利家(としいえ) 従二位・権大納言、贈従一位 |
|
| 2.前田利長 (としなが)従三位・権中納言、贈正二位・権大納言 |
1599-1605 |
利家の長男 |
| 3.前田利常 (としつね)従三位・権中納言、肥前守、贈従二位 |
1605-1639 |
利家の四男 |
| 4.前田 光高(みつたか)正四位下・左近衛権少将兼筑前守 |
1639-1645 |
利常の長男 |
| 5.前田 綱紀(つなのり)従三位、肥前守 |
1645-1723 |
光高の長男 |
| 6.前田 吉徳(よしのり)正四位下左近衛権中将兼若狭守 |
1723-1745 |
綱紀の三男 |
| 7.前田 宗辰(むねとき)正四位下左近衛権中将 |
1745-1746 |
吉徳の長男 |
| 8.前田 重煕(しげひろ正四位下、加賀守、左近衛権中将 |
1746-1753 |
吉徳の次男 |
| 9.前田 重靖(しげのぶ)正四位下、左近衛権少将、加賀守 |
|
吉徳の五男 |
| 10.前田 重教(しげみち)正四位下、左近衛権中将、加賀守 |
1753-1771 |
吉徳の七男 |
| 11.前田 治脩(はるなが)左近衛中将、従三位・参議 |
1771-1802 |
吉徳の十男 |
| 12.前田 斉広(なりなが)左近衛権中将、筑前守→加賀守→肥前守 |
1802-1822 |
重教の次男 |
| 13.前田 斉泰(なりやす)正二位、権中納言、加賀守 |
1822-1866 |
斉広の長男 |
| 14.前田 慶寧(よしやす)正四位下左近守権少将、筑前守 |
1866-1871 |
斉泰の長男 |
廃藩置県
|
七代藩主前田宗辰以降は早世する当主が多く、加賀騒動などのお家騒動が頻発し、藩政は停滞することが多かった。
加賀騒動
| 加賀藩(前田氏)は100万石以上の外様の大大名であり、江戸幕府はその力を削ぐことに力を注いでいた。その一つが目付役と |
| して幕府より加賀藩に派遣された本多家の存在であった。藩の運営は本多家をはじめとする年寄衆を含む重臣会議で |
| 決定されることになっていた。第五代藩主となった前田綱紀は藩主による独裁体制をめざし、藩政改革を進めた。 |
| 一方加賀藩の財政は元禄期以降、100万石の家格を維持するための出費の増大、領内の金銀山の不振により悪化の |
| 一途を辿っていた。享保8年(1723年)、藩主綱紀が隠居し息子の前田吉徳が第六代藩主となった。 |
| 吉徳はより強固な藩主独裁を目指した。足軽の三男で御居間坊主にすぎなかった大槻伝蔵を側近として抜擢し、 |
| 吉徳・大槻のコンビで藩主独裁体制を目指す一方、藩の財政改革にも着手する。大槻は米相場を用いた投機、新税の |
| 設置、公費削減、倹約奨励を行った。しかし、それらにより藩の財政は悪化が止まったものの、回復には至らなかった |
| 保守的な家臣たちの不満はますます募り、前田直躬を含む藩内の保守派たちは、吉徳の長男前田宗辰に大槻を非難する |
| 弾劾状を四度にわたって差出すに至った。その後、宗辰は藩主の座に就いてわずか1年半で病死し、異母弟の前田重煕が |
| 第八代藩主を継いだ。ところが延享5年の6月26日と7月4日に、藩主重熙と浄珠院への毒殺未遂事件が発覚する。 |
| これは奥女中浅尾の犯行であり、さらにこの事件の主犯が吉徳の側室だった真如院であることが判明した。これを受けて真如院の |
| 居室を捜索したところ、大槻からの手紙が見つかり不義密通の証拠として取り上げられ一大スキャンダルとなる |
支藩
前田 利次(としつぐ)
元和3年(1617年)4月29日、加賀藩主・前田利常の次男として金沢で生まれる。寛永16年(1639年)6月20日、利常から10万石を
分与されて支藩である富山藩を立藩し、その初代藩主となる。
| |
富山藩 |
外様。10万石 越中国
| 1.前田 利次(としつぐ) |
従四位下、侍従、淡路守、贈正四位 |
利常の次男 |
| 2.前田 正甫(まさとし) |
従四位下、大蔵大輔、近江守 |
利次の次男 |
| 3.前田 利興(としおき) |
従四位下、長門守 |
正甫の次男 |
| 4.前田 利隆(としたか) |
従四位下、出雲守 |
正甫の五男 |
| 5.前田 利幸(としゆき) |
従四位下、出雲守 |
利隆の長男 |
| 6.前田 利與(としとも) |
従四位下、淡路守 |
利隆の四男 |
| 7.前田 利久(としひさ) |
従五位下、出雲守、長門守 |
利幸の長男 |
| 8.前田 利謙(としのり) |
従四位下、出雲守 |
利与の長男 |
| 9.前田 利幹(としつよ) |
従五位下、出雲守、淡路守 |
利道の八男 |
| 10.前田利保(としやす) |
従四位下、出雲守、長門守 |
利謙の次男 |
| 11.前田利友(としとも) |
従四位下、出雲守 |
利保の六男 |
| 12.前田利聲(としかた) |
従四位下、大蔵大輔、贈従二位 |
利保の七男 |
| 13.前田利同(としあつ) |
従四位下、淡路守 |
斉泰の十一男 |
廃藩置県
|
前田 利治(としはる)
元和4年(1618年)、加賀藩主・前田利常の三男として生まれる。寛永16年(1639年)、父利常が隠居するにあたり、江沼郡を
中心に7万石を分封される。当初、鉱山の開発に力を注ぎ、領内に金山銀山を発見した。この鉱山開発の途上で見つかった
良質の陶土と、利治が茶人であったことが、後の九谷焼の生産に結びついた。
| |
大聖寺藩 |
外様。7万石→10万石 加賀国
| 1.前田 利治(としはる) |
正四位下、飛騨守、侍従 |
|
利常の三男 |
| 2.前田 利明(としあき) |
従四位下、飛騨守、贈正四位 |
|
利常の五男 |
| 3.前田 利直(としなお) |
従四位下、飛騨守 |
|
利明の長男 |
| 4.前田 利道(としみち) |
従四位下、遠江守 |
|
利章の長男 |
| 5.前田 利精(としあき) |
従五位下、備後守 |
|
利道の次男 |
| 6.前田 利物(としたね |
従五位下、美濃守 |
|
利道の三男 |
| 7.前田 利考(としやす) |
従四位下、飛騨守 |
|
利精の長男 |
| 8.前田 利之(としこれ) |
従四位下、侍従 |
|
利物の三男 |
| 9.前田 利極(としなか) |
従四位下、駿河守 |
|
利之の次男 |
| 10.前田 利平(としひら) |
従四位下、備後守 |
|
利之の六男 |
| 11.前田 利義(としのり) |
従四位下、美濃守 |
加賀藩主 |
斉泰の三男 |
| 12.前田 利行(としみち) |
|
加賀藩主 |
斉泰の五男 |
| 13.前田 利鬯(としか) |
正二位、子爵 |
加賀藩主 |
斉泰の七男 |
廃藩置県
|
| |
大聖寺
新田藩 |
外様 1万石 加賀国
前田 利昌(としまさ) 大聖寺藩の2代藩主前田利明の四男
廃藩
宝永6年1月15日、東叡山寛永寺で行われた5代将軍綱吉の葬儀に際し、中宮使饗応役を命じられる
同役の大准后使饗応役は以前から仲が悪かった大和国柳本藩主の織田秀親であった。
利昌は寛永寺吉祥院の宿坊で秀親を刺殺した。その後山城国淀藩主石川義孝に預けられ、
同月18日に切腹となった。
|
前田 利孝(としたか
前田利家の五男、父・利家の死後、兄の利長が徳川家康と本多正信が画策した「家康暗殺計画」の疑惑をかけられたため、
その弁明の証として利長の生母・芳春院(まつ)と共に人質として江戸に送られて幼年期を過ごした。
大坂の陣では徳川方として参戦して武功を挙げたことから、元和2年(1616年)12月26日、七日市に1万石の所領を与えられた。
| |
七日市藩 |
外様 1万石 上野国 現在の群馬県富岡市
| 1.前田 利孝(としたか |
従五位下、大和守 |
利家の五男 |
| 2.前田 利意(としもと |
従五位下、右近大夫 |
利孝の長男 |
| 3.前田 利広(としひろ |
大坂御加番代 |
利意の長男 |
| 4.前田 利慶(としよし |
|
利広の長男 |
| 5.前田 利英(としふさ |
|
利広の次男 |
| 6.前田 利理(としただ) |
従五位下、大和守、丹後守 旗本・前田孝始(苗木山前田家の孝矩の子 |
| 7.前田 利尚(としひさ) |
従五位下、大和守、丹後守 |
利理の四男 |
| 8.前田 利見(としあきら) |
従五位下、右近将監、大和守 |
利尚の次男 |
| 9.前田 利以(としもち) |
従五位下、大和守 |
利道の六男 |
| 10.前田 利和(としよし) |
従五位下、大和守 旗本・前田武宣(第7代藩主・利尚の弟)の三男 |
| 11.前田 利豁(としあきら) |
従五位下、大和守、丹後守 富山藩の第9代藩主・前田利幹の八男 |
| 12.前田 利昭(としあき) |
贈従四位、子爵 |
利豁の長男 |
廃藩置県
|
| |
 |
 |
| |
前田利家 |
前田利長 |
|
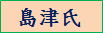

|
| 島津氏は、鎌倉時代初期に薩摩・大隅・日向3か国の守護に任ぜられて以来、この地方を本拠地として来た |
| 守護大名・戦国大名であり、1587年(天正15年)に豊臣秀吉の九州征伐によって豊臣氏に服属、薩摩・大隅・ |
| 日向の一部に跨がる所領の支配を認められた。 |
| 1600年の関ヶ原の戦いでは西軍につくが、徳川四天王の一人井伊直政の取りなしで本領を安堵され、 |
| 島津義弘の三男・家久が当主と認められた。この時点をもって正式な薩摩藩成立と見なすのが通説である |
|
島津 義久(しまづよしひひさ)
| 戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。薩摩国の守護大名・戦国大名。島津氏第16代当主 |
| 島津氏の家督を継ぎ、薩摩・大隅・日向の三州を制圧する。 |
| 義久は優秀な3人の弟(島津義弘・歳久・家久)と共に、精強な家臣団を率いて九州統一を目指し躍進し、 |
| 一時は筑前・豊後の一部を除く九州全てを手中に収めるなど、島津氏の最大版図を築いた。 |
島津 義弘(しまづ よしひろ)
| 関ヶ原の戦いの時は、家康から援軍要請を受けて1,000の軍勢を率い、家康の家臣である鳥居元忠が |
| 籠城する伏見城の援軍に馳せ参じた。しかし元忠が家康から義弘に援軍要請したことを聞いていないとして |
| 入城を拒否したため、当初の意志を翻して西軍への参戦を決意した。 |
| 西軍が総崩れとなり敗走を始めた時に義弘は徳川本陣に突撃を開始して転進、伊勢街道をひたすら南下した |
| この退却戦は「島津の退き口」と呼ばれ全国に名を轟かせた。 |
| 慶長5年家康は九州諸大名に島津討伐軍を号令。黒田、加藤、鍋島勢を加えた3万の軍勢を島津討伐に |
| 向かわせるが、家康は攻撃を命令できず睨み合いが続いた。関ヶ原に主力を送らなかった島津家には1万を |
| 越す兵力が健在であり、戦上手の義弘も健在。もしここで長期戦になり苦戦するようなことがあれば家康に |
| 不満を持つ外様大名が再び反旗を翻す恐れがあった。慶長7年(1602年)に家康は島津本領安堵を決定する。 |
江戸時代の島津家
島津 忠恒(ただつね) / 島津 家久( いえひさ)
| 天正4年(1576年)11月7日、島津義弘の三男として生まれる。 |
| 慶長7年(1602年)、関ヶ原の戦いで父の義弘が西軍に属したため、講和交渉をしていた伯父の義久に代わり |
| 徳川家康に謝罪のために上洛し、本領を安堵された。 |
| 慶長11年(1606年)、徳川家康から偏諱を受け、家久と名乗る。 |
| 元和3年(1617年)、将軍徳川秀忠から、松平の名字を与えられ、薩摩守に任官される。 |
| |
薩摩藩
島津家 |
外様 77万石 薩摩・大隅国
| 1.忠恒 ただつね家久 従三位、中納言、大隅守、薩摩守、陸奥守 |
義弘の三男 |
| 2.光久(みつひさ)従四位上、侍従、左近衛中将 |
忠恒(家久)の子 |
| 3.綱貴(つなたか)従四位上、左近衛中将、薩摩守 |
島津 綱久の子 |
| 4.吉貴(よしたか)正四位下、左近衛中将、薩摩守 |
綱貴の子 |
| 5.継豊(つぐとよ)従四位上・大隅守、左近衛中将 |
吉貴の長男 |
| 6.宗信(むねのぶ)従四位上・薩摩守、左近衛中将 |
継豊の長男 |
| 7.重年(しげとし)従四位下・薩摩守、左近衛少将 |
綱久の次男 |
| 8.重豪(しげひで)従四位上・薩摩守、左近衛中将 隠居後・従三位 |
重年の長男 |
| 9.斉宣(なりのぶ)正四位上・薩摩守、左近衛中将〕 |
重豪の長男 |
| 10.斉興(なりおき)〔正四位上・大隅守、参議 隠居後・従三位〕 |
斉宣の長男 |
| 11.斉彬(なりあきら)〔従四位上・薩摩守、左近衛権中将 (贈正一位・権中納言〕 |
斉興の長男 |
| 12.忠義(ただよし)〔従一位・大隅守、参議〕 |
久光の長男 |
廃藩置県 |
支藩
島津 忠将(しまづ ただまさ)
薩摩島津氏の分家、相州家の4代当主。父は相州家3代(伊作家10代)当主の島津忠良。兄の貴久が島津宗家を
継いだため、相州家を継ぐ。武勇に長けた人物で、兄・貴久をよく補佐して各地を転戦。宗家の義久、義弘は甥になる
忠将の子以久が砂土原藩主となる。もともとはこの地は元々島津一族の一人であった島津家久・豊久親子の領地で
あったのが、関ヶ原の戦いで豊久が死去し無嗣断絶扱いになり、改めて江戸幕府より以久に与えられたものである。
| |
佐土原藩 |
外様 3万石→2万7千石 日向国那珂郡
| 1.以久(ゆきひさ)〔従五位下・右馬頭〕 |
忠将の子 |
| 2.忠興(ただおき)〔従五位下・右馬頭〕 |
以久の三男 |
| 3.久雄(ひさたか)〔従五位下・右馬頭〕 |
忠興の子 |
| 4.忠高(ただたか)〔従五位下・飛騨守〕 |
久雄の長男 |
| 5.久寿(ひさとし)〔従五位下・式部少輔〕 |
島津久富の長男 |
| 6.惟久(これひさ)〔従五位下・淡路守〕 分与により2万7千石 |
忠高の長男 |
| 7.忠雅(ただまさ)〔従五位下・加賀守〕 |
惟久の三男 |
| 8.久柄(ひさもと)〔従五位下・淡路守〕 |
忠雅の三男 |
| 9.忠持(ただもち)〔従五位下・淡路守〕 |
久柄の三男 |
| 10.忠徹(ただゆき)〔従五位下・筑後守〕 |
忠持の長男 |
| 11.忠寛(ただひろ)〔従五位下・淡路守〕 |
忠徹の三男 |
廃藩置県
|
島津 久光(しまづ ひさみつ) 従四位上・左近衛権中将
江戸時代末期から明治時代初期にかけての日本の政治家、重富島津家当主、のち玉里島津家初代当主
幕末の薩摩藩における事実上の最高権力者で、公武合体運動を推進した。
お由羅騒動(おゆらそうどう)
| 江戸時代末期(幕末)に薩摩藩(鹿児島藩)で起こったお家騒動。別名は高崎崩れ、嘉永朋党事件。 |
| 藩主・島津斉興の後継者として側室の子・島津久光を藩主にしようとする一派と嫡子・島津斉彬の藩主襲封を |
| 願う家臣の対立によって起こされた。事件の名前になったお由羅の方は、江戸の町娘(三田の八百屋、舟宿、大工など |
| 多数の説がある)から島津斉興の側室となった人物である。彼女が息子・久光の藩主襲着を謀り、正室出生の斉彬廃嫡を |
| 目したことが事件の原因とされる。しかし、これはただお由羅が望んだだけのことではなく、祖父・重豪の影響が |
| 強い斉彬を嫌っていた斉興や家老・調所広郷などの重臣達の方が久光を後継者にと望んでいたとされる。 |
| 彼ら久光擁立派は、重豪同様の「蘭癖大名」と見られていた斉彬がこの頃ようやく黒字化した薩摩藩の |
| 財政を再び悪化させるのではと恐れていたのである。 |
薩摩藩 主人物
| |
 |
 |
 |
|
 |
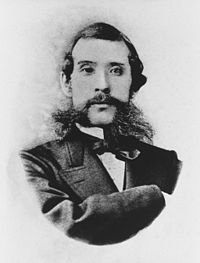 |
| |
島津 義久 |
島津 家久 |
島津 斉彬 |
|
西郷 隆盛 |
大久保利通 |
|
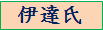
 |
| 鎌倉時代から江戸時代まで東北地方南部を本拠とした一族で、藤原北家山蔭流と称する。 |
| 出自は常陸国伊佐郡、あるいは下野国中村荘と伝えられる。魚名流藤原山蔭の子孫である。 |
| 鎌倉時代、源頼朝による奥州合戦に従軍し、石那坂の戦いで戦功を挙げた常陸入道念西が、頼朝より |
| 伊達郡の地を与えられ、伊佐あるいは中村に変わり伊達朝宗(ともむね)を名乗った。 |
| 南北朝時代の伊達行朝の代には、義良親王を奉じて奥州鎮定のために下向した北畠顕家に属し、 |
| 行朝は結城宗広らとともに式評定衆となった。南北朝時代にも伊達政宗同名がいて3度にわたり鎌倉府に |
| 反旗を翻している(伊達政宗の乱)。伊達成宗が上洛し将軍足利義政・日野富子らに献上物贈り、 |
| 幕府は陸奥には奥州探題職を置き、守護は置かない方針であったが伊達稙宗は陸奥守護を望み補任された。 |
| 天正12年(1584年)に当主になった17代・伊達政宗は強硬な領土拡張政策を進めて、会津の蘆名氏を滅ぼし |
| 伊達氏の領土は最大となった。 |
| しかしこれは関白・豊臣秀吉が発した惣無事令に背くものであったため、天正18年に政宗が秀吉が服属した |
| 秀吉が去ると、関ヶ原の戦いで徳川家康に味方し、その恩賞として62万石に加増された。 |
| 翌年には仙台城を築いて岩出山城から移り、江戸時代を通じて国持大名の家格を維持し、仙台藩62万石の |
| 大藩として繁栄した。 |
| 外様大名の中では別格の扱いを受け、将軍家から降嫁がある数少ない家のひとつとされ、松平の姓を |
| 与えられて松平陸奥守を称した。 |
|
伊達 政宗(だて まさむね)
伊達氏第16代当主・伊達輝宗と正室最上義守の娘・義姫(最上義光の妹)の間に生まれた嫡男。
幼少時に患った疱瘡(天然痘)により右目を失明し、隻眼となったことから後世独眼竜と呼ばれた。
秀吉の小田原攻囲(小田原征伐)中である天正18年(1590年)5月に政宗は秀吉に服属
関ヶ原の戦いは東軍に属した。慶長6年(1601年)には仙台城、仙台城下町の建設を始め、居城を移す。ここに、伊達政宗を
藩祖とする仙台藩が誕生した。石高62万石は加賀・前田氏、薩摩・島津氏に次ぐ全国第3位である。
| |
仙台藩 |
外様 大広間 国主(大身国持) 62万石→28万石
| 1.政宗(まさむね)〔従三位、陸奥守・権中納言・参議〕 |
輝宗の長男 |
| 2.忠宗(ただむね)〔従四位下、美作守のち陸奥守・権少将・侍従〕 |
政宗の二男 |
| 3.綱宗(つなむね)〔従四位下、陸奥守・(隠居後)若狭守・権少将〕 |
忠宗の六男 |
| 4.綱村(つなむら)〔従四位上、陸奥守・左近衛権中将〕 |
綱宗の長男 |
| 5.吉村(よしむら)〔従四位上、陸奥守・左近衛権中将〕 宮床伊達氏初代当主・伊達宗房の嫡男 |
| 6.宗村(むねむら)〔従四位上、陸奥守・左近衛権中将・侍従〕 |
吉村の四男 |
| 7.重村(しげむら)〔従四位上、陸奥守・左近衛権中将・侍従〕 |
宗村の長男 |
| 8.斉村(なりむら)〔従四位下、陸奥守・左近衛権少将・侍従〕 |
重村の次男 |
| 9.周宗(ちかむね)〔早世のため官位なし〕 |
斉村の長男 |
| 10.斉宗(なりむね)〔従四位下、陸奥守・左近衛権少将〕 |
斉村の次男 |
| 11.斉義(なりよし)〔従四位下、陸奥守・左近衛権少将〕 |
吉村の八男 |
| 12.斉邦(なりくに)〔従四位上、陸奥守・左近衛権中将〕 |
登米伊達 宗充の長男 |
| 13.慶邦(よしくに)〔従四位下、陸奥守・権中将〕 |
斉義の次男 |
| 14.宗基(むねもと)〔正四位〕 反明治新政府の罪により28万石に減封 |
慶邦の四男 |
| 15.宗敦(むねあつ)〔正四位〕 宇和島藩主・伊達宗城の次男 |
廃藩置県
|
仙台藩の支藩
田村家
伊達政宗の正室・愛姫の実家である田村家は、天正18年の豊臣秀吉による小田原征伐に参陣しなかった
ため、改易に処せられた。愛姫の生子である伊達忠宗は母の遺言により承応2年、忠宗の三男・田村宗良に田村家を再興させ、
栗原郡岩ヶ崎に1万石を与えられる。
| 1 |
岩沼藩 |
外様 。3万石 陸前国 現在の宮城県岩沼市
1.田村宗良(むねよし) 従五位下、右京亮、隠岐守 忠宗の3男
寛文11年、伊達騒動(寛文事件)に際して指導的役割を果たすことが出来ず、幕命によって
連座処分により閉門に処された
2.田村建顕(たつあき) 従五位下、右京大夫、因幡守 宗良の次男
画をなし学問に秀でていたため、徳川綱吉から寵愛されて、元禄4年(1691年)に譜代格となり
江戸城奥詰に任じられた。
|
| 2 |
一関藩
田村家 |
外様 。3万石 陸奧国 陸奥磐井郡一関
| 1.建顕(たけあき)〔従五位下、右京大夫〕奏者番 宗良の次男 |
| 2.誠顕(のぶあき)〔従五位下、下総守〕 |
旗本の田村顕当の五男 |
| 3.村顕(むらあき)〔従五位下、隠岐守〕 |
宇和島藩の第3代藩主・伊達宗贇の次男 |
| 4.村隆(むらたか)〔従五位下、下総守〕 |
仙台藩主・伊達吉村の五男 |
| 5.村資(むらすけ)〔従五位下、左京大夫〕 |
伊達村良の庶長子 |
| 6.宗顕(むねあき)〔従五位下、右京大夫〕 |
堀田正敦(伊達宗村の八男)の次男 |
| 7.邦顕(くにあき)〔従五位下、左京大夫〕 |
宗顕の次男 |
| 8.邦行(くにゆき)〔従五位下、右京大夫〕 |
宗顕の四男 |
| 9.通顕(ゆきあき)〔字:磐二郎〕 |
邦行の長男 |
| 10.邦栄(くによし)〔従五位下、右京大夫〕 |
角田石川氏当主・石川義光の七男 |
| 11.崇顕(たかあき)〔従五位下、右京大夫〕 |
角田石川氏当主・石川義光の九男 |
廃藩置県
|
伊達 村和(だて むらより)
寛文元年(1661年)8月25日、前仙台藩主・伊達綱宗の二男として、江戸の品川屋敷にて生まれる。
元禄8年(1695年)6月19日、仙台藩第4代藩主伊達綱村は、水沢伊達家第5代当主であった同母弟の
伊達村任に桃生郡中津山ほか3万石を分知して、新たに内分分家を立てることを幕府に申請する。
次第に中津山藩は藩としての体裁を整えていった。
| |
中津山藩 |
外様 。3万石 陸前国
1.伊達村和(むらより)〔従五位下、美作守〕 - 仙台藩第3代藩主・伊達綱宗の次男
元禄12年(1699年)9月9日、江戸城に登城する途上で、供回りの者が行列を横切った旗本・岡孝常と
刃傷沙汰に及び手傷を負わせたため謹慎を命じられた後、改易に追い込まれる。村和の身柄は
兄の綱村預かりとなり、中津山藩への分知は仙台藩領に戻され、六本木の藩邸も仙台藩の所有地となった。 |
伊達騒動
| 江戸時代前期に仙台藩で起こったお家騒動である。黒田騒動、加賀騒動または仙石騒動とともに三大お家騒動と呼ばれる。 |
| 仙台藩3代藩主の伊達綱宗は遊興放蕩三昧であったため、叔父にあたる一関藩主の伊達宗勝がこれをこのため宗勝は |
| 親族大名であった岡山藩主池田光政、柳川藩主立花忠茂、宮津藩主京極高国と相談の上、老中・酒井忠清に綱宗と |
| 仙台藩家老に注意するよう提訴した。にもかかわらず綱宗の放蕩は止まず、ついに1660年(万治3年)7月に家臣と |
| 親族大名(池田、立花、京極)の連名で幕府に綱宗の隠居と、嫡子の亀千代(後の伊達綱村)の家督相続を願い出た。 |
| 7月18日に幕府より綱宗は21歳で強制隠居させられ、4代藩主にわずか2歳の伊達綱村が就任した。 |
| 綱村が藩主になると、初めは大叔父にあたる宗勝や最高の相談役である立花忠茂が信任する奉行(他藩の家老相当) |
| 奥山常辰が、その失脚後に宗勝自身が実権を掌握し権勢を振るった。大老酒井忠清邸2度目の審問が行われるが、 |
| その審問中の控え室にて原田はその場で宗重を斬殺し、原田は即死、柴田もその日のうちに、蜂屋は翌日死亡した。 |
| 年長の後見人としての責務を問われた宗勝の一関藩は改易となった。 |
反伊達宗勝派
(柴田、古内、片倉、茂庭が宗重の国目付差出を一度妨害したり、古内と柴田が伊東重孝の死刑を
上申したりしているので確固たる派閥とは言い難い
主な伊達宗勝派
伊達兵部少輔宗勝、奥山大学常辰、原田甲斐宗輔、津田玄蕃景康・・・・
| 寛文事件が落着した後、藩主としての権力を強めようとした綱村は、次第に自身の側近を藩の重職に |
| 据えるようになった。これに不快感を示した伊達一門と旧臣は綱村に諌言書を提出したが、 |
| 聞き入れられなかった。このため1697年(元禄10年)、一門7名と奉行5名の計12名の連名で、 |
| 幕府に綱村の隠居願いを提出しようと試みた。これに対し、伊達家親族の高田藩主稲葉正往は隠居願いを |
| 差し止めた。元禄16年、この内紛が5代将軍徳川綱吉の耳に達し、仙台藩の改易が危惧されるようになった |
| 綱村は幕府に対して隠居願いを提出し、綱村には実子が無かったため従弟の伊達吉村が5代藩主となった。 |
| 山本周五郎の小説『樅ノ木は残った』などの題材となった。 |
|
|
|
|
|
戊辰戦争の敗北と北海道開拓
| 戊辰戦争では奥羽越列藩同盟を結成し、盟主となった。仙台藩は当時、日本国内有数の兵力を有していた |
| 仙台藩は東北地方の列藩会議を主宰し、奥羽鎮撫総督府に対して会津藩の赦免を懇願した。 |
| しかし、それが奥羽鎮撫総督府下参謀・世良修蔵(長州藩)によって握りつぶされると、 |
| 仙台藩士・姉歯武之進らが世良を殺害する。 |
| その後仙台藩は、奥羽鎮撫総督府軍を撃破して総督九条道隆や参謀醍醐忠敬らの身柄を確保して、 |
| 仙台藩は北上する薩長軍と相馬口駒ヶ嶺付近で戦ったが、中村藩の降伏により戦線を維持できなくなると、 |
| 仙台藩も降伏した。後、明治政府より責任を問われ、仙台藩は表高62万石から実高28万石に減封される。 |
|
|
|
|
|
| |
 |
| |
伊達政宗 |
|
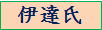

|
伊達 秀宗(だて ひでむね)
天正19年(1591年)9月25日、伊達政宗の庶長子として陸奥国柴田郡村田城にて生まれる。
文禄5年(1596年)5月9日、豊臣秀吉の猶子となり、秀吉のもとで元服し、偏諱を受けて秀宗と名乗った。
秀吉死後の慶長5年(1600年)に五奉行の石田三成らが五大老の徳川家康に対して挙兵
(関ヶ原の戦い)すると、三成方の宇喜多秀家の邸にて、対伊達政宗の人質となる。
秀宗は側室の子で、正室に高齢出産であった)との間に虎菊丸(のちの伊達忠宗)が生まれ、夭逝せずに
無事に育ったため、慶長8年(1603年)1月に政宗は虎菊丸を家康に拝謁させ、秀宗の立場は微妙になりだした
慶長14年(1609年)、秀宗は家康の命令で徳川四天王で重臣の井伊直政の娘の亀を正室として、
徳川陣営に取り込まれる事になる。弟の虎菊丸が慶長16年(1611年)12月に江戸城で元服し、将軍秀忠から
一字を賜って忠宗と名乗った事により、事実上秀宗は伊達家の家督相続者から除外される事になった
|
慶長19年(1614年)の大坂冬の陣には父と共に参陣し、初陣を飾る。戦後、大御所徳川家康から参陣の功として政宗に与えられた
伊予宇和島10万石を別家として嗣ぎ、同年12月25日にその初代藩主となった。
元和6年(1620年)、家老山家公頼が対立していた桜田元親に襲撃されて一族皆殺しにあう。秀宗はこれを幕府や
政宗に報告しなかったことから、激怒した父によって勘当される。秀宗は、長男であるにもかかわらず徳川時代に入って
仙台藩の家督を嗣げなかったことや、長期にわたって人質生活を送らされていたことから、政宗に対しかなりの恨みを
持っていることを話した。政宗もその秀宗の気持ちを理解し、勘当は解かれた。この件をきっかけとして親子の関係は
良好になったとされる。政宗と秀宗の仲は親密になりる
| |
宇和島藩 |
外様 大広間 国主格 10万石→7万石 伊予国 (1614年 - 1871年) 宇和島城
| 1.秀宗(ひでむね)〔従四位下・遠江守、侍従〕 10万石→分知により7万石 |
政宗の長男 |
| 2.宗利(むねとし)〔従四位下・大膳大夫、侍従〕 |
秀宗の三男 |
| 3.宗贇(むねよし)〔従四位下・遠江守、侍従〕7万石→新田分をして10万石格 |
綱宗の3男 |
| 4.村年(むらとし)〔従四位下・遠江守〕 |
宗贇の3男 |
| 5.村候(むらとき)〔従四位下・遠江守、左近衛権少将〕 |
村年の長男 |
| 6.村寿(むらなが)〔従四位下・遠江守、右近衛権少将〕 |
村候の四男 |
| 7.宗紀(むねただ)〔従四位下・遠江守、左近衛権少将〕 |
村寿の長男 |
| 8.宗城(むねなり)〔従四位下・遠江守、侍従〕 大身旗本・山口直勝の次男 |
| 9.宗徳(むねえ)〔従四位下・遠江守〕 |
宗紀の三男 |
廃藩置県
|
大身旗本・山口直勝
父・山口直清は宇和島藩5代藩主・伊達村候の次男で山口家の養嗣子となった人物である。
支藩
| |
伊予
吉田藩 |
外様 柳間 陣屋 3万石 伊予国
明暦3年、宇和島藩の初代藩主・伊達秀宗の五男・宗純が宗藩より3万石を分知されて立藩した支藩である。
| 1.宗純(むねずみ)〔従五位下・宮内少輔〕 |
|
| 2.宗保(むねやす)〔従五位下・能登守〕 |
宗純の次男 |
| 3.村豊(むらとよ)〔従五位下・左京亮〕 |
宇和島藩士・伊達宗職(宇和島藩主伊達秀宗の七男)の次男 |
| 4.村信(むらのぶ)〔従五位下・紀伊守〕 |
村豊の次男 |
| 5.村賢(むらやす)〔従五位下・和泉守〕 |
村信の次男 |
| 6.村芳(むらよし)〔従五位下・若狭守〕 |
村賢の次男 |
| 7.宗翰(むねもと)〔従五位下・紀伊守〕 |
宇和島藩の第6代藩主・伊達村寿の四男 |
| 8.宗孝(むねみち)〔従五位下・若狭守〕 |
山口直勝の三男 |
| 9.宗敬(むねたか)〔従四位下・若狭守〕 |
旗本・山口直信の次男 |
廃藩置県
|
|
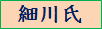
 |
| 本姓は源氏、鎌倉時代から江戸時代にかけて栄えた武家。清和源氏の名門足利氏の支流。 |
| 細川という名字は鎌倉時代に三河国額田郡細川郷(現在の岡崎市細川町)に土着したことに由来する |
| 細川氏は初め四国と淡路の守護にすぎなかったが赤松氏から摂津の守護を、山名氏から丹波の守護を |
| 譲り受けたことにより急速に発展、嫡流は幕府の管領の一つに列した。 |
| 南北朝時代、細川氏は足利尊氏に従い北朝・室町幕府方として活躍し、畿内・四国を中心に一門で8か国の |
| 守護職を占める有力守護大名となる。 |
|
細川 幽斎(ほそかわ ゆうさい)/ 細川 藤孝(ほそかわ ふじたか)
| 傍流の和泉上守護家出身の細川藤孝(幽斎)は、足利義昭の側近としてその将軍職就任に尽力した。 |
| しかし、義昭と信長の対立以降は、長男の忠興(三斎)とともに信長に従い上山城の長岡を賜い名字を長岡に |
| 改め明智光秀の組下として活躍、丹後一国を領した。本能寺の変では光秀に味方せず、秀吉に服した。 |
| 秀吉の死後、忠興は徳川家康に属し、細川に復姓し関ヶ原の戦いの功により豊前小倉藩39万9千石を領する |
| その子忠利の代に肥後熊本藩54万石の領主となり、明治維新に至る。明治時代には侯爵となる。 |
| 細川氏は、多くの大名の中でも、鎌倉、室町から江戸、現代まで名門として続いた希有な家である。 |
細川 忠興(ほそかわ ただおき)
永禄6年(1563年)11月13日、室町幕府13代将軍・足利義輝に仕える細川藤孝の長男として京都で生まれる。
正室は明智光秀の娘・玉子(通称細川ガラシャ)。
慶長4年(1599年)には加藤清正・福島正則・加藤嘉明・浅野幸長・池田輝政・黒田長政らと共に三成襲撃に加わった。
同年、豊臣家の大老の筆頭であった家康の推挙で、丹後12万石に加え豊後国杵築6万石が加増された。これにより、
都合18万石の大名となった。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは東軍に与した。
慶長5年(1600年)、徳川家康から戦後の論功行賞で丹後12万石から豊前国中津33万9,000石に国替のうえ加増となった。
| 1 |
中津藩 |
外様 39万9千石 豊前国(1600年 - 1632年)
1.忠興(ただおき)従三位、参議 細川藤孝の長男
2.忠利(ただとし)〈小倉藩〉従四位下左少将 忠興の三男
|
| 2 |
熊本藩 |
外様 54万石 熊本国 (1632年~1871年)
| 1.忠利(ただとし)〔従四位下、越中守・左近衛権少将・侍従〕 |
忠興の三男 |
| 2.光尚(みつなお)〔従四位下、肥後守・侍従〕 |
忠利の長男 |
| 3.綱利(つなとし)〔従四位下、越中守・左近衛権少将・侍従〕 |
光尚の長男 |
| 4.宣紀(のぶのり)〔従四位下、越中守・侍従〕 |
熊本新田藩主・細川利重の次男 |
| 5.宗孝(むねたか)〔従四位下、越中守・侍従〕 |
宣紀の四男 |
| 6.重賢(しげかた)〔従四位下、越中守・左近衛権少将・侍従〕 |
宣紀の五男 |
| 7.治年(はるとし)〔従四位下、越中守・侍従〕 |
重賢の次男 |
| 8.斉茲(なりしげ)〔従四位下、越中守・侍従〕 |
興文の三男 |
| 9.斉樹(なりたつ)〔従四位下、越中守・左近衛権少将・侍従〕 |
斉茲の三男 |
| 10.斉護(なりもり)〔従四位下、越中守・左近衛権中将・侍従〕 |
宇土藩主・細川立之の長男 |
| 11.韶邦(よしくに)〔正四位下、越中守・左近衛権中将・侍従〕 |
斉護の次男 |
| 12.護久(もりひさ)〔従四位下、右京大夫・侍従〕 |
斉護の三男 |
廃藩置県
|
支藩
細川 行孝(ほそかわ ゆきたか)
寛永14年(1637年)3月4日に熊本八代で生まれた。熊本藩2代藩主細川光尚の従兄弟行孝(初代忠利の弟・立孝の子)
祖父・忠興は忠利の跡を継いだ細川光尚は、八代の代わりに宇土・益城郡内に3万石の領地を設け、立孝嫡男の行孝に授けた。
| |
宇土藩
細川 |
外様 3万石 (1646年~1870年)
| 1.行孝(ゆきたか)〔従五位下、丹後守〕 |
立孝の長男 |
| 2.有孝(ありたか)〔従五位下、和泉守〕 |
行孝の三男 |
| 3.興生(おきなり)〔従五位下、山城守〕 |
有孝の長男 |
| 4.興里(おきさと)〔従五位下、大和守〕 |
興生の長男 |
| 5.興文(おきのり)〔従五位下、中務少輔〕 |
興生の三男 |
| 6.立礼(たつひろ)〔従五位下、和泉守〕→熊本藩8代細川斉茲となる |
興文の三男 |
| 7.立之(たつゆき)〔従五位下、和泉守〕 |
斉茲)の長男 |
| 8.立政(たつまさ)〔従五位下、中務少輔〕→熊本藩10代藩主細川斉護となる |
立之の長男 |
| 9.行芬(ゆきか)〔従五位下、豊前守〕 |
立之の次男 |
| 10.立則(たつのり)〔従五位下、山城守〕 |
行芬の次男 |
| 11.行真(ゆきざね)〔従五位下、豊前守〕 |
行芬の五男 |
廃藩置県
|
肥後新田藩、のち高瀬藩
肥後新田藩は熊本藩の支藩。寛文6年(1666年)熊本藩3代藩主・細川綱利の弟・利重が熊本藩の蔵米より
3万5千石を分与され立藩した。江戸鉄砲洲に住み参勤交代を行わない定府大名であった。
| |
肥後新田藩
高瀬藩
細川家
|
外様 3万5千石 (1666年~1870年)
| 1.利重(とししげ)〔従五位下、若狭守〕 |
光尚の次男 |
| 2.利昌(としまさ)〔従五位下、采女正〕 |
利重の長男 |
| 3.利恭(としやす)〔従五位下、備後守〕 |
利昌の次男 |
| 4.利寛(としひろ)〔従五位下、采女正〕 |
利昌の長男 |
| 5.利致(としゆき)〔従五位下、若狭守〕 |
利寛の三男 |
| 6.利庸(としつね)〔従五位下、能登守〕 |
利寛の四男 |
| 7.利国(としくに)〔夭折により官位官職無し〕 |
利庸の長男 |
| 8.利愛(としちか)〔従五位下、采女正〕 |
利庸の次男 |
| 9.利用(としもち)〔従五位下、能登守〕 |
利国の長男 |
| 10.利永(としなが)〔従五位下、若狭守〕 |
利愛の三男 |
廃藩置県
|
|
細川 興元(ほそかわ おきもと)
細川幽斎の次男、兄の忠興が細川輝経の養子になり奥州細川家を継いだため、興元は藤孝の和泉半国守護細川家の
分家として家を興した。はじめ父や兄と共に織田信長に仕え、大和片岡城攻めなどで活躍した。
秀吉没後は徳川家康に仕えて関ヶ原の戦いでも軍功を挙げた。
| 1 |
茂木藩 |
外様 1万石 下野国
1.細川興元(おきもと)
|
| 2 |
谷田部藩 |
外様 1.62万石 常陸国 茨城県つくば市谷田部
| 1.細川興元(おきもと) 従五位下 玄蕃頭 |
細川幽斎の次男 |
| 2.細川興昌(おきまさ) 従五位下 玄蕃頭 |
興元の長男 |
| 3.細川興隆(おきたか) 従五位下 豊前守 |
興昌の長男 |
| 4.細川興栄(おきなが) 従五位下 長門守 |
興隆の長男 |
| 5.細川興虎(おきとら) 従五位下 玄蕃頭 |
細川興誠の長男 |
| 6.細川興晴(おきはる) 従五位下 玄蕃頭 |
興虎の長男 |
| 7.細川興徳(おきのり) 従五位下 長門守 |
興晴の長男 |
| 8.細川興建(おきたつ) 従五位下 長門守 第8代藩主・有馬頼貴の長男・有馬頼瑞の次男 |
| 9.細川興貫(おきつら) 従五位下 玄蕃頭 後に正三位 |
興建の長男 |
廃藩置県
|
| |
 |
| |
細川 忠興 |
|
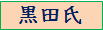

|
佐々木氏流を称する黒田氏
鎌倉時代末期、京極宗氏の弟とされる宗満(むねみつ)が近江国伊香郡黒田村に住み黒田氏を称したのが
したのが始まりといわれる。16世紀初め高政のとき備前国邑久郡福岡に移って赤松氏の被官となり、
高政の子重隆の時に播磨国姫路に移り家伝の目薬を製造、販売しやがて土豪として成長したとされる。
同国の有力豪族である小寺氏に仕えた。
黒田重隆の子職隆が赤松氏の一族である播磨の有力豪族・小寺氏に仕え、その養女を迎えて自らも
小寺氏を称した。職隆の子・孝高は織田信長に従い、その重臣である羽柴秀吉の麾下に入った。その際、
小寺氏が織田氏に敵対して衰退すると孝高は氏を黒田に復している。
1587年(天正15年)豊前国中津城主12万石となる。
|
黒田 孝高(くろだ よしたか) 黒田官兵絵
| 戦国時代から江戸時代前期にかけての武将・大名。孝高は諱で、一般には通称をとった黒田 官兵衛、 |
| あるいは出家後の号をとった黒田 如水(くろだ じょすい)として広く知られる |
| 天文15年11月29日(1546年12月22日)、黒田職隆の嫡男として播磨国の姫路に生まれる。永禄2年(1559年) |
| 母親を亡くし、文学に耽溺したと言われる |
| 豊臣秀吉の側近として仕え、調略や他大名との交渉などに活躍した。竹中重治(半兵衛)と双璧をなす |
| 秀吉の参謀であり、後世「両兵衛」「二兵衛」と並び称された。キリシタン大名でもあった。 |
| 織田家の重臣で摂津国を任されていた荒木村重が信長に対して謀反を起こし、有岡城に籠城した |
| 孝高は村重を翻意させるため交渉に有岡城に乗り込んだが、成功せず逆に幽閉される。1年後、有岡城は |
| 落城し、孝高は家臣の栗山利安によって救出された。 |
| 天正17年、家督を嫡男・長政に譲って隠居の身となり、以後も如水は秀吉の側近として仕えた。 |
黒田 長政(くろだ ながまさ)
豊臣秀吉の軍師である黒田孝高(官兵衛・如水)の長男。九州征伐の功績で中津の大名となり、
文禄・慶長の役などでも活躍した。特に関ヶ原の戦いで大きな戦功を挙げたことから
筑前名島に52万3,000石を与えられ、福岡藩初代藩主になった。
父の孝高と同じくキリシタン大名であったが、棄教した。 正室は栄姫(大涼院・徳川家康養女)で嫡男忠之、次男長興の母
黒田親子は豊臣時代は豊前中津藩12万石の賜り九州平定
| |
福岡藩
黒田家
黒田藩/
筑前藩 |
外様 52万3千石→43万3千石→47万3千石 筑前国 (1600年 - 1871年)
| 1.長政(ながまさ)〔従四位下・筑前守〕 |
孝高の長男 |
| 2.忠之(ただゆき)〔従四位下・筑前守、侍従〕 分知により43万3千石 |
長政の長男 |
| 3.光之(みつゆき)〔従四位下・右京大夫、侍従〕 |
忠之の長男 |
| 4.綱政(つなまさ)〔従四位下・肥前守、侍従〕 東蓮寺藩の3代長寛である光之の三男 |
| 5.宣政(のぶまさ)〔従四位下・肥前守、侍従〕 |
綱政の次男 |
| 6.継高(つぐたか)〔従四位下・筑前守、侍従〕 直方藩廃藩により47万3千石直方藩主・黒田長清の長男 |
| 7.治之(はるゆき)〔従四位下・筑前守、侍従〕 |
一橋徳川家初代当主・徳川宗尹の五男 |
| 8.治高(はるたか)〔従四位下・筑前守、侍従〕 |
讃岐国多度津藩主・京極高慶の七男 |
| 9.斉隆(なりたか)〔従四位下・筑前守、侍従〕 |
一橋徳川家2代当主・徳川治済の三男 |
| 10.斉清(なりきよ)〔従四位下・備前守、侍従〕 |
斉隆の長男 |
| 11.斉溥(なりひろ)のち長溥(ながひろ)〔従四位下・美濃守、侍従〕 |
薩摩藩主・島津重豪の十三男 |
| 12.長知(ながとも)〔正二位・下野守、左近衛権少将〕 |
伊勢津藩主・藤堂高猷の三男 |
廃藩置県
|
支藩
黒田 長興(くろだ ながおき)
福岡城内にて、長政と栄姫の次男として生まれる。 元和9年(1623年)、父長政が死去するとその遺言により、
長興には5万石が分与され、秋月藩を立藩した。黒田長政は本来、優秀な長興を本藩の跡継と生前に考え、兄で既に
本家を継いでいた暗愚な黒田忠之は長興の存在を恐れていた。
| |
秋月藩
黒田家 |
外様 5万石 筑前国 (1623年~1871年)
| 1.長興(ながおき) |
従五位下・甲斐守 |
長政の三男 |
| 2.長重(ながしげ) |
従五位下・甲斐守 〔奏者番〕 |
長興の次男 |
| 3.長軌(ながのり) |
従五位下・甲斐守 |
長重の長男 |
| 4.長貞(ながさだ) |
従五位下・甲斐守 |
福岡藩家臣・野村祐春の次男 |
| 5.長邦(ながくに) |
従五位下、甲斐守、河内守 |
長貞の長男 |
| 6.長恵(ながよし) |
従五位下、甲斐守 |
長邦の長男 |
| 7.長堅(ながかた) |
|
交代寄合御礼衆・山崎義俊の次男 |
| 8.長舒(ながのぶ) |
従五位下、甲斐守 |
向高鍋藩主・秋月種茂の次男 |
| 9.長韶(ながつぐ) |
従五位下、甲斐守 |
長舒の次男 |
| 10.長元(ながもと) |
|
土佐藩主・山内豊策の五男 |
| 11.長義(ながよし) |
従五位下、甲斐守。近江守 |
長元の六男 |
| 12.長徳(ながのり) |
従五位下、甲斐守 |
長元の八男 |
廃藩置県
|
黒田 高政(くろだ たかまさ)
福岡城内にて、長政と栄姫の四男として生まれる。元和9年(1623年)、父の死去による遺言で4万石を与えられて東蓮寺藩を立藩した。
| |
東蓮寺藩
黒田家 |
外様 4万石 筑前国 (1623年~1677年)
| 1.高政(たかまさ)〔従五位下・東市正〕 |
|
長政の四男 |
| 2.之勝(ゆきかつ)〔従五位下・市正〕 |
|
忠之の次男 |
| 3.長寛(ながひろ)〔従五位下・宮内少輔〕 |
本家4代綱政となる |
光之の三男 |
長寛は実父で福岡藩3代藩主・光之の後任となり領地を本藩に返還した。
福岡藩4代藩主・綱政となった。
第2期は元禄元年(1688年)光之(本家3代藩主)の四男・長清が5万石を分知されたことにより成立
外様 5万石 (1688年~1720年)
1.長清(ながきよ)〔従五位下・伊勢守〕 光之の四男
長清の嫡子の継高は本家6代藩主を継いでおり、他に嗣子が無かったため、ここに直方藩は廃藩となり
その所領は福岡藩に還付された。
|
| |
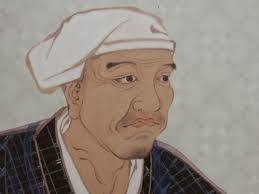 |
 |
| |
黒田 孝高/黒田官兵衛 |
黒田 長政 |
|
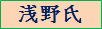

|
| 家系は清和源氏頼光流土岐氏の庶流で、土岐光衡の次男で判官代土岐光時が承久の乱で宮方で |
| であったために乱後、土岐郡浅野の浅野館に蟄居すると共に浅野氏を名乗り、光時に始まる |
| 土岐氏草創期の一族であるとされている。 |
| 浅野長勝の頃には、織田信長弓衆であったが、長勝の養女ねねが織田信長の家来だった木下藤吉郎に |
| 嫁いだことが浅野氏の転機となる。藤吉郎が出世街道をひた走ってついに天下人になると、浅野氏はその |
| 姻戚として重用された。 |
|
浅野 長政(あさの ながまさ)
| 戦国時代から江戸時代前期にかけての武将・大名。豊臣政権の五奉行筆頭。常陸真壁藩主。 |
| 尾張国春日井郡北野(現在の名古屋市)に安井重継の子として生まれる。織田信長の弓衆ををしていた叔父・浅野長勝に |
| 男子がなかったため、長勝の娘・やや(彌々)の婿養子として浅野家に迎えられ、のちに家督を相続した。長吉は秀吉に |
| もっとも近い姻戚として、信長の命で秀吉の与力となる。信長の死後は秀吉に仕え、天正11年の賤ヶ岳の戦いで |
| 戦功を挙げて、近江国大津2万石を与えられる。天正12年(1584年)には京都奉行職となり、のちに豊臣政権下で |
| 五奉行の筆頭となる。慶長4年(1599年)、前田利長らとともに家康から暗殺の嫌疑をかけられて謹慎し、家督を幸長に譲って |
| 武蔵国府中に隠居した。慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いでは家康を支持し、家康の三男・秀忠の軍に従軍して中山道を進み、 |
| 幸長は東軍の先鋒として岐阜城を攻め落とし、関ヶ原の本戦で活躍した。この功績により紀伊国和歌山37万石へ加増転封された。 |
| 1 |
紀州藩 |
外様 37.6万石 紀伊国 1600年 - 1613年
| 1.浅野 幸長(ゆきなが)従四位下・紀伊守 |
長政の長男 |
| 2.浅野 長晟(ながあきら)但馬守、従四位下 |
長政の次男 |
長兄・幸長が嗣子無くして病死したため、家督を相続
関ヶ原の戦い以後は徳川家康に従い、徳川秀忠の小姓を務め、備中足守に2万4,000石を与えられる。
大坂冬の陣、翌20年(1615年)の夏の陣に参戦し、樫井の戦いでは塙直之らを討つという功績を挙げた。
紀伊国内では北山一揆、紀州一揆と土着勢力の相次ぐ蜂起に遭い、戦後すぐに領内に
戻り一揆の鎮圧にあたった。
|
| 2 |
広島藩
浅野家 |
外様 42.6万石 安芸国 ( 1619年 - 1871年)
| 1.長晟(ながあきら) 〔従四位下・但馬守、侍従〕 |
長政の次男 |
| 2.光晟(みつあきら) 〔従四位下・安芸守、左少将〕 |
長晟の次男 |
| 3.綱晟(つなあきら) 〔従四位下・弾正大弼、侍従〕 |
光晟の長男 |
| 4.綱長(つななが) 〔従四位下・安芸守、侍従〕 |
綱晟の長男 |
| 5.吉長(よしなが) 〔従四位下・安芸守、左少将〕 |
綱長の長男 |
| 6.宗恒(むねつね) 〔従四位下・安芸守、左少将〕 |
吉長の長男 |
| 7.重晟(しげあきら) 〔従四位下・安芸守、左少将〕 |
宗恒の長男 |
| 8.斉賢(なりかた) 〔従四位下・安芸守、侍従〕 |
重晟の次男 |
| 9.斉粛(なりたか) 〔従四位下・安芸守、少将〕 |
斉賢の長男 |
| 10.慶熾(よしてる) 〔従四位下・安芸守、侍従〕 |
斉粛の長男 |
| 11.長訓(ながみち) 〔従四位下・安芸守、侍従〕 |
浅野長懋の五男 |
| 12.長勲(ながこと) 〔従四位下・安芸守、左近衛少将〕 |
浅野長懋の長男 |
廃藩置県
|
支藩
三次藩:江戸時代中期まで備後北部を領有した藩。藩庁として三次に三次城が置かれた。知行高は5万石。
初代広島藩主・浅野長晟の庶子で長男の長治が三次郡・恵蘇郡を与えられ立藩した。
| |
三次藩
浅野家 |
外様 5万石 安芸国(1632年 - 1720年)
| 1.長治(ながはる)〔従五位下・因幡守〕 |
広島浅野藩初代藩主長晟の長男(庶子) |
| 2.長照(ながてる)〔従五位下・式部少輔〕、 |
広島浅野藩2代藩主光晟の三男 |
| 3.長澄(ながずみ)〔従五位下・土佐守〕、 |
広島浅野藩3代藩主綱晟の次男 |
| 4.長経(ながつね)〔官位官職なし(夭折のため)〕、 |
3代藩主長澄の三男 |
| 5.長寔(ながざね)〔官位官職なし(夭折のため)〕、 |
3代藩主長澄の四男 |
享保4年(1719年)4月に数え年11歳で没した。三次浅野家は無嗣絶家となり除封され、
に所領は一旦は広島藩に還付されたが、ところが長寔は翌年、享保5年に数え年8歳で没したため
三次藩は再び廃藩となり、再興されることはなかった。
|
広島新田藩:享保15年(1730年)より広島藩の蔵米3万石を与えられ、広島藩4代・綱長の三男・長賢により立藩した。
藩主は参勤交代を行わず江戸定府の大名であった。
| |
広島
新田藩
浅野家 |
外様 3万石 安芸国(1730年 - 1869年)
| 1.長賢(ながかた)〔従五位下・兵部少輔〕、 |
広島浅野藩4代藩主綱長の三男 |
| 2.長喬(ながたか)〔従五位下・兵部少輔〕、 |
初代藩主長賢の長男 |
| 3.長員(ながかず)〔従五位下・近江守〕 |
広島浅野藩6代藩主宗恒の三男 |
| 4.長容(ながかね)、 |
2代藩主長喬の長男 |
| 5.長訓(ながみち)、 |
7代藩主重晟の孫→広島藩11代藩主となる |
| 6.長興(ながおき)、 |
7代藩主重晟の曾孫→広島藩12代藩主長勲 |
| 7.長厚(ながあつ)、 |
5代藩主長訓の兄の四男 |
廃藩置県
|
|
浅野 長重(あさの ながしげ)
浅野長政の三男として近江国に生まれる。秀忠の小姓として仕えるようになった。この年春に従五位下采女正
関ヶ原の戦いでの浅野一族の戦功は著しかったので、慶長6年(1601年)に芳賀高武の旧領である
下野真岡2万石が与えられた。さらに慶長7年(1602年)には家康の養女となっていた松平家清の娘と結婚。
| 1 |
真岡藩 |
外様 2万石 下野国
1.浅野長重(ながしげ) 従 五位下、采女正 長政の三男
幸長の父・浅野長政は慶長10年(1605年)に隠居して家督を幸長に譲ったが、翌年に隠居料として
幕府から常陸真壁などに5万石を与えられた。これが真壁藩の立藩である。浅野長重は真岡藩2万石を
幕府に返上し父のあとを継ぐ
|
| 2 |
真壁藩 |
外様 5万石 常陸国
| 1.浅野長政(ながまさ) |
宗家は長晟に譲って隠居 |
|
| 2.浅野長重(ながしげ) |
従五位下、采女正 |
長政の三男 |
|
| 3 |
笠間藩 |
外様 5.3万石 常陸国 元和8年-正保2年(1645年)
| 1.浅野長重 - 従五位下、采女正 |
|
| 2.浅野長直 - 従五位下、内匠頭 |
浅野長重(浅野長政の三男 |
|
|
| 4 |
赤穂藩 |
外様 5.3万石→5万石→5.3万石 播磨国 (1645年 - 1701年)
| 1.長直(ながなお)〔従五位下、内匠頭〕 |
|
| 2.長友(ながとも)〔従五位下、采女正〕 分知により5万石 |
長直の長男 |
| 3.長矩(ながのり)〔従五位下、内匠頭〕 |
長友の長男 |
浅野長矩は江戸城松の廊下で吉良義央を切りつける殿中刃傷事件を起こし
即切腹させられお家断絶して、家老の大石内蔵助以下47士吉良邸討ち入りで有名
|
|
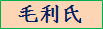
 |
| 鎌倉幕府の名臣大江広元の四男・大江季光を祖とする一族、したがって大江広元の子孫ではあるが |
| 嫡流ではない。名字の「毛利」は、季光が父・広元から受け継いだ所領の相模国愛甲郡毛利庄、 |
| 現在の神奈川県厚木市周辺)を本貫とする。 |
| 鎌倉時代末期から南北朝時代初期にかけて、越後国佐橋庄南条(現在の新潟県柏崎市)から |
| 安芸国高田郡吉田へ移った後に国人領主として成長し、山名氏および大内氏の家臣として栄えた。 |
| 戦国時代には国人領主からついに戦国大名への脱皮を遂げ、中国地方最大の勢力となる。 |
| しかし1600年(慶長5年)の関ヶ原の戦いでは西軍の総大将となり、敗戦後、周防国・長門国の2か国に |
| 減封され36万9千石の長州藩(萩藩)になり外様大名となるも、江戸時代を通じて安泰であった。 |
| 江戸時代末期には長州藩から数々の優秀な志士が現れ、明治維新を成就させる原動力となった。 |
江戸時代に周防国と長門国を領国とした外様大名・毛利氏を藩主とする藩。家格は国主・大広間詰
藩庁は長く萩城(萩市)に置かれていたために萩藩(はぎはん)とも呼ばれていたが、幕末には
周防山口の山口城に移ったために、周防山口藩(すおうやまぐちはん)と呼ばれることとなった。
|
|
毛利 輝元(もうり てるもと)
天文22年(1553年)1月22日、毛利隆元の嫡男として安芸国(現在の広島県)に生まれる。
永禄8年(1565年)、13代将軍・足利義輝より「輝」の一字を許され元服し、輝元と名乗り[注 1]、実質的な当主となるが、
元就が死没するまで当主権限を元就が掌握する二頭政治体制が続くことになる
足利義昭は毛利氏のもとにおいて反信長勢力を糾合し、越後国の上杉謙信はそれまで信長と同盟関係にあったが
将軍家の呼びかけにより信長と敵対する。
天正14年(1586年)の九州征伐にも先鋒として参加し、武功を挙げ、秀吉の天下統一に大きく寄与した。
1600年(慶長5年)の関ヶ原の戦いでは西軍の総大将となり、敗戦後、周防国・長門国の2か国に減封され36万9千石の
長州藩(萩藩)になり外様大名となるが輝元は隠居して子の秀就に家督を継がせた。
| |
長州藩
毛利家 |
外様 36.9万石 長門国
| 1.秀就(ひでなり) |
従四位下長門守、侍従、右近衛権少将 |
輝元の子 |
| 2.綱広(つなひろ) |
従四位下。長門守。薨後贈従三位 |
秀就の子 |
| 3.吉就(よしなり) |
従四位下長門守 |
綱広の長男 |
| 4.吉広(よしひろ) |
従四位下、侍従 |
綱広の次男 |
| 5.吉元(よしもと) |
従四位下、長門守 |
長府藩主・毛利綱元の長男 |
| 6.宗広(むねひろ) |
従四位下、大膳大夫、侍従 |
吉元の五男 |
| 7.重就(しげなり) |
従四位下、侍従、大膳大夫、左近衛少将 |
長府藩主毛利匡広の十男 |
| 8.治親(はるちか) |
壱岐守、従四位下、侍従 |
重就の四男 |
| 9.斉房(なりふさ) |
従四位下、侍従 |
治親の長男 |
| 10.斉熙(なりひろ) |
従四位下、侍従、中務大輔、大膳大夫、左近衛権少将 |
治親の次男 |
| 11.斉元(なりもと) |
従四位上、左近衛権少将 |
重就六男 |
| 12.斉広(なりとう) |
従四位下・修理大夫、左近衛権少将 |
斉熙の子 |
13.敬親/慶親
|
従四位上、左近衛権中将 |
親著の長子 |
| 14.元徳/定広 |
従三位・長門守、侍従、左近衛少将 徳山藩第8代藩主・毛利広鎮の十男 |
廃藩置県
|
| 関ヶ原の戦いの後に毛利輝元が中国地方120万石から減封され防長2カ国36万石となった際に、輝元が東の守りとして |
| 岩国に吉川広家を置き、西の守りとして改めて長門国豊浦郡(現在の山口県下関市)に秀元が領地を与えられた。 |
| なお、綱元の時に叔父の毛利元知に1万石を分知し、支藩の清末藩を立藩させている。 |
| 歴代藩主の中では3代・綱元の子である毛利吉元と、8代藩主の匡敬(重就)が宗藩の長州藩主を継いでいる。 |
支藩
穂井田 元清(ほいだ もときよ)
天文20年(1551年)、安芸国の戦国大名・毛利元就の四男として誕生する。
元就の正室の子である毛利隆元、吉川元春、小早川隆景の3人の兄たちが元就から大切にされたのに対して、
元清をはじめとする側室の子達は、父から「虫けらなるような子どもたち」と表現されている。
永禄11年(1568年)、村上水軍との関係を強化する必要もあり、来島の村上通康の娘を妻として迎えた。
元清が三村家親の子である穂井田元祐(庄元資)の養子となり穂井田姓を名乗ったとしている
天正13年(1585年)の四国攻めに出陣。また同年、長男の毛利秀元が毛利輝元の養子となったため、元清も毛利姓に
復した。天正15年(1587年)、九州征伐に出陣する。
文禄元年(1592年)、文禄の役では、病床にあった輝元に代わって自ら毛利軍の総大将となった。
慶長2年(1597年)、桜尾城において47歳で死去する。
江戸時代初期に、元清の子孫は長州藩の支藩である長府藩、清末藩の藩主として存続する。
| |
長府藩
毛利家 |
| 外様 6万石→5万石→3.8万石→4.7万石→5万石 櫛崎城 |
| 1.元清、毛利元就四男 |
|
| 2.秀元、 伊予守、治部大輔、従四位、侍従 |
穂井田元清の子 |
| 3.光広、 従四位下、和泉守 |
初代藩主秀元二男 |
| 4.綱元 従四位下、甲斐守 2代藩主光広長男(※綱元の長男は宗藩を継いで5代藩主毛利吉元となる) |
5.元朝、宗藩の嗣子となって毛利宗元に改名継ぐことなく死去
|
宗藩5代藩主毛利吉元の長男 |
| 6.元矩、 |
3代藩主綱元四男 |
| 7.匡広、 従五位下、甲斐守 長門清末藩2代藩主毛利元平が継いで改名 |
| 8.師就、 従五位下、主水正 |
6代藩主匡広五男 |
| 9.匡敬、 従四位下 6代藩主匡広十男(※のちに宗家を継いで7代藩主毛利重就となる) |
| 10.匡満、 従五位下。能登守宗家7代藩主毛利重就長男 |
宗家7代藩主毛利重就長男 |
| 11.匡芳、 従五位下、甲斐守宗家7代藩主毛利重就五男 |
宗家7代藩主毛利重就五男 |
| 12.元義、 従四位下、左京亮、甲斐守10代藩主匡芳長男 |
10代藩主匡芳長男 |
| 13.元運、 従五位下、左京亮、甲斐守11代藩主元義三男 |
11代藩主元義三男 |
| 14.元周、 従五位下、左京亮11代藩主元義長男元寛の三男 |
11代藩主元義長男元寛の三男 |
| 15.元敏、1 |
12代藩主元運六男 |
廃藩置県 |
毛利 就隆(もうり なりたか
毛利輝元の次男。母は児玉元良の娘・清泰院。正室は長府藩主・毛利秀元の娘・松菊子、
元和3年、周防都濃郡に3万石を与えられた。後に4万5,000石に加増され、その所領を下松藩として認められて初代藩主となった。
1650年(慶安3年)6月、下松は交通に適していないという理由から就隆は藩庁を同国徳山に移した。
| |
下松藩
くだまつ
徳山藩
毛利家
|
外様 4万5千石→3万石→4万石 周防国 長州藩(萩藩)の支藩
| 1.就隆 |
毛利輝元の二男 |
| 2.元賢もとかた 従五位下、日向守 |
就隆の五男 |
| 3.元次 もとつぐ 従五位下、飛騨守 |
就隆の四男 |
| 4.元尭もとたか 従五位下、日向守 |
元次の二男 |
| 5.広豊ひろとよ 従五位下、但馬守、山城守 |
元次の三男 |
| 6.広寛ひろのり 従五位下、志摩守 |
広豊の二男 |
| 7.就馴なりよし 従五位下・大和守 |
広豊の十一男 |
| 8.広鎮ひろしげ 従五位下、大和守、日向守 |
就馴の二男 |
| 9.元蕃もとみつ従五位下、従三位、山城守 (広鎮の十男は宗家を継いで、14代元徳となる) |
| 10.元功もといさ従五位下、大和守 |
長府藩主・毛利元運の子 |
| 11.元秀 |
元功の長男 |
| 12.元靖 |
元秀の長男 |
| 13.就擧 |
元靖の長男 |
| 14.就慶 |
就擧の長男 |
| 15.元晴 |
|
| 廃藩置県 |
|
| |
清末藩
毛利家 |
外様 1万石 長門国 長府藩支藩の支藩
| 1.元知(もととも)〔従五位下、刑部少輔〕 |
長府藩初代藩主・毛利秀元の三男 |
| 2.元平(もとひら)〔従五位下、甲斐守〕 |
元知の次男 |
| 3.政苗(まさなり)〔従五位下、讃岐守〕 |
平(のち匡広)の七男 |
| 4.匡邦(まさくに)〔従五位下、讃岐守〕 |
政苗の七男 |
| 5.政明(まさあき) |
伊勢長島藩主・増山正賢の次男 |
| 6.元世(もとよ) 〔従五位下、讃岐守〕 |
下野国佐野藩主・堀田正敦の六男 |
| 7.元承(もとつぐ)〔従五位下、出雲守〕 |
長門長府藩主・毛利元義の十一男 |
| 8.元純(もとずみ)〔従五位下、讃岐守〕 |
豊後日出藩主・木下俊敦の四男 |
廃藩置県
|
|
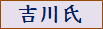
 |
藤原南家工藤流の流れを汲む。吉川の名乗りは駿河入江荘吉川(現在静岡市清水区)の地名に基づくもので、
吉川以外に「吉河」「吉香」とも書かれる。 安芸吉川氏(宗家)、石見吉川氏、播磨吉川氏、駿河吉川氏、
境氏吉川氏に分れ
安芸吉川氏(宗家)
南北朝時代から室町時代にかけては土佐国の分郡守護に任命される。
戦国時代初期に吉川国経の娘を毛利元就が、国経の嫡男・元経が元就の姉を、それぞれ娶った関係から、
利家と吉川家は姻戚関係となる。元就の次男・毛利元春を養子に迎え、隠居に追い込まれる。
|
吉川 元春(きっかわ もとはる) / 毛利 元春(もうり もとはる)
毛利元就の次男。母は吉川国経の娘・妙玖。同母の兄弟に兄の毛利隆元、弟の小早川隆景、その他異母の兄弟が多くいる。
父・元就によって藤原南家の流れを汲む安芸国の名門・吉川氏に養子として送り込まれ、家督を乗っ取る形で相続した。
天正10年(1582年)末、家督を嫡男の元長に譲って隠居した。これは、秀吉に仕えることを嫌ってのことであるとされている。
吉川 元長(きっかわ もとなが)
天文17年(1548年)、吉川元春の嫡男として生まれた。
天正10年(1582年)、本能寺の変を契機として羽柴秀吉と毛利氏が和睦すると、秀吉への姿勢において輝元・小早川隆景と
元春の間に差が生じたため、元春は12月に隠居した。
吉川 広家(きっかわ ひろいえ)
永禄4年(1561年)11月1日、吉川元春と新庄局の三男として生まれ、元亀元年(1570年)、父と共に尼子勝久の討伐戦で初陣する。
天正14年(1586年)11月に九州平定従軍中の(身分上は隠居の)父・元春が、次いで翌天正15年(1587年)6月に同じく従軍中で
吉川家当主である長兄の元長が相次いで死去したため、吉川氏の家督を相続し居城日野山城などの所領も継承する。
毛利輝元から、毛利氏の祖先・大江広元の諱から「広」の一字書出を与えられ、「広家」と改名した。
慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは、毛利輝元が石田三成、安国寺恵瓊らによって西軍の総大将とされた(広家は
徳川家康率いる東軍に加勢するよう提言したが、三成らの裏工作で広家が知らないうちに輝元が担ぎ出されたとされる)。
あくまで家康率いる東軍の勝利を確信していた広家は、同じく毛利重臣である福原広俊と謀議を練り、恵瓊や輝元には
内密にしたうえ独断で朝鮮の役以来の友人である黒田長政を通じて家康に内通
家康は関ヶ原の戦い終結後、毛利宗家を改易にして広家には周防・長門の2ヶ国37万石(29万石とも)を与えるとの沙汰があったが
広家はこの沙汰に対して、毛利本家存続のために家康に以下の内容の起請文を提出した。
防長への減封を受諾した毛利氏は、長門国の一隅萩に本拠を置いた(長州藩)。藩内を分割して長府、徳山の分家
(後に清末の孫家が加わる)と岩国吉川領を置き、広家には本拠地萩からもっとも遠く東の守り、本家及び直系一門の
盾の位置となる岩国3万石の所領が与えられて岩国領の初代領主となった。
| |
岩国藩
吉川家 |
外様 3万石 → 6万石 周防国 長州藩の支藩
| 1.元春(もとはる) 従四位下、治部少輔、駿河守 |
元就の次男 |
| 2.元長(もとなが )治部少輔 |
元春の嫡男 |
| 3.広家(ひろいえ) (従四位下・民部少輔、侍従) |
元春の三男 |
| 4.広正(ひろまさ) |
広家の長男 |
| 5.広嘉(ひろよし) |
広正の長男 |
| 6.広紀(ひろのり) |
広嘉の長男 |
| 7.広逵(ひろみち) |
広紀の長男 |
| 8.経永(つねなが) |
広逵の長男 |
| 9.経倫(つねとも) |
徳山藩5代藩主・毛利広豊の九男 |
| 10.経忠(つねただ) |
吉川経倫の長男 |
| 11.経賢(つねかた) |
経忠の長男 |
| 12.経礼(つねひろ) |
経忠の次男 |
| 13.経章(つねあきら) |
経忠の三男 |
| 14.初代藩主 経幹(つねまさ)(従五位下・駿河守) |
経章の長男 |
| 15.2代藩主 経健(つねたけ)(正四位・駿河守) |
経幹の長男 |
廃藩置県
長州藩の支藩とみなされるが、長州藩では幕府に岩国領(いわくにりょう)を支藩とする届けを出しておらず、
吉川家は毛利家の家臣であり、徳川家の陪臣であるによって諸侯に非ず(大名ではない)と主張していた。
その一方で幕府からは6万石の外様大名格として扱われるという、極めて変則的な存在が江戸時代を
通じて続いた。正式に岩国藩が認められたのは、大政奉還後の慶応4年3月、新政府によってのことである。
|
|
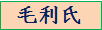
 |
毛利 高政(もうり たかまさ)
長州毛利家とは全く関係なく、父 森高次は羽柴秀吉の馬廻衆であったことから、高政は
1577年(天正5年)より出仕している。高政は毛利輝元に気に入られて毛利姓を名乗るようになる。
関ヶ原の戦いでははじめは西軍に与し、丹後田辺城(舞鶴城)攻めに参加するも途中、東軍に寝返った。
藤堂高虎のとりなしが改易を免れた要因の一つとなった。
|
| |
佐伯藩
毛利
|
外様 2万石 豊後国海部郡 佐伯城
| 1.高政(たかまさ)〔従五位下、伊勢守〕 |
森高次の子 |
| 2.高成(たかなり)〔従五位下、摂津守〕 |
高政の長男 |
| 3.高直(たかなお)〔従五位下、伊勢守〕 |
高成の長男 |
| 4.高重(たかしげ)〔従五位下、安房守〕 |
高直の長男 |
| 5.高久(たかひさ)〔従五位下、駿河守〕 |
豊後森藩主・久留島通清の四男 |
| 6.高慶(たかやす・たかよし)〔従五位下、周防守〕 |
豊後森藩主・久留島通清の六男 |
| 7.高丘(たかおか)〔従五位下、周防守〕 |
毛利高慶の子・毛利高通の子 |
| 8.高標(たかすえ)〔従五位下、伊勢守〕 |
高丘の次男 |
| 9.高誠(たかのぶ)〔従五位下、美濃守〕 |
高標の長男 |
| 10.高翰(たかなか)〔従五位下、若狭守〕 |
高誠の長男 |
| 11.高泰(たかやす)〔従五位下、伊勢守〕 |
高翰の子 |
| 12.高謙(たかあき・たかかた)〔従五位下、伊勢守〕 |
高泰の長男 |
廃藩置県
|
|
|
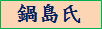

|
| 宇多源氏佐々木一族の長岡伊勢守経秀が、山城国から肥前国小城郡主千葉氏を頼って、下向したことに |
| はじまると伝えている。経秀は肥前国鍋島村に居住し、在名をもって鍋島氏とした。 |
| 経秀の子経直は、肥前守護少弐教頼を支援し、娘の一人をその側室に配し、生まれた男子経房に鍋島氏を |
| 相続させた。その後、龍造寺氏に従って活躍する。とくに享禄3年(1530年)の田手畷の戦いでは、 |
| 鍋島清久が龍造寺軍の危機を救う大活躍を示すと、その功績により清久の子の鍋島清房が、龍造寺氏の |
| 娘を娶り、血縁関係を結んだ。清房の次男直茂は、龍造寺隆信の副将として、龍造寺氏の発展・興隆に尽力 |
|
佐賀藩は天正18年(1590年)に鍋島氏の主君であった龍造寺政家が病弱であったため、豊臣秀吉に
によって隠居させられ、家督は政家の長男・龍造寺高房が引き継いでいた。
鍋島 勝茂(なべしま かつしげ)
| 天正8年(1580年)10月、龍造寺隆信の重臣であった鍋島直茂の長男として、石井生札の屋敷で生まれる。 |
| 慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは西軍に与し、伏見城攻め(伏見城の戦い)に参加した後、 |
| しかし幼少であることから、筆頭重臣である鍋島直茂が代わって国政を行う状態という、 |
| つまり鍋島氏は正式な大名ではなかったわけであるが、勝茂は豊臣時代からすでに大名世子としての |
| 扱いを受け、朝鮮出兵においても、父の直茂が総大将として出陣している。 |
| 伊勢安濃津城攻めに参加するなど、西軍主力のひとりとして行動した。しかし、父直茂の急使により、 |
| すぐに東軍に寝返り、筑後柳川の立花宗茂、同久留米の小早川秀包らを攻撃した。 |
| 関ヶ原本戦には参加せず、西軍が敗退した後に黒田長政の仲裁で徳川家康にいち早く謝罪し、また、 |
| 先の戦功により、本領安堵を認められた。家督と国政の実権が異なる状況が続いていた。 |
| 慶長12年(1607年)に高房、後を追うように政家も死去した。すると勝茂は幕府公認の下後を継いで佐賀藩の |
| 初代藩主となり、父の後見下で藩政を総覧した。 |
| |
佐賀藩
龍造寺家 |
外様 35万7千石 肥前国
1.龍造寺(りゅうぞうじ)高房(たかふさ)〔従五位下・駿河守〕 龍造寺政家の四男
慶長12年(1607年)、鍋島氏に実権を握られて憤慨して失望し、妻を殺害して自らも腹を斬り
死のうとしたが果たせず、そのときの傷を養生するために肥前に帰ることを許されたが、
故郷で再び自害し死去した。
|
| |
佐賀藩
鍋島家 |
外様 35万7千石 肥前国
| 1.勝茂(かつしげ)〔従四位下・信濃守、侍従〕 |
鍋島直茂の長男 |
| 2.光茂(みつしげ)〔従四位下・丹後守、侍従〕 |
鍋島忠直(鍋島勝茂の四男)の長男 |
| 3.綱茂(つなしげ)〔従四位下・信濃守、侍従〕 |
光茂の長男 |
| 4.吉茂(よししげ)〔従四位下・丹後守、侍従〕 |
光茂の次男 |
| 5.宗茂(むねしげ)〔従四位下・信濃守、侍従〕 |
光茂の十五男 |
| 6.宗教(むねのり)〔従四位下・丹後守、侍従〕 |
宗茂の長男 |
| 7.重茂(しげもち)〔従四位下・信濃守、侍従〕 |
宗茂の七男 |
| 8.治茂(はるしげ)〔従四位下・肥前守、左近衛権少将〕 |
宗茂の十男 |
| 9.斉直(なりなお)〔従四位下・肥前守、侍従〕 |
治茂の長男 |
| 10.直正(なおまさ)〔従四位下・肥前守、侍従〕 |
斉直の十七男 |
| 11.直大(なおひろ)〔従四位・信濃守〕 |
斉正(直正)の次男 |
廃藩置県
|
鍋島家 御三家(三支藩)
1)小城藩(小城鍋島家) 鍋島 元茂(なべしま もとしげ
肥前佐賀藩主・鍋島勝茂の長男。当初は嫡男として扱われていたが、元茂が4歳の時、父・勝茂が徳川家康の養女
(岡部長盛の娘)と結婚したとき、廃嫡された。これは、家康の養女である菊姫との間に生まれた子供を後継ぎにしようと
したためとも言われている。寛永19年(1642年)に肥前小城に7万3000石を与えられ廃嫡されたとはいえ、父から冷遇はされて
いなかったようである。島原の乱にも父・勝茂と共に従軍している。
| |
小城藩
鍋島家 |
外様 7.3万石 肥前国
廃藩置県
|
2)蓮池藩(蓮池鍋島家) 鍋島 直澄(なべしま なおずみ)
| 蓮池藩は立藩の時期は諸説ありはっきりしないが、江戸時代初期に初代佐賀藩主・鍋島勝茂の五男・直澄が |
| 佐賀藩領内の佐嘉郡・神埼郡・杵島郡・松浦郡・藤津郡において5万2000石(肥前藩の内高)を |
| 与えられたことに始まる。当初、佐賀城3の丸に政庁を構えたが、後に蓮池(佐賀市内)に陣屋を構えた。 |
| 小城藩と同じく参勤交代を行っていたが、享保15年)、参勤交代の免除を願い出たが、佐賀藩より却下された |
| |
蓮池藩
鍋島家 |
外様 5.2万石 肥前国
| 1.直澄(なおずみ) 〔従五位下・甲斐守〕 |
勝茂の五男 |
| 2.直之(なおゆき) 〔従五位下・摂津守〕 |
直澄の次男 |
| 3.直称(なおのり) 以後、官位は従五位下、 |
直澄の五男 |
| 4.直恒(なおつね) 従五位下、朝散大夫、摂津守 |
直称の次男 |
| 5.直興(なおおき) 従五位下、朝散大夫、甲斐守 |
直恒の長男 |
| 6.直寛(なおひろ) 従五位下、朝散大夫、摂津守 |
直恒の四男 |
| 7.直温(なおはる) 従五位下、朝散大夫、甲斐守 |
直寛の長男 |
| 8.直与(なおとも) 従五位下、摂津守 |
治茂の七男 |
| 9.直紀(なおただ) 従五位下、朝散大夫、甲斐守 |
直与の長男 |
廃藩置県
|
3)鹿島藩(鹿島鍋島家) 鍋島 忠茂(なべしま ただしげ)
天正12年(1584年)11月28日、鍋島直茂の次男として佐賀城で生まれる。兄は佐賀藩の初代藩主である鍋島勝茂。
忠茂は、早くから父や兄と共に豊臣秀吉に仕え、文禄4年(1595年)の文禄の役では父や兄と共に朝鮮に渡海して朝鮮軍と戦った。
慶長5年(1600年)9月の関ヶ原の戦いで、兄の勝茂が西軍に与したため、戦後に徳川家康によって処罰されかけたが、父の命令で
西軍の立花宗茂を攻めて鍋島氏の存続に尽力した。慶長6年(1601年)には家康への人質として江戸に赴いた。
慶長7年(1602年)から家康の三男・秀忠の近習として仕えたが、秀忠に寵愛されて「忠」の偏諱を授けられて忠茂と改名した。
慶長19年(1614年)に大坂冬の陣が始まると、忠茂は病身を押して参加したため、秀忠に激賞された。
| |
鹿島藩
鍋島家 |
外様 2.5万石 肥前国
| 1.忠茂(ただしげ) 〔従五位下・和泉守〕 |
直茂の次男 宗家初代藩主勝茂の弟 |
| 2.正茂(まさしげ) 〔従六位・布衣〕 |
忠茂の長男 |
| 3.直朝(なおとも) 〔従五位下・和泉守〕 |
勝茂の九男 |
| 4.直條(なおえだ) 〔従五位下・備前守〕 |
直朝の三男 |
| 5.直堅(なおかた) 〔従五位下・和泉守〕 |
第2代藩主直條の五男 |
| 6.直郷(なおさと) 〔従五位下・備前守〕 |
第3代藩主・鍋島直堅の長男 |
| 7.直熙(なおひろ) 〔従五位下・和泉守〕 |
佐賀藩第5代藩主・鍋島宗茂の十男 |
| 8.直宜(なおよし) 〔従五位下・備前守〕 |
肥前小城藩の第6代藩主・直員の四男 |
| 9.直彜(なおのり) 〔従五位下・丹波守〕 |
肥前佐賀藩藩主・鍋島治茂の六男 |
| 10.直永(なおなが )〔従五位下・丹波守〕 |
佐賀藩第9代藩主・鍋島斉直の十三男 |
| 11.直晴(なおはる) 〔官位官職なし〕 |
直彜の長男 |
| 12.直賢(なおかた) 〔従五位下・丹波守〕 |
佐賀藩第9代藩主・斉直の二十八男 |
| 13.直彬(なおよし)〔従五位下・備前守〕 |
直永の三男 |
廃藩置県
|
| 明治維新を推進させた人物を輩出した藩を指す薩長土肥に数えられ、副島種臣、江藤新平、、大隈重信、大木喬任、 |
| 佐野常民らが活躍した。また田中久重等、多藩の有能な人材を積極的に重用し、日本の近代化に貢献した。 |
| 江藤新平は明治7年(1874年)に佐賀の乱を起こし処刑されている。 |
| |
 |
| |
鍋島 勝茂 |
|
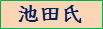
美濃池田氏家紋
 |
池田氏は和泉国池田村を発祥とし、摂津国と美濃国に荘官として赴任し池田荘を開いたとされる。
源平合戦の頃に、源頼政の弟源泰政が池田氏の養子に入り、泰政の子の泰光が摂津豊島郡を
時景(摂津池田氏)、美濃池田郡を泰継(美濃池田氏)に継がせた。
 |
摂津池田氏
平安時代から戦国時代にかけて、摂津の有力国人として、源氏楠氏、足利氏、細川氏、三好氏、織田氏と主君を変えて
勢力を保ったが、池田知正の代に荒木村重により下克上がなされ勢力を失った。その後、知正は江戸時代に
旗本となったが池田光重の代に家臣(親戚とも)の不祥事に連座して改易された。
美濃池田氏
池田恒興の代に織田家重臣となり清洲会議に出席し、その子池田輝政は徳川家康の愛娘督姫を後妻にし松平姓を
許され、一族で播磨、備前、淡路、因幡に計100万石近い諸藩を有し「播磨宰相」「姫路宰相」「西国将軍」などと称された。
その他の池田氏
伊予池田氏 伊予周敷郡池田郷に住み、池田氏を称した。
近江池田氏 近江佐々木氏の一族。六角氏、織田氏、羽柴氏に仕えて豊臣時代に大名となった池田秀氏を輩出した
出羽池田氏 出羽庄内に住み、朝日山城主池田盛周が戦国時代の代表的な人物である。近代以降において、
一族より政治家や実業家を輩出した。
池田 恒利(いけだ つねとし)
池田政秀には娘(養徳院)がいたが男子が無かったため、滝川貞勝の次男である恒利を婿養子に迎えた。
この恒利と養徳院との間に嫡男の恒興が生まれている
池田 恒興(いけだ つねおき)
| 尾張織田氏重臣で織田信長・豊臣秀吉(羽柴秀吉)に仕える。母・養徳院は信長の乳母であり、信長の父の織田信秀と |
| 再婚して側室となっているため、恒興は信長とは乳兄弟であり同時に義理の兄弟にあたる。幼少の頃から |
| 小姓として織田家に仕える。織田家の後継を巡る清洲会議では、柴田勝家らに対抗して、秀吉・丹羽長秀と共に |
| 信長嫡孫の三法師を擁立し、領地の再分配では摂津の内大坂・尼崎・兵庫において12万石を領有した。 |
| 天正12年、徳川家康・織田信雄との小牧・長久手の戦いでは、去就が注目されたが結局は秀吉方として参戦 |
| 長久手にて嫡男の元助も共に討ち死にしたため、池田家の家督は次男の輝政が相続した。 |
池田 輝政(いけだ てるまさ)
織田信長の重臣・池田恒興の次男として尾張清洲に生まれた。天正12年の小牧・長久手の戦いで、父の恒興と兄の元助が
|
| 討死したため家督を相続し、美濃大垣城主13万石を領した。天正13年(1585年)には同じ13万石で岐阜城主となった。 |
| 豊臣時代、輝政は豊臣一族に準じて遇され、従四位下侍従、および豊臣姓を許された。 |
| 文禄3年、秀吉の仲介によって、徳川家康の娘・督姫を娶る。慶長3年8月、秀吉が没すると家康に接近した。前田利家が |
| 死去すると、七将の一人として福島正則・加藤清正・加藤嘉明・浅野幸長・黒田長政らと共に石田三成襲撃事件を起こした |
| 関ヶ原の戦いでは徳川方に与し、岐阜城攻略の功績から播磨姫路52万石に加増移封され、初代姫路藩主に |
| 慶長17年、正三位参議、および松平姓を許され「播磨宰相」「姫路宰相」「西国将軍」などと称された次男・忠継の |
| 備前国岡山藩28万石、三男・忠雄の淡路国洲本藩6万石、弟・長吉の因幡国鳥取藩6万石を合せ 一族で計92万石 |
| (一説に検地して100万石)もの大領を有した。徳川家との縁組は家格を大いに引き上げ、明治に至るまで池田家が |
| 繁栄する基盤となった。 |
| 1 |
姫路藩
池田家 |
外様 52万石 播磨国
| 1.輝政 |
参議、正三位、贈従二位 |
恒興の次男 |
| 2.利隆としたか |
従四位下、侍従、右衛門督、武蔵守、秀忠のの養女・鶴姫が正室輝政の長男 |
| 3.光政みつまさ |
従四位下、左近衛権少将、贈正三位 |
利隆の長男 |
幼少を理由に因幡鳥取32万5000石に減転封となった
|
| 2 |
鳥取藩
池田家 |
外様 32万石 因幡・伯耆国 (1617年 - 1632年)
1.光政(みつまさ)〔従四位下・左近衛権少将〕
叔父の岡山藩主・池田忠雄が死去し、従弟で忠雄の嫡男・光仲が3歳の幼少のため
山陽道の要所である岡山を治め難いとし、岡山31万5000石へ移封となり、
光仲が鳥取32万5000石に国替えとなった
|
| 3 |
岡山藩
池田家 |
外様 31.5万石 備前国 (1632年 - 1871年)
| 1.光政(みつまさ) 従四位下・左近衛権少将 |
利隆の長男 |
| 2.綱政(つなまさ) 従四位下・伊予守、左近衛権少将 |
光政の長男 |
| 3.継政(つぐまさ) 従四位下・大炊頭、左近衛権少将 |
綱政の四男 |
| 4.宗政(むねまさ) 従四位下・伊予守、左近衛権少将 |
継政の長男 |
| 5.治政(はるまさ) 従四位下・内蔵頭、左近衛権少将 |
宗政の長男 |
| 6.斉政(なりまさ) 従四位下・上総介、左近衛権少将 |
治政の次男 |
| 7.斉敏(なりとし) 従四位下・伊予守、左近衛権少将 |
薩摩藩主・島津斉興の次男 |
| 8.慶政(よしまさ) 従四位下・内蔵頭、左近衛権少将 |
豊前国中津藩主奥平昌高の十男 |
| 9.茂政(もちまさ) 従四位上・弾正大弼、左近衛権少将 |
常陸水戸藩主徳川斉昭の九男 |
| 10.章政(あきまさ) 従四位下・備前守、左近衛権少将 |
肥後国人吉藩主相良頼之の次男 |
廃藩置県
|
支藩
| |
鴨方藩
岡山新田藩
池田家 |
外様 2.5万石 備中国
| 1.政言(まさこと) - 従五位下・信濃守 |
光政の次男 |
| 2.政倚(まさより) - 従五位下・内匠頭 |
政言の長男 |
| 3.政方(まさみち) - 従五位下・信濃守 |
身旗本・池田由道の次男 |
| 4.政香(まさか) - 従五位下・内匠頭 |
政方の長男 |
| 5.政直(まさなお) - 従五位下・信濃守 |
政方の次男 |
| 6.政養(まさよし) - 従五位下・内匠頭 |
政直の長男 |
| 7.政共(まさとも) - 従五位下・信濃守 |
政養の次男 |
| 8.政善(まさよし) - 従五位下・信濃守 |
政養の三男 |
| 9.政詮(まさあき) - 従五位下・信濃守 最後の岡山藩主・章政となる人吉藩主相良頼之の次男 |
| 10.政保(まさやす) - 従五位 岡山藩の第10代藩主池田章政(政詮)の長男 |
備中国浅口郡(現:岡山県浅口市)・小田郡・窪屋郡を領有し、藩庁は鴨方陣屋
廃藩置県
|
| |
生坂藩
岡山
新田藩
池田家 |
外様 1.5万石 備中国
| 1.輝録(てるとし) - 従五位下・丹波守 |
光政の三男 |
| 2.政晴(まさはる) - 従五位下・丹波守 池田軌隆(岡山藩主・池田綱政の次男)の長男 |
| 3.政員(まさかず) - 従五位下・中務少輔 |
政晴の次男 |
| 4.政弼(まさすけ) - 従五位下・丹波守 |
政晴の三男 |
| 5.政恭(まさゆき) - 従五位下・山城守 |
治政 ? |
| 6.政範(まさのり) - 従五位下・丹波守 |
政恭の長男 |
| 7.政和(まさかず) - 従五位下・山城守 |
大身旗本・池田喜長の次男 |
| 8.政礼(まさのり) - 従五位下・丹波守 |
政和の次男 |
備中国窪屋郡生坂(現・倉敷市)周辺を領有した。石高は1万5千石であるが、この石高は岡山藩の内高に含
まれる。寛文12年(1672年)光政の三男・輝録が立藩した。藩主は岡山城下に居住していた。
廃藩置県
|
|
池田 忠継(いけだ ただつぐ)
| 1599年(慶長4年)2月18日、輝政の次男で伏見で生まれる。徳川家康の外孫にあたるため、 |
| わずか5歳で備前岡山28万石に封じられた。幼年の忠継に政務を取り仕切ることができるはずもなく、 |
| 異母兄の利隆が執政代行として岡山城に入り、忠継は父の姫路城に留まった。 |
婚姻前に死去して嗣子はなく、同母弟の忠雄が跡を継いだ。
|
| 1 |
岡山藩
池田家 |
外様(準親藩) 28万石→38万石→31万5千石 (1603年 - 1632年)
| 1.忠継(ただつぐ) - 従四位下・左衛門督、侍従 、28万石 → 38万石 |
輝政の次男 |
| 2.忠雄(ただかつ) - 正四位下・宮内少輔、参議 、31万5千石 |
輝政の三男 |
淡路国洲本藩主6万石であったが、兄が死去で後を継ぐ
寵愛する小姓の渡辺源太夫が藩士・河合又五郎に殺害されるという事件が起こり(鍵屋の辻の決闘)、
脱藩した又五郎をかくまった旗本と外様大名の争いに発展した。忠雄は31歳の若さで死去した
死因は天然痘だが、毒殺されたという説もある。死後、家督は長男・光仲が継いだが、幼少だったために
因幡鳥取に移封された
|
池田 忠雄(いけだ ただかつ)
江戸時代前期の大名。淡路国洲本藩主、のち備前国岡山藩第2代藩主。鳥取藩池田家宗家2代。播磨姫路藩主・池田輝政の
三男(実は六男)。母は徳川家康の次女・督姫。岡山藩初代藩主・池田忠継の同母弟。
慶長7年(1602年)10月28日、姫路城で生まれる。慶長13年(1608年)、7歳で元服する。家康の孫に当たることから
慶長15年(1610年)、9歳で淡路洲本に6万石の所領を与えられたが、父の姫路城に留まり、池田氏重臣が政務にあたった。
元和元年(1615年)、岡山藩主である同母兄・忠継が17歳で早世したため、その跡を継いだ。
池田 光仲(いけだ みつなか)
寛永7年(1630年)6月18日、備前岡山藩主・池田忠雄の長男として岡山藩江戸藩邸で生まれる。
寛永9年(1632年)父・忠雄が死去し、わずか3歳で家督を継ぐこととなった。幼少のため山陽道の要所備前岡山を治め難いと
されたが、徳川家康の外曾孫ということもあり改易とはならず、光仲は因幡・伯耆を有する鳥取藩32万石に、従兄で鳥取藩主と
なっていた池田光政が備前岡山藩31万5,000石へ国替えとなった。
| 2 |
鳥取藩
池田家 |
外様(準親藩) 28万石→38万石→31万5千石 因幡・伯耆国 (1632年 - 1871年)
| 1.光仲(みつなか)〔従四位下・左近衛少将〕 |
忠雄の長男 |
| 2.綱清(つなきよ)〔従四位下・伯耆守、左少将〕 |
光仲の長男 |
| 3.吉泰(よしやす)〔従四位下・相模守、侍従〕 |
鹿奴藩初代藩主池田仲澄の長男 |
| 4.宗泰(むねやす)〔従四位下・相模守、侍従〕 |
吉泰の長男 |
| 5.重寛(しげのぶ)〔従四位下・相模守、左少将〕 |
宗泰の長男 |
| 6.治道(はるみち)〔従四位下・相模守、侍従〕 |
重寛の次男 |
| 7.斉邦(なりくに)〔従四位下・相模守、侍従〕 |
治道の長男 |
| 8.斉稷(なりとし)〔従四位上・因幡守、左近衛中将〕 |
治道の次男 |
| 9.斉訓(なりみち)〔従四位上・因幡守、左近衛少将〕 |
斉稷の次男 |
| 10.慶行(よしゆき)〔従四位下・因幡守、左近衛少将〕 |
鹿奴藩(東館)主・池田仲律の長男 |
| 11.慶栄(よしたか)〔従四位上・因幡守、侍従〕 |
加賀藩主・前田斉泰の四男 |
| 12.慶徳(よしのり)〔従四位上・因幡守、左近衛中将〕 |
常陸国水戸藩主徳川斉昭の五男 |
廃藩置県
|
支藩
鹿奴藩(しかのはん):
鹿野藩・鳥取東館新田藩ともいう。ただし、同地には池田氏が転封される以前の領主である亀井氏による
「鹿野藩」も存在していたため、混同に注意する必要がある。
貞享2年(1685年)に鳥取藩主・池田光仲が鳥取藩の新田2万5000石を次男の池田仲澄に与えて
新田分知による分家としたのが始まりである。
| |
鹿奴藩
池田家 |
外様。2万5000石→3万石 因幡・伯耆国
| 1.仲澄(なかずみ)〔従五位下・壱岐守〕 |
光仲の次男 |
| 2.仲央(なかてる)〔従五位下・摂津守〕 |
仲澄の次男 |
| 3.仲庸(なかつね)〔従五位下・摂津守〕 |
仲央の長男 |
| 4.澄延(すみのぶ)〔従五位下・摂津守〕 |
仲庸の長男 |
| 5.延俊(のぶとし)〔従五位下・修理亮〕 |
仲庸の次男 |
| 6.澄時(すみとき)〔なし〕 |
鳥取藩の第5代藩主・池田重寛の三男 |
| 7.仲雅(なかまさ)〔従五位下・摂津守〕 |
鳥取藩の第5代藩主・池田重寛の四男 |
| 8.仲律(なかなり)〔従五位下・壱岐守〕 |
仲雅の三男 |
| 9.仲建(なかたつ)〔従五位下・伊勢守〕 |
仲律の三男 |
| 10.徳澄(のりずみ)〔従五位下・摂津守〕 |
鹿奴藩主家一族・池田仲諟の三男 |
廃藩置県
|
若桜藩(わかさはん)
鳥取西館新田藩ともいい、鳥取藩の第2代藩主・池田綱清が元禄13年5月に弟の池田清定(光仲の四男)
に新田1万5000石を分知したのが始まりで、藩庁は鹿奴藩と同じく鳥取に置かれた。
2万石の大名となり、さらに幕府から松平姓を許され、柳間詰となった。
| |
若桜藩
池田家 |
外様。 2万石 因幡・伯耆国
| 1.清定(きよさだ)〔従五位下・河内守〕 |
光仲の四男 |
| 2.定賢(さだまさ)〔従五位下・近江守〕 |
鹿奴藩主仲澄の四男 |
| 3.定就(さだより)〔従五位下・兵庫頭〕 |
定賢の長男 |
| 4.定得(さだのり)〔従五位下・大隅守〕 |
定就の長男 |
| 5.定常(さだつね)〔従五位下・縫殿頭〕「柳間の三学者」「文学三侯」と称された 旗本・池田政勝の次男 |
| 6.定興(さだおき)〔夭折のため官位官職なし〕 |
定常(松平冠山)の長男 |
| 7.定保(さだやす)〔従五位下・長門守〕 |
定常の六男 |
| 8.清直(きよなお)〔従五位下・淡路守〕 |
仲雅の八男 |
| 9.清緝(きよつぐ)〔従五位下・左衛門佐〕 |
池田仲諟の長男 |
| 10.徳定(のりさだ)〔従五位下・相模守〕 |
池田仲諟の次男 |
廃藩置県
|
|
池田 輝澄(いけだ てるずみ)
| 慶長9年(1604年)4月29日、播磨姫路藩主・池田輝政の四男として姫路城で生まれる。 |
| 家康の外孫にあたるため慶長14年(1609年)4月、松平姓を下賜され、松平左近と称した。 |
| 慶長20年(1615年)5月28日、兄で岡山藩主だった池田忠継が早世すると、その所領から |
| 播磨宍粟郡3万8000石を与されて山崎藩主となり、従五位下に叙任する。 |
| 1 |
山崎藩
池田家 |
外様 3.8万石→6.8万石 播磨国 (1615年 - 1640年)
| 1.輝澄(てるずみ)〔従四位下、石見守・侍従〕 |
輝政の四男 |
急激な所領拡大で新たに召抱えた家臣団と、それより前に仕えていた古い家臣団との間で争いが
起こるようになり、寛永17年(1640年)にはお家騒動(池田騒動)に発展した。
幕府の裁定により伊木伊織以下20名が切腹、輝澄は家中不取締りを理由に改易され、
甥の鳥取藩主・池田光仲預かりとなった。輝澄は家康の外孫ということもあって鳥取藩内の
鹿野において堪忍料1万石を与えられた。
|
| 2 |
鹿野藩
池田家 |
外様 1万石 因幡国国 (1640年 - 1662年)
| 1.輝澄(てるずみ)〔従四位下・侍従〕 |
輝政の四男 |
|
寛文2年(1662年)、輝澄の跡を継いだ政直は播磨福本へ移り、鹿野藩は再び廃藩となった。
|
|
池田 長吉(いけだ ながよし)
| 安土桃山時代から江戸時代初期の武将、大名。長吉系池田家初代、池田恒興の三男で兄・池田輝政と共に |
| 豊臣秀吉に仕えて近江国佐倉に3万石の所領を与えられた。関ヶ原の戦いでは兄と共に東軍に属して美濃岐阜城攻めに参加 |
| 戦後にそれを徳川家康に賞されて因幡鳥取藩6万石に加増移封された |
| 1 |
鳥取藩
池田家 |
外様 6万石 因幡国 (1600年 - 1617年)
| 1.長吉(ながよし)〔従五位下・備中守〕 |
池田恒興の三男 |
| 2.長幸(ながゆき)〔従五位下・備中守〕 |
長吉の長男 |
|
| 2 |
備中
松山藩
池田家 |
外様 6.5万石 備中国 (1617年 - 1641年)
| 1.長幸(ながよし)〔従五位下・備中守〕 |
|
| 2.長常(ながつね)〔従五位下・出雲守〕 |
長幸の長男 |
徳川家光に兜を受領するなど、寵愛を受けていた。
寛永9年(1632年)の父の死去により家督を継ぐ。しかしこの時、次弟の長純と分割相続
すべきとの遺言で、叔父の長頼と脇坂安信が口論、長頼が安信の弟・安経を殺害、長頼は切腹
安信も改易された。長常にはお咎めなく一括相続されている。
幕府から末期養子を許されず、結局、備中松山における池田氏は断絶した。
三弟の長信が1000石の旗本となって池田家の家名はかろうじて存続した。
|
|
池田 長政(いけだ ながまさ)
| 池田恒興の四男として尾張犬山に生まれる。幼少時に片桐俊元の養子となり、慶長2年(1597年)に |
| 俊元が死去すると、家督と三河国新庄7000石の所領を継いだ |
| 関ヶ原の戦いで兄・輝政と共に東軍に与して織田秀信の籠る岐阜城攻めで軍功を挙げ、戦後に1万5000石の |
| 加増を受けて播磨赤穂城主に任命されたが、一説には東西どちらが勝っても池田氏が存続できるように、 |
| 兄の命令で西軍に与していたともいわれる。 |
| 最終的に備前国下津井3万2000石の領主となる。江戸城普請や駿府城普請でも功績を挙げた。 |
| 長政の家系は輝政の孫・池田光政から始まる岡山藩の家老(片桐池田家)として明治時代まで存続した。 |
|
天城池田家
天城池田家(あまきいけだけ)は、江戸時代の岡山藩主池田氏の一族で備前天城の領主。
初代由之は、池田輝政の兄池田元助の嫡男で輝政に仕え、伯耆米子3万2,000石を領した。
2代由成が、藩主光政の岡山移封に伴い米子から備前に移り、寛永16年(1639年)天城に陣屋を構え、
代々領したため天城池田家と呼ばれた。元禄14年(1701年)4代由勝は、元禄赤穂事件の際に、
大石良雄の縁戚であったため、2,000石を減じられ以降禄高3万石となる。
池田 由之(いけだ よしゆき)
天正5年(1577年)、尾張国犬山で池田元助の嫡男として誕生。
慶長14年(1609年)には3万2000石に加増され、備前国下津井城の城番になる。
慶長18年(1613年)に叔父の輝政が死去し、その嫡男の利隆が家督を継ぐと、由之も下津井から播磨国明石城へ移るが、
その利隆も元和2年(1616年)に死去すると、家督を継いだ光政は、江戸幕府から幼少を理由に翌元和3年(1617年)に
因幡国鳥取藩へ移封させられる。これに伴い由之も明石城から米子城へと移ることとなった。
この頃の池田家中では筆頭家老の伊木忠繁ら要職にある人物も死去しており、幼君の光政を補佐したが、
元和4年(1618年)に江戸から米子へ戻る途中、怨みにより大小姓の神戸平兵衛により刺殺された。享年42。
代々天城池田家は宗家池田家の家老として仕える。
| 1 |
米子藩 |
外様 3.2万石 伯耆国
1.池田由之(よしゆき) 池田元助の嫡男 |
| 2 |
天城領
池田家 |
外様 3.2万石 備前国
| 2.池田由成(よしなり)天城3万2,000石 |
由之の子 |
| 3.池田由孝(よしたか) |
岡山藩家老・池田由成の三男 |
| 4.池田由勝(よしかつ)天城3万石 |
由孝の子 |
| 5.池田保教(やすのり)(岡山藩第3代藩主池田継政、本家に戻り藩主を相続) 綱政の四男 |
| 6.池田政純(まさずみ) |
岡山藩第3代藩主池田綱政の子 |
| 7.池田政喬(まさたか) |
岡山藩第4代藩主池田継政 |
| 8.池田政孝(まさたか) |
政喬の次男 |
| 9.池田政徳(まさのり) |
政恭の三男 |
| 10.池田政昭(まさあき) |
政徳の長男 |
| 11.池田政和(まさやす) |
政昭の次男 |
| 12.池田政佑(まさすけ) |
政和の嫡男 |
廃藩置県 2代以後は宗家が岡山藩へ移封された為に備前天城に移転し代々家老と |
|
池田 恒元(いけだ つねもと
池田利隆の次男で、池田光政の弟である。
慶安元年(1648年)、2万石を与えられて児島藩を立藩したが、慶安2年(1649年)から山崎藩主となる。
| |
山崎藩
池田家 |
外様 3万石 播磨国 (1649年 - 1678年) 宍粟藩(しそうはん)とも呼ばれる。
| 1.恒元(つねもと)〔従五位下、備後守〕 |
利隆の次男 |
| 2.政周(まさちか)〔従五位下、豊前守〕 |
恒元の長男 |
| 3.恒行(つねゆき)〔夭折のため官位官職なし〕 |
備前岡山藩主池田綱政の六男 |
先代藩主の政周が延宝5年(1677年)に嗣子なくして早世したため、その跡を継いだが、
翌年12月27日に江戸にて7歳で死去した。嗣子がいるはずもなく、こうして播磨山崎における池田氏は断絶した。
|
|
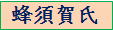
 |
羽柴秀吉に仕えた蜂須賀正勝(小六・小六郎)の一族が著名。もともとは須賀氏と呼ばれたという。
蜂須賀氏の出自に関しての確証は未だにない、正勝の祖父・蜂須賀正永(正則、一説に
蜂須賀正昭の子とも)を始祖とする。とするあたりという。正利・正勝・家政と3代続いて、
小六(小六郎)を通称としている。
|
蜂須賀 正勝(はちすか まさかつ)
| 戦国時代から安土桃山時代にかけての日本の武将。羽柴氏(豊臣氏)の家臣。 |
| 蜂須賀氏は、尾張国海東郡蜂須賀郷(現・愛知県あま市蜂須賀)を根拠とした国人領主であり、 |
| 正勝は大永6年(1526年)、蜂須賀正利の長男として蜂須賀城に生まれる。 |
| 永禄9年(1566年)、美濃国において秀吉の手で果たされた墨俣城の築城に川並衆の前野長康らと協力し |
| 天正5年(1577年)から始まった中国攻めにも従軍 |
| 正勝は、秀吉の片腕として秀吉に従軍して数多くの合戦に参加しているが、槍働き(白兵)としての活躍よりも |
| 参謀として民政や調略に手腕を発揮した人物であったことが |
| 長宗我部元親への押さえとして秀吉から阿波一国を与えられるが、正勝は秀吉の側近として |
| 仕えることを望んでこれを辞退し、嫡男の家政に譲り渡された。自身は結局、阿波に入国することはなかったといわれる。 |
蜂須賀 家政(はちすか いえまさ)
| 戦国時代から江戸時代前期にかけての武将・大名。蜂須賀正勝の子で、父の代わりに阿波国の大名に任じられて |
| 徳島藩祖となる。天正14年に阿波18万石の大名となり、同年1月2日、従五位下阿波守に叙任する。一宮城の城主となり、 |
その後徳島城を築城した。一説に阿波踊りは、城が竣工した折、家政が城下に「城の完成祝いとして、好きに踊れ」という
|
| 触れを出したことが発祥ともいう。子の至鎮と徳川家康の養女の縁組を結ぶなど、典型的な武断派・親家康大名として |
| 活動している。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは、西軍から親徳川の姿勢を糾弾され高野山へ追放されたが、 |
| 家康の上杉景勝征伐に同行させていた至鎮は関ヶ原の本戦で東軍として参加して武功を挙げたため、戦後に家康から所領を |
| 安堵された。しかし自身は家督を至鎮に譲り、蓬庵と号して隠居した。慶長19年(1614年)から始まった大坂の陣では、 |
| 豊臣方からの誘いに「自分は無二の関東方」と称して与力を拒絶するとともに、駿府城の家康を訪ねて密書を提出している。 |
| 冬・夏の陣で嫡男の至鎮が戦功を挙げたため、戦後に蜂須賀家は淡路一国を与えられ、25万7,000石に加増された。 |
| 元和6年に至鎮が夭折した後は、幼くして襲封した嫡孫・忠英の後見を幕府から命じられ、忠英が成人する寛永6年)まで政務を |
| 取り仕切り、藩政の基礎を築いた。戦国以来の長老として、第3代将軍・徳川家光の側に御伽衆として出仕することもあったという。 |
| |
徳島藩
蜂須賀家 |
外様 17.5万石→25.7万石→20.7万石→25.7万石 阿波・淡路国 徳島城
| 1.至鎮(よししげ)〔従四位下、阿波守〕加増により25万7千石 |
家政の長男 |
| 2.忠英(ただてる)〔従四位下、阿波守・侍従〕 |
至鎮の子 |
| 3.光隆(みつたか)〔従四位下、阿波守・侍従〕 |
忠英の長男 |
| 4.綱通(つなみち)〔従四位下、阿波守・侍従〕 |
光隆の長男 |
| 5.綱矩(つなのり)〔従四位下、淡路守・侍従〕分知により20万7千石 |
隆矩の長男 |
| 6.宗員(むねかず)〔従四位下、淡路守・侍従〕領地還付により25万7千石 綱矩の四男 |
| 7.宗英(むねてる)〔従四位下、阿波守・侍従〕 |
蜂須賀隆喜の三男 |
| 8.宗鎮(むねしげ)〔従四位下、阿波守・侍従〕 |
松平志摩頼煕の次男 |
| 9.至央(よしひさ)〔官位官職なし〕 |
松平志摩頼煕の三男 |
| 10.重喜(しげよし)〔従四位下、阿波守・侍従〕 出羽国秋田新田藩主佐竹義道の四男 |
| 11.治昭(はるあき)〔従四位下、阿波守・侍従〕 |
重喜の長男 |
| 12.斉昌(なりまさ)〔正四位下、阿波守・侍従〕 |
治昭の次男 |
| 13.斉裕(なりひろ)〔正四位上、阿波守・参議・侍従〕 11代将軍・徳川家斉の二十二男 |
| 14.茂韶(もちあき)〔従四位上、阿波守・侍従〕 |
斉裕の次男 |
廃藩置県
|
支藩
| |
富田藩 |
外様 5万石 阿波国 (1678年 - 1725年)
徳島藩の支藩として江戸時代中期に存在した藩である。延宝6年(1678年)に蜂須賀隆重が
徳島藩5代藩主蜂須賀綱矩より5万石の分知を得て、名東郡富田(徳島市内)に居所を営み立藩した。
| 1.隆重(たかしげ) |
従五位下、飛騨守 |
忠英の次男 |
| 2.隆長(たかなが) |
|
蜂須賀隆喜の長男 |
| 3.正員(まさかず) |
従四位下、淡路守 |
綱矩の四男 |
阿波徳島藩の第6代藩主となったために所領を徳島藩に返納して廃藩となった
|
|
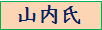
 |
藤原北家秀郷流の備後山内氏の分家で山内宗俊の五男俊家を祖とする。
活躍の場は戦国時代、池田恒興や前田利家、柴田勝家や佐々成政が下級武士だった時代、
山内盛豊は尾張国守護代の織田氏嫡流の岩倉織田家家老で黒田城主であり上級武士として
岩倉織田家を支えてきたが、当時山内氏よりも下級だった清洲三奉行の一つであった
清洲織田家当主織田信長に侵攻され自害して果てる。
|
山内 一豊(やまうち かつとよ)
| 父は岩倉織田氏の重臣・山内盛豊、永禄11年(1568年)頃に織田信長に仕え、木下秀吉(後の豊臣秀吉)の |
| 与力となったと考えられる。天正13年(1585年)には若狭国高浜城主、まもなく近江長浜城主として2万石を領した。 |
| 天正18年(1590年)の小田原征伐にも参戦し、山中城攻めに参加している。まもなく遠江国掛川に5万1000石の所領を与えられた。 |
| 秀吉の死後の慶長5年(1600年)には五大老の徳川家康に従って会津の上杉景勝の討伐に参加し、一豊は下野国小山における |
| 軍議(いわゆる「小山評定」)で諸将が東軍西軍への去就に迷う中、真っ先に自分の居城である掛川城を家康に提供する旨を |
| 発言しその歓心を買っている。戦後はこれらの功績を高く評価され、土佐国一国・9万8000石を与えられた。後に、高直しにより |
| 20万2,600石を幕府から認められている。 |
見性院(けんしょういん)
山内一豊の正室である。本名は「千代」とも「まつ」ともいわれるが、定かではない。
「内助の功」に関する逸話
嫁入りの持参金またはへそくりで夫・一豊の欲しがった名馬(鏡栗毛)を購入し、主君織田信長の馬揃えの際に信長の目に
留まり、それが元で一豊は加増されたといわれる。一豊の築城監督の経費を出すために、髪を売ったと言う話もある。
| |
土佐藩
山内家 |
外様 20万2600石→24万石 土佐国
| 1.一豊 (かつとよ) 〔従四位下・土佐守〕 |
山内盛豊の子 |
| 2.忠義 (ただよし) 〔従四位下・土佐守、侍従〕 |
山内康豊の長男 |
| 3.忠豊 (ただとよ) 〔従四位下・対馬守、侍従〕 |
忠義の長男 |
| 4.豊昌 (とよまさ) 〔従四位下・土佐守、侍従〕 |
忠豊の長男 |
| 5.豊房 (とよふさ) 〔従四位下・土佐守、侍従〕 |
山内一俊の長男 |
| 6.豊隆 (とよたか) 〔従四位下・土佐守、侍従〕 |
山内一俊の次男 |
| 7.豊常 (とよつね) 〔従四位下・土佐守、侍従〕 |
豊隆の次男 |
| 8.豊敷 (とよのぶ) 〔従四位下・土佐守、侍従〕 |
山内規重の長男(家老深尾家の分家) |
| 9.豊雍 (とよちか) 〔従四位下・土佐守、侍従〕 |
豊敷の四男 |
| 10.豊策 (とよかず) 〔従四位下・土佐守、侍従〕 |
豊雍の長男 |
| 11.豊興 (とよおき) 〔従四位下・土佐守、侍従〕 |
豊策の長男 |
| 12.豊資 (とよすけ) 〔従四位下・土佐守、右近衛少将〕 |
豊策の次男 |
| 13.豊熈 (とよてる) 〔従四位下・土佐守、侍従〕 |
豊資の長男 |
| 14.豊惇 (とよあつ) 〔官職位階なし〕 |
豊資の次男 |
| 15.豊信 (とよしげ) 〔従四位上・土佐守、侍従、号は容堂〕 |
山内南家当主・山内豊著の長男 |
| 16.豊範 (とよのり) 〔従四位上・土佐守、侍従、侯爵〕 |
豊資の十一男 |
| 廃藩置県 |
|
支藩
中村藩
江戸時代初期から中期にかけて3代33年間存在した。明暦2年(1656年)土佐藩2代藩主・山内忠義の
二男・忠直が幡多郡中村(四万十市)付近3万石を与えられ立藩。
| |
中村藩
山内家 |
第一期: 外様 2万石 (1601年 - 1629年)
| 1.康豊 (やすとよ) |
一豊の同母弟山内盛豊の四男 |
| 2.政豊 (まさとよ) |
康豊の次男 |
嗣子無くして32歳で死去し、土佐中村藩は断絶した。
第二期: 外様 3万石 ( 1656年 - 1689年)
| 1.忠直 (ただなお) 〔従五位下・修理大夫〕 |
忠義の次男 |
| 2.豊定 (とよさだ) 〔従五位下・右近大夫〕 |
忠直の長男 |
| 3.豊明 (とよあきら)〔従五位下・大膳亮 若年寄〕 |
忠直の次男 |
徳川綱吉の寵愛を受けて元禄2年(1689年)4月14日に奥詰衆となり、同年5月3日には
若年寄に任じられるという異例の栄進を遂げている。豊明は病気により若年寄辞職を綱吉に求めた
これが不敬として綱吉の怒りに触れ、5月12日に江戸屋敷を召し上げられて謹慎を命じられる綱吉の怒りに触れて改易。
|
| |
土佐
新田藩
山内家 |
外様 1.3万石
| 1.豊産 (とよただ) 〔従五位下・遠江守〕 |
豊成の四男 |
| 2.豊泰 (ただよし) 〔従五位下・摂津守〕 |
豊敷の五男 |
| 3.豊武 (とよたけ) 〔従五位下・遠江守〕 |
豊泰の長男 |
| 4.豊賢 (とよかた) 〔従五位下・遠江守〕 |
豊武の長男 |
| 5.豊福 (とよよし) 〔従五位下・遠江守〕 |
筑前国秋月藩主・黒田長元の次男 |
| 6.豊誠 (とよしげ) 〔従五位・侍従〕 |
豊充の長男 |
廃藩置県 |
| |
 |
 |
 |
 |
| |
初代 山内一豊 |
2代 山内忠義 |
3代 山内忠豊 |
15代 山内豊信(容堂 |
|
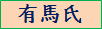
 |
赤松氏(村上源氏)の庶流で、室町時代に摂津国有馬郡を拠点とした。他流の有馬氏とは区別して
摂津有馬氏、赤松有馬氏とも呼ばれる。江戸時代、一族からは久留米藩主家などが出た。
明徳2年(1391年)の明徳の乱ののち、赤松則村の孫で赤松則祐の五男・有馬義祐が摂津国有馬郡の
地頭に補せられ、その地に移り住んだため有馬氏を称した。義祐の子・有馬持家は足利義教に側近として
仕え、足利義政初期の寵臣として知られる。
|
久留米藩有馬家
| 庶流にあたる有馬重則は播磨国美嚢郡に進出し、同族の別所氏やその縁戚の淡河氏と対立した。その子の則頼は |
| 豊臣秀吉に従い、後に御伽衆に列した。則頼の子豊氏は豊臣秀次の家老渡瀬繁詮に仕えて文禄4年に繁詮が秀次事件により |
| 改易されるとその領地である遠江国横須賀3万石を引き継いで治めた。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで有馬父子は東軍に |
| 与し、その戦功から則頼は一族の 旧領摂津国有馬郡三田藩2万石、豊氏は丹波国福知山藩6万石に封ぜられる。 |
有馬 豊氏(ありま とようじ)
| 摂津有馬氏の一族である有馬則頼の二男として播磨国三木の満田城にて誕生 |
| 摂津有馬氏は、赤松氏の庶流で有馬赤松家ともいい、室町時代に摂津国有馬郡を本拠としたことから |
| 有馬を苗字とした一族である。 |
| 元和6年(1620年)12月8日、筑後国久留米に21万石を与えられ国持ち大名となった。 |
| 1 |
福知山藩 |
外様 6万石→8万石 丹波国
1.有馬豊氏(とようじ) 従四位下 玄蕃頭、侍従 有馬則頼の二男
|
| 2 |
久留米藩
有馬家 |
外様 21万石 筑後国
| 1.豊氏(とようじ) 従四位下、玄蕃頭・侍従 |
有馬則頼の二男 |
| 2.忠頼(ただより) 従四位下、中務大輔・侍従 |
豊氏の次男 |
| 3.頼利(よりとし) 従四位下、玄蕃頭 |
忠頼の長男 |
| 4.頼元(よりもと) 従四位下、中務大輔・侍従 |
忠頼の次男 |
| 5.頼旨(よりむね) 従四位下、筑後守 |
頼元の次男 |
| 6.則維(のりふさ) 従四位下、玄蕃頭・侍従 |
旗本石野則員の五男 |
| 7.頼?(よりゆき) 従四位下、左少将・侍従 |
則維の四男 |
| 8.頼貴(よりたか) 従四位下、左少将・侍従 |
頼?の長男 |
| 9.頼徳(よりのり) 従四位下、玄蕃頭・左少将・侍従 有馬頼瑞(藩主・頼貴の三男)の長男 |
| 10.頼永(よりとう) 従四位下、筑後守・侍従 |
頼徳の四男 |
| 11.頼咸(よりしげ) 正四位、中務大輔・左中将 |
頼徳の七男 |
廃藩置県
|
支藩
松崎藩
江戸時代前期に16年間存在した、久留米藩の支藩である。藩庁は筑後国御原郡松崎
寛文8年、有馬頼利(久留米藩第3代藩主)の遺領から、有馬豊祐(久留米藩第2代藩主・忠頼の養子)に
御原郡内19か村1万石が分与されて立藩した。
| |
松崎藩
有馬家 |
外様 1万石 筑後国
1.豊祐(とよすけ)〔従五位下、伊予守〕
貞享元年、豊祐は実姉の夫である陸奥窪田藩主・土方雄隆の後継者問題に巻き込まれ、
親族として解決に力を尽くさなかったとして改易された。旧領地は幕府直轄領となったのち、
元禄10年(1697年)に久留米藩に還付さ
|
|

 |
佐竹氏(さたけし)は、日本の武家。本姓は源氏。家系は清和源氏の一家系 河内源氏の流れを汲み、
新羅三郎義光を祖とする常陸源氏の嫡流。武田氏に代表される甲斐源氏と同族である。
佐竹氏は甲斐源氏の一族と同じく源頼義の子で源義家の弟の源義光の子孫である義光流源氏の一族。
佐竹氏は鎌倉府の重鎮として活躍し、第3代鎌倉公方の足利満兼より関東の8つの有力武家に
屋形号が与えられ関東八屋形の格式が制定されると、佐竹氏もこのひとつに列せられ、以後、佐竹氏の
当主は「お屋形さま」の尊称を以って称された。戦国時代になると、佐竹氏第15代当主で「中興の祖」と
呼ばれた佐竹義舜が現れ、山入氏を討ち、常陸北部の制圧に成功した。佐竹氏第18代当主の義重は、
「鬼義重」の異名をとる名将であった。義重は戦国時代を通じて領国を拡大し、子の義宣の時代には
豊臣秀吉の小田原征伐に参陣して、秀吉の太閤検地の結果常陸54万5800石の大名として認められた |
佐竹 義宣(さたけ よしのぶ)
元亀元年(1570年)7月16日、太田城に生まれ、天正14年(1586年)から天正18年(1590年)の間に、義宣は、父・義重の隠居に
よって家督を相続した。佐竹氏は、伊達氏と対立する傍ら、豊臣秀吉と音信を通じ、石田三成及び上杉景勝と親交を結んでいた。
佐竹氏は徳川氏や前田氏、島津氏、毛利氏、上杉氏と並んで豊臣政権の六大将と呼ばれたという
関ヶ原の戦いにおいて佐竹氏の動向は、東軍につくとも西軍につくともいえないものであった。
慶長7年(1602年)3月、義宣は大阪城の豊臣秀頼と徳川家康に謁見した。その直後の同年5月8日、義宣は、家康から、
国替えの命令を受けた。無傷の大兵力を温存していた佐竹氏を江戸から遠ざける狙いがあったとする説がある
| |
久保田藩
(秋田藩)
佐竹家 |
外様 20万石 出羽国秋田藩 久保田城
| 1.佐竹義宣 |
従四位上、左近衛中将、右京大夫 |
義重の子 |
| 2. 義隆(よしたか |
従四位下・左近衛少将 |
岩城貞隆の長男(佐竹義重)の三男 |
| 3 義処(よしずみ |
従四位下侍従、左少将、右京大夫 |
義隆の次男 |
| 4. 義格(よしただ |
従四位下侍従、大膳大夫 |
義処の三男 |
| 5. 義峯(よしみね |
従四位下、侍従。少将 |
岩崎藩初代藩主・佐竹義長の次男 |
| 6. 義真(よしまさ |
従四位下侍従、左兵衛督 |
佐竹義堅の長男 |
| 7. 義明(よしはる |
従四位下侍従、右京大夫 |
出羽国岩崎藩主・佐竹義道の長男 |
| 8. 義敦(よしあつ |
従四位下侍従、右京大夫 |
義明の長男 |
| 9. 義和(よしまさ |
従四位下侍従、右京大夫 出羽久保田藩第9代藩主。佐竹義敦(曙山)の長男 |
| 10. 義厚(よしひろ |
従四位下侍従、左少将、右京大夫 |
義和の長男 |
| 11 義睦(よしちか |
従四位下侍従、右京大夫 |
義厚の次男 |
| 12. 義堯(よしたか |
従四位下、左中将、右京大夫 |
陸奥相馬中村藩主・相馬益胤の三男 |
廃藩置県
|
支藩
| |
岩崎藩
佐竹家 |
外様 2万石 出羽国
久保田藩の支藩。本来は久保田新田藩あるいは秋田新田藩という。
1701年(元禄14年)に久保田藩第3代藩主・佐竹義処が弟の義長に新田2万石を蔵米で分知したことに始まる
| 1.佐竹義長 従五位下 壱岐守・兵部少輔 |
義隆の四男 |
| 2.佐竹義道 従五位下 壱岐守・和泉守 |
佐竹義本の子 |
| 3.佐竹義忠 従五位下 壱岐守・和泉守 |
義道の三男 |
| 4.佐竹義祇 従五位下 壱岐守 |
佐竹義敏の長男 |
| 5.佐竹義知 従五位下 壱岐守 |
佐竹義恭の長男 |
| 6.佐竹義純 従五位下 壱岐守 |
陸奥相馬中村藩主・相馬益胤の三男 |
| 8.佐竹義諶 従五位下 壱岐守・播磨守 |
陸奥相馬中村藩主・相馬益胤の四男 |
| 9.佐竹義理 |
陸奥相馬中村藩主・相馬充胤の三男 |
廃藩置県
|
| |
久保田
新田藩
|
外様 2万石 出羽国
三代藩主義処が甥式部少輔義都(佐竹義都)に新田1万石を分与したことに始まる。
1.佐竹式部少輔義都 1701年(元禄14年)-1720年(享保5年)
2.佐竹豊前守義堅 1720年(享保5年)-1732年(享保17年) 宗家養子(1742年(寛保2年)相続以前に死去)
|
| |
 |
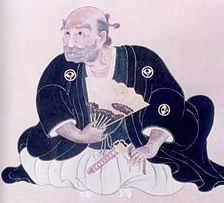 |
 |
| |
初代:佐竹 義宣 |
2代:佐竹 義隆 |
12代:佐竹 義堯 |
|


|
陸奥の武家で本姓は源氏。本貫地は甲斐国南部郷で家祖は南部光行。
南部氏初代の光行は、平安時代に活躍した清和源氏の一流である河内源氏 源義光や、平安時代から
平安時代末期に活躍した黒源太清光の子孫、甲斐源氏・加賀美遠光の流れを汲む。
戦国時代
陸奥では三戸南部氏の出身で南部氏第24代当主である南部晴政が現われ、他勢力を制して
陸奥北部を掌握した。天正10年(1582年)に晴政、晴継父子が没し、南部一族内の家督争いの結果、
石川(南部)信直が相続する。南部氏第26代当主である南部信直は八戸直栄を随伴し兵1000を率いて、
豊臣秀吉の「小田原征伐」に参陣する。 |
南部 利直(なんぶ としなお)
天正4年(1576年)、第26代当主・南部信直の長男として三戸の田子城にて生まれる。天正18年(1590年)、前田利家を
烏帽子親として元服し、その偏諱(「利」の1字)を受けて利直と名乗る.
慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いにおいて、東軍の家康は東北・北陸の大名に対し西軍の石田三成に通じた会津上杉景勝の
征伐を命じ、利直は最上義光の後援として山形に出陣する。元和元年(1615年)には盛岡城を築城して城下町を形成し、
三戸城下の市民も盛岡に移した。
| |
南部藩
南部家 |
外様 10万石 陸中国 盛岡城
| 1.南部利直(としなお) |
従四位下、信濃守 |
信直の長男 |
| 2.南部重直(しげなお) |
従五位下、山城守8万石 |
利直の三男 |
| 3.南部重信(しげのぶ) |
従四位下、大膳大夫 |
利直の五男 |
| 4.南部行信(ゆきのぶ) |
従四位下、信濃守 |
重信の長男 |
| 5.南部信恩(のぶおき) |
従五位下、備後守 |
行信の三男 |
| 6.南部利幹(としもと) |
従五位下、信濃守、大膳亮 |
行信の四男 |
| 7.南部利視(としみ) |
従四位下、修理大夫、大膳大夫 |
信恩の次男 |
| 8.南部利雄(としかつ) |
従四位下、大膳大夫 |
利幹の長男 |
| 9.南部利正(としまさ) |
従五位下修理太夫、大膳大夫 家格旗本寄合席の南部信起の婿養 |
| 10.南部利敬(としたか) |
従四位下、大膳大夫 |
利正の次男 |
| 11.南部利用(としもち) |
享年15歳将軍・徳川家斉と御目見せずに死去 |
南部信丞の長男 |
| 11.南部利用(としもち) |
従四位下、大膳大夫
1人目の利用(幼名:吉次郎)の替え玉として藩主に擁立された。
|
南部信浄の三男 |
| 12.南部利済(としただ) |
従四位下、信濃守、少将 南部利謹(藩主・南部利雄の長男)の次男 |
| 13.南部利義(としとも) |
正四位、甲斐守 |
利済の長男 |
| 14.南部利剛(としひさ) |
従四位→正三位、美濃守 |
利済の三男 |
| 15.南部利恭(としゆき |
従二位、甲斐守 |
利剛の長男 |
廃藩置県
|
支藩
七戸藩(盛岡新田藩)
盛岡新田藩と言われる盛岡藩の支藩。元々は江戸幕府旗本寄合席の石高5000石の旗本であったが、
本家より加増を受けて成立したもの。定府(江戸住まい)大名であるが、南部信鄰が幼少の南部吉次郎利用
を補佐する際には幕府の許可をもらって盛岡に下向し、本家藩政に参画した。
南部利敬から蔵米で6,000石を加増、11,000石の定府大名として、盛岡新田藩を立藩し諸侯に列する。
| |
七戸藩
南部家 |
外様 1.2万石 陸中国
| 1.南部信鄰(のぶちか)従五位下、播磨守 |
旗本の南部信喜の子 |
| 2.南部信誉(のぶのり)従五位下丹波守 |
信鄰の長男 |
| 3.南部信民(のぶたみ )従五位下、美作守 |
信也の四男 |
| 4.南部信方(のぶかた |
利剛の三男 |
廃藩置県
|
|

八戸藩
|
八戸藩は陸奥国三戸郡八戸(青森県八戸市内丸)に存在した南部氏族の藩である。
寛文4年に八戸藩が分立され、藩庁は八戸城である。盛岡藩との関係については、独立した関係とされる。
寛文4年(1664年)、南部盛岡藩3代藩主・南部重直が嗣子を定めずに病没したため、幕府の命により
遺領10万石を、重直の2人の弟、七戸重信の本藩8万石と、中里数馬の八戸藩2万石に分割され、
将軍の裁定により成立した藩であるため独立した藩とされ、翌寛文5年(1665年)、領地が配分される。
|
| |
八戸藩
南部家 |
外様 2万石 陸奥国
| 1.南部直房(なおふさ)従五位下、左衛門佐 |
南部藩利直の七男 |
| 2.南部直政(なおまさ)従五位下、遠江守側用人 |
直房の長男 |
| 3.南部通信(みちのぶ従五位下、遠江守 |
重信の四男 |
| 4.南部広信(ひろのぶ従五位下、甲斐守 |
通信の長男 |
| 5.南部信興(のぶおき従五位下、遠江守、左衛門尉 |
広信の長男 |
| 6.南部信依(のぶより従五位下、甲斐守 |
信興の長男 |
| 7.南部信房(のぶふさ従五位下、伊勢守 |
信依の長男 |
| 8.南部信真(のぶまさ |
信依の三男 |
| 9.南部信順(のぶゆき従四位下、遠江守、侍従 |
薩摩藩主・島津重豪の十四男 |
廃藩置県
|
|
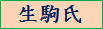

|
生駒の名字は大和国平群郡生駒(現在の奈良県生駒市)を本貫とする
藤原忠仁公(良房)の子孫が生駒の地に移り住み本拠とするようになり、後に生駒を名乗るようになった。
室町時代に応仁の乱の戦禍から逃れるため、家広の頃尾張国丹羽郡小折の地に移住したと伝えられる
讃岐生駒氏(矢島生駒氏)
大名生駒氏、土田生駒氏(どたいこまし)、美濃生駒氏とも称される。生駒豊政の妹が嫁いだ土田氏より
子親重を養子に迎え生駒姓を与え養子分家としたのが始まりであり、元は六角氏傍系の
土田氏、土田甚助である。 |
生駒 一正(いこま かずまさ)
織田氏の家臣・生駒親正の長男として誕生。信長死後は羽柴秀吉に仕えて数々の合戦に参加する。
関ヶ原の戦いでは、父・親正の代わりに会津出兵に参加し、そのまま東軍に与して関ヶ原本戦で武功を挙げた
国許の親正は西軍に加わっていたが一正の功により罪を問われず、1万5千石の加増となった。
| 1 |
高松藩
生駒家 |
外様 17.3万石 讃岐国 (1587年 - 1640年)
| 1.親正(ちかまさ)〔従四位下、雅楽頭〕 |
生駒親重の子 |
| 2.一正(かずまさ)〔従四位下、讃岐守〕 |
親正の長男 |
| 3.正俊(まさとし)〔従四位下、讃岐守〕 |
一正の長男 |
| 4.高俊(たかとし)〔従四位下、壱岐守〕 |
正俊の長男 |
成年した高俊は、政務を放り出して美少年たちを集めて遊興に専ら耽ったこともあって、
家臣団の間で藩の主導権をめぐって内紛が起こった(生駒騒動)。改易
寛永17年、幕府は藩主高俊の責任を追及し、領地を没収し、出羽国由利郡に流罪とした。
由利郡矢島(現在の秋田県由利本荘市矢島町と鳥海町の部分)で1万石を堪忍料として与え
高俊は矢島村に陣屋を構えた。
|
| 2 |
矢島藩
生駒家 |
外様 1万石→8000石→1万5200石 羽後国
| 1.高俊(たかとし)〔従四位下、壱岐守〕 |
|
| 2.高清(たかきよ) |
高俊の長男 |
| 3.親興(ちかおき) |
高俊の三男 |
| 4.正親(まさちか) |
交代寄合生駒親興の長男 |
| 5.親猶(ちかなお) |
親興の三男 |
| 6.親賢(ちかたか) |
親猶の長男 |
| 7.親信(ちかのぶ) |
|
| 8.親睦(ちかとし) |
駿河国田中藩主本多正矩の七男 |
| 9.親章(ちかあきら) |
親睦の長男 |
| 10.親孝(ちかのり) |
丹羽長貴の三男 |
| 11.親愛(ちかよし) |
奥平昌高の六男 |
| 12.親道(ちかみち) |
奥平昌高の十一男 |
| 13.親敬(ちかゆき)〔従五位下、讃岐守〕 |
旗本・生駒親道の息子 |
廃藩置県
|
|


|
真田氏は清和源氏の発祥で、信濃国小県郡(現在の長野県東御市)の海野棟綱あるいは真田頼昌の子という
真田幸綱(幸隆)が小県郡真田郷を領して以後、真田姓を名乗ったという。
上杉の援助による旧領奪回が困難になると、信濃侵攻を行っていた甲斐の武田信玄に仕えて旧領を
回復すると共に、縁故の滋野氏の支族が多い信濃や上野方面で活躍し、次第に真田氏の勢力基盤が
築かれていった。昌幸は武田氏が滅んだ後織田信長に恭順した。しかし本能寺の変で信長が横死すると、
昌幸は本拠地として上田城の築城に着手しながら混乱する信濃にあって主家を転々と変え、真田家の
勢力維持に奔走する。昌幸は上杉景勝を通じて豊臣秀吉の臣下に入り、秀吉の命で徳川家康と和解する。
そして徳川氏の与力大名となったとなったことから、嫡男・信幸と本多忠勝の娘で家康の養女となった
小松姫との婚姻が成った。これらの過程で真田宗家は、名目上は徳川氏の与力大名だが実際は豊臣の
家臣である昌幸と次男・信繁(上田城)と、名目上は昌幸の所領の一部を収める領主だが実際は
徳川の与力大名である長男・信幸(沼田城)の2家体制となる。 |
関ヶ原の戦い
関ヶ原の戦いが起こると、昌幸と次男・信繁は西軍に、長男・信幸は東軍に分かれることになった。
昌幸と信繁は上田城で徳川秀忠率いる約3万の軍勢をわずか数千で迎え撃って秀忠軍を釘付けにし(第二次上田合戦)、
秀忠の関ヶ原遅参の一因を作った。しかし努力のかいもなく戦いは東軍の勝利となり、戦後に昌幸と信繁は紀伊の
九度山に蟄居となる。大坂の役でも信之は徳川方についたが、弟の信繁は豊臣方に馳せ参じて家康を手こずらせた
のち討死している。
真田 信之(さなだ のぶゆき)
武藤喜兵衛(後の真田昌幸)の長男として生まれる。父昌幸が甲斐国の武田氏に臣従したため、
信幸は武田氏の人質として過ごした。天正7年(1579年)、武田勝頼の嫡男・信勝の元服と同時に
元服を許され、信勝の1字を賜って信幸と名乗った。
信幸の才能を高く評価した家康は重臣の本多忠勝の娘・小松姫を養女とし、駿府城に信幸を出仕させて娶らせた
関ヶ原の戦い家康の養女を妻とする信幸は家康らの東軍に参加することを決め、徳川秀忠軍に属して上田城攻め
(第二次上田合戦)に参加する。戦いの前に義弟の本多忠政と共に父の説得に赴いたが、結局失敗に終わったとされる。
| 1 |
上田藩 |
外様 9.5万石 信濃国
1.真田信之(のぶゆき) 従五位下 伊豆守 真田昌幸)の長男
|
| 2 |
松代藩 |
外様(譜代格) 10万石 信濃国
| 1.信之(のぶゆき)〔従五位下、伊豆守〕 |
|
| 2.信政(のぶまさ)〔従五位下、内記〕 |
信之の次男 |
| 3.幸道(ゆきみち)〔従四位下、伊豆守〕 |
信政の六男 |
| 4.信弘(のぶひろ)〔従五位下、伊豆守〕 |
真田信就(2代藩主真田信政の長男)の七男 |
| 5.信安(のぶやす)〔従五位下、伊豆守〕 |
信弘の三男 |
| 6.幸弘(ゆきひろ)〔従四位下、右京大夫〕 |
信安の長男 |
| 7.幸専(ゆきたか)〔従四位下、弾正大弼〕 |
近江彦根藩主・井伊直幸の九男 |
| 8.幸貫(ゆきつら)〔従四位下、右京大夫〕 老中 |
松平定信の次男 |
| 9.幸教(ゆきのり)〔従四位下、右京大夫〕 |
真田幸良の長男 |
| 10.幸民(ゆきたみ)〔従二位、信濃守〕 |
伊予宇和島藩主・伊達宗城の長男 |
廃藩置県
|
| |
沼田藩 |
外様 3万石 上野国
| 1.真田信之(のぶゆき) 従五位下 伊豆守 |
|
| 2.真田信吉(のぶよし) 従五位下 河内守 |
信之の長男 |
| 3.真田熊之助(くまのすけ) なし |
信吉の長男 |
| 4.真田信政(のぶまさ) 従五位下 内記 |
松代藩の第2代藩主信之の次男 |
| 5.真田信利(のぶとし) 従五位下 伊賀守 |
公式には初代藩主信吉の次男 |
当時の沼田3万石は独立した藩ではなく、松代藩の分領(分地)であった。沼田は信吉死後、信利の兄の熊之助が
統治していたが、寛永15年(1638年)に幼くして没した。
|
松代藩相続争い
| 松代藩の第2代藩主信政は2年後の明暦4年(1658年)2月に死去し、松代藩はまだ存命だった隠居の信之の |
| 決定により、信政の子の幸道を後継者とし、幕府に届け出た。その時、信利は信之の長子信吉の子で |
| あることを理由に「松代藩の後継者は自分である」と幕府に訴え出て撤回を求めた。 |
| 信利には正室の実家の土佐藩や老中で下馬将軍酒井忠清が後ろ盾となり、大規模な家督騒動を展開したが |
| 幕府は幸道をもって松代藩の後継者と最終決定した。 |
| 沼田領は松代藩から独立して正式に沼田藩として立藩している。 |
| これ以降、信利は10万石の松代藩に対抗するため、沼田城を修築して5層の大天守閣を立て、 |
| 領民は重税を強いられ多数の餓死者を出すなど、ますます窮乏していった。 |
| 沼田藩は幕府から治世不良、納期遅滞の責めを問われ、改易された。 |
| |
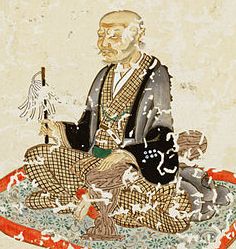 |
 |
 |
| |
父 真田昌幸 |
真田 信之 |
弟 真田信繁 / 真田幸村 |
|
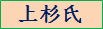

|
| 藤原北家勧修寺流の流れを汲み、鎌倉時代の中頃まで京都の中級公家の家柄であった、重房の代に至って |
| 丹波国何鹿郡上杉荘(うえすぎのしょう、現在の京都府綾部市上杉町周辺)を領して本貫とし、上杉氏を称した。 |
| 室町時代は鎌倉府にあって鎌倉公方の執事、次いで関東管領の職を世襲し、相模、武蔵、上野、越後など |
| 一門で4か国の守護職を占める有力守護大名としても栄えた。しかし、従来より鎌倉府に仕え関東に |
| 拠点のあった山内上杉家と、当初は室町幕府に仕えて京都に在住した扇谷上杉家が、関東の覇権をかけて |
| 内紛を起こし次第に勢力を衰退させる。戦国時代には関東における覇権を新興勢力である後北条氏に |
| 押され、山内上杉家の当主上杉憲政は、越後守護代として勢力を台頭させていた三条長尾家の長尾景虎 |
| (後の上杉謙信)に上杉の名跡を譲った。景虎は山内上杉家の家督、関東管領就任により |
| 上杉政虎(輝虎)と名乗った。これにより再び上杉氏は勢いを取り戻し、甥で養子の景勝 |
| (越後長尾氏のうち上田長尾家より)は豊臣政権の五大老を務め会津藩120万石、江戸時代は |
| 米沢藩30万石(実高51万石)を領した。後に無嗣の危機に瀕したこともあり15万石(実高33万石)に |
| 減知されたが、幕末まで大名としての地位を維持した |
|
上杉 景勝(うえすぎ かげかつ)
| 戦国時代から江戸時代初期にかけての武将・大名。豊臣政権の五大老の一人。 |
| 弘治元年(1555年)、越後国魚沼郡上田庄の坂戸城下に上田長尾家当主・長尾政景の次男として生まれる |
| 天正6年(1578年)3月13日、謙信が死去すると、後北条氏から人質として出され謙信が養子に迎えた |
| 上杉景虎との相続争いが勃発する。慶長3年8月、秀吉が死去すると、家老の直江兼続が五奉行の石田三成と懇意にあった事などの |
| 慶長3年、秀吉が死去すると、家老の直江兼続が五奉行の石田三成と懇意にあった事などの |
| 経緯から徳川家康と対立する。東軍に与した伊達政宗や最上義光らと戦った(慶長出羽合戦)。関ヶ原の戦いで、三成ら西軍が |
| 敗れたため、12月に家康に降伏することを余儀なくされた。改易は免れたものの、置賜・信夫・伊達の3郡からなる |
| 出羽米沢(30万石)藩主として減移封され、上杉家は景勝一代において北信越の大大名から出羽半国の一大名へと没落した。 |
| |
米沢藩
上杉家 |
外様・国主・大広間 30万石→15万石→18万石→14.7万石 羽前国
| 1.上杉景勝(かげかつ)〔従三位・権中納言、弾正少弼 |
長尾政景の次男 |
| 2.上杉定勝(さだかつ)〔従四位下・左近衛権少将、弾正大弼〕 |
景勝の長子 |
| 3.上杉綱勝(つなかつ)〔従四位下・侍従、播磨守〕 |
定勝の子 |
| 4.上杉綱憲(つなのり)〔従四位下・侍従、弾正大弼〕15万石に減知 |
吉良義央の長男(定勝の孫) |
| 5.上杉吉憲(よしのり)〔従四位下・侍従、民部大輔〕 |
綱憲の長男 |
| 6.上杉宗憲(むねのり)〔従四位下・侍従、弾正大弼〕 |
吉憲の長男 |
| 7.上杉宗房(むねふさ)〔従四位下・侍従、民部大輔〕 同母弟 |
吉憲の次男 |
| 8.上杉重定(しげさだ)〔従四位下・侍従、大炊頭〕 同母弟 |
杉吉憲の四男 |
| 9.上杉治憲(はるのり)〈鷹山〉〔従四位下・侍従、弾正大弼のち越前守 |
高鍋藩主・秋月種美の次男 |
| 10.上杉治広(はるひろ)〔従四位下・左近衛権少将、弾正大弼〕 |
重定の次男 |
| 11.上杉斉定(なりさだ)〔従四位下・左近衛権少将、弾正大弼、贈従三位〕 |
上杉勝煕の長男 |
| 12.上杉斉憲(なりのり)〔従四位上・左近衛権中将、弾正大弼、〕18万石に加増 斉定の長男 |
| 13.上杉茂憲(もちのり)〔従四位下・侍従、式部大輔〕 |
斉憲の庶子 |
廃藩置県
|
支藩
| |
米沢新田藩
上杉家 |
外様 1万石 羽前国
米沢藩の支藩。外様。柳間詰。代々駿河守を称し、駿府城加番役を務めた。
享保4年(1719年)に5代藩主吉憲が弟の勝周に領内の新田分1万石を分与して成立した。
| 1.勝周(かつちか)〔従五位下、駿河守〕 |
1719-1747 |
綱憲の四男 |
| 2.勝承(かつよし)〔従五位下、駿河守〕 |
1747-1785 |
勝周の子 |
| 3.勝定(かつさだ)〔従五位下、駿河守〕 |
1785-1815 |
米沢藩主・重定の三男 |
| 4.勝義(かつよし)〔従五位下、佐渡守〕 |
1815-1842 |
上杉勝煕の四男 |
| 5.勝道(かつみち)〔従五位下、駿河守〕 |
1842-1869 |
上杉斉定の四男 |
明治2年(1869年)7月、新田藩の所領を本藩に返し、新田藩は廃藩となった。
|
| |
 |
 |
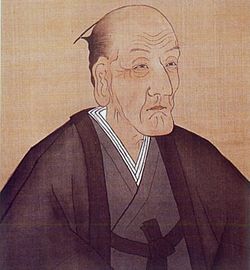 |
 |
| |
上杉 謙信 |
初代:上杉景勝 |
9代上杉 治憲/ 鷹山 |
上杉家家老の直江兼続 |
|
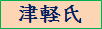
 |
津軽氏の系譜には諸説あるが多くの系図は、南部氏の庶家・大浦光信を祖とする津軽大浦家として
家系を開始しており、延徳3年(1491年)、十三安藤氏残党の反抗に対処させるために久慈から種里に
移封したと「可足記伝」「津軽一統志」などで伝えられているが、久慈氏から養子に入った
大浦(津軽)為信が近衛家の傍流を自称して以来、藤原氏を称している。 |
津軽 為信(つがる ためのぶ)
| 戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、大名。陸奥弘前藩初代藩主津軽為信の出自には様々な説や伝承があり、 |
| 南部氏支族で下久慈城主であった久慈氏の出とも、久慈氏の出とも、為信の実家と言われる久慈氏の出自は、 |
| 南部氏始祖である南部光行が建久2年(1191年)地頭職として陸奥国糠部郡に入部して以降、 |
| その四男・七戸三郎朝清の庶子の家系が久慈に入部して久慈氏を称したとされ、室町期には |
| 南部嫡流の時政の子・信実が久慈修理助治政の養子となっている。慶長5年(1600年)1月27日、右京大夫に任官される |
| (藤原姓)。同年の関ヶ原の戦いでは領国の周囲ががすべて東軍という状況から三男・信枚と共に、東軍として参加した。 |
| |
弘前藩
津軽家 |
外様 4.7万石→4.6万石→7万石→10万石 陸奧国
| 1. 為信(ためのぶ)〔従五位下、右京大夫〕( - 1607年) |
大浦守信の子 |
| 2. 信枚(又は「信牧」 のぶひら)〔従五位下、越中守〕(1607年 - 1631年) 為信の三男 |
| 3. 信義(のぶよし)〔従五位下、土佐守〕(1631年 - 1655年) |
信枚の長男 |
| 4. 信政(のぶまさ)〔従五位下、越中守〕(1656年 - 1679年) |
信義の長男 |
| 5. 信寿(のぶひさ)〔従五位下、土佐守〕(1679年 - 1731年) |
信政の次男 |
| 6. 信著(のぶあき)〔従五位下、出羽守〕(1731年 - 1744年) |
津軽信興の長男 |
| 7. 信寧(のぶやす)〔従五位下、越中守〕(1744年 - 1784年) |
信著の長男 |
| 8. 信明(のぶはる、のぶあきら)〔従五位下、土佐守〕(1784年 - 1791年) 信寧の長男 |
| 9. 寧親(やすちか)〔従五位下、土佐守〕(1791年 - 1820年) 黒石藩第5代当主・津軽著高の長男 |
| 10. 信順(のぶゆき)〔従四位下、出羽守・侍従〕(1820年 - 1839年) |
寧親の次男 |
| 11. 順承(ゆきつぐ)〔従四位下、左近将監〕(1839年 - 1859年) |
三河吉田藩松平信明の五男 |
| 12.承昭(つぐあきら)〔従四位下、土佐守・左近衛権少将・侍従 〕 1869年) 熊本藩主・細川斉護の四男 |
廃藩置県
|
支藩
黒石藩 :交代寄合 5000石→4000石 津軽家(黒石津軽家)
| 弘前藩の支藩に、陸奥国津軽郡黒石(現在の青森県黒石市)に置かれた黒石藩(くろいしはん)がある。 |
| 黒石藩は本家4代藩主信政が藩主就任時幼少だったため、幕府の指示により叔父の信英 |
| (3代藩主・信義の弟)を本藩の後見人とすべく、明暦2年(1656年)信政が本藩を継ぐと同時に |
| 弘前藩より5,000石を分知されたのに始まる |
| 文化6年(1809年)弘前本藩より更に6,000石の分与があり、1万石の外様大名として柳間に列した。 |
| |
黒石藩
津軽家 |
外様 4000石→1万石 陸奧国
| 1.信英(のぶふさ)(1656年 - 1662年) |
信枚の次男 |
| 2.信敏(のぶとし)(1663年 - 1683年)弟津軽信純に1000石分与 |
信英の長男 |
| 3.政?(まさたけ)〔正六位下、釆女正〕交代寄合から外されると伝わる。 |
信敏の子 |
| 4.寿世(ひさよ)(1743年 - 1758年)本家4代藩主信政の五男。婿養子 |
|
| 5.著高(あきたか)(1758年 - 1778年) |
寿世の子 |
| 6.寧親(やすちか)〔従五位下、土佐守〕(1778年 - 1791年)弘前藩9代藩主となる。著高の長男 |
| 7.典暁(つねとし)(1791年 - 1805年) |
津軽寧親の長男 |
| 8.親足(ちかたり)(1805年 - 1809年)1万石となり大名へ 上総国久留里藩主黒田直亨の四男 |
9.順徳(ゆきのり)〔従五位下、左近将監〕弘前藩11代藩主を相続し、津軽順承と改名。
三河吉田藩松平信明の三男 |
| 10.承保(つぐやす)〔従五位下、出雲守〕(1839年 - 1851年) |
津軽親足の二男 |
| 11.承叙(つぐみち)〔従五位下、式部少輔 贈・正三位〕弘前本藩一門、 |
津軽順朝の二男 |
廃藩置県
|
| |
 |
 |
| |
初代:津軽 為信 |
弘前城 |
|


|
清和源氏の一流、河内源氏の流れを汲む武家である。八幡太郎源義家の七男源義隆が相模国
愛甲郡毛利庄の領主ととなって、森冠者と名乗った。その三男、源頼隆は後に若槻を号するが、出家の後は
森蔵人入道西阿と称した。有名な森氏の名は、信長の小姓となった森蘭丸(成利)も父兄の治めた
美濃国金山に6万石を与えられ、森氏はかつてない栄華を極めたが、そうした栄光も本能寺の変において
織田家の有力家臣である明智光秀が謀叛を起こし、信長主従を討つと、森蘭丸はじめその弟の
森坊丸(長隆)、森力丸(長氏)ともども討ち死にしてしまう。
森家当主森長可やその弟 忠政は本能寺の場にはおらず領国にいたために生き延びていた。 |
森 忠政(もり ただまさ)
| 元亀元年(1570年)、美濃金山城で織田信長の家臣、森可成の6男として生まれる。(森蘭丸の弟) |
| 天正15年2月6日、従四位下侍従に昇る。また同時に羽柴姓と桐紋の使用を認められ、以後「羽柴右近大夫忠政」と称す。 |
| 慶長3年(1598年)に秀吉が死亡すると徳川家康に接近、信濃国川中島13万7,500石への加増転封 |
| 慶長8年(1603年)、小早川秀秋の死によって小早川家が無嗣改易されると美作一国18万6,500石への加増転封が決定。 |
| 1 |
松代藩 |
外様 13.75万石 (川中島藩) 信濃国
1.忠政(ただまさ)〔従四位下、右近大夫・侍従〕 森可成の6男
|
| 2 |
津山藩
森家 |
外様 18.65万石 美作国
| 1.忠政(ただまさ) |
従四位下、右近大夫・侍従 |
| 2.長継(ながつぐ) |
従四位下、侍従、大内記 |
森忠政(外孫)の重臣・関成次の長男 |
| 3.長武(ながたけ) |
従四位下、伯耆守 |
長継の三男 |
| 4.長成(ながなり) |
従四位下、侍従、美作守 |
第2代藩主森長継の長男・忠継の三男 |
| 5.衆利(あつとし) |
|
長継の十二男 |
将軍拝謁のための道中に幕政を批判して発狂した。浪人たちがその収容した犬たちを沢山殺す
件を起こし、管理を怠ったとして家臣の切腹したことに対し、なぜこのような法令のために
死なねばならぬのかという疑問があったからとされる幕政を批判して発狂した。改易
聞こえおぼしき家柄であるため特別に再勤を命じられ、備中西江原藩2万石を与えられ、
孫は同藩主として存続した。
|
| 3 |
西江原藩
森家 |
外様 2万石 備中国
| 1.長継(ながつぐ |
従四位下・大内記(津山藩主時代) |
| 2.長直(ながなお |
従五位下・和泉守 |
長継の八男 |
|
| 4 |
赤穂藩
森家 |
外様 2万石 播磨国
| 1.長直(ながなお) 〔従五位下、和泉守〕 |
長継の八男 |
| 2.長孝(ながたか) 〔従五位下、志摩守〕 |
森家の家老森三隆の三男 |
| 3.長生(ながなり) 〔従五位下、越中守〕 |
赤穂藩重臣の各務利直の長男 |
| 4.政房(まさふさ) 〔従五位下、伊勢守〕 |
利直の六男 |
| 5.忠洪(ただひろ) 〔従五位下、和泉守〕 |
森家の家老・森正典の子 |
| 6.忠興(ただおき) 〔従五位下、山城守〕 |
忠洪の長男 |
| 7.忠賛(ただすけ) 〔従五位下、大内記〕 |
忠洪の三男 |
| 8.忠哲(ただあきら) 〔従五位下、和泉守〕 |
忠賛の四男 |
| 9.忠敬(ただたか) 〔従五位下、肥後守〕 |
忠賛の十男 |
| 10.(忠貫)(ただつら) |
忠敬の長男 |
| 11.忠徳(ただのり) 〔従五位下、越中守〕 |
忠敬の三男 |
| 12.忠典(ただつね) 〔従五位下、美作守〕 |
忠徳の次男 |
| 13.忠儀(ただのり) 〔従五位下、越後守〕 |
忠徳の三男 |
廃藩置県
|
森 長俊(もり ながとし
美作津山藩主森長継の五男。母は側室で湯浅丹後の娘の継光院
美作の鶴山城にて生まれる。延宝4年(1676年)4月、1万5000石を父より与えられる。
元禄10年(1697年)8月、本家の津山藩森家が 改易されると、同年10月19日に三日月藩に移封された。
| |
赤穂藩
森家 |
外様 1.5万石 (1697年 - 1871年) 播磨国
| 1.長俊(ながとし)〔従五位下・対馬守) |
長継の五男 |
| 2.長記(ながのり)〔従五位下・安芸守〕 |
長俊の長男 |
| 3.俊春(としはる)〔従五位下・対馬守〕 |
長記の五男 |
| 4.俊韶(としつぐ)〔従五位下・対馬守〕 |
俊春の長男 |
| 5.快温(はやあつ)〔従五位下・丹波守〕 |
安芸広島藩主・浅野重晟の三男 |
| 6.長義(ながよし)〔従五位下・河内守〕 |
備中新見藩主・関長誠の次男 |
| 7.長篤(ながあつ)〔従五位下・対馬守〕 |
播磨赤穂藩主・森忠賛の十一男 |
| 8.長国(ながくに)〔従五位下・佐渡守〕 |
長義の長男 |
| 9.俊滋(とししげ)〔従五位下・伊豆守〕 |
長国の次男 |
廃藩置県 |
|

 |
京極氏の源流である佐々木氏は、鎌倉時代以前より近江にあり、近江源氏とも称された家系である。
始祖の京極氏信は鎌倉幕府の評定衆を務めた。跡を継いだ宗綱は、幕府が朝廷に対し天皇の譲位を
促した際の使者を務めている。足利尊氏が倒幕の兵を挙げるとそれに寄与し、建武の新政に加わる。
室町幕府が開かれると、導誉は功績を評されて引付頭人、評定衆、政所執事、さらに近江・飛騨・出雲・
若狭・上総・摂津の6カ国の守護を務めることとなる。 |
京極 高次(きょうごく たかつぐ) 高次流 (若狭京極家)
永禄6年(1563年)、京極高吉と京極マリア(浅井久政の娘。浅井長政の姉)の長男として、浅井氏の居城である近江国の
小谷城京極丸で生まれる。 |
| 本能寺の変で信長が明智光秀に討たれると、高次は妹の竜子が嫁いでいた若狭国の武田元明と共に光秀に与し、羽柴秀吉の |
| 居城である長浜城を攻めるが、13日(7月2日)の山崎の戦いで光秀は秀吉に討たれ元明は自害した。高次は初め美濃国、そして |
| 若狭国の武田領へと逃れる、秀吉の側室となった妹・竜子の嘆願などにより、高次は許されて秀吉に仕えることとなり、 |
| 九州征伐の功により、1万石に加増文禄4年(1595年)には近江大津城6万石へと加増された。 |
| 秀吉が没した後は関ヶ原の戦いの前に、家康・光成より西軍東軍からの誘いが再三あるが、高次は大津城の守りが弱いことから |
| 一旦は西軍へ属することを決め、大津城を訪れた三成と面会する。しかし関ヶ原への出陣に備えつつ、西軍の動向を東軍に伝える。 |
| 城に兵を集め兵糧を運び込み、籠城し西軍を抑える旨を、家康の重臣である井伊直政に伝える。高次の行動は即大坂へと伝えられ、 |
| 城近くの逢坂関にいた毛利元康軍が大津の町へと攻め寄せた。高次の篭城により大足止めされた毛利元康および立花宗茂らの |
| 大軍勢は移動に時間がかかったため、関ヶ原に参陣することができなかった。 |
| 1 |
小浜藩
京極家 |
外様 9.2万石→11.3万万石 若狭国
| 1.京極高次(たかつぐ)従三位。若狭守。参議 |
|
| 2.京極忠高(ただたか)従四位下。左近衛権少将 |
正室は徳川秀忠の四女・初姫高次の長男 |
関ヶ原の戦いの戦功により、小浜には近江大津6万石を領し大津城主であった京極高次が若狭一国を与らる
|
| 2 |
松江藩
|
外様 24万石 出雲国 (1634年 - 1637年)
1.忠高(ただたか)〔従四位下・若狭守、左少将〕 高次の長男
将軍家姻戚として優遇された京極家だったが、正室・初姫との夫婦仲はあまり良くなかった
くなかったとみられる。寛永7年(1630年)に初姫が死去した際は、忠高は臨終に立ち会うこともなく
相撲見物に興じていたと伝えられる。大御所・秀忠や義弟の3代将軍・家光の怒りを買い、
寛永14年(1637年)、45歳で死去した。嗣子がなかったため、京極氏は改易されかけたが
甥の高和が播磨龍野に6万石の所領を与えられることで大名として存続を許された。
|
| 3 |
龍野藩
|
外様 6万石 播磨国 ( 1637年 - 1658年)
1.高和(たかかず)〔従五位下、刑部少輔〕 安毛高政の長男 |
| 4 |
丸亀藩
|
外様 6万石→5万1千石 讃岐国
| 1.高和(たかかず)〔従五位下、刑部少輔〕 |
安毛高政の長男 |
| 2.高豊(たかとよ)〔従五位下、備中守〕 |
高和の次男 |
| 3.高或(たかもち)〔従五位下、若狭守〕分封により5万1千石 |
高豊の五男 |
| 4.高矩(たかのり)〔従五位下、佐渡守〕 |
高或の長男 |
| 5.高中(たかなか)〔従五位下、若狭守〕 |
高矩の長男 |
| 6.高朗(たかあきら)〔従五位下、長門守〕 |
高中の四男 |
| 7.朗徹(あきゆき)〔従五位下、佐渡守〕 |
京極高周(右近)の五男 |
廃藩置県
|
支藩
多度津藩 :多度津藩(たどつはん)は丸亀藩の支藩である。多度津周辺(香川県仲多度郡多度津町)
丸亀藩3代藩主の高或が3歳で藩主となったため、庶兄である高通を後見人として幕府に分封を願い出た。
| |
多度津藩
京極家 |
外様 1万石 讃岐国
| 1.高通(たかみち)〔従五位下、壱岐守〕 |
丸亀藩2代藩主・京極高豊の四男 |
| 2.高慶(たかよし)〔従五位下、出羽守〕 |
高通の長男 |
| 3.高文(たかぶみ)〔従五位下、壱岐守〕 |
高慶の六男 |
| 4.高賢(たかかた)従五位下、壱岐守 |
高文の長男 |
| 5.高琢(たかてる)従五位下、壱岐守 |
高賢の長男 |
| 6.高典(たかまさ) |
京極高宝(第5代藩主・京極高琢の庶弟)の次男 |
廃藩置県
|
京極 高知(きょうごく たかとも)
近江守護の名門京極高吉の次男として生まれる。早くから豊臣秀吉に仕え、その功により羽柴姓を許されて
羽柴伊奈侍従と称す。秀吉死後は徳川家康に接近し、慶長5年(1600年)には岐阜城攻めに参戦し、関ヶ原の戦いでは
大谷吉継隊と戦うなどの戦功を挙げた。戦後は丹後12万3000石を与えられ、国持大名として京極丹後守を称した。
| |
宮津藩
京極家 |
外様 12.3万石→7.8万石 丹後国
| 1.高知(たかとも)〔従四位下、丹後守・侍従〕 |
|
| 2.高広(たかひろ)〔従四位下、丹後守〕分知により7万8千石 |
高知の次男 |
| 3.高国(たかくに)〔従四位下、丹後守・侍従〕 |
高広の長男 |
父の隠居により家督を継いで藩主となる。しかし隠居した高広が藩政に介入したことから父と対立し
さらに高国自身も年貢が納められていないとして、その村そのものを取り潰すなどの悪政を布いた
寛文6年(1666年)5月3日、親子不和や悪政を理由に幕命によって改易
|
京極 高三(きょうごく たかみつ)
丹後国主・京極高知の三男、京都二条城で大御所の徳川家康と、江戸幕府第2代将軍・徳川秀忠に拝謁した
| 1 |
丹後
田辺藩
京極家 |
外様 3.5万石→3.3万石 丹後国 (1600年 - 1668年)
| 1.高三(たかみつ)従五位下、修理大夫 |
京極高知の三男 |
| 2.高直(たかなお)従五位下、飛騨守 |
高三の長男 |
| 3.高盛(たかもり)従五位下、伊勢守 分知により3万3千石 |
高直の長男 |
|
| 2 |
豊岡藩
京極家 |
外様 3.5万石→1.5万石 但馬国 (1668年 - 1871年)
| 1.高盛(たかもり)〔従五位下、伊勢守〕 |
高直の長男 |
| 2.高住(たかずみ)〔従五位下、甲斐守〕 |
高直の四男 |
| 3.高栄(たかよし)〔従五位下、加賀守〕 |
高住の長男 |
| 4.高寛(たかのり)〔夭折のため官位官職なし〕 |
高栄の長男 |
| 5.高永(たかなが)〔従五位下、甲斐守〕 家名相続により1万5千石に減封 高栄の次男 |
| 6.高品(たかかず)〔従五位下、甲斐守〕 |
高永の長男 |
| 7.高有(たかあり)〔従五位下、加賀守〕 |
丹後峰山藩主京極高久の五男 |
| 8.高行(たかゆき)〔従五位下、甲斐守〕 |
高有の長男 |
| 9.高厚(たかあつ)〔従五位下、飛騨守〕 |
高行の長男 |
廃藩置県
|
京極 高通(きょうごく たかみち
朽木宣綱の次男。母は京極高吉の娘。京極高知の甥で養子。元和2年、徳川秀忠の小姓となり3,000石を賜う。
元和8年には丹後宮津藩主の養父高知の遺領のうち中郡1万石を分与され、旧領と併せて峰山1万3,000石を
領することとなり、峰山に立藩した。
| |
峰山藩
京極家 |
外様 1.3万石 丹後国
| 1.高通 - 従五位下、主膳正 |
朽木宣綱の次男 |
| 2.高供 - 従五位下。主膳正 |
高通の長男 |
| 3.高明 - 従五位下。隼人正。備後守。主膳正 |
高供の長男 |
| 4.高之 - 従五位下。主膳正 |
高明の長男 |
| 5.高長 - 従五位下。備後守。主膳正 |
|
| 6.高久 - 従五位下。備前守。若年寄 |
|
| 7.高備 - 従五位下。周防守。若年寄 |
高久の長男 |
| 8.高倍 - 従五位下。備前守 |
高備の五男 |
| 9.高鎮 - 官位は不詳 |
高備の七男 |
| 10.高景 - 従五位下。右近将監 |
肥前島原藩主・松平忠馮の六男 |
| 11.高富 - 従五位下。備中守 |
高景の長男 |
| 12.高陳 - 従五位下。備中守 |
御小姓の京極高紀の次男 |
廃藩置県
|
| |
 |
 |
| |
京極 高次 |
京極 高知 |
|
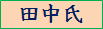
 
|
出自は近江国人で近江源氏とも橘氏ともいわれるが、吉政の父の名も系図により食い違うなど判然とせず、
実際は近江国高島郡田中村(滋賀県高島市安曇川町田中)の農民の子にすぎなかったともいわれる。
しかし家紋に「一つ目結」紋(釘抜き紋ともいう)をもちいたことから、なんらかの形で先祖は佐々木氏と
血縁関係があったと推測される。
|
田中 吉政(たなか よしまさ)
| 戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。 |
| 吉政の出生地は浅井郡の三川村または宮部村(現在の長浜市三川町、宮部町)で、吉政自身はそこに住む |
| 農民であったという説もある。天正10年(1582年)頃、宮部家中から5,000石を与えられ、秀吉の甥の |
| 羽柴秀次(のちの豊臣秀次)の宿老となった |
| 天正13年(1585年)に秀次が近江八幡43万石を与えられると、吉政はその筆頭家老格となった。 |
| 小田原征伐でも秀次軍として活躍した吉政は三河国岡崎城5万7400石の所領が与えられた。 |
| 秀吉の死後は徳川家康に接近し、慶長5年(1600年)9月の関ヶ原の戦いでは東軍に属した。関ヶ原の |
| 合戦前の岐阜城攻略では黒田長政・藤堂高虎と共に大垣城から岐阜城へ向かう西軍を河渡で殲滅した。 |
| 戦後、これらの勲功が認められて、筑後一国柳川城32万石を与えられ、国持ち大名となった。 |
| 1 |
柳河藩 |
外様 32.5万石 筑後国 (1600年 ~ 1620年)
| 1.吉政(よしまさ)〔従四位下、筑後守・侍従〕 |
| 2.忠政(ただまさ)〔従四位下、筑後守・侍従〕 |
吉政の四男 |
慶長19年(1614年)からの大坂冬の陣では徳川方として参戦する。翌年の大坂夏の陣でも
徳川方として参戦しようとしたが、家臣団の一部で旧主の豊臣氏に与するべきという反論が起こり、
さらに財政難などもあって遅参した。駿河にいる家康に謝罪し、罪は許されたが代償として
7年間の江戸滞留を命じられた。
元和6年8月、36歳で死去した。嗣子が無く、柳河藩田中氏は無嗣断絶となり、改易された。
|
田中 吉興(たなか よしおき)
| 柳川藩主・田中吉政の三男として生まれる。 |
| 長兄の吉次は父吉政と不和のため廃嫡され、逐電した。次兄の康政もすでに分家していたことから、 |
| 長幼の順では吉興が後継者となるところであったが、病弱を理由として弟の忠政が継嗣とされ、 |
| 第2代柳川藩主となった。吉興は、のちに忠政から3万石を分知され、支藩を立藩する。 |
| 吉興には男子がなかったため、元和8年(1622年)8月に徳川譜代の菅沼定盈の八男を娘婿に迎え、 |
| 田中吉官(よしすけ)と名乗らせて家督を譲った。 |
| 吉興の家を継いだ吉官は幕府小姓頭を務めていたが、小姓組の同輩・三宅藤五郎が罪を犯して処罰されると |
| 組頭として連帯責任を負い、除封となった。改易 |
| 2年後の寛永2年(1625年)に赦免されると、蔵米2000俵を給され御書院番として起用される。 |
| のちに大番頭と、累進を重ねた。この際に蔵米を改め、上総国周准郡・天羽郡、安房国朝夷郡の3郡において |
| 3000石を加増されて、都合5000石を知行することとなった。 |
元禄15年、定賢の子・定安が狂気により改易となり、同族の定堅が名跡を相続し、子孫は500俵の旗本として存続した。
|


|
立花氏は、大友氏の流れを汲む武家。同訓の橘氏とは系統上の関係はない。大友立花氏とも称す。
南北朝時代に、大友貞宗の子の大友貞載が筑前国糟屋郡立花城に拠り立花を称したことより始まる。
以来大友氏の重臣として重きをなしたが、立花鑑載のとき大友義鎮(宗麟)に背いたため、
同じく大友氏支流の戸次鑑連(立花道雪)により攻め滅ぼされ、鑑載の子・立花親善の代で断絶した。
立花宗茂は斜陽の大友氏を支え島津氏との戦いに活躍し、豊臣秀吉の九州征伐の後、筑後国柳川に
13万2000石を与えられた。 |
立花 宗茂(たちばな むねしげ)
| 永禄10年(1567年)11月18日、大友氏の重臣・吉弘鎮理(のちの高橋紹運)の長男として生まれたとされる |
| 関ヶ原の戦いでは、その直前に徳川家康から法外な恩賞を約束に東軍に付くように誘われたが、 |
| 宗茂は「秀吉公の恩義を忘れて東軍側に付くのなら、命を絶った方が良い」と言い拒絶した。 |
| 石田三成率いる西軍に属し、伊勢方面に進出する。 |
| 大坂城に退いた後、宗茂は城に籠もって徹底抗戦しようと総大将の毛利輝元に進言したが、輝元はその |
| 進言を容れずに徳川家康に恭順したため、宗茂は自領の柳川に引き揚げた。開城後は改易されて浪人となる。 |
| その器量を惜しんで加藤清正や前田利長から家臣となるように誘われるが宗茂はこれを謝絶した。 |
| 宗茂はこれを謝絶した。そこで清正は家臣にすることを諦め、食客として遇したという。江戸に下った宗茂は本多忠勝の世話で、 |
| 由布惟信、十時連貞など従者らとともに高田の宝祥寺を宿舎として蟄居生活を送り始め、慶長9年(1604年)忠勝の |
| 推挙で江戸城に召し出される。宗茂の実力をよく知っていた将軍・徳川家康から幕府の御書院番頭(将軍の親衛隊長)として |
| 5,000石を給されることになり、まもなく嫡男・徳川秀忠の御伽衆に列せられて陸奥棚倉に1万石を与えられて大名として復帰した。 |
| 大坂夏の陣は2代将軍・徳川秀忠の麾下に列してその軍師参謀を兼ね警固を担当し、毛利勝永と交戦して |
| 元和6年、幕府から旧領の筑後柳川10万9,200石を与えられ、関ヶ原に西軍として参戦し一度改易されてから |
| 1 |
棚倉藩 |
外様 1万石→2.55万石→3.5万石 陸奥国
1.立花宗茂(むねしげ) 従四位下 左近将監、侍従
|
| 2 |
柳河藩
立花家 |
外様 10.9万石 筑後国 (1620年 ~ 1871年)
| 1.宗茂(むねしげ) 〔従四位下、左近将監・侍従〕 大友氏の重臣・吉弘鎮理(のちの高橋紹運)の長男 |
| 2.忠茂(ただしげ) 〔従四位下、左近将監・侍従〕 |
立花宗茂の弟 直次の四男 |
| 3.鑑虎(あきとら) 〔従四位下、左近将監・侍従〕 |
忠茂の四男 |
| 4.鑑任(あきたか) 〔従四位下、飛騨守〕 |
鑑虎の次男 |
| 5.貞俶(さだよし) 〔従四位下、飛騨守〕 |
茂高の子 |
| 6.貞則(さだのり) 〔従四位下、飛騨守〕 |
貞俶の次男 |
| 7.鑑通(あきなお) 〔従四位下、左近将監・侍従〕 |
貞俶の三男 |
| 8.鑑寿(あきひさ) 〔従四位下、左近将監・侍従〕 |
鑑通の五男 |
| 9.鑑賢(あきかた) 〔従四位下、左近将監〕 |
鑑一の長男 |
| 10.鑑広(あきひろ) 〔夭折のため官位官職なし〕 |
鑑賢の長男 |
| 11.鑑備(あきのぶ) 〔従四位下、左近将監〕 |
鑑賢の次男 |
| 12.鑑寛(あきとも) 〔従二位、左近将監・少将・侍従〕 |
鑑寿の次男 |
廃藩置県
江戸藩邸は上屋敷が下谷御徒町にあり、中屋敷と下屋敷は浅草鳥越にあった。
|
|
立花 直次(たちばな なおつぐ
高橋鎮種(紹運)の次男で、初めは高橋姓を名乗った。立花宗茂の実弟。元亀3年(1572年)生まれた。はじめ、父・鎮種(紹運)や
兄・統虎(宗茂)とともに大友氏に仕える。豊臣秀吉による九州征伐後は、兄と共に豊臣氏の直臣となり、
天正15年(1587年)6月25日、筑後国三池郡江浦に1万8,000石の所領を与えられた。
慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで兄と共に石田三成の西軍に与して、伏見城の戦い、大津城の戦いなどに出陣したので、
戦後に改易されて失領、慶長18年(1613年)1月28日に家康に拝謁を許される。慶長19年(1614年)10月9日に常陸国筑波郡内の
柿岡5,000石を与えられて旗本となった。この時に家号を高橋より、立花に改めた。11月から始まる大坂の陣にも出陣して功があった。
立花 種次(たちばな たねつぐ)
立花直次の長男として、慶長9年(1604年)8月に生まれた。高橋紹運は祖父。立花宗茂は伯父で、宗茂の養嗣子忠茂は実弟にあたる。
将軍徳川秀忠に初めて拝謁し、11月に常陸国柿岡藩5,000石の遺領の継承を許された。
元和7年(1621年)1月10日、5,000石を加増されて合計1万石とされた上に、父の旧領である筑後国三池郡のうち1万石に移封された。
これが三池藩となる。柳河藩の立花氏とは一族であるが、互いに独立した藩であり、同藩は柳河藩のの支藩ではない。
| 1 |
三池藩
立花家 |
外様 1万石 筑後国 (1621年~1806年、1868年~1871年)
| 1.種次(たねつぐ)〔従五位下、主膳正〕 |
立花宗茂の弟・直次の長男 |
| 2.種長(たねなが)〔従五位下、和泉守〕 |
種次の長男 |
| 3.種明(たねあきら)〔従五位下、主膳正〕 |
種長の長男 |
| 4.貫長(つらなが)〔従五位下、出雲守〕駿府加番 |
種明の長男 |
| 5.長煕(ながひろ)〔従五位下、和泉守〕 |
貫長の長男 |
| 6.種周(たねちか)〔従五位下、出雲守 若年寄〕 |
長煕の次男 |
| 7.種善(たねよし)〔従五位下、豊前守〕→陸奥下手渡へ |
種周の四男 |
文化2年(1805年)12月、幕閣での政争に敗れた父の隠居により、跡を継いだ。しかし、種周が若年寄在任中に幕府の
機密情報を漏洩させたということから、さらに罪を問われて、文化3年(1806年)6月5日に陸奥下手渡に移封された。
|
| 2 |
下手渡藩
立花家 |
外様 1万石 陸奥国 (1806年~1868年)
| 1.種善(たねよし)〔従五位下、豊前守〕 |
|
| 2.種温(たねはる)〔従五位下、主膳正 老中格〕 |
種善の長男 |
| 3.種恭(たねゆき)→三池藩へ |
花種道(立花種周の五男)の長男 |
|
| 3 |
三池藩
立花家 |
外様 1万石 筑後国
1.種恭(たねゆき)〔従二位、出雲守〕
廃藩置県 |
| |
 |
 |
| |
立花 宗茂 |
立花忠茂 |
|

 |
宗氏(そうし)はかつて対馬国を支配した守護・戦国大名。惟宗氏の支族だが、室町時代中期頃より
平知盛を祖とする桓武平氏を名乗るようになった。
12世紀頃に対馬国の在庁官人として台頭し始め、現地最大の勢力阿比留氏を滅ぼし、対馬国全土を
手中に収める。惟宗氏の在庁官人が武士化するさいに苗字として宗を名乗りだしたことが古文書からうかがえる。
元寇の際には、元及び高麗の侵攻から日本の国境を防衛する任に当たり、当主宗助国が討ち死にするが、
その後も対馬国内に影響力を保った。
|
宗 義智(そう よしとし)
永禄11年(1568年)、宗家第15代当主宗将盛(まさもり)の四男(異説として五男)として生まれる。
天正7年(1579年)1月に義調の養子となって家督を継ぎ、宗家の当主となった(天正8年(1580年)相続説もある)。
天正15年(1587年)5月、隠居していた養父・義調が当主として復帰したため、義智は家督を義調に返上することとなった。
同年に豊臣秀吉による九州征伐が始まったためであり、義智は義調と共に秀吉に従ったため対馬国一国を安堵された。
その後義智は5,000人の軍勢を率いて天正20年(1592年)4月12日に対馬北端の大浦を出港し釜山に上陸する。
翌13日に総攻撃をかけて攻略した。義智は小西行長らとともに釜山を経て帰国を果たし、前後7年に及ぶ朝鮮出兵は終結した。
関ヶ原の戦いで西軍に属したが、宗氏が持つ朝鮮との取引を重視され、本領を安堵された。後年、朝鮮との国交回復に
尽力した功績が認められ、国主格・十万石格の家格を得、朝鮮と独占的に交易することも認められた。
江戸時代は対馬府中藩の藩主となり、参勤交代で3年に一度江戸に出仕することとされ、江戸に屋敷を構え対馬府中(厳原)との間を
大名行列を仕立てて行き来した。
|
| |
対馬
府中藩
宗 氏 |
外様 2万石格 → 10万石格外様 対馬国
| 1.義智(よしとし) |
従四位下、対馬守・侍従 |
宗将盛の四男 |
| 2.義成(よしなり) |
従四位下、対馬守・侍従 |
宗義智の長男 |
| 3.義真(よしざね) |
従四位下、対馬守・侍従 |
宗義成の長男 |
| 4.義倫(よしつぐ) |
〔従四位下、右京 大夫・侍従〕 |
宗義真の次男 |
| 5.義方(よしみち) |
従四位下、対馬守・侍従 |
宗義真の四男 |
| 6.義誠(よしのぶ) |
従四位下、対馬守・侍従 |
宗義真の七男 |
| 7.方熈(みちひろ) |
従四位下、対馬守・侍従 |
宗義真の九男 |
| 8.義如(よしゆき) |
従四位下、対馬守・侍従 |
宗義誠の長男 |
| 9.義蕃(よしあり) |
従四位下、対馬守・侍従 |
宗義誠(旧名:氏江方誠)の次男 |
| 10.義暢(よしなが) |
従四位下、対馬守・侍従 |
義如の三男 |
| 11.義功(よしかつ) |
〔官位官職無し〕幼名:猪三郎 |
義暢の四男 |
| 12.義功(よしかつ) |
従四位下、対馬守・侍従幼名:富寿(猪三郎の弟) |
義暢の六男 |
| 13.義質(よしかた) |
従四位下、対馬守・侍従 |
義功(富寿)の次男 |
| 14.義章(よしあや) |
従四位下、対馬守・侍従 |
義質の長男 |
| 15.義和(よしより) |
従四位下、対馬守・侍従 |
義質の次男 |
| 16.義達(よしあきら) |
版籍奉還の後、重正(しげまさ)と改称 |
義和の三男 |
廃藩置県
|
江戸藩邸は向柳原に上屋敷、水道橋外に中屋敷、三ノ輪に下屋敷があった。
| |
 |
| |
宗 義智 |
|
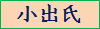
 |
小出氏の出自は藤原南家二階堂氏流とされ、本貫の地は信濃伊那とされる。安土桃山時代、
江戸時代に大名となった。小出氏の子孫が尾張中村に流れてきたものとされるが定かではない。
小出秀政が豊臣秀吉の母方の縁者として大名に取り立てられ、秀吉没後の関ヶ原の戦いでは
西軍に属したが、秀政の一子遠江守秀家が東軍に属したため改易を免れ、江戸時代も大名として存続した。
|
小出 秀政(こいで ひでまさ)
| 秀吉に仕え、後に和泉岸和田に3万石の所領を領した。秀吉の死の直前に、遺児秀頼の補佐を秀吉から依頼された。 |
| その経緯から、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは長男の吉政と共に西軍に与して、東軍に与した細川幽斎の守る |
| 丹後国田辺城を攻撃した、そのため、本来ならば戦後に処罰されるはずであったが、次男の秀家が東軍に属して関ヶ原本戦で |
| 活躍したため、所領を安堵された |
| 小出 吉政(こいで よしまさ) |
小出秀政(岸和田藩初代藩主)の長男。弟の秀家が東軍に属して関ヶ原本戦で活躍したため、戦後に6万石の所領を安堵された。
慶長8年(1603年)に秀家が父に先立って病死し、翌年に秀政が死去すると、吉政は父の遺領である岸和田城3万石に移り、
長男の吉英が出石を領することになった。
|
| 1 |
岸和田藩
小出氏 |
外様 3万石→5万石 和泉国 (1600年 - 1619年)
| 1.秀政(ひでまさ)〔従五位下、播磨守〕 |
織田氏の家臣小出政重(正重)の長男 |
| 2.吉政(よしまさ)〔従五位下、播磨守〕 |
秀政の長男 |
| 3.吉英(よしひさ)〔従五位下、大和守〕加増により50000石 |
吉政の長男 |
|
| 2 |
出石藩
小出氏 |
外様 5万石→6万石 (1600年 - 1696年) 但馬国
| 1.吉政(よしまさ)〔従四位下、信濃守〕 和泉国岸和田藩へ移封 |
| 2.吉英(よしふさ)〔従五位下、大和守〕 岸和田藩を継承 |
| 3.吉親(よしちか)〔従四位下、信濃守〕 丹波国園部藩へ移封 |
吉政の次男 |
| 4.吉英(よしふさ)〔従五位下、大和守〕 岸和田藩より5万石で再封 |
| 5.吉重(よししげ)〔従五位下、修理亮〕 |
吉英の次男 |
| 6.英安(ふさやす)〔従五位下、備前守〕 |
吉重の長男 |
| 7.英益(ふさえき)〔従五位下、大和守〕 |
英安の長男 |
| 8.英長(ふさなが)〔従五位下、播磨守〕 |
旗本・小出英信の次男 |
| 9.英及(ふさのぶ)〔夭折のため官位官職なし〕 |
英長の長男 |
英及の死去は元禄9年(1696年)10月22日となっている。わずか数え年の3歳(満1歳)で嗣子が
いるはずもなく、小出家嫡流は断絶した。
|
小出 吉親(こいで よしちか
但馬出石藩第2代藩主・小出吉政の次男,慶長18年(1613年)に父・吉政が没すると、兄・吉英は和泉国岸和田藩に移封されたため、
吉親が但馬出石3万石を領することとなる。しかし、元和5年に兄・吉英が出石に再封されたため、新たに丹波国に園部藩を
2万8000石で立藩した。
| |
園部藩
小出氏 |
外様 2.98万石→2.5万石→2.4万石。丹波国
| 1.小出吉親(よしちか |
従四位下、信濃守 但馬出石藩第2代藩主・小出吉政の次男 |
| 2.小出英知(ふさとも |
従五位下、信濃守 |
吉親の長男 |
| 3.小出英利(ふさとし |
従五位下、伊勢守 |
英知の長男 |
| 4.小出英貞(ふささだ |
従五位下、信濃守 |
英利の長男 |
| 5.小出英持(ふさよし |
従五位下、信濃守、伊勢守 |
英貞の長男 |
| 6.小出英常(ふさつね |
従五位下、伊勢守 |
英持の次男 |
| 7.小出英?(ふさたけ |
従五位下、信濃守、伊勢守 |
英常の長男 |
| 8.小出英発(ふさおき |
従五位下、伊勢守、播磨守 |
英?の次男 |
| 9.小出英教(ふさのり |
従五位下、加賀守、信濃守 |
肥前大村藩主・大村純昌の八男 |
| 10.小出英尚(ふさなお |
従五位下、伊勢守 |
英教の長男 |
廃藩置県
|
小出 秀家(こいで ひでいえ)
小出秀政の次男。母・栄松院は大政所の妹で、豊臣秀吉の従弟にあたる。吉政は同母兄、異母弟に小出三尹などがいる。兄同様、
幼少の頃より秀吉に馬廻として仕える。慶長5年(1600年)、徳川家康が上杉景勝討伐に向かった際(会津征伐)、父の名代として
兵300を率いてこれに加わった。父や兄が三成率いる西軍に加勢したことを知るが、家康にそのまま従って東軍として
関ヶ原の戦いに参加した。西軍についた父や兄の所領安堵を許した。
慶長8年、秀家は37歳の若さで大坂で病死した。法名は了俊。家康はその早すぎる死を惜しんで改易にはせず、弟三尹が
養子となって家督を相続するのを許した。その翌年に秀政が死去すると、家康は吉政に命じて1万石を割かせ、秀家の後継である
三尹に分けるように命じ、陶器藩として立藩させた。
|
| |
陶器藩
小出氏 |
外様 1万石 和泉国
| 1.小出 三尹(みつただ |
従五位下、大隅守 |
小出秀政の四男で兄秀家の養子 |
| 2小出 有棟(ありむね) |
従五位下、大隅守 |
小出三尹の長男 |
| 3.小出 有重(ありしげ |
従五位下、大隅守 |
有棟の長男 |
| 4.小出 重興(しげおき |
|
有重の長男 |
重興には実子が無く、死に臨んで弟の重昌を養子にして跡を継がせようとしたが、幕府から許可が出る前に
重興が死去し、陶器藩は無嗣子を理由に改易となった。
なお、陶器藩小出氏は、後に重興の叔父(有棟の四男)・小出有仍(ありより)が別家の有棟の弟小出尹明の養子として
跡を継ぎ、5000石の旗本として幕末で続く
|
|
| |
 |
 |
| |
宗家2代 小出吉政 |
園部藩祖 小出吉政 |
|
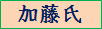
 |
加藤嘉明系
加藤氏の初代と思われるのは源頼義に仕えた武士藤原景道で、加賀介となったことから加賀の藤原を略して
「加藤」を称するようになったとされる。景道の孫といわれる加藤景廉は源頼朝の挙兵に参加し、平家が滅亡して
鎌倉幕府が成立すると鎌倉御家人となった。
その末裔としては、美濃の遠山氏やその係累である加藤光泰系の加藤氏が挙げられるが、なかでも異色の
経歴を持つ者は賤ヶ岳の七本槍の一人加藤嘉明である。嘉明の祖父加藤朝明は、元来は甲斐の武田氏の
家臣であったが、何らかの事情があり、三河国に移住し、徳川家康の祖父松平清康、父松平広忠に仕えた。
その子、加藤教明は三河の一向一揆に加担し、松平氏を退去し、尾張の織田家に仕え、
後の豊臣秀吉に見出されたという。 |
戦国時代
加藤光泰系:加藤光泰は豊臣秀吉に仕え、甲斐24万石を領した。光泰の子の加藤貞泰は伊予大洲藩の初代藩主となった。
加藤嘉明系:伊予松山藩20万石の大名。嘉明の子、加藤明成は陸奥会津藩40万石の大名となったが、御家騒動が起こり改易された。
加藤 嘉明(かとう よしあき)
| 三河国の松平家康の家臣である加藤教明(岸教明)の長男として生まれる。生まれた年の三河一向一揆で、 |
| 父が一揆側に属して家康に背き、流浪の身となったため、嘉明も放浪する。 |
| やがて尾張国で、加藤景泰(加藤光泰の父)の推挙を受けて羽柴秀吉(豊臣秀吉)に見出され、 |
| その小姓として仕えるようになる。 |
| 賤ヶ岳の戦いで、福島正則、加藤清正らと共に活躍し、賤ヶ岳七本槍の一人に数えられた。 |
| 慶長3年(1598年)8月に秀吉が死去すると帰国し、豊臣政権における五奉行の石田三成らと五大老の |
| 徳川家康の争いでは家康派に属する。戦後、その功績により伊予松山20万石に加増移封される。 |
| 1 |
伊予松山藩
|
外様 20万石 伊予国 (1600年 - 1627年)
1.嘉明(よしあき)〔従四位下、左馬頭〕 加藤教明(岸教明)の長男
|
| 2 |
会津藩 |
外様 - 40万石 岩代国 (1627年 - 1643年)
| 1.嘉明(よしあき) 〔従四位下、左馬頭〕 |
|
| 2.明成(あきなり)従四位下、式部少輔。侍従 |
嘉明の長男 |
堀主水を始めとする反明成派の家臣たちが出奔すると、これを追跡して
殺害させるという事件(会津騒動)を起こし、そのことを幕府に咎められて改易された。
|
| 3 |
水口藩
|
加藤嘉明の孫で、外様の石見吉永藩(1万石)藩主・加藤明友が祖父と自身の功により1万石の加増を受け、
2万石で近江国水口城主となり立藩。
外様 2万石 近江国
| 1.明友(あきとも)〔従五位下・内蔵介〕 |
明成の庶長子 |
| 2.明英(あきひで)〔従五位下・越中守・若年寄〕 |
明友の長男 |
|
|
| 4 |
壬生藩
|
外様 (譜代格) 2.5万石 下野国
| 1.加藤明英(あきひで) 従五位下 越中守 |
明友の長男 |
| 2.加藤嘉矩(よしのり) 従五位下 和泉守 |
加藤明友の三男・明治の長男 |
|
| 5 |
水口藩
|
外様 (譜代格) 2.5万石 近江国
| 1.嘉矩(よしのり) 〔従五位下・和泉守〕 |
加藤明友の三男・明治の長男 |
| 2.明経(あきつね) 〔従五位下・伊勢守〕 |
嘉矩の長男 |
| 3.明煕(あきひろ) 〔従五位下・豊後守〕 |
明教の次男 |
| 4.明堯(あきたか) 〔従五位下・能登守〕 |
摂津尼崎藩主・松平忠名の次男 |
| 5.明陳(あきのぶ) 〔従五位下・能登守〕 |
明煕の次男 |
| 6.明允(あきまさ) 〔従五位下・能登守〕 |
明陳の長男 |
| 7.明邦(あきくに) 〔従五位下・能登守〕 |
明允の長男 |
| 8.明軌(あきのり) 〔従五位下・越中守〕 |
明邦の次男 |
| 9.明実(あきざね) 〔正三位・能登守〕 |
明邦の七男 |
廃藩置県
|
吉永藩: 外様 1万石 石見国
加藤明友が近江水口藩に転封する前に治めていた藩。石見国安濃郡吉永(大田市)周辺で1万石を領有し、吉永に陣屋を構えた。
父・明成が陸奥会津藩40万石を収公されたが、祖父・嘉明の勲功により家名存続を許され、6月に立藩した。
明成の死後、第2代藩主の座は明友が相続し、天和2年(1682年)6月、明友は1万石加増の2万石で、
水口藩に転封となり、廃藩となって天領(石見銀山領)となった。
|
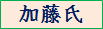
 |
加藤光泰系
加藤 光泰(かとう みつやす)
天文6年(1537年)、美濃国多芸郡今泉村橋詰庄で加藤景泰の長男として生まれた。はじめ斎藤龍興に仕えて
勇将として知られたが、稲葉山城が陥落して斎藤氏が流浪すると、浪人となって、一旦、近江国に逃れた。
尾張国の織田信長は、美濃衆との戦いで光泰の活躍を目に留めていて、木下秀吉(後の豊臣秀吉)の仲介で
拝謁が許され、召し抱えられて秀吉の家臣とされた。天正13年(1585年)には大垣城主2万石
その後甲府24万石を与えられる。西生浦の陣中で発病、病死した。享年57
三成が家康打倒のために挙兵した関ヶ原の戦いにおいては、加藤貞泰は反三成勢力となる徳川方に属した。
この戦いで貞泰は本領安堵、後に伊予国大洲藩初代藩主となった。 |
| |
大洲藩
|
外様 6石 伊予国
| 1.貞泰(さだやす) 〔従五位下、左衛門尉〕 |
光泰の次男 |
| 2.泰興(やすおき) 〔従五位下、出羽守〕 |
貞泰の長男 |
| 3.泰恒(やすつね) 〔従五位下、遠江守〕 |
加藤泰義(第2代藩主・加藤泰興の長男)の次男 |
| 4.泰統(やすむね) 〔従五位下、出羽守〕 |
泰恒の次男 |
| 5.泰温(やすあつ) 〔従五位下、遠江守〕 |
泰統の長男 |
| 6.泰?(やすみち) 〔従五位下、出羽守〕 |
旗本加藤泰都(第3代藩主加藤泰恒の六男)の長男 |
| 7.泰武(やすたけ) 〔従五位下、遠江守〕 |
泰温の長男 |
| 8.泰行(やすゆき) 〔従五位下、出羽守〕 |
泰?の次男 |
| 9.泰候(やすとき) 〔従五位下、遠江守〕 |
泰?の四男 |
| 10.泰済(やすずみ) 〔従五位下、遠江守〕 |
泰候の長男 |
| 11.泰幹(やすもと) 〔従五位下、遠江守〕 |
泰済の長男 |
| 12.泰祉(やすとみ) 〔従五位下、出羽守〕 |
泰幹の長男 |
| 13.泰秋(やすあき) 〔従五位下、遠江守〕 |
泰幹の四男 |
廃藩置県
|
支藩
大洲藩の支藩である。藩庁として新谷(現・大洲市内)に新谷陣屋が置かれた。
元和9年(1623年)、大洲藩2代藩主・加藤泰興の弟・直泰が幕府より1万石分知の内諾を得て成立した。
藩内分知は本来は陪臣の扱いであるが、新谷藩は幕府より大名と認められた全国唯一の例である。
| |
新谷藩
|
外様 1万石 伊予国 (1623年 - 1871年)
| 1.直泰(なおやす)〔従五位下、織部正〕 |
貞泰の次男 |
| 2.泰觚(やすかど)〔従五位下、出雲守〕 |
泰義の長男 |
| 3.泰貫(やすつら)〔従五位下、大蔵少輔〕 |
泰觚の長男 |
| 4.泰広(やすひろ)〔従五位下、織部正〕 |
大洲藩主・加藤泰恒の七男 |
| 5.泰宦(やすのぶ)〔従五位下、近江守〕 |
泰広の長男 |
| 6.泰賢(やすまさ)〔従五位下、出雲守〕 |
泰宦の長男 |
| 7.泰儔(やすとも)〔従五位下、山城守、長門守〕 |
泰賢の長男 |
| 8.泰理(やすただ)〔従五位下、大蔵少輔〕 |
泰儔の長男 |
| 9.泰令(やすのり)〔従五位下、山城守、出雲守〕 |
泰理の長男 |
廃藩置県
|
|

  |
道長流加藤氏
尾張愛知郡中村より起こった。藤原道長流(藤原長家の御子左家の流れを汲む)とはされているが、
真偽の程は定かではない。 |
加藤 清正(かとう きよまさ)
| 安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将・大名。肥後国熊本藩初代藩主。 |
| 永禄4年(1561年)刀鍛冶の加藤清忠の子として尾張国愛知郡中村(現在の名古屋市中村区)に生まれる。 |
| 父が清正の幼いときに死去したため、母とともに津島に移る。母が羽柴秀吉の生母である大政所の従姉妹 |
| であったことから、天正元年(1573年)、近江長浜城主となったばかりの秀吉に小姓として仕え、 |
| 秀吉の親戚として将来を期待され、秀吉に可愛がられた。清正もこれに応え、生涯忠義を尽くし続けた。 |
| 慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは九州に留まり、黒田如水とともに家康ら東軍に協力して小西行長の |
| 宇土城、立花宗茂の柳川城などを開城、調略し、九州の西軍勢力を次々と破った。 |
| 戦後の論功行賞で、小西旧領の肥後南半を与えられ52万石の大名となる。 |
|
| |
熊本藩
|
外様 52万石 肥後国 (1588年~1632年)
| 1.清正(きよまさ)〔従四位下、肥後守・侍従〕 |
|
|
| 2.忠広(ただひろ)〔従四位下、肥後守・侍従〕 |
改易 |
加藤清正の三男 |
11歳の若年であったため、重臣による合議制となり、藤堂高虎が後見人を務めたと言われている。
家臣団を完全に掌握することができず、牛方馬方騒動など重臣の対立が発生し、政治は混乱したと言われている。
また、細川忠興は周辺大名の情報収集に努めていたが、忠広の行状を「狂気」と断じて警戒していた
寛永9年、江戸参府途上、品川宿で入府を止められ、池上本門寺にて上使稲葉正勝より改易の沙汰があり
出羽庄内藩主・酒井忠勝にお預けとなった。
|
|
|
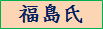
 |
桓武平氏が出自との話もあるが、源姓説も藤原姓説もあるため、詳細は不明。なお、彼の父とされる
市兵衛(正信)は尾張国のただの桶屋であったといわれる。
福島氏(ふくしまし)は、日本の氏族。櫛間・九島・久島氏とも。美濃国発祥で摂津源氏山県氏の流れを
汲むと言う。後に遠江国に移動し、福島正成の代に今川氏に仕えていた。高天神城を中心にし勢力を
広げたが、花倉の乱において今川義元に敵対し敗北し、残党は岡部親綱、小笠原春義(春茂)に
討滅され、一部は甲斐国に逃げ延びたが武田信虎に討たれ没落したとされる
|
福島氏(ふくしまし)
| 安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将・大名。賤ヶ岳の七本槍、七将の一人永禄4年、福島正信の長男として |
| 尾張国海東郡(現在の愛知県あま市)で生まれる。母が豊臣秀吉の叔母だったため、その縁から幼少より小姓として秀吉に |
| 仕え、天正6年(1578年)に播磨三木城の攻撃で初陣を飾る。始めの禄高は200石であった。 |
| 賤ヶ岳の戦いのときは一番槍・一番首として敵将・拝郷家嘉を討ち取るという大功を立てて賞され、七本槍の中でも突出して |
| 5,000石を与えられた(他の6人は3,000石)。秀吉の死後武勇に優れた正則は文治派の石田三成らと朝鮮出兵を契機として |
| その仲が一気に険悪になり、慶長4年(1599年)の前田利家の死後、朋友の加藤清正と共に三成を襲撃するなどの事件も起こしている。 |
| 慶長4年(1599年)の前田利家の死後、朋友の加藤清正と共に三成を襲撃するなどの事件も起こしている。 |
| 東軍の勝利に貢献第一と目された正則は西軍総大将・毛利輝元からの大坂城接収にも奔走し、 |
| 戦後安芸広島と備後鞆49万8,200石の大封を得た。(広島藩) |
| 1 |
広島藩
福島家 |
外様 49.8万石 安芸国 (1600年 - 1619年)
1.正則(まさのり)〔従三位・左衛門大夫、右少将、侍従、参議〕
家康死後まもなくの元和5年(1619年)、台風による水害で破壊された広島城の本丸・二の丸・三の丸及び
石垣等を幕府に無断で修理したことが武家諸法度違反に問われる。安芸・備後50万石を没収、
信濃国川中島四郡中の高井郡と越後国魚沼郡の4万5,000石(高井野藩)に減封・転封される。
|
| 2 |
高井野藩
福島家 |
外様。4.5万石→2万石 信濃国 (越後国魚沼郡2万5000石)
| 1.正則(まさのり) |
従四位下、従三位、参議 |
| 2.忠勝(ただかつ) |
備後守、従四位下 |
正則の次男 |
父に先立って死去した。この時、正則は悲しみのあまり、越後国魚沼郡2万5,000石を幕府に返上している。
初名は正勝だが、2代将軍徳川秀忠の諱を賜って、忠勝と名乗った。
寛永元年(1624年)に正則も64歳で死去する。このとき、家臣団が正則の遺体を幕府の検使である
堀田正吉(正利)が到着する前に火葬してしまったことから、またも法度違反であるとして、残りの2万石も
没収されてしまった。
三男の正利が3,000余石の旗本として福島氏を再興したが、のち嗣子なく断絶した。しかしその後、京に住んでいた
忠勝の子・正長の長男で孫にあたる正勝が召し出され、小姓組番頭として仕え、以後福島氏は2,000石の
旗本として存続した 福島家は大名として改易となる。
|
豊臣秀吉の子飼
の武将 両家とも改易 |
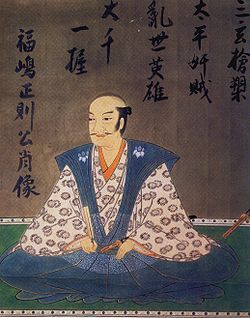 |
 |
| |
福島 正則 |
加藤清正 |
|
|
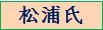
 |
源融流嵯峨源氏・渡辺綱の系譜
中世には肥前の水軍の松浦党の惣領氏。
諸般の松浦家系図によると嵯峨源氏渡辺氏の祖の源綱(渡辺綱)の孫の源久(渡辺久、松浦久)を
祖とするとされる。松浦氏は、渡辺綱にはじまる渡辺氏を棟梁とする摂津国の滝口武者(大内守護
(天皇警護))の一族にして水軍として瀬戸内を統括した渡辺党の分派である。
|
安倍宗任の系譜
| 平家物語・百二十句本(国会本)剣の巻によれば、安倍宗任が前九年の役で敗れたあと、治暦三年(1067年)に太宰府に |
| 流されるが、子孫繁栄して、松浦党となった。この伝えは、百練抄、前太平記、歴代鎮西要略でも記されている。 |
| 平戸松浦氏 |
| 松浦党のうち下松浦党の本来の嫡流は松浦直の嫡男の松浦清の末裔の一族であるが、松浦氏の数多くの傍流のうち、 |
| 松浦直の五男の峯被の子孫から平戸を本拠とする平戸松浦家(平戸氏)が興った。 |
| 松浦隆信の代には、惣領家や上松浦党をも従えて松浦半島を統一する戦国大名となった。 |
| 隆信とその子の松浦鎮信は豊臣秀吉に従い豊臣政権の下で近世大名としての道を確立した。 |
|
|
松浦 鎮信(まつら しげのぶ)
| 松浦隆信の長男。戦国時代から江戸時代前期にかけての大名。平戸の松浦氏第26代当主。 |
| 肥前国平戸藩初代藩主。永禄11年(1568年)、父から家督を譲られた。この頃、肥前国では龍造寺隆信の勢力が台頭し、 |
| 鎮信もその膝下に組み込まれることを余儀なくされたが、天正12年(1584年)に龍造寺隆信が戦死すると、再び独立した。 |
| 天正15年、父と共に豊臣秀吉の九州平定に参陣して所領を安堵されている。関ヶ原の戦いでは、本国に在国していた |
| 鎮信は肥前の神集島で開かれた去就会議に参加して東軍に与することを決定した。 |
| |
平戸藩
|
外様 6.32万石→6.17万石→5.17万石→6.17万石 肥前国
| 1.鎮信(しげのぶ)〈法印〉〔従四位下、肥前守〕 |
|
| 2.久信(ひさのぶ)〈泰岳〉〔従五位下、肥前守〕 |
鎮信の長男 |
| 3.隆信(たかのぶ)〈宗陽〉〔従五位下、壱岐守〕 |
久信の長男 |
| 4.鎮信(しげのぶ)〈天祥〉〔従五位下、肥前守〕分知により61,700石 |
隆信の長男 |
| 5.棟(たかし)〈雄香〉〔従五位下、壱岐守 奏者番・寺社奉行〕分知により51,700石 鎮信の長男 |
| 6.篤信(あつのぶ)〈松英〉〔従五位下、肥前守〕 |
鎮信の四男 |
| 7.有信(ありのぶ)〈等覚〉〔従五位下、壱岐守〕 |
篤信の長男 |
| 8.誠信(さねのぶ)〈安靖〉〔従五位下、肥前守〕 |
篤信の次男 |
| 9.清(きよし)〈静山〉〔従五位下、壱岐守〕 松浦政信(松浦誠信の三男)の長男 |
| 10.熈(ひろむ)〈観中〉〔従五位下、肥前守〕 |
清の三男 |
| 11.曜(てらす)〈諦乗〉〔従五位下、壱岐守〕 |
熈の長男 |
| 12.詮(あきら)〈心月〉〔従五位下、肥前守〕支藩併合により61,700石 松浦秋(藩主・松浦熈の三男)の長男 |
廃藩置県
|
支藩 平戸藩5代藩主棟の弟・昌は1万石を分与され、平戸新田藩が立藩した。
| |
平戸
新田藩 |
外様 1万石 肥前国
| 1.昌(まさし) |
|
平戸藩第4代藩主・松浦鎮信の次男 |
| 2.邑(さとし) |
従五位下、豊後守 |
昌の長男 |
| 3.鄰(ちかし) |
従五位下、豊後守 |
邑の子 |
| 4.到(いたる) |
従五位下。豊後守 |
平戸藩第6代藩主・松浦篤信の六男 |
| 5.宝(たかし) |
従五位下。大和守。伊予守。大隅守 |
到の長男 |
| 6.矩(ただし) |
従五位下、大和守、豊後守 |
宝の長男 |
| 7.良(ちかし) |
従五位下、織部正 松浦義信(平戸藩6代藩主松浦篤信の十男)の子 |
| 8.晧(ひかる) |
従五位下、大和守 |
清の四男 |
| 9.脩(ながし) |
従五位上。左近将監 |
晧の長男 |
明治3年(1870年)9月に本家の平戸藩と合併したため、平戸新田藩は廃藩となった。廃藩置県
|
|
|
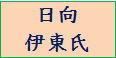
 |
平安時代末期から鎌倉時代にかけて伊豆国田方郡伊東荘(現静岡県伊東市)を本貫地としていた豪族。
藤原南家・藤原為憲の流れを汲む工藤氏の一支族。
一族である工藤祐経の子孫が日向国へ下向して戦国大名の日向伊東氏・飫肥藩藩主となり、
伊東祐親の子孫が尾張国岩倉に移り住んで備中岡田藩主となる。 |
源頼朝と伊東祐親
| 源頼朝は平治元年(1159年)の平治の乱で父源義朝が敗死した事により、14歳で伊豆国へ流罪となり、伊東祐親は |
| 在地豪族としてその監視の任にあたっていた。頼朝と祐親の三女八重姫が通じ、千鶴という男子をもうけると |
| 子が3歳になった時に祐親が帰郷して事を知り激怒、平家への聞こえを恐れ、千鶴を川底へ投げ捨てて殺害する。 |
鎌倉時代から室町時代
| 祐経の子祐時は伊東を称し、その後子孫は全国に広まった。主だったものでは、祐時の子の祐光の子孫が日向国へ |
| 下向してのちの日向伊東氏となり、現地で勢力を誇った。 |
| 伊東祐親の子孫の一派は尾張国岩倉に移り住んでのち、その子孫が織田信長や豊臣秀吉・秀頼に仕え、 |
| 江戸時代には備中国で大名となった。この系統を備中伊東氏(または尾張伊東氏)と呼称する。 |
日向 伊東氏 安土桃山時代から江戸時代
| 日向伊東氏の伊東義祐・祐兵親子らは薩摩の島津氏に圧されて(伊東崩れ)本領の日向飫肥を追われた。 |
| 祐兵主従は当時織田信長の家臣として播磨にて作戦行動中だった羽柴秀吉(のちの豊臣秀吉)の与力として行動していた |
| その後本能寺の変を経て秀吉の家臣団に組み込まれ、山崎の戦いなどで活躍した後、秀吉による九州征伐にて |
| も戦功を挙げた。九州征伐により島津氏は日向の伊東氏旧領を明け渡し、秀吉の奇跡的とも言える天下取りの過程にて、 |
| 日向伊東氏もまた奇跡的に、十年越しに日向飫肥の旧領に復帰することに成功した。 |
伊東 祐兵(いとう すけたか
| 伊東義祐の3男。永禄11年(1568年)から飫肥城に入り、島津氏と戦う。伊東氏12代当主 |
| 慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは、祐兵は大坂にいた。しかし重病の床に伏していたために |
| 自身は出陣せず、密かに嫡男・祐慶を領国へ送って軍備を整え、さらに黒田孝高を頼って徳川家康に通じた。 |
| |
飫肥藩
おび
|
外様 5.7万石→5.4万石→5.1万石 日向国
| 1.祐兵(すけたけ)〔従五位下、豊後守〕 |
|
| 2.祐慶(すけよし)〔従五位下、修理大夫〕 |
祐兵の長男 |
| 3.祐久(すけひさ)〔従五位下、大和守〕分知により5万4千石 |
祐慶の長男 |
| 4.祐由(すけみち)〔従五位下、左京亮〕分知により5万1千石 |
祐久の長男 |
| 5.祐実(すけざね)〔従五位下、大和守〕 |
祐久の四男 |
| 6.祐永(すけなが)〔従五位下、修理亮〕 |
伊東左門祐信の子 |
| 7.祐之(すけゆき)〔従五位下、大和守〕 |
祐永の九男 |
| 8.祐隆(すけたか)〔従五位下、修理大夫〕 |
祐永の三男 |
| 9.祐福(すけよし)〔従五位下、大和守〕 |
祐隆の長男 |
| 10.祐鐘(すけあつ)〔従五位下、左京亮〕 |
祐福の長男 |
| 11.祐民(すけたみ)〔従五位下、修理大夫〕 |
祐鐘の長男 |
| 12.祐丕(すけひろ)〔従五位下、修理大夫〕 |
祐鐘の次男 |
| 13.祐相(すけとも)〔従五位下、右京大夫〕 |
祐民の長男 |
| 14.祐帰(すけより)〔正四位、修理大夫〕 |
祐相の長男 |
廃藩置県
|
|
|
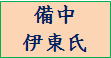
 |
藩主家の備中伊東氏は日向国飫肥藩主家の日向伊東氏と同族である。藩祖・長実は豊臣秀吉・秀頼に
仕えて大坂の陣までも豊臣氏の家臣であった。
関ヶ原の戦いに際し、上方での石田三成挙兵の報をいち早く徳川家康に伝えたとされる。
大坂の陣では子の長昌共々豊臣方として家康に敵対し、大坂城に籠城するも、戦後許された。
|
| |
岡田藩
|
外様 1.0343万石 備中国 (1615年 - 1871年)
| 1.長実(ながざね)〔従五位下、丹後守〕 尾張国岩倉の国人・伊東長久の長男 |
| 2.長昌(ながまさ)〔従五位下、丹後守〕 |
長実の次男 |
| 3.長治(ながはる)〔無冠〕 |
長昌の長男 |
| 4.長貞(ながさだ)〔従五位下、信濃守〕 |
長治の長男 |
| 5.長救(ながひら)〔従五位下、播磨守〕 |
長貞の長男 |
| 6.長丘(ながおか)〔従五位下、若狭守〕 |
長救の長男 |
| 7.長詮(ながとし)〔従五位下、伊豆守〕 |
長丘の三男 |
| 8.長寛(ながとも)〔従五位下、播磨守〕 |
長詮の長男 |
| 9.長裕(ながやす)〔従五位下、若狭守〕 |
長寛の五男 |
| 10.長※(ながとし)〔従五位下、播磨守〕 |
長寛の十五男 |
廃藩置県
|
|
|

 |
戸沢氏は平忠正の子、平維盛より始まり大和国三輪を本拠地とした。その子、平衡盛の代に木曾義仲に
属していたが、その不義を憎み奥州磐手郡滴石庄(岩手県雫石町)に下向した。
明応5年(1496年)に大曲地方への進出をかけて、安東忠季と戦う。
|
戸沢 政盛(とざわ まさもり)
| 天正13年(1585年)、戸沢盛安の長男として生まれる。生母は盛安が鷹狩に出た際に見初めた小古女沢の |
| 百姓・源左衛門の娘。このため身分の低い母を持つ庶子であるため、家督を継ぐ資格がなく、 |
| 父・盛安と叔父の戸沢光盛も死に継嗣がなかったため、戸沢家は断絶の危機に見舞われた。そこで家臣団は |
| 東光坊を斬って盛安の遺児・政盛を奪い取り、至急大坂に上坂させて豊臣秀吉に謁見させ、家督を相続させた |
政盛は鳥居忠政の娘と縁戚を結び、徳川方へ急速に接近していく。関ヶ原の戦いでは東軍に属し、最上氏と共に上杉氏と戦う。
しかし上杉討伐で秋田氏の勢力が増大することを恐れ、消極策に終始する。戦後、この行動が咎められて、
常陸国松岡へ減転封される。徳川氏重臣の鳥居忠政から養子を迎え、自身の娘と縁戚を結ばせた。
慶長19年(1614年)の大坂冬の陣では小田原城の守備、翌20年の大坂夏の陣では江戸城の留守居役を命じられる。
鳥居氏との縁戚により、本来江戸幕府内での扱いは外様大名であるはずの戸沢氏は譜代大名とされた(願譜代)。
元和8年(1622年)、最上氏の改易を受けて、譜代大名鳥居氏の一族として、角館に比較的近い新庄へ加増転封される。
|
|
| 1 |
常陸
松岡藩
|
外様. 4万石 常陸国
| 1.戸沢政盛(まさもり) |
従五位下、右京亮 |
戸沢盛安の長男 |
|
| 2 |
新庄藩
|
外様→譜代 6.82万石→83.2万石 羽前国
| 1.戸沢政盛(まさもり)〈従五位下・右京亮〉 |
| 2.戸沢正誠(まさのぶ)〈従五位下・上総介〉 |
政盛の次男 |
| 3.戸沢正庸(まさつね)〈従五位下・上総介〉 |
戸沢家の家臣・楢岡兵右衛門友清の四男 |
| 4.戸沢正勝(まさよし)〈従五位下・上総介〉 |
正庸の三男 |
| 5.戸沢正諶(まさのぶ)〈従五位下・上総介〉 |
正庸の四男 |
| 6.戸沢正産(まさただ)〈従五位下・上総介〉 |
正諶の長男 |
| 7.戸沢正良(まさすけ)〈従五位下・主計頭〉 |
正諶の次男 |
| 8.戸沢正親(まさちか)〈従五位下・上総介〉 |
3代藩主・正庸の七男・正備の長男 |
| 9.戸沢正胤(まさたね)〈従五位下・右京亮〉 |
正親の長男 |
| 10.戸沢正令(まさよし)〈従五位下・能登守〉 |
正胤の次男 |
| 11.戸沢正実(まさざね)〈従四位下・上総介〉 |
正令の長男 |
廃藩置県
|
|
|


|
清和源氏の足利氏の支流である。三管領の一つ斯波氏の分家にあたる。室町幕府の羽州探題を
世襲できる家柄で、のち出羽国の戦国大名として成長した。最上氏の起源である斯波氏は、
本来足利宗家となるはずだったものの北条氏の介入によって廃嫡され分家した足利家氏を祖とする。
最上義光の妹の義姫は伊達輝宗へ嫁ぎ、伊達政宗を生んでいる。
豊臣秀吉の小田原征伐を機に臣従、本領を安堵され、山形城を居城にして24万石を領する。
関ヶ原の戦いの際は東軍に与し、西軍の雄である上杉景勝の侵攻を退けた
|
最上 義光(もがみ よしあき)
天文15年(1546年)1月1日、第10代当主・最上義守と母・小野少将の娘との間に長男として生まれる。
義光は上杉軍を撃退した功により、攻め取った庄内地方などを加えられ、計57万石を領し、出羽山形藩の初代藩主となった。
| |
山形藩
最上家 |
外様 57万石 羽前国(1600年 - 1622年)
| 1.義光(よしあき)〔従四位上・出羽守、左近衛権少将〕 |
| 2.家親(いえちか)〔従四位・駿河守、侍従〕 |
義光の次男 |
| 3.義俊(よしとし)〔官位官職なし〕 |
家親の嫡子 |
当初の名乗りは家信(いえのぶ)「家」の字は徳川将軍家(家親に1字を与えた家康であろう)
からの一字拝領だったらしく、改易後に返上して義俊と改名している。
13歳で跡を継いだ。しかし、若年の義俊は藩主の器とは到底いえず、老臣たちの反発を招いた。
|
最上騒動
| 山形藩の初代藩主である最上義光の晩年頃から、最上家では後継者をめぐっての暗闘が繰り広げられるよう |
| げられるようになった。義光には長男に最上義康があり、本来なら彼が家督を継ぐのが筋であった。 |
| しかし義光がこの長男と不和になっていたこと、次男の最上家親が徳川家康・徳川秀忠らに近侍して |
| 御家存続のために義光は家親に家督を譲ろうと画策する。義康が何者かによって暗殺されたのである |
| 家親は元和3年(1617年)に急死する。37歳、第3代藩主となった。しかし義俊は若年であったために、 |
| 重要な決定は幕府に裁断を求めることが取り決められた。 |
| 最上家臣団は、義俊を廃して義光の4男・山野辺義忠を擁立しようと画策する一派と、義俊をあくまで |
| 擁護しようという一派に分裂して激しい内紛を引き起こした。幕府は最上家57万石は改易を命じられた |
|
|
|
|

  |
藤原秀郷を祖と称する藤原氏の一族。近江国蒲生郡を中心に勢力を築き、藤原惟俊の代から
蒲生氏を称した。室町時代には近江国の守護大名となった六角氏に客将として仕えた。
蒲生氏郷が織田信長の娘婿に迎えられるなど重用されたため、織田政権とそれを継承した豊臣政権において
豊臣政権において蒲生氏は大大名として大きく躍進した。
|
蒲生 氏郷(がもう うじさと)
| 蒲生賢秀の三男(嫡男)。天正10年(1582年)、信長が本能寺の変により自刃すると、安土城にいた 信長の妻子を保護し、 |
| 父賢秀と共に居城・日野城(中野城)へ走って明智光秀に対して対抗姿勢を示した。その後は羽柴秀吉(豊臣秀吉)に仕えた。 |
| 秀吉は氏郷に伊勢松ヶ島12万石を与えた。高山右近らの影響で大坂においてキリスト教の洗礼を受ける。 |
| 文禄4年(1595年)2月7日、伏見の蒲生屋敷において、病死した。享年40 |
| 1 |
会津藩
|
外様 91.9万石 岩代国 (1590年 - 1598年)
| 1.蒲生 氏郷 うじさと |
正四位下、参議 |
|
| 2.蒲生 秀行(ひでゆき |
従四位下、飛騨守、侍従 |
氏郷の嫡男 |
秀行は家康の娘と結婚していたため、江戸幕府成立後も徳川氏の一門衆として重用された。
しかし、会津地震や家中騒動の再燃なども重なり、その心労などのため、慶長17年5月に死去した
|
| 2 |
上山藩
|
外様 4万石 羽前国
| 1.蒲生忠知(ただとも) 従四位下 侍従、中務大輔 |
秀行の次男 |
|
|
| 3 |
伊予
松山藩
|
外様 24万石 伊予国 (1627年 - 1634年)
| 1.蒲生忠知(ただとも) 従四位下 侍従、中務大輔 |
秀行の次男 |
寛永7年(1630年)、再び勃発した重臣の抗争を裁いた。この裁判沙汰はなかなか決着がつかず3年にも及び
忠知は幕府の裁定を仰いで決着を図り、ようやくにして事態の解決を見た。
結果として、福西・関・岡・志賀らの老臣が流罪・追放されるだけでなく、家老の蒲生郷喜の弟である
蒲生郷舎も暇を出され、召し放つ事態に陥った。
寛永11年(1634年)、参勤交代の途上、京都の藩邸で急死した。享年31。死因は不明だが、兄・忠郷と同じく
疱瘡が原因とも言われる。嗣子がなかったため、蒲生氏は断絶した。
|
| 忠知の死により近江蒲生氏の系統は断絶したが、これは祟りが遠因となったという巷説がある。 |
| 忠知が藩主の座を継いで以降、世継ぎの男子が生まれないまま時を重ねていたが、やがて藩内の妊婦に憎悪を向けること |
| けることとなり、妊婦を捕まえては腹を割き、母子共々殺害するという惨劇を繰り返していたという。 |
| 非業の死を遂げた妊婦の怨念により、蒲生家は断絶に至ったと伝えられ、その証拠として松山城には「まな板石」なる物が |
| 残され、城址公園となった今でもすすり泣く声が聞こえるという |
|
|
|
|
|
|
|

 |
織田一族の発祥地は越前国織田庄(福井県丹生郡越前町)にある劔神社である。甲斐氏、朝倉氏と同じく、
三管領の斯波武衛家の守護代であり、序列は甲斐氏に次いで二位であった。
室町時代は尾張国の守護代を務める。戦国時代には一族同士の争いの結果、弾正忠家の織田信長が
勢力を大きく広げた。天下統一を目前に本能寺の変で信長および嫡子の織田信忠が討たれると
織田家有力家臣の勢力争いとなった。関ヶ原の戦いで西軍についたことで徳川家康により織田家(嫡流)は
滅ぼされた。本能寺の変以降、織田信長の血筋を引き継いで明治まで続いた系統は、主として
次男信雄・七男信高・九男信貞の子孫である。 |
織田信長の子
長男:織田信忠
本能寺の変の際には、父信長と共に討死
次男:織田信雄
北畠信雄(北畠具房養子)本能寺の変後に織田信意と改名し信意は尾張・伊賀・南伊勢約100万石を相続した。
その際、織田姓に復して信勝、次いで信雄と称し、賤ヶ岳の戦いが発生した。信雄は秀吉方に属し、小牧・長久手の戦いでは
徳川側に付くが、その後豊臣秀吉に服従、小田原征伐にも従軍し、伊豆韮山城攻めで武功を挙げる。しかし、戦後の論功行賞で
東海地方の家康旧領への移封命令を拒否した結果、秀吉の怒りを買って改易される。改易後は下野国烏山(一説に那須とも)に
流罪となり、出家して常真と号した。その後、出羽国秋田、伊予国へと流され、文禄元年(1592年)の文禄の役の際に家康の仲介で
赦免され、御伽衆に加えられて大和国内に1万8,000石を領した。肥前名護屋城にも兵1,500を率いて着陣したという
(『太閤記』)。この際、嫡男・秀雄も越前国大野に5万石を与えられた。
関ヶ原の戦いでは、西軍の情勢を密かに家康へ報じていたとも伝えられる。しかし、傍観的態度を西軍に与したと判断されたためか、
秀雄ともども改易されている。戦後は豊臣家に出仕したが、慶長19年(1614年)の大坂冬の陣の直前に徳川方へ転身する。
元和元年(1615年)7月23日、家康から大和国宇陀郡、上野国甘楽郡などで5万石を与えられる。
三男:織田 信孝
神戸城(三重県鈴鹿市)城主・神戸具盛の養子、織田氏に復して新たに一家を興した。
本能寺の変が勃発した。逃亡兵が相次ぎ、「変事を聞いて大部分は彼(信孝)を棄て去った
天正11年(1583年)、賤ヶ岳の戦いが起きると、信孝は再度挙兵する。しかし兄・信雄によって同年4月に居城の岐阜城を包囲され、
頼みの勝家も北ノ庄城で自害すると、岐阜城を開城して秀吉に降伏した。
信孝は尾張国知多郡野間(愛知県美浜町)の大御堂寺(野間大坊)に送られ、自害させられた。切腹の際、腹をかき切って腸を
つかみ出すと,床の間にかかっていた梅の掛け軸に投げつけたといわれている。その血の跡は今なお掛け軸に残っている
四男:羽柴 秀勝 永禄11年(1568年)、織田信長の四男として生まれた
織田信長の四男で、家臣羽柴秀吉が養嗣子として迎え入れた。
実父の織田信長が本能寺の変で突然横死した後は秀吉の中国大返しに同行し、「信長の四男」としての立場で6月13日の
山崎の戦いに参加して異母兄神戸信孝と共に弔い合戦の旗印となった
天正11年(1583年)の賤ヶ岳の戦いに参加。天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いにも参加し、近江草津に陣を布き、
木曽川筋攻撃で活躍。『兼見卿記』によるとこの頃より体調が悪化して、途中から大垣城に留め置かれた。
天正13年(1585年)7月、従三位・左近衛権少将に叙され、ほどなく正三位・権中納言にまでなったが、病床に就き、
12月10日、丹波亀山城で病死した。享年18。
五男:織田 勝長 養子名:津田信房
美濃国岩村城(岐阜県恵那市)の城主・遠山景任が亡くなった後、養子として岩村城へ入府したという
遠山景任・武田信玄養子のち離縁、織田家返還後の天正9年11月24日に「勝長」として元服し、源三郎と称したとしている
本能寺の変において信忠と共にあり、明智光秀の軍勢に攻められて二条御新造で奮戦ののちに討ち死にした。
長男の勝良は織田信雄に仕え、のち加賀前田家に600石で仕えた
六男:織田 信秀 元亀2年(1571年)頃の誕生
本能寺の変の際は美濃の仏照寺に落ちて難を避けた。天正15年(1587年)、九州征伐に兵を率いて従軍した文禄年間、京都で
癩病のために病死したとされる
七男:織田 信高 1576年(天正4年)、信長の七男として生まれる。
豊臣政権時代の冷遇、江戸開幕後に高家に取り立てられ厚遇されたことの説明がつく
関ヶ原の戦いでは弟信貞と共に東軍を支持したものの、本戦には間に合わず、凱旋後の徳川家康に拝謁したという。
しかし、『関原軍記大成』などでは、弟信吉・信貞らとともに西軍に属して戦後赦免されたとする。おそらくは後者が正しく、
弟信吉と同様に西軍に 属したために失領したと思料される。もっとも、本戦に参加したとする記録はない。
1603年(慶長7年)12月12日、死去。享年28。子孫
1616年(元和2年)1月、嫡男高重は幕臣として召し出されて近江・安房に2000石を与えられた。高重の孫信門は高家となり、
以後、同家は明治維新まで高家旗本として存続した。尚、フィギュアスケート選手織田信成は信高系の旗本織田家の末裔で
あると称しているが、不明
八男:織田 信吉
関ヶ原の戦いでは西軍につき、弟の織田長次とともに平塚為広勢に加わり、兵500で大谷吉継隊の前備えをなした。
信吉は戦場を離脱に成功した。戦後に改易となり、豊臣家を頼り、大坂城下で暮らす。
九男:織田 信貞
関ヶ原の戦いでは、西軍に与して伏見城攻撃に参加して、戦後に改易された
慶長19年(1614年)からの大坂の陣では徳川方として従軍した。
その孫の世代になって1,000石取りに復し、徳川氏に高家旗本として仕えて、分家も旗本として仕えた。
十男:織田 信好
慶長14年(1609年)7月14日、死去。
十一男:織田 長次
関ヶ原の戦いでは西軍に与し、兄・信吉とともに大谷吉継の隊に所属して平塚為広と同陣して戦ったが、9月15日の本戦で
大谷軍壊滅の際、為広らとともに戦死した
織田 秀信:織田信忠の嫡男、織田信長の嫡孫 幼名は三法師
天正10年(1582年)の本能寺の変の際、父・信忠の居城岐阜城に在城していたが、前田玄以、長谷川嘉竹あるいは木下某
(小山木下氏)に保護されて清洲城へと避難した。 同年、清洲会議において羽柴秀吉の周旋により、わずか3歳で織田弾正忠家の
家督を相続、直轄領として近江国坂田郡3万石を得る。天正16年(1588年)、9歳で岐阜に入って元服し三郎秀信と名乗る
関ヶ原の戦いに際しては、前年から戦支度を進めていた節が見られる。慶長4年(1599年)閏3月、岐阜の家臣・瀧川主膳に対し、
石田三成の奉行職引退、佐和山城蟄居を受けて稲葉山、町口の防備を固めるよう書面で指示している。
改易された秀信は高野山で修行を積むことになったが、祖父・信長の行った高野山攻めが仇となって当初は入山が許されず、
10月28日まで待たされた。慶長10年5月27日、向副で生涯を閉じた。この事からも、健康を害していたための下山療養とも
考えられるが、死因は自害であるとも伝わる。高野山側では山を下りた5月8日を死亡日としている。享年26。
織田信雄系の大名
| 1 |
小幡藩
|
外様 2万石 上野国
| 1.織田信良(のぶよし) 従四位下 左少将 |
織田信雄の四男 |
| 2.織田信昌(のぶまさ) 従四位下 兵部大輔 |
信良の次男 |
| 3.織田信久(のぶひさ) 従四位下 越前守 侍従 |
大和宇陀松山藩主織田高長の四男。 |
| 4.織田信就(のぶなり) 従四位下 美濃守 侍従 |
信久の次男 |
| 5.織田信右(のぶすけ) 従四位下 兵部大輔 |
信就の四男 |
| 6.織田信富(のぶとみ) 従五位下 和泉守 |
信就の七男 |
| 7.織田信邦(のぶくに) 従五位下 美濃守 |
高家旗本信栄の四男 |
藩主となった信邦は吉田玄蕃を家老として登用し、藩政改革と財政再建を目指した。玄蕃は幕政に批判的であった学者の
山県大弐の門弟であり、玄蕃と対立関係にあった用人の松原郡太夫らは、「玄蕃が大弐と謀反の疑いを企てている」と
信邦に讒訴、失脚をはかった。信邦は幕府に相談することなく、藩の独断で吉田らを処分し、事件の収拾をはかった。しかし
幕府は信邦及びその家老らの対応は不適切として処分を決めた。幕府は信邦に蟄居すなわち強制隠居を命じ、実弟の
信浮に家督を相続させた。信邦の仮養子であった実弟の信浮に家督の相続を許可したが、陸奥信夫郡、出羽置賜郡、
出羽村山郡内2万石への転封を命じた。
|
| 2 |
高畠藩
|
外様 2万石 羽前国 現在の山形県東置賜郡
| 1.織田信邦(のぶくに)〔従五位下 美濃守〕 |
高家旗本織田信栄の四男 |
| 2.織田信浮(のぶちか)〔従五位下 左近将監〕 |
織田信栄(織田高長の三男・長政の子孫)の五男 |
| 3.織田信美(のぶかず)〔従五位下 越前守〕 |
信浮の九男 |
|
| 3 |
天童藩
|
外様 - 2万石→1.8万石 出羽国
| 1.織田 信美のぶかず |
従五位下若狭守、越前守 |
|
| 2.織田 信学のぶみち |
従五位下、伊勢守、兵部少輔、左近将監 |
信美の長男 |
| 3.織田 信敏のぶとし |
従五位下兵部大輔。後に従三位 |
信学の四男 |
| 4.織田 寿重丸(すえまる |
|
信学の六男 |
| 5.織田 信敏のぶとし |
従五位下兵部大輔。後に従三位 |
信学の四男 |
幼少のために寿重丸は免職となり、隠居していた信敏が藩知事になった。
廃藩置県
|
|
|
織田信雄系の大名
| 1 |
宇陀
松山藩
うだまつやま
織田家 |
外様 2.8万石 大和国
| 織田 信雄(のぶかつ |
正二位、内大臣 |
信長の次男 |
| 織田 高長(たかなが) |
従四位下、侍従 |
信雄の五男 |
| 織田 長頼(ながより |
従四位下侍従、伊豆守、山城守 |
高長の子 |
| 織田 信武(のぶたけ) |
従四位下出雲守兼侍従、伊豆守 |
織田長頼の長男 |
元禄7年(1694年)10月30日、松山陣屋において信武は突然自殺する。享年40。長男・信休を
丹波柏原藩2万石に減転封とした。
|
| 2 |
丹波
柏原藩
織田家 |
外様 2万石 丹波国
| 1.織田信休(のぶやす)〔従五位下 近江守〕 |
信武の子 |
| 2.織田信朝(のぶとも)〔従五位下 出雲守〕 |
信休の次男 |
| 3.織田信旧(のぶひさ)〔従五位下 山城守〕 |
信休の三男 |
| 4.織田信憑(のぶより)〔従四位下 出雲守〕 |
高家旗本・織田信栄の次男 |
| 5.織田信守(のぶもり)〔従五位下 山城守〕 |
信憑の長男 |
| 6.織田信古(のぶもと)〔従五位下 近江守〕 |
柏原藩世嗣だった織田信応の長男 |
| 7.織田信貞(のぶさだ)〔従五位下 出雲守〕 |
信守の長男 |
| 8.織田信敬(のぶのり)〔従五位下 出雲守〕 |
肥後宇土藩主細川行芬の三男 |
| 9.織田信民(のぶたみ)〔従五位上 山城守〕 |
筑前秋月藩主黒田長元の四男 |
| 10.織田信親(のぶちか)〔従五位下 出雲守〕 |
交代寄合(のち備中成羽藩主)・山崎治正の三男 |
廃藩置県
|
|
織田信包系
織田 信包(おだ のぶかね)
| 天文12年(1543年)、尾張国の戦国大名・織田信秀の子として生まれたといわれる。 |
| 永禄12年(1569年)、兄・信長の命で北伊勢を支配する長野工藤氏(長野氏)に養子入りして伊勢国上野城を |
| 居城としたが、後に信長の命令によってこの養子縁組を解消し、織田氏に復したという。 |
| 天正10年(1582年)の本能寺の変で信長と甥信忠が殺害された後は豊臣秀吉に従い、伊勢津城15万石を |
| 領して「津侍従」と称された。天正11年には甥・織田信孝らと対立し、柴田勝家や滝川一益を攻略している。 |
| 慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いでは西軍に属して丹後田辺城攻撃などに参戦したものの、戦後に家康は |
| 信包の罪を問わず、所領を安堵された。 |
| 1 |
丹波
柏原藩
織田家 |
外様 3.6万石 丹波国
| 1.織田信包(のぶかね)〔従三位 左近衛中将〕 |
織田信秀の子 |
| 2.織田信則(のぶなり)〔従四位下 刑部大輔〕 |
信包の三男 |
| 3.織田信勝(のぶかつ)〔従五位下 上総介〕 |
信則の長男 |
慶安3年(1650年)5月17日、28歳で死去子供は3人の娘だけで息子がいなかったため、丹波柏原藩は改易
|
織田信重(のぶしげ)
織田信包の長男・信重は、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで東軍に与したため、戦後に林1万石の所領を安堵され、林藩を立藩した。
しかし実際の家督と実権は父の信包が握っていた。その信包が大坂冬の陣直前に72歳で死去すると、遺言により家督は三男の
信則が後を継ぐこととなった
| |
林 藩
織田家 |
外様 1万石 伊勢国 1594年 - 1615年
1.織田信重(のぶしげ)従五位下、民部大輔 織田信包の長男
父・信包の死去にともなって、弟・信則が遺領を相続したことに不満を抱いて、大坂の陣後に
江戸幕府に対して異議を申し立てた。幕府は信則の相続を遺言によるものとの判断を信重に伝え
同年閏6月、幕府は信重の異議申し立てを「僻事」として所領を没収した。
|
|
|
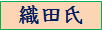

|
織田 長益(おだ ながます) (有楽流) 織田信長の弟
織田信秀の十一男で、有楽斎如庵(有樂齋如庵)と号し、後世では有楽、有楽斎と称される
千利休に茶道を学び、利休十哲の一人にも数えられる。後には自ら茶道有楽流を創始した。
本能寺の変の際は、信忠とともに二条御所にあったが、長益自身は城を脱出。
小牧・長久手の戦いでは信雄方として徳川家康に助力。
天正18年(1590年)の信雄改易後は、秀吉の御伽衆として摂津国島下郡味舌(の摂津市)2,000石を領した。
|
秀吉死後、家康と前田利家が対立した際には、徳川邸に駆けつけ警護している。関ヶ原の戦いでは東軍に属し、長男・長孝と
ともに総勢450の兵を率いて参戦。大坂冬の陣の際にも大坂城にあり、大野治長らとともに穏健派として豊臣家を支える中心的な
役割を担った。大坂夏の陣を前にして再戦の機運が高まる中、家康・秀忠に対し「誰も自分の下知を聞かず、もはや城内にいても
無意味」と許可を得て豊臣家から離れた。庶長子の長孝は関ヶ原の合戦において父と共に東軍として参加して戦功を挙げ、
1万石を与えられて大名に取り立てられ(野村藩)、
| |
野村藩
織田家 |
外様 1万石 美濃国 (1600年 - 1631年)
| 1.織田長孝(ながたか)従五位下河内守 |
織田長益(有楽斎)の長男 |
| 2.織田長則(ながのり)従五位下、河内守 |
長孝の長男 |
寛永8年(1631年)7月4日、死去。嗣子がなかったため、野村藩織田氏は改易となった
|
織田長政(おだ ながまさ
織田長益(有楽斎)の四男、徳川家康の小姓となり、3,000石を与えられる。
元和元年(1615年)8月12日に父から大和・摂津国内で1万石を分け与えられる。大和柳本藩を設立した。
| |
芝村藩
織田家 |
外様 1万石 大和国 戒重藩(かいじゅうはん)とも呼ばれる
| 1.織田長政(ながまさ |
従五位下、丹後守、左衛門佐 |
織田長益(有楽斎)の四男 |
| 2.織田長定(ながさだ |
従五位下豊前守 |
長政の長男 |
| 3.織田長明(ながあきら |
|
長定の長男 |
| 4.織田長清(ながずみ |
従五位下豊前守、摂津守 |
宇陀松山藩主織田長頼の三男 |
| 5.織田長弘(ながひろ |
|
長清の三男 |
| 6.織田長亮(ながあき |
従五位下、肥前守 |
長清の五男 |
| 7.織田輔宜(すけよし |
従五位下豊前守、摂津守 |
長亮の長男 |
| 8.織田長教(ながのり |
従五位下豊前守 |
長亮の三男 |
| 9.織田長宇(ながのき |
従五位下左衛門佐 |
長教の長男 |
| 10.織田長恭(ながやす |
従五位下豊前守、摂津守 |
長宇の三男 |
| 11.織田長易(ながやす |
従五位下豊前守、摂津守 |
美濃国苗木藩主遠山友寿の五男 |
廃藩置県
|
織田尚長(おだ なおなが
織田信長の弟・織田長益の五男、大坂冬の陣の終結に際し、豊臣家から徳川家に人質に出される。長益が豊臣家の
重臣であったためである。慶長20年(1615年)4月、大坂城を退去した長益とともに徳川家康に御目見する。
| |
柳本藩
織田家 |
外様 1万石 大和国
| 1.織田尚長(なおなが |
従五位下武蔵守、越後守、大和守 |
長益の五男 |
| 2.織田長種(ながたね |
従五位下、修理亮 |
尚長の長男 |
| 3.織田秀一(ひでかず |
従五位下信濃守 |
長種の長男 |
| 4.織田秀親(ひでちか |
監物 |
秀一の長男 |
| 5.織田成純(しげずみ |
従五位下豊後守、播磨守 |
秀一の次男 |
| 6.織田秀行(ひでゆき |
従五位下伊予守 |
秀親の四男 |
| 7.織田信方(のぶかた |
従五位下下野守 |
旗本・織田信清の三男 |
| 8.織田秀賢(ひでかた |
従五位下信濃守、安房守、出羽守 |
信方の長男 |
| 9.織田長恒(ながつね |
従五位下筑前守 |
信方の五男 |
| 10.織田秀綿(ひでつら |
従五位下筑前守、大和守 |
秀賢の三男 |
| 11.織田信陽(のぶあきら |
従五位下大和守、越前守、安芸守 |
秀綿の七男 |
| 12.織田信成(のぶしげ |
従五位下筑前守。後に正四位 |
信陽の九男 |
| 13.織田信及(のぶひろ |
従五位下大和守 |
信陽の十男 |
廃藩置県
|
|
|
|
|