| 1相馬氏 |
2秋田氏 |
3稲葉氏 |
4喜連川氏 |
5木下氏 |
6中川氏 |
7丹羽氏 |
8溝口氏 |
| 9脇坂氏 |
10分部氏 |
11村上氏 |
12金森氏 |
13平岡氏 |
14徳永氏 |
15関 氏 |
16美濃関氏 |
| 17松前氏 |
18大村氏 |
19亀井氏 |
20北条氏 |
21岩城氏 |
22秋月氏 |
23市橋氏 |
24大関氏 |
| 25大田原氏 |
26片桐氏 |
27九鬼氏 |
28六郷氏 |
29堀 氏 |
30成田氏 |
31佐野氏 |
32那須氏 |
| 33藤田氏 |
34滝川氏 |
35佐久間氏 |
36土方 |
37青木 |
38久留島 |
39五島 |
40相良 |
| 41新庄 |
42仙石 |
43建部 |
44谷 |
45一柳 |
46田村 |
|
|
|


|
初代の相馬師常は、鎌倉時代初期の武将千葉常胤の次男である。師常が父常胤より相馬郡
相馬御厨(現在の千葉県松戸から我孫子にかけての一帯)を相続されたことに始まる。
師常の子孫は相馬御厨を中心として活動していたが、4代胤村の死後、先妻の子・胤氏と後を
託した後妻の子・師胤(5代)が家督を争った。師胤は父の譲状を鎌倉幕府に提出したが、
鎌倉幕府はこれを認めず、胤氏を継承者として認めた。このため、師胤の子・重胤(6代)の代に
横領の恐れが高まったとして、源頼朝により所領として許されていた。陸奥国行方郡に入った。
なお、胤氏一族は下総に残留して下総相馬氏となる。
|
下総相馬氏(流山相馬氏)
徳川家康に内応したことで治胤旧領の5,000石を与えられた。特別に末弟の政胤が徳川秀忠に召し出され、
旗本として相馬郡内1,000石で家名再興が許された。一族には一橋徳川家に出仕した者もある。
陸奥相馬氏
| 陸奥相馬氏(中村相馬氏)は、遠祖・千葉氏が源頼朝から奥州の小高に領地を受けた後、千葉氏族・ |
相馬重胤が移り住み、南北朝時代の初期は南朝が優勢な奥州において数少ない北朝方の一族として
|
| 活躍。関ヶ原の戦いにおいては中立。 |
| 豊臣政権時代に西軍・石田三成と親密であった佐竹義宣の弟・岩城貞隆と婚姻を結ぶなどしていたため |
| 西軍寄りとみなされ、徳川家康によって改易された。しかし、中村相馬氏は訴訟を起こして伊達氏を友に |
| 付けてこれを凌ぎきり、再び旧領を奪還して近世大名(中村藩主)として生き抜くことに成功した。 |
相馬 利胤(そうま としたね
| 相馬義胤(第16代)の長男,はじめ父・義胤が佐竹義宣と共に石田三成と親密な関係であったため |
| 三胤と名乗った。関ヶ原の戦いでは父の義胤が佐竹家とともに中立を決め込んだため、徳川家康によって |
| 所領を没収され、改易の危機に立たされた。三胤は石田三成由来の「三」の字を改め蜜胤と名前を |
変えて、僅かの家臣を伴い直訴のため自ら江戸に赴いた。 本多正信へ取り次ぐことに成功した。
家康・秀忠への正信の説得もあり、所領を安堵された。
|
慶長16年(1611年)、居城を小高城から相馬中村城へ移した。慶長20年(1615年)の大坂夏の陣では、
|
| 徳川秀忠軍の先鋒として奮戦している。 利胤と名乗る |
| |
相馬
中村藩
相馬家
|
外様 6万石 磐城国 外様~譜代並み~譜代
藩主は一貫して相馬氏で、家格は柳間詰め外様大名、後に帝鑑間詰め譜代大名に列せられる。
| 1.相馬 利胤(としたね |
従四位下、大膳亮如元 |
義胤の子 |
| 2.相馬 義胤(よしたね |
従五位下、大膳亮 |
利胤の長男 |
| 3.相馬 忠胤(ただたね |
従五位下長門守譜代並み |
土屋利直の次男 |
| 4.相馬 貞胤(さだたね |
従五位下、出羽守 |
忠胤の長男 |
| 5.相馬 昌胤(まさたね |
従五位下、弾正少弼奥詰 |
忠胤の次男 |
| 6.相馬 叙胤(のぶたね |
従五位下、図書頭、長門守 出羽久保田藩主・佐竹義処の次男 |
| 7.相馬 尊胤(たかたね |
従五位下、弾正少弼譜代 |
昌胤の次男 |
| 8.相馬 恕胤(もろたね |
従五位下、因幡守 |
叙胤の三男 |
| 9.相馬祥胤(よしたね |
従五位下、因幡守 |
恕胤の三男 |
| 10.相馬 樹胤(むらたね |
従五位下、豊前守 |
祥胤の長男 |
| 11.相馬 益胤(ますたね |
従五位下、長門守 |
祥胤の四男 |
| 12.相馬 充胤(みちたね |
従五位下、大膳亮 |
益胤の長男 |
| 13.相馬 誠胤(ともたね |
従五位下因幡守 |
充胤の次男 |
廃藩置県
|
相馬野馬追(そうまのまおい)
中村を初めとする福島県浜通り北部(旧相馬氏領。藩政下では中村藩)で行われる、馬を追う神事
および祭りである。 |
神事に関しては国の重要無形民俗文化財に指定されている。中村相馬氏の遠祖である平将門が、
領内の下総国相馬郡小金原 |
| (現在:千葉県の松戸)に野生馬を放し、敵兵に見立てて軍事訓練をした事に始まると言われている |
2011年から神事と祭りは日程が分離されることになり、神事は24日・25日に日にち固定で実施し祭りは
7月最終週の土曜日に開幕することになった |
|

 |
安倍貞任の後裔を称し平安時代後期から室町時代にかけて出羽北部から津軽地方に
かけてを領した安東氏の後身である。安東氏は安倍貞任の末裔と伝承される北方の
名門であり、鎌倉時代にあっては津軽(青森県西部)の十三湊を本拠として勢力を拡げ、
日本海交易と蝦夷沙汰を担った一族として蝦夷管領を名乗り、南北朝時代には内外に
「日の本将軍」を号するほどであった。 |
安東 愛季(あんどう ちかすえ) 檜山系安東氏第8代当主
長く分裂していた檜山系と湊系の安東氏を統一し、安東氏の戦国大名化を成し遂げた智勇に優れた人物で
信長の死後は 羽柴秀吉と誼を通じるなど、中央権力とも連絡を密にしており、安東氏の最盛期を築く、
晩年には名字を安東から秋田へと改めている。
秋田 実季(あきた さねすえ) 安東愛季の次男
慶長5年の関ヶ原の戦いでは東軍方に立ち、小野寺義道を平鹿郡大森城(秋田県横手市大森町)に
攻めた嫡男の俊季との不和説や、従来からの檜山系・湊系による家臣間の対立が背後にあったので |
| はないかとする見解もあるが、詳細は不明である。なお、秋田氏は俊季の幕府への忠節と、俊季の母が |
| 将軍秀忠の妻崇源院の従姉妹にあたることも幸いして、陸奥三春5万5,000石に移され存続を許された。 |
| 戦国大名らしい気骨が横溢していることが幕府の忌み嫌うところとなり、寛永7年以降約30年にわたり、 |
| 実季は伊勢朝熊の永松寺草庵にて蟄居生活を余儀なくされた |
| 1 |
常陸
宍戸藩
|
外様 5万石 常陸国
| 1.秋田実季(さねすえ) 従五位下 秋田城介 |
安東 愛季の次男 |
| 2.秋田俊季(としすえ) 従五位下 伊豆守 |
実季の長男 |
|
| 2 |
三春藩
|
外様 5万石 磐城国
| 1.秋田俊季 |
従五位下 伊豆守 |
実季の長男 |
| 2.秋田盛季もりすえ |
従五位下、安房守 |
俊季の長男 |
| 3.秋田輝季てるすえ |
従五位下、信濃守 |
盛季の長男 |
| 4.秋田頼季よりすえ |
従五位下、信濃守 三春藩の重臣だった荒木高村の長男 |
| 5.秋田延季のぶすえ(治季 |
従五位下、河内守 |
頼季の長男 |
| 6.秋田定季さだすえ |
従五位下、主水正 |
頼季の次男 |
| 7.秋田倩季よしすえ(千季) |
従五位下、山城守 |
延季の次男 |
| 8.秋田長季ながすえ(謐季) |
従五位下、信濃守 |
倩季の次男 |
| 9.秋田孝季のりすえ |
従四位下、主水正 |
倩季の三男 |
| 10.秋田肥季ともすえ |
従五位下、安房守 |
孝季の長男 |
| 11.秋田映季あきすえ |
従三位、信濃守 |
肥季の次男 |
廃藩置県
|
|


|
伊予の豪族・河野氏(伊予橘氏)の一族とするのが定説である。しかしそれを疑わしいとし、
生駒氏、楠木氏、服部氏、伊賀氏(美濃安藤氏)と同族とする説もある。戦国時代の稲葉氏
当主良通(一鉄)ははじめ斎藤氏に仕え、安藤守就・氏家卜全と共に西美濃三人衆として
権勢を振るう良通の子貞通は関ヶ原の戦いで西軍から東軍に寝返り、本戦に参加して
武功を挙げた。美濃郡上八幡4万石から豊後臼杵5万石に加増移封され、
臼杵藩の藩祖となった。良通の庶長子の重通は分家して大名となり、美濃清水を領した。
家督は、稲葉氏の一族の尾張林氏より養子に入った正成が継ぎ、子孫は正成の妻の
春日局が3代将軍徳川家光の乳母となったため出世し、姻戚関係にあった堀田氏と共に
譜代大名として栄えた。正成の家系からは館山藩主のほか、数家の旗本の分家を分出しる |
| |
臼杵藩
うすき
|
外様 5万石 常陸国
| 1.貞通(さだみち)〔従四位下、右京亮・侍従〕 |
良通の次男 |
| 2.典通(のりみち)〔従四位下、侍従〕 |
貞通の長男 |
| 3.一通(かずみち)〔従五位下、民部少輔 〕 |
典通の長男 |
| 4.信通(のぶみち)〔従五位下、能登守〕 |
一通の長男 |
| 5.景通(かげみち)〔従五位下、右京亮〕 |
信通の長男 |
| 6.知通(ともみち)〔従五位下、能登守〕 |
信通の三男 |
| 7.恒通(つねみち)〔従五位下、伊勢守〕 |
知通の次男 |
| 8.菫通(まさみち)〔従五位下、能登守〕 |
恒通の長男 |
| 9.泰通(やすみち)〔従五位下、能登守〕 |
菫通の長男 |
| 10.弘通(ひろみち)〔従五位下、能登守〕 |
泰通の長男 |
| 11.雍通(てるみち)〔従五位下、伊予守〕 |
弘通の次男 |
| 12.尊通(たかみち)〔従五位下、民部少輔〕 |
雍通の長男 |
| 13.幾通(ちかみち)〔従五位下、備中守〕 |
雍通の三男 |
| 14.観通(あきみち)〔従五位下、伊予守〕 |
稲葉通孚の長男 |
| 15.久通(ひさみち)〔従五位下、右京亮〕 |
旗本・岡野知英の五男 |
廃藩置県
|
|

  |
足利氏の後裔。足利尊氏の次男で室町将軍代理家だった鎌倉公方の足利基氏を祖とする。
古河公方家と小弓公方家は後北条氏や千葉氏との戦によってすでに衰亡していた。
しかし名門家系であったことから豊臣秀吉に再興を許された。国朝は関ヶ原の戦いの後、
徳川家康によって1000石を加増され、4500石の旗本となった。国朝の死後、姫と国朝の
弟頼氏が再婚し、喜連川の所領と名跡を受け継いで喜連川氏を称した。
|
喜連川 頼氏(きつれがわ よりうじ)
天正20年(1593年)、兄の足利国朝が文禄の役で九州に赴く途上の安芸国で病死したため、兄の正室であった
足利氏姫が頼氏と再婚することで足利氏後裔喜連川氏の名跡を継いだ。 |
| 関ヶ原の戦いでは頼氏は出陣しなかったが、戦後に徳川家康に対して戦勝を祝う使者を派遣したため |
| 1,000石を加増され、喜連川藩が立藩された。喜連川藩の知行地はわずか5,000石弱に過ぎなかったが、 |
江戸幕府を開いた徳川家康から足利氏の名族としての伝統を重んじられ、10万石並の国主格大名の
待遇を受けた。 |
| |
喜連川藩
きつれがわ
喜連川家 |
外様、 3500石→4500石→5000石 下野国
| 藩祖・足利国朝(喜連川国朝) |
|
| 1.喜連川頼氏よりうじ |
左馬頭 |
足利頼純(頼淳)の次男 |
| 2.喜連川尊信たかのぶ |
左兵衛督 |
喜連川頼氏の長男・義親の長男 |
| 3.喜連川昭氏あきうじ |
左馬頭、右兵衛督 |
尊信の長男 |
| 4.喜連川氏春うじはる |
左兵衛督 |
宮原義辰の次男 |
| 5.喜連川茂氏しげうじ |
左兵衛督 |
氏春の長男 |
| 6.喜連川氏連うじつら |
右兵衛頭 |
茂氏の次男 |
| 7.喜連川恵氏やすうじ |
左兵衛督、大蔵大輔 |
伊予大洲藩主加藤泰?の長男 |
| 8.喜連川彭氏ちかうじ |
右兵衛督、左兵衛督 |
恵氏の長男 |
| 9.喜連川煕氏ひろうじ |
左馬頭 |
彭氏の三男 |
| 10.喜連川宜氏のりうじ |
|
細川定良の長男 |
| 11.喜連川縄氏つなうじ |
左馬頭 |
水戸藩主徳川斉昭の十一男 |
| 12.足利聡氏(足利姓に復姓) |
従五位下、左馬頭 |
高家職・宮原摂津守義直の次男 |
廃藩置県
|
|

 |
豊臣秀吉系統の木下氏
木下氏の系譜の発祥は諸説があり、浅井氏の分家とする説等があるものの、
明確になっていない。
秀吉(豊臣秀吉)は、尾張大名織田信長に仕え活躍し、北近江長浜城主となった際に、
姓を「木下」から「羽柴」へと変更し、秀吉に仕えていた異父弟の秀長もそれに追随した。
秀吉は功があったものへの恩賞として旧姓の木下姓を与えている。 |
杉原系木下氏
この系統は、杉原氏(前述の浅井氏庶家で、浅井政貞と同族とされたり、桓武平氏系等々の各説あり)と
同族である。杉原は豊臣秀吉の正室高台院の生家の姓である。 |
| 彼女の兄・家定は秀吉より木下姓を与えられ、旧姓の杉原から木下家定と改称、そして秀吉に仕え、 |
| 播磨姫路城を与えられた。関ヶ原の合戦では妹高台院を警護した功により、家定は備中足守藩の |
| 初代藩主に任じられた。この系統から幕末まで2系統大名で続く |
木下 家定(きのしたいえさだ)
安土桃山時代から江戸時代初期の武将、本姓は豊臣氏家系はもともとは桓武平氏流の杉原氏だったが、
後に木下氏と改称する。杉原定利の長男。母は朝日殿。豊臣秀吉の正室であった |
| 高台院の兄(弟とする説もある)。関ヶ原の戦いでは、東軍・西軍のどちらにもも属さず中立を保ち、妹の |
| 高台院の警護を務めた功績を家康に賞賛され、戦後、備中足守に2万5000石の所領を与えられた。 |
子供は木下勝俊(長男)、木下利房(次男)、木下延俊(三男)、木下延貞(四男)、小早川秀秋(五男)、
木下秀規(六男)、木下俊定 |
| |
足守藩
あしもり
木下家 |
外様 2.5万石 備中国 (1601年 - 1609年)
| 1. 家定(いえさだ) 従五位下 肥後守 |
杉原定利の長男 |
| 2. 勝俊(かつとし) 従四位下 左近衛権少将 - |
家定の長男 |
| 2. 利房(としふさ) 従五位下 宮内少輔 - |
家定の次男 |
父・家定の死後、兄・勝俊と父の遺領(備中足守2万5000石)を巡って争った結果、遺領は家康
父・家定の死後、兄・勝俊と父の遺領(備中足守2万5000石)を巡って争った結果、遺領は家康
| 2. 利房(としふさ) 従五位下 宮内少輔 - 再封 |
| 3. 利当(としまさ) 従五位下 淡路守 |
利房の長男 |
| 4. 利貞(としさだ) 従五位下 淡路守 |
利当の長男 |
| 5. ?定(きんさだ) 従五位下 肥後守 |
利貞の長男 |
| 6. 利潔(としきよ) 従五位下 美濃守 |
利貞の次男藤栄の三男 |
| 7. 利忠(としただ) 従五位下 肥後守 |
利潔の長男 |
| 8. 利彪(としとら) 従五位下 淡路守 |
利忠の次男 |
| 9. 利徽(としよし) 官位不詳 |
利彪の長男 |
| 10. 利徳(としのり) 従五位下 肥後守 |
伊勢国津藩主藤堂高嶷の七男 |
| 11. 利愛(としちか) 従五位下 肥後守 |
利徽の次男 |
| 12. 利恭(としゆき) 従五位下 石見守 |
利愛の次男 |
廃藩置県
|
木下 延俊(きのしたのぶとし)
備中国足守藩の領主となった木下家定の三男、関ヶ原の戦いの際には東軍に属し、
父・家定の姫路城を守備、西軍所属と思われる弟・小早川秀秋の姫路城入城を拒んでいる。 |
| 西軍所属と思われる弟・小早川秀秋の姫路城入城を拒んでいる。 |
| 家康から豊後日出3万石を与えられ日出藩初代藩主 |
| |
日出藩
ひじ
木下家 |
外様 3万石→2.5万石 豊後国
| 1.延俊(のぶとし) 〔従五位下、右衛門大夫〕 |
木下家定の三男 |
| 2.俊治(としはる) 〔従五位下、伊賀守〕 |
延俊の三男 |
| 3.俊長(としなが) 〔従五位下、右衛門大夫〕 |
俊治の長男 |
| 4.俊量(としかず) 〔従五位下、式部少輔〕 |
俊長の長男 |
| 5.俊在(としあり) 〔従五位下、伊賀守〕 |
俊量の六男 |
| 6.俊保(としやす) 〔従五位下、和泉守〕 |
俊長の四男 |
| 7.俊監(としてる )〔夭折のため官位なし〕 |
俊量の八男 |
| 8.俊能(としよし) 〔従五位下、式部少輔〕 |
俊量の九男 |
| 9.俊泰(としやす )〔従五位下、大和守〕 |
俊量の十男 |
| 10.俊胤(としたね )〔従五位下、左衛門佐〕 下野国宇都宮藩主・戸田忠余の五男 |
| 11.俊懋(としまさ )〔従五位下、主計頭〕 |
俊胤の長男 |
| 12.俊良(としよし) 〔従五位下、佐渡守〕 |
俊懋の次男 |
| 13.俊敦(としあつ) 〔従五位下、大和守〕 |
俊懋の四男 |
| 14.俊方(としかた) 〔従五位下、主計頭〕 |
俊敦の次男 |
| 15.俊程(としのり) 〔従五位下、飛騨守〕 |
俊敦の五男 |
| 16.俊愿(としよし) 〔従五位下、大和守〕 |
俊敦の七男 |
廃藩置県
|

|
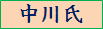

|
中川 清秀(なかがわ きよひで)
本姓は源氏。家系は清和源氏の一家系摂津源氏の流れを汲む多田源氏(あるいは
河内源氏傍系石川源氏)の後裔と称した。父は中川重清天正11年、賤ヶ岳の戦いにも |
| 秀吉方先鋒二番手として参戦したが、大岩山砦を右近、三好秀次らと守っている時、 |
| 柴田勝家軍の勇将・佐久間盛政の猛攻に遭って奮戦したものの戦死した。享年42。 |
| 中川清秀の子、中川秀成は関ヶ原の戦いにおいて東軍に属したため |
| 徳川家康より所領を安堵され、一度の移封もなく廃藩置県まで存続した。 |
|
| |
岡 藩
おか
中川家 |
外様 7万石 豊後国 (1594年 - 1871年)
| 1.秀成(ひでなり)〔従五位下、修理大夫〕 |
中川清秀の次男 |
| 2.久盛(ひさもり)〔従五位下、内膳正〕 |
秀成の長男 |
| 3.久清(ひさきよ)〔従五位下、山城守〕 |
久盛の長男 |
| 4.久恒(ひさつね)〔従五位下、佐渡守〕 |
久清の長男 |
| 5.久通(ひさみち)〔従五位下、因幡守〕 |
久恒の長男 |
| 6.久忠(ひさただ)〔従五位下、内膳正〕 |
久通の三男 |
| 7.久慶(ひさよし)〔従五位下、山城守〕 |
安芸広島藩主・浅野綱長の四男 |
| 8.久貞(ひささだ)〔従五位下、修理大夫〕 |
三河吉田藩主・松平信祝の次男 |
| 9.久持(ひさもち)〔従五位下、修理大夫〕 |
藩主・中川久貞の次男・久徳の次男 |
| 10.久貴(ひさたか)〔従五位下、修理大夫〕 |
大和郡山藩主・柳沢保光の五男 |
| 11.久教(ひさのり)〔従五位下、修理大夫〕 |
近江彦根藩主・井伊直中の七男 |
| 12.久昭(ひさあき)〔従五位下、修理大夫〕 |
伊勢津藩主・藤堂高兌の次男 |
| 13.久成(ひさなり)〔従五位下、内膳正〕 |
久昭の長男 |
廃藩置県
|
|
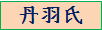

|
児玉丹羽氏 - 武蔵七党のうちの一つである児玉氏の出身
良岑氏を本姓としている。児玉党の末裔とされるが、長秀以前の系譜ははっきりしていない。
尾張守護斯波氏に仕えていた丹羽長秀は織田信長に仕え活躍した。信長が天正10年に
本能寺の変で明智光秀に殺害されると、羽柴秀吉に付き、共に光秀を討った。
その後は50万石の大大名となった。天正13年(1585年)に長秀が没すると、跡を継いだ
丹羽長重は秀吉によって加賀国松任4万石に減封されてしまうが、長重は戦功を挙げて
加賀国小松12万石に再び加増された。
関ヶ原の戦いでは長重は西軍に付き、いったん改易となる。だが慶長8年に徳川家康より
常陸国古渡に1万石の領地を与えられ大名として復帰。
その後陸奥国白河藩10万石の藩主となる。 |
大坂の陣での武功により、元和5年(1619年)に常陸国江戸崎2万石、元和8年(1622年)には陸奥国棚倉5万石、
寛永4年(1627年)白河10万700石と加増された。
| 1 |
白河藩
丹羽家 |
大広間 外様 10万石 陸奥国 (1627年 - 1643年)
| 1.長重(ながしげ) 従三位 参議 |
織田氏の家臣・丹羽長秀の長男 |
| 2.光重(みつしげ) 従四位下 侍従 |
長重の三男 |
|
| 2 |
二本松藩
|
外様 10万石→5万700石 陸奥国
| 1.丹羽光重(みつしげ)<従四位下。左京大夫。侍従> |
|
| 2.丹羽長次(ながつぐ)<従四位下。左京大夫> |
光重の長男 |
| 3.丹羽長之(ながゆき)<従五位下。越前守> |
光重の次男 |
| 4.丹羽秀延(ひでのぶ)<従四位下。左京大夫> |
長之の長男 |
| 5.丹羽高寛(たかひろ)<従四位下。左京大夫> |
丹羽長道の長男 |
| 6.丹羽高庸(たかつね)<従四位下。若狭守> |
高寛の長男 |
| 7.丹羽長貴(ながたか)<従四位下。左京大夫。侍従> |
高庸の長男 |
| 8.丹羽長祥(ながあき)<従四位下。左京大夫> |
長貴の長男 |
| 9.丹羽長富(ながとみ)<従四位下。左京大夫。侍従> |
長祥の長男 |
| 10.丹羽長国(ながくに)<従四位下(後に正三位)。左京大夫。侍従> |
長富の六男 |
| 11.丹羽長裕(ながひろ)<従五位> |
出羽米沢藩主・上杉斉憲の九男 |
廃藩置県
|
一色丹羽氏 - 足利氏の支流の一つである一色氏の出身 譜代大名に記載してあります
|
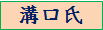
 |
甲斐源氏武田氏の庶流で、尾張国中島郡溝口郷(溝口村)に土着し溝口氏を称した。
織田信長の時代、溝口秀勝は丹羽長秀に仕える。天正9年、丹羽長秀より
若狭国高浜城5000石を給される。天正12年、丹羽長秀の遺領に堀秀政が封じられると、
秀政の与力として加賀大聖寺4万4000石を領する。
|
溝口 秀勝(みぞぐち ひでかつ)
| 溝口勝政の長男として尾張国中島郡西溝口村(現愛知県稲沢市西溝口町)に生まれた。 幼少時より丹羽長秀に仕えたが、 |
| 天正9年(1581年)に織田信長からその才能を見出され、直臣として若狭国大飯郡高浜城(高浜町)5000石を与えられた。 |
| 関ヶ原の戦いでは東軍に与し、越後において上杉景勝が煽動する一揆の鎮圧に努めた。戦後、徳川家康から所領を安堵され、 |
| 新発田藩初代藩主となる。 |
| |
新発田藩
しばた
|
外様 6万石 越後国
| 1.溝口 秀勝 ひでかつ |
従五位下、伯耆守 |
|
| 2.溝口 宣勝のぶかつ |
従五位下、伯耆守沢海藩を立て5万石 |
秀勝の長男 |
| 3.溝口 宣直のぶなお |
従五位下、出雲守 |
宣勝の長男 |
| 4.溝口 重雄しげかつ |
従五位下、信濃守 |
宣直の長男 |
| 5.溝口 重元しげもと |
従五位下、伯耆守 |
重雄の長男 |
| 6.溝口 直治 なおはる |
従五位下、信濃守 |
重元の次男 |
| 7.溝口 直温 なおあつ |
従五位下、出雲守 |
旗本溝口直道の四男 |
| 8.溝口 直養なおやす |
従五位下、主膳正 |
直温の長男 |
| 9.溝口 直侯なおとき |
従五位下、出雲守 |
直養の養嗣子・直信の長男 |
| 10.溝口 直諒なおあき |
従五位下、伯耆守 |
直侯の長男 |
| 11.溝口 直溥なおひろ |
従五位下、主膳正 |
直諒の長男 |
廃藩置県
|
支藩
溝口 善勝(みぞぐち よしかつ
| 加賀国大聖寺にて溝口秀勝の次男として生まれる。はじめ父と共に豊臣氏に仕えたが、慶長5年の関ヶ原の戦いでは東軍に与し、 |
| 戦後は徳川秀忠の家臣となった。父が死去して家督(越後新発田藩主)は兄の宣勝が継いだが、兄から1万2,000石を分与され、 |
| 父が死去して家督(藩主)は兄の宣勝が継いだが、兄から1万2,000石を分与され、1万4,000石の大名・越後沢海藩主となった。 |
| |
沢海藩
そうみ
|
外様 1万4000石→1万石 越後国 (1610年 - 1687年)
| 1.溝口善勝(よしかつ) |
従五位下伊豆守 |
秀勝の次男 |
| 2.溝口政勝(まさかつ) |
従五位下、土佐守 |
善勝の長男 |
| 3.溝口政良(まさよし) |
従五位下、伊予守 |
政勝の子 |
| 4.溝口政親(まさちか) |
|
水口藩主加藤明友の次男 |
天和3年(1683年)、養父・政良の死去により跡を継ぐ。しかし酒乱であったため、
家臣が実兄の水口藩主加藤明英や幕府に訴え、(1687年)に改易
|
|
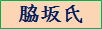
 |
脇坂氏が史上に現れるのは脇坂安明の子の安治の代からであり、藤原姓を称していたものの、
安明以前の系譜は不明、系図によっては近江国浅井郡脇坂庄の下司となった浅井秀政の三男浅井生秀の
孫浅井教政が祖であるという説がある。安治は織田・豊臣に歴仕し、賤ヶ岳の七本槍として名を揚げた。
淡路洲本藩に3万石を与えられ、水軍の大将となった |
脇坂 安治(わきざか やすはる)
| 脇坂氏は近江国東浅井郡脇坂野に居住し、その土地の名から脇坂と称した。脇坂安明の長男として、 |
| 近江国浅井郡脇坂庄(現在の滋賀県長浜市小谷丁野町)で生まれる。関ヶ原の戦い戦前に通款を明らかにしていた為、 |
裏切り者ではなく当初からの味方と見なされ、戦後に家康から所領を安堵された。慶長14年9月、伊予大洲藩5万3,500石に
|
| 加増移封された。慶長19年(1614年)からの大坂の陣では徳川・豊臣のどちらにも参加しなかった。 |
| 1 |
大洲藩
おおず
脇坂家 |
外様 5万3千石 伊予国 (1608年 - 1617年)
| 1.安治(やすはる)〔従五位下、中務少輔〕 |
脇坂安明の長男 |
| 2.安元(やすもと)〔従五位下、淡路守〕 |
安治の次男 |
|
| 2 |
飯田藩
脇坂家 |
外様→譜代 5.5万石 伊予国
| 1.脇坂安元(やすもと) 従五位下 淡路守 |
| 2.脇坂安政(やすまさ) 従五位下 中務少輔 |
武蔵国川越藩主堀田正盛の次男 |
|
| 3 |
龍野藩
脇坂家 |
外様→願譜代→譜代 53000石→51000石 播磨国 (1672年 - 1871年)
| 1.安政(やすまさ)〔従五位下、中務少輔〕 |
|
| 2.安照(やすてる)〔従五位下、淡路守〕 |
安政の五男 |
| 3.安清(やすずみ)〔従五位下、淡路守〕 分知により51000石 |
安照の長男 |
| 4.安興(やすおき)〔従五位下、淡路守〕 |
安清の三 |
| 5.安弘(やすひろ)〔従五位下、中務少輔〕 |
安興の長男 |
| 6.安実(やすざね)〔従五位下、伊勢守〕 |
安興の次男 |
| 7.安親(やすちか)〔従五位下、淡路守〕 |
正陳の四男 |
| 8.安董(やすただ)〔従四位下、中務大輔・侍従 老中〕 |
安親の次男 |
| 9.安宅(やすおり)〔従三位、中務大輔・侍従 老中〕 |
安董の長男 |
| 10.安斐(やすあや)〔正三位、淡路守〕 伊勢津藩の第11代藩主藤堂高猷の四男 |
廃藩置県
|
|
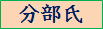
 |
伊勢国安濃郡分部村より起る。工藤祐経之六世孫、二郎右衛門高景が足利尊氏に仕え、
安濃郡長野地頭となる、曽孫四郎次郎光久に至り分部を称す。その弟、光恒も祖
分部氏は戦国時代、伊勢国中部を領していた長野氏の長野豊藤の五男・分部祐成から
始まる一族である。
|
分部 光嘉(わけべ みつよし)
| 北伊勢に勢力を持つ長野氏の一族、細野藤光の次男として生まれる。光嘉は豊臣家の直参となり、伊勢上野城1万石を領した。 |
| 関ヶ原の戦いでは徳川家康の会津征伐に従軍したが、西軍挙兵の報を受け急ぎ帰国し、富田信高と共に安濃津城を守備した。 |
| 安濃津城の戦いでは総勢3万の西軍に対して安濃津城に籠城する東軍はわずか1700という劣勢だったが、光嘉は毛利家臣の |
| 宍戸元次と双方重傷を負うほど奮闘し、西軍の攻撃をしのいだ。 |
分部 光信(わけべ みつのぶ
| 長野正勝の長男,関ヶ原の戦いの際には分部氏本家によって同じ東軍に属した富田信高への人質として差し出された。 |
| 慶長6年(1601年)から徳川氏に仕える。同年に先代藩主の光嘉が死去する。光嘉の長男・光勝は早世していたため、娘婿に |
| 当たる長野正勝の子で外孫にあたる光信が養嗣子として跡を継ぐこととなった。慶長19年(1614年)の大坂冬の陣では |
| 本多忠政に属して功を挙げ、翌年の夏の陣でも功を挙げたため、元和5年(1619年)8月に近江大溝藩に移封された。 |
| 1 |
伊勢
上野藩
|
外様 2万石 伊勢国
| 1.分部光嘉(みつよし) 従五位下、左京亮 |
細野藤光の次男 |
| 2.分部光信(みつのぶ) <従五位下。左京亮> |
長野正勝の長男 |
|
| 2 |
大溝藩
おおみぞ
|
外様 2万石 近江国
| 1.分部光信(みつのぶ |
|
|
| 2.分部嘉治(よしはる |
従五位下、伊賀守 |
光信の三男 |
| 3.分部嘉高(よしたか |
従五位下。若狭守 |
嘉治の長男 |
| 4.分部 信政(のぶまさ |
従五位下、隼人正、若狭守 池田長信(備中松山藩主・池田長幸の三男)の三男 |
| 5.分部光忠(みつただ |
従五位下、左京亮 |
信政の三男 |
| 6.分部光命(みつなり |
従五位下、和泉守、若狭守 |
光忠の長男 |
| 7.分部光庸(みつつね |
従五位下、隼人正、若狭守。 |
光命の長男 |
| 8.分部光賓(みつざね |
従五位下、左京亮 |
光庸の長男 |
| 9.分部光邦(みつくに |
従五位下、若狭 |
光賓の次男 |
| 10.分部光寧(みつやす |
従五位下、左京亮 |
光邦の長男 |
| 11.分部光貞(みつさだ |
従五位上、若狭守 |
上野国安中藩主・板倉勝尚の次男 |
| 12.分部光謙(みつのり |
従五位、従四位 |
光貞の次男 |
廃藩置県
|
|

 |
信濃村上氏(清和源氏頼清流)
清和源氏(河内源氏)頼清を祖とする信濃の国人領主。鎌倉時代から同国村上郷を領し、その後埴科郡を
拠点とする北信の有力国人領主として、建武2年(1335年)の中先代の乱では「信濃惣大将」として
鎮圧に当たった。天文22年(1553年)村上義清・国清親子は越後の上杉謙信を頼り、信濃村上氏は
終焉を迎える。このとき村上氏族のうち一部は、下総や上野等の周辺の国々に飛散したといわれる。
伊予村上氏(村上水軍)
瀬戸内海の豪族で、水軍を率いた。能島・来島・因島の三つの家の総称で「三島村上氏」とも呼ばれる。
上記の信濃村上氏の庶流で、保元の乱や平治の乱で活躍した村上為国の弟定国を祖とする説が
有力とされているが、鎌倉期から戦国期にかけての水軍村上氏の各種系図には不明な点も多く正確な
系譜は不明であり、他にも諸説ある。 |
村上 頼勝(むらかみ よりかつ)
| 信濃村上氏、伊予村上氏(村上水軍)の一族ともいわれるが、いずれも根拠に乏しく、詳細は不明である。はじめ丹羽長秀に |
| 仕えていたが、天正13年に長秀が死去すると、嫡男長重のもとから去って豊臣秀吉の直臣となり、加賀国能美郡に6万5000石を |
| 与えられた。その後、秀吉の命で堀秀政・秀治の与力大名となり、九州征伐、小田原征伐に従軍した。 |
| 慶長5年、関ヶ原の戦いでは東軍に与して越後に在国し、国内で起こった西軍方の上杉旧臣による一揆鎮定に努めた。 |
| その戦功により戦後、徳川家康から所領を安堵された。 |
| |
村上藩
|
外様 9万石 越後国
| 1.村上頼勝(よりかつ)(村上義明とも)<従五位下。周防守> |
|
| 2.村上忠勝(ただかつ)<従五位下。周防守> |
戸田内記の長男 |
元和4年、家臣の魚住角兵衛が暗殺されると、その黒幕が家老高野権兵衛ではとの風評が立ち
論争となる。幕府に報告して裁決されたが騒動が収まらず、家中の論争が多いとの理由で改易され
|
|

  |
清和源氏土岐氏流を称す。美濃土岐氏当主の土岐成頼の子の一人である定頼が領地を大桑
(現在の岐阜県山県市大桑)に持ったことから大桑氏を称し、後に船田合戦の功によって領を大畑
(岐阜県多治見市)に移した事により大畑氏を称す。そして定頼の子の大畑定近は後に近江国の
金森村に居を移し、金森姓を称したという。 |
金森 長近(かなもり ながちか)
| 大永4年(1524年)に美濃の多治見に生まれる。父・定近は土岐氏の後継者争いで土岐頼武を支持したが、 |
| 頼武は土岐頼芸に敗れて失脚し、定近も程なくして美濃を離れ近江国野洲郡金森へと移住した。 |
| 慶長5年、関ヶ原の戦いでは可重とともに東軍に与し、戦後、美濃郡上八幡城攻めなどの功を賞されて |
| 2万石を加増、初代高山藩主となる。 |
| 1 |
飛騨
高山藩
金森家 |
外様 3.3万石 飛騨国 (1586年 - 1692年)
| 1.長近(ながちか) |
飛騨守、兵部大輔 |
土岐成頼の次男 |
| 2.可重(よししげ) |
従五位下・出雲守 |
美濃国の長屋景重の子 |
| 3.重頼(しげより) |
従五位下・出雲守 〔御小姓〕 |
可重の三男 |
| 4.頼直(よりなお) |
従五位下、長門守 |
重頼の長男 |
| 5.頼業(よりなり) |
従五位下、飛騨守 |
頼直の長男 |
| 6.頼時(よりとき) |
従五位下出雲守 〔奥詰・側用人〕 |
頼業の長男 |
|
| 2 |
上山藩
|
外様 3.87万石 出羽国
|
| 3 |
郡上
八幡藩
|
外様 3.8万石 美濃国
| 1.金森頼時(よりとき) 従五位下 出雲守 |
|
| 2.金森頼錦(よりかね) 従四位下 兵部少輔 |
金森頼時の長男 可寛の子 |
(郡上一揆)が勃発した。さらに神社の主導権をめぐっての石徹白騒動まで起こって藩内は大混乱し、
この騒動は宝暦8年(1758年)12月25日、頼錦が幕命によって改易される。
|
|

 |
平岡 頼勝(ひらおか よりかつ)
永禄3年(1560年)、平岡頼俊の子として誕生。はじめ諸国を流浪する浪人であったが、豊臣秀吉に才能を
認められ、その家臣となった。関ヶ原の戦いにおいて長政と通じ、正成と共に主君・秀秋に東軍に寝返ること
勧めた。戦後は秀秋とは別に備前児島郡2万石を与えられ家老に任じられた。
|
| |
徳野藩
|
外様 1万石 美濃国
| 1.平岡頼勝(よりかつ) |
|
|
| 2.平岡頼資(よりすけ) |
従五位下、石見守 |
頼勝の長男 |
平岡氏は家督争いの他、頼重の不行跡等により、家督相続が認められず、改易
|
|

 |
徳永 寿昌(とくなが ながまさ)
はじめ柴田勝豊に仕え、天正11年(1583年)の賤ヶ岳の戦いでは羽柴秀吉に協力した。
後に豊臣秀次付の家老として美濃国松ノ木城に3万石の所領を与えられた。
関ヶ原の戦いでは東軍に与し、西軍に属した隣城高須城1万石の城主高木盛兼を攻めてこれを落とし、
また駒野城に篭城した池田秀氏を降伏させた。戦後、戦功により高須にて2万石を加増され、高須藩初代藩主
|
| |
高須藩
徳永家 |
外様 5万石 美濃国 1600年 - 1628年 岐阜県海津市
| 1.寿昌(ながまさ)〔従五位下、石見守〕 |
| 2.昌重(まさしげ)〔従五位下、左馬介〕 |
寿昌の長男 |
寛永5年(1628年)2月28日、大坂城石垣普請助役工事の遅延を理由に除封され、改易
|
|

 |
いくつかの血流があり、伊勢国の豪族で桓武平氏の平姓関氏及び、藤原秀郷を祖とする常陸国の
藤姓関氏、美濃国を根拠地とする美濃関氏などがある。
平姓関氏
伊勢国鈴鹿郡を本拠とした豪族。出自には諸説あり、『吾妻鏡』では伊勢平氏平維衡の五世の孫、
関信兼(出羽守)をもって祖とする説があり、実際は維衡の末裔とされる鎌倉時代の御家人である関実忠が
伊勢国鈴鹿郡関谷を賜り、関氏を称したのが初代と伝わり、実忠以降の数代の事跡は明らかでない。 |
関 一政(せき かずまさ)
関盛信(万鉄)の次男。父と共に織田信長、豊臣秀吉に仕え、天正12年の小牧・長久手の戦いに参加した。
関ヶ原の戦いでは、当初は西軍に属して尾張国犬山城を守備したが、後に東軍に寝返り、
本戦では井伊直政隊に属して功を挙げた。関氏の故地である伊勢亀山に復帰を許された。
| 1 |
伊勢亀山藩 |
外様 3万石 伊勢国
1.関一政(かずまさ)従五位下。長門守 |
| 2 |
黒坂藩 |
外様 5万石 伯耆国
1.関一政(かずまさ)従五位下。長門守
元和4年、家中における内紛を理由に幕命により改易され、黒坂藩は廃藩となった。
|
|
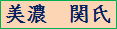
 |
源氏説
摂津源氏山県氏族。家祖は山県氏頼(兵庫)頭の三男氏昌(彦三郎)。
その八世孫の長重(十郎右衛門尉)は織田信長に仕え、近江桜馬場の陣や、対浅井戦で武功を飾ったという
これにより尾張一宮城主となり晴れて城持ちへと昇進した。
藤原氏説
藤原北家佐野氏族。その後裔の佐野師綱が美濃国武儀郡に一時的に居住していた時に生まれた子である
十郎太郎長綱を家祖と位置づける。長綱の子である小十郎は土岐頼遠に仕えたといい、
以後土岐家臣として美濃に土着。その後裔である綱長の代に土岐頼芸が没落した為に斎藤道三に仕え、
その子である長重の代に斎藤氏から織田信長に仕えた。
戦国期以降
長重の子である成政は織田信忠付きの家臣として活躍し、元亀3年(1572年)に同じ織田家臣の
兼山城主・森可成の娘と結婚し森家と血縁関係を持った。
長可亡き後は弟の忠政がその跡を継ぎ、関家は森家の家臣筋となった。 |
関成次(せき なりつぐ)
美作津山藩家老。津山藩第2代藩主森長継、宮川藩初代藩主関長政の実父。
関 長政(せき ながまさ)
慶長17年(1612年)、美作津山藩主・森忠政の重臣・関成次の次男として生まれる。兄・長継が第2代津山藩主として外祖父・忠政の
跡を継ぐと、兄より1.8万石を分与されて津山藩の支藩である宮川藩を立藩した。
| 1 |
宮川藩
関家 |
外様 1万8700石 備中国(1634年-1697年) 森家時代の津山藩の支藩
| 1.長政(ながまさ)〔従五位下、備前守〕 |
| 2.長治(ながはる)〔従五位下、備前守〕 |
森長継の六男 |
元禄10年(1697年)、本家森家の津山藩主・森長成が改易されたため、備中に
移封されて新見藩を立藩した。
|
| 2 |
新見藩
関家 |
外様 1万8000石 備中国 (1697年 - 1871年)
| 1.長治(ながはる)〔従五位下・備前守〕 |
|
| 2.長広(ながひろ)〔従五位下・但馬守〕 |
長治の兄長俊の次男 |
| 3.政富(まさとみ)〔従五位下・播磨守〕 |
長広の長男 |
| 4.政辰(まさとき)〔無冠(早世のため)〕 |
政富の次男 |
| 5.長誠(ながのぶ)〔従五位下・備前守〕 |
政富の長男 |
| 6.長輝(ながてる)〔従五位下・但馬守 隠居後、備前守〕 |
長誠の長男 |
| 7.成煥(しげあきら)〔従五位下・大蔵少輔 隠居後、備前守〕 |
長輝の長男 |
| 8.長道(ながみち)〔従五位下・備前守〕 |
長誠の次男 |
| 9.長克(ながかつ)〔従五位下・備前守〕 |
長輝の次男 |
廃藩置県
|
|

 |
糠部郡蠣崎(青森県むつ市川内町)を領して蠣崎氏(かきざきし)を称する家系があり、
その子孫との説がある。
蠣崎氏/松前氏は、、戦国時代から蝦夷地を本拠とした大名。江戸時代には松前氏と改姓したが、
庶流の中には引き続き蠣崎氏と名乗る者もいた。
本姓は源氏。家系は清和源氏(河内源氏)義光流で甲斐源氏の庶流にあたる。 |
松前 慶広(まつまえ よしひろ
天文17年9月3日(1548年)、蠣崎季広の三男として大館(松前)の館山城で生まれる。天正18年豊臣秀吉が
小田原征伐を終え |
奥州仕置をはじめると、主家安東実季の上洛に蝦夷地代官として帯同した。慶広は前田利家らに取りいって、同年12月
|
| (1591年1月)、 豊臣秀吉に謁見を果たすと、所領を安堵と同時に従五位下・民部大輔に任官された。 |
| 慶長3年(1598年)に秀吉が死去すると、徳川家康と誼を通じた。家康の臣従を示すものとして「蝦夷地図」を献上した。 |
| また、姓を家康の旧姓の「松平」と前田利家の「前」をとって松前に改めた。 |
| |
松前藩
|
| 1.松前 慶広(よしひろ) |
従五位下、民部大輔、志摩守 |
蠣崎季広の三男 |
| 2.松前 公広(きんひろ) |
従五位下、志摩守 |
松前盛広の長男 |
| 3.松前 氏広(うじひろ) |
官位無し |
公広の次男 |
| 4.松前 高広(たかひろ) |
官位無し |
氏広の長男 |
| 5.松前 矩広(のりひろ) |
従五位下、志摩守 |
高広の長男 |
| 6.松前 邦広(くにひろ) |
従五位下、志摩守 |
松前本広の六男 |
| 7.松前 資広(すけひろ) |
従五位下、若狭守 |
邦広の長男 |
| 8.松前 道広(みちひろ) |
従五位下、美作守、志摩守 |
資広の長男 |
| 9.松前 章広(あきひろ) |
従五位下、若狭守 |
道広の長男 |
| 10.松前 良広(よしひろ |
第9代藩主・松前章広の次男・松前見広の長男 |
| 11.松前 昌広(まさひろ) |
従五位下、志摩守 第9代藩主・松前章広の次男・松前見広の次男 |
| 12.松前 崇広(たかひろ) |
伊豆守、従四位下 |
章広の六男 |
| 13.松前 徳広(のりひろ) |
従五位下、志摩守、贈従四位 |
昌広の長男 |
| 14.松前 修広(ながひろ) |
従五位 |
徳広の長男 |
廃藩置県 |
|
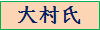
 |
大村氏の系図や史書では、先祖は藤原純友の孫・藤原直澄とされている。
直澄が正暦5年(994年)に伊予から肥前に入部し、肥前大村を本拠として領主化したのが
始まりだとされている。また一説には、平清盛の祖父・平正盛の追討を受けた肥前藤津領主・平直澄
(平清澄の子)が先祖であるとされる。
戦国時代
戦国時代に入ると大村氏の勢力は急速に衰え、文明6年(1474年)から文明12年(1480年)にかけて、
大村純伊は有馬貴純によって大村から追放された。大村純忠は日本最初のキリシタン大名である。
天正15年(1587年)に純忠は死去し、嫡男の大村喜前が後を継いだ。 |
大村 喜前(おおむら よしあき
| 永禄12年(1569年)、大村純忠の長男として誕生。関ヶ原の戦いでは、東軍に就いたために所領を安堵された。 |
| ドン・サンチョという洗礼名を持つキリシタンであったが、慶長7年(1602年)、熱狂的な日蓮宗徒であった、加藤清正の薦めもあって |
キリスト教を捨てて日蓮宗に改宗し、領内におけるキリシタンを弾圧した。このため元和2年(1616年)、それを恨んだキリスト教徒に
よって毒殺されたという。 |
| |
大村藩
大村家 |
外様 2.79万石 肥前国
| 1.喜前(よしあき)〔従五位下、丹後守〕 |
1587-1616 |
純忠の長男 |
| 2.純頼(すみより)〔従五位下、民部大輔〕 |
1616-1619 |
喜前の長男 |
| 3.純信(すみのぶ)〔従五位下、丹後守〕 |
1620-1650 |
純頼の長男 |
| 4.純長(すみなが)〔従五位下、因幡守〕 |
1651-1706 甲斐国徳美藩主・伊丹勝長の四男 |
| 5.純尹(すみまさ)〔従五位下、筑後守〕 |
1706-1712 |
純長の次男 |
| 6.純庸(すみつね)〔従五位下、伊勢守〕 |
1712-1727 |
純長の四男 |
| 7.純富(すみひさ)〔従五位下、河内守〕 |
1727-1748 |
純庸の次男 |
| 8.純保(すみもり)〔従五位下、弾正少弼〕 |
1748-1760 |
純富の長男 |
| 9.純鎮(すみやす)〔従五位下、信濃守〕 |
1761-1803 |
純保の次男 |
| 10.純昌(すみよし)〔従五位下、丹後守〕 |
1803-1836 |
純鎮の長男 |
| 11.純顕(すみあき)〔従五位下、丹後守〕 |
1836-1847 |
純昌の四男 |
| 12.純熈(すみひろ)〔従五位下、丹後守 長崎奉行〕 |
1847-1871 |
純昌の十男 |
廃藩置県
|
|

 |
亀井氏は紀伊国亀井を発祥とし、宇多源氏の佐々木氏の流れを汲むとされるが、信憑性に乏しく、
穂積姓鈴木氏流とする説もある。尼子氏が毛利氏に滅ぼされると豊臣秀吉に仕えて因幡国気多郡鹿野に
1万3500石を領することになる。慶長5年の関ヶ原の戦いにおいては東軍に属し、3万8000石に加増された。 |
亀井 茲矩(かめい これのり)
| 1557年、尼子氏の家臣・湯永綱の長男として出雲国八束郡湯之荘(現在の島根県松江市)に生まれる。 |
| 本能寺の変後の秀吉の中国大返しの際には後詰めとして鹿野城に残留し、毛利氏への牽制・監視役 |
| を果たした。秀吉死後は徳川家康に接近し、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは徳川方に与して |
| 山名豊国を従えて最前衛で戦った。 |
| 1 |
鹿野藩
しかの
亀井家 |
外様 3.8万石→4.3万石 因幡国 (1600年 - 1617年)
| 1.茲矩(これのり)〔従五位下・武蔵守〕 |
尼子氏の家臣・湯永綱の長男 |
| 2.政矩(まさのり)〔従五位下・豊前守〕4万3000石に加増 |
茲矩の次男 |
|
| 2 |
津和野藩
亀井家 |
外様 4.3万石 石見国 (1618年 - 1871年)
| 1.政矩(まさのり)〔従五位下・豊前守〕 |
茲矩の次男 |
| 2.茲政(これまさ)〔従五位下・豊前守〕 |
政矩の次男 |
| 3.茲親(これちか)〔従五位下・隠岐守〕 |
茲政の三男 |
| 4.茲満(これみつ)〔従五位下・因幡守〕 |
茲親の六男 |
| 5.茲延(これのぶ)〔従五位下・豊前守〕 |
茲長の長男 |
| 6.茲胤(これたね)〔従五位下・隠岐守〕 常陸府中藩第3代藩主・松平頼明の五男 |
| 7.矩貞(のりさだ)〔従五位下・能登守〕 旗本菅沼定好(第3代藩主亀井茲親の次男)の次男 |
| 8.矩賢(のりかた)〔従五位下・隠岐守〕 |
矩貞の長男 |
| 9.茲尚(これなお)〔従五位下・大隅守〕 |
矩貞の三男 |
| 10.茲方(これかた)〔従五位下・能登守〕 |
茲尚の三男 |
| 11.茲監(これみ)〔従五位下・隠岐守〕 |
頼徳の六男 |
廃藩置県
|
|
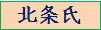
 |
北条氏の祖は、関東地方で勢威を振るった北条早雲である。しかし北条氏は天正18年(1590年)、豊臣秀吉の
小田原征伐により滅亡してしまう。戦後の処罰により、北条氏第4代当主・北条氏政と北条氏照は戦争責任を
問われ切腹となったが、第5代当主・北条氏直は徳川家康の娘婿であるという所以から、北条氏規
(北条氏康の五男で氏政、氏照の弟)は和平に尽力し、特別に許され、高野山での蟄居を命じられた。
天正19年(1591年)、氏直は嗣子無くして30歳の若さで死去した。このため、北条氏の嫡流は断絶したが、
氏規がその跡を継いで後北条氏の当主となる。慶長5年1600年、氏規が没すると氏盛はその家督と
遺領を継いで1万1,000石の大名となる。これが狭山藩の始まりである。 |
北条 氏盛(ほうじょう うじもり
父は北条氏政の弟である氏規であり、宗家氏直に継いで宗家となり、豊臣秀吉の小田原征伐によって後北条氏が滅亡した後、
父と共に高野山に向かったが、やがて秀吉に許され、天正19年(1591年)、養父氏直が病死するとその遺跡である下野4千石の
所領を与えられた。翌天正20年(1592年)、朝鮮出兵で肥前名護屋に従軍した。
関ヶ原の戦いでは東軍の西尾吉次隊に属し本領安堵、家康の将軍就任後は徳川氏へ仕えた。
| |
狭山藩
北条家 |
外様 1万1,000石→1万石 河内国
| 1.氏盛(うじもり)〔従五位下、美濃守〕 |
北条氏規の長男 |
| 2.氏信(うじのぶ)〔従五位下、美濃守〕 |
氏盛の長男 |
| 3.氏宗(うじむね)〔官位官職なし〕 |
氏信の長男 |
| 4.氏治(うじはる)〔従五位下、美濃守〕 |
北条氏利の次男 |
| 5.氏朝(うじとも)〔従五位下、遠江守〕 |
北条氏利の3男 |
| 6.氏貞(うじさだ)〔従五位下、美濃守〕 |
氏朝の長男 |
| 7.氏彦(うじひこ)〔従五位下、遠江守〕 |
氏貞の長男 |
| 8.氏昉(うじあきら)〔従五位下、相模守〕 |
氏彦の長男 |
| 9.氏喬(うじたか)〔従五位下、遠江守〕 |
氏昉の長男 |
| 10.氏久(うじひさ)〔従五位下、相模守〕 |
美濃国大垣藩主・戸田氏庸の三男 |
| 11.氏燕(うじよし)〔従五位下、遠江守〕 |
北条氏喬の弟・北条氏迪の次男 |
| 12.氏恭(うじゆき)〔従五位下、相模守〕 |
下野国佐野藩主・堀田正衡の三男 |
廃藩置県
|
玉縄北条氏
北条 氏時:伊勢盛時(北条早雲)の子、北条氏綱の弟、初代玉縄城主で 玉縄北條の祖である。
北条 康成/北条 氏繁:天文5年(1536年)、後北条氏の家臣・北条綱成の嫡男として誕生
岩富藩の北条家は譜代大名となる
|


|
岩城氏は常陸平氏の血を汲む名族であり、その子孫が陸奥国南部(現在の浜通り夜ノ森以南)に
土着したことが岩城氏の始まりであると言われているが、常陸平氏とは別系統で石城国造の末裔である
とも言われている。戦国時代に入ると、近隣戦国大名である相馬氏や田村氏との抗争が激化し、
さらに伊達氏、蘆名氏、佐竹氏などの勢力が強まったため、その狭間で岩城氏の影響力は減退した。
豊臣秀吉の小田原征伐が勃発すると、岩城常隆は小田原に参陣することで、所領を安堵された。
常隆は小田原征伐直後に病死し、子(政隆)が幼少であったため、常隆の後継には佐竹義重の
三男・岩城貞隆が継いだ。 |
岩城 貞隆(いわき さだたか)
| 天正11年(1583年)、佐竹義重の三男として生まれる。常隆の養嗣子となり、天正18年(1590年)に常隆が病死したため、家督を |
| 継ぐこととなった。関ヶ原の戦いでは当初は東軍方についたが、兄の佐竹義宣の命に従って上杉景勝征伐に参加しなかった |
| ため、戦後の慶長7年(1602年)に義宣と共に処分を下された。大坂夏の陣で正信に従って従軍し、戦功を挙げたため、 |
| 元和2年(1616年)に信濃中村に1万石を与えられ、大名として復帰した。伊達政宗、岩城常隆は従兄弟にあたる。 |
| 1 |
信濃
中村藩
岩城家 |
外様 1万石→2万石 信濃国
| 1.貞隆 |
|
佐竹義重の三男 |
| 2.吉隆 |
従四位下・左近衛少将 |
貞隆の長男 |
|
| 2 |
亀田藩
|
外様、2万石 羽後国
| 1.岩城吉隆(佐竹義隆) |
従四位下・左近衛少将 |
1623-1628 |
| 2.岩城宣隆のぶたか |
従五位下、但馬守 |
1628-1656 |
佐竹義重の四 |
| 3.岩城重隆しげたか |
従五位下伊予守 |
1656-1704 |
宣隆の長男 |
| 4.岩城秀隆ひでたか |
従五位下、伊予守 |
1704-1718 |
景隆の長男 |
| 5.岩城隆韶たかつぐ |
従五位下、但馬守、河内守 |
伊達村興(第5代藩主伊達吉村の弟)の子 |
| 6.岩城隆恭たかよし |
従五位下、伊予守、左京亮 |
岩谷堂伊達家第5代当主・伊達村望の子 |
| 7.岩城隆恕たかのり |
|
|
隆恭の次男 |
| 8.岩城隆喜たかひろ |
従五位下、伊予守 |
|
隆恕の長男 |
| 9.岩城隆永たかなが |
従五位下、但馬守 |
|
隆喜の四男 |
| 10.岩城隆信たかのぶ |
|
|
隆喜の五男 |
| 11.岩城隆政たかまさ |
従五位下、修理大夫 |
|
隆喜の六男 |
| 12.岩城 隆邦 たかくに |
従五位下、左京大夫、従三位 |
|
隆喜の七男 |
| 13.岩城 隆彰 たかあき |
|
近江宮川藩主・堀田正誠の三男 |
廃藩置県
|
|

  |
秋月氏の祖は、平安時代に伊予で反乱を起こした藤原純友を討伐した大蔵春実である。
平安時代後期から九州に土着した松浦氏や蒲池氏など他の豪族と同じく秋月氏も平家の家人だったが、
源平合戦においては源氏方に与したため、鎌倉幕府の鎮西御家人となった。しかし源頼朝からの信頼は薄い、
戦国時代に入ると、少弐氏の家臣となったが、少弐氏が大内義隆と争って敗れたため、大内氏の家臣となる。
島津義久と手を結んで大友氏に対して反抗し、一時期は筑前に六郡、筑後に四郡、豊前に一郡と
推定36万石にも及ぶという広大な所領を築き上げ、秋月氏の最盛期を現出する。
関ヶ原の戦いで、種実の子・秋月種長は西軍に属して大垣城を守備していたが、9月15日の本戦で西軍が
敗れると東軍に内応して大垣城にて反乱を起こし、木村由信らを殺害した。戦後、その功績を認められて
徳川家康から所領を安堵され、その後の秋月氏は江戸時代を通じて、高鍋藩として存続した。 |
秋月 種長(あきづき たねなが)
| 永禄10年(1567年)2月7日、筑前の戦国大名である秋月種実の長男として生まれる。天正14年の豊臣秀吉の九州征伐では |
| 父と共に豊臣軍と戦ったが、敗れて父と共に降伏した。関ヶ原の戦いでは、西軍に属して大垣城を守備していたが、 |
| 関ヶ原の本戦で西軍が壊滅した直後守将の福原長堯は大垣城を開城して東軍に明け渡した。 |
| これによって徳川家康から所領を安堵され、高鍋藩の初代藩主となった。 |
| |
高鍋藩
秋月家 |
外様 3万石→2.7,万石 日向国
| 1.種長(たねなが)〔従五位下、長門守〕 |
秋月種実の長男 |
| 2.種春(たねはる)〔従五位下、長門守〕 藩主・秋月種長の甥・秋月種貞と種長の娘の長男 |
| 3.種信(たねのぶ)〔従五位下、佐渡守〕 |
種春の長男 |
| 4.種政(たねまさ)〔従五位下、山城守〕分与により27,000石 |
種信の次男 |
| 5.種弘(たねひろ)〔従五位下、長門守〕 |
種政の長男 |
| 6.種美(たねみつ)〔従五位下、長門守〕 |
種弘の長男 |
| 7.種茂(たねしげ)〔従五位下、山城守〕 |
種美の長男 |
| 8.種徳(たねのり)〔従五位下、山城守〕 |
種茂の長男 |
| 9.種任(たねただ)〔従五位下、筑前守〕 |
種徳の次男 |
| 10.種殷(たねとみ)〔従五位下、長門守〕 |
種任の長男 |
廃藩置県
|
|
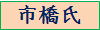
 |
大和源氏の祖となった源頼親の末裔と伝わる。
戦国時代中期、長利が美濃の覇権を掌握した斎藤道三に従い、道三の没後は義龍、龍興に従うが
、尾張より織田信長が攻めてくると信長に通じてその側近となる。信長没後、長勝は天下の覇権を
握った豊臣秀吉に従い、美濃の今尾で1万石の所領を与えられて大名に列した。秀吉没後は
徳川家康に接近。
関ヶ原の戦いでは東軍(徳川方)に従い、功績により伯耆矢橋藩2万1000石に加増された。 |
市橋 長勝(いちはし ながかつ)
美濃の豪族であった市橋長利の長男。関ヶ原の戦いでは東軍に与して、西軍に属した丸毛兼利の福束城を
落とす武功を挙げた。戦後今尾城で1万石を加増されている。
| 1 |
今尾藩
|
外様 1万石 美濃国
| 1.市橋長勝(ながかつ) |
従五位下、下総守 |
市橋長利の長男 |
|
| 2 |
矢橋藩
やばし
|
外様 2.13万石 伯耆国
| 1.市橋長勝(ながかつ) |
従五位下、下総守 |
市橋長利の長男 |
|
| 3 |
三条藩
|
外様 4万1300石→2万石 越後国
| 1.市橋長勝(ながかつ) |
従五位下、下総守 |
市橋長利の長男 |
| 2.市橋長政(ながまさ) |
従五位下・下総守。伊豆守 |
林右衛門左衛門の三男 |
|
| 4 |
仁正寺藩
にしょうじ
|
外様 2万石→1.8万石→1.7万石 近江国
| 1.市橋長政(ながまさ |
従五位下・下総守。伊豆守 |
林右衛門左衛門の三男 |
| 2.市橋政信(まさのぶ |
従五位下。下総守 市橋政直(第2代藩主・市橋政信の弟)の長男 |
| 4.市橋直方(なおかた |
従五位下。壱岐守 越後新発田藩主・溝口重雄の次男 |
| 5.市橋直挙(なおたか |
従五位下。下総守 立花種盈(筑後三池藩主・立花種明の次男)の長男 |
| 6.市橋長輝(ながてる |
従五位下、伊豆守 |
豊後臼杵藩主・稲葉菫通の次男 |
| 7.市橋長昭(ながあき |
従五位下、下総守 |
長璉の長男 |
| 8.市橋長発(ながはる |
従五位下。伊豆守 |
長昭の長男 |
| 9.市橋長富(ながとみ |
従五位下主殿頭 |
出羽庄内藩主・酒井忠徳の四男 |
| 10.市橋長和(ながかず |
正五位。正四位。壱岐守。下総守 |
出羽庄内藩主・酒井忠器の四男 |
廃藩置県
|
|
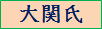
 |
桓武平氏大掾流小栗氏の子孫と称したが、後世の仮冒の可能性が高く、実際は出自は武蔵七党丹党流の
出身という。下野の那須氏の家臣として上那須地方に拠り、那須七党と呼ばれる存在となった。
秀吉の小田原征伐には主家の那須氏を見限りいち早く参陣し、主家が改易の憂き目を見るのをよそに所領を
安堵された。高増の三男大関資増は関ヶ原の戦いで東軍に付き活躍。その後黒羽藩の藩祖となり、
以後幕末まで存続した。
|
大関 資増(おおぜき すけます)
| 慶長元年(1596年)、兄・大関晴増が死を間近に迎えた際に嫡子である大関政増が幼少であった事から後継に弟の資増が |
| 指名され家督を相続した。関ヶ原の戦いの時には徳川家康の東軍に属し、上杉景勝の抑えとして領地の黒羽が陸奥国の境に |
| あるという事を重要視され、榊原康政の家臣の伊奈主水が黒羽城の修造を行った。家康より宇多国宗の刀と金100両を賜った。 |
| |
黒羽藩
くろはね
大関家 |
外様 2万石→1.8万石 下野国 栃木県大田原
| 1.資増(すけます) |
|
|
| 2.政増(まさます) |
|
資増の長兄、晴増の長男 |
| 3.高増(たかます) |
従五位下、土佐守 |
政増の長男 |
| 4.増親(ちかます) 従五位下、土佐守 分知により18,000石 |
高増の長男 |
| 5.増栄(ますなが) |
従五位下、信濃守 |
高増の次男 |
| 6.増恒(ますつね) |
従五位下、信濃守、能登守 |
増栄の世子・増茂の庶長子 |
| 7.増興(ますおき) |
従五位下、伊予守、能登守 |
増恒の次男 |
| 8.増備(ますとも) |
従五位下、因幡守 |
増興の長男 |
| 9.増輔(ますすけ) |
従五位下、伊予守 |
増備の長男 |
| 10.増陽(ますはる) |
従五位下、美作守 |
増輔の長男 |
| 11.増業(ますなり) |
従五位下、土佐守 |
伊予国大洲藩主・加藤泰?の八男 |
| 12.増儀(ますのり) |
従五位下、伊予守 |
増陽の次男 |
| 13.増昭(ますあきら) |
従五位下、信濃守 |
増儀の次男 |
| 14.増徳(ますよし) |
従五位下能登守 丹波篠山藩主・老中青山忠良の五男 |
| 15.増裕(ますひろ) |
従五位下、肥後守 遠江横須賀藩主・西尾忠善の子の西尾忠宝の三男 |
| 16.増勤(ますとし) |
従五位下、美作守 |
丹波山家藩主谷衛滋の庶子 |
廃藩置県
|
|
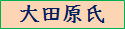
  |
武蔵七党の丹党の一族である安保氏の分流とされ阿保忠清が大俵氏の初代であると伝承されている。
戦国時代に入り、康清の子、大田原胤清とその子、大田原資清の時代になると、大田原氏は貪婪な
野望を抱くようになる。豊臣秀吉が北条氏を攻めると、いち早く、大田原晴清は豊臣秀吉に従い、
その領地を保全し、那須氏には時期尚早として秀吉に従うことの非を唱えた。
|
大田原 晴清(おおたわら はるきよ)
関ヶ原の戦いでは東軍に属し、上杉景勝の領地の様子を諜報し徳川家康に報告を入れている。
家康から正恒の太刀と黄金100両、秀忠から金熨斗付きの長船師光の刀を与えられた。
下野国芳賀郡・那須郡、陸奥国磐城郡に加増され、合わせて1万2,400石を領する大名となり大田原藩を立藩
| |
大田原藩
大田原家 |
外様 1.2万石→1.1万石 下野国 那須郡 大田原城
| 1.晴清(はるきよ)〔従五位下・備前守〕 |
縄清の子 |
| 2.政清(まさきよ)〔従五位下・備前守〕 |
晴清の長男 |
| 3.高清(たかきよ)〔従五位下・山城守〕分知により1万1,000石 |
政清の長男 |
| 4.典清(のりきよ)〔従五位下・備前守〕 大和戒重藩主・織田長政の次男・織田政時の長男 |
| 5.純清(すみきよ)〔従五位下・和泉守〕 |
典清の子 |
| 6.清信(きよのぶ)〔従五位下・備前守〕 第2代藩主・大田原政清の三男・織田吉清の長男 |
| 7.扶清(すけきよ)〔従五位下・飛騨守〕 第2代藩主・大田原政清の六男・大田原晴川の長男 |
| 8.友清(ともきよ)〔従五位下・出雲守〕 |
扶清の六男 |
| 9.庸清(つねきよ)〔従五位下・山城守〕 |
友清の次男 |
| 10.光清(みつきよ)〔従五位下・山城守〕 |
庸清の長男 |
| 11.愛清(よしきよ)〔従五位下・飛騨守〕 |
庸清の三男 |
| 12.広清(ひろきよ)〔従五位下・出雲守〕 |
愛清の次男 |
| 13.富清(とみきよ)〔従五位下・飛騨守〕 丹波綾部藩の第9代藩主・九鬼隆都の次男 |
| 14.一清(かずきよ)〔従五位下・飛騨守〕 |
富清の長男 |
廃藩置県
|
|

  |
清和源氏満快流。信濃国伊那郡片切郷より発祥した。一族は平安末期には河内源氏嫡流家の
郎党として従軍した。 |
| 従軍した。源為基に始まる豪族・片切氏の一族と伝える。その後、為頼の代に近江国に移住し、 |
伊香郡高月村(現・滋賀県長浜市)に土着する。為頼の子孫にあたる戦国時代の当主片桐直貞は
|
| 北近江の戦国大名である浅井氏の家臣となり、その子且元は浅井氏の滅亡後に賤ヶ岳の |
| 七本槍の一人として豊臣政権下で頭角を現し摂津国茨木に1万石を与えられて諸侯に列した。 |
そして関ヶ原の戦いの後に大和国竜田藩へ移封され、大坂の陣の後には4万石に加増されるが、
且元の子孝利には嗣子はなく、且元・四男為元が継ぐが後に断絶した。 |
|
片桐 且元(かたぎり かつもと)
| 戦国時代から江戸初期にかけての武将、奉行、大名。賤ヶ岳の七本槍の1人。豊臣家より豊臣姓を許される。 |
| 近江国浅井郡須賀谷(滋賀県長浜市須賀谷)の浅井氏配下の国人領主・片桐直貞の長男として生まれる。 |
| 関ヶ原の戦いでは文治派奉行衆を中心とした石田三成方・西軍に付き、秀政、頼明、弟の貞隆などの旗本も加わる大津城の |
戦いに、増田長盛と同じく家臣を派遣した[10]が、武断派武将らを中心に支持を得た家康方・東軍勝利の後は、長女を家康への
|
人質に差し出し、豊臣と徳川両家の調整に奔走し、逆に家康から播磨・伊勢国の所領6,000石と引替に
大和国竜田藩2万4千石を与えられる |
| |
竜田藩
くろはね
片桐家 |
外様 1万石→2万8000石→4万石→1万石 大和国
| 1.片桐且元(かつもと) |
従五位下、東市正 |
片桐直貞の長男 |
| 2.片桐孝利(たかとし) |
従五位下、出雲守 |
且元の次男 |
| 3.片桐為元(ためもと) |
|
且元の四男 |
| 4.片桐為次(ためつぐ) |
|
為元の長男 |
15歳の若さで死去した。嗣子がなく、ここに竜田藩は無嗣改易となった。 |
片桐 貞隆(かたぎり さだたか)
| 片桐直貞の次男で、片桐且元は兄である。21歳の時に兄と共に豊臣秀吉に仕え、播磨国に150石の所領を関ヶ原の戦いでは |
| 西軍に就いて大津城の戦いに加わったが、所領は安堵された。慶長19年の方広寺鐘銘問題を契機に徳川家康との内通を |
| 疑われるようになり、兄と共に豊臣氏の下を去って家康に仕えるようになり、大坂夏の陣の後、1615年、大和国小泉に |
| 1万6千石を知行された。 |
| |
小泉藩
片桐家 |
外様 1万石→→1.6万石→1.3万石→1.1万石 大和国
| 1.貞隆〔従五位下 主膳正〕 |
|
| 2.貞昌〔従五位下 石見守〕 |
茶道石州流の祖貞隆の長男 |
| 3.貞房〔従五位下 主膳正〕 |
貞昌の三男 |
| 4.貞起〔従五位下 石見守〕 松田貞尚(第3代藩主・片桐貞房の弟)の次男 |
| 5.貞音〔従五位下 主膳正〕 |
貞起の次男 |
| 6.貞芳〔従五位下 石見守〕 |
貞音の長男 |
| 7.貞彰〔従五位下 主膳正〕 |
貞芳の長男 |
| 8.貞信〔従五位下 石見守〕 |
貞彰の長男 |
| 9.貞中〔従五位下 主膳正〕 |
貞信の長男 |
| 10.貞照〔従五位下 石見守〕 |
貞信の四男 |
| 11.貞利〔官位なし〕 美濃国高富藩主・本庄道美の次男 |
| 12.貞篤〔従五位下 主膳正〕 松平頼功(常陸石岡藩主・松平頼縄の弟)の長男 |
廃藩置県
|
|

 |
九鬼氏(くきし)は南北朝時代から江戸末期まで活躍した一族。江戸時代に作成した家系図には藤原氏の
末裔と記したが明確にはわかっていない。九鬼氏は熊野で勢力を伸ばせずにおり、3代目隆房の次男の
九鬼隆良は新天地を求め戦国時代初期、九鬼氏は伊勢北畠氏に仕えていたが、伊勢北畠氏の勢力範囲が
弱まると、織田信長の幕下に入った。信長没後は織田信雄に仕えたが、蟹江城合戦にて羽柴秀吉方に寝返り、
天正13年、従五位下・大隅守に叙位・任官された。関ヶ原の戦いでは、石田三成挙兵の報を受け、徳川家康の
上杉討伐に参加していた守隆は急遽志摩に戻る。そして西軍方で桑名城に篭城した氏家行広・行継らを
破り、東軍最初の勝報を挙げた。 |
九鬼 守隆(くき もりたか)
天正元年(1573年)、九鬼嘉隆の次男として生まれる。慶長2年(1597年)、嘉隆から家督を継ぐ。慶長5年(1600年)には徳川家康の
会津征伐に従軍した。鳥羽藩の初代藩主として5万6000石を領した。九鬼水軍を率いて大坂の陣を戦い、江戸城の築城時は
木材や石材を海上輸送して幕府に協力した
| 1 |
鳥羽藩
九鬼家 |
外様 3.5万石→5.5万石→5.6万石 志摩国
| 1.九鬼守隆(もりたか) 従五位下 長門守 |
相続と同時に摂津国三田藩へと転封 |
守隆の五男 |
九鬼 良隆は守隆の長男で病弱のため、家督を継ぐことなく廃嫡された。同年、父守隆が死去し家督相続を
巡って、三弟・隆季と末弟・久隆の争いとなる。幕府からその責任を問われて久隆は志摩鳥羽から
摂津三田3万6,000石に減転封、隆季は丹波綾部藩2万石に移され、祖父嘉隆以来の水軍力を失った。
|
| 2 |
三田藩
さんだ
九鬼家 |
外様 3.6万石 摂津国 (1632年 - 1871年)
| 1.久隆(ひさたか)〔従五位下、大和守〕 |
守隆の五男 |
| 2.隆昌(たかまさ)〔従五位下、長門守〕 |
久隆の長男 |
| 3.隆律(たかのり)〔従五位下、和泉守〕 |
因幡鳥取藩主池田光仲の三男 |
| 4.副隆(すえたか)〔従五位下、長門守〕 大和柳生藩主柳生宗冬の嫡子柳生宗春の次男 |
| 5.隆久(たかひさ)〔従五位下、大和守〕 大和柳生藩主柳生宗在の長男 |
| 6.隆抵(たかやす)〔従五位下、丹後守 |
大身旗本戸田忠章の次男 |
| 7.隆由(たかより)〔従五位下、伊勢守〕 |
丹波綾部藩主九鬼隆寛の次男 |
| 8.隆邑(たかむら)〔従五位下、長門守〕 |
丹波綾部藩主九鬼隆寛の三男 |
| 9.隆張(たかはる)〔従五位下、長門守〕 |
隆邑の長男 |
| 10.隆国(たかくに)〔従五位下、和泉守〕 |
隆張の長男 |
| 11.隆徳(たかのり)〔従五位下、長門守〕 |
隆国の長男 |
| 12.精隆(きよたか)〔従五位下、長門守〕 |
隆徳の長男 |
| 13.隆義(たかよし)〔従五位下、長門守〕 |
丹波綾部藩主・九鬼隆都の三男 |
廃藩置県
|
九鬼 隆季(くき たかすえ
慶長13年(1608年)、初代志摩鳥羽藩主・九鬼守隆の三男として生まれる。九鬼水軍で知られる九鬼嘉隆の孫にあたる。
父・守隆の死後、弟・久隆との間で家督争いが生じ、藩内を二分する騒ぎとなったが、江戸幕府は遺言書に基づき久隆がこれを
相続するものと裁可を下した。ただし、隆季にも2万石を与え、寛永10年3月5日に丹波綾部へ転封とし綾部藩を立藩した。
| |
綾部藩
あやべ
|
外様 2万石→1.95万石 丹波国
| 1.九鬼隆季(たかすえ |
従五位下。式部少輔 |
志摩鳥羽藩主・九鬼守隆の三男 |
| 2.九鬼隆常(たかつね |
従五位下、大隅守 |
隆季の長男 |
| 3.九鬼隆直(たかなお |
従五位下、豊前守、長門守 |
大身旗本・松平信定の十一男 |
| 4.九鬼隆寛(たかのぶ |
従五位下、備前守、大隅守 |
播磨国林田藩主・建部政周の三男 |
| 5.九鬼隆貞(たかさだ |
従五位下。式部少輔 |
隆寛の四男 |
| 6.九鬼隆棋(たかよし |
従五位下、大隅守 |
遠江相良藩主・田沼意次の七男 |
| 7.九鬼隆郷(たかさと |
従五位下、式部少輔 |
隆貞の三男 |
| 8.九鬼隆度(たかのり |
従五位下、出雲守、河内守 |
隆郷の長男 |
| 9.九鬼隆都(たかひろ |
従五位下、大隅守、式部少輔 |
隆郷の次男 |
| 10.九鬼隆備(たかとも |
従五位上、大隅守 |
隆都の長男 |
廃藩置県
|
|

 |
工藤氏流六郷氏は、羽後国仙北郡六郷邑を本拠とした武家。本姓は藤原氏。羽後国仙北郡六郷邑より起る。
本姓は藤原氏。羽後国仙北郡六郷邑より起る。
二階堂行貞の孫・行光の系統であり、二階堂晴泰(はるやす)は足利義晴から偏諱を賜ってってその名を称し
その孫・通行(みちゆき)の代に六郷と称す。
|
六郷 政乗(ろくごう まさのり)
| 永禄10年(1567年)、六郷道行の長男として生まれる。天正15年(1587年)、出羽国横手城の小野寺義道の配下(仙北七人衆)に属し |
| 秋田実季と戦った。天正18年(1590年)、豊臣秀吉の小田原征伐に参陣したため出羽国内にあった4,500石の所領を安堵された |
| 関ヶ原の戦いでは東軍に与し、西軍に与した小野寺氏を攻撃した。戦後の慶長7年(1602年)、その功績により常陸府中1万石の |
| 所領を加増移封された。 |
| 1 |
常陸府中藩
六郷家 |
外様 1万石 常陸国
| 1.六郷政乗(まさのり) 従五位下 兵庫頭 |
六郷道行の長男 |
|
| 2 |
本荘藩
六郷家 |
外様 2万石 羽後国
| 1.政乗(まさのり) 従五位下。兵庫頭 |
|
| 2.政勝(まさかつ) 従五位下。伊賀守 |
政乗の長男 |
| 3.政信(まさのぶ) 従五位下。佐渡守 |
政勝の長男 |
| 4.政晴(まさはる) 従五位下。伊賀守 |
政信の長男 |
| 5.政長(まさなが) 従五位下。伊賀守 |
政晴の次男 |
| 6.政林(まさしげ) 従五位下。兵庫頭 5代藩主・六郷政長の弟・六郷政陰の子 |
| 7.政速(まさちか) 従五位下。佐渡守 |
政林の三男 |
| 8.政純(まさずみ) 従五位下。阿波守 |
政速の次男 |
| 9.政恒(まさつね) 従五位下。兵庫頭 |
六郷政芳の子 |
| 10.政殷(まさただ) 従五位下。兵庫頭 |
政恒の次男 |
| 11.政鑑(まさかね) 従三位。兵庫頭 |
政殷の長男 |
廃藩置県
|
|

 |
堀氏にも他氏と同様異流がいくつかある。後述の堀秀政の系統は藤原氏利仁流斎藤氏族、秀政の
従兄弟堀直政は元は清和源氏の斯波氏族庶流奥田氏の血脈だが、秀政より堀氏を賜り、藤原姓に改める。
他には、清和源氏頼光流(多田源氏)、桓武平氏良文流の千葉氏族、近江国の藤原氏秀郷流、近江国
浅井郡堀村の菅原氏族、若狭武田氏族、宇多源氏佐々木氏族、藤原氏利仁流大神氏族などがある。
戦国時代後期から安土桃山時代にかけて織田信長、豊臣秀吉に仕え活躍した
堀秀政の一族が著名である。
|
堀 秀政(ほり ひでまさ)
堀秀重の長男として美濃国で生まれる。幼い頃は一向宗の僧となっていた伯父・堀掃部太夫の元で従兄弟・奥田直政
(後の堀直政)と共に育てられたという。13歳の若さで織田信長の小姓・側近として取り立てられた。山崎の戦いに参陣。
中川清秀・高山右近らと先陣小田原征伐にも参陣、左備の大将を命ぜられる
堀 秀治(ほり ひではる)
堀秀政の長男,関ヶ原の戦いが起こると東軍に与し、戦後、その功により家康から所領を安堵された。
|
| 1 |
福嶋藩
(高田藩)
|
堀一族の領土は坂戸藩、蔵王堂藩、三条藩など含め30万石、越後国主としては与力の新発田藩溝口家の
6万石、村上藩の9万石を含めて45万石)
外様 45万石 越後国
| 1.堀秀治(ひではる) |
従五位下、左衛門督、侍従 |
秀政の長男 |
| 2.堀忠俊(ただとし) |
|
秀治の長男 |
直政死後の慶長15年(1610年)、家老堀直清と堀直寄との争乱を発端とする御家騒動が勃発する
これにより、幕府は閏2月2日に忠俊と直清を改易、直寄を1万石減封に処した。
|
|
堀 直政(ほり なおまさ)
| 戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。従弟の堀秀政の家老となり、堀姓を与えられたが、奥田直政と呼ばれることもある。 |
| 近世大名としては秀政の家系よりも直政の家系のほうが有力となった。秀政は小田原征伐の最中に陣中で病没した。 |
| 秀政の死後、息子の秀治が跡継ぎにはまだ早すぎると判断した。豊臣秀吉は、所領の北ノ庄を召し上げようと考え、 |
| 秀治の襲封は滞った。怒った直政は次男の直寄を秀吉に使いに出し、秀治の襲封を許した。子は直清、直寄、直之、直重 |
| |
三条藩
|
外様 5万石 越後国
| 1.堀直政(なおまさ) |
| 2.堀直清(なおきよ) |
堀直政の長男 |
慶長15年(1610年)、僧侶殺害を直寄が徳川家康に訴えたため、改易となる。
|
|
堀 直寄(ほり なおより)
堀直政の次男(または三男)。兄に直清、弟に直之、直重ら秀治と親良、直清と直寄の兄弟相克が引き金になり、家康に
堀家除封の口実を与えてしまったのである。飯山藩4万石を領してからは、駿府にいて家康に仕えた。
元和2年7月、松平忠輝が改易となり、10月に直寄は3万石加増で再び長岡の領主となり藩が立藩された。
| 1 |
坂戸藩
|
外様。2万石→5万石 越後国
|
| 2 |
飯山藩
|
外様。4万石 信濃国
|
| 3 |
長岡藩
|
外様。8万石 越後国
|
| 4 |
村上藩
|
外様。10万石 越後国
| 1.堀直寄(なおより)<従五位下。丹後守> |
|
| 2.堀直次(なおつぐ)<従五位下、兵部少輔 |
堀直寄の長男 |
| 3.堀直定(なおさだ)<不明> |
直次の長男 |
4歳で跡を継ぐこととなった。この時、幕府の実力者である土井利勝の外孫であるという経緯から
3万石を加増されたが、その3万石はすべて叔父の直時に分与している。7歳で死去
村上藩堀家は断絶
|
その後の堀家
元家老の直寄は着実に出世し、長岡城の建設や新潟町発展の寄与、村上の城下町の整備も進めた。
直寄の次男直時の家系の越後村松藩3万石と、直政の五男直之の家系の越後椎谷藩1万石が存続
|
堀 直時(ほり なおとき)
元和2年(1616年)、信濃飯山藩主・堀直寄の次男として生まれる。寛永16年(1639年)、父の死去に際し、3万石を分与されて
大名となり、安田藩を立藩した。
| |
村松藩
(安田藩)
|
外様、 3万石(一説に4万石) 越後国
| 1.堀直時(なおとき) 従五位下 丹後守 |
信濃飯山藩主・堀直寄の次男 |
| 2.堀直吉(なおよし) 従五位下 丹波守 |
時の次男 |
| 3.堀直利(なおとし) 従五位下 丹後守 |
直吉の次男 |
| 4.堀直為(なおゆき) 従五位下 右京亮 |
直利の次男 |
| 5.堀直堯(なおたか) 従五位下 丹波守 |
直為の長男 |
| 6.堀直教(なおのり) 従五位下 左京亮 |
直堯の六男 |
| 7.堀直方(なおやす) 従五位下 左京亮 |
藩主・堀直堯の長男 堀直泰の長男 |
| 8.堀直庸(なおつね) 従五位下 丹後守 |
直方の次男 |
| 9.堀直央(なおひで/なおひさ) 従五位下 丹後守 |
直方の三男 |
| 10.堀直休(なおやす) 従五位下 丹後守 |
直央の次男 |
| 11.堀直賀(なおよし) 従五位下 左京亮 |
藩主・堀直教の長男・奥田教明の長男 |
| 12.堀直弘(なおひろ) 従五位下 |
直央の三男 |
廃藩置県
|
|
堀 親良(ほり ちかよし) 堀秀政の次男
| 父・秀政や兄・秀治と共に豊臣秀吉に仕える。小田原征伐のとき、11歳で初陣を飾り、父の死後越前国に2万石を領し、 |
| 天正19年(1591年)従五位下、美作守に叙任され、秀吉より羽柴氏と秀家の名を賜る。関ヶ原の戦いでは兄と共に東軍に与する。 |
| 慶長7年(1602年)同族の堀直政と不和になって対立し、病と称し京都伏見にあった亡父の屋敷に隠遁した。 |
| 慶長16年下野国真岡に1万2000石を賜り、江戸で秀忠に拝謁する。 |
| 大坂の陣では土井利勝の旗下で奮戦。この頃、羽柴氏を廃して堀氏へ戻し、秀家の名も親良と改めた。 |
| |
蔵王堂藩
堀 家 |
(1600年~1606年)
| 1.親良(ちかよし) |
|
堀秀政の次男 |
| 2.鶴千代(つるちよ) |
従五位下、美作守 |
堀秀治の次男、堀忠俊の弟 |
叔父の堀親良の養子となる。1602年、養父・親良が秀治や堀直政と不仲になり隠居したた為、
家督を譲られる。しかし1606年に9歳ほどで夭折。嗣子が無かった為、断絶となった。
鶴千代の有していた蔵王堂藩3万石は、鶴千代の後見人である堀直寄の坂戸藩に編入された
|
堀 直之(ほり なおゆき
堀直政の三男、兄に直清、直寄、弟に直重、1610年)に堀氏が除封されると一時、信濃飯山藩主であった
兄の直寄のもとへ身を寄せ、翌年、はじめて2代将軍・徳川秀忠に拝謁し、書院番の士となる。
大坂冬の陣では兄・直寄に属して戦い、先鋒を務めた。
旗本、江戸幕府北町奉行、寺社奉行。椎谷堀家の初代。
堀 直景(ほり なおかげ)
堀 直之の長男で元和7年(1621年)に書院番となり、寛永19年(1642年)、父の死により遺領9500石を相続する。
合計1万石を領する譜代大名として諸侯に列したことから、上総苅谷藩が立藩した。譜代大名参照
堀 直重(ほり なおしげ
堀直政の四男。兄に直清、直寄、直之。関ヶ原の戦いで東軍に与して軍功を挙げたことにより、
下総矢作と信濃須坂に8000石の所領を与えられた。慶長19年(1614年)からの大坂の陣でも徳川方として
参戦し、功績を挙げて加増され、信濃国須坂に立藩した。最終的に1万2000石の所領を領した。
| |
須坂藩
|
外様。柳間。陣屋 1万石 信濃国
| 1.堀直重(なおしげ)従五位下。淡路守 |
1615-1617 |
|
| 2.堀直升(なおます)従五位下。淡路守 |
1617-1637 |
直重の長男 |
| 3.堀直輝(なおてる)従五位下。肥前守 |
1637-1669 |
直升の長男 |
| 4.堀直佑(なおすけ)従五位下。長門守 |
1669-1719 |
直輝の長男 |
| 5.堀直英(なおひで)従五位下。淡路守 |
1719-1735 |
直利の三男 |
| 6.堀直寛(なおひろ)従五位下。長門守 |
1735-1768 |
直英の長男 |
| 7.堀直堅(なおかた)従五位下。淡路守 |
1768-1779 |
直寛の長男 |
| 8.堀直郷(なおさと)従五位下。長門守 |
1779-1784 |
直寛の三男 |
| 9.堀直皓(なおてる)従五位下。内蔵頭 |
1784-1813 後国三池藩主・立花長煕の七男 |
| 10.堀直興(なおおき)従五位下。淡路守 |
1813-1821 |
直皓の長男 |
| 11.堀直格(なおただ)従五位下。内蔵頭 |
1821-1845 |
直皓の三男 |
| 12.堀直武(なおたけ)従五位下。淡路守 |
1845-1861 |
直格の長男 |
| 13.堀直虎(なおとら)従五位下。長門守 |
1861-1868 |
直格の五男 |
| 14.堀直明(なおあきら)従五位下。長門守 |
1868-1871 |
直格の六男 |
廃藩置県
|
|

 |
鎌倉時代から安土桃山時代にかけて武蔵国に栄えた一族が著名である
成田氏の菩提寺たる龍淵寺の開祖とされるのが成田五郎家時で、中興の祖と伝わる。室町時代後期
(戦国時代)に山内上杉氏の家臣として活躍した成田顕泰またはその子・成田親泰は、児玉氏、忍氏などを
滅ぼすなど勢力を広げ、忍城を中心に成田氏の最盛期を演出した。しかし上杉顕定の死後の
上杉家家督争いで上杉顕実に味方して敗れ、 |
成田 長泰(なりた ながやす
| 成田親泰の子で、後北条氏との抗争で主家が衰えると、天文14年(1545年)4月の父・親泰の死を受けて家督を継いだ長泰は、 |
| 5月には後北条氏に服した。関東管領に就任した上杉謙信が関東に進出してその配下になる。しかし謙信が小田原城を |
包囲して後に帰国すると(小田原城の戦い)、北条氏康に降伏し、その家臣となった。永禄6年、謙信に忍城を攻められて
|
| 降伏した。氏長に家督を譲る |
成田 氏長(なりた うじなが
| 成田長泰の嫡男、天正18年(1590年)、豊臣秀吉の小田原征伐では、自身は小田原城に籠城し、居城の武蔵国忍城は |
| 家臣に守らせた。忍城は石田三成の水攻めを受けたがその効果はあがらず、豊臣勢の攻撃を持ちこたえている。 |
北条氏滅亡後、弟の長忠と共に蒲生氏郷に仕え、のち娘の甲斐姫が秀吉の寵愛を受けたこともあって下野国烏山2万石に
|
| 封ぜられた。氏長の跡は弟の成田長忠が家督を継承し関ヶ原の戦いの後は徳川氏に属したが、その子の代に後 |
| 継者争いが起きたため改易となった。子孫は御家人、次いで旗本となった。 |
| |
烏山藩
|
外様、 2万石→3.7万石 下野国
| 1.成田氏長(うじなが) 従五位 下総守 |
成田長泰の嫡男 |
| 2.成田長忠(ながただ) 従五位 左衛門尉 |
長泰の次男 |
| 3.成田氏宗(うじむね) 従五位 左馬助 |
長忠の次男 |
継者争いが起こった。これを幕府に咎められて、3万7000石から1万石へ減封された。
元和8年(1622年)11月、死去した。氏宗の死後、弟の泰直と甥の房長との間で家督争いが起き、
幕府は氏宗に実子がないという理由から改易した。
|
|

 |
平安時代末期から江戸時代初期にかけて下野国を中心に栄えた一族。
本宗である藤姓足利氏当主足利忠綱が志田義広と手を組んだのに対し、基綱は早くから源頼朝に
味方したため、頼朝によって藤姓足利氏の嫡流が滅亡したのちも、鎌倉幕府の御家人として勢力を維持した。
鎌倉幕府の滅亡後は足利氏に属し、室町時代を通して鎌倉公方、古河公方に仕え活躍した。
|
佐野 房綱(さの ふさつな)
永禄元年、下野国の戦国大名・佐野氏第13代当主・佐野泰綱(一説には兄・佐野豊綱)の子として誕生
豊臣氏による小田原征伐がおこると、房綱と道及は佐野家に対して呼びかけ、少数の兵しか集まらなかったが
奮戦し、佐野(北条)氏忠の領地である3万9,000石の所領及び家督を事実上継ぐことを許された
佐野 信吉(さの のぶよし)
天正20年、佐野房綱の養嗣子となって佐野政綱と名を改め、佐野氏の家督を継ぐ。小田原の役によって
佐野氏忠が追放された後、豊臣秀吉の宇都宮仕置によって一族の房綱が佐野氏の名代となったが、後日正式な当主を改め
て擁立することになっており、房綱の奔走で信吉が佐野氏の養子として跡を継ぐことになった
慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは東軍に与したため、戦後に所領を安堵された。
| |
佐野藩
佐野家 |
外様、 3.9万石 下野国
| 1.佐野信吉 |
従五位下、修理大夫 |
富田一白(長家)の五男 |
1614年(慶長19年)3月に江戸で火災が起きた際に駆けつけて消火作業に活躍するが、
これを無断参府として幕府に咎められた(豊臣家に縁深い大名が、江戸
での変事にすぐに気付いて急行出来る場所にいることを危険視されたと推察される)。
また、伊予宇和島藩主の兄富田信高の改易に連座して同年7月に改易された。
|
|


|
| 藤原北家の後裔を称し、各種系図によると藤原道長の六男・藤原長家の孫資家(貞信)を祖とし、元は須藤氏を |
| 称していたが、那須資隆(太郎)の時、那須氏を称したとされる。一般には屋島の戦いで扇の的を射落とした |
| 那須与一(資隆の子)で知られるが、吾妻鏡によって明確に存在が確認される鎌倉時代初期の那須光資からで |
| あり、与一の存在も含めそれ以前の系図や事跡・伝承には疑わしい部分も多い永正11年(1514年)、上那須家が |
| 内紛により滅亡し、下那須家の那須資房が那須氏を統一するが、その後は宇都宮氏や佐竹氏との抗争に |
| 明け暮れる。関ヶ原の戦いでは東軍に属し、江戸時代には下野那須藩1万4,000石の大名となる。 |
|
那須 資景(なす すけかげ)
| 天正18年(1590年)、父那須資晴が、豊臣秀吉の小田原征伐に参陣しなかったため、一度は改易されたが、重臣大田原晴清の |
| の陳謝により、当時5歳であった藤王丸に5000石の所領が与えられ、那須氏は存続を許される。さらに資晴も後に赦され、 |
| 5000石を与えられた。慶長5年の関ヶ原の戦いでは東軍に属し、同年に300石を加増された。慶長7年にも1000石を与えられる。 |
| 慶長15年に資晴が死亡するとその遺領6000石を継ぎ、合計して1万4080石の大名として那須藩を立藩した。 |
| |
那須藩
|
外様 1.4万石 下野国
| 1.那須資景(すけかげ) 従五位下 左京大夫 |
|
| 2.那須資重(すけしげ) 従五位下 美濃守 |
資景の長男 |
寛永19年(1642年)に跡継ぎのないまま没し、那須氏は無嗣断絶となった。
幕府は那須与一以来の名家の廃絶を惜しみ、隠居の資景が所領の一部5000石を
継承し、家名を再興することが許されている。
|
|


|
常陸国久慈郡の静神社祠官を世襲した一族に藤田氏がある。
藤田 信吉(ふじた のぶよし)
藤田(小野)康邦の次男といわれているが、疑問である、上杉景勝から越後長島城を与えられた信吉は、
以降上杉家中で数々の武功を挙げていく。小田原征伐では上杉軍の先鋒を務め、上野・武蔵の北条方の
諸城を次々と攻略した。慶長3年に上杉氏が会津に移封されると、景勝から越後津川城代として1万5,000石の
所領を与えられた。慶長5年(1600年)、信吉は景勝の代理として新年の祝賀のために上洛する。
この際、徳川家康は信吉に銀子や青江直次の刀等を贈るなどして好意的に接している。関ヶ原の戦いの後、
信吉は家康に下野国西方に1万5,000石の所領を与えられたため、還俗して諱を重信と改めた。
|
| |
西方藩
|
外様 1.5万石 下野国
大坂の陣にも従軍したが、慶長20年(1615年)の夏の陣後に改易された。
理由は榊原康勝軍の軍監を務めていたときの失態、戦功に対する不満からの
失言など諸々の理由を挙げられている。元和2年(1616年)7月信濃奈良井で死去
|
|

 |
滝川一益は織田家の重臣
藩祖は滝川雄利である。雄利は織田信長に仕え、信長没後はその次男信雄の家臣となった。
信雄が改易されると豊臣秀吉の家臣として伊勢国神戸に2万石を与えられた。(一益の娘婿の
滝川雄利が該当する。)慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは西軍に与したため、
戦後に改易されたが、徳川秀忠に召し出されてその家臣にになったことから、常陸片野に
2万石を与えられた。これが片野藩の立藩である。
|
| |
片野藩
|
外様 2万石 常陸国
| 1.滝川雄利(かつとし) |
|
|
| 2.滝川正利(まさとし) |
従五位下、壱岐守 |
|
慶長19年からの大坂の陣で武功を挙げた。しかし生来から病弱で嗣子がなく、
幕府の公務に耐えられないという理由から、寛永2年に所領2万石のうち
1万8000石を幕府に返還し、2000石の旗本となった。同年11月7日、36歳で死去した。
|
|
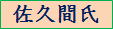
 |
日本の氏族の一つ。三浦氏の一族、佐久間家村を祖とする家柄である。
佐久間家は、三浦義明の三男である義春(よしはる)の四男・家村が安房国狭隈郷で称したのが
始まりと言われる。
|
尾張佐久間氏
戦国時代、佐久間盛重(大学)・佐久間信盛は重臣として織田信長に仕えたが、盛重は桶狭間の戦いで戦死
信盛は石山合戦の際の不手際により1580年に追放された。佐久間盛次の系統は、盛次の子で柴田勝家の与力として北陸で戦った
金沢城主・盛政がよく知られているが盛政は賤ヶ岳の戦いの敗戦により捕らえられ刑死する。盛政の弟は、安政が
信濃飯山藩3万石の藩祖に、勝之が信濃長沼藩1万8,000石の藩祖にそれぞれなった。
佐久間 安政(さくま やすまさ)
織田家の武将・佐久間盛次の次男。小牧・長久手の戦いでは徳川家康・織田信雄方に属して
関ヶ原の戦いで東軍に属し、その戦功により近江国高嶋郡(現滋賀県高島市)の内に加増を受け、合計で1万5,000石を
領するようになり、大名に列した。元和元年(1615年)大坂の陣の戦功により信濃国飯山(現長野県飯山市)に1万石の加増を
受け合計3万石となり、飯山藩の藩祖となった
| |
飯山藩
|
外様 3万石 常陸国
| 1.佐久間安政(やすまさ従五位下。備前守 |
佐久間盛次の次男 |
| 2.佐久間安長(やすなが従五位下。日向守 |
安政の次男 |
| 3.佐久間安次(やすつぐ |
安長の長男 |
父が死去したためにわずか3歳で家督を継いだ。このため、藩政は重臣の手によって
執り行われている。しかし寛永15年11月9歳で死去、佐久間家は断絶し、改易となった。
|
佐久間 勝之(さくま かつゆき
永禄11年(1568年)、織田氏の家臣・佐久間盛次の四男として生まれる。
はじめ叔父・柴田勝家の養子となったが、後に佐々成政の娘を娶り婿養子となった。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは
東軍に属した。慶長12年(1607年)江戸城内に移転。その際に常陸国北条(現茨城県つくば市北条)3,000石を加増され、
合計1万石を領し、大名となった。大坂夏の陣では豊臣方の将竹田永翁を討ち取る手柄を挙げたといい、その戦功により
信濃国川中島と近江国高嶋郡(現滋賀県高島市)の内に加増され、信濃長沼藩1万8,000石の藩祖となった。
| |
長沼藩
|
外様 1.8万石→1.3万石→1万石 信濃国
| 1.佐久間勝之(かつゆき) 従五位下 大膳亮 |
佐久間盛次の四男 |
| 2.佐久間勝友(かつとも) 従五位下 蔵人 |
勝之の次男 |
| 3.佐久間勝豊(かつとよ) 従五位下 安房守 |
勝友の長男 |
| 4.佐久間勝親(かつちか) |
秋月種信の五男 |
20歳のとき5代将軍徳川綱吉より側小姓を命ぜられるも、病と称して辞退した
これが仮病であったことが幕府に知られたため、不敬であるとして改易
|
|


|
土方 雄久(ひじかた かつひさ)
父の代から織田氏の家臣であり、織田信長とその次男の信雄に仕え、伊賀国平定で功を挙げる。
慶長3年、秀吉が死去した後は豊臣秀頼に仕えたが、「幻の家康暗殺計画」で、家康の暗殺を企でたとして
改易された。関ヶ原の戦い前の会津遠征で治長と共にその罪を許されて家康に仕え、従兄弟の前田利長を
東軍へ勧誘する使者を務めた功により、同年越中国布市に1万石の所領を与えられた(布市藩)。土方雄重に継ぐ
|
| 1 |
布市藩 |
外様 1万石 越中国
|
| 2 |
多胡藩 |
外様 1.5万石 下総国
| 1.土方雄久(かつひさ) 従五位下 河内守 |
|
| 2.土方雄重(かつしげ) 従五位下 掃部頭 |
雄久の次男 |
|
| 3 |
窪田藩 |
外様 2万石→1.8万石 陸奥国 現在の福島県いわき市
| 1.土方雄重(かつしげ) |
|
|
| 2.土方雄次(かつつぎ) |
従五位下、河内守 |
雄重の長男 |
| 3.土方雄隆(かつたか) |
従五位下、山城守、伊賀守 |
雄次の次男 |
子が無く、弟の貞辰を仮養子として跡を継がせようとしたが家臣は他家に入った貞辰ではなく、
雄信の子の内匠に跡を継がせるように進言した。
雄隆はこれを受け入れて、内匠を養子にするために伴って参府したが、江戸の家臣は貞辰を4
推しており騒動となった。雄隆の側室の射殺事件が起き、そのため7月22日に改易となり
|
|
土方 雄氏(ひじかた かつうじ)
| 土方雄久の長男、文禄3年、豊臣秀吉に仕えて伊勢国内に3,000石を与えられ、豊臣秀頼の近臣となった。 |
| 秀吉没後の覇権を狙う徳川家康とその軍師・本多正信が策した幻の家康暗殺事件に父が容疑者にされると、 |
| 長男の雄氏も連座で罪に問われて父と共に常陸国の佐竹義宣預かりの身とされた。 |
| 慶長5年、関ヶ原の戦い直前に家康から罪を許されて、その後は徳川氏の家臣となる。 |
| |
窪田藩 |
外様 1.2万石 伊勢国 現在の三重県三重郡菰野町菰野
| 1.土方雄氏(かつうじ)<従五位下。丹後守> |
土方雄久の長男 |
| 2.土方雄高(かつたか)<従五位下。丹後守> |
雄氏の長男 |
| 3.土方雄豊(かつとよ)<従五位下。市正> 土方氏久(初代菰野藩主・土方雄氏の次男)の三男 |
| 4.土方豊義(とよよし)<従五位下。丹後守> |
豊高の長男 |
| 5.土方雄房(かつふさ)<従五位下。丹後守> |
豊義の長男 |
| 6.土方雄端(かつまさ)<従五位下。備中守> |
豊義の次男 |
| 7.土方雄年(かつなが)<従五位下。近江守> |
雄端の長男 |
| 8.土方雄貞(かつさだ)<従五位下。丹後守> 遠江相良藩主田沼意次の六男 |
| 9.土方義苗(よしたね)<従五位下。大和守> 第6代藩主・土方雄端の三男・木下俊直の次男 |
| 10.土方雄興(かつおき)<従五位下。主殿頭> |
義苗の長男 |
| 11.土方雄嘉(かつよし)<従五位下。備中守> |
雄興の長男 |
| 12.土方雄永(かつなが)<従五位下。大和守> |
雄嘉の長男 |
| 13.土方雄志(かつゆき)<従五位> |
土方久己の長男 |
廃藩置県
|
|

  |
武蔵七党の一つ丹党の末裔の一族が、武蔵国入間郡青木の地を領して本貫とし、青木姓を称したといわれる。
戦国時代には、その青木氏の末裔を称する美濃出身の青木重直・青木一重の一族が徳川家康や豊臣秀吉に
仕えて出世し江戸時代には小藩ながら外様大名として摂津麻田を支配し、明治維新後は華族となった。
|
青木 重直(あおき しげなお
永禄2年に織田信長が上洛した際に斎藤義龍の命令で信長の命を狙った刺客の一人だったといわれる
斎藤氏滅亡後は織田氏家臣の丹羽長秀に仕え、山崎の戦い、賤ヶ岳の戦いに参加した
後に豊臣秀吉の家臣となり御伽衆となる。
青木 一重(あおき かずしげ
| 一重は父の重直の下を離れ、はじめ今川氏真に仕えて新阪の戦いで首級を挙げ、褒美に黄金を賜った。今川氏没落後は |
| 徳川家康に仕えて元亀元年の姉川の戦いで真柄直隆を討ち取る武功を挙げたといわれる。丹羽氏に仕えて山崎の戦い、 |
| 賤ヶ岳の戦いなどに参加したが、長秀の死後は羽柴秀吉の家臣に転じ、天正13年(1585年)に摂津国豊島郡内や備中国・ |
| 伊予国内などに合わせて1万石を与えられる。天正14年(1586年)、従五位下民部少輔任官。秀吉死後は豊臣秀頼に仕え、 |
| 速水守久や伊東長実らと共に秀頼の親衛隊である七手組の組頭を務めた。 |
| 慶長19年の大坂冬の陣の後、和議交渉の一環として家康のもとへ赴いた帰りに京で板倉勝重に捕らえられ大坂には戻らず、 |
| 元和元年の大坂夏の陣には参加出来なかった。その後、剃髪して隠棲していたが、家康に家臣として召し出され、 |
| 摂津国豊嶋郡をはじめとする地域に1万2,000石の所領を与えられた。 |
| |
窪田藩
青木家 |
外様 1.2万石 摂津国 大阪府豊中市蛍池
| 1.一重(かずしげ)〔従五位下・民部少輔〕 |
|
| 2.重兼(しげかね)〔従五位下・甲斐守〕 旗本・青木可直(藩主・青木一重の四弟)の長男 |
| 3.重正(しげまさ)〔従五位下・甲斐守〕 |
朝倉宣親の長男 |
| 4.重矩(しげのり)〔従五位下・甲斐守〕 |
重正の次男 |
| 5.一典(かづつね)〔従五位下・甲斐守〕 |
重矩の長男 |
| 6.一都(かづくに)〔従五位下・出羽守〕 |
一典の長男 |
| 7.見典(ちかつね)〔従五位下・内膳正〕 |
一典の次男 |
| 8.一新(かづよし)〔従五位下・美濃守〕 |
一典の三男 |
| 9.一貫(かづつら)〔従五位下・甲斐守〕 |
伊予国宇和島藩主伊達村年の三男 |
| 10.一貞(かづさだ)〔従五位下・甲斐守〕 |
一貫の四男 |
| 11.重龍(しげたつ)〔従五位下・駿河守〕 |
一貞の長男 |
| 12.一興(かづおき)〔従五位下・美濃守〕 |
一貞の六男 |
| 13.一咸(かづひろ)〔従五位下・甲斐守〕 |
豊前中津藩主・奥平昌高の十二男 |
| 14.重義(しげよし)〔従五位下・民部少輔〕 |
重龍の五男 |
廃藩置県
|
|
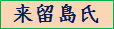
 |
来島 通総(くるしま みちふさ)
永禄4年(1561年)、村上水軍の一族である来島村上氏当主・村上通康の四男として生まれる
来島 通親/長親(くるしま みちちか
来島通総の次男、慶長2年(1597年)、父の通総が慶長の役で戦死したため、家督を継いだ。
慶長5年の関ヶ原の戦いでは、西軍に属し所領を没収された。しかし妻の伯父である福島正則の取りなしに
より本多正信を通じ、慶長6年に幕府より豊後国の、森(大分県玖珠郡玖珠町)に1万4000石を与えられた。
|
| |
森 藩
来島家 |
外様 1.4万石→1.25万石 豊後国
| 1.康親(やすちか)〔従五位下、右衛門佐 |
|
| 2.通春(みちはる)〔従五位下、丹波守 |
姓を久留島と改めた 長親の長男 |
| 3.通清(みちきよ)〔従五位下、信濃守 |
通春の長男 |
| 4.通政(みちまさ)〔従五位下、伊予守 |
通清の長男 |
| 5.光通(てるみち)〔従五位下、信濃守 伏見奉行 |
旗本・久留島通貞(通春の次男)の次男 |
| 6.通祐(みちすけ)〔従五位下、信濃守 伏見奉行・大番頭 |
光通の五男 |
| 7.通同(みちとも)〔従五位下、出雲守 大番頭 |
光通の七男 |
| 8.通嘉(みちひろ)〔従五位下、伊予守 |
通同の次男 |
| 9.通容(みちかた)〔従五位下、安房守 |
通嘉の三男 |
| 10.通明(みちあき)〔従五位下、出雲守 |
通容の長男 |
| 11.通胤(みちたね)〔従五位下、信濃守 |
通嘉の七男 |
| 12.通靖(みちやす)〔従五位下、伊予守 |
通胤の長男 |
廃藩置県
|
|


|
壇ノ浦の戦い後に伊勢平氏の一族で平清盛の弟家盛が宇久島へ上陸し、同島の領主となって宇久次郎と
名乗り宇久氏を興したともいう。宇久氏は鎌倉時代から戦国時代にかけて宇久島から五島列島全域に支配を
広げていった。玉之浦納の反乱により一時衰退するも、宇久盛定が松浦氏の援助により中興を果たす。
盛定の跡は子の宇久純定が継いだが、純定は晩年にキリスト教への傾倒を強め、子の宇久純尭は
キリシタン大名「ドン・ルイス」となる。純尭の子の宇久純玄(五島純玄)は一転してキリシタンに対する
弾圧者に転じる。純玄が五島姓を名乗り、以後は五島氏となった。天正15年(1587年)6月、豊臣秀吉は
九州を平定した(九州征伐)。その際、宇久純玄(第20代当主)は、1万5,530石の本領を安著された。 |
五島 玄雅(ごとう はるまさ)
| 宇久純定の三男。先代当主・五島純玄の叔父に当たる。豊臣姓を賜る。当初は大浜姓を名乗っていたが、文禄3年に甥の純玄が |
| 文禄の役に出陣中、天然痘にかかってにかかって死亡したため、その跡を継いで当主となり、朝鮮出兵に参加した。 |
| 慶長5年の関ヶ原の戦いでは中立を保ち、戦後に徳川家康から所領を安堵されて初代福江藩主となった。 |
| |
福江藩
五島家 |
外様 1.5万石→1.2万石→1.5万石 肥前国
| 1.玄雅(はるまさ)〔従五位下・淡路守〕 |
宇久純定の三男 |
| 2.盛利(もりとし)〔従五位下・淡路守〕 |
盛長の長男 |
| 3.盛次(もりつぐ)〔病弱のため官位官職無し〕 |
盛利の長男 |
| 4.盛勝(もりかつ)〔従五位下・淡路守〕分知により1万2千石 |
盛次の長男 |
| 5.盛暢(もりのぶ)〔従五位下・佐渡守〕 |
盛勝の長男 |
| 6.盛佳(もりよし)〔従五位下・大和守〕 |
盛暢の長男 |
| 7.盛道(もりみち)〔従五位下・淡路守〕 |
盛佳の長男 |
| 8.盛運(もりゆき)〔従五位下・大和守〕 |
盛道の次男 |
| 9.盛繁(もりしげ)〔従五位下・大和守〕 |
盛運の次男 |
| 10.盛成(もりあきら)〔従五位下・大和守〕 |
盛繁の長男 |
| 11.盛徳(もりのり)〔従五位下・飛騨守〕合併により1万5千石 |
盛成の三男 |
廃藩置県
|
|

さがら
 
|
藤原南家の流れを汲み、遠江相良荘に住んだことから相良を苗字とした。相良頼景の時代に、伊豆で兵を
挙げた源頼朝に協力せず、その後も不遜な振る舞いを続けたため、鎌倉幕府が成立すると、頼景は
肥後国多良木荘に追放された。しかし頼景はその後、頼朝に許され、多良木荘の地頭に任命された。
室町時代の文安5年(1448年)、下相良氏の相良長続が上相良氏を滅ぼし、球磨・八代・葦北の肥後三郡の
統一に成功した。しかし晴広の子の相良義陽の時代に入ると、南の薩摩から島津義久の侵攻を受けて
天正9年に降伏する。しかし義陽の次男相良頼房が、家臣の犬童頼安や深水長智らの補佐を受けて存続した。
九州征伐後、豊臣秀吉より人吉2万石の領主として存続を許された。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで、
頼房は西軍に属して伏見城攻防戦などに従軍したが、本戦で西軍が東軍に敗れると寝返ったため、戦後に
徳川家康より所領を安堵され、相良氏は人吉藩として存続した。相馬氏、島津氏と並び、明治維新まで
800年以上領地替えされることもなく続いた大名の一つである。 |
| |
人吉藩
相良家
さがら |
外様 2.2万石 肥後国
| 1.相良頼房(よりふさ |
従五位下、左衛門佐、宮内大輔 |
相良義陽の次男 |
| 2.頼寛(よりひろ |
従五位下、壱岐守 |
頼房の長男 |
| 3.頼喬(よりたか |
従五位下、遠江守 |
頼寛の長男 |
| 4.頼福(よりとみ |
従五位下、志摩守 |
藩主相良頼寛の弟・相良長秀の次男 |
| 5.長興(ながおき |
従五位下、近江守 |
頼福の長男 |
| 6.長在(ながあり |
従五位下、遠江守 |
頼福の五男 |
| 7頼峯(よりみね |
従五位下、志摩守 |
長在の長男 |
| 8.頼央(よりひさ |
従五位下、遠江守 |
長在の次男 |
| 9.晃長(みつなが |
官位無し |
日向高鍋藩主・秋月種美の三男 |
| 10.福将(とみもち |
従五位下、越前守 |
美濃苗木藩主・遠山友明の次男 |
| 11.長寛(ながひろ |
従五位下、壱岐守 |
備前岡山藩主池田宗政の次男 |
| 12.頼徳(よりのり |
従五位下、志摩守、紀伊守 |
長寛の長男 |
| 13.頼之(よりゆき |
従五位下、近江守、壱岐守 |
頼徳の長男 |
| 14.長福(ながとみ |
従五位下、遠江守、壱岐守 |
頼之の長男 |
| 15頼基(よりもと |
従五位下、越前守、遠江守 |
頼之の四男 |
廃藩置県
|
|

 |
新庄 直昌(しんじょう なおまさ
戦国時代の武将。近江新庄城主、朝妻城主。通称は蔵人。新庄直寛の子
天文7年(1538年)、父の死により後を継いだ。天文年間、近江坂田郡に朝妻城を築く。
畿内で細川晴元と三好長慶の対立が発生すると晴元の救援に赴いたが、摂津江口の戦いで
討ち死にした。享年37。朝妻城は嫡男の直頼、新庄城は次男の直忠が受け継いだ。 |
新庄 直頼(しんじょう なおより
| 父は近江朝妻城主新庄直昌、天文18年(1549年)、父が江口の戦いで戦死、11歳で後を継いだ。後に戦国大名浅井氏に仕え、 |
| 姉川の戦いに参戦して第4陣を構成している。浅井氏滅亡後は織田信長に属し、信長の死後は豊臣秀吉に仕え、 |
| 賤ヶ岳の戦いでは近江坂本城を守備した。関ヶ原の戦いでは西軍に与し、東軍に与した筒井定次の伊賀上野城を占拠した。 |
| 当初は東軍に与しようとしたが、周囲の大名全てが西軍に与していたため、やむなく西軍に属したとされる。 |
| 戦後改易され、身柄は蒲生秀行預かりとなる。慶長9年に赦免され、常陸麻生3万石を与えられて立藩した。 |
| |
麻生藩
新庄家
|
外様 3万石→2万3000石→1万石 常陸国
| 初代 新庄直頼 |
従五位下駿河守 |
父は近江朝妻城主新庄直昌 |
| 2.直定なおさだ |
従五位下越前守 |
直頼の長男 |
| 3.直好なおよし |
従五位下越前守。 |
直定の長男 |
| 4.直時なおとき |
従五位下、隠岐守御書院番 新庄直頼の四男・新庄直房の次男 |
| 5.直矩なおのり |
3歳で直時に |
直好の次男 |
| 6.直時(第4代藩主の再任) |
従五位下、主殿頭 |
|
| 7.直詮なおのり |
|
直時の長男 |
| 8.直祐なおすけ |
従五位下、駿河守 |
直詮の五男 |
| 9.直隆なおたか |
従五位下・越中守 |
直祐の長男 |
| 10.直侯なおよし |
従五位下・越前守 |
直祐の次男 |
| 11.直規なおのり |
従五位下、駿河守 |
直隆の長男 |
| 12.直計なおかず |
従五位下・越前守 |
直規の長男 |
| 13.直彪なおとら |
従五位下、駿河守 |
直計の五男 |
| 14.直??なおはつ |
|
直彪の長男 |
| 15.直敬 |
従五位下、下野守 旗本の嫡子新庄長門守直孝の長男 |
廃藩置県
|
|

 |
美濃国の豪族出身。清和源氏頼光流土岐流を称す。藤原北家魚名流の分家である
利仁流後藤氏を興した、後藤則明を祖とし、千石氏とも呼ばれた。仙石基秀の代に甥で
ある仙石久重が娘婿として家督を引き継いだが、久重は清和源氏頼光流(美濃源氏)に
属する土岐氏の血を引いており、以降は美濃源氏を称した |
仙石 秀久(せんごく ひでひさ
豊臣秀吉の最古参の家臣で、家臣団では最も早く大名に出世した。戸次川の戦いでの独断専行により、
島津軍に大敗を喫し改易されるが、小田原征伐で許された。家康と懇意であった秀久は早くから |
| 家康と懇意であった秀久は早くから徳川氏に接近した。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦い |
| でも東軍として家康から北国筋の鎮撫を命じられている。 |
| 1 |
小諸藩
|
外様 5万石 信濃国 1590年 - 1622年
| 1.仙石秀久(ひでひさ) 従五位下 越前守 |
豪族・仙石久盛の四男 |
| 2.仙石忠政(ただまさ) 従五位下 兵部大輔 |
秀久の三男 |
|
| 2 |
上田藩
|
外様 6石→5.8万石 信濃国
| 1.仙石忠政(ただまさ) 従五位下 兵部大輔 |
|
| 2.仙石政俊(まさとし) 従五位下 越前守 |
忠政の長男 |
| 3.仙石政明(まさあきら) 従五位下 越前守 |
政俊の長男・仙石忠俊の長男 |
|
| 3 |
出石藩
いずし
仙石家 |
外様 5.8万石→3万石 但馬国(1706年 - 1871年)
| 1.政明(まさあきら)〔従五位下、越前守〕 |
| 2.政房(まさふさ)〔従五位下、信濃守 寺社奉行〕 |
仙石政治(仙石久治の子)の子 |
| 3.政辰(まさとき)〔従五位下、越前守〕 |
旗本である仙石政因の七男 |
| 4.久行(ひさゆき)〔従五位下、刑部少輔〕 |
旗本である仙石久近の三男 |
| 5.久道(ひさみち)〔従五位下、越前守〕 |
久行の長男 |
| 6.政美(まさよし)〔従五位下、越前守〕 |
久道の長男 |
| 7.久利(ひさとし)〔従五位下、越前守〕 仙石騒動により3万石 |
久道の四男 |
| 8.政固(まさかた)〔従五位下、越前守。従二位、子爵〕 |
久道の三男 |
廃藩置県
|
仙石騒動
| 「江戸時代の三大お家騒動」の一つとして紹介される |
| 第6代藩主仙石政美の代になると仙石藩の財政は逼迫し、藩政改革の機運が盛り上がった。仙石氏一門で文政7年藩主仙石政美が |
| 参勤交代で出府する途中で発病し、江戸についてまもなく28歳の若さで病没する。政美には嗣子が無く隠居していた政美の父久道が |
| 江戸で後嗣を選定するため、分家の旗本を含めての会議を開いた。仙石左京は筆頭家老であるため国許の代表者として |
| 江戸へ出るが、実子小太郎を同伴させた。これを左京が小太郎を後継に推すのではと不信感を抱いた造酒は実弟の |
| 酒匂清兵衛を同道させ監視した。跡取りの件の騒動で幕末の最終裁定では天保6年裁定が下され、仙石左京は獄門になり、 |
| 鈴ヶ森に晒首された。左京の側近宇野甚助も斬罪となり、左京の子小太郎は八丈島へ流罪になるなど、左京派は |
| 壊滅的打撃を受けた。藩主久利に直接お咎めは無かったが、出石藩は知行を5万8千石から3万石に減封となった。 |
| また幕府内でも、老中松平康任は同時に発覚した密貿易(竹島事件)の責も含め失脚、隠居を余儀なくされた他、 |
| 南町奉行筒井政憲と勘定奉行の曾我助弼も失脚した。 |
仙石藩はその後も抗争のしこりが残り、文久2年(1862年)藩主久利が実権を握り、親政を開始するまで
長く藩内の政争は続いた。
|

たけべ
|
日本の古代氏族の一つである建部氏がある。日本武尊の名代部(ヤマトタケルノミコトを奉際する
軍事的部民)で倭健尊から健部を正字とする。また、近世大名となった近江の建部氏は佐々木氏の一門で
あるというが、上記の古代健部氏との関連も指摘されており、その一族であった可能性もある。
近江建部氏
戦国時代後期の建部寿徳(高光)は、近江六角氏(佐々木嫡流)に仕えていたが、六角氏が没落した後は
織田信長に仕え、中川重政、丹羽長秀の下で吏僚として領内統治に辣腕を振るった。
豊臣恩顧の一族で、関ヶ原の戦いの際には西軍に属し一時所領を没収されたが縁戚の池田輝政の
執り成しによって許され改易を免れた。
|
建部 政長(たけべ まさなが
建部光重の三男、母は池田輝政の養女。慶長19年(1614年)からの大坂の陣においては縁戚の池田利隆、池田重利らの援軍を
受けている。元和元年(1615年)7月21日、大坂の陣による武功により1万石を与えられて尼崎藩主となった。
|
| 1 |
尼崎藩
建部家 |
外様 1万石 摂津国 (1615年 - 1617年)
| 1.政長(まさなが) 〔従五位下、丹波守〕 |
建部光重の三男 |
|
| 2 |
林田藩
建部家 |
外様 1万石 摂播磨 (1617年 - 1871年)
| 1.政長(まさなが)〔従五位下、丹波守〕 |
| 2.政明(まさあき)〔従五位下、丹波守〕 |
政長の三男 |
| 3.政宇(まさのき)〔従五位下、内匠頭 寺社奉行〕 |
政長の五男 |
| 4.政周(まさちか)〔従五位下、丹波守〕 |
政宇の次男 |
| 5.政民(まさたみ)〔従五位下、丹波守〕 |
政周の長男 |
| 6.長教(ながのり)〔従五位下、近江守〕 |
政民の長男 |
| 7.政賢(まさかた)〔従五位下、内匠頭 大番頭〕 |
政民の四男 |
| 8.政醇(まさあつ)〔従五位下、内匠頭 大番頭〕 |
政賢の四男 |
| 9.政和(まさより)〔従五位下、内匠頭 大番頭〕 |
政醇の長男 |
| 10.政世(まさよ)〔従五位下、内匠頭〕 |
政和の長男 |
廃藩置県
|
|

 |
谷氏は山城、近江、磐城などに分布し、このうち山城の谷氏は渡来系倭漢氏の後裔
戦国期の谷衛好の谷家は宇多源氏佐々木氏流で、高島氏の末裔と伝わるが、衛好の父である
福田正之は美濃の土豪でであり、この正之以前の経歴・系図は疑問点が多々あって明確ではない。
衛友は武勇に優れて秀吉の下で各地を転戦。加増を受けて最終的には丹波何鹿郡山家で
1万6000石を領した。関ヶ原の戦いでは西軍に与して田辺城の戦いに参加したが、やがて東軍に
寝返ったために所領を安堵される。
|
| |
林田藩
谷 家 |
外様、 1.6万石→1万石 丹波国
| 1.衛友(もりとも)〔従五位下、出羽守〕 |
谷衛好の3男 |
| 2.衛政(もりまさ)〔従五位下、大学頭〕 |
衛友の四男 |
| 3.衛広(もりひろ)〔従五位下、出羽守〕 |
藩主・谷衛政の長男・衛利の長男 |
| 4.衛憑(もりより)〔従五位下、播磨守〕 |
衛広の次男 |
| 5.衛衝(もりみち)〔従五位下、出羽守〕 |
衛憑の長男 |
| 6.衛将(もりまさ)〔従五位下、大学頭〕 |
衛衝の長男 |
| 7.衛秀(もりひで)〔従五位下、播磨守〕 |
衛衝の次男 |
| 8.衛量(もりかど)〔従五位下、播磨守〕 |
衛秀の次男 |
| 9.衛萬(もりたか)〔従五位下、大学頭〕 |
衛量の長男 |
| 10.衛弥(もりみつ)〔従五位下、右京亮〕 |
衛量の次男 |
| 11.衛昉(もりやす)〔従五位下、出羽守〕 |
摂津国麻田藩主・青木一貞の次男 |
| 12.衛弼(もりのり)〔従五位下、播磨守〕 |
近江膳所藩主・本多康禎の三男 |
| 13.衛滋(もりしげ)〔従五位下、大膳亮〕 |
常陸府中藩主松平頼説の五男 |
廃藩置県
|
|

ひとつやなぎ氏
 |
日本の氏族(武家)。本姓は越智氏。伊予国(現在の愛媛県)の河野氏の庶流。家紋は一柳釘抜
河野通直(弾正正弼通宣)の子の宣高のときに美濃国(岐阜県)の土岐氏の家臣になって一柳氏を称したと
言われている。宣高の孫の一柳直末・一柳直盛兄弟が豊臣秀吉に仕え、兄の直末は美濃国の
軽海西城主となったが小田原征伐のときに、緒戦の山中城攻めで戦死した。弟の直盛は尾張国
(今の愛知県西部)黒田城3万石の領主となり、関ヶ原の戦いでは東軍に属して伊勢国(三重県)
神戸藩5万石に加増転封された。更に寛永13年(1636年)には伊予国西条藩6万8600石に移転したが
同年死没した。彼の遺領は直重・直家・直頼の3人の息子たちによって分割された。 |
一柳 直重(ひとつやなぎ なおしげ)
慶長19年(1614年)からの大坂の陣では父と共に参戦している。父の死去により、3万石の伊予西条藩主
| |
西条藩
|
外様 3万石 伊予国
| 1.一柳 直盛 なおもり従五位下、監物 |
一柳直高の次男 |
| 2.一柳 直重 なおしげ従五位下、丹後守 |
直盛の長男 |
| 3.一柳 直興 なおおき従五位下、監物 |
直重の長男 |
参勤交代の遅参の届けが遅れ、しかも老中に届け出なかったこと、さらに藩政の悪政や
無作法などを理由とされて、寛文5年(1665年)7月29日、改易されてる
改易になったため、娘は母方の叔父である松平英親の養女となって竹腰正晴に嫁している。
なお、弟直照の系統は5000石の旗本として存続している。
|
一柳 直家(ひとつやなぎ なおいえ)
伊予西条藩主・一柳直盛の次男、直家は、寛永13年(1636年)の父の死に際し、播磨小野・伊予川之江領
2万8600石を与えられ、川之江藩の初代藩主となった。
| |
小野藩
一柳家 |
外様 2.8万石→1万石 播磨国 (1636年~1871年)兵庫県小野市万石
| 1.直家(なおいえ)〔従五位下、美作守〕 |
伊予西条藩主・一柳直盛の次男 |
| 2.直次(なおつぐ)〔従五位下、土佐守〕遺領相続により1万石 |
丹波園部藩主・小出吉親の次男 |
| 3.末礼(すえひろ)〔従五位下、土佐守 御側衆〕 |
直次の長男 |
| 4.末昆(すえひで)〔従五位下、土佐守 駿河加番〕 |
直次の次男 |
| 5.末栄(すえなが)〔従五位下、土佐守 駿河加番〕 |
末昆の長男 |
| 6.末英(すえふさ)〔従五位下、土佐守 駿河加番〕 |
末栄の長男 |
| 7.末昭(すえあきら)〔従五位下、対馬守〕 |
末英の次男 |
| 8.末周(すえちか)〔従五位下、土佐守 駿河加番〕 |
末英の三男 |
| 9.末延(すえのぶ)〔従五位下、土佐守 駿河加番〕 |
末周の長男 |
| 10.末彦(すえよし)〔従五位下、土佐守〕 |
末延の長男 |
| 11.末徳(すえのり)〔従五位下、対馬守〕 |
丹波綾部藩主・九鬼隆都の五男 |
廃藩置県
|
一柳 直頼(ひとつやなぎ なおより)
一柳直盛の三男、大坂の陣では人質として江戸に留められた。寛永13年(1636年)の父の死去により、
その遺領が分割されたため、直頼は小松1万石を相続して小松藩を立藩した。
| |
小松藩
一柳家 |
外様 1万石 伊予国 (1636年~1871年) 現・愛媛県西条市小松町
| 1.直頼(なおより)〔従五位下、因幡守〕 |
一柳直盛の三男 |
| 2.直治(なおはる)〔従五位下、兵部少輔〕 |
直頼の長男 |
| 3.頼徳(よりのり)〔従五位下、因幡守〕 |
直治の長男 |
| 4.頼邦(よりくに)〔従五位下、兵部少輔〕 |
一柳治良(第2代藩主一柳直治の次男)の長男 |
| 5.頼寿(よりかず)〔従五位下、美濃守〕 |
頼邦の三男 |
| 6.頼欽(よりよし)〔従五位下、兵部少輔〕 |
頼寿の次男 |
| 7.頼親(よりちか)〔従五位下、美濃守〕 |
頼欽の長男 |
| 8.頼紹(よりつぐ)〔従五位下、兵部少輔〕 |
一柳寿重(第5代藩主・一柳頼寿の七男)の長男 |
| 9.頼明(よりあきら)〔従五位下〕 |
頼紹の長男 |
廃藩置県
|
|

一関車前草
|
伊達政宗の正室・愛姫の実家である田村家は、天正18年の豊臣秀吉による小田原征伐に
参陣しなかったため、改易に処せられた。愛姫の生子である伊達忠宗は母の遺言により
承応2年、忠宗の三男・田村宗良に田村家を再興させ、栗原郡岩ヶ崎に1万石を与えられる。
仙台藩の支藩 岩沼藩 |
田村 建顕(たむら たつあき)
明暦2年(1656年)5月8日、陸奥仙台藩一門・田村宗良の次男として生まれる。万治3年(1660年)、父・宗良が陸奥岩沼藩3万石の
大名に取り立てられると、世子となる。寛文4年2月21日、元服して宗永と名乗り、同年11月、第4代将軍・徳川家綱に御目見する。
延宝9年(1681年)5月、岩沼から一関に移封された。宗永は学問に秀でていたため、第5代将軍・徳川綱吉に重用され、
元禄4年(1691年)には奥詰衆に取り立てられて譜代格となり、元禄5年(1692年)には奏者番を拝命する。同年大晦日、
建顕に改名する。
| 1 |
岩沼藩
田村家 |
外様 3万石 陸前国 現在の宮城県岩沼市
| 1.田村宗良(むねよし) 従五位下、右京亮、隠岐守 |
忠宗の3男 |
| 2.田村建顕(たつあき) 従五位下、右京大夫、因幡守 |
宗良の次男 |
寛文11年、伊達騒動(寛文事件)に際して指導的役割を果たすことが出来ず、幕命によって連座処分により閉門に処された。 |
| 2 |
一関藩
田村家 |
外様 3万石 陸奧国 陸奥磐井郡一関
| 1.建顕(たけあき)〔従五位下、右京大夫〕奏者番 宗良の次男 |
| 2.誠顕(のぶあき)〔従五位下、下総守〕 |
旗本の田村顕当の五男 |
| 3.村顕(むらあき)〔従五位下、隠岐守〕 |
宇和島藩の第3代藩主・伊達宗贇の次男 |
| 4.村隆(むらたか)〔従五位下、下総守〕 |
仙台藩主・伊達吉村の五男 |
| 5.村資(むらすけ)〔従五位下、左京大夫〕 |
伊達村良の庶長子 |
| 6.宗顕(むねあき)〔従五位下、右京大夫〕 |
堀田正敦(伊達宗村の八男)の次男 |
| 7.邦顕(くにあき)〔従五位下、左京大夫〕 |
宗顕の次男 |
| 8.邦行(くにゆき)〔従五位下、右京大夫〕 |
宗顕の四男 |
| 9.通顕(ゆきあき)〔字:磐二郎〕 |
邦行の長男 |
| 10.邦栄(くによし)〔従五位下、右京大夫〕 |
角田石川氏当主・石川義光の七男 |
| 11.崇顕(たかあき)〔従五位下、右京大夫〕 |
角田石川氏当主・石川義光の九男 |
廃藩置県
|
|
|
|