| 実 業 家 |
渋沢 栄一
しぶさわ えいいち

旭日桐花大綬章 |
天保11年2月:榛沢郡(現埼玉県深谷市血洗島)に父・市郎右衛門、母・エイの長男として生まれた。
渋沢家は藍玉の製造販売と養蚕を兼営し米、麦、野菜の生産も手がける豪農だった。
7歳の時には従兄の尾高惇忠の許に通い、四書五経や『日本外史』を学ぶ。剣術は、大川平兵衛より
神道無念流を学んだ。北辰一刀流の千葉栄次郎の道場(お玉が池の千葉道場)に入門し、剣術修行の
傍ら勤皇志士と交友を結ぶ。
江戸遊学の折より交際のあった一橋家家臣・平岡円四郎の推挙により一橋慶喜に仕えることになる。
主君の慶喜が将軍となったのに伴い幕臣となり、パリで行われる万国博覧会に将軍の名代として
出席する慶喜の弟・徳川昭武の随員として御勘定格陸軍付調役の肩書を得て、フランスへと渡航する。
大政奉還に伴い、慶応4年(1868年)5月には新政府から帰国を命じられ、1868年10月19日に
マルセイユから帰国の途につき、同年11月3日(12月16日)に横浜港に帰国した。
帰国後は静岡に謹慎していた慶喜と面会し、静岡藩より出仕することを命ぜられるも慶喜より
「これからはお前の道を行きなさい」との言葉を拝受し、フランスで学んだ株式会社制度を実践するため、
及び新政府からの拝借金返済の為、明治2年(1869年)1月、静岡にて商法会所を設立するが、
大隈重信に説得され、10月に大蔵省に入省する。大蔵官僚として民部省改正掛(当時、民部省と
大蔵省は事実上統合されていた)を率いて改革案の企画立案を行ったり、度量衡の制定や
国立銀行条例制定に携わる。
しかし、予算編成を巡って、大久保利通や大隈重信と対立し、明治6年に井上馨と共に退官した。
退官後間もなく、官僚時代に設立を指導していた第一国立銀行(第一銀行、第一勧業銀行を経て、
現:みずほ銀行)の頭取に就任し、以後は実業界に身を置く。
第一国立銀行ほか、東京瓦斯、東京海上火災保険、王子製紙(現王子製紙・日本製紙)、田園都市
(現東京急行電鉄)、秩父セメント(現太平洋セメント)、帝国ホテル、秩父鉄道、京阪電気鉄道、
(現東京急行電鉄)、秩父セメント(現太平洋セメント)、帝国ホテル、秩父鉄道、京阪電気鉄道、
その数は500以上といわれている。
渋沢が三井高福・岩崎弥太郎・安田善次郎・住友友純・古河市兵衛・大倉喜八郎などといった
他の明治の財閥創始者と大きく異なる点は、「渋沢財閥」を作らなかったことにある。
「私利を追わず公益を図る」との考えを、生涯に亘って貫き通し、後継者の敬三にもこれを固く戒めた。
昭和6年(1931年)11月11日)死去 (満91歳没) |
岩崎 弥太郎
いわさき やたろう
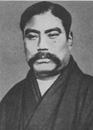 |
天保5年12月:土佐国(現在の高知県安芸市)の地下浪人・岩崎弥次郎と美和の長男として生まれる。
14歳頃には当時の藩主・山内豊熈に漢詩を披露し才を認められる。21歳の時、学問で身を
立てるべく江戸へ遊学し安積艮斎の塾に入塾する
慶応3年、後藤象二郎に藩の商務組織・土佐商会主任・長崎留守居役に抜擢され、藩の貿易に従事する
明治元年(1868年)、長崎の土佐商会が閉鎖されると、開成館大阪出張所(大阪商会)に移る。
明治2年(1869年)10月、大阪商会は九十九(つくも)商会と改称、弥太郎は海運業に従事する。
このころ、土佐屋善兵衛を称している。廃藩置県後の明治6年(1873年)に後藤象二郎の
肝煎りで土佐藩の負債を肩代わりする条件で船2隻を入手し海運業を始め、現在の大阪市西区堀江の
土佐藩蔵屋敷に九十九商会を改称した「三菱商会(後の郵便汽船三菱会社)」を設立。
各藩が発行していた藩札を新政府が買い上げることを事前に察知した弥太郎は、10万両の
資金を都合して藩札を大量に買占め、それを新政府に買い取らせて莫大な利益を得る。
三菱商会は、明治7年(1874年)の台湾出兵に際して軍事輸送を引き受け、政府の信任を得る。
大久保利通が暗殺や、大隈重信が失脚したことで、弥太郎は強力な後援者を失う。
明治15年(1882年)7月には、渋沢栄一や三井財閥の益田孝、大倉財閥の大倉喜八郎などの
反三菱財閥勢力が投資し合い共同運輸会社を設立して海運業を独占していた三菱に対抗した。
三菱と共同運輸との海運業をめぐる戦いは2年間も続き、運賃が競争開始以前の10分の1にまで
引き下げられるというすさまじさだった。
外国資本とも熾烈な競争を行い、これに対し弥太郎は船荷を担保にして資金を融資するという
荷為替金融(この事業が後の三菱銀行に発展)を考案し勝利した。
こうしたライバルとの競争の最中、明治18年2月7日18時30分、弥太郎は51歳で病死した。
弥太郎の死後、三菱商会は政府の後援で熾烈なダンピングを繰り広げた共同運輸会社と合併して
日本郵船となった。現在では日本郵船は三菱財閥の源流と言われている。 |
岩崎 弥之助
いわさき やのすけ
 |
嘉永4年1月岩崎弥次郎・美和夫妻の三男として土佐国安芸郡井ノ口村に生まれた。
明治2年)には大阪に出て、重野安繹の私塾成達書院に入門した。
明治5年)4月、アメリカに留学。横浜で貿易商をしていたウォルシュ・ホール社のウォルシュ家に寄宿し、
コネチカット州エリントンにある男子校で学ぶ、明治6年)11月に父の弥次郎が急逝し、
兄の懇願もあって留学を中断し帰国。1874年(明治7年)の秋、後藤象二郎の長女・早苗と結婚した。
敬愛する弥太郎の事業を助けるとともに、2代目総帥として三菱の多角化に尽力。
銀行・倉庫・地所・造船などの事業を興した。三菱の総帥の座を甥の久弥(弥太郎の長男)に
譲った後に第4代日本銀行総裁となった。
1908年3月25日(満57歳没)
|
岩崎 久弥
いわさき ひさや
 |
慶応元年8月:岩崎弥太郎・喜勢夫妻の長男として土佐国に生まれた。父・弥太郎は三菱財閥の創設者。
福澤諭吉の慶應義塾に幼稚舎から入塾。3年後に父が開設した三菱商業学校(明治義塾)に転じ、
英語や簿記、法律、経済を学んだ。慶應義塾普通部を卒業後、1886年(明治24年)にアメリカの
ペンシルベニア大学に留学。
1891年に帰国後、副社長として三菱社に入り、1893年、三菱社の合資会社転換と共に、
叔父・岩崎弥之助に代わって社長に就任。
以後、1916年にいとこの岩崎小弥太に社長を譲るまで、三菱財閥三代目として長崎造船所の
近代化や東京・丸の内地区の開発など事業の拡充を図り、麒麟麦酒などの創業にも関わった。
太平洋戦争後の1947年、財閥解体政策により、3人の息子と共に財閥家族に指定され、三菱傘下
企業の全役職を辞任。千葉県富里にあった末廣農場の別邸にて引退生活を送った。
東京都江東区清澄の清澄庭園、文京区本駒込の六義園(りくぎえん)は、それぞれ1924年と
1938年に久弥が東京市に寄付したものである。
寧子(しずこ)夫人(旧上総国飯野藩第10代藩主・保科正益子爵の長女)との間に3男3女がいる。
長男・彦弥太は三菱本社副社長、三菱地所取締役を歴任。
次男・隆弥は三菱製紙元会長。
三男・恒弥は東京海上火災保険元常務。
1955年12月2日(満90歳没)
|
岩崎 小弥太
いわさき こやた
 |
明治12年8月:2代目岩崎弥之助(岩崎弥太郎の弟)の長男として東京府(現・東京都)に生まれた。
母は後藤象二郎の長女早苗である。
1896年(明治29年)に高等師範学校附属中学校(現・筑波大学附属中学校・高等学校)を卒業。
旧制第一高等学校の寮の同室には馬場鍈一がいた。一高を経て東京帝国大学法科大学に
入学するが中退。
明治38年)ケンブリッジ大学を卒業し、翌年帰国して三菱合資会社の副社長となり、
大正5年、いとこである3代目岩崎久弥(弥太郎の長男)のあとをつぎ、社長に就任、
三菱財閥の4代目となった。
大正6年)から各事業部を株式会社として独立させることにより、三菱財閥の形態を完成させた。
ほかに三菱造船、三菱製鉄、三菱電機、三菱内燃機、三菱重工業、三菱航空機、三菱化成などの
各企業によって、三菱を日本最大の重工業企業集団に成長させ、日本が富国強兵を進める上で
中心的な役割を果たした。ちなみに、現在も使われている「重工業」という言葉は、小弥太が英文の
「Heavy Industries」に当てて発案した造語である。
昭和20年8月の日本の敗戦時には病の床にあり、GHQの圧力による財閥解体には最後まで抵抗したが、
適わず、それに落胆したのか、同年12月に没した。1945年12月2日(満66歳没)
|
安田 善次郎
やすだ ぜんじろう
 |
天保9年10月:富山藩下級武士(足軽)の安田善悦の子としてうまれる。 安田財閥の祖
安政5年)、奉公人として江戸に出る。最初は玩具屋、ついで鰹節兼両替商に勤めた。
1870年代には北海道で最初の私鉄である釧路鉄道(本社 安田銀行本店)を敷設し硫黄鉱山開発
硫黄の輸送や加工のための蒸気機関の燃料調達を目的に釧路炭田(後の太平洋興発の前身
を開発した。北米への硫黄輸出のためにそれまで小さな漁港に過ぎなかった釧路港を特別輸出港に
指定させた。現在のみずほ銀行釧路支店の礎となる根室銀行を設立し、
魚場集落だった釧路は道東最大の都市へと急激に発展した。
このように金融財閥家の基礎は釧路の硫黄鉱山経営と輸出で築かれたといわれている。
自分の天職を金融業と定め、私的に事業を営むことを自ら戒めたが、同郷だった浅野総一郎の
事業を支援するなど事業の育成を惜しむことはなかった(現在の鶴見線である鶴見臨港鉄道の
安善駅は、安田善次郎の名前に因む)。また日本電気鉄道や、帝国ホテルの設立発起人、
東京電燈会社や南満州鉄道への参画、日銀の監事など、この時代の国家運営にも深く関わった。
東京大学の安田講堂や、日比谷公会堂、千代田区立麹町中学校校地は善次郎の寄贈によるもの
安田銀行(後の富士銀行。現在のみずほフィナンシャルグループ)を設立
損保会社(現在の損害保険ジャパン)、生保会社(現在の明治安田生命保険)、
東京建物等を次々と設立した。
1921年9月28日(満82歳没) |
住友 友純
すみとも ともいと
 |
元治元年12月:東山天皇の5世孫である従一位右大臣徳大寺公純の第6子として生まれた。
兄に従二位権中納言徳大寺実則、正三位右中将西園寺公望、従四位中院通規
明治16年11月、隆麿20歳の時父公純没。明治17年東京神田錦町に移り、徳大寺邸に入り、
習院に入学した。
明治25年4月18日、隆麿(29歳)は、長女満寿(19歳)の婿として住友登久の養嗣子となった。
明治26年4月、住友15世をつぎ、隆麿を改め、住友吉左衛門友純と称した。のちに春翠と号した。
明治26年4月28日相続の式をあげ、以来家業を継承して、別子銅山の鉱業を経営し、
神戸市に銅貿易をなし、また再製茶及び樟脳製造業を行い、滋賀県坂田郡醒ヵ井村において
生糸業を営む、広瀬宰平が総理人としてあり、実際の経営に当たるが、友純は別子銅山を巡視し、
各社を視察し、庄司炭坑を買収した。
住友家では明治28年には本店を富島町より中之島5丁目に移し、同所に住友銀行を開業し、
神戸支店、川口、兵庫出張所をおいている。
大正15年3月2日逝去。享年63。
大正15年3月9日、住友厚が吉左衛門を襲名し、5月1日、吉左衛門が襲爵。 |
古河 市兵衛
ふるかわ いちべえ
 |
天保3年3月:生家の木村家は京都岡崎で代々庄屋を務める家柄であったが、父の代には没落しており、
巳之助は幼少の頃から豆腐を売り歩く貧乏暮らしで苦労を重ねた。
嘉永2年(1849年)、盛岡に向かう。盛岡では叔父のもとで貸金の取立てを手伝う。
やがて南部藩御用商人の鴻池屋伊助店(草間直方が旧名時代に起こした店)に勤めるが、まもなく倒産。
安政4年、叔父の口利きで京都小野組の番頭だった古河太郎左衛門の養子となり、
翌年には古河市兵衛と改名した。
その後養父と共に生糸の買い付けを行っていたが、養父に才能を認められ、順調に小野組内の
地位を高めていく。明治維新期の時流にも乗り、東北地方の生糸を横浜に送り巨利を挙げるなどの
成功を収めるが、明治新政府の公金取り扱い業務の政策変更の結果、小野組は壊滅的な打撃を蒙り、
市兵衛は再び挫折を味わうことになる。
小野組と取引があった渋沢栄一が経営していた第一銀行に対し、市兵衛は倒産した小野組の
資産や資材を提供して第一銀行の連鎖倒産を防ぎ、渋沢栄一という有力な協力者を得ることに成功した。
小野組破綻後、市兵衛は独立して事業を行うことにした。まず手始めに秋田県にある当時官営で
であった有力鉱山、阿仁鉱山と院内鉱山の払い下げを求めたが、これは却下された。
明治10年(1877年)には市兵衛は鉱山業に専念する決意を固め、いよいよ足尾銅山を買収することになる
(現在の古河機械金属)
古河財閥は足尾銅山発展の中で形成されていった。
鉱山経営を進める一方で、銅山を中心とした経営の多角化にも着手。
明治17年(1884年)には精銅品質向上による輸出拡大と、銅加工品の生産による国内市場開拓を目指して
本所溶銅所を開設した。この事業は後の古河電気工業へと発展していくことになる。
明治36年(1903年)4月5日)死去
|
大倉 喜八郎
おおくら きはちろう
 |
天保8年9月越後国北蒲原郡新発田町の下町に父・千之助、母・千勢子の三男として生まれる。
23歳の時に尊敬していた祖父の通称・喜八郎から名を取り、喜八郎と改名
江戸到着後、狂歌仲間の和風亭国吉のもとで塩物商いの手伝い経たのち、中川鰹節店で
丁稚見習いとして奉公した。丁稚時代に安田善次郎と親交を持つようになる。
安政4年(1857年)には奉公中に貯めた100両を元手に独立し、乾物店大倉屋を開業。
横浜で黒船を見たことを契機に乾物店を慶応2年(1866年)に廃業し、同年10月に小泉屋鉄砲店に
に見習いに入る。約4ヶ月間、小泉屋のもとで鉄砲商いを見習い、慶応3年(1867年)に独立し、
鉄砲店大倉屋を開業
大倉は明治元年(1868年)に有栖川宮熾仁親王御用達となり、奥州征討軍の輜重にあたる。
明治4年(1871年)3月に新橋駅建設工事の一部を請け負う。
同じ頃、高島嘉右衛門らとともに横浜水道会社を設立し、建設工事に着工
明治14年に鹿鳴館建設工事に着工、藤田伝三郎らとともに発起人となった大阪紡績会社も設立した。
明治15年3月には日本初の電力会社・東京電燈を矢島作郎、蜂須賀茂韶とともに設立し、
明治26年に大倉土木組を設立し、日本土木会社の事業を継承、大倉組商会と内外用達会社を
合併するなど、この頃から大倉財閥の片鱗を窺わせ始める。
明治39年(1906年)に麦酒三社合同による大日本麦酒株式会社設立に関係し、
翌40年には日清豆粕製造(現日清オイリオ)、日本皮革(現ニッピ)、日本化学工業、
帝国製麻(現帝国繊維)、東海紙料(現東海パルプ)を設立。
昭和3年(1928年)4月22日死去、没年92歳
|
益田 孝
ますだ たかし
 |
嘉永元年10月現在の新潟県佐渡市相川に生まれる。幼名は徳之進。
父の鷹之助は箱館奉行を務めた後、江戸に赴任。
孝も江戸に出て、ヘボン塾(現・明治学院大学)に学び、麻布善福寺に置かれていたアメリカ公使館に
勤務、ハリスから英語を学ぶ。
文久3年(1863年)、フランスに派遣された父とともにヨーロッパを訪れている。
慶応3年(1867年)6月15日には旗本となり、慶応4年(1868年)1月には騎兵頭並に昇進した。
明治維新後は横浜の貿易商館に勤務、明治5年(1872年)に井上馨の勧めで大蔵省に入り
造幣権頭となり大阪へ。
明治7年には、英語力を買われ井上が設立した先収会社では東京本店頭取(副社長)に就任。
明治9年先収会社を改組して三井物産設立と共に同社の初代総轄(社長)に就任する。
三井物産では綿糸、綿布、生糸、石炭、米など様々な物品を取扱い、明治後期には日本の
貿易総額の2割ほどを占める大商社に育て上げた。
1938年12月28日(満90歳没)
|
中上川
彦次郎
なかみがわ ひこじろう
 |
嘉永7年8月:大分県中津市金谷森ノ丁に豊前中津藩士・中上川才蔵・婉夫妻の長男として生まれる。
明治2年)には東京留学が許され慶應義塾に入学。卒業後、中津市学校・伊予宇和島藩の
洋学会社の教員などを歴任後、小泉信吉と共にイギリス留学、元老院議官井上馨を知る。
1878年、工部卿・井上馨に誘われて工部省に入省。井上馨の秘書官となる。
井上が外務卿となると中上川も外務省に入り、従六位に叙せられ太政官少書記官となり、
1880年に、外務省太政官権大書記官に昇進、従五位に進む。
三菱の荘田平五郎から社長就任の要請があり、1887年山陽鉄道(現在のJR山陽本線の前身
創設時の社長となる。1891年、山陽鉄道を辞して三井銀行に入行、理事となる。
王子製紙・鐘淵紡績・芝浦製作所などを傘下に置いて三井財閥の工業化を推進した。
1893年、日本郵船会社取締役に就任
|
團 琢磨
だん たくま
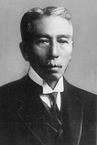 |
安政5年8月:筑前国福岡荒戸町で、福岡藩士馬廻役神尾宅之丞の四男として生まれる。
12歳の時、藩の勘定奉行、團尚静の養子となり、藩校修猷館に学ぶ。
明治4年(1871年)、金子堅太郎らと共に旧福岡藩主黒田長知の供をして岩倉使節団に
同行して渡米し、そのまま留学する。
明治11年)、マサチューセッツ工科大学鉱山学科を卒業し帰国する。
明治17年)に工部省に移り、鉱山局次席、更に三池鉱山局技師となる。
明治21年)に三池鉱山が政府から三井に売却された後はそのまま三井に移り、
三井三池炭鉱社事務長に就任する。
明治26年)、三井鉱山合資会社専務理事となる。1899年(明治32年)、工学博士号を受ける。
明治42年)、三井鉱山会長となる。この頃、團の手腕により三井鉱山の利益は三井銀行を追い抜いて
三井物産と肩を並べるようになり、「三井のドル箱」と言われた三池が三井財閥形成の原動力となった。
大正3年)には益田孝の後任として三井合名会社理事長に就任し、三井財閥の総帥となる。
昭和7年)3月5日、東京日本橋の三越本店寄り三井本館入り口で血盟団の
菱沼五郎に狙撃され、暗殺された |
朝吹 英二
あさぶき えいじ
 |
嘉永2年2月豊前国中津藩宮園村の大庄屋・朝吹泰蔵の次男として生まれた
維新後の明治3年(1870年)、開明派の福澤諭吉暗殺を企てるが、転向し福澤とその甥
中上川彦次郎の庇護を受け、彦次郎の妹・澄(スミ)と結婚する。
慶應義塾に学び、明治11年、三菱商会に入社。明治13年、貿易商会に入って取締役となる。
独立して横浜で貿易業を営むもののうまくいかず大隈重信に近い政商となり、義父・彦次郎の
三井財閥に転じて三井呉服店理事となり、明治25年(1892年)に鐘ヶ淵紡績専務、明治27年に
三井工業部専務理事に就任。
明治34年(1901年)、中上川が死去すると、益田孝により中上川の工業化路線は一旦は止まったが、
それでも明治35年に三井管理部専務理事に就任し、王子製紙会社では役員を務めて会長となり、
また、芝浦製作所、堺セルロイドなど王子と共に業績不振とされたこれら企業の建て直しを
担当することとなった。このように三井系諸会社の重職を歴任し、「三井の四天王」の一人と言われた。
|
| 思 想 家 |
福澤 諭吉
ふくざわゆきち
 |
天保5年12月12日(1835年1月10日)- 明治34年(1901年)2月3日
日本の武士(中津藩士のち旗本)、蘭学者、著述家、啓蒙思想家、教育者。慶應義塾の創設者であり
安政元年(1854年)、19歳で長崎へ遊学して蘭学を学ぶ。
を圧倒していた足守藩下士で蘭学者・緒方洪庵の適塾(適々斎塾)で学ぶこととなった。
安政3年(1856年)、再び大坂へ出て学ぶ。同年、兄が死に福澤家の家督を継ぐことになる。
幕末の時勢の中、無役の旗本で石高わずか40石の勝安房守(号は海舟)らが登用されたことで、
安政5年(1858年)、諭吉にも中津藩から江戸出府を命じられる(差出人は江戸居留守役の岡見清熙)。
江戸の中津藩邸に開かれていた蘭学塾[8]の講師となるために築地鉄砲洲にあった奥平家の
中屋敷に住み込み、そこで蘭学を教えた。
万延元年1月19日(1860年2月10日)、諭吉は咸臨丸の艦長となる軍艦奉行・木村摂津守の従者として、
アメリカへ立つ。同年5月5日(1860年6月23日)に帰国。
諭吉と咸臨丸の指揮官を務めた勝海舟はあまり仲が良くなかった様子で、晩年まで険悪な関係が続いた
諭吉も翻訳方として幕府直参で、150俵・15両を受けて、御目見以上となり、「御旗本」となった
慶応3年1月23日(1867年2月27日)には使節主席・小野友五郎と共に幕府の軍艦受取委員会随員として
再渡米、同年6月27日(1867年7月28日)に帰国した。現地で小野と揉めたため帰国後はしばらく
謹慎することとなったが、中島三郎助の働きかけですぐに解けた。
この年の末(12月9日)、朝廷は王政復古を宣言した。江戸開城後、諭吉は新政府から出仕を求められ
たが辞退し、以後も官職に就かなかった。翌年には帯刀をやめて平民となった
慶応4年(1868年)には蘭学塾を慶應義塾と名付け、教育活動に専念する。
明治8年(1875年)、諭吉は懇意にしていた森有礼の屋敷で寺島宗則や箕作秋坪らと共に、
初めて大久保利通と会談した。
岩倉具視・九鬼隆一らも加わって大隈一派を政府内から一掃する明治十四年の政変が起こる
諭吉は伊藤と井上馨との交際を絶つこととなった。
日清戦争の支援
明治27年(1894年)3月に日本亡命中の金玉均が朝鮮政府に上海におびき出されて暗殺される
事件があり、再び日本国内の主戦論が高まった
諭吉も金玉均の死を悼み、相識の僧に法名と位牌を作らせて自家の仏壇に安置している
戦費の募金運動を積極的に行い、自身で1万円という大金を募金するとともに、
三井財閥の三井八郎右衛門、三菱財閥の岩崎久弥、渋沢財閥の渋沢栄一らとともに
戦費募金組織「報国会」を結成した
晩年の諭吉の主な活動には海軍拡張の必要性を強調する言論を行ったり、
男女道徳の一新を企図して『女大学評論 新女大学』を著したり、
北里柴三郎の伝染病研究所の設立を援助したことなどがあげられる
明治34年(1901年)1月25日に脳溢血が再発し、2月3日に東京で死去した。
|
幸徳 秋水
こうとく しゅうすい
 |
1871年11月5日(明治4年9月23日) - 1911年(明治44年)1月24日
明治時代のジャーナリスト、思想家、社会主義者、無政府主義者である。
高知県幡多郡中村町(現在の高知県四万十市)に生まれる。
幸徳家は、酒造業と薬種業を営む町の有力者で、陰陽道をよくする陰陽師の家であった。
秋水の名は、師事していた中江兆民から与えられたもの。大逆事件(幸徳事件)で処刑された12名の1人
幸徳事件(こうとくじけん)は、大逆事件の一つであり、明治天皇を爆裂弾で暗殺しようとした計画が
発覚した事件である。明治43年1月24日処刑された
|
内村 鑑三
うちむら かんぞう
 |
万延2年2月13日(1861年3月23日)- 昭和5年(1930年)3月28日
日本のキリスト教思想家・文学者・伝道者・聖書学者。福音主義信仰と時事社会批判に基づく
日本独自のいわゆる無教会主義を唱えた。
高崎藩士・内村宜之とヤソの6男1女の長男として江戸小石川の武士長屋に生まれる。
明治6年(1873年)に単身で上京して、有馬学校英語科に入学した。
在学中、一年だけ病気のために休学し、杉田玄端から治療を受けた。一年遅れたことにより
新渡戸稲造、宮部金吾と同級になる。明治11年(1878年)6月2日には、アメリカ・メソジスト教会の
M.C.ハリスから洗礼を受ける。
内村は水産学を専攻し明治14年(1881年)7月、札幌農学校を農学士として主席で卒業した。
明治15年(1882年)に開拓使が廃止されると、札幌県御用係になり、漁業調査と水産学の研究を行った。
アメリカ留学時代
明治18年)6月にカーリンはワシントンD.C.の全米慈善矯正会議に出席する際に内村を同行した。
内村はペンシルベニア大学で医学と生物学を学び医者になる道を考えていた。
(明治21年)1月まで学業を続けたが退学。神学の学位は得ないまま、5月に帰国。
明治22年(1889年) - 東洋英和学校、東京水産伝習所、明治女学校に教える。
明治36年 - 日露非開戦論、戦争絶対反対論を「萬朝報」「聖書之研究」で発表。萬朝報客員を辞す
大正7年(1918年) - 中田重治、木村清松らと共に、再臨運動を始める。
昭和5年(1930年) - 3月28日死去
|
中江 兆民
なかえ ちょうみん
 |
弘化4年11月1日(1847年12月8日) - 明治34年(1901年)12月13日
日本の思想家、ジャーナリスト、政治家(衆議院議員)
高知城下の土佐郡北街山田町に生まれる。
文久2年(1862年)には藩校の文武館開校と同時に入門し、細川潤次郎、萩原三圭らの門下で学ぶ。
明治政府が派遣した岩倉使節団には司法省9等出仕として採用される。
明治8年(1875年)には東京外国語学校の校長となるが、徳育教育を重視する兆民は教育方針をめぐり
文部省と対立したとされ、直後に辞職。
後藤象二郎の農商務大臣辞職を求める封書を代筆するなど運動に関わったため、
同年公布の保安条例で東京を追われる。また、明治21年(1888年)には仏学塾も廃塾となる。
翌明治22年(1889年)には大日本帝国憲法発布の恩赦を得て追放処分が解除され、
明治23年(1890年)の第1回衆議院議員総選挙では大阪4区から出馬し、一位で当選、国会議員となる。
明治24年(1891年)9月に立憲自由党が結党され、『立憲自由新聞』の主筆を務めたが、
自由党土佐派の裏切りによって政府予算案が成立したことに憤り2月に辞職。
明治24年(1891年)7月には北海道の小樽へ移り、実業家として活動を行う。
明治26年(1893年)には山林組を起業して札幌で材木業を始める。
国民同盟会の会議に出席するが、大阪で病床に臥せ、満54歳で死去、死因は喉頭癌。
|
西 周
にし あまね
 |
文政12年2月3日(1829年3月7日) - 明治30年(1897年)1月31日
江戸時代後期から明治時代初期の幕臣、官僚、啓蒙思想家、教育者。
石見国津和野藩(現、島根県津和野町)の御典医の家柄。
天保12年(1841年)に藩校・養老館で蘭学を学んだ。
文久2年(1862年)には幕命で津田真道・榎本武揚らとともにオランダに留学し、
慶応元年(1865年)に帰国した後、目付に就任、徳川慶喜の側近として活動する。
慶応4年(1868年)、徳川家によって開設された沼津兵学校初代校長に就任。
明治6年(1873年)には森有礼・福澤諭吉・加藤弘之・中村正直・西村茂樹・津田真道らと共に明六社を
結成し、翌年から機関紙『明六雑誌』を発行。啓蒙家として、西洋哲学の翻訳・紹介等、哲学の基礎を
築くことに尽力した。
明治17年(1884年)頃から右半身が麻痺しはじめ、明治20年(1887年)、健康上の理由により
文部省・陸軍省・学士会院会員の公職を辞職した。
明治23年(1890年)には貴族院議員に任じられ、同年10月20日、錦鶏間祗候となる
明治30年(1897年)、明治天皇は西の功績に対し勲一等瑞宝章、男爵の位を授けた。
同年1月31日に死去。享年68
|
高野 房太郎
たかの ふさたろう |
1869年1月6日(明治元年11月24日)-1904年3月12日
明治期日本の労働組合運動の先駆者。長崎県出身。
高等小学校卒業後、1886年に渡米してアメリカでアメリカ労働総同盟(AFL)会長の
サミュエル・ゴンパーズの教えを請う。
生活協同組合運動の先駆者でもある。中国青島で亡くなった。
|
新島 襄
にいじま じょう
|
天保14年1月14日(1843年2月12日) - 明治23年(1890年)1月23日
天保14年、江戸の神田にあった上州安中藩江戸屋敷で、安中藩士・新島民治の子として生まれる。
慶応2年(1866年)12月、アンドーヴァー神学校付属教会で洗礼を受ける。慶応3年(1867年)に
フィリップス・アカデミーを卒業。
明治5年(1872年)、アメリカ訪問中の岩倉使節団と会う。襄の語学力に目をつけた木戸孝允は、
4月16日から翌年1月にかけて自分付けの通訳として使節団に参加させた。
明治8年(1875年)京都府知事・槇村正直、府顧問・山本覚馬の賛同を得て官許同志社英学校を
開校し初代社長に就任する。明治9年(1876年)1月3日、山本覚馬の妹・八重と結婚する。
明治10年(1877年)には同志社女学校(のちの同志社女子大学)を設立。
明治23年(1890年)1月23日死去する。死因は急性腹膜炎。
|
岡倉 天心
おかくら てんしん |
1863年2月14日(文久2年12月26日) - 1913年(大正2年)9月2日
横浜の本町1丁目(現・横浜開港記念会館付近)に生まれる。福井藩出身の武家で、
1871年に家族で東京に移転
東京美術学校(現・東京藝術大学の前身の一つ)の設立に大きく貢献し、日本美術院を創設した。
|
夏目 漱石
なつめそうせき
 |
1867年2月9日(慶応3年1月5日) - 1916年(大正5年)12月9日
江戸の牛込馬場下に名主・夏目小兵衛直克、千枝の末子(五男)として出生。
父・直克は江戸の牛込から高田馬場一帯を治めている名主で、公務を取り扱い、
かなりの権力を持っていて、生活も豊かだった
大学時代に正岡子規と出会い、俳句を学ぶ。帝国大学(現在の東京大学)英文科卒業後、
松山で愛媛県尋常中学校教師、熊本で第五高等学校教授などを務めた後、イギリスへ留学。
帰国後、東京帝国大学講師として英文学を講じながら、「吾輩は猫である」を雑誌『ホトトギス』に発表。
これが評判になり「坊っちゃん」「倫敦塔」などを書く。
その後朝日新聞社に入社し、「虞美人草」「三四郎」などを掲載。
|
正岡 子規
まさおか しき
 |
1867年10月14日(慶応3年9月17日) - 1902年(明治35年)9月19日
松山藩士正岡常尚と八重の間に長男として生まれた。母は、藩の儒者大原観山の長女。
愛媛一中、共立学校で同級だった秋山真之とは、松山在住時からの友人であり、また共通の。
友人として勝田主計がいた。東大予備門では夏目漱石・南方熊楠・山田美妙らと同窓。
明治27年)夏に日清戦争が勃発すると、翌1895年(明治28年)4月、近衛師団つきの従軍記者として
遼東半島に渡ったものの、上陸した2日後に下関条約が調印されたため、同年5月、
第2軍兵站部軍医部長の森林太郎(鴎外)等に挨拶をして帰国の途についた
その船中で喀血して重態に陥り、神戸病院に入院。7月、須磨保養院で療養したのち、松山に帰郷した。
明治30年)に俳句雑誌『ホトトギス』(ほとゝぎす)を創刊し、俳句分類や与謝蕪村などを研究し、
俳句の世界に大きく貢献した。明治35年)9月:死去。享年34 |
与謝野 晶子
よさのあきこ
 |
1878年(明治11年)12月7日 - 1942年(昭和17年)5月29日
堺県和泉国第一大区甲斐町(現在の大阪府堺市)で老舗和菓子屋「駿河屋」を営む、
父・鳳宗七、母・津祢の三女として生まれた。
堺市立堺女学校(現・大阪府立泉陽高等学校)に入学すると『源氏物語』などを読み始め古典に親しんだ。
日本の歌人、作家、思想家。
女性の官能をおおらかに謳う処女歌集『みだれ髪』を刊行し、浪漫派の歌人としてのスタイルを確立した。
明治37年)9月、『君死にたまふことなかれ』を『明星』に発表。
大正10年)に建築家の西村伊作と、画家の石井柏亭そして夫の鉄幹らとともにお茶の水駿河台に
文化学院を創設する。昭和17年)、死去
|
樋口 一葉
ひぐち いちよう
 |
1872年5月2日(明治5年3月25日)- 1896年(明治29年)11月23日
東京府第二大区一小区内幸町の東京府庁構内(現在の東京都千代田区)の長屋で生まれる。
一葉の家庭は転居が多く、生涯に12回の引っ越しをした。
一葉は、遠視や弱視ではなく、近眼のため細かい仕事に向いていないということはないはずだが、
針仕事を蔑視していたので、自分にできる他の収入の道を探していたところ、
同門の姉弟子である田辺花圃が小説『薮の鶯』で多額の原稿料を得たのを知り、
小説を書こうと決意する。
20歳で「かれ尾花一もと」を執筆。同年に執筆した随想で「一葉」の筆名を
明治29年)には『文芸倶楽部』に「たけくらべ」が一括掲載されると鴎外や露伴らから絶賛を受け、
森鴎外は「めさまし草」で一葉を高く評価した。
明治29年一葉は当時治療法がなかった肺結核が進行しており、8月に恢復が絶望的との診断を受けた。
11月23日に24歳と6ヶ月で死去
一葉の作家生活は14ヶ月余りで、死後の翌年『一葉全集』『校訂一葉全集』が刊行された。
|
森 鷗外
もり おうがい |
1862年2月17日(文久2年1月19日) - 1922年(大正11年)7月9日 津和野藩
亀井家の御典医をつとめる森家 陸軍軍医になり、陸軍省については陸軍総覧を参考して下さい。
小説家、評論家、翻訳家について記載
明治22年8月 - 『国民之友』に訳詩編「於母影」を発表
明治23年1月 - 『医事新論』を創刊。『国民之友』に「舞姫」を発表
8月 - 『しからみ草紙』に「うたかたの記」を発表。この作品は、石橋忍月との論争の火種になる。
明治24年9月 - 『しからみ草紙』に「山房論文」を発表。早稲田文学で坪内逍遙と没理想論争を交わす。
明治25年11月 - 『しからみ草紙』にアンデルセンの「即興詩人」を連載
明治29年1月 - 『めさまし草』を創刊
明治44年月 - 『スバル』に「雁」を連載。
大正5年1月、『中央公論』に「高瀬舟」を、『新小説』に「寒山拾得」を発表
大正2年1月 - 『中央公論』に「阿部一族」を発表
|
野口 英世
のぐち ひでよ |
|
 |
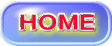 |