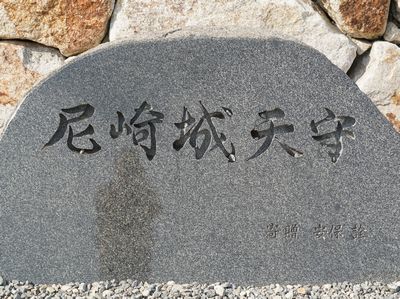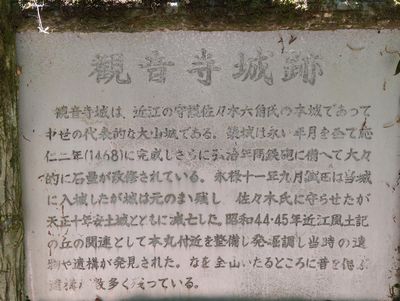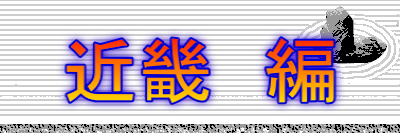| |
| |
| |
| |
2025.11.に日本三大山城へ行きました
| 高取城(奈良)日本100名城(61番) |
高取城(奈良) |
高取城(奈良)
|
 |
 |
|
高取城の碑(二の丸)
標高583メートル、比高350メートルの高取山山上に
築かれた山城である。日本三大山城(備中松山城・岐阜県
岩村城・高取城) |
壺坂門跡
南北朝時代、南朝方であった越智邦澄が1332年に築城した
のが始まりと伝えられている。高取城は1580年に一旦は
廃城となった。大和国は秀長の配下となった。
|
壺坂門跡の石垣
秀長の重臣脇坂安治が入ったが、後に同じく重臣の
本多利久に与えられた。利久の子俊政は秀吉の直臣
となり1万5千石が与えられた。秀吉没後の混乱期に、
俊政は徳川家康についた。 |
|
| 高取城(奈良) |
高取城(奈良)大手門 |
高取城(奈良)
|
 |
 |
|
大手門跡
寛永17年(1640年)旗本の植村家政が2万5,000石の
大名に取り立てられ新たな城主となった。以後、明治維新
植村氏が14代って城主となった。 |
高取城の登城するルートは3ヶ所あり、①壷阪山駅から一升坂
、猿石、二の門、三の門、矢ノ門、矢場門、松ノ門、宇陀門、
千早門、大手門 2時間20分
②壺坂寺から壺坂口登城ルート1時間40分
③壺坂登城口まで車にて 1時間 今回は③コースにて登城
|
十三間多門跡
高取城は建物無いが石垣が立派に残っており圧巻です
25000石としては大規模の城である
|
|
|
|
|
|
| 2024年5月14日~19日まで滋賀県・兵庫県・徳島県・愛知県のお城巡りへ |
| 伊丹城(有岡城)(兵庫) |
伊丹城(有岡城)(兵庫) |
伊丹城(有岡城)(兵庫)
|
 |
 |
|
南北朝時代、摂津国人の伊丹氏によって建築、伊丹城が
日本最古の天守台を持つ平城、1574年11月28日)、
荒木村重によって攻め落とされ大改修し、有岡城に改称
|
荒木村重は後に謀反を起こし、黒田孝高(如水・官兵衛)
謀反をやめるように説得へ行が、当城内にあった牢内に
1年弱幽閉されていた。織田信長に滅ぼし去れ逃亡
|
天正11年(1583年)廃除となる。現在は当時の石垣
一部が残ってJR伊丹駅付近が城内となっている
城の範囲は南北1.7km、東西0.8kmで南北に細長く |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 尼崎城(兵庫) |
尼崎城(兵庫) |
尼崎城(兵庫)
|
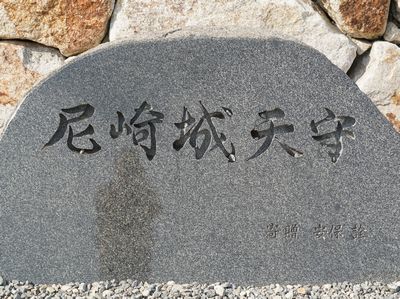 |
 |
|
元和3年(1617年)、戸田氏鉄(うじかね)が5万石で
入封し築いた。3重の堀をもち、本丸には2重の付櫓を
2棟付属させた複合式の四重天守と3棟の |
三重櫓が上げられた。城主は、築城から廃城まで3氏12代が
入れ替わった。建部家-池田家-戸田家-青山家4代-
松平〔桜井〕家7代
|
平成30年(2018年)には資産家の寄贈による外観復元
天守が完成した。
|
|
| 徳島城(徳島) 日本100名城(76番) |
復元された鷲の門 |
腰曲輪
|
 |
 |
|
この地は鎌倉時代より伊予国地頭の河野氏が支配
1582年(天正10年)には土佐国の長宗我部元親が侵攻し
阿波が平定、1585年(天正13年)、豊臣秀吉の四国征伐
に勲功のあった蜂須賀家政(蜂須賀正勝の子)が |
阿波1国18万6000石を賜った。
江戸時代を通して外様ながら徳島藩蜂須賀氏25万7千石
の居城となり、明治維新を迎える。
|
吉野川河口の三角州に位置の標高61mの渭山に本丸を
配置して天守閣は建てられず、西二の丸、西三の丸
東二の丸に天守代用の御三階櫓が建てられた、
|
|
| 徳島城(徳島) 日本100名城(76番) |
黒門(大手門)枡形の石垣 |
堀と黒門
|
 |
 |
|
1526年(大永6年)、三好氏の重臣・安宅治興が築城
1581年(天正9年)の淡路討伐の際、羽柴秀吉に降り、
城は仙石秀久に与えられた。 |
徳島城は石垣が綺麗に整備されいる
|
月見櫓が建っていた。奥の橋は黒門(大手門)に架かる
下乗橋
|
|
| 徳島城(徳島) 日本100名城(76番) |
数奇屋橋 |
数奇屋橋
|
 |
 |
|
下乗橋
太鼓橋で殿様の住む御殿への出入り口で枡形の門で
厳重に守られていた |
徳島城の鬼門にあたる門で別門「不明門」という
城内での凶事の際以外には開かない門である
|
徳島城は明治初期に壊され、昭和の空襲により破壊
今回は午後6時頃に登城で本丸まで上がらず
|
|
| 洲本城(兵庫淡路)続日本100名城(164番) |
大手門付近 駐車場左側 |
腰曲輪
|
 |
 |
|
1526年(大永6年)三好氏の重臣・安宅治興が築城
1581年(天正9年)の淡路討伐の際、羽柴秀吉に降り、
城は仙石秀久に与えられた。 |
1585年10月に脇坂安治が城主となり、城の大改修を行った。
大坂夏の陣の後、徳島藩の蜂須賀氏の所領となる
|
壮大な総石垣、大石段、全国で数例しかない登り石垣など
があります。
|
|
| 洲本城(兵庫淡路)続日本100名城(164番) |
本丸大石段 |
本丸虎口
|
 |
 |
|
| 南の丸と右石垣は本丸台 |
階段の石垣で本丸虎口へ
|
本丸虎口直角に曲がり
|
|
| 洲本城(兵庫淡路)続日本100名城(164番) |
洲本城からの眺望 |
本丸
|
 |
 |
|
模擬天守と天守台
老朽化で天守閣には登れない、模擬天守は昭和3年に
築造された
|
洲本市の町並みと大阪湾 素晴らしい景観です
|
天守台から見る本丸跡で広い空間で
江戸時代は蜂須賀氏の所領となり、筆頭家老の
稲田氏一族を配置
|
|
| 龍野城(兵庫) |
埋門 |
隅櫓
|
 |
 |
|
明応8年(1499年)に塩屋城の龍野赤松氏・赤松村秀が
龍野に鶏籠山城を築いた。天正5年(1577年)に開城し
て赤松氏から豊臣秀吉の手に渡り、播磨平定 |
寛文12年(1672年)に脇坂安政によって龍野城が再建され
脇坂家外様→願譜代→譜代 53000石 初代は豊臣秀吉
に仕え、加藤清正と同じ七本槍の一人で
|
脇坂家3代目は譜代大名下総国佐倉藩主・堀田正盛の
次男・安政を養子として、以後譜代大名となり9代は老中
までになった名門
|
|
| 赤穂城(兵庫) 日本100名城(60番) |
本丸表門(復元)高麗門 |
二の丸門
|
 |
 |
|
赤穂城の前身となる城郭は、池田長政が慶長5年
(1600年)に築城したと伝わり、正保2年(1645年)に
浅野長直が赤穂へ入封、13年かかって完成し、 |
10の隅櫓門が12基、曲輪の延長は2847mに及んだ。
天守そのものは建築されなかった。
|
歴代城主
池田家:外様 3万5千石2代 浅野家:外様 5万石3代
永井家:譜代 3万2千石1代 森 家:外様 2万石13代
|
|
| 赤穂城(兵庫) 日本100名城(60番) |
本丸御殿の遺構と表門 |
天守台
|
 |
 |
|
表門入口の堀と石垣
浅野家3代の浅野内匠頭長矩は江戸城松の廊下で
吉良義央を切付けてて怪我させ即切腹と改易を宣告した。 |
浅野内匠頭長矩の仇討ちについて、城近くに大石神社
大石内蔵助の長屋門跡がある
|
天守台はりっぱな石垣となっているが天守閣は建設
されず、本丸御所はコンクリート盤上に部屋の間仕切りを
示し、坪庭跡には中高木を植栽。
|
|
| 赤穂城(兵庫) 日本100名城(60番) |
大手門 |
大手門(高麗門)二層隅櫓
|
 |
 |
|
本丸厩口門)
厩口門は、浅野家時代の呼び名で、森家時代には台所門
と呼ばれていました。 |
大手門が登城口になります。三之丸は堀の外側にあり
門は、虎口は内枡形をなし、東面する高麗門と南面する櫓門
|
大手隅櫓は大手門の北にある二重櫓で、大手門を監視
するための防御施設でした。
|
|
| 観音寺城(滋賀) 日本100名城(52番) |
観音寺城・観音正寺へ |
階段途中の石垣(門跡)
|
 |
 |
|
繖(きぬがさ)山(観音寺城・観音正寺)
観音寺城は近江源氏の佐々木氏、後に近江守護六角氏
の居城で、戦国時代の永禄期に浅井長政、織田信長に
攻められて六角氏は逃亡無血開城、その後は廃城となる。 |
観音寺城への登城登山口数ヶ所あります、今回は
観音正寺駐車場に止めて、キツイ400段の階段を登る
疲れを癒やすキンラン一輪咲いている
|
あ-登りキツイょ 足場も悪く昔の階段
誰もいなく3組だけすれ違う
|
|
| 観音寺城(滋賀) 日本100名城(52番) |
観音正寺 参拝 |
本丸への石垣
|
 |
 |
|
観音正寺からの展望
観音寺城・観音正寺への車での行き方は表門の駐車場
と五個莊ルート』裏駐車場あり、表からは車止め急な階段
裏ルート駐車場からは登りやすい道
|
観音正寺は天台宗で本尊は千手観音、
西国三十三所第32番札所、山号は繖山(きぬがささん)
創建時期は不明であるが11世紀平安時代には既に存在
入山料500円
|
濡佛(銅造釈迦如来坐像)の横を下り本丸へ
樹木が生い茂り整備されてない中を15分歩くと本丸
|
|
| 観音寺城(滋賀) 日本100名城(52番) |
裏虎口より本丸跡へ |
本丸のある看板
|
 |
 |
|
本丸の石垣
本丸跡は樹木が多く整備されてなく不満あり
|
今回は本丸まで到着して石垣の名物である平井丸、
潜り門、平井丸虎口、池田丸跡などには体力的に
キツイので中止した
|
今回の観音寺城としてまず登りから始まり大変な
道のりで、情報を詳細に調査してから登城すべき
だったと反省する
|
|
| 八幡山城(滋賀) 続日本100名城(157番) |
本丸周りは石垣が多く残り |
出丸 広場
|
 |
 |
|
本丸下の石垣
独立丘鶴翼山、通称八幡山(標高283m)の南半分
山上に築城された。安土城の焼失から3年後、1585年
(天正13年)築城を開始、豊臣秀次はは18歳で入城する
が3年しか八幡山城に居なかったと言われている。
|
築城から5年後(1590年)、秀次は100万石を領し清州へ
移封となり京極高次が城主となりましたが、1595年、秀次が
自刃後に八幡山城は廃城となる
|
八幡山城は廃城後は石垣だけ残り、出丸下の石垣は
1540年代のまま残っている。八幡山城の本格的な調査は
これから本格的に始まる
|
|
| 八幡山城(滋賀) 続日本100名城(157番) |
本丸の裏側石垣 |
北の丸より安土城と観音寺城を望む
|
 |
 |
|
北の丸の広場
山城部分は総石垣作りで、本丸、二の丸、北の丸、
西の丸、出丸がY字形に延びる放射状に配置され、
それぞれに高石垣で構築されている。
|
本丸周りが石垣を積んで今でも崩れなく残っている
|
左側低い山が安土城 高い山が観音寺城
|
|
| 八幡山城(滋賀) 続日本100名城(157番) |
瑞龍寺 |
出丸下の石垣(1580年代頃)
|
 |
 |
|
本末虎口門跡
昭和38年に京都より移築された瑞龍寺の門が
八幡山城の本丸虎口となっている。
瑞龍寺は日蓮宗唯一の門跡寺院です。
|
瑞龍寺
1596年(文禄5年)、豊臣秀次の生母(秀吉の姉)日秀尼公に
より、秀次の菩提を弔うため、後陽成天皇から瑞龍寺の寺号と
京都村雲の地に賜り創建され、昭和36年)に京都より この
八幡山へ主要建物が移築されました。
|
城下町は、安土城の城下町の町民を移して町づくり、
近隣の町村からも移住を促した。八幡堀は琵琶湖から
引いた八幡町の外に巡らし、八幡山の麓を八幡堀と塁で
囲み、その中に羽柴秀次居館や武家屋敷を配し、防御と
同時に運河として重視した。
|
|
| 安土城 日本100名城(51番) |
安土城 大手道 入り口 右側 前田利家邸跡 |
安土城 (豊臣秀吉邸跡)
|
 |
 |
|
安土城跡 碑
安土城は織田信長によって現在の安土山に建造され
標高約200mの安土山山上にあり、天正4年(1576年)
から3年有余をかけ完成した五層七重の、わが国最初の
天主閣を有する城。
|
大手道に入るまえに700円支払い直ぐに左側の広場は
豊臣秀吉の館跡で石垣が良し、と右側には前田利家の
館跡あり、上右側には元は徳川家康邸跡で現は摠見寺
本殿の建物あり,階段410段あり、途中には石仏を使用
|
織田信長公が天下統一を目標に天正四年(1576)
1月十四日重臣である丹羽長秀を総普請奉行に据えて
安土山に築城させる。岐阜城より京に近く、利便性良く
北陸・東海の要所である
|
|
| 安土城 日本100名城(51番) |
安土城 天主閣への階段 |
安土城 本丸跡 周りは石垣 |
 |
 |
|
黒金門跡
虎口(90度曲がって攻めにくい門で安土城の中でも
もっとも大きな石が使われている
黒金門は安土城の中心部に入る最初の入口である |
天主閣へ入る最後の階段で5重6階、地下1階の天主
高さは46m、43mの説
|
本丸広場となって千畳敷で回りは石垣囲まれ東西
約50m、南北約34mの東西に細長い敷地
天皇を迎える御殿もあったようです
奥から三の丸へ |
|
| 安土城 日本100名城(51番) |
安土城 天主閣から望む琵琶湖 |
安土城 二の丸跡の信長 本廟 |
 |
 |
|
天主閣跡
1582年(天正10年)に起きた本能寺の変の後、
まもなくして焼失、豪華絢爛の天主閣は3年にて焼失した |
天主台から見る琵琶湖と近江八幡の田園
本丸、天守台等に関してはまだ発掘途中である
|
安土城の二の丸跡と伝えられる場所に織田信長の
本廟があります。1583年(天正11年)2月に羽柴秀吉に
よって建立された |
|
| 安土城 日本100名城(47番) |
摠見寺跡より琵琶湖 |
摠見寺の山門 重要文化財 |
 |
 |
|
摠見寺三重塔 重要文化財
摠見寺は織田信長が安土城築城にあわせて建立した寺院、
天主崩落の際にも焼け残ったのですが、1854年
(安政元年)11月16日に火災により焼失してしまい、
現在は礎石のみが残されています。 |
摠見寺跡より琵琶湖を望む
江戸時代末期の嘉永7年大手道脇の伝徳川家康邸跡に
寺院を移し、現在に至るまで法灯を守り続けています。
|
天主閣から帰り道、織田信忠邸上から摠見寺跡へ
寺院跡の広場は展望良くゆっくり琵琶湖を望む
追加
織田信忠邸・森 蘭丸邸・織田信澄邸など碑があります
長谷川秀一邸跡には織田信雄とその子孫の供養塔 |
|
近畿編 平成28年4月5日~4月8日まで関西方面のお城巡りに行ってきました。春欄間で各お城の桜満開で
ライトアップが奇麗で特に姫路城は特別で何回見ても飽きない |
| 伏見城 |
伏見城 |
伏見城 |
 |
 |
|
伏見城
豊臣秀吉の隠居として建設慶長2年)に完成した
秀吉の死後、五大老筆頭の徳川家康が
入り政務をとった。
|
関ヶ原前に家康の家臣鳥居元忠ら石田三成に
迫られ自刃焼失した伏見城は1602年(慶長7年)
頃に家康によって再建され、1619年(元和5年)に
廃城とされた。
|
昭和36年に伏見桃山城キャッスルランド」が建設され、
その後倒産して京都に寄贈するが、耐震に問題があり
修復に高価格2012年10月時点では具体的に活用がない |
|
| 水口城跡 |
水口城跡 |
甲賀忍術館 |
 |
 |
|
水口城
3代将軍徳川家光が京都への上洛の際の宿館として、
道中の水口に築かせた。1682年(天和2年)に
加藤明友が2万石で入城し、水口藩が成立した。 |
水口藩歴代藩主
加藤家:(譜代格) 2万石(1682年 - 1695年)2代
鳥居家:譜代 2万石(1695年 - 1712年)1代
加藤家:(譜代格) 2万5,000石(1712年-1871年)9代
|
甲賀五十三家筆頭望月本家の旧邸
からくり仕掛け、忍者の道具等の展示や説明 |
|
| 伊賀上野城 日本100名城(47番) |
伊賀上野城 |
伊賀上野城 |
 |
 |
 |
伊賀上野城
織田信雄(北畠信雄)の家臣である滝川雄利は
平楽寺の跡に砦を築いた。その後天正13年(1585年)
に筒井定次によって改修
|
慶長16年に徳川家康の命を負って藤堂高虎が拡張した
筒井家:20万石。外様 富田:外様。5万石(1595年-)
藤堂家:外様 27万950石 12代 |
大阪に続ぐ石垣の高さ約30mである |
|
| 伊賀上野城 日本100名城(47番) |
伊賀上野城 |
伊賀上野城 |
 |
 |
 |
伊賀上野城 2024年11月7日 石垣のみ撮影
素晴らしい石垣
|
|
大阪城に続ぐ石垣の高さ約30mである |
|
|
|
2025年11月に2回目の登城しました
|
| 大和郡山城 続日本100名城(165番) |
大和郡山城 |
大和郡山城 |
 |
 |
 |
天守台
前回の登城時には天守台は工事中で行けない状態
で今回は薬師寺より4kmと近い |
天守台より追手向櫓
正面は番屋カフェにて昼食をとる。広場には柿が豊富
|
天守台より薬師寺
|
|
| 岸和田城 続日本100名城(161番) |
岸和田城 |
岸和田城 |
 |
 |
 |
岸和田城
羽柴秀吉の紀州征伐の拠点として再築城され。
豊臣秀吉は小出秀政3万石城主に
|
岸和田藩歴代藩主
小出家:外様 3万石→5万石(1600年~1619年)
松平〔松井〕家:譜代5万石→6万石(1619年~1640年)
岡部家:譜代5.3万石 (1640年~1871年) 13代
|
大雨の中で桜満開で綺麗な堀、天守は10:00よりで
登城せずライトアップも良いようで再度来たい
昭和29年天守再建、昭和44年城門と櫓再建 |
|
| 和歌山城 日本100名城(62番) |
和歌山城 |
和歌山城 |
 |
 |
 |
和歌山城
豊臣秀吉の弟・秀長が築城して紀伊・和泉の2ヶ国を
治める普請奉行に藤堂高虎、補佐役に羽田正親、
横浜良慶を任じ、1年で完成させた。
|
紀州藩 藩主
江戸期は徳川御三家の一つ紀州藩紀州徳川家の
居城である。
浅野家:外様 37万6,000石
徳川家(紀州徳川家):親藩 55万5,000石11代
|
明治4年廃城令により解体もしくは移転、昭和10年国宝に
昭和20年に空襲により炎上、昭和33年により再建
平成18年御橋廊下復元開始 |
|
| 明石城 日本100名城(58番) |
明石城 |
明石城 |
 |
 |
 |
明石城
徳川幕府が西国の外様大名の抑えの城として、
譜代大名たる小笠原氏10万石の居城として城郭を、
建設するよう、第2代・将軍徳川秀忠より築城命令された。
|
明石藩 藩主
小笠原家 、松平〔戸田)〕家 、大久保家、
松平〔藤井〕家、本多家、
松平〔越前〕家:親藩6万石→8万石(10万石格)10代
|
天守は建設なく櫓合計:20基、門合計:27棟あった。
現在の櫓は2つで明治34年- 巽櫓と坤櫓の修理 |
|
2024年5月16日8年ぶりに関西方面へ
| 姫路城 日本100名城(59番) |
姫路城 |
姫路城 |
 |
 |
 |
姫路城 国宝
強風の中8年ぶりに姫路城へ70%以上が外国人
今回は西の丸だけ内部をみる |
姫路城の堀と石垣
2024年5月16日 撮影
|
現在の大手門(桐二の門) |
|
| 姫路城 日本100名城(59番) |
姫路城 |
姫路城 |
 |
 |
 |
| 姫路城 三の丸広場 |
菱の門 |
西の丸より天主閣
|
|
| 姫路城 日本100名城(59番) |
姫路城 |
姫路城 |
 |
 |
 |
姫路城 国宝
姫路城の始まりは、1346年の赤松貞範による
築城が有力戦国時代は黒田家、羽柴家が
城代となる、山陽道上の交通の要衝で姫路城は
本格的な城郭に拡張
|
姫路藩 藩主
池田家:外様 52万石3代、本多家:譜代15万石3代、
松平(奥平)家、松平(越前)家、榊原(松平)家
、松平(越前)家本多家、榊原家、松平(越前)家、
酒井家:10代
雨降りの中、突然に西の空から太陽出て城を照らす
|
昭和6年)1月、大小天守など8棟が国宝に指定
1993年世界文化遺産
平成大修理後ライトアップ奇麗、
中央の画像は夕陽照す
|
|
| 立雲峡より竹田城 日本100名城(56番) |
立雲峡より竹田城 |
立雲峡より竹田城 |
 |
|
 |
竹田城
永享3年(1431年)に但馬守護山名宗全(持豊)
によって築城され、太田垣光景が初代城主と
言われる伝承を紹介している。
秀吉は秀長を有子山城主に、秀長の武将で
ある桑山重晴を竹田城主にそれぞれ命じた。
|
江戸幕府の方針により、竹田城は廃城となった。
東に立雲峡を望む標高353.7mの古城山(虎臥山)
の山頂に築かれ縄張りは南北約400m、東西約100m。
|
立雲峡から撮影予定で山頂へ登る途中雨降り出し
山頂断念する。桜が両方満開で綺麗、立雲峡の
駐車場は天気悪いのか空き多い
|
|
| 福知山城 続日本100名城(158番) |
福知山城 |
福知山城 |
 |
 |
 |
福知山城
小笠原長清の末裔とされる福知山地方の国人
塩見頼勝が、八幡山の脇に掻上城を築城した
のが始まりと言われる。丹波国を平定した
明智光秀が築城し、女婿の明智秀満を
城主とした。 |
福知山 藩主
江戸幕府歴代藩主
有馬家:6万石→8万石 外様、岡部家、稲葉家、
松平(深溝)朽木(くつき)家:3万2000石。譜代 13代
|
天守の石垣には宝篋印塔、五輪灯篭どの石造物が
大量に使用。
明智光秀は丹波を平定後に福知山城と
改名する。
|
|
| 丹波篠山城 日本100名城(57番) |
丹波篠山城 |
丹波篠山城 |
 |
|
|
丹波篠山城
徳川家康は豊臣、西国諸大名のおさえとするのが
目的で築城を命じた。藤堂高虎が縄張を担当した。
普請総奉行を池田輝政が務め6か月で完成した。
|
歴代藩主
松平〔松井〕家、松平〔藤井〕家、松平〔形原〕家5代
青山家:譜代 5万石 (1748年 - 1871年)6代
|
明治6年) - 城郭の建造物が取り壊され始めた
昭和19年)1月6日 - 失火により大書院が焼失
昭和28年)頃 - 内堀が埋め立てられ、公園化が進む
|
|
| 追加画像 |
| 大阪城 日本100名城(54番) |
大阪城 |
大阪城 |
 |
 |
 |
大阪城 1984年撮影
1583年に豊臣秀吉が築城後1629年徳川家康が修築
江戸時代は天領地となり、大阪城代が預かる
1665年落雷により天守火災消失し、その後天守はない
1931年復興天守建設(SCR)現代にいたる |
大阪城 天守閣 2025年11月撮影
今回で4回目の登城 全景を撮影するに大阪歴史博物館
10階へ、外人観光客が多く天守閣には登れず
|
大阪城 天守閣 2025年11月撮影
天気快晴、紅葉には1週間早いようで、石垣は素晴らしい
|
|
| 大阪城 日本100名城(54番) |
|
|
 |
 |
 |
大阪城 大阪歴史博物館 10階より撮影
天守閣の後の高層ビルがきになる、石垣はみごと1 |
大阪城 南外堀の石垣と六番櫓
大手前芝生広場付近より撮影 櫓と石垣が堀水に映り良い |
大阪城 大阪歴史博物館 10階より撮影
大手門と内堀の石垣と天守閣 |
|
| 大阪城 日本100名城(54番) |
|
|
 |
 |
 |
大阪城 大阪歴史博物館 10階より撮影
天守閣のズームアップ |
大手門前より千貫櫓と多門櫓
石垣が高く敵からの防御完璧である、千貫櫓
|
大手門付近の多門櫓と巨石が2つ配置
重要文化財 |
|
| 大阪城 日本100名城(54番) |
|
|
 |
 |
 |
大手門枡形 多門櫓 重要文化財
右側に巨石2ヶ所 順位が4.5位
|
桜門 重要文化財
豊臣時代に桜並木があったそうで桜門となっている
本丸の入口で内堀を渡る |
蛸石 巨大 巨石 城内第1位
高さ:5.5m、横幅:11.7m、重さ:130t 岡山藩池田忠雄
|
|
| |
|
|