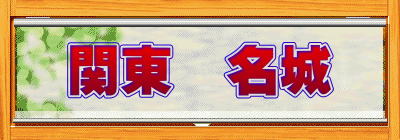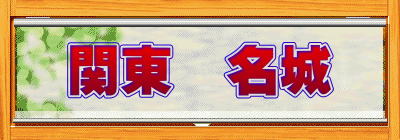| |
| (埼玉県の城) |
| 2021年11月24日~25日 埼玉県 百名城巡りと川越古町並み・神社/仏閣巡り及び渋沢栄一生誕地へ |
| 忍 城 続日本100名城(118番) |
忍 城 |
小田原城 |
|
|
|
|
|
忍城 (埼玉)2013.6 撮影 平山城
1478年成田氏築城で豊臣秀吉が成田家を攻める。
水攻めで落城しなかった。
別名:忍の浮き城、亀城 映画「のぼうの城」で有名
|
忍藩歴代藩主
松平(深溝)家、松平(東条)家、松平(大河内)家
阿部家9代 10万石、松平(奥平)5代 10万石 幕末
|
小田原城(神奈川)2013.4 撮影 平山城
耐震対策前
|
|
| 深谷城跡(公園) |
深谷城跡 |
深谷城跡 |

|
|
|
|
深谷城の概要 平城
1456年に深谷上杉氏の上杉房憲が築いたものである
徳川家康の関東入部に伴い、長沢松平家の松平康直が
1万石で入城した。
|
石垣復元
家康の七男松千代、兄の六男忠輝が継いだ。
1610年に桜井松平氏の松平忠重が入封
その後酒井忠勝が1万石を領有して入封したが
武蔵国川越へ移封となり、深谷藩は廃藩となり廃城
|
石垣と曲輪復元
1924年(大正13年)に県指定旧跡となり城址公園として
整備されているが、遺構の多くは埋没している。
|
|
| 鉢形城跡 日本100名城(18番) |
鉢形城跡 |
鉢形城跡 |
 |
 |
 |
|
鉢形城の概要 笹曲輪
鉢形城は、深沢川が荒川に合流する付近の両河川が
谷を刻む断崖上の天然の要害に立地をなしています。
鉢形城歴史館
24日は休館で予約が必要で入館できず
|
四脚門(復元) 三ノ曲輪
築城したのは関東管領山内上杉氏の家臣である
長尾景春と伝えられている。
小田原の後北条氏に北条氏邦となるが、1590年豊臣秀吉
による小田原征伐がはじまり、前田利家やその他の
武将により落城
|
復元石垣 三の曲輪
本曲輪付近は建物や駐車場がなく碑があるが見れず
|
|
| 鉢形城跡 日本100名城(18番) |
鉢形城跡 |
鉢形城跡 |
|
|
 |
|
|
ニノ曲輪西側の馬出 堀と橋
深い空堀で防御は完璧である。
|
伝逸見曲輪とおくり泉水
近くに駐車できる広場あり
針形城を見学方法としては鉢形城歴史館を見て
裏側から登ると車道に出て公園地図に従って歩くといい
|
大手口から外郭より本郭を見る
荒川から見た鉢形城。断崖絶壁の上に築かれている。
正喜橋(荒川)の手前にセブンイレブンあり駐車して
対岸の針形城 撮影出来ます。 |
|
| 杉山城跡 続日本100名城(119番) |
杉山城跡 |
杉山城跡 |
 |
|
|
|
杉山城の概要
市野川左岸の山の上に築かれた山城だが、築城の主や
年代についてはほとんど分かっていない。
地元豪族の金子主水による築城との伝承はあるが、
文献資料には現れない。
|
馬出郭から南三ノ郭
基本的には曲輪とそれに伴う堀や土塁のほか井戸跡の
遺構が確認されている。本郭で、土塁及びそれに伴う
溝、本郭の東虎口に平坦な石を用いて石列がつくられていた。
|
大手口から外郭より本郭を見る
杉山城について、山内上杉家の家宰を務めた長尾顕忠
(あきただ)の居城であったとする説がある。
杉山城の築城を山内上杉氏によるものとする根拠 |
|
| 杉山城跡 続日本100名城(119番) |
杉山城跡 |
杉山城跡 |
|
|
|
|
|
本郭の碑と説明板
室町時代に関東管領の役職にあった山内上杉氏が、
対立関係にあった扇谷上杉氏に対抗して築いたと
考えられています。
|
本郭から東二ノ郭と東三の郭
左右は深い谷で敵の攻撃を防げる構造である。
玉ノ丘中学校の校舎が見える。
|
本郭(ほんくるわ)より大手口方面
杉山城に登城するには玉ノ岡中学校門下に駐車場あり
校門に入り途中から右に曲がるとお墓あり
大手口にはいる |
|
| 菅谷館跡 続日本100名城(120番) |
菅谷城跡 |
菅谷城跡 |
|
|
|
|
|
菅谷城は平城
築城は不明で鎌倉幕府の有力御家人として知られる
畠山重忠の館跡である。
1488年、菅谷館そばの菅谷原において山内上杉家と
扇谷上杉家が激戦を繰り広げ、山内上杉顕定の命を
受けた太田資康が菅谷の旧城を再興した。
|
畠山重忠公の像
1205年、畠山重忠が武蔵国二俣川(現・横浜市旭区)で
戦死したのちは畠山の名跡を継いだが、15世紀後半に
至るまでの詳細は不明である。
|
本郭(ほんくるわ)
本郭は東西150m、南北60mn長方形をしており、
約9000㎡の広さ、周りは四方土塁で囲まれて奥側に
出入り口生門跡ある |
|
| 菅谷館 続日本100名城(120番) |
菅谷城 |
菅谷城 |
|
|
|
|
|
出枡形土塁と本郭の土塁
空堀で
|
西ノ郭から見る木橋(復元)と
正坫門(しょうてんもん)跡
|
三ノ郭
現在は雑木林になっており、紅葉綺麗
|
|
| 川越城 日本100名城(19番) |
川越城 |
川越城 |
|
|
|
 |
|
川越城は平山城
1457年太田道真・道灌親子が築城 上杉朝定(扇谷)と
北条氏康の戦いで再々により「川越夜戦」で扇谷上杉氏は
滅亡するが、豊臣秀吉による小田原征伐で滅び、
川越城は前田利家に攻められて落城
|
川越城本丸御殿
1848年に越前松平4代藩主松平 斉典が建てられた
入母屋造りで、豪壮な大唐破風と霧除けのついた
間口19間・奥行5間の大玄関 現存する御殿は高知城だけ
城郭御殿には二条城と掛川城がある。 |
現在本丸御殿周りが工事中で整備さてるようである。
川越藩の歴代藩主
酒井〔雅楽頭〕家→酒井〔雅楽頭家分家〕2→堀田家→
松平〔大河内〕家3→柳沢家→秋元家4→松平〔越前〕家7
→松平〔松井〕家2 |
|
| 川越城 日本100名城(19番) |
川越城 |
川越城 |
|
|
 |
 |
|
御殿の中庭
当時は16棟、1025坪の規模をもっていた。
明治に入ると廃城令で多くの建物は解体され、現在残る
建物は玄関・大広間部分と家老詰所のみとなっている
|
富士見櫓跡
本丸御殿から南西へ直線で150メートル所に小高い丘に
城内で最も高い位置にあたり、この地に三層の富士見櫓あった
川越城には天守がなく富士見櫓が天守の代わりとなっていた。
|
中の門堀跡
本丸御殿から市役所方面へ約300メートル西方
現在は門を再現して堀あり、
かつての西大手門は川越市役所前に、
本丸門は初雁球場近くに田曲輪門は富士見櫓近くに
、南大手門は第一小学校西門近辺にあった。、
|
|
| (茨城県の城) |
| 2021年11月11日~12日に茨城県のお城巡りと紅葉(別項参照)の旅 |
| 水戸城 日本100名城(14番) |
水戸城 |
水戸城 |
|
|
|
|
|
連郭式平山城 復元の大手門
水戸市の中心部、水戸駅の北側に隣接する丘陵に築城
平安時代から馬場氏 室町は江戸氏 戦国は佐竹氏
江戸時代は徳川御三家の居城
|
大手門の内側より
2021年6月より一般公開する。
水戸城の二の丸は現在小中高学校と幼稚園となっており
今は空堀を道路や常磐線が走る
|
二の丸を真ん中に道が整備され右側に案内所あり
正面は杉山門で手前を右側350m進むと二の丸角櫓再建
|
|
| 水戸城 日本100名城(14番) |
水戸城 |
水戸城 |
|
|
|
|
二の丸隅櫓
二の丸隅櫓 再建 令和3年6月公開
外側からは駅又は、三の丸ホテルから撮れそう
|
弘道館の入口
三の丸は弘道館で第9代徳川斉昭により創設された。
以前は重臣屋敷があった
|
正門 (重要文化財)
本瓦葺きの四脚門、総檜作り、藩主の来館や正式な行事
の際にのみ開聞 |
|
| 笠間城 続日本100名城(112番) |
笠間城 |
笠間城 |
|
|
|
|
|
笠間城は佐白山にある山城である
築城主は笠間時朝 1219年築城 改修は蒲生郷成
現在は大手門前にある駐車場に止め本丸まで20分
車道途中に坂本九さんのプレートあり
|
笠間藩歴代藩主 大手門跡の碑
戦国期笠間氏は宗家の宇都宮氏に滅ぼされる。その後宇都宮氏
は豊臣時代に下野国18万石所領であるが突然改易
その後蒲生郷成が入城して城郭に改修した
|
天守台付近の石垣
東日本大地震で一部石垣破損している。
|
|
| 笠間城 続日本100名城(112番) |
笠間城 |
笠間城 |
|
|
|
|
|
天守台跡の碑でここから急な石階段
江戸時代の城主 3万~8万石
松平(松井)家→小笠原家→松平(戸田)家→
永井家→浅野家2→井上家2→本庄家2→
本庄家2→井上家3→牧野家9代(1740~1871)
笠間藩の牧野氏は越後長岡藩の支藩とされる
|
天守曲輪城道
本丸八幡台上にあった八幡台櫓が真浄寺に移築され現存
今回は行くのを忘れてしまい残念
3代の藩主牧野 貞喜は名君で藩政改革と笠間焼を発展
|
天守曲輪に鎮座する佐志能神社
今後笠間市のお城整備を期待する
|
|
| 土浦城 続日本100名城(113番) |
土浦城 |
土浦城 |
|
|
|
|
|
土浦城 別名 亀城 輪郭式平城
室町時代に築かれ、江戸時代に段階的に増改築されて
形を整えた。土浦は時々水害にあうが城は水没せず
亀のように浮いたので亀城と言われる。
|
太鼓櫓門 本丸から
1429年 若泉三郎が築城 1562年頃 菅谷勝貞の居城
菅谷氏は小田氏の配下で、豊臣秀吉の小田原征伐の際に
菅谷・小田は後北条氏と結んだため家康・佐竹に滅ぼされる |
太鼓櫓門 二の丸より
土浦藩の歴代藩主
松平(藤井)家2代3.5万石→西尾家2代2万石→
朽木家2→土屋家2代4.5万石→松平(大河内)家→
土屋家10代9.5万石(1687年~1871年) |
|
| 土浦城 続日本100名城(113番) |
土浦城 |
土浦城 |
|
|
|
|
|
西櫓
平成4年に保管されていた部材を用いて復元された
2011年の東日本大地震で壁破損 太鼓櫓門も破損
|
東櫓と堀
平成10年)には東櫓が再建する
2011年の東日本大地震で壁破損
土屋家は元は武田家の家臣であり、その後井伊直政家臣
武田家の山本勘助4代の家臣もいたそうである
|
前川門口
土屋家は譜代大名で徳川幕府綱吉から4代にわたって
老中となり、9.5万石までになった。
|
|
| (千葉県の城) |
| 大多喜城 続日本100名城(122番) |
大多喜城 |
大多喜城 |
|
|
|
|
|
大多喜城(千葉)2014.2.6 連郭式平山城
1521年に真里谷信清(武田氏)が小田喜城を築城
江戸初期に徳川家康の武将”本多忠勝”によって
|
大多喜藩歴代藩主
本多家 3代10万石 ~3万石、阿部家・青山家・・・
松平(大河内)譜代 2万石→改易→2万石 9代 幕末 |
撮影スポットは新丁交差点の近くにある夷隅川に
かかる橋上からいすみ鉄道鉄橋と大多喜城がベスト
1975年再建 |
|
コロナ感染減少により2021年11月4日千葉県の日本100名城巡りへ 本佐倉城と佐倉城へ
| 佐倉城 日本100名城(20番) |
佐倉城 |
佐倉城 |
|
|
|
|
|
佐倉城 連郭式平山城 別名 鹿島城
戦国時代、本佐倉城主千葉親胤が大叔父にあたる
鹿島幹胤に命じて築城を開始したが、親胤が
暗殺されたために工事は中断、千葉邦胤の代にも
工事が試みられたが邦胤の暗殺によって頓挫
|
復元された椎木門・馬出
1610年(慶長15年)に、徳川家康の命を受けた土井利勝に
よって築城が再開され、佐倉城が完成した。
城郭は石垣を一切用いず、 天守は三重櫓を代用
城は、鹿島山(標高30メートル)に築き周りは川と湿地
|
二の丸跡
歴代城主
武田家→松平→小笠原家→土井家→石川家→松平(形原)2
→堀田家2→松平(大給)家→大久保家→戸田家2
→稲葉家2→松平(大給)家2→堀田家6 11万石 |
| 佐倉城 日本100名城(20番) |
佐倉城 |
佐倉 |
|
|
|
|
|
天守台と本丸跡
佐倉城には江戸時代の建物は一つもなく深い空堀だけが
昔の面影を残す、明治初期に廃城後陸軍歩兵第2連隊
明治43年からは歩兵第57連隊が戦後まで駐屯地
となっていた。
|
堀田正睦(正義)銅像
堀田 正睦は下総国佐倉藩5代藩主
天保12年3月23日に本丸老中に任命され
安政2年(1855年)10月老中首座、幕末動乱で安政の大獄で
井伊直弼は正睦を始めとする一橋派の排斥を始めた。
|
武家屋敷とひよどり坂
ひよどり坂付近は武家屋敷があり、現在3家だけ
内部公開しております。
国立国立歴史民俗博物館が見ごたえあり、
レストランもあります。 |
|
| 本佐倉城 続日本100名城(121番) |
本佐倉城 |
本佐倉城 |
|
|
 |
|
|
本佐倉城(千葉) 連郭式平山城
千葉 輔胤が室町中期文明に千葉市にある亥鼻城から
移転する。以後戦国時代9代に千葉氏宗家の本拠地
となる。豊臣秀吉に滅ぼすまで100年9代の居城となる
|
江戸時代
千葉氏は小田原征伐後改易となり徳川家に接収され
松平忠輝が5万石→小笠原氏→土井氏へ1615年藩庁
を佐倉城に移転して廃城となる。 |
城の構造
城域は内郭と外郭に分かれており、内郭は南方に谷が
刻まれた半島状の丘陵、往時は三方湿地帯に囲まれた
要害である。 上図は大堀切で左側が城山で右は奥ノ山
|
| 本佐倉城 続日本100名城(121番) |
本佐倉城 |
本佐倉城 |

|
 |
|
|
本佐倉城(千葉)
図のように区分けされている、まったく石垣や水堀は
なく、千葉県内でも最大級の規模となる城跡である
|
画像は 奥ノ山
現在でも城の土塁や空堀などの遺構がほぼ完全な姿で
遺存しておる。妙見宮跡がある |
東山虎口の曲輪より筑波山望み、印旛沼が京成線
の所まであり、本佐倉駅付近は湿地帯であった。
京成電車が走っている |
|
| |
| 久留里城 |
久留里城 |
久留里城 |
|
|
|
|
| 久留里城(千葉県君津市) 連郭式山城
室町時代に上総武田氏の武田信長が築城
戦国時代は里見氏、江戸時代には久留里藩として
藩庁となる。現代の模擬天守は日本で
一番小さな天守1979年のRCにて建造される
|
久留里藩歴代藩主
大須賀(松平)家1代 3万石・土屋家3代 2万石
黒田家9代 3万石 幕末
|
現在の天守からの見る景色
|
|
| 舘山城 |
舘山城 |
千葉城 |
|
|
|
|
|
舘山城(千葉)2013.8撮影 連郭式山城
1580年 里見義頼が築城
1614年舘山藩改易で廃城
別名:根古屋城
|
舘山藩歴代藩主
里見家 3代 12万石 改易
その後しばらく天領となり
1785年より稲葉家 5代 1.3万石 幕末
|
千葉城(亥鼻城)(千葉)2015.9撮影
連郭式山城で中世は千葉氏の館があったが
江戸時代には天領地で藩ない
|
|
| (神奈川県・静岡県の城) |
2020年度お城巡り画像集
今年2月より世界的にコロナウィルスが流行となり、日本も3月~5月まで季節良い時期に不要不急の外出自粛要請に入り、今年のお城巡り計画が白紙となりました。
関東地区の日本100名城の北条氏の本城・支城を巡りしております |
| 小田原城 日本100名城(23番) |
小田原城 |
小田原城 |
|
|
|
|
|
小田原城 銅門
2020年3月25日 馬出門を入り馬屋曲輪通り銅門
天守は1960年のRC造復興 平成28年耐震改造
平成9年銅門復元 21年馬出門を復元
日本100名城(23番)
|
小田原城 隅櫓
戦国時代は北条氏の居城で3代氏康が難攻不落となる
豊臣軍対抗するために作られた広大な外郭9km
北条氏は5代で終わる。
江戸期の藩主
大久保家2代 6.5万石 阿部家1代 稲葉家3代10万石
大久保家10代 11万石
|
小田原城 常盤木門
桜の名所と菖蒲とアジサイが綺麗で有名
|
|
| 小田原城 |
小田原城 |
小田原城 |
|
|
|
|
|
小田原城 天守閣
耐震対策 外観 綺麗に修復
|
小田原城 天守閣より常盤木門
以前は象がいました
|
小田原城 天守より小田原駅方面
と丹沢山系
|
|
2022年 7月20日 3度目の登城
| 石垣山城一夜城 続日本100名城(126番) |
石垣山一夜城 |
石垣山一夜城 |
|
|
|
|
|
豊臣秀吉が天正18年(1590年)の小田原征伐の際に
小田原城の西3kmにある笠懸山の山頂に構築した。
小田原城を攻略するために小田原城を見下ろす山上に
城を80日で構築された
|
入口 南曲輪の石垣
この城の縄張りは黒田官兵衛であったと推測される
石垣のほとんどは関東大震災で崩落した
|
二ノ丸【馬屋曲輪】
小田原北条氏に対して豊臣秀吉はは海陸から16万
以上で取り囲み、一夜城は完成後一挙に小田原城
から見える方面の樹木を伐採して心理的に恐怖を
|
|
| 石垣山一夜城 |
石垣山一夜城 |
石垣山一夜城 |
|
|
|
|
本丸跡
一夜城完成後北条氏直は10日後に降伏した
|
本丸から望む小田原城
一夜城の出来事
①伊達政宗が参戦に遅れ豊臣秀吉に惨殺される恐れあった
②徳川家康に関東への移封を言い渡す。 |
天守台
天守の建物があっか不明
|
|
2020年11月17日 箱根紅葉と野鳥撮影をかねて、山中城跡へ
| 山中城跡 日本100名城 40番 |
山中城跡 |
山中城跡 |
|
|
|
|
|
山中城跡 2020年11月17日撮影
中山城は三島市より国道1号線を箱根方向へ登ると
左右に城跡があります。西側は近年整備されて本丸跡
がある位置で、東側は豊臣軍が攻めてくるので急遽
岱崎出丸と畝堀を作るが未完成で落城
|
山中城跡 御馬場曲輪
中山城は戦国時代の永禄年間(1560)小田原 北条氏康
が築城北条氏の本拠地である小田原の西の防衛を担う
最重要拠点 城主は松田康長 1590年豊臣軍4万人が攻めて
4000人守るが半日で落城する
|
山中子城跡 一ノ堀
岱崎出丸と畝堀
1国道1号線を挟んで西側にある三ノ丸は現在
宗閑寺となっており、城主:松田康長や北条軍の墓
と豊臣軍の武将 一柳直末の墓もある
|
|
|
|
|
|
|
山中城跡 二の丸 広場
現在は芝の広場となっている。尾根を区切る曲輪の
造成法、架け橋や土塁の配置など箱根山の自然の地形
を巧みに取り入れた山城である。
石垣は全くなく土手だけの曲輪である
|
山中城跡 二の丸から本丸へ
本丸へは土橋を渡って行くが敵が攻めって橋を破棄すると
北側には堀止め斜面にはV字状の薬研堀、
南側は箱堀となっている
|
中山城跡 本丸から北の丸へ
北橋を渡って北の丸へ、深い堀があり
|
|
|
|
|
|
|
中山城跡 西ノ丸 広場
西ノ丸から本丸方面を望む
|
山中城跡 西ノ丸の下にある障子堀
西ノ丸の周りにはこのような障子堀があります。
|
中山城跡 西ノ丸 見晴台より西櫓
西ノ丸・櫓台をぐるりと帯曲輪
|
|
| 小机城跡 続日本100名城(125番) |
小机城跡 |
小机城跡 |
|
|
|
|
|
小机城跡 本丸 広場前の表杭
2021年1月21日初めて登城する。
横浜線小机駅下車徒歩15分にある小高い丘
第三京浜高速が小机城を分断している
|
小机城跡 本丸入口の土塁空堀
永享の乱(1438年)の頃に関東管領上杉氏によって築城
であるが不明である。長尾景春の乱のうち1478年に起きた
攻守戦である。敵方の太田道灌が攻撃をした。
|
小机城跡 二ノ丸広場
その後は廃城となったが、後北条氏の北条氏綱の
手により修復され、家臣の笠原信為が城主となる
|
|
|
|
|
|
|
小机城跡 配置図看板
1590年の豊臣秀吉による小田原征伐の
際には、無傷のまま落城した。その後、徳川家康の
関東入府のときに廃城とされた。
|
小机城跡 本丸から二の丸へ行く空堀
小机城跡には石垣は無く土塁による。
小机城址市民の森として整備されている
|
小机城跡 空堀と曲輪跡
主要な二つの郭のうちどちらが主郭で
あったかは不明である。横浜市に11つだけの城
近くには新横浜サッカー場と遊水地があり
|
|
| (東京都の城) |
| 2020年10月28日 八王子城跡に行く、近くていつでも行けると思っていましたが、野鳥とお城跡とハイキングへ |
| 八王子城 日本100名城(22番) |
八王子城 |
八王子城 |
|
|
|
|
|
八王子城跡 碑
八王子城は北条氏の本城である小田原城の支城であり、
関東の西に位置する軍事上の拠点であった。
標高445 mの深沢山(現在の城山)に築城された
中世山城である。
|
八王子城跡 大手門跡 付近
北条氏康の三男・氏照が1571年頃より
築城し、1587年(天正15年)頃に本拠とした。
野鳥はカケス・ジョウビタキ・シジュウガラ・・・
|
八王子城跡 曳橋(推定復元)と
御主殿石垣(一部復元)
御主殿跡は氏照の館があった場所で落城当時の
ままの状態で保存されていた。礎石や遺物が出土した。
|
|
|
|
|
|
|
八王子城跡の石垣
先方の石垣は当時のままである
|
八王子城跡 御主殿跡へ通じる
虎口と冠木門 |
八王子城跡 御主殿跡
発 掘では大量の遺物が出土している
|
|
|
|
|

|
|
八王子城跡 御主殿跡から望む曳橋
小田原征伐の一環として1590年7月24日、
八王子城は天下統一を進める豊臣秀吉の軍勢に
加わった上杉景勝、前田利家、真田昌幸ら
の部隊1万5千人に攻められた。
|
八王子城跡 本丸への登り口
本丸へは急な登り坂で40分かかる
当時、城主の氏照以下家臣は小田原本城に駆けつけており、
八王子城内には城代の横地監物吉信、家臣の狩野主善一庵、
中山勘解由家範、近藤出羽守綱秀らわずかの将兵の他、
領内から動員した農民と婦女子を主とする領民を加えた
約3000人が立て籠った。
|
八王子城跡 途中の金子曲輪
今回は5合目で断念
|
|
2024年4月19日 お台場へ
| 品川御台場 (続日本100名城(124番) |
第三台場 |
第三台場 |
|
|

|
|
|
第三台場
品川台場は、幕末・嘉永6年(1853)のアメリカ国
ペリー来航に伴い幕府が江戸湾の海防強化として
海の中に石垣を築き砲台を配置する
|
第三台場の入口
現在は第三台場だけ陸続きで散策できて整備されて
います、当時は7つの台場があったが、現在は第6台場
と第三台場だけで他は埋め立てられた
|
第三台場の内側平坦な窪地
周りは石垣と土で高くして中央部は陣屋跡と火薬庫
食事造るかまど跡がある
|
|
| 品川御台場 (続日本100名城(124番) |
第三台場 |
第六台場 |
|
|
|

|
|
第三台場の砲台跡
それぞれの御台場何基砲台を配置したか不明
第三台場の総面積8526坪
|
火薬庫 跡
周辺に土堤をめぐらした木造亙葺の建物で園内に
火災や被弾の危険に備え数カ所に分散
|
第六台場
現在は第六台場が現存しているが海に囲まれて
登島出来ない「
|
|
| 滝山城 (続日本100名城(123番) |
本丸の霞神社 |
本丸 広場 |
|
|
|
|
|
永禄12年(1569年)、小田原攻撃に向かう武田信玄
軍約2万人が滝山城の北側の拝島に陣を別働隊の
小山田信茂隊1千が未整備の間道(甲州街道の前身)を
通り小仏峠から進入、
|
滝山城三の丸まで攻め込まれ落城寸前にまで追い込まれたが、
2千の寡兵で凌いだ。しかしこの戦いは、滝山城の防御体制が
不十分であることを痛感させ、
|
八王子城を築城し移転するきっかけとなったともいわれて
いるが、真相は謎である。遺構として本丸・中の丸・空堀・
・空堀・竪堀・虎口・曲輪・土橋・土塁・竪堀、曲輪など
|
|
| 滝山城 (続日本100名城(123番) |
引橋の上 |
曳橋と大堀切 引橋の下 |
|
|
|
|
|
本丸の井戸
多摩川と秋川の合流点にある加住丘陵の複雑な地形を
巧みに利用した天然の要塞で、関東随一の規模を
誇ったという。
|
1521年山内上杉氏の重臣で、武蔵国の守護代大石定重、
定久が築城、その後小田原 北条氏康の三男氏照が大石
の養子となる
|
本丸と中の丸をつなぐ橋で中の丸が攻められるとき
ひき橋を破壊して本丸への攻撃を防ぐ
|
|
| 滝山城 (続日本100名城(123番) |
本丸 霞神社裏側より昭島市市と多摩川 |
本丸方面へ |
|
|
|
|
|
中の丸
中の丸は政庁の館があった所で、現在の建物は以前
国民宿舎があって宿泊出来たそうで、休み所でトイレ
あり、今日は子供の日で甲冑イベント
|
本丸の裏から昭島市市外と多摩川を見る
この方面からは崖が急で攻められない |
今回は登城する道を間違いで三の丸、千畳敷の
道を通らずに家臣屋敷跡を見て二の丸、中ノ丸へ
再チャレンジする予定です
|
|
| |
| |
|
|