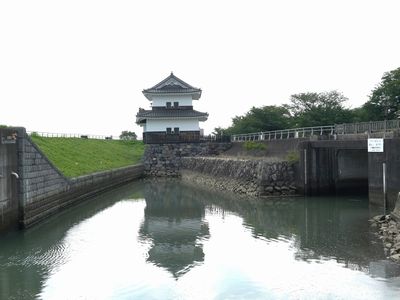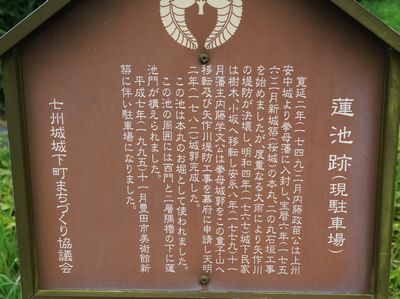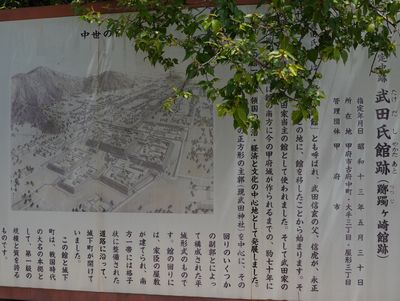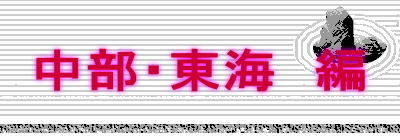| |
| 2023年7月11日~14日愛知・三重・静岡のお城巡りへ行きました |
| 二俣城跡 2023.7.14 |
二俣城跡 2023.7.14 |
二俣城跡 |
|
|
|
 |
本丸跡
静岡県浜松市天竜区二俣町二俣)にあった日本の城。
山城。天竜川と二俣川に挟まれた天嶮に恵まれた
中世城郭として名高く、武田信玄・勝頼親子と徳川家康
がこの城を巡って激しい攻防を繰り広げた。 |
天守台の石垣
二俣城といえば、家康の長男・松平信康が若くして父に
切腹させられた悲劇の地としても知られる。このとき
服部半蔵が介錯を務めたが、涙のあまり刀が振り下ろせ
なかったとの話が残る
|
天守台より本丸
天正18年(1590年)、家康の関東転出に伴い堀尾吉晴が
浜松城に入り、二俣城はその支城となったが、
慶長5年(1600年)に堀尾氏が出雲に転封すると
廃城となった。 |
|
| 鳥羽城跡 2023.7.13 |
鳥羽城跡 2023.7.13 |
鳥羽城跡 |
|
|
|
 |
三の丸より本丸方面望む
三重県鳥羽市鳥羽三丁目)にあった日本の城。
鳥羽藩の藩庁が置かれた。水軍の城で、大手門が
海側へ突出して築かれたため、鳥羽の浮城
|
上から三の丸を見る
文禄3年(1594年)当時、豊臣秀吉の家臣であった
九鬼嘉隆がその跡地に築城した。鳥羽城は、大手水門を
海岸側に向け、周囲を海で囲まれた
|
本丸より海方面望む
九鬼家5.6万石 外様2代、内藤家3.5万石 譜代3代
土井家7万石 譜代1代、松平(大給)家6万石 譜代1代
板倉家5万石 譜代1代、松平(戸田)家7万石 譜代1代
稲垣家3万石 譜代8代
|
|
| 鳥羽城跡 2023.7.13 |
鳥羽城跡 2023.7.13 |
鳥羽城跡 |
|
|
|
 |
本丸方面の石垣跡
左側は崖で三の丸・二の丸は下に配置 |
表門左側石垣と蓮花
|
本丸広場と天守台
|
|
| 田丸城跡 続日本100名城(154番) |
田丸城跡 2023.7.13 |
田丸城跡 |
|
|
|
 |
田丸城表門跡(玉城町立玉城中学校)
中世から近世をとおして現在の三重県度会郡玉城町
田丸字城郭にあった日本の城
南北朝時代に南朝方の拠点として北畠親房、
北畠顕信によって築かれたといわれる平山城
|
表門左側石垣と蓮花
上は玉城町立玉城中学校があり右車道を100m進むと
上に登ると富士見門があり駐車場あり
|
表門の入口
田丸城城主
天正12年(1584年)、小牧・長久手の戦いののち、
松ヶ島城主となった蒲生氏郷の支配下に入る。
江戸初期田丸藩として稲葉家2代
久野家:紀伊和歌山藩の御附家老として
1万石で田丸藩主となり8代続く
|
|
| 田丸城跡 続日本100名城(154番) |
田丸城跡 2023.7.13 |
田丸城跡 |
|
|
 |
 |
田丸城の本丸石垣
田丸城跡は建物は復元されないが石垣は見事 |
本丸方面の石垣
天守本丸の西側は急な崖で田園と山並み綺麗 |
御殿門
|
|
| 田丸城跡 続日本100名城(154番) |
田丸城跡 2023.7.13 |
田丸城跡 |

|
|
 |
田丸城天守台の石垣
天守台の石垣と本丸広場、綺麗に整備されている |
天守台の下からの石垣
石垣は見事である
|
富士見門(移転)
|
|
| 松阪城跡 日本100名城(48番) |
松阪城跡 2023.7.12 |
松阪城跡 |
|
|
|
 |
松阪城表門跡
松阪市の中心地の北部に位置する。阪内川が城北を
流れ天然の堀となっている。
伊勢国司・北畠家の武将・潮田長助が四五百森城を
当地に築城していた
|
表門入り口左側石垣
1584年(天正12年) - 近江国日野城6万石の蒲生氏郷が
伊勢国12万3千石を与えられ飯高郡松ヶ島城に入城した
1588年(天正16年) - 氏郷は、松ヶ島は伊勢湾に面し
城下町の発展性がないと考え、現在の城地に新たに
築城を開始する
|
表門の入口
1600年(慶長5年) - 関ヶ原の戦いの軍功により
徳川家康より2万石を加増された。
1619年(元和5年) - 古田氏は石見国浜田城に転封と
なり、南伊勢は紀州藩の藩領となった。
|
|
| 松阪城跡 日本100名城(48番) |
松阪城跡 2023.7.12 |
松阪城跡 |
|
|
|
 |
中御門跡
1644年(正保元年)に天守が台風のため倒壊した
とされ、以後は天守台のみが残ることとなった。 |
右太鼓櫓跡
1794年には二の丸に紀州藩陣屋が建てられた。
以後、紀州藩領として明治維新を迎えた。 |
本丸広場と奥天守台
安土城の築城に加わった蒲生氏郷だが、松坂城にも
この時の石垣作りが取り入れられている。 |
|
| 松阪城跡 日本100名城(48番) |
松阪城跡 2023.7.12 |
松阪城跡 |
|
|
|
 |
中御門跡
蒲生氏郷は自分の出身地でもある穴太衆を中心に
地元の農民をかり出し石垣をくみ上げていった。
|
徳川陣屋跡より御城番屋敷
紀州藩家老田辺安藤家に紀州藩主徳川頼宣から遣わされて
いた与力衆の200-300石取り紀州藩士が、安藤家の陪臣と
なるよう命じられたことに抗議して、幕末の1856年
(安政3年) 与力衆20人が脱藩して浪人となった
|
御城番屋敷
脱藩から6年後、紀州藩主の直臣40石取りとして帰参を
許され、松坂御城番職に就いた。
1863年(文久3年)松坂城南東の三の丸に藩士とその
家族の 住居として新築されたのがこの組屋敷である。 |
|
| 津城跡 続日本100名城(152番) |
津城跡 2023.7.12 |
津城跡 |
|
|
|
 |
津城跡
津城は三重県津市丸之内にあり、市街の中心部に位置
北は安濃川、南は岩田川に挟まれ、これらを天然の
大外堀としていた。(1558年 - 1569年)に、
長野氏の一族の細野藤光が安濃・岩田の両河川の
三角州に小規模な安濃津城を構えたことに始まる
|
藤堂高虎像
1568年)織田信長の伊勢侵攻により織田掃部頭
(津田一安)が入城。翌年には織田信包が入城した。
1608年)伊予今治藩より藤堂高虎が伊勢・伊賀22万石
をもって入城し 虎は城の大改修に着手し輪郭式の
城郭変貌させ、城下町を整備した。以後、明治維新まで
藤堂氏の 居城となった。
|
本丸広場
元和3年(1617年)に5万石ずつの加増を受け、藤堂氏は
32万3,000石の大大名となった。
天守は関ヶ原の戦いで焼失し再建されなかったとされる。
津は江戸期を通じて伊勢神宮参拝の宿場町として栄え
「伊勢は津でもつ津は伊勢でもつ、尾張名古屋は
城でもつ」 と伊勢音頭に謡われた。 |
|
| 津城跡 続日本100名城(152番) |
津城跡 2023.7.12 |
津城跡 |
|
|
|
 |
| 丑寅櫓 |
北側の内堀と石垣 |
門 |
|
| 亀山城跡 2023.7.12 |
亀山城跡 |
亀山城跡 |
|
|
|
 |
亀山城多門櫓石垣
文永2年(1265年)に関実忠によって若山(現在の
三重県亀山市若山町)に築城され、その後現在の
位置に移された。永禄10年(1567年)の織田信長
の伊勢進攻以降は、たびたび戦場となった。 |
多聞櫓石垣
伊勢亀山藩歴代藩主
関家3万石(外様)1代 、松平(奥平)家5万石(譜代)1代
三宅家1万石→2万石(譜代)2代、板倉家5万石(譜代)5代
石川家6万石(譜代)11代
|
天守台および本丸
現在神社となっている
|
|
| 神戸城跡 2023.7.12 |
神戸城跡 |
神戸城跡 |

|
|
 |
神戸城跡
三重県鈴鹿市神戸本多町にあった日本の城である。
神戸氏4代の神戸具盛が天文年(1532年 - 1555年)
に築城、城跡は公園として整備され、本丸の石垣
および 堀の一部が残る。 |
天守台(野ずら積み)と碑
神戸藩歴代藩主
一柳家外様 5万石1代 、石川家譜代 2万石3代 、
本多家譜代 1.5万石7代
|
天守台より本丸広場
かつては神戸信孝により5重6階の天守が築かれ、北東に
小天守と南西に付櫓がある複合連結式の天守で
あったことが確認されている。
|
|
| 桑名城跡 2023.7.12 |
桑名城跡 |
桑名城跡 |
|
|
|
 |
桑名城跡(九華公園)
三重県桑名市にあった日本の城である
桑名市街の東端に位置し揖斐川に臨む水城である。
1513年に伊藤武左衛門が城館を築いた
|
辰巳櫓跡にある大砲
城の北辺には東海道桑名宿「七里の渡し」があり、交通の
要衝となっていた。城跡には現存建造物はなく、石垣、堀が
残るのみ、天守台は神社内にひっそりとあります。 |
蟠龍櫓(外観復元) - 「ばんりゅうやぐら」
安藤広重の有名な浮世絵『東海道五十三次』
でも、海上の名城と謳われた桑名を表すために
この櫓を 象徴的に描いています。 |
|
| 桑名城跡 2023.7.12 |
桑名城跡 |
桑名城跡 |
|
|
|
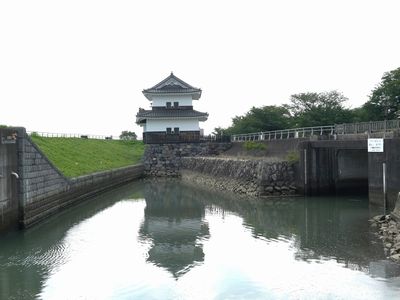 |
七里の渡し跡
桑名藩歴代城主
本多家2代(10万石)、松平(久松)家5代(11万石、
松平(奥平)家7代(10万石)
松平(久松)家5代(11万石)
幕末には松平容保の実弟である松平定敬が藩主 |
七里の渡し跡の碑
東海道五十三次で知られる宮宿(名古屋市熱田区)から
桑名宿(桑名市)までの海路で、七里の渡しの名称は、
移動距離が7里であったことに由来する。渡し船によって
移動し、所要時間は約4時間であった。
|
七里の渡し跡
4重6階(4重4階の説もあり)の天守は約30年かけて
寛永12年に松平定綱の代に完成した。
元禄14年に焼失したが、復興されなかった。
天守台の場所は現在の神社付近
|
|
| 小牧山城跡続日本100名城(149番) |
小牧山城跡 2023.7.11撮影 |
西尾城跡 |
|
|
|
 |
小牧山城
織田信長が美濃攻めの拠点として築城し、後の
小牧・長久手の戦いでは、徳川家康の陣城となった。
近年の発掘調査の結果で、城郭を取り巻く三重の石垣
(三段の石垣で一番下の段は腰巻石垣)が発見された。
|
小牧市歴史館(小牧城)
小牧・長久手の戦い
織田・徳川連合軍と豊臣秀吉の小牧山で戦い
秀吉軍10万人が小牧山を取り囲み織田・徳川軍3万人
で小牧山に対陣状態その後、両軍は長久手の戦いで
徳川軍が勝利する |
小牧山山頂より犬山方面
16:30から山頂へ行くが歴史館は閉館していた。
急な階段を上り、標高86mより高速道路方面
|
|
| 七州城跡 2023.7.11撮影 |
七州城跡 |
七州城跡 |
|
|
|
 |
隅櫓 平成24年4月に建築
七州城(しちしゅうじょう)は、豊田市小坂本町
正式には「挙母城」(ころもじょう)という
鎌倉時代の1309年に中條景長によって
金谷城が 築かれた
|
蓮池跡
七州とは寛延2年(1749年)、内藤氏が城の改修、桜城から
高さ65メートルほどの丘である童子山に移し、「三河国」
「尾張国」「美濃国」「信濃国」「伊賀国」「伊勢国」
「近江国」の 7つの国が見える高台にあることから、
「七州城」といった
|
蓮池跡(駐車場)
挙母藩歴代藩主
三宅家4代 、本多家3代 、内藤家7代 2万石
現在豊田市美術館敷地内に櫓台の石垣が残り
隅櫓を再建する
|
|
| 西尾城跡 2023.7.11撮影 |
西尾城跡 |
西尾城跡 |
|
|
|
 |
鍮石門(ちゅうじゃくもん)
西尾城は、愛知県西尾市錦城町にあった日本の城
別名は「鶴城、鶴ヶ城」
三河国守護に任じられた足利義氏が築城した
西条城が 始まりと伝わる。
|
本丸丑寅櫓(うしとら)
天正13年)に酒井重忠によって、東の丸と帯曲輪の拡張と
堀や石塁の造成、櫓門、櫓類、天守などが増築された。
天正18年)田中吉政によって、三の丸の拡張や大手黒門、
新門の楼門2棟、櫓門2棟が建てられている。
|
丑寅櫓と内堀
西尾藩 歴代藩主:本多(膳所)家、
松平(府内大給)家、 太田家、井伊(与板)家、
増山家2代、土井(刈谷)家4代
三浦家2代、松平(西尾大給)家5代 6万石 |
|
| 西尾城跡 |
西尾城跡 |
西尾城跡 |
|
|
|
 |
二の丸広場
西尾城の特色は、天守が本丸ではなく二の丸にあり、
城下に士農工商が混在していたこと、
「総構え(そうがまえ)」といって城下町の周囲を堀と
土塁で囲んだことです。 |
天守台の石垣と土塀
丑寅櫓から天守台につづく土塀は約52m、高さは約2m。
木造で控え柱である構造で、2ヶ所の折れを持つ
「屏風折れ」と なっています。
現在の施設は西尾市資料館と旧近衛邸
|
二之丸丑寅櫓
二之丸丑寅櫓は天守があったとされる二之丸の
北東隅(丑寅の方角)、鍮石門の北に位置する櫓で、
江戸の初期に建てられたと推定されます。
|
|
2022年11月8日~10日岐阜県の山城巡りと紅葉及び愛知県長篠城へ3回目に行って来ました。
苗木城と岩村城へ |
| 苗木城跡続日本100名城(142番) |
苗木城跡 |
苗木城跡 |
|
|
|
 |
苗木城跡の碑
岐阜県中津川市にあった日本の城。
別名は霞ケ城。鎌倉時代初期に岩村城を
本拠地とした遠山氏が恵那郡を統治
天文年(1532年~)に遠山正廉が苗木城を築く
武田氏、織田氏、森氏の苗木城攻めて遠山氏は
徳川家康を頼り浜松に走る |
駐車場から歩いて5分 天守台を望む
木曽川から山頂の天守跡までは、標高差約170メートル。
急峻な地形を生かして築かれた山城です。
天守跡に展望台が設けられ、恵那山や木曽川を
はじめ中津川市街を360度見渡すことができ、
美しい景色が見ものです。
|
石畳みを歩くと風吹門(大手門)
苗木城の石垣には、なんと自然の巨岩がそのまま
活用されています。苗木城の特徴は、大人の背丈を
優に超える巨石や断崖など自然の地形を
最大限に生かした城壁
|
|
| 苗木城跡 続日本100名城(142番) |
苗木城跡 |
苗木城跡 |
|
|
|
 |
大矢倉
「岐阜のマチュピチュ」と呼ばれる所以となった
「大矢倉」は、かつて3階建ての櫓があった
土台部分が残っています。 |
本丸下の石垣
高さ7m以上ある石垣で素晴らしい加工で苗木城は
門跡と石垣が多く保存されている。天然の巨岩を利用
して頑固な城郭を築いている |
本丸からみる大矢倉
1600年(慶長5年)頃に遠山友政によって築かれた
天守、関ヶ原合戦で東軍に属して、苗木藩として
1万500石と幕末まで遠山氏12代続く |
|
| 苗木城跡続日本100名城(142番) |
苗木城跡 |
苗木城跡 |
|
|
|
 |
天守台と石垣
天守閣は2重3階で巨岩の上に建てられていた
360度の展望である。1万石の領地大名としては
このような規模の大きい城壁を持つのは異例
|
天守台より望む木曽川と恵那山
苗木城は人気で多くの人達が登城している。
駐車場は上には20台程度可能
下に歴史資料館があり、駐車場もあります
|
天守台
日本続100名城142番
|
|
| 岩村城跡日本100名城(38番) |
岩村城跡 |
岩村城跡 |
|
|
|
 |
太鼓櫓、表御門、平重門 藩主邸
岐阜県恵那市岩村町にある中世の日本の城
(山城跡)で、「霧ヶ城」とも呼ばれる。
奈良県の高取城、岡山県の備中松山城と並び、
日本三大山城の一つとされる。 |
大手一ノ門
鎌倉幕府の御家人加藤景廉の長男遠山景朝が築き、
その子孫の岩村遠山氏が戦国時代まで城主であった
戦国時代に遠山氏最後の城主は遠山景任病没すると
信長は5男で幼少の坊丸(織田勝長)を遠山氏の養子
|
土岐門
となって後見は信長の叔母にあたる女性
(通称はおつやの方など)で幼少の養子に代わって
女城主として差配を振るった。岩村城は武田方に敗れ、
おつやの方は秋山虎繁と婚姻するという条件で降伏 |
|
| 岩村城跡日本100名城(38番) |
岩村城跡 |
岩村城跡 |
|
|
|
 |
畳橋付近の追手門
1575年(天正3年)武田勢が弱体化した期に乗じ
信長は岩村城奪還を行った。 |
追手門跡
土岐門に続く第三の門が追手門で、前面の空堀には
畳橋と呼ばれる木橋がかかっていまし た。 |
六段壁
本丸の北東面には雛壇に築かれた六段の
見事な石垣が残されています。 |
|
| 岩村城跡日本100名城(38番) |
岩村城跡 |
岩村城跡 |
 |
|
 |
六段壁
戦国時代のおんな城主で有名 おやつ と言う
織田信長の伯母上(歳は若い)で武田方の武将
秋山虎繁が岩村城を攻め落としておやつうは
苦渋の末、城兵・領民を守る為に虎繁の妻となる
その後、武田氏の勢力が衰え信長は夫婦を処刑
|
長局埋門
二の丸から本丸へ入る門。位置的には本丸北口で有り、
裏門にあたります。
|
本丸より長局埋門
江戸時代初期、家康は徳川秀忠に将軍職を譲り、
駿府に隠居した。1610年(慶長15年)完成した。
天守台は、石垣上端で約55m×48mという城郭
史上最大級の規模であった。
|
|
| 岩村城跡日本100名城(38番) |
岩村城跡 |
岩村城跡 |
|
|
 |
 |
南曲輪
高さ7mあり、出丸と本丸にある石垣
|
出丸 現在は駐車場
本丸と六段崖等の石垣見るだけでは楽な駐車場
本丸の海抜717mで資料館口から登城すると800m
約150m登る、約45分で本丸まで |
本丸跡
江戸時代の岩村藩主と石高
1.大給松平家(宗家) 2代 2万石 譜代
2.丹羽家 5代 2万石 譜代
3.大給松平家(分家) 7代 3万石譜代 |
|
| 長篠城跡日本100名城(46番) |
長篠城跡 |
長篠城跡 |
|
|
|
 |
長篠城跡碑
豊川と宇連川が合流する場所に突き出した
断崖絶壁の上にあり、1508年奥三河の土豪である
菅沼元成が築城した菅沼氏は今川氏の部将で5代
武田信玄に屈する
|
内堀
信玄死後、1575年6月武田勝頼が15000の兵を率いて
奥平信昌が約五百の手勢で守る長篠城を攻め囲み、
長篠の戦いが始まる。
奥平信昌は長篠の戦い後、新城に新たな城を築き
長篠城は廃城となる |
長篠城址史跡保存館
長篠の戦い
長篠城の守備隊は500人の寡兵であった200丁の
鉄砲や大鉄砲を有しており、地形のおかげで
武田軍の猛攻に何とか持ちこたえていた。
|
|
| 長篠城跡日本100名城(46番) |
長篠城跡 |
長篠城跡 |
|
|
|
 |
本丸跡
兵糧蔵の焼失により食糧を失い落城必至の状況
城側は貞昌の家臣である鳥居強右衛門(すねえもん)
を密使として放ち、約65km離れた岡崎城の家康へ
緊急事態を訴えて、援軍を要請させることにした。
|
本丸・野牛曲輪跡
岡崎城では、既に信長の率いる援軍3万人が、家康の
手勢8000人とともに長篠へ出撃する態勢であった。
この朗報を一刻も早く長篠城に伝えようと
引き返したが、16日の早朝、城の目前まで
来たところで武田軍に見つかり、捕らえられる
豊川と宇連川が合流する中央が長篠城
|
鳥居強右衛門の磔つけの場所
武田勝頼は、鳥居に向かって『援軍は来ない。
あきらめて早く城を明け渡せ』と叫べ。お前の命を
助け、所領も望みのままに与えてやろう」と
取引を持ちかけた。鳥居は、「あと二、三日で、
数万の援軍が到着する。それまで持ちこたえよ」と、
勝頼の命令とは全く逆のことを大声で叫んだ。
鳥居は槍で突き殺ろされた |
|
| 設楽原古戦場 |
設楽原古戦場 |
設楽原古戦場 |
|
|
|
 |
馬防柵
信長軍30,000と家康軍8,000は、5月18日に
長篠城手前の設楽原に着陣。
信長はこの点を利用し、30,000の軍勢を敵から
見えないよう、途切れ途切れに布陣させた
|
馬防柵と徳川陣地
小川・連吾川を堀に見立てて防御陣の構築に努める。
馬防柵を設けるという当時の日本としては異例の
野戦築城だった。火縄銃3000丁で武田の騎馬隊を
撃ち落とすのである
|
馬防柵から見た武田軍側
酒井忠次に率い長篠城包囲の要であった鳶ヶ巣山砦
を4000名の別働隊を組織し、奇襲を命じた
設楽原では、武田軍が織田・徳川軍を攻撃。戦いは
昼過ぎまで続いた(約8時間)武田軍は10,000名
以上と重臣がほとんど犠牲となり敗戦 |
|
2022年7月28日~29日静岡県の100名城・続100名城巡りと神社巡りに猛暑の中行って来ました。
静岡県の名城 興国寺城「続日本100名城145番」だけ残りです |
| 駿府城跡日本100名城(41番) |
駿府城跡 |
駿府城跡 |
|
|
|
 |
駿府城跡碑
4世紀に室町幕府の駿河守護に任じられた今川氏に
この地には今川館が築かれ今川領国支配の中心地。
武田領国化される
|
東御門 高麗門(復元)
天正13年) 駿河国を支配した徳川家康が浜松城より
居城を移して築城開始。
天正18年) 小田原征伐後、江戸に移封となった徳川家康に
代わり、中村一氏が大名として入城
|
巽櫓 東御門(復元)
江戸時代初期、家康は徳川秀忠に将軍職を譲り、
駿府に隠居した。1610年(慶長15年)完成した。
天守台は、石垣上端で約55m×48mという城郭
史上最大級の規模であった。 |
|
| 駿府城跡日本100名城(41番) |
駿府城跡 |
駿府城跡 |
|
|
|
|
坤櫓(ひつじさるやぐら)
1616年(元和2年) 家康、駿府城で死去(75歳)
1624年(寛永元年) 徳川忠長が駿府城主となる
1631年(寛永8年) 忠長が乱心、改易と蟄居 |
鷹狩り姿の徳川家康公之像
駿府は公儀御料(江戸幕府直轄領)となり、駿府城代・
駿府定番が置かれる。
|
二ノ丸水路
1635年(寛永12年) 城下の火災が城に延焼
1707年(宝永4年)宝永地震により駿府城石垣等が大破
1854年(安政元年)安政の大地震によりほぼ全壊する |
|
| 駿府城跡日本100名城(41番) |
駿府城跡 |
駿府城跡 |

|
|
|
紅葉山公園
紅葉山庭園は駿府城公園内に平成13年秋に
完成した日本庭園と茶室です。
|
県庁別館21階展望室より東御門
本丸堀と巽櫓、東御門、奥に紅葉山公園及び中堀
県庁別館21階は誰でも展望室に入ります。無料駐車場
1時間だけOKです
|
県庁別館21階展望室より天守台発掘
2016年(平成28年)8月 天守台発掘調査開始
発掘現場の中にも入れます
|
|
| 諏訪原城跡 続日本100名城(146番) |
諏訪原城跡 |
諏訪原城跡 |
|
|
|
 |
諏訪原城跡碑
諏訪原城(牧野城)は遠江国の東端近くの
牧之原台地の舌 状台地の先端部に立地する。
武田軍が遠江(徳川領)攻略の出城として築城 |
諏訪原城の図
(1575)8月、長篠で敗戦した後、遠江に進攻した
徳川家康の手に落ち、牧野城と改名。
|
二の曲輪中馬出(三月日堀)
武田流築城術の特徴と言われる丸馬出
|
|
| 諏訪原城跡 続日本100名城(146番) |
諏訪原城跡 |
諏訪原城跡 |
|
|
|
 |
外堀
諏訪原城は地形に守られた「後ろ堅固」の城
虎口側は平坦ですが本曲輪東側が断崖で大井川
が流れて自然地形に守られていた |
薬医門(やくいもん)
発掘調査で確認された門の礎石から復元した
平成28年
|
本丸台から大井川を望む
本曲輪から望む島田市街 東側は断崖で
なかなか攻められない地形
|
|
| 高天神城跡 続日本100名城(147番) |
高天神城跡 |
高天神城跡 |
|
|
|
|
北口 搦手門(からめてもん)より登城
山の高さは海抜132m、城郭全体の面積も
なく、山自体が急斜面
|
高天神城図
高天神城には治承・寿永の乱(源平合戦)の際に築城された
との伝承があるが、不明、戦国時代末期には武田信玄
・勝頼と徳川家康が 激しい争奪戦を繰り広げた。
|
高天神城 北側搦手門
勝頼も天正2年(1574年)に高天神城を攻撃、
猛攻を加えて結果二ノ丸が落城した。
|
|
| 高天神城跡 続日本100名城(147番) |
高天神城跡 |
高天神城跡 |
|
|

|

|
本丸広場
天正8年(1580年)9月、徳川軍は満を持して
高天神城を攻撃した(第二次高天神城の戦い)。
天正9年(1581年)3月下旬、岡部以下の将兵が
突撃を敢行し討死して高天神城は陥落した。
|
本丸より北側を望む
落城後、高天神城は廃城となり、城の山頂に 高天神社が
あったために、山自体は地元のシンボル
|
本丸方面
今回の登城は3日前に豪雨で湿気多く登城する
人は誰もいない、北側の階段はかなり急坂
汗流しで山頂へ尾根で左右は直角の崖
|
|
| 横須賀城跡 |
横須賀城跡 |
横須賀城跡 |
|
|
|

|
本丸広場と天守台
大須賀家2代、能見(松平)家2代、井上家2代、
本多家1代、西尾忠成が2万5千石で7代をもって
明治維新まで続く、西尾家は老中になり3.5万石
|
横須賀城の特徴
他に類を見ない、天竜川より運ばれた玉石垣を用いた
築城法である。天守閣は三層四階であったが
宝永地震で隆起
|
横須賀城
綺麗な玉石垣が見ものでよく整備されています。
近くには城下町で古い家並みあり
|
|
| 掛川城 日本100名城(42番) |
掛川城 |
横須賀城跡 |
|
|
|
|
掛川城 別名:懸川城、懸河城、雲霧城、
慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは山内一豊は
居城である掛川城を真先に家康に提供する、
|
2014年11月に登城しております。今回は立ち寄り
今天守の回り工事で大型クレーンにより荷物上げ
良い画像撮れず
|
掛川市 横須賀城跡
横須賀城は武田氏が高天神城攻撃で徳川家康が
大須賀康高に命じて築いた城で、江戸時代も
横須賀藩として、家、田んぼ付近まで海であった
。
|
|
2022年5月19日山梨県の100名城・続100名城巡りと神社仏閣巡りに行きました。
新府城・甲府城・躑躅ヶ崎館・要害山城及び武田神社・甲州善光寺・恵林寺 日帰りにて |
| 甲府城 日本100名城(25番) |
甲府城 |
甲府城 |
|
|
|
|
稲荷曲輪門
稲荷曲輪南西部にあった。薬医門。復元されている。
|
数寄屋櫓跡を望む
階段上がると数寄屋曲輪広場へ
|
甲府城全体図
全体に石垣が美しく良い城でありました。
これで3回登城しましたが、復元門、櫓があり
楽しかった。
|
|
| 甲府城 日本100名城(25番) |
甲府城 |
甲府城 |
|
|
|
|
銅門跡
本丸西側に位置し、鉄門と対だとされる門です。
当時の礎石が残っています
|
本丸広場より天守台
そもそも天守が存在していたのか否かについて、
議論や検証が続いている。
|
稲荷櫓
稲荷曲輪北東にあった。復元されている。古写真が
発見されている。二重櫓二階に千鳥破風別名丑寅櫓。
平成15年に復元された。
|
|
| 甲府城 日本100名城(25番) |
甲府城 |
甲府城 |
|
|
|
|
上がると天守曲輪へ
上側には櫓か門があったような石垣である
|
鉄門
本丸搦手門にあたる。櫓門 平成22年には鉄門の復元が
決定され、2013年度に完成
|
謝恩碑 高さ約35m
この記念碑は明治40年の大水害など度重なる水害に
よって荒廃した山梨県内の山林に対し、明治天皇より
山梨県内の御料地の下賜(かし)が行われたことに
対する感謝と水害の教訓を後世に伝えるために
大正11年)に建設された。
|
|
| 甲府城 日本100名城(25番) |
甲府城 |
甲府城 |
|
|
|
|
甲府城 遊亀橋 別名は舞鶴城、一条小山城
梯郭式平山城 築城主:豊臣秀吉・徳川家康?
1583年~1586年頃 |
天守台と石垣 甲府藩歴代藩主
尾張徳川家→駿河徳川家→甲府徳川家2代→柳沢家2代
1724年より幕府直轄領となり |
坂下門石垣
積み方が違っていることから積んだ時代が違うと
考えられている石垣が並んでいます。 |
|
| 躑躅ヶ崎館 日本100名城(24番) |
躑躅ヶ崎館 |
躑躅ヶ崎館 |
|
|
|
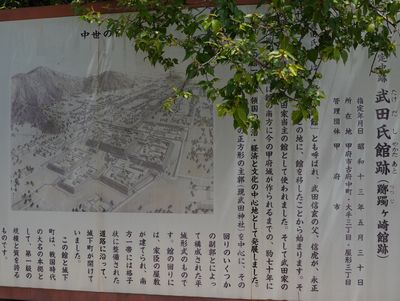 |
躑躅ケ崎舘 別名は武田氏館跡 連郭式平城
築城主:武田信虎 築城年:1519年
甲斐国守護武田氏の本拠である甲府に築かれた館
武田氏3代が60年あまり本拠地として
使用されました。
|
躑躅ケ崎舘 (武田神社)堀に架けられた神橋
武田神社の由来:武田信玄を祭神とする
1915年(大正4年)、大正天皇の即位記念に武田信玄に
従三位が追贈されたのを大正8年)には社殿が竣工し、
信玄の命日にあたる4月12日には初の例祭が行われた。
|
躑躅ケ崎舘の説明掲示板
左図の左右に昔の舘の門石垣があります。
じっさいには戦時のために裏山に詰城である要害山城を
配置して、守りを固める構造になっています。
|
|
|
|
| 要害山城 続日本100名城(128番) |
要害山城 |
要害山城 |

|
|
 |
要害山城 別名は積翠山城
甲府市上積翠寺町(かみせきすいじまち)にあった
日本の城。躑躅ヶ崎館(武田氏館跡)の詰城として
築かれた山城である。 |
要害山城
標高770メートルの丸山と呼ばれる要害山中腹の傾斜地を
中心に築かれている。築城は武田信虎時代の永正17年
(1520年)6月であるという。 |
要害山城への登山口
途中まで登るが引き返す
|
|
| 新府城跡 続日本100名城(127番) |
新府城跡 続日本100名城(127番) |
新府城跡 続日本100名城(127番) |
|
|
|

|
新府城 別名は韮崎城 連郭式平城
甲府盆地西部に位置。釜無川と塩川が侵食して形成
西側は侵食崖で、東に塩川が流れる。 天正3年
(1575年)5月21日の長篠の戦いで敗れた後
|
車道から鳥居階段を登る(緩やかな登城口あり)
築城は天正9年(1581年)から開始され、年末には勝頼が
躑躅ヶ崎館から新府城へ移住している。翌年信濃の木曽義昌
謀反鎮圧で諏訪へ出兵するが、
|
階段を登りと稲荷神社本殿
織田・徳川連合軍に阻まれて帰国、勝頼は3月に家臣の
小山田信茂の岩殿城に移るために、城に火をかける。
岩殿城に向う途中に笹子峠で信茂の謀反にあい、
天目山に追いつ詰められ武田一族は滅亡する。 |
|
| 新府城跡 続日本100名城(127番) |
新府城跡 続日本100名城(127番) |
新府城跡 続日本100名城(127番) |

|
|
 |
新府城本丸後
石垣を使われない平山城で、本曲輪・二の曲輪・
東の三の曲輪・西の三の曲輪・帯曲輪などにより
構成され、丸馬出し・三日月堀・枡形虎口どの
防御施設を持つ。 |
新府城の構成図
築城の時、普請奉行として真田昌幸と言われ、配下の
国衆に人足動員を命じたものとされる
|
新府城本丸跡
本丸跡は平地で整備され、トイレも完備、野鳥も多く
飛び回っております、コゲラ・キビタキ・オオルリ
・ガビチョ ゆっくり野鳥撮影したいと思います。
|
|
| 新府城跡 続日本100名城(127番) |
新府城跡 続日本100名城(127番) |
新府城跡 続日本100名城(127番) |
 |
|
 |
東大手門の馬出し跡
大手馬だしは城門の前に築いて敵から人馬が見えない
土手のことで、馬出しは甲州流築城法の特徴である
二の丸等はまだ整備されず |
東出構と西出構の堀の跡
画像の盛り土が西出構で手前に東出構がある
奥に乾門があります。
|
乾門 枡形虎口
発掘で門跡の柱穴が発見して現在は鉄蓋されている
右側は七里岩の絶壁で下は釜無川である
|
|
|
| 東海・中部編 2014年11月18日より中部・東海のお城巡りに行きました |
| 大垣城 続日本100名城(144番) |
大垣城 |
大垣城 |
|
|
|
|
大垣城 別名は麋城、巨鹿城 平城
1500年(明応9年)に竹腰尚綱によって造られる
1600年(慶長5年)の関ヶ原の戦いの際には
石田三成らが入城して西軍の根拠地 |
旧柳口門と右に艮櫓あり
大垣藩歴代藩主
石川家 譜代 5万石 ・松平(久松)家 親藩 2万石
阿部家 譜代 5万石 ・松平(久松)家 親藩 6万石
戸田家 譜代 10万石 11代 |
天守台より市街地望む
昭和11年に国宝にしていされたが太平洋戦争
の空襲により天守や艮櫓などが焼失
天守の再建は1959年 |
|
| 墨俣城 |
墨俣城 |
墨俣城 |
|
|
|
|
|
岐阜県大垣市墨俣町墨俣
1566年美濃侵攻にあたって、木下藤吉郎が
短期間で造った一夜城で江戸期にはない
|
墨俣城天守閣より岐阜城を望む
岐阜城を模写して作る
|
天守閣より長良川見て遠くに岐阜城
|
|
| 岐阜城 日本100名城(39番) |
岐阜城 |
岐阜城 |
|
|
|
|
|
岐阜城
(稲葉山)にある山城跡。稲葉山城とも言う
1539年斎藤利政が、稲葉山山頂に城作り
1601年家康は岐阜城の廃城を決め加納城を築城
|
山頂からの岐阜城は撮影困難
天守閣より長良川を望む
1956年再建
|
長良川の河川敷より撮影
2015年10月に再度撮影
|
|
| 犬山城 日本100名城(43番) |
犬山城 |
犬山城 |
 |
|
 |
犬山城 (国宝)
愛知県犬山市にあった城である。 国宝の一つ
別名は白帝城、木曽川沿いの高さ約88メートル
ほどの丘に築かれた平山城である
|
木曽川対岸より夕日の犬山城
犬山藩歴代藩
小笠原家:譜代5万
平岩家 :11万石 (尾張藩家老)
成瀬家 :3万石 (尾張藩家老 |
天守閣より木曽川の堰を見る。
御嶽山も見える |
|
| 清州城 |
清州城 |
清州城 |
 |
 |
 |
愛知県清須市一場にあった城。平城
信長は、この城から桶狭間の戦いに
出陣するなど、約10年間清須を居城とした。
望楼型3重4階 1989年RC造模擬 |
織田信長がたおれて、跡目相続で清洲会議後、
織田信雄が城主となる
1595年)には福島正則の居城
慶長12年(1607年)には家康の九男徳川義直
慶長14年(1609年)名古屋と統合され廃城となる。 |
天守閣の最上階より名古屋城を望む |
|
|
|
| 岩崎城 |
岩崎城 |
岩崎城 |
 |
 |
 |
愛知県日進市岩崎)にあった戦国時代の平山城
天正12年(1584年)に起きた岩崎城の戦いとは、
小牧・長久手の戦いのうち長久手の戦いの緒戦と
なった戦いである。 |
昭和62年(1987年)には、展望塔として五重構造の
天守閣(模擬天守)が築城、「岩崎城址公園」として
整備された |
岩崎城の駐車場と入口 お城好きの友人
|
|
| 吉田城 続日本100名城(151番) |
吉田城 |
吉田城 |
 |
 |
 |
愛知県豊橋市今橋町、豊橋公園内)にあった城
幕藩体制の下で吉田城に三河吉田藩の
藩庁が置かれた別名:吉祥郭、峯野城、歯雑城。
|
三河吉田藩歴代藩主
松平(竹谷)家3万石→松平(深溝)家3万石→
小笠原家4万石→牧野家8万石→
松平(大河内)家7万石 |
吉田城は豊川と朝倉川合流地点に立地。
天守閣はなく画像の鉄櫓が代わりとなる |
|
| 岡崎城 日本100名城(45番)
|
岡崎城ライトアップ
|
大手門(復元) |
|
|
|
 |
| 岡崎城
別名:龍城
連郭式平山城 徳川家康の生地である。
1452年西郷稠頼・頼嗣 築城m 松平氏3代松平信光
が城主西郷頼嗣を破り岡崎松平家が成立、
|
岡崎藩歴代藩主
本多家 4代 5万石、水野家 7代 6万
松平家(松井)1代 5万
本多家 6代 5万石 幕末
|
実際の位置は七間門付近
|
|
2024年5月4度目の登城する
| 岡崎城 日本100名城(45番) |
二の丸より入る持仏堂曲輪へ |
天守閣 |
|
|
|
 |
| 徳川家康の銅像 |
太鼓門跡 |
|
|
| 岡崎城 日本100名城(45番) |
晩年の家康像 |
辰巳櫓台下石垣 |
|
|
 |
 |
1542年(天文11年):城内で竹千代(後の徳川家康)が
生まれる。その後今川家へ人質として過ごす。 |
織田信長により今川家を滅ぼし、岡崎へ戻る。子の信康に
岡崎城を渡し、浜松城に入る |
城内で最も完成度の高い石垣で石材が布積み
「江戸切り」で仕上げてある |
|
| 岡崎城 日本100名城(45番) |
持仏堂曲輪・本丸腰巻石垣 |
家康産湯の井戸 |
|
|
|
 |
| 本丸埋門(うずみもん)北袖石垣 |
|
|
|
|
|
| |
| 掛川城 日本100名城(42番) |
掛川城 |
掛川城 |
 |
 |
 |
掛川城 別名:懸川城、懸河城、雲霧城、
慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは山内一豊は
居城である掛川城を真先に家康に提供する、
|
掛川藩歴代藩主
松平(久松)家1万石→安藤家3万石→
松平(桜井)家4万石→井伊家3.5万石→
小笠原家6万石→太田家5万石 |
豊臣時代に山内一豊の居城で、関ヶ原開戦前に
徳川家康に引き渡して味方した功績で土佐国を
与えられた有名な話である。 |
|
| 小山城 |
小山城 |
小山城 |
 |
 |
 |
静岡県榛原郡吉田町にかつてあった城である。
今川氏を倒した武田氏により、1571年築城された。
1582年(天正10年)、甲州征伐のため駿河・甲斐に
向け出陣した徳川家康の攻撃を受け落城した。
江戸時代は藩と城はない |
土塁と橋を復元
城内部には地元刀工島田義助系の刀剣が多く展示 |
天守閣より富士山を望む |
|
| |
|
|