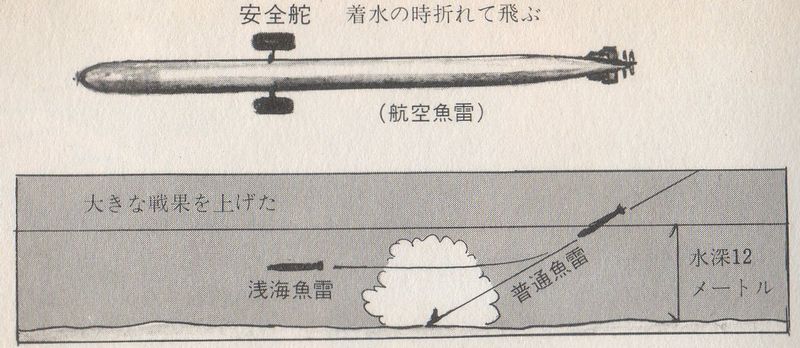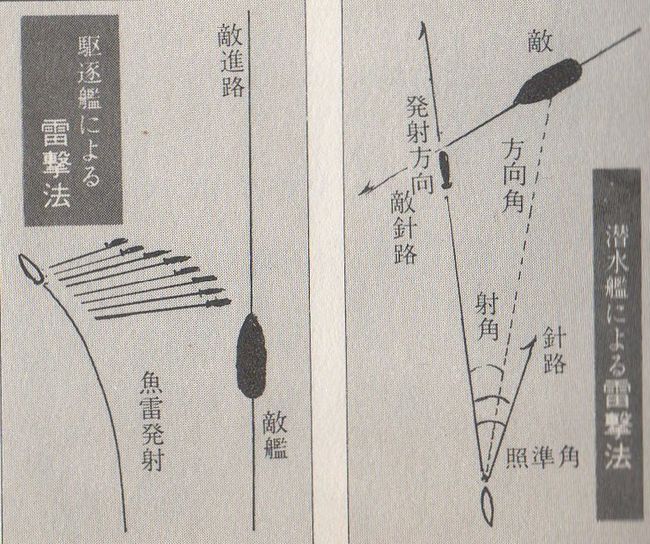�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F��X0�R0�@
����E�����ɂ��������{�鍑�C�R�̎�͊͏�퓬�@�B
���(�g�[����h�Ƃ��j�̗��̂Œm���Ă���B
�C�R�̊͏�퓬�@�Ƃ��Ă͎����I�ɍŏI�^���ŁA�����푈�̔�����
�����m�푈�̏I��܂őO���ʼn^�p���ꂽ�B
���́A��평���ɂ����āA���̒���ȍq��,�����A�d�����D�ꂽ
�i�����\�ɂ��A�A�����̐퓬�@�ɑ����|�I�ȏ��������߂��B
���͓����̘A�����p�C���b�g����u�[���t�@�C�^�[�v�̖��ŋ����ꂽ�B
���̊J�����͎O�H�d�H�Ɓi�u�O�H�v�Ƃ����j�ł���B���Y�́A�O�H�̂�
�Ȃ炸������s�@�ł����C�Z���X���Y����A�����Y����
�����ȏ�͒������ł���B
|
 |
�@�����̓��{�̌R�p�@�́A�̗p�N���̍c�I��2���𖼏̂Ɋ�����K��ɂȂ��Ă����B
�@���́u�뎮�v�Ƃ̖��̂́A�����̗p���ꂽ1940�N�͍c�I2600�N�ɂ�����A���̉�2�����u00�v�ł��邽�߂ł���B
�@�@�J��
�@�@�@�@�@�@���̊J����1937�N�i���a12�N�j9���ɊC�R������ꂽ�u�\�͏�퓬�@�v��v�����v�ɒ[����B
�@�@�@�@�@�@�O�H�ł́A�O��ł����Z���͏�퓬�@�ɑ����Ėx�z��Y�Z�t��v�喱�҂Ƃ��ĊJ���Ɏ��g�B
�@�@�@�@�@�@1939�N4���Ɋ��̗��R�e������s��Ŏ���ꍆ�@������s�A��1940�N7���ɐ����̗p���ꂽ�B
�@�@�v�����\
| �p�r |
�퓬�@ |
|
���Ȑ� |
�@�P |
| ���� |
�͏�퓬�@ |
|
�q���� |
���K���ڎ��S��1���� |
| �v�� |
�x�z��Y |
|
�@�e |
20mm1�`2�B1�̏ꍇ��7.7mm 2��lj�
�e����20mm 1�ɂ�60�A7.7mm 1�ɂ�300 |
| ������ |
�O�H�d�H�� |
|
| �^�p�� |
���{�C�R |
|
�ʐM�� |
�d�M300�\�A�d�b30�\ |
| ����s |
1939�N�i���a14�N�j4�� |
|
���p���x |
3,000m�T��5,000m |
| ���Y���F |
10,430�@ |
|
- |
- |
| �^�p�J�n |
1940�N�i���a15�N�j7�� |
|
- |
- |
�@�@�@�@�P�D���������\�ǍD�Ȃ邱�ƁB���͋��� ��������10m/s�ɂ�����70m�ȓ�
�@�@�@�@�Q�D�������p�̏ꍇ6���Ԉȏ��s�����邱��
�@�@�@�@�R�D���i�\�Ȃ邱��
�@�@�@�@�S�D�v�ɂ��30kg���e2�g�s�����邱��
�@�@����
|
��평���^�ɂ́A20mm�@�e2���i�����j��7.7mm�@�e2���i�@��j�����ڂ���Ă����B
�����͈ꍆ�e�iFF�j��600m/s�A�e�iFFL�j��750m/s�A�g�s�e����
60���h�������e/100����^�h�����e�q
|
 |
�@�@������A�O��13.2mm�@�e��1�`3���i�@��1�A����2�j���ڂ����^���o��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��㎮�ꍆ��Z���@�e(��)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��㎮��Z���@�e(���j
�@�@�h��
�@�R�͓�����̘r���������U�����ő�̖h��Ƃ��ē��ɒ������Ȃ������Ƃ����B
�@���a18�N�j�����Y�J�n�̌ܓ�^������Y�^���痃���^���N�ɒY�_�K�X�ɂ�鎩�����Α��u���A���a19�N�j���Y�J�n��
�@�ܓ^���瑀�c�Ȃ�50mm�h�e�K���X���t���A�X�Ɍܓ^����͍��Ȍ����8mm�h�e�|��lj����A�ꕔ�̋@�̂�
�@���̃^���N�������h�R���ɂ��Ă���B
�@�@�ʐM���u
�@���ɂ͑O��̋�Z���͐퓯�l�ɖ����d�b�E�d�M�@���W����������Ă���A�����͋�Z����ꍆ�����d�b�@
�@�i�Βn�ʐM����100km�A�d�M�d�b���p�j�𓋍ڂ��Ă����B���㔼�͂�荂���\��
�@�O����ꍆ�����d�b�@�i�Βn�ʐM����185km�A�d�M�d�b���p�j�ɕύX���Ă���B
�@�@�퓬�@�Ƃ��Ă̓���
�@�y�ʉ��ɂ�鍂���]��n�͂̂��߁A500km/h����ō����x�ƍ����^�����\�A����ȍq������20mm�@�e
�@2���̑�Η͂��@���������A������̍����Z�ʂ������ď��w�ƂȂ��������푈���瑾���m�푈�̏���ɂ�����
�@���G�Ƃ������銈������������Ƃ���A�@��평���̗D�G�퓬�@�ƌ�����B
�@����E��평���ɂ����āA���q���������Ȃ��ĉ��u�n�܂Ŕ����@�����삵�����N�U���邱�Ƃ��o���������Ȃ�
�@�P���P���퓬�@�@�{���g��˂��ȂǍו��Ɏ���܂œO�ꂵ���y�ʉ���Nj�����
�@�@�@���̒���
�@���đo���ŗ��̊i�����\�̍������]������Ă���B���x�Ώd�u���̋Z�p�҂ɉԖ{���o�i�퓬�@�����j�͎���ŗ�킪
�@�G�𐧂���̂͑��x�����ł͂Ȃ��i�����\���D��Ă��邱�Ƃɂ��Ƒi�����B�q���͂����݂ƂȂ����B����ȍq���͍͂���
�@�����L����p�ʂł̗D�ʂ������炷�B
�@�@���̒Z��
�@���͓O�ꂵ���y�ʉ��ɂ��@�����̌��オ�d�����ĊJ�����ꂽ���߁A���b�E�h�e�R���^���N�E�h�e�K���X�E
�@�������Α��u�Ȃǂ��@���ڂ���Ă��炸�A�ČR�@�ɔ�ׁA��e�Ɏォ�����B
�@�O�ꂵ���y�ʉ��ɂ��@�̋��x�̌��E���Ⴍ�A�����^�̋}�~���������x�́A������̕ČR�@����
�@�Ⴂ�ᑬ��ł̑��c�����@�d�����ċ���ȕ⏕�����������߁A�ᑬ��ł͗ǍD�Ȑ��\������ꂽ
�@���ʁA������s���ɂ͑ǂ��d���@���������������B
�@�@�e�^�̐��Y����
| ���Y�H�� |
�O�H�d�H�� |
������s�@ |
�����Y |
| �^�� |
�P�P�^ |
�Q�P�^ |
�R�Q�^ |
�Q�Q�^ |
�T�Q�^ |
�T�Q�^ |
�T�Q�^ |
�U�Q�^ |
�T�S�^ |
�Q�P�^ |
�T�Q�^ |
�T�Q/�U�Q�^ |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
�b�^�� |
�� |
- |
- |
- |
- |
�� |
- |
| 1940 |
137 |
35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
172 |
| 1941 |
- |
400 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
- |
- |
408 |
| 1942 |
- |
306 |
340 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
547 |
- |
- |
1243 |
| 1943 |
- |
- |
- |
510 |
499 |
- |
- |
- |
- |
1760 |
2 |
- |
2771 |
| 1944 |
- |
- |
- |
- |
248 |
248 |
- |
- |
- |
508 |
1598 |
168 |
2770 |
| 1945 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
93 |
158 |
2 |
- |
- |
1417 |
1670 |
| ���Y���v |
137 |
741 |
343 |
560 |
747 |
248 |
93 |
158 |
2 |
2821 |
1600 |
1585 |
9034 |
�@�@��Ȍ��ċL�^�ێ���
�@���{�C�R�ɂ͌����E��������܂߁A�G�[�X�E�p�C���b�g�Ƃ����l�P�ʂ̃q�[���[���̂���J�e�S���[�͑��݂��Ȃ���
�@����邪�A��ʓI�ɑ��ʌ��ċL�^�ێ��҂Ƃ��ẮA���L�̓�������L���ł���B
��{ �O�O
�ŏI�K���F�C�R��� |
���{�C�R�̐퓬�@������B�u�ŋ��̗��p�C���b�g�v��搂�ꂽ�����c�m�ł���B
�����m�푈���̓��ăp�C���b�g�̒��ŗB�ꌂ�Đ�200�@�������咣����G�[�X�E�p�C���b�g�ł���A
�����푈���瑾���m�푈�I��܂ōőO���Ő킢�������B
|
���V �A�`
�ŏI�K���F�C�R���� |
�����m�푈���̓��{�C�R�̐퓬�@������B���쌧�㐅���S���쑺�o�g�B�������̊K���͔��B
�펀��A�u�S�R�z����K�����i�v�̉h�ɗ������тɔC����ꂽ�B���a19�N10��26���A
��@���Z�u��n�̓��ʍU�����Ɉ��n���A�V������s�@��̂̂��߃}�o���J�b�g��n��
�뎮�A���@�ɕ֏悵�Ĉړ�����B���̓r���A�A���@���~���h�����k�[���ɒB�����Ƃ���ŁA
�n�����h�EP�E�j���E�F�����т̃O���}��F6F�ɍU�����Č��Ă���A�펀�����B
|
���c ����
���тɏ��i |
�����m�푈���̑���{�鍑�C�R�̐퓬�@������B�V���������S���ˑ��i����z�s�j�o�g�B
�������̊K���͏㓙��s�����A�ŏI�K���͏��сB���Ĕj120�@�ȏ�ƌ�����B
43������n�Ɉڂ������a20�N4��15���ߌ�3���O��A�G�@�ڋ߂̕���Č��c���i�߂�
�o�����߂��A���c�͂�������@�ɔ�я���ė�@1�@�ƂƂ��Ɋ������J�n�����B
���������̎����łɓG�@�̃O���}��F6F�w���L���b�g���@�͐��c�����̔w����ɍ���
�|�����Ă����B���\m�����яオ�����Ƃ����VF-46�������@�͐��c�����̔w�����
�����|�����Ă����B���\m�����яオ�����Ƃ����VF-46����
|
��� �O�Y
�ŏI�K���C�R����
|
�I�펞�͊C�R���сA�ŏI�K���͊C�R���сB�I��܂łɑ召�̓G�@64�@���ẴX�R�A���c��
���{�̃G�[�X�E�p�C���b�g�Ƃ��Ēm����B����������A�Ҍ��1944�N�i���a19�N�j8�����тɏ��i
����̊�n������{�{�y��@�̂��߂ɔ���B-32�h�~�l�[�^�[2�@�Ɠ��{�C�R�@���[����������
�ɓ������̏��Ō�킵���B����E���Ō�̋�ɍ����Q�����Ă���B
|
���� ����
�ŏI�K��
�C�R����
|
���{�C�R�̐퓬�@������ŗ��̌��ĉ��B�C�R�����i����A���т����K�����i�j�B
���a17�N�K�_���J�i�������Ō}���̕ĊC������F4F�퓬�@12�@�ƌ�킵�A�ĊC�������ĉ���
�}���I���E�J�[����т�P�@�Œǔ��B�J�[����т��K�_���J�i����s��ւ̒����̐��ɓ������Ƃ����
�_���čU��������������n����̑�C�Ō��Ăɂ͎���Ȃ������B
����@�̋@��������Ɉ����N�������J�[����т͍���ɑ��Ď̂Đg�̈�A�˂𑗂����B�����Ă���
�ꌂ���ˌ��ʒu�ɓ����Ă�������̗����A���̏u�ԋ@�͉̂�f���������Ƃ������A
��n�t�߂̊C�ݐ��ɍӂ��U�����B����́A���̉����ȓ����S����C�������ɂ́u�R�{�v�Ƃ���������A
�܂����̕��e�A�l�]�A��т���u���o�E���̋M���q�v�A�u���o�E���̃��q�g�z�[�t�F���v�ٖ̈������B���N24�B
|
���� ��
�ŏI�K������ |
�{�錧�p�c���i���p�c�s�j�o�g�B�C�R���w�Z70���A��38����s�w���B�ŏI�K���͒����B
�뎮�͏�퓬�@�E�ǒn�퓬�@���d���𑀂�A�l�E�����܂ߓG�@���Ĕj��72�@
���a20�N2��ڎO�l�O�q����A�ʏ̌������̐퓬301��s���u�V�I�g�v�����ɒ��C�B�������i�߂�
���c���B1945�N8��1����������ȉ����d��20���@�͋�B�Ɍ����Ėk�㒆��B-24�����@�ґ�
�����̕���A�����籌����ׂ��呺��n���o�������B����͍ŏI�I��P-51��
���Ă��ꂽ�Ǝv����B����͑�343��ɂ�����18�@�����Ă����Ƃ����Ă���B
|
�@�@�@�e�^���̑���
|
�@�@�@�뎮�͏�퓬�@���^ |
�@�@�@�뎮�͏�퓬�@�ܓ�^ |
�@�@�@�뎮�͏�퓬�@�l�^ |
| �@�̗��� |
�@�@A6M2b |
�@�@A6M5 |
�@�@A6M8 |
| �S�� |
�@�@2.0m |
�@�@11.0m |
�@�@11.0m |
| �S�� |
�@�@9.05m |
�@�@9.121m |
�@�@9.237m |
| �S�� |
�@�@3.53m |
�@�@3.57m |
�@�@3.57m |
| ���ʐ� |
�@�@22.44m? |
�@�@21.30m? |
�@�@21.30m? |
| ���d |
�@�@1,754kg |
�@�@1,876kg |
�@�@2,150kg |
| �d�� |
�@�@2,421kg |
�@�@2,733kg |
�@�@3,150kg |
| �ō����x |
�@�@533.4km/h�i���x4,550m�j |
�@�@564.9km/h�i���x6,000m�j |
�@�@572.3km/h�i���x6,000m�j |
| �q������ |
�@�@���q3,350km�i��������j/ |
�@�@�S��30��+2,560km�i��������j |
�@�@�S��30��+850km�i���K�j |
| �@�@���q2,222km�i���K�j |
�@�@/1,920km�i���K�j |
�E |
| ���� |
�@�@����20mm�@�e2�� |
�@�@����20mm�@�e2�� |
�@�@����20mm�@�e2�� |
| �@�@�i�g�s�e���e60���j |
�@�@�i�g�s�e���e100���j |
�E |
| �@�@�@��7.7mm�@�e2�� |
�@�@�@��7.7mm�@�e2�� |
�E |
| �@�@�i�g�s�e���e700���j |
�@�@�i�g�s�e���e700���j |
�E |
| ���� |
�E |
�E |
�@�@250kg���e1�� |
| �E |
�E |
�@�@30kg���^���P�b�g�e4�� |
| �E |
�E |
�@�@�ȏ���I�� |
| ����@���� |
1940�N7�� |
1943�N4�� |
1945�N4�� |
���̐���@��
�@���̐��쐔�͂P�X�O�X�W�@�ƌ����āA�O�H�P�Q�X�W�O�@�E�����U�T�S�T�E�����ł͗������̗��K�@A6M2K�Q�V�Q�P�@�B
�@�I�펞�Ɏc�������͂V�R�O�@�B�����̒l�i��@��Q�O���~�@�P�X�V�V�N�������i�Q���~
���ɏ������[����
�@�\���������ʁF�T�O�O�O�@�@�E�@���\�����F�R�O�O�O�@�@�E�@�u�[�Q���r���i���o�E���j�Q�T�O�O�@�@�E�@�}���A�i�����F�P�T�O�O�@
�@��p�t�߁F�P�Q�O�O�@�@�E�@����F�R�Q�O�O�@�@�E�@�����F�R�P�O�O�@�@�E�@�~���_�i�I�F�U�O�O�@�@�E�@�j���[�M�j�A�F�Q�T�O�@
�@�}�[�V�����A�M���o�[�g���F�R�T�O�@�@�E�@����F�Q�O�O�@�@�E�@�}���[�F�Q�O�O�@�@�E�@�������F�T�O�@�@�E�@�g���b�N���F�R�O�O�@�E�@
�@��x�x�߁F�Q�O
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F��P�O�V�O�@
�@�O�HA5M�́A���{�C�R�ŏ��̑S�����P�t�퓬�@�B
�@���{�Ǝ��̐v�v�z�̉��ɐ��삳�ꂽ�ŏ��̋@�́B�A���R�̃R�[�h�l�[���́gClaude �h�B��p�@�͗뎮��
�@�O�H�q��@�ł́A�����͏�퓬�@�ɑ����x�z��Y�Z�t��v�喱�҂ɔC���āA�J���v�ɓ����点���B
�@��Z���ꍆ�͏�퓬�@(A5M1)
�@�@�@�@�ŏ��̗ʎY�^�Ŕ����@�́A����^��1���B������ 7.7mm�@�e2��B�O�H�q��@��30�@���Y�B
�@��Z���ꍆ�͏�퓬�@��(A5M1a)
�@�@�@�@��^�̎嗃�ɃG���R��FF�^20mm�@�֖C���e1�傸�������������@�B
�@��Z����^�͏�퓬�@(A5M2a)
�@�@�@�@�����@�����O�^�Ɋ����A�v���y����3���Ƃ����B
�@��Z����^�͏�퓬�@(A5M2b)
�@�@�@�@�����@�̉ߗ�h�~�A�����ɑ��鑀�c�ҕی�̂��߁A���̂����ăJ�E���t���b�v�A����і������h�����t�����B
�@�@�@�@���������ꂪ���E�s�ǂƂ���A������Y�^�ł͕��h�͎��O����đ���ɑ��c�ҕی�̂��ߔw�т�����������B
�@�@�@�@��^�A��^������39�@���O�H���Y�B
�@��Z���O���͐�(A5M3a)
�@�@�@�@�ꍆ�͐���������A20mm�C�X�p�m�^���[�^�[�J�m���C�ƃC�X�p�m12Xcrs���┭���@�����������@��2�@����
�@��Z���l���͐�(A5M4)
�@�@�@�@�����@�����l��^�Ɋ����B�ł��������Y���ꂽ�^�ŁA�O�H�̑��ɍ����ۍH���A��B��s�@�Ȃǂ�
�@�@�@�@���v�� 1,000�@�����Y���ꂽ�B
�@�������K�p�퓬�@(A5M4-K)
�@�@�@�@��Z���͐�����������K�@
| �@�̖� |
��Z���ꍆ�͏�퓬�@ |
�E |
| �S�� |
�@11.00 m |

 |
| �S�� |
�@7.71 m |
| �S�� |
�E |
| ���d |
�@���d�F 1075 kg |
| �d�� |
�E |
| �ō����x |
�@460km/h |
| �q������ |
�@1200 km |
| ���� |
�@�����F 7.7 mm�@�e�~2 |
| �@30 kg���e�~2�܂���50 kg���e�~1 |
| ��� |
�@�P�� |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F��P�S�Q�R�@
�@����E��풆�ɊJ�������퓬�@�ł���B���̖��͎̂��d�̊e�^�̂����A���^�ȍ~�̋@�̂��ĂԂ��̂ł���B
�@1944�N�ȍ~�̓��{�C�R�ɂ����Ă̗B��G�ɐ��ʂ���R�\�Ȑ���퓬�@�Ƃ��đ����m�푈�����̓��{�{�y�h����
�@�����B���a16�N�j���A�쐼�q��@�i�ȉ��A�쐼�j�͐���@�̎��v�����������ݐ쐼���O�В��̉��A���@�퐧��c����
�@�@�@�h���^
�@���̈ꍆ�ǒn�퓬�@��/���d���^�iN1K2-J�j
�@�@���d���̍ŏ��̗ʎY�^��99�@���Y���ꂽ�B51���@�ȍ~��20mm�@�e�̎��t���x��3�x������ɕύX�B���e�����͎蓮��
�@���d���b�^�iN1K2-Ja�j
�@�@���^�̔�����60kg���e4���܂���250kg���e2���ɋ��������^�B��������O�������A�ʐς�13%���ς����B
�@�@�e�X�g�p�C���b�g�߂��R�{�d�v�����ɂ��ƁA���c���ƈ��萫�̃o�����X�����P���ꂽ�B���Y�@101�`200���@
�@�������d�O��^�iN1K3-J�j
�@�@���e�������d�C�������ɉ��ǁB�����@�˂�O����150mm�������A�@��ɎO���\�O���@�e��^2����lj��������������^�B
�@�@���Y201���@�ȍ~�ŁA1945�N2���ɏ��������Y�B
�@�������d����iN1K3-A�j
�@�@�������d�O��^�ɒ��̓t�b�N�A�����̕⋭�Ȃǂ̉������{�����͏�퓬�@�^�B����2�@
�@�@1944�N11��12���A�R�{�v�d�����̑��c�œ����p�ōs��ꂽ�q���͐M�Z�ł̒��͎����ɎQ���B
�@�������d�O��^�iN1K4-J�j
�@�@�������d���O�B�O��^�̔����@��ሳ�R�����ˑ��u�t���̗_��O�^�ɕύX�����^�B��517�A520���@�̂�
�@�������d���l�iN1K4-A�j
�@�@�������d���O�i�������d�O��^�j�ɒ��̓t�b�N�Ȃǂ�lj������͏�퓬�@�^�B����@�����삳�ꂽ���͕s��
�@�������d���܁iN1K5-J�j
�@�@���b�^�̔����@�����@�͏�퓬�@�ƂȂ�͂��ł������u�v�Ɠ����n�l�O-���^�i����2,200�n�́j�ɕύX�����^
| �������� |
���d���^ |
|
���d���^ |
�E |
| �@�̗��� |
N1K1-J |
|
N1K2-J |
 |
| �S�� |
11.99m |
| �S�� |
8.885m |
|
9.376m |
| �S�� |
4.058m |
|
3.96m |
| ���ʐ� |
23.5m? |
|
23.5m? |
| ���d |
2,897kg |
|
2,657kg |
| �ō����x |
583km/h�i���x5,900m�j |
|
594km/h�i���x5,600m�j |
| �q������ |
1,432km�i���K�j/2,545km�i�߉ׁj |
|
1,715km�i���K�j/2,392km�i�߉ׁj |
| ���� |
�嗃���|�b�h20mm�@�e2�� |
|
����20mm�@�e4�� |
| �i�g�s�e���e100���j |
|
�g�s�e�������e200�� |
|
| �@��7.7mm�@�e2�� |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O���e250�� |
| �i�g�s�e���e550���j |
|
�@�@�v900�� |
| ���� |
60kg���e4���A250kg���e2�� |
| ���Y�@�� |
1,007�@ |
|
415�@ |
|
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F��200�@
�㎎�͏�U���@�Ƃ��Ē����A�O�H�A��Z����3�҂��������삵�A
��Z�����̂��̂���Z���͏�U���@�Ƃ��č̗p���ꂽ�B
�C�R�ɂ�����L����B4Y�B
���a11�N)11����Z���͏�U���@�Ƃ��Đ����̗p���ꂽ�B
���
1937�N�ɑ��C���ς��u������ƁA��͕����Ɗ�n�q�����
�������Z���͍U�����n�֔h������A��ɒn��U���Ɏg�p���ꂽ�B
�{���̗����̋@��ɂ͌b�܂�Ȃ��������A�p�i�C�������ł͐�������
�ɂ��p�i�C�������������B���̌�A��p�@�̋㎵���͏�U���@�̔z����
�Ƃ��ɁA����ɑ�����ނ����B
|
 |
�@�����m�푈�����܂ŁA���^���̓��ڋ@�A���ݏ����A���K�@�Ƃ��Ďg�p���ꂽ�B
��v�����@�@�@�@�@�@�@�@
| �S�� |
�S�� |
���d: |
���x |
��� |
�q������ |
���� |
| :10.15m |
15.00m |
1,825 -2,000kg |
277km/h |
3�� |
8����(1,574km) |
7.7mm�@�e�~2�i�@��Œ�E�㕔����e1�j
����1�܂��͔��e500�`800kg
|
|
���̖�������s�@�ɂ͑S���v�̈قȂ钆�����iB5N�j�ƎO�H���iB5M�j
��2��ނ����݂��邪�A�ʏ�͒������iB5N�j���w���B
���{�C�R�Ƃ��ẮA���̑S�������̒ᗃ�P�t�@�ł���A
�ꍆ�^�͍��Y�P���@���̈����r���̗p�A1937�N�j�ɂ͏���s�ɐ������Ă���B
���̈ꍆ�̔����@���u���v�O�^����u�h�v11�^�ɕύX�������̂��㎵���O��
�͏�U���@�i��ɋ㎵���͏�U���@���^�Ɖ��́j�Ƃ��č̗p���A�Ȍ㐶�Y��
���S�͎O���Ɉڂ�B
�ꍆ�A�O�����킹��1250�@�قǂ��A������s�@�̏���H��i�@�́j��
���Y����Ă���B �̂��A�ꍆ�͢�㎵���͏�U���@���^��A�O����
��㎵���͏�U���@���^��Ɖ��̂��ꂽ�B
|
 |
�@�@�@���́F377 km/h�@�@�@�����F800 kg �����܂��͔��e�~1�A7.7mm�@�e�~1�@�@�@
�@�@
�@�@�@�㎵���͏�U���@
�O�H�d�H�ƂŊJ�����ꂽ�i��ɋ㎵���͏�U���@�Z��^�Ɖ��́j��
�ێ�I�ȌŒ�r�ł���A�����@�ɔ�אU�������Ȃ��������߁A
�̂ق����D�ޓ�����������Ƃ����B
�͏��a15�N�ɐ��Y���I�����A���P���⏣���Ȃǂɗp����ꂽ�B
���v��150�@�قǂ��i120�@�Ƃ��j���Y����Ă���B
��ɁA�{�^�͢�㎵���͏�U���@�Z��^��Ɖ��̂��ꂽ�B
|
 |
�@�@�@���́F380 km/h�@�@�����F800 kg �����܂��͔��e�~1�A7.7mm�@�e�~1
�X�y�b�N�i�O���j
| �S�� |
�S�� |
���d: |
���x |
��� |
�q�����ԁE���� |
���� |
| 10.3m |
15.52m |
2,170kg |
378km/h |
3�� |
1,021km�@ |
����7.7mm�@�e�~�P 582���i6�e�q�j
800kg����1�{�����800kg�܂���250kg���e2��
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F1,266�@
���{�C�R���㎵���͏�U���@�i�ȉ��A�㎵���͍U�j�̌�p�@�Ƃ���
�J���E����z�������͏�U���@�A�@�̗�����B6N�B�v�E���Y�͒�����s�@
���a14�N�i1939�N�j10���A�C�R�͐����̗p���O�̋㎵���O���͍U��
��p�͏�U���@�Ƃ��āu�\�l���͏�U���@�v��v�����v��
������s�@�ɒ����B
���a17�N�i1942�N�j2��20����B6N1����ꍆ�@������
|
 |
�@�@����
�@���a18�N�i1943�N�j7���A�J������̑�O��q�����B6N1�����߂Ĕz�����ꂽ�B
�@6���̃}���A�i���C����}���Ă���B���̊C��ł͑�Z�Z��q�����29�@�����ԗ������s�������̂́A
�@F6F�w���L���b�g�̌}���Ƒ�C�ɂ��o���@��8������24�@�����A�҂ɂȂ�Ƃ����呹�Q���Ă���B
�@�@�h���^
�@�V�R���^�iB6N1�j
�@�@�\�l���͍U���l�A����^�������^�B���Y��124�@
�@�V�R���^�iB6N2�j
�@�@�@�����@���ΐ���܌^�Ɋ��������^�B�v��ł͏��a18�N11������ʎY�����\�肾�������K�v���̌삪
�@�@�@���B�ł��Ȃ��������߁A�ʎY�J�n��1�������߂��Ă���B
�@�V�R���b�^�iB6N2a�j
�@�@�@���^�̌�������@�e��13mm�@�e�Ɋ����������������^
�@�V�R��O�^�iB6N3�j
�@�@�@�����@���ΐ���ܕ��^�Ɋ������A�G���W���J�E���A���h�����Đv�������\����^�B����@2�@�̂�
�@�@����
| �������� |
�V�R���^ |
|
�V�R���b�^ |
| �@�̗��� |
B6N1 |
|
B6N2a |
| �S�� |
14.894m�i�嗃��7.1935m�j |
| �S�� |
10.865m |
| �S�� |
3.800m |
|
3.820m |
| ���ʐ� |
37.202m2 |
| ���d |
3,223kg |
|
3,083kg |
| �ō����x |
�S64.9km/h�i���x4,800m�j |
|
481.5km/h�i���x4,000m�j |
| �q������ |
1,460km�i���K�j�^3,447km�i�߉ߏd�j |
|
1,746km�i���K�j�^3,045km�i�߉ߏd�j |
| ���� |
7.7mm����@�e2���i�����E�㉺���j |
|
13mm����@�e1���i�����j |
|
|
7.92mm����@�e1���i�㉺���j |
| ��� |
3�� |
|
3�� |
| ���� |
60kg6���A250kg2���A500kg�܂���800kg���e1���A��ꎮ�q��1�� |
| ���Y�@�� |
124�@ |
|
|
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�͏㔚���@ |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F1486�@
1936�N�j�u�\�ꎎ�͏㔚���@�v�Ƃ��Ď��삪�n�܂�A���m�q��@
�i1943�N���m���v�d�@����Ɨ��j���E���Y���s���A�����m�푈����
�Ɋ����A���{�C�R�̊͏�}�~�������@�B�ʏ́u��㎮�͔��v�A
�������́u���͔��v�B�L����D3A�B
���a14�N12��16���A�u��㎮�͏㔚���@���^�v�Ƃ��ĊC�R�ɐ����̗p���ꂽ�B
���a17�N8���ɉ��̋�㎮�͏㔚���@���^�ƌĂꂽ���nj^�����삳�ꂽ�B
���a18�N�j1���ɋ�㎮�͏㔚���@���^�iD3A2�j�Ƃ��Đ����̗p���ꂽ�B
|
 |
�@�@���Y
�@���Y��1939�N�i���a14�N�j����J�n����A���m�ɂ����Ĉ��^��476�@�i��������@���܂ށj�A���^��816�@���Y���ꂽ�B
�@���a��s�@�ł����^�̌�����Y�^��220�@���Y���ꂽ�B���̓��A�I�펞�Ɏc�����Ă����̂�135�@�������B
�@�@���
�@���͔��́A�뎮�͏�퓬�@�E�㎵���͏�U���@�Ƌ��ɁA�����m�푈�O���̓��{�C�R�̉��i�����x���A�^��p�U����
�@�Z�C�������C��Ȃǂō����}�~���������������������B���͔��̋�ꂩ��̍��Q���̓}���A�i���C��ɂ���ďI�������B
�@����
| �������� |
��㎮�͏㔚���@���^ |
|
��㎮�͏㔚���@�j�j�^ |
| �@�̗��� |
D3A1 |
|
D3A2 |
| �S�� |
10.185 m |
|
10.231 m |
| �S�� |
14.360 m |
| �S�� |
3.348 m |
| ���ʐ� |
34.970 m? |
| ���d |
2,390 kg |
|
2,750 kg |
| �ō����x |
381.5 km/h�i���x2,300 m�j |
|
427.8 km/h�i���x5,650 m�j |
| �q������ |
1,472 km |
|
1,050 km |
| ���� |
�@��Œ�F7.7mm�~2�A�������F7.7mm�~1 |
| ��� |
�Q�� |
| ���� |
250kg �~ 1�A60kg �~ 2 |
| ���Y�@�� |
476�@ |
|
1036 |
 |
 |
 |
| ��\�������C����Ēߊ͍ڋ@ |
���i������ |
�^��p�U���̒��O�B
���Ɍ�����̂͋�ꑓ�� |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F2,253�@
����{�鍑�C�R�̊͏㔚���@�B�@�̗�����D4Y�B
�����m�푈�㔼�̓��{�C�R��͋@�ƂȂ�A���U�@�Ƃ��Ă��������ꂽ�B
�P�������̍����͏㔚���@�Ƃ��Đv���ꂽ�a���́A�͏㔚���@
�Ƃ��Đv���ꂽ�a���́A�͏㔚���@�Ƃ��Ă͂��Ȃ�̏��^�@�ŁA
�뎮�͏�퓬�@�Ƃقړ��T�C�Y�ł���B
���a18�N6������A�@�̋��x�����コ�����͏㔚���@�^���a�����^�iD4Y1�j
�Ƃ��ėʎY�Ɉڂ�A���a18�N�㔼�̃\�������킩����퓊�����ꂽ�B
|
 |
�@�@�@�h���^
�@�\�O���͏㔚���@�iD4Y1�j
�@�@�@�@�@DB 601A�G���W���𓋍ڂ�������^�B���Y��5�@�B
�@�͏��@�@���^�iD4Y1-C�j
�@�@�@�@�@��@�p�J�����Ɣ��e�q�����������R���^���N��lj������͏��@�@�^�B
�@�͏��@�@���^�iD4Y2-C/R�j
�@�@�@�@�@�����@���A�c�^�O��^�Ɋ��������͏��@�@�^�B�������@�e��13mm�@�e�ɋ����������b�^�����Y���ꂽ
�@�a�����^�iD4Y1�j
�@�@�@�͏㔚���@�^�Ƃ��Ă͍ŏ��̗ʎY�^�B
�@�a�����^�iD4Y2�j
�@�@�@�@�@�����@���A�c�^�O��^�Ɋ��������͏㔚���@�^�B�͒���^���l�A�������@�e��13mm�@�e�ɋ�������
�@�@�@���b�^�iD4Y2a�j�����Y���ꂽ�B
�@�a������^�iD4Y2-S�j
�@�@�@���^�̒�@���Ȍ����20mm�Ώe��lj�������Ԑ퓬�@�^�B�O�Z�����n�߂Ƃ���A�{�y�h���ƕ��u�����ɔz���B
�@�a�����^�iD4Y2���j
�@�@�@�q���͂ɉ������ꂽ�ɐ��^��͓��ڗp�ɋ@�̂��������ăJ�^�p���g�ˏo�\�Ƃ����@�́B���^�܂��͈��^����
�@�@�@�����i���^�͔M�c�O��^�ւ̊������܂ށj�B
�@�a���O�O�^�iD4Y3�j
�@�@�@���@�������Z��^�i����1,560�n�́j�Ɋ����������㔚���@�^�B����@���������̓t�b�N�����B
�@�@�@���^���l�A�������@�e��13mm�@�e�ɋ��������O�O�b�^�iD4Y3a�j�����Y���ꂽ�B
�@�a���O�O��^�iD4Y3-S�j
�@�@�@�O�O�^�̒�@���Ȍ����20mm�Ώe��lj�������Ԑ퓬�@�^�B��햖���A����^
�@�@�@�̑�ւƂ��ĎO�Z���Ȃǂɏ����@���z��
�@�a���l�O�^�iD4Y4�j
�@�@�@��Ȕp�~�i�ꕔ�͕����^�ɖ߂���Ă���j�A�h�e���������A���e�q���p�~�Ȃǂ̉��C���{�����ȈՌ^�B
�@�@�@800kg���e1���̓��ڂ��\�B��ʓI�ɂ͓��U�d�l�Ƃ��ĔF�m����邱�Ƃ������B
�@�@����
| �������� |
�a�����^ |
�a�����^ |
�a���O�O�^ |
| �@�̗��� |
D4Y1 |
D4Y2 |
D4Y3 |
| �S�� |
11.50m |
11.50m |
11.50m |
| �S�� |
10.22m |
10.22m |
10.22m |
| �S�� |
3.175m |
3.069m |
| ���ʐ� |
23.6m2 |
23.6m2 |
23.6m2 |
| ���d |
2,510kg |
2,635kg |
2,501kg |
| �ō����x |
546.3km/h�i���x4,750m�j |
579.7km/h�i���x5,250m�j |
574.1km/h�i���x6,050m�j |
| �q������ |
1,783km�i���K�j�`2,196km�i�߉ׁj |
,517km�i���K�j�`2,389km�i�߉ׁj |
1,519km�i���K�j�`2,911km�i�߉ׁj |
| ���� |
�@��7.7mm�Œ�@�e2��600�� |
�@��7.7mm�Œ�@�e2��400�� |
�@��7.7mm�Œ�@�e2��400�� |
| ����7.7mm����@�e1���@ |
����7.7mm����@�e1�� |
����7.92mm����@�e�P�� |
| �@�@�@�@�@�@�@�i97���e�q�~6�j |
�@�@�@�@�@�@�@�i97���e�q�~6�j |
�@�@�@�@�@�@�@�@�i75���e�q�~3�j |
| ��� |
2�� |
2�� |
2�� |
| ���� |
����250kg�܂���500kg |
����250kg�܂���500kg���e1�� |
����250kg�܂���500kg���e1�� |
|
���e1�� |
����30�`60kg���e2�� |
����250kg���e2�� |
| ���Y�@�� |
�E |
�E |
�E |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F114�@
�����m�푈�����ɓo�ꂵ������{�鍑�C�R�̊͏�U���@�ł���B
�v�E�J���͈��m�q��@�B�J���҂̊Ԃł́u�������v�ƌĂꂽ�B
�@�̗��Ԃ�B7A�B�s�퓖���A�؍X�ÊC�R�q���n����
�[���������̋�ꃈ�[�N�^�E���ɓ��U�U�����s���A
�C�R�����L�^��u�Ō�̓��U�v�ƂȂ����B
���C���͏�U���@�ŋ}�~�������E���������E�����A���Ȃ킿�͏㔚���@��
�͏㗋���@�̗��@��̖��������˂�B
|
 |
�@�@�@�����ҁF���m�q��@�@�@����s�F1942�N12���@
�@�@�@���Y�J�n�F1941�N�`1945�N
| �S�� |
�@14.40 m�i�嗃�܂��ݎ�8.30 m�j |

�嗃��܂肽������

|
| �S�� |
�@11.49 m |
| �S�� |
�@4.07 m |
| ���ʐ� |
�@35.40 m2 |
| ���d |
�@3,614 kg |
| �ō����x |
�@542.6 km/h�i���x6,200 m�j |
| �q������ |
�@�������K�F1852km�@�����߉ׁF2982 km |
|
�@����20mm�@�e2�� |
| ���� |
�@����13mm����@�e1�� |
| ���� |
�@����500�`800kg���e1���A�܂���250kg���e2�� |
|
�@����30-60kg���e4�� |
| ���� |
�@850�`1,060kg����1�{ |
| ��� |
�@2�� |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y�@��428�@
���t�͏㔚���@�B���m�q��@�����Ђ̋�l���͏㔚���@�W�����Đ������A
���{�C�R��1936�N�i���a11�N�j�ɐ����̗p�����B�C�R�̋L����D1A2
���a11�N�j10���ɋ�l���͏㔚���@���Ə̂��ꂽ
�x�ߎ����̎�͂Ƃ��Ċ͏ゾ���łȂ����ォ������i���Ċ����B
���a16�N�j12���ɍ̗p����A���K�q����Ŏg�p���ꂽ�B�܂��A�J�평����
��@�@�Ƃ��ĉ^�p����ΐ����͏����p�Ƃ��Čy���u���v�ʼn^�p
�L�^���c���Ă���B���Y��1936�N����1940�N�܂ōs���A
|

|
�����ҁF���m�q��@�@�@�@�@����s�F1936�N�@�@�@�@�^�p�J�n�F1936�N11��
| �S�� |
�S�� |
���d |
�ō����x |
��� |
�q������ |
���� |
| 9.40 m |
11.40 m |
1,775 kg |
309 km/h |
2 ���@ |
1,330 km�@ |
7.7mm �~3�i�@��Œ�2+��Ȑ���1�j
�����F250kg �~1�A30kg �~2
|
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��@�@�E�����@ |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Y���͖�220�@
���m�q��@�����Y�������{�C�R�̐����@�@�ł���B�@�̗��Ԃ�E16A
���a17�N�j3���Ɏ���1���@������������
���a18�N�j8���ɐ��_11�^�Ƃ��Đ����̗p���ꂽ�B
���a19�N�j�t���畔���z�����J�n����t�B���s�����ʂł̖�Ԕ�������
�g�p���ꂽ�B���ɋ������U���ɂ����ẮA����Ȃ�̐�ʂ������Ă���B
|

|
�@�d�l
�@
| �S�� |
�S�� |
�S�� |
�ō����x |
��� |
�q������ |
���� |
| 10.84 m |
12.80 m |
4.74 m |
448 km/h |
2�� |
2,535 km�@ |
20mm�@�֖C�~2
7.7mm����@�e�~1�i�����^�j�E
13mm����@�e�i�ʎY�^�j
60kg���e�~2�܂���250kg���e�~1
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F398�@
�����m�푈��������^�p���ꂽ����{�鍑�C�R�̊͏��@�@�ł���
�J���L����C6N�B����E��풆�ł͗B��A��@��p�Ƃ��ĊJ�����ꂽ
�͏�@�ł���B
���{�C�R�̊͏��@�@�̗��j�́A1921�N�i�吳10�N�j���̍��Y��@�@�Ƃ���
��Z���͏��@�@�i�̗p�����͏\�N���͏��@�@�j�삵�����ƂɎn�܂�
������s�@�Ŏ������\�肳��Ă����@�̂��u�\�����͏��@�@�v�Ƃ���
���씭�����邱�ƂƂȂ����B
|
 |
�@���a19�N�j9���ɁA�͏��@�@�u�ʉ_�v(C6N1)�Ƃ��Đ����̗p�ƂȂ邪�A����͎葱����̂��Ƃł���A
�@�ʎY�@�͂��ł�6������@����z������Ă����B�{�y���킪���������Ă���ƁA���ʍU�����p�̓��U�@�Ƃ���
�@�^�p���邱�Ƃ��l������悤�ɂȂ��Ă����B
�@�@�d�l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�^�p�J�n�F1944�N�i���a19�N�j6���@�@�@�����ҁF������s�@�E���{��s�@
| �S�� |
�S�� |
���d |
�ō����x |
��� |
�q������ |
���� |
| 11.15m |
12.50m |
2.908kg |
609.5km/h |
3�� |
5,308km |
7.92mm�@�e�~1 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F8�@
���{�C�R�̐����@�@�ł���B�@�̗��Ԃ�E15K�B
���a18�N�i1943�N�j8���ɓ����x�����@�@���_11�^�Ƃ���
�����̗p���ꂽ���A�^�p��̖����������������̐��Y�ŏI������B
���������@�@�̎����쐼�q��@�Ɏw�������B
���a18�N�i1943�N�j8���ɓ����x�����@�@���_11�^�Ƃ��Đ����̗p���ꂽ
���a19�N�i1944�N�j6���ɂ̓p���I���̃A���J�x�T�������n�ɔz������
���G��@�⏣���C���Ɏg�p���ꂽ�B
|
 |
| �S�� |
�S�� |
���d |
�ō����x |
��� |
�q������ |
���� |
| 11.588 m |
14.00 m |
4,100 kg |
468 km/h |
2�� |
1,408 km |
�����F 7.7 mm�@�e �~ 1�A60 kg���e �~ 2 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F�O�@
�����m�푈���Ɏ��삳�ꂽ���{�C�R�̒�@�@
�@�̔ԍ��́uR2Y�v�B���̒������ɑo�q�^�̔����@��z�u���A
���a�Q�O�N�T����x�̎�����s���s�������A�G���W���̕s�����ŏ����
���\�ɒB���Ȃ��܂I����}�����B
���a18�N�j�A��Z���͍ō����x740km�A�q������3,333km�ȏ�Ƃ��������\��
���X�x��@�@�̊J�����J�n�����B���ꂪ�A18�������@�@�u�i�_�v�ł���B
|
 |
�@���a20�N�j4���Ɏ���1���@���r�C�^�[�r�������Ȃ��`�Ŋ������A5���ɖ؍X�Ô�s��Ŏ�����s���s�����B
�@�@���\
| �S�� |
�S�� |
���d |
�ō����x |
��� |
�q������ |
���� |
| 13.05 m |
14.00 m |
:8,100 kg |
741 km/h |
2�`3�� |
:3,610 km |
�E |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Y��1423�@
���m�q��@���J�����A���a15�N�ɐ����̗p���ꂽ���{�C�R�̐���@�B
���̂ł���뎮����ƌĂ�邱�Ƃ������A�뎮���^�����@�@�Ƃ̈Ⴂ��
���m�ɂ���ꍇ�ɂ͗뎮�O�������@�@�Ƃ��\�L�����B
���{�C�R�ɂ�����L����E13A�B���a16�N����͑D���n�ւ̔z�����{�i�������B
�J�펞�ɂ͊C�R�̎�͊͑D�ɂ͖{�@�����ڂ���Ă���͑���O�n�̊�n��
�ڂƂ��Đ���Ɋ��������B
|
 |
���Y�͈��m�q��@�̑��A�n�ӓS�H���i��ɋ�B��s�@�ɂȂ�j�A�L�H���ł��s��ꂽ�B
| �S�� |
�S�� |
���d |
�ō����x |
��� |
�q������ |
���� |
| 11.49m |
4.70 m |
3,650 kg |
367 km/h |
3�� |
3,326 km /14.9h |
7.7 mm �@�֏e �~ 1
60 kg ���e �~ 4 �܂���250kg ���e �~ 1
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Y����708�@
�����m�푈���ɉ^�p���ꂽ���{�C�R�̐���ϑ��@�E��@�@�B
�@�̗�����F1M�A���̂͗�ρi�ꂢ����܂��̓[���J���j
���a15�N�j���ɐ����̗p����āA�u�뎮����ϑ��@�v�ƂȂ���
2�N��Ɏ���w�����o���u�\�͏�퓬�@�v�i���j�Ɠ��N�ɐ��������ꂽ
���Ƃ���A�����ɂ��̋@��̊J������q������������B
|
 |
�@���a18�N�j�ȍ~�́A�D�c��q��ΐ��������喱�ƂȂ��������͑ނ������I��܂Ŋ����𑱂��A�ꕔ�̋@�̂�
�@���U�@�Ƃ��ĉ����Ŏg�p���ꂽ�B
| �S�� |
�S�� |
���d |
�ō����x |
��� |
�q������ |
���� |
| 9.50m |
11.00m |
2,550 kg |
�F370 km/h |
2�� |
1,070 km |
�㎵��7.7mm�@�e�i�@��2��j
���7.7mm�@�e�E60kg���e�~2 |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�O�H528�@�i����@4�@�܂ށj�A�����ۖ�180�@�j�ł���i���Y���ɂ��Ă�1,118�@���ِ̈�������j
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F167�@
����E��풆�ɋ㎵����s���̌�p�@�Ƃ��Ď��p������
4����^��s���B����s��1941�N�i���a16�N�j�@�Ԃ́uH8K�v�B
���V�v���G���W�������̔�s���Ƃ��Ă͓������E�ō��̐��\���ւ�
����@�Ƃ����B�Ȃ��A�A���^�́u����v�ƌĂ�Ă����B
���a14�N9���ɑ���E��킪�u���A���Ăْ̋������܂钆�A
�a�c���q�Z�����͏��a15�N���ɖ{�@������������悤��������B
���N12��29���A�\�O������͐쐼���H��Ŋ����A����������s���s��
�@�@�@����
|
 |
�@���a17�N�j3��4���ɂ́A��q���͂�����3�@�Ő^��p���ċ�P�����B
�@����3��7���̃~�b�h�E�F�[����������@�ŁAK��������w���������Y��ы@���ČR�퓬�@�̌}���Ō��Ă���A
�@����ŏ��̐퓬�r���@�ƂȂ���
�@�@�@���� �@�@�������́F��s�����^�i�������FH8K2�j
| �S�� |
�S�� |
���d |
�ō����x |
��� |
�q������ |
���� |
| 38.00m |
28.13m |
18,400kg |
465km/h |
10 - 13�� |
7,153km
�i��@�߉ׁj |
20mm����e5��A7.7mm����e4��
�܂��͍q���~2
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F153�@
���{�C�R�̗���ΐ������@�ł���BQ1�̖��������悤�ɏ����@�Ƃ���
�J�����ꂽ���{�ŏ��̋@�̂ł���B153�@�����Y����I�펞�ɂ�68�@�c�������B
�@�@�@�^�p
�ŏ��ɓ��C��z�������͍̂����C�R�q����ŁA1944�N10���ɓ��C�ɂ��
���������߂ĕҐ����ꂽ�B�����͐��Y�@�͑S�č����C�R�q����ɔz������
��s����̌P�������B
�{�@�͎�ɍϏB��?��Y��n�Ȃǂ��A���V�i�C�A���}���������ʂɂ�����
�ΐ����������ɏ]�������B
|
 |
�@�@�@�����@�@�@�@�@��B���㏣���@�@�u���C�v[Q1W1]�@�@�@�^�p�J�n�F1945�N1��
| �S�� |
�S�� |
�S��: |
�ō����x |
��� |
�q������ |
���� |
| 12.09 m |
16.00 m |
4.12 m |
320 km/h |
3 �� |
2,415 km |
20 mm�~1�A 7,7 mm�~1
250kg���e�~2 |
|
|
|
�@��́F����@�̎�C�@
�@41cm�i45���a�j�A���C 4��F���������̐��\�́A����790m/s�A�ő�˒�30,300m�i�ő�p30�x/��p5�x�j�A�C�e�d��1,000kg
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���O�b�e�j�A�C�g�̖�����250���A����20�L���ł̐������b�ѓO�͂�271�~���ł�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������̐��\�͏���790m/s�A�ő�˒�38,430m�i�ő�p43�x/��p2�x�j�A�C�e�d��1,020kg
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��ꎮ�O�b�e�j�A�C�g�̖�����250���A����20�L���ł̐������b�ѓO�͂�454�~���ł������B
�@��́F��a�@�̎�C�@
�@45���a46cm3�A���C 3��F
�@�@�@�@�@��a�^��͂����ڂ���46cm45���a�C�̍ő�˒���42,026m�A46cm��C�̑��U���x��29.5 - 30.5�b��
�@�@�@�@�@����Ă���B�܂�ő�p45�x�Ŕ��C�����ꍇ�́A���U�p�x��3�x����45�x�ɖC�g���グ��̂�4.2�b�A
�@�@�@�@�@���낷�̂ɂ�4.2�b�����邽�߁A���e���˂܂łɒP�����v��37.9 - 38.9�b��v����B
�@�@�@�@�@30,000���Ŏˌ�����ƁA�e������܂�50�b������B
�@�@�@�@�@��a�^��͂̑��U���x29.5 - 30.5�b/���́A�r�X�}���N����͂�26�b/��
�@�@�@�@�@�i�p4�x�B�������A���U�p�x��2.5�x�j��ĐV�^��͂̃}�j���A���ɂ���30�b/���Ƒ卷�Ȃ��B
�@�@�@�@�@�C�e
�@�@�@�@�@46cm�C�̏ꍇ�A�C�e�S���͋�ꎮ����2m�A�O���e��1.6m�B�C�e�d�ʂ͋�ꎮ����ї뎮�e��1,460kg�A
�@�@�@�O���e��1,360kg�ł������B1��̓��ڒ萔�͓���100���A1�C��300�����l����ꂽ���A���ۂ̐v�ł�
�@�@�@1�傠����120���{�P���p�C�e6���ɕύX
 |
 |
 |
| ��̓A�C�I���̎�C |
��͑�a |
��a�̎�C |
|
�@���^�_�f�����u��������v�͐��E�ō������̐��\���ւ�B
�@�_�f���͊e���ł��J�����Ă������A�����m�푈�܂łɐ��������͓̂��{�����ł���B
�@�����́A���`�����̗��̂ł���A�e���ɃG���W���ƍ����X�N�����[��g�ݍ��킹�A�������q�s���A
�@�Փ˂����͑D�Ȃǂ��ɂ���Ĕj�邱�Ƃ�ړI�Ƃ�������ł���B
�@���a8�N�j�ɓ��{�C�R�͎_�f�������J���E���p�����A����E���ɂ����Ďg�p���Ă����B
�@��풆�ɓ��{�R���g�p�����_�f�����́A�ČR�̋����ɔ�ׂ��y��ʁA�˒��̓_�ŗD�ʂɂ������B
�@�����̍q��@����ł������ł���{�i�I�ȍq���𐢊E�ɐ�삯�Ď��������̂́A
�@���{�C�R�̋�ꎮ�����������B�@���̋�����2�_�̓����������Ă����B
�@�����ɂ͊͒��p�E�����͗p�E�q��p�ɋ敪�����B
�@�@�_�f����
�@���܂Ƃ��ċ�C�̑���Ɏ_�f��p���������ł���B�P�Ɏ_�f�����Ƃ������ꍇ�A����E��풆�A
�@�B����p������^�p���ꂽ����{�鍑�C�R�̋�O�������������͋���������w�����Ƃ������B
�@�e��_�f�����̗v��
|
�S�� |
���a |
�d�� |
�˒� |
�e���d�� |
| ��O���_�f����1�^�i�͒��p�j |
900 cm |
61 cm |
2,700 kg |
36 kt �� 40,000 m
48 kt �� 20,000 m
|
490 kg |
| ��O���_�f����3�^�i�͒��p�j |
900 cm |
61 cm |
2,800 kg |
36 kt �� 30,000 m
48 kt �� 15,000 m |
780 kg |
| ����_�f����1�^�i�����͗p�j |
715 cm |
53.3 cm |
1,665 kg |
45 kt �� 12,000 m
49 kt �� 9,000 m |
400 kg |
| ��l���_�f����1�^�i�q���j |
670 cm |
53 cm |
1,500 kg |
45 kt �� 4,000 m |
350 kg |
| ��l���_�f����2�^�i�q�� �j |
527 cm |
45 cm |
810 kg |
45 kt �� 2,000 m |
200 kg |
| ��Z����C������ |
�i�͒��p �r���^�쒀�͂��珉�t�^�쒀�͂܂ł̋쒀�͈ȉ��̊͒��ɓ��ځj |
| 850 cm |
61 cm |
2,500 kg |
42 kt �� 10,000 m
46 kt �� 7,000 m |
400 kg |
�@��ꎮ����
����{�鍑�C�R���q��@����̓����p�ɐv�����q���B
��ꎮ�q���́A���x 20m�A���x 180 �m�b�g (333km/h) �ŁA�������R�`�Ŕ��˂ł���悤�ɂȂ����B
�㎵���͏�U���@�̐����ō����x 204 �m�b�g (378km/h) ��������x�~�������ŁA�g���r�ꂽ�C�ł����˂ł���B
| ��ꎮ�q��ڋ��� |
5.270m |
45cm |
848kg |
42�m�b�g (77.8km/h)
2,000m |
�y���� 235kg,
�����d�� 323.6kg |
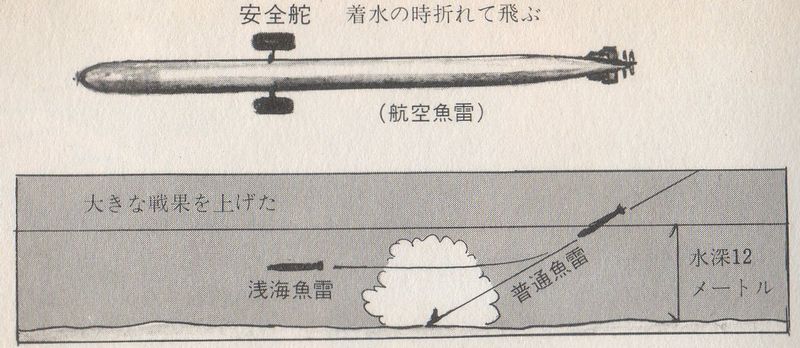
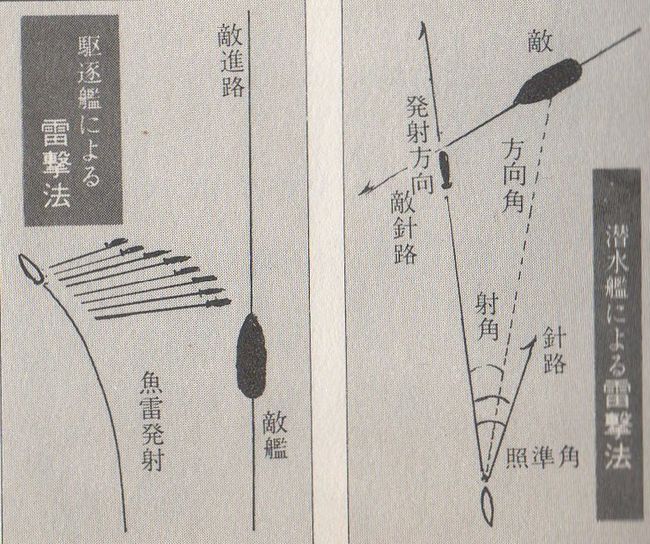
|
�X�㏬���a�i12.7cm�܂Łj�A�����a�i20.3cm�܂Łj�A����a�C�i����ȏ�j�ɕ�����B
�����a�C
| ��ނƖ��� |
���ڊ͒� |
|
45���a�O�N��12cm�C�F
�@�ʏ�G�^�C |
�����^�A�_���^(2���)�A�r���^�쒀�́A
�璹�^������(������) |

50���a�O�N��14cm�C
 |
45���a�\��N��12cm
�ʏ�M�^�C |
���^������ |
| 50���a�O�N��12.7cm |
|
| A�^�P���C |
�璹�^(�����O)�B |
| A�^��1�P���C |
���t�^�쒀�́A���I |
| B�^�P���C |
���I�^�쒀�� |
| A�^�A���C |
���^�쒀�͇T�B |
| B�^�A���C |
���^�U�V�A���t�^�A�璹�^ |
| B�^��1�A���C |
�L���A�[�� |
| C�^�A���C |
���I�^�A�����^�A�z���^�쒀�� |
| D�^�A���C |
�[�_�^�쒀�́A���� |
�����a�C
| 50���a�O�N��14cm�C |
|
|
| �P���C |
�V���^�A�[���A�A�ɐ��^�A����^�A�����͗p |

50���a�l�\�ꎮ15cm�C |
| �A���C |
�[���A����^ |
| 50���a�l�\�ꎮ15cm�C |
|
| �P���C |
�V���^�A�[���A5500�g���^�A�ɐ��^�A����^ |
| �A���C |
�[���A����^ |
| 50���a�l�\�ꎮ15cm�C |
|
| �P���C |
�����^�A�}�K�^ |
| �A���C |
�����^ |
| 60���a�O�N��15.5cm3�A���C |
�ŏ�^�A��a�^�A�嗄 |
| 50���a�O�N��20cm |
|
| A�^�P���C |
��^ |
| A1�^�P���C |
�ԏ�A���� |
| B�^�A���C |
�ԏ�A���� |
| C�^�A���C |
�t�^ |
| D�^�A���C |
�����^ |
|
| 50���a�O�N��2��20cm�F���a203.2mm |
|
| E�^�A���C |
���Y�^�i����������j |
|
| E1�^�A���C |
����A�ŏ�^ |
|
| E2�^�A���C |
��^ |
|
| E3�^�A���C |
�����^ |
|
����a�C
| 45���a����36cm�A���C�F���a35.6cm |
�����A��b |
| 45���a�l�ꎮ36cm�A���C�F�����̍��Y�� |
�Y���A�����A�}�K�^�A�ɐ��^ |
| 45���a�O��40cm�A���C�F���a41.00cm |
����^ |
| 45���a��l��46cm3�A���C�@�@�����ď́u�l�܌��a��l���l�Z�W�C |
��a�^ |
�@�e���\��r�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@50���a�O�N��20cm�C
| ���� |
50���a�O�N��14cm�C |
50���a�l�\�ꎮ15cm�C |
60���a�O�N��15.5cm |
1�� |
2�� |
| ���a |
140mm���a / 50���a |
�@�@�@�@152mm |
�@�@�@�@155mm���a |
200mm |
203mm |
| �C�g�� |
|
�@�@�@�@7,600mm |
|
50���a |
50���a |
| �C�g�d�ʁi�P���C�j |
�@�@�@�@�@�@21t |
|
|
17.9�g�� |
19�g�� |
| �@�@�@�@�@�@�i�A���C�j |
�@�@�@�@�@�@50t |
�@�@�@�@�@72�g�� |
|
|
|
| ����p |
���x: 8�x/�b |
�@�@�@�@6�x�^�b |
�@�@�@�@�@360�� |
|
|
| �ő�˒� |
�@�@�@�@�@�@�@�@19,100 m |
�@�@�@�@21�C000m |
�@�@�@�@�@27,400m |
26,673m |
29,432m |
| ���ˑ��x |
�@�@�@�@�@�@�@10��/�� |
�@�@�@�@�@6��/�� |
�@�@�@�@�@5 ��/�� |
����5�� |
����4�� |
| �e�ۏd�� |
�@�@�@�@�@�@�@38 kg |
�@�@�@�@�@45.4kg |
�@�@�@�@�@55.9 kg |
110kg |
125.85kg |
| ����d�� |
|
�@�@�@�@�@12.3kg |
|
32.63kg |
33.8kg |
�@�@�@�܁Z���a�O�N�����W���C�@�d�l
| ���a |
127mm |
| �C�g�� |
50���a |
| �C�g�d�� |
4.205�g�� |
| �ő�˒� |
18,445m�i�p44�x�j |
| ���� |
550�� |
| ���ˑ��x |
10��/���i���ˎ� |
| �e�ۏd�� |
23.5kg |
| ����d�� |
7.67kg |
|
| �@�@�@���p�C |
�@40���a�O�N��8cm�P�����p�C�i�ʏ�8�Z���`���p�C�j
| ���� |
�E |
�@�@�@�@���ڊ͑D |
�E |
| ���a |
�@�@�@76.2mm���a |
�}�K�^ - �ɐ��^ |

�l�Z���a�O�N�����W���p�C |
| �C�g�� |
�E |
�P�āA�Ñ�^ |
| �C�g�d�ʁi�P���C�j |
�@�@�@�@�@2.6�g�� |
�V���^ - �����^ |
| �@�@�@�@�@�@�i�A���C�j |
�E |
���nj^ - ����^ |
| ����p |
�@���x: 11��/s |
�}���^�A�v�~�^ |
| �ő�˒� |
�@�@�@�@�@10,800 m |
�F��{ �\�o�C �_�� |
| �ő�ˍ� |
�@�@�@�@�@6,800 m |
�E |
| ���ˑ��x |
�@�@�@�@�@13��/�� |
�E |
| �e�ۏd�� |
�@�@�@�@�@9.43kg |
�E |
| ����d�� |
�E |
�E |
�吳11�N�j3���Ɏl�Z���a�O�N�����W���p�C�Ɖ��̂��ꂽ
|
�@�Z�Z���a�㔪�����W���p�C�i�ʏ̒�8�Z���`���p�j
| ���� |
�E |
�@�@�@�@���ڊ͑D |
| ���a |
�@�@�@76.2mm���a |
�E |
| �C�g�� |
�@�@�@�@60���a |
�y���m�́F�����^ |
| �C�g�d�ʁ@�i�P���C�j |
�@�@�@�@�@11�g�� |
�E |
| �@�@�@�@�@�@�@�i�A���C�j |
�E |
�E |
| ����p |
�@���x: 11��/s |
�E |
| �ő�˒� |
�@�@�@�@�@13,600 m |
�E |
| �ő�ˍ� |
�@�@�@�@�@9,100 m |
�E |
| ���ˑ��x |
�@�@�@�@�@26��/�� |
�E |
| �e�ۏd�� |
�@�@�@�@�@5.99kg |
�E |
| ����d�� |
�@�@�@�@�@1.96���� |
�E |
|
�@�Z�܌��a�㔪����Z�W���p�C�@���Y���P�U�X��
| ���� |
�E |
�@�@�@�@���ڊ͑D |
�E |
| ���a |
�@�@�@100mm���a |
�E |

|
| �C�g�� |
�@�@�@�@6,500mm |
�E |
| �d�ʁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
�@20.4�g��(A�^�C�� |
�E |
| �@33.4�g���iA�^�C�� |
��P |
| ����p |
���x: 11��/s10.6�x/�b |
�嗄 |
| �ő�˒� |
�@�@�@�@�@18,700m |
�H���^ |
| �ő�ˍ� |
�@�@�@�@�@13,300m |
�E |
| ���ˑ��x |
�@�@�@�@�@26��/�� |
�E |
| �e�ۏd�� |
�@�@�@�@�@13kg |
�E |
| ����d�� |
�@�@�@�@�@5.83���� |
�E |
|
�@�l�Z���a���㎮�\��W�����p�C�i�ʏ�12.7�Z���`���p�C�j�������F��1,300��
| ���� |
|
�@�@���ڊ͑D |
�E |
| ���a |
�@�@�@�@127mm���a |
�E |
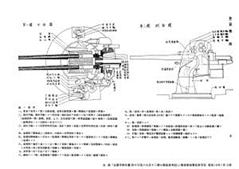 |
| �C�g�� |
�@�@�@�@6,500mm |
�E |
| �d�ʁ@�@�@�@ |
�@�@�@�@20.4�g�� |
��P |
| ����p |
���x: �U/s6�x/�b |
�嗄 |
| �ő�˒� |
�@�@�@�@�@14,622 m |
�H���^ |
| �ő�ˍ� |
�@�@�@�@�@9,439 m |
�E |
| ���ˑ��x |
�@�@�@�@�@14��/�� |
�E |
| �e�ۏd�� |
�@�@�@�@�@23.00 kg |
�E |
| ����d�� |
�@�@�@�@�@5.83���� |
�E |
|
�@�\��W�A�����i�C
�\��W�A�����i�C�́A���{�C�R�̊J���������P�b�g�����`���[�B
���Łi���傤����j�e�i���P�b�g�����Œe�A�ʏ̃��T�e�j�˂���ˑ�ł���B
| ���� |
�E |
�@�@�@�@���ڊ͑D |
| ���a |
120mm |
��́F�ɐ� - ���� |
| �C�g�� |
1,500mm |
�q���́F |
| �d�ʁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
2.5�g�� |
���� - �_�� - �V�� - |
| ���� - �M�Z - ���P |
| ����p |
�S�� |
���P - ��� - ���c |
| �ő�˒� |
4,800m |
���� |
| �ő�ˍ� |
2,600m |
�E |
|
�@�@��Z����\�ܖ����p�@�e
�@����E��풆�ɓ��{�C�R�Ŏg�p���ꂽ�Œ莮��@�֖C
�@�t�����X�̃I�`�L�X�i�z�`�L�X�j��25mm�@�֖C�����1935�N�i���a10�N�j�ɊJ�����ꂽ
�@�K�X���쓮�����̑�@�֖C�ł���B
| ���� |
�E |
�@�@�@�@���ڊ͑D |
�E |
| ���a |
25mm |
�E |
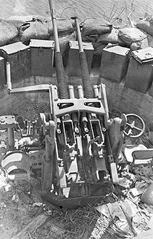 |
| �C�g�� |
1.5m |
| �d�ʁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
1100kg(�A��) |
| 785kg(�P��) |
| ����p |
360�� |
| �ő�˒� |
5,500m |
 |
| �ő�ˍ� |
�E |
| ���ˑ��x |
260��/�� |
| �e�� |
��E�Ί͗��p�e |
| �ĈΞ֒e |
| ������ |
��33,000�� |
�@��͑�@�e�Ƃ��Đ�́A�q���͂���A���͓��̕⏕�͒��Ɏ���܂ŗl�X�Ȋ͒��ɓ��ڂ��ꂽ�B |
|
|
|