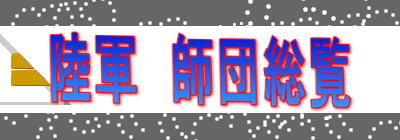師団と軍の性格の相違
師団と軍とでは著しく性格が異なることを明確にしたい。師団というのは、平時から編制表によって厳密に
その部編制と 人員・馬数・装備品の数量とを規定されている編制部隊である。
しかし軍というのは、固定的な編制が定められているものではなく、
戦時または事変等に際して、その必要に応じて編成する。軍令部の編制にはある程度の標準があるが、
その軍にどれだけの師団や直轄所部隊を編合するか、その時の情勢に応じて変化する。 |
昭和の師団戦時編制
1.師団(3単位)の例
師団総勢
・師団司令部: 人304、自41
人員 :14、640人
・歩兵団 (人8732 馬1227 自41) 馬 : 2,470頭
・歩兵団司令部 (人89、自8) 自動車: 490両
・歩兵連隊X3 (人2881、馬409、自11)
・聯隊本部 (人107、馬17、自11)
・歩兵大隊X3
・大隊本部 (人103、馬59)
・中隊X3 (人180、軽機9、重擲弾筒9、小銃144
(中隊は3小隊、小隊は4分隊に区分)
・機関銃中隊 (人122、馬29、重機8)
・歩兵砲小隊 (人45、馬10、大隊砲2)
・歩兵砲中隊 (人132、馬62、四一式山砲4)
・速射砲中隊 (人72、馬13、九四式37粍砲4)
・通信 中隊 (人133、馬23)
・捜索聯隊:(人439、自35、軽装甲車16)

2.師団 (4単位)の例
・師団司令部
・歩兵旅団X2 (人7103、馬874)
・歩兵旅団司令部 (人53、馬16)
・歩兵聯隊X2 (人3525、馬429)
*聯隊本部1、大隊3、歩兵砲中隊1、聯隊機関銃中隊1
大隊は、大隊本部、中隊4、機関銃中隊1
・騎兵大隊 (人451、馬431(中隊2、機関銃1)
・山砲兵聯隊 (人2407、馬1402、自34)
*(聯隊本部1、大隊3、聯隊段列1、第1,2大隊が山砲、第3大隊が野砲装備)
・工兵聯隊 (人672、馬99(中隊2))
・師団通信隊 (人246、馬45)
・輜重兵聯隊 (人1898、馬1451、自2)
・師団兵器勤務隊 (人121、自11) 師団総勢
・師団衛生隊 (1095、馬128) 人員 : 21,710人
・師団野戦病院X3 (人236、馬75) 馬 : 5,550頭
・師団病馬廠 (人48、 馬5) 車 : 50両 |
| 各師団 |
一般の師団とは異なり、最精鋭かつ最古参の部隊組織として天皇と皇居を警衛する
「禁闕守護」(きんけつしゅご)の責を果たし、 また儀丈部隊として「鳳輦供奉」(ほうれんぐぶ)の任にあたった
帝国陸軍における軍隊符号はGD。太平洋戦争 中後期には編制の改編が行われ、最終的には近衛第1師団
(1GD)・近衛第2師団 (2GD)・近衛第3師団 (3GD) の 3個近衛師団が編成された。創設:明治24年12月14日
昭和18年6月1日に近衛第1師団及び近衛第2師団に改編
日中戦争
昭和14年)、日中戦争(支那事変)に動員下令、近衛第2師団の前身となる近衛混成旅団となる
近衛混成旅団は第21軍隷下となり、 南支那方面軍として広東に上陸する。近衛混成旅団は広東作戦、
南寧作戦に従軍し、南寧を包囲する国民革命軍と激戦を展開した。
第二次世界大戦
近衛師団は、太平洋戦争中は南方戦線で活躍し、1941年(昭和16年)12月8日から昭和17年)1月31日の
マレー作戦には第25軍隷下として、近歩3・近歩4・近歩5及び近衛捜索連隊等が加わった。また、
同年のシンガポールの戦いでも活躍した
改編
昭和18年)6月1日に、スマトラ島メダン方面で作戦中の近衛師団は近衛第2師団(2GD)に改称され東京にあった
留守近衛師団を基幹として近衛第1師団(1GD)が、更に昭和19年7月18日には留守近衛第2師団を基幹として、
近衛第3師団(3GD)が編成される。終戦時の近衛第3師団は千葉県成東にあって連合国軍の関東上陸作戦
(本土決戦・決号作戦)に備えていた。
全中将
| 近衛師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 27.橋本虎之助 |
昭和10年12月 |
二・二六事件では宮城警備を指揮する |
| 28.香月清司 |
昭和11年3月 |
- |
| 29.西尾寿造 |
昭和12年3月 |
- |
| 30.飯田貞固 |
昭和12年8月 |
- |
| 31.飯田祥二郎 |
昭和14年9月 |
- |
| 32.西村琢磨 |
昭和16年6月 |
シンガポールの戦いを指揮する。 |
| 33.武藤章 |
昭和17年4月 |
昭和18年6月1日近衛第2師団に改称 |
| 近衛第1師団長 |
- |
- |
| 1.豊嶋 房太郎 |
昭和18年10月 |
留守近衛師団長から転じる。 |
| 2.赤柴 八重蔵 |
昭和18年10月 |
- |
| 3.森赳 |
昭和20年4月 |
音放送盤を奪う叛乱計画に反対して殺害される |
| 4.後藤光蔵 |
昭和20年8月 |
師団の復員を指揮した後に初代禁衛府長官に転じる。 |
| 近衛第2師団長 |
- |
- |
| 1.武藤章 |
昭和18年6月 |
- |
| 2.久野村 桃代 |
昭和19年10月 |
- |
| 近衛第3師団長 |
- |
- |
| 1.林 芳太郎 |
昭和19年7月 |
- |
| 2.山崎 清次 |
昭和20年5月 |
- |
終戦時には近衛連隊でも軍旗奉焼・復員が行われた。一部の将兵は禁衛府皇宮衛士総隊に移ったが、
禁衛府解体に伴い完全に消滅した。なお、近衛師団司令部庁舎は現在、東京国立近代美術館工芸館と
なっている。

最終所属部隊
近衛歩兵第1連隊 東京府
昭和18年)6月1日 - 近衛師団から近衛第1師団に所属変更
昭和20年8月15日 - 終戦
近衛歩兵第2連隊
近衛歩兵第1連隊とならび日本陸軍最初の歩兵連隊である。
昭和18年)6月1日 - 近衛師団から近衛第1師団に所属変更
昭和20年8月15日 - 終戦
近衛歩兵第6連隊
昭和18年6月1日編成される9月7日 - 軍旗拝受 昭和20年8月14日 - 大宮御所の警備に当たる
近衛歩兵第7連隊
昭和18年6月1日編成される9月7日 - 軍旗拝受

最終所属部隊
近衛歩兵第3連隊 東京
昭和15年月 - 動員下令、漢口作戦や広東作戦に参加する広東省中山県に駐留中に馬匹編制から
自動車編制に変わる、 自動車約80台と自転車3000台から成る
昭和17年1月 - 仏印サイゴンに駐屯、第3大隊を基幹にシンガポールの戦いに参加する
3月3日 - シンガポールから北部スマトラ島の平定作戦を開始
昭和18年第1大隊をスマトラに残し、連隊主力はアンダマン諸島に移駐するもスマトラに復帰
昭和20年月15日 - 終戦
近衛歩兵第4連隊 甲府 スマトラ島メダン
昭和15年6月 - 動員下令、漢口作戦などに参加する
昭和16年7月 - 仏印サンジャック湾に上陸、サイゴン(現 ホーチミン市)に駐屯
12月8日 - 太平洋戦争開戦、連隊主力は陸路でタイ王国へ進攻、第3大隊は
海上機動しバンコクに進出、マレー作戦を開始
シンガポール港を出発し北部スマトラ島平定作戦に従事、その後警備と防御陣地の構築をする
近衛歩兵第5連隊 佐倉 スマトラ島ラビンチンギ
昭和16年 広東省中山県唐家に上陸。8月初旬 - 雷州作戦ののち、南部仏印、12月 - タイ王国に進出
昭和17年1月8日 - マレー国境突破、2月25日 - シンガポールの戦いに参加、
3月 - スマトラ島平定作戦に参加
昭和18年8月 - 近衛師団から近衛第2師団に所属変更
昭和19年1月 - 編成改正完了し海上機動旅団と同様の大規模部隊となる

最終所属部隊
近衛歩兵第8連隊 東京 千葉 東金
昭和19年4月26日 - 軍旗拝受、以後は九十九里浜中央部の防御を担当し陣地構築に当たる
近衛歩兵第9連隊 甲府
昭和19年4月26日 - 軍旗拝受、以後は九十九里浜中央部の防御を担当し陣地構築に当たる
近衛歩兵第10連隊
昭和19年4月26日 - 軍旗拝受、以後は九十九里浜中央部の防御を担当し陣地構築に当たる


旧近衛師団司令部庁舎
 |
編成地:東京 略称:玉
明治21年5月に東京鎮台を母体に編成された。同時に第2師団から第6師団が夫々鎮台を改編して
創設されたが、 第1師団も含めこの時編成された6個師団が日本で最も古い師団である。
東京防禦総督が置かれるまでは、第1師団長が東京衛戍司令官とされていた。
師団は衛戍地である東京近郊の 警備を主任務としているが戦役にも参加し、
日清戦争・日露戦争・乾岔子島事件・ノモンハン事件・ 太平洋戦争に参加。
昭和12年)9月1日には、留守第1師団の担当で第101師団が編成された。
二・二六事件と第1師団
昭和11年2月22日師団に満州駐箚の命令が下されたが、これはその頃第1師団所属の青年将校の中に
昭和維新を叫ぶ者が居り、それらを満州へ遠ざける狙いがあったという。これが二・二六事件である。
クーデター自体は失敗に終わるが、首魁として処罰された。野中四郎大尉を始め、香田清貞大尉・
安藤輝三大尉・ 山口一太郎大尉ら決起将校の多くは何れも第1師団所属であった。
太平洋戦争ではフィリピン方面に出征。フィリピン防衛戦では山下奉文陸軍大将率いる第14方面軍に属し、
レイテ島の戦いが勃発するとレイテ島西部オルモック湾に上陸する。
師団は1万を超える兵力でレイテ島に渡ったものの、アメリカ軍との圧倒的な火力の差と補給が途絶えたこと
えたことからほぼ壊滅状態となった。1945年(昭和20年)1月に野砲兵第1連隊を残しセブ島に移動したときの
残存兵力僅か800名であった。その後、セブ島でも防衛戦を行った。
歴代第1師団長 (各人の階級は中将)
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 河村恭輔 |
昭和11年3月23日 - |
山口県出身昭和13年7月、参謀本部付となり予備役に編入された。 |
| 岡部直三郎 |
昭和13年)7月15日 - |
広島県、第6方面軍司令官として転補され漢口で終戦を迎えた病死 |
| 横山勇 |
昭和14年)9月12日 - |
福島県、第16方面軍司令官兼西部軍管区司令官として福岡で終戦 |
| 中沢三夫 |
昭和16年)10月15日 - |
山梨県、第40軍司令官、鹿児島県伊集院で本土決戦に備えたが終戦 |
| 服部暁太郎 |
昭和19年)3月1日 - |
兵庫県、昭和20年3月教育総監部付となり、同月、孫呉で死去した。 |
| 片岡董少将 |
昭和19年)8月3日 - |
兵庫県、レイテ島の戦いにおいて敗退。終戦をセブ島で迎えた。 |
| 片岡董中将 |
昭和19年)10月26日 - |
- |
最終上級:第14方面軍
所属部隊
昭和12年)の日中戦争勃発前の陸軍常備団隊配備表によると、第1師団は次のように配備されていた
昭和15年)8月には、歩兵第3連隊を第28師団に転出し三単位編制に改編され衛戍地は満州となったが
補充は内地より行われた
日中戦争勃発前 終戦時
・師団司令部(東京 ・師団司令部(東京):片岡董中将
・歩兵第1旅団(東京) ・歩兵第1連隊(東京):揚田虎己大佐
・歩兵第1連隊(東京)・歩兵第49連隊(甲府) ・歩兵第49連隊(甲府):小浦次郎大佐
・歩兵第2旅団(佐倉) ・歩兵第57連隊(佐倉):宮内良夫大佐
・歩兵第3連隊(東京)・歩兵第57連隊(佐倉) ・捜索第1連隊(東京):今田義男少佐
・騎兵第2旅団(習志野) ・野砲兵第1連隊(東京):熊川致長大佐
・騎兵第1連隊(東京)・騎兵第15連隊(習志野) ・工兵第1連隊(東京):原準一中佐
・騎兵第16連隊(習志野) ・輜重兵第1連隊(東京):朝倉好信大佐
・野戦重砲兵第3旅団(国府台) ・第1師団通信隊
・野戦重砲兵第1連隊(国府台) ・第1師団兵器勤務隊
・野戦重砲兵第7連隊(国府台) ・第1師団野戦病院
・野砲兵第1連隊(東京) ・第1師団防疫給水部
・横須賀重砲兵連隊(横須賀)
・高射砲第2連隊(国府台)
・戦車第2連隊(習志野)
・工兵第1連隊(東京)
・輜重兵第1連隊(東京)

|
編成地:仙台 略称:勇 最終上級:第14方面軍
明治21年)5月14日に仙台鎮台を改編して宮城県仙台区(翌年より仙台市)に設立された師団である。
昭和20年)の陸軍解体まで、日本の主要な戦争に参加した。
太平洋戦争では南方に投入され、緒戦は蘭印で快勝するがガダルカナルでは7000名を越す損害を出す。
その後マレー・シンガポール方面の警備を担当、1944年(昭和19年)からはビルマ戦線に参戦した。
師団司令部は仙台市川内(かわうち)の旧仙台城二の丸に、射撃場は仙台市台原に設置された。
歴代第2師団長
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 岡村寧次 中将 |
昭和11年)3月23日 - |
東京、昭和19年支那派遣軍総司令官、昭和16年)4月に陸軍大将 |
| 安井藤治 中将 |
昭和13年)6月23日 - |
富山県、1939年に第6軍司令官、昭和20年国務大臣 |
| 吉本貞一 中将 |
昭和14年)11月6日 - |
徳島県、昭和17年第1軍司令官、昭和20年第11方面軍司令官となり大将に進級 |
| 丸山政男 中将 |
昭和16年)4月10日 - |
長野県、ジャワ島守備に着いていた、1944年3月、予備役 |
| 岡崎清三郎 中将 |
昭和18年)6月10日 - |
島根県、本土決戦に備え第2総軍参謀長として広島に被爆する |
| 奈木敬信 中将 |
昭和20年)3月1日 - |
福岡県、昭和17年ボルネオ守備軍参謀長、サイゴンに司令部 |
参謀長:木下武夫大佐(陸士33期) 参謀:大江卓馬少佐、金富与志二中佐、松田三雄少佐
高級副官:荻原行雄少佐 兵器部長:鈴木喜芳大佐 経理部長:三好完六主計大佐
軍医部長:井美猛軍医大佐 獣医部長:鈴木福三郎獣医中佐
最終上級:第38軍
所属部隊
歩兵第4連隊(仙台):一刈勇策大佐 第2師団兵器勤務隊:細貝作蔵少佐
歩兵第16連隊(新発田):堺吉嗣大佐 第2師団衛生隊:西山秀雄中佐
歩兵第29連隊(若松):三宅犍三郎大佐 第2師団第1野戦病院:細見禎一少佐
捜索第2連隊:原好三大佐 第2師団第2野戦病院:武田正大尉
野砲兵第2連隊:石崎益雄大佐 第2師団第4野戦病院:丸茂三千穂少佐
工兵第2連隊:高瀬克巳大佐 第2師団病馬廠:伊藤辰男大尉
輜重兵第2連隊:山口英男少佐 第2師団防疫給水部:沼沢保少佐
第2師団通信隊:石橋一男大尉

|
編成地:名古屋 略称:幸 人員:25000名
名古屋方面出身者から構成される師団で、その前身は1873年(明治6年)1月に設置された名古屋鎮台。
明治21年)全国に6つあった鎮台が師団へ改編される中、第3師団と名前を変えた。
200個を数える陸軍師団でも 最も古い師団の一つである。開戦後も第11軍隷下華中に在り、この方面で行われた
さまざまな作戦に参戦した
昭和19年)には大陸打通作戦第二段の湘桂作戦に参戦して広西省に進攻、9月6日に零陵飛行場を、
11月4日には桂林第1飛行場を占領し、11月4日に柳城・柳州北岸を攻略した。作戦終了後は第11軍司令部の
置かれた柳州の 南側の南寧方面の警備を担当、なお西側の宜山方面は第13師団、北東側の桂林方面は
第58師団が担当した。 昭和20年)になると戦局の変化から広西省方面の日本軍は撤退を開始、4月18日に
第13師団とともに 支那派遣軍直轄師団となり南寧の警備を第58師団に譲って上海方面に向けて
移動中鎮江で終戦を迎えた。
歴代第3師団長
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 伊東政喜 中将 |
昭和11年)3月- |
1937年第101師団長となり出征。翌年9月に戦傷を受け帰国。 |
| 藤田進 中将 |
昭和12年)8月 |
昭和16年予備役編入から昭和20年)4月1日金沢師管区司令官に就任。 |
| 山脇正隆 中将 |
昭和14年)10月 |
1941年陸軍大学校校長、1942年ボルネオ守備軍司令官 大将 |
| 豊島房太郎 中将 |
昭和15年)9月 |
1943年6月、近衛第1師団長、第2軍司令官に発令、セレベス島で終戦 |
| 高橋多賀二 中将 |
昭和16年)12月 |
- |
| 山本三男 中将 |
昭和18年)3月 |
- |
| 辰巳栄一 中将 |
昭和20年)3月 |
1945年2月、第12方面軍参謀長に就任、第3師団長に中国鎮江で終戦 |
最終上級:第11軍隷下→支那派遣軍直轄師団
所属部隊(昭和20年)
歩兵第8連隊(大阪) 歩兵第37連隊(大阪) 歩兵第61連隊(和歌山) 捜索第4連隊 (金岡)
野砲兵第4連隊 (信太山) 工兵第4連隊 (高槻) 輜重兵第4連隊 (金岡) 師団通信隊
師団兵器勤務隊 師団衛生隊
 |
編成地:大阪 通称号/略称:淀 司令部は大阪城内(有)
第4師団の前身は大阪鎮台。創設時の歩兵連隊は、第8、第9、第10及び第20連隊からなる
昭和12年)2月、師団は満州に駐屯し、まもなく盧溝橋事件が勃発。昭和15年)7月に中支に派遣され、
漢水作戦、予南作戦、 江北作戦等に参加。昭和16年)9月には、第一次長沙作戦に従事。この後、師団は
大本営直轄となり、来るべき南方作戦に 備えて部隊の集結と再編成を行った。開戦後フィリピン攻略作戦に
参加し、第2次バターン半島攻略作戦に従事。
第4師団はコレヒドール島上陸に成功し同攻略戦の勝利に大きく寄与した。その後は本土警備に当たり、
1943年(昭和18年)9月、 再動員されることとなり、スマトラ島警備やビルマ方面を担当する第15軍の隷下に入り
タイに移動、同国の ランパンにおいて終戦を迎えた。司令部庁舎には昭和15年より中部軍管区司令部が入り、
第4師団司令部は二の丸に移転した。
歴代第4師団長
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 松井命 中将 |
昭和12年)3月 - |
福井県、昭和15年)3月、予備役に編入 |
| 沢田茂 中将 |
昭和13年)7月 - |
高知県、昭和15年第13軍司令官となり太平洋戦争を迎え、17年予備役に編入 |
| 山下奉文 中将 |
昭和14年)9月 - |
高知県、「マレーの虎」第14方面軍司令官、 絞首刑 陸軍大将 |
| 北野憲造 中将 |
昭和15年)7月 - |
滋賀県、昭和17年)7月、陸軍公主嶺学校長、第12方面軍兼東部軍管区司令官 |
| 関原六 中将 |
昭和17年)7月 - |
- |
| 馬場正郎 中将 |
昭和18年)9月 - |
熊本県、第37軍司令官 |
| 木村松治郎 中将 |
昭和19年)12月 - |
奈良県、第15軍隷下となり、タイのランパンに進出したが、同地で終戦 |
最終上級:第15軍
最終所属部隊
歩兵第8連隊(大阪) 歩兵第37連隊(大阪 歩兵第61連隊(和歌山) 捜索第4連隊 (金岡)
野砲兵第4連隊 (信太山) 工兵第4連隊 (高槻) 輜重兵第4連隊 (金岡)
師団通信隊 師団兵器勤務隊 師団衛生隊

編成地:広島 通称号/略称:鯉 人員:25000名
明治6年に設置された広島鎮台を母体に明治21年5月14日に編成された。マレー作戦後の昭和17年に
フィリピン攻略の 増援として、歩兵第9旅団司令部及び歩兵第41連隊基幹の河村支隊を編成、その後
歩兵第41連隊(福山)は、堀井富太郎少将指揮の南海支隊に編入され、第5師団は三単位師団に改編された。
開戦前の昭和15年10月12日に大本営直轄となった。
昭和16年)11月6日山下奉文中将率いる第25軍に編入、南方作戦に投入された。
12月8日の開戦とともにイギリス領マラヤに向けタイ領のシンゴラとバタニから上陸し、昭和17年1月11日には
クアラルンプールを占領、さらにシンガポール攻略の主力となった。
昭和18年)1月に師団は第19軍隷下となるが、1945年(昭和20年)2月28日に第19軍は廃止、第2軍隷下となった。
歴代第5師団長
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 板垣征四郎 中将 |
昭和12年3月- |
昭和13年第29代陸軍大臣、陸軍大将、巣鴨プリズンにて絞首刑。 |
| 安藤利吉 中将 |
昭和13年5月- |
昭和16年予備役、昭和19年陸軍大将、第10方面軍司令官 台湾総督 |
| 今村均 中将 |
昭和13年11月- |
昭和17年第8方面軍司令官、昭和18年陸軍大将、禁錮10年 |
| 中村明人 中将 |
昭和15年3月- |
昭和16年憲兵司令官、昭和20年第18方面軍司令官 |
| 松井太久郎 |
昭和15年10月- |
支那派遣軍総参謀長、第13軍司令官を勤め、上海で終戦を迎えた。 |
| 山本務 中将 |
昭和17年5月 - |
- |
| 山田清一 中将 |
昭和19年10月- |
インドネシア、カイ諸島の守備を担当し、セラム島で終戦 自決 |
| 小堀金城 少将 |
昭和20年8月 |
- |
参謀長の浜島厳郎大佐→自決
最終上級:第25軍→第19軍→第2軍
最終所属部隊
歩兵第11連隊(広島):佐々木五三大佐 第5師団通信隊:後藤好夫大尉
歩兵第21連隊(浜田):佐々木慶雄大佐 第5師団兵器勤務隊:守田晟大尉
歩兵第42連隊(山口):吉川章大佐 第5師団衛生隊:寺松芳松少佐
野砲兵第5連隊:中平峯吉大佐 第5師団第2野戦病院:呉羽新次軍医少佐
捜索第5連隊:藤村信吉大佐 第5師団第4野戦病院:松下勲雄軍医中佐
工兵第5連隊:後藤之敏中佐 第5師団経理勤務隊
輜重兵第5連隊:上木隆之大佐

編成地:熊本 通称号/略称:明 人員:25000名
明治21年)5月14日に編成された師団であり、熊本・大分・宮崎・鹿児島の九州南部出身の兵隊で編成され
衛戍地を熊本とする師団である。昭和15年)には歩兵第47連隊(大分)を第48師団に転用し
三単位編制に改編された。
開戦後、1942年(昭和17年)11月にソロモン諸島方面の作戦担当の第17軍に編入される。
昭和18年)初頭にソロモン諸島のブーゲンビル島(Bougainville)南部に進出する。主戦場がサイパンから
レイテ島へと 移り長く兵器弾薬が欠乏し飢餓と疫病に苦しむ(第2次タロキナ作戦後の
歩兵連隊は4,923名(外、戦傷1,787名)、 終戦時には1,654名になったという)。
歴代第6師団長
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 稲葉四郎 中将 |
昭和12年12月 - |
大阪府、昭和16年予備役に編入、 |
| 町尻量基 中将 |
昭和14年12月 - |
昭和17年)11月10日印度支那駐屯軍司令官 |
| 神田正種 中将 |
昭和16年4月 |
1945年4月、第17軍司令官となり、ブーゲンビル島の戦いに従軍し終戦 |
| 秋永力 中将 |
昭和20年4月 - |
- |
最終上級:第17軍
最終所属部隊
歩兵第13連隊(熊本):牟田豊治大佐 第6師団通信隊:定岡正憲大尉
歩兵第23連隊(都城):福田環中佐 第6師団兵器勤務隊:岩下鉄男大尉
歩兵第45連隊(鹿児島):福永康夫大佐 第6師団衛生隊:安部政太郎中佐
歩兵第45連隊(鹿児島):福永康夫大佐 第6師団第1野戦病院:鈴木文治軍医少佐
騎兵第6連隊:越沢三郎大佐 第6師団第2野戦病院:永田盛雄軍医少佐
工兵第6連隊:柴原貞喜少佐 第6師団第4野戦病院:石原定次軍医少佐
工兵第6連隊:柴原貞喜少佐 第6師団病馬廠:永友登獣医大尉
第6師団架橋材料隊:矢部茂少佐

編成地:札幌 通称号/略称:熊
北海道に置かれた常備師団として北辺の守りを担う重要師団であり、道民は畏敬の念を多分に含め、
「北鎮部隊」と呼んでいた
昭和17年)に一木支隊を編成しミッドウェー島からガダルカナル島に派遣し、また北海支隊を編成して
アリューシャン列島のアッツ島へ派遣したものの、師団本体は1940年(昭和15年)8月に天皇直属隷下に置かれ
以後、「動かざる師団」として北海道に在り続けた。昭和19年)2月には留守第7師団を基幹に第77師団が
新設され、 3月には師団司令部を帯広に移駐して道東方面防衛に専念することになった。これに伴い、
歩兵第26連隊を帯広、 歩兵第27連隊を釧路、歩兵第28連隊を北見に配置し、計根別平野(現中標津町)を
決戦地として定め、海岸陣地や トーチカの構築に専念するものの、予期された連合軍の襲来が無いまま、
第二次世界大戦の終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 園部和一郎 中将 |
昭和12年8月- |
1941年6月、予備役、1945年3月、召集を受け、留守第6師団司令部付 |
| 国崎登 中将 |
昭和14年8月 - |
広島県昭和16年予備役、昭和19年留守第7師団長となり |
| 鯉登行一 中将 |
昭和16年11月- |
群馬県、昭和16年、第6師団長に親補され終戦まで北海道に駐屯 |
最終上級:天皇直属隷下
最終所属部隊
歩兵第26連隊(旭川):山口定大佐 第7師団兵器勤務隊:西條初太郎中尉
歩兵第27連隊(旭川):長嶋秀雄大佐 第7師団衛生隊:山根正純少佐
歩兵第28連隊(旭川):新井花之助大佐 第7師団第1野戦病院:小原徳行軍医大尉
山砲兵第7連隊(旭川):佐竹千代光大佐 第7師団第2野戦病院:山田大秋軍医大尉
捜索第7連隊(旭川):西川勝雄少佐 第7師団第3野戦病院:青野茂軍医大尉
工兵第7連隊(旭川):中村松寿少佐 第7師団第4野戦病院:鈴木鉄太郎軍医大尉
輜重兵第7連隊(旭川):寺尾明中佐 第7師団病馬廠:岩上雄三郎獣医中尉
第7師団通信隊:山根福重少佐 第7師団防疫給水部:太田藤市郎軍医少佐

編成地:弘前 通称号/略称:杉
東北地方出身者から構成された。編成時の所属歩兵連隊は歩兵第5連隊・歩兵第17連隊・歩兵第31連隊・
歩兵第32連隊。 初代師団長は台湾総督府幕僚参謀長だった立見尚文中将。
明治35年)1月八甲田山における行軍訓練を行ったが、
この時死者199名という惨事を起こしている。
昭和16年)9月19日、第8師団は第25師団とともに第20軍の戦闘序列に編入されて、掖河に移駐した以後、
満州守備の 中核部隊として満州国内にて対ソ戦の訓練や抗日パルチザン掃討等の治安維持活動に従事
昭和19年)7月から、師団本隊はフィリピン戦線に投入された。
レイテ島の戦いに歩兵第5連隊基幹の高階支隊を増援として送ったが、支隊はアメリカ軍や抗日ゲリラによって
即座に殲滅された。なお、同支隊はレイテに投入された最後の陸上戦力である。師団主力はルソン島南部に
第41軍の 核として展開した。第8師団はルソン島の戦いでアメリカ軍や抗日ゲリラとの戦いでなす術なく
消耗していき、 全滅寸前で終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 本多政材 中将 |
昭和15年10月 |
長野県、昭和18)3月 第20軍司令官、昭和19)4月 第33軍司令官 |
| 横山静雄 中将 |
昭和17年6月 |
福岡県、満州の鶏寧県に駐屯、戦犯として逮捕され1953年12月釈放 |
| 横山静雄 中将 |
昭和20年3月 |
(第41軍司令官に移り、第8師団長事務取扱を兼ねる) |
最終上級:第20軍→第41軍
最終所属部隊
歩兵第5連隊(青森):高階於兎雄大佐(戦死) 第8師団通信隊:高橋良行少佐
歩兵第17連隊(秋田):藤重正従少将 第8師団第2野戦病院
歩兵第31連隊(弘前):小林島司少将 第8師団第4野戦病院
捜索第8連隊:箕田治六少佐 第8師団制毒隊:斎藤彰一大尉
野砲兵第8連隊:瀬戸口岩次郎大佐(戦死) 第8師団防疫給水部:三崎要一軍医少佐
代理:村上実中佐(戦死) 第8師団病馬廠:赤井哲治獣医少佐
工兵第8連隊:小原武大佐
輜重兵第8連隊:河田六次郎大佐
ルバング島に残置諜者として潜伏し30年を経て帰還した小野田寛郎少尉は、辞令の上では
第14方面軍司令部附であったが、同司令部情報部を通して第8師団参謀部に所属していた。
 |
編成地:金沢 通称号/略称:武 人員:25000名
明治31年)に新設された6個師団の一つで、北陸の富山・石川・福井各県の兵士で構成され衛戍地を
金沢として編成された師団である。第18師団(久留米市)と、陸軍内部でその精鋭さでは双璧といわれた。
昭和15年)8月から師団の衛戍地は満州となり、代替の常設師団として第52師団が編成された
またこの時、歩兵第36連隊を第28師団に転出させて三単位編制に改編された。
| 太平洋戦争開戦後は、師団は第3軍の指揮下衛戍地である満州に在り、昭和19年)7月に絶対国防圏の |
| 要石とされたサイパンが玉砕するなど戦局が緊迫化したことを受け、長勇参謀長の要望により、沖縄担当の |
| 第32軍戦闘序列に編入され、精鋭師団として防衛の中核を期待されていた。 |
| 大本営・第10方面軍・第32軍が台北で会議を開いたが、台北会議は要領の得ないまま散会となった。 |
| しかし、同年11月17日、台湾へ転出命令が下され、12月末に台湾に移転したものの、連合国軍は台湾を通り越して |
| 直接沖縄本島に上陸したため、戦うことなく同地で終戦を迎えた。 |
| 第9師団は武勲高い歴戦の師団であるが太平洋戦争時、一度も交戦することが無かった。 |
| 歴代師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 吉住良輔 中将 |
昭和12年)8月26日- |
三重県、昭和14年)12月、待命となり予備役 |
| 樋口季一郎 中将 |
(昭和14年)12月1日- |
兵庫県、昭和19年3月 第5方面軍司令官、 |
| 原 守 中将 |
昭和17年)8月1日 - |
広島県、昭和20年最後の陸軍次官 |
| 田坂八十八 中将 |
昭和20年)4月7日 - |
- |
最終上級:第3軍→第32軍
最終所属部隊
歩兵第7連隊(金沢):朝生平四郎大佐 工兵第9連隊:三池明少佐
歩兵第7連隊(金沢):朝生平四郎大佐 輜重兵第9連隊:鈴木幸一大佐
歩兵第35連隊(富山):三好喜平大佐 第9師団通信隊
山砲兵第9連隊:都村宗一大佐

編成地:姫路 通称号/略称:鉄
明治31年)10月に編成された。補充担任は姫路師管区で、主に兵庫だが、岡山・鳥取三県と島根県の一部も
徴兵区としている。開戦後には関東軍の直属兵団として、佳木斯に駐屯していた。満州国内にて対ソ戦の
訓練や抗日パルチザン掃討等の治安維持活動に従事していた。フィリピンルソン島に投入、
尚武集団としてバレテ峠、サラクサク峠で約半年に渡る持久戦を展開、衆寡敵せず壊滅状態となり、終戦を迎える。
| 歴代師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 篠塚義男 中将 |
昭和13年)6月- |
、昭和16年)6月には軍事参議官となる、昭和20年)9月17日に自決した |
| 佐々木到一 中将 |
昭和14年)9月- |
1945年7月召集され、第149師団長、シベリア抑留 |
| 十川次郎 中将 |
昭和16年)3月- |
昭和19年)1月、第6軍司令官に就任し、杭州で終戦を迎えた |
| 岡本保之 中将 |
昭和19年)1月- |
- |
最終上級:関東軍の直属兵団→第14方面軍 旧第十師団兵器部西倉庫:現姫路市立美術館:
最終所属部隊
歩兵第10連隊(岡山):岡山誠夫大佐 第10師団兵器勤務隊:村松忠雄大尉
歩兵第39連隊(姫路):永吉実展大佐 第10師団第1野戦病院:森金弥軍医少佐
歩兵第63連隊(松江):林葭一少佐 第10師団第2野戦病院:岸本貞夫軍医大尉
捜索第10連隊:鈴木重忠少佐 第10師団第4野戦病院:古川喜四郎軍医大尉
野砲兵第10連隊:多勢清作大佐 第10師団制毒隊:江西煥少佐
工兵第10連隊:杉藤民信少佐 第10師団防疫給水部:大木一雄軍医少佐
輜重兵第10連隊:相沢光二郎少佐 第10師団病馬廠:尾郷幹夫獣医大尉
第10師団通信隊:山下陽之助少佐

編成地:善通寺 通称号/略称:錦 所属軍:第5軍- 最終地:四国 (一部はグアム)
日清戦争後に、新設された6個師団の一つ。徴兵区は四国四県で、補充は善通寺師管区が担当した。
開戦後には、第5軍の指揮下密山に駐屯していた。満州国内にて対ソ戦の訓練や抗日パルチザン掃討等の
治安維持活動に従事した。昭和19年)2月、歩兵第12連隊と第43連隊、山砲兵第11連隊の各第3大隊が、
第1師団の一部と共に第6派遣隊として抽出され、グアム島に送られた。この第6派遣隊は同年6月に
独立混成第10連隊(通称号:備17584部隊)に改編され、グアムの戦いで玉砕した。
昭和20年)4月、師団主力は本土防衛の為四国に移駐し、同地で終戦を迎える。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 乃木希典中将 |
明治31年10月 - |
日露戦争に乃木希典大将率いる第3軍に編入され旅順攻略戦に当たる。 |
| 渡久雄 中将 |
昭和13年7月 - |
東京都、昭和13年12月病に罹り、翌年1月、密山で死去 |
| 内藤正一 中将 |
昭和14年1月 - |
- |
| 牛島満 中将 |
昭和14年12月- |
鹿児島県、沖縄戦において、第32軍を指揮し、自決した。 大将 |
| 鷹森孝 中将 |
昭和16年10月- |
三重県、昭和20年)4月、第12軍司令官に就任し、華北で終戦 |
| 大野広一 中将 |
昭和20年4月- |
- |
最終上級:第5軍
最終所属部隊
歩兵第12連隊(丸亀):原田喜代蔵大佐 輜重兵第11連隊:中島秀次大佐
歩兵第43連隊(徳島):多田金治大佐 第11師団通信隊:三宅悌吉大尉
歩兵第44連隊(高知):坂本俊馬大佐 第11師団制毒隊:稲垣庄平大尉
騎兵第11連隊:長谷川詮治中佐 第11師団野戦病院:高橋三郎軍医少佐
山砲兵第11連隊:小幡実大佐 第11師団防疫給水部:伊藤正彦軍医少佐
工兵第11連隊:岩本清大佐 第11師団病馬廠:佃正光大尉

編成地:小倉 通称号/略称:剣 所属軍:第3軍-第10方面軍 最終地:台湾西部 人員:25000名
日清戦争後に新設された6個師団の一つであり、1898年(明治31年)に、小倉町付近に設置され、所属の兵士は
主に 北部九州方面出身者からなる。戦前の1940年(昭和15年)7月に師団の衛戍地が満州に変わり、
第3軍の指揮下東寧に駐屯、 開戦後も満州国内にて対ソ戦の訓練や抗日パルチザン掃討等の
治安維持活動に従事していた。
昭和19年台湾派遣が決まり、第10方面軍戦闘序列に編入、新竹に在って台湾西部方面の警備に当たったが
連合国軍は台湾を通り越して直接沖縄本島に上陸したため、戦うことなく陣地構築中に同地で終戦を迎えた。
| 歴代師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 河辺正三 中将 |
昭和15年3月 - |
昭和19年)12月1日 中部軍司令官 陸軍大将 |
| 笠原幸雄 中将 |
昭和16年3月- |
支那派遣軍第6方面軍第11軍司令官 |
| 沼田多稼蔵 中将 |
昭和17年8月 - |
昭和18年)10月、第2方面軍参謀長、戦犯で重労働7年の判決 |
| 人見秀三 中将 |
昭和18年10月 |
- |
最終上級:第3軍→第10方面軍
最終所属部隊(戦前)
師団司令部(久留米):人見秀三中将 輜重兵第18連隊(久留米):宮川鶴松大佐
歩兵第24連隊(福岡):菊池三郎大佐 第12師団通信隊:猪原豊志大尉
歩兵第46連隊(大村):山根五郎大佐 第12師団兵器勤務隊:石橋九二七少佐
歩兵第48連隊(久留米):田中亮吉大佐 第12師団制毒隊:石川幾平大尉
野砲兵第24連隊(久留米):小倉三郎大佐 第12師団病馬廠:古河清獣医少佐
兵第18連隊(久留米):緒方武二少佐
 |
編成地:高田/仙台 通称号/略称:鏡 所属軍:天皇直隷/支那派遣軍 最終地:湖南省長沙
| 日露戦争中の1905年(明治38年)と、日中戦争勃発後の1937年(昭和12年)に編成された。 |
| 第二次編成 |
| 第13師団も、1937年(昭和12年)9月10日に留守第2師団の担当で復活し、上海派遣軍司令官松井石根大将の |
| 要請により、第9師団および第101師団とともに第二次上海事変の増援軍として上海戦線に赴いた。 |
| 太平洋戦争開戦後も第11軍隷下華中に在り、1944年には大陸打通作戦第二段の湘桂作戦に参加して広西省に進攻、 |
| 全県を攻略し、11月1日には桂林第2・第3飛行場を占領した。作戦終了後は第11軍司令部の置かれた柳州の |
| 西側の宜山方面の警備を担当した。なお南側の南寧方面は第3師団、北東側の桂林方面は第58師団が担当した。 |
| 1945年(昭和20年)になると戦局の変化から広西省方面の日本軍は撤退を開始、4月18日に第3師団とともに |
| 支那派遣軍直轄師団となり、南京方面に向けて移動中湖南省長沙で終戦を迎えた。 |
| 師団長名 |
補職日 |
その後の履歴 |
| 内山英太郎 中将 |
1940年9月 |
|
| 赤鹿理 中将 |
1942年8月 |
|
| 吉田峯太郎 中将 |
1945年1月 |
|
| 参謀長:中村従吉大佐 参謀:鎌沢到良少佐 |
| 最終上級:天皇直隷/支那派遣軍 |
| 最終所属部隊 |
|
歩兵第65連隊(会津若松):服部卓四郎大佐 |
第13師団衛生隊:橋本匡中佐 |
|
歩兵第104連隊(仙台):野口義男大佐 |
第13師団第1野戦病院:藤井清士軍医少佐 |
|
歩兵第116連隊(新発田):岩下栄一大佐 |
第13師団第2野戦病院:中山恵夫軍医少佐 |
|
山砲兵第19連隊:石浜勲大佐 |
第13師団第4野戦病院:山田暢雄軍医少佐 |
|
工兵第13連隊:石川省三大佐 |
第13師団病馬廠:増田健治獣医大尉 |
|
輜重兵第13連隊:田原親雄大佐 |
|
第13師団通信隊:大薗広志少佐 |

編成地:宇都宮 通称号/略称:照 所属軍:関東軍第3軍- 最終地:パラオ諸島
明治38年)6月13日 - 福岡県小倉に第14師団が結成され、大阪歩兵第53連隊、善通寺歩兵第54連隊、
廣島歩兵第55連隊、 熊本歩兵第56連隊がその隷下となる。8月に乃木希典大将の指揮する関東軍第3軍の
隷下に入り満州遼東半島警備の任に就く。
昭和18年)に大本営が策定した絶対国防圏の防衛のため満州駐剳師団が南方へ転用されることとなり、
師団は パラオ諸島へ向かった。師団は主力をパラオ本島に、歩兵第2連隊(およびその配下に編入された
歩兵第15連隊第3大隊)をペリリュー島に、歩兵第59連隊第1大隊をアンガウル島に配備した。
| 歴代師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 喜多誠一 中将 |
昭和15年3月 - |
昭和19年9月満州国敦化第1方面軍司令官に就任、陸軍大将 |
| 川並密 中将 |
昭和16年10月- |
昭和19年7月、第44師団長となり、昭和20年3月、通信兵監 終戦 |
| 野田謙吾 中将 |
昭和17年12月- |
昭和20年)3月、陸軍機甲本部長、第51軍司令官となり土浦で終戦 |
| 井上貞衛 中将 |
(昭和18年10月- |
パラオ諸島方面の守備を担当、戦犯裁判で終身刑に減刑 |
参謀長:多田督知大佐 参謀:泉莱三郎大佐、中川廉大佐、矢島俊彦中佐 軍医部長:山田勲軍医中佐
高級副官:川又宗一少佐 兵器部長:石井勇之大佐 経理部長:山本憲一主計中佐
最終所属部隊(戦前)
歩兵第2連隊(水戸):中川州男大佐(戦死後中将) 第14師団経理勤務部:岡林直樹主計大佐
歩兵第15連隊(高崎):福井義介大佐 第14師団野戦病院:羽田野義夫軍医大佐
歩兵第59連隊(宇都宮):江口八郎大佐 第14師団防疫給水部:鈴木泰軍医大尉
第14師団戦車隊:天野国臣大尉 第14師団編合
第14師団通信隊:平原辰雄大尉 第23野戦飛行場設定隊
第14師団兵器勤務隊 第57兵站地区隊本部:長谷川長大佐
独立自動車第42大隊:住田徳雄少佐

編成地:豊橋・京都 通称号/略称:祭 所属軍:第15軍 最終地:ビルマ 25000名/15000名戦死
日露戦争中の1905年(明治38年)と、日中戦争勃発後の1938年(昭和13年)に編成された
第15師団は1905年(明治38年)4月1日に愛知県豊橋市で編成され、日露戦争後講和条約で認められた
朝鮮半島の警備に従事する。大正14年)に加藤高明内閣で行われた所謂「宇垣軍縮」によって4個師団の
廃止が決まり、 第15師団も第13・第17・第18師団と共に廃止された。日中戦争が起こると1925年(大正14年)に
廃止された師団は悉く復活し、 第15師団も第26師団に引き続き三単位師団として再度編成された。
師団は1938年(昭和13年)4月4日に留守第16師団の担当で編成され、中国大陸に渡り日本占領地の
治安維持にあたった。その後、1943年(昭和18年)6月にはビルマに在った第15軍に編入されインパール作戦に
参加した。インパール作戦では作戦開始時に1万5000名を越えた将兵の半数を失う結果となった。
1945年(昭和20年)8月タイに転進し同地で終戦を迎える。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 酒井直次 中将 |
昭和16年8月- |
東京、昭和17年)5月28日、乗馬が地雷を踏み戦死する 庄内藩主の末裔 |
| 山内正文 中将 |
昭和17年6月- |
上官である牟田口廉也に忌避され、昭和19年6月師団長を解任され参謀本部付 |
| 柴田夘一 中将 |
昭和19年6月- |
福岡、昭和20年)2月に待命となり、熊本陸軍予備士官学校長 |
| 山本清衛 少将 |
昭和20年2月 |
高知県、陸軍中将に進みイラワジ会戦で苦戦を強いられ、重傷を受けた。 |
| 渡左近 中将 |
昭和20年7月 |
- |
参謀長:佐孝俊幸大佐 参謀:今岡久夫中佐、山中雅太少佐、菅野周男少佐 高級副官:北村将臣少佐
兵器部長:檜垣克雄中佐 経理部長:坂田輝一主計大佐 軍医部長:岸本春栄軍医大佐
最終所属部隊
歩兵第51連隊(京都):上田孝中佐 第15師団兵器勤務隊:石井孝晴大尉
歩兵第67連隊(敦賀):瀧口一郎大佐 第15師団衛生隊:古北光太郎少佐
歩兵第60連隊(京都):北部邦雄大佐 第15師団第1野戦病院:弘中忠男少佐
野砲兵第21連隊:藤岡勇大佐 第15師団第2野戦病院:網谷郁少佐
工兵第15連隊:千葉磨少佐 第15師団病馬廠:瀬川忠直大尉
輜重兵第15連隊:小川義弘中佐 第15師団通信隊:福永哲郎少佐

編成地:京都 通称号/略称:垣 所属軍:14軍 最終地:レイテ 25000名
明治38年)7月18日に京都で編成された大日本帝国陸軍の師団である。
第16師団の他、1905年(明治38年)4月1日に第13師団と第15師団が、同年7月6日に第14師団が創設された。
昭和16年11月6日に第14軍戦闘序列に編入され、緒戦のフィリピン攻略に参戦し、マニラ陥落後フィリピンに
駐屯した。レイテ島に上陸し、大本営はレイテ島での決戦を予定したが第16師団は壊滅した。当初13,000名で
臨んだレイテ決戦も生還者は僅か620名で、3人の連隊長が戦死しており、師団長牧野四郎中将も自決
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
石原莞爾 中将 |
昭和14年8月- |
満州事変を成功させた首謀者、開戦前、東條英機との対立から予備役 |
| |
森岡皐 中将 |
昭和16年3月- |
- |
| |
大場四平 中将 |
昭和17年8月- |
宮城県、昭和19年東京湾要塞司令官、 |
| |
牧野四郎 中将 |
昭和19年3月- |
鹿児島県、昭和20年)8月 比島レイテ島にて師団壊滅の責任を取り自決 |
参謀長:松岡賢一 大佐(陸士33期):1944年6月 - 終戦) 作戦参謀:三町進 少佐(陸士40期)
情報参謀:宮田健二 中佐(陸士40期) 後方参謀:北川衛 少佐(陸士47期)
高級副官:中島金右衛門 少佐 軍医部長:内藤勝樹 軍医大佐
最終所属部隊
歩兵第9連隊(京都):神谷保孝 大佐 第16師団通信隊:渡辺竹司 大尉
歩兵第20連隊(福知山):鉾田慶次郎 大佐 第16師団兵器勤務隊:田頭好夫 大尉
後任連隊長:山森友吉 大佐 第16師団衛生隊:辻忠三郎 大佐
歩兵第33連隊(津):鈴木辰之助 大佐 第16師団第1野戦病院:安藤棋尾夫 少佐
捜索第16連隊:日比知 大佐 第16師団第2野戦病院:糸井八寿治 少佐
野砲兵第22連隊:近藤喜名男 大佐 第16師団第4野戦病院:畫間和男 少佐
工兵第16連隊:加藤善元 中佐 第16師団病馬廠:森田栄二郎 少佐
輜重兵第16連隊:牧野文一 大佐 第16師団防疫給水部:佐藤幸雄 中佐

編成地:岡山・姫路 通称号/略称:月 所属軍:中支那派遣軍-第8方面軍 最終地:ラバウル
| 日中戦争勃発後の1938年(昭和13年)に編成された 岡山・姫路 |
| 大正14年)に廃止された師団は悉く復活し、第17師団も第26師団に引き続き三単位師団として再度編成された。 |
| 昭和13年)4月4日に留守第10師団の担当で編成され、中国大陸に渡り中支那派遣軍戦闘序列に編入、 |
| 一部部隊が武漢作戦に参戦する。昭和18年)9月に南方に転用され、ニューブリテン島に渡る。 |
| 第8方面軍隷下に移った師団は同島中心地のラバウルやツルブにて米軍の攻撃に耐えた持久戦の中終戦となる |
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
広野太吉 中将 |
昭和13年7月 - |
- |
| |
平林盛人 中将 |
昭和15年8月 - |
長野県、長野県松本市の第13代市長、昭和20年長野師管区司令官 |
| |
酒井 康 中将 |
昭和17年12月- |
東京府、ニューブリテン島ラバウルで米軍と交戦し、持久戦の最中終戦を迎える。 |
最終所属部隊
歩兵第53連隊(鳥取):大島廉治大佐 野砲兵第23連隊:菅井房吉大佐
歩兵第54連隊(岡山):丸山巖大佐 工兵第17連隊:糸川僖一中佐
混成第2連隊:坂本康一大佐 輜重兵第17連隊:今村武雄大佐
混成第6連隊:永井元大佐 第17師団通信隊:繁田武一郎大尉

編成地:久留米 通称号/略称:菊 所属軍:第25軍 最終地:ビルマ 人員:25000~30000名
大正14年第18師団も第13・第15・第17師団と共に廃止された。
昭和12年)9月9日に、留守第12師団の担当で、四単位編制の特設師団として再度編成された
昭和16年)南方に転用、11月6日第25軍(司令官:山下奉文中将)戦闘序列に編入され、マレー作戦・
シンガポール攻略戦に従事する。陥落後は飯田祥二郎中将の第15軍に移り、ビルマ攻略戦に参戦する。
師団の指揮下を離れフィリピン戦・ガダルカナル戦に参戦した。その後川口支隊は、
昭和18年)3月に第31師団に転用、第18師団は三単位編制に改編された。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 百武晴吉 中将 |
昭和15年2月 - |
佐賀県、昭和19年脳出血で倒れ、昭和20年、第8方面軍司令部付となり終戦 |
| 牟田口廉也 中将 |
昭和16年4月- |
佐賀県、昭和18年第15軍司令官、インパール作戦を指揮 |
| 田中新一 中将 |
昭和18年3月- |
新潟県、昭和20年プノンペン近くで飛行機が墜落し重傷 |
| 中永太郎 中将 |
昭和19年9月 |
北海道、終戦をビルマ・チャイトで迎えた。 |
最終司令部構成 参謀長:白崎嘉明 大佐 作戦参謀:三橋泰夫 少佐 参謀:鈴木重直 少佐、正宝治平 少佐
高級副官:猪瀬重雄 少佐 軍医部長:大橋要人 軍医大佐
最終所属部隊
歩兵第55連隊(大村):山崎四郎 大佐 第18師団第1通信隊:山崎達男 大尉
歩兵第56連隊(久留米):佐藤又三郎 大佐 第18師団第2通信隊:土生洋平 少佐
歩兵第114連隊(福岡):大塚宏 大佐 第18師団衛生隊:小倉弘成 中佐
山砲兵第18連隊:江口太郎 大佐 第18師団第1野戦病院:鈴木行雄 少佐
後任連隊長:松川信正 大佐 第18師団第2野戦病院:荻生謙修 少佐
工兵第12連隊:井上義一郎 中佐 第18師団第3野戦病院:佐藤進 少佐
輜重兵第12連隊:水谷虎吉 中佐 第18師団第4野戦病院:原田大六 少佐

編成地:朝鮮・羅南 通称号/略称:虎 所属軍:第14方面軍 最終地:フィリピン
大正4年)12月24日に編成が決まった。昭和6年)、満州事変に第19師団から抽出した兵力を基に
混成第38連隊 を編成して派遣し、同連隊は第20師団隷下で長春・ハルビンで戦闘を行い
その後満州に駐屯する。
昭和16年)7月、動員下令となるが直ぐには戦地へ行かず、羅南にて訓練を行っていた。
昭和18年)5月、師団隷下の歩兵第74連隊が新設の第30師団隷下に移る。
昭和19年)12月から師団は第14方面軍隷下に移りフィリピン・ルソン島に渡りアメリカ軍と交戦する。
山岳地帯で持久戦を行っている最中終戦を迎える。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 尾高亀蔵 中将 |
昭和12年3月- |
佐賀県、1941年6月、予備役に編入された。 |
| 波田重一 中将 |
昭和13年11月 |
広島県、昭和15年)9月、第5軍司令官、昭和16年)12月、予備役 |
| 上月良夫 中将 |
昭和15年9月- |
熊本県、昭和17年 第2軍司令官、昭和19年 第11軍司令官 |
| 尾崎義春 中将 |
昭和17年7月 |
北海道、北朝鮮からフィリピンへと転戦。リンガエン湾・プロム山の戦闘 |
最終所属部隊
歩兵第73連隊(羅南):田中実少将 輜重兵第19連隊:長谷川政男大佐
歩兵第75連隊(会寧):名越透大佐 第19師団通信隊:市村信義少佐
歩兵第76連隊(羅南):古見政八郎大佐 第19師団第1野戦病院:曽田義雄軍医少佐
捜索第19連隊:秋山太郎中佐 第19師団第4野戦病院:加藤正司軍医大尉
山砲兵第25連隊:谷口暚之助大佐 第19師団防疫給水部:永井啓軍医大尉
工兵第19連隊:竹内忠中佐 第19師団病馬廠

編成地:朝鮮・瀧山 通称号/略称:朝 所属軍:18軍 最終地:ニューギニア 人員:25000
| 日露戦争に勝利し朝鮮半島を獲得した日本は、半島警備の為に2個師団増設が計画され、大正4年12月24日に |
| 編成が決まった。同時に編成されたのが第19師団である。 |
| 1941年(昭和16年)7月、動員下令となるが直ぐには戦地へ行かず、京城にて引き続き訓練を行っていた。 |
| 1942年(昭和17年)に野砲から山砲への改編が行われたことにより、満州以南への派遣が決定的となった。 |
| なお、1943年(昭和18年)9月、師団隷下の歩兵第77連隊が第30師団隷下に移る。 |
| 1943年(昭和18年)から師団はニューギニア戦線に動員され、同地でオーストラリア軍と交戦し、終戦を迎える。 |
| ニューギニアには25,000名の兵力で臨んだものの敵軍との交戦やマラリアによって多大な損害を被り、 |
| 還し復員したのは僅か1,711名であった |
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 牛島実常 中将 |
昭和13年6月- |
福岡県、、1941年1月、予備役に編入された |
| 七田一郎 中将 |
昭和14年9月- |
駐蒙軍司令官、第2軍司令官、、陸軍科学学校長、兼陸軍戸山学校長 |
| 永津佐比重 中将 |
昭和16年4月- |
愛知県、第58軍司令官に就任。済州島にて終戦 |
| 青木重誠 中将 |
昭和17年8月- |
石川県、1943年6月、マラリアにより戦病死 |
| 片桐茂 中将 |
昭和18年7月- |
戦死 |
| 中井増太郎 将 |
昭和19年5月- |
- |
| 中井増太郎中将 |
昭和20年4月- |
- |
最終所属部隊
1944年(昭和19年)3月14日大陸命第963号を以って第18軍戦闘序列に編入される。
・第20歩兵団:三宅貞彦少将
・歩兵第78連隊(龍山):松本松次郎少将
・歩兵第79連隊(龍山):林田金城少将
・歩兵第79連隊(龍山):林田金城少将
・野砲兵第26連隊:佐伯縄四郎大佐 ・工兵第20連隊:小泉義純中佐
・輜重兵第20連隊:井場通敏大佐 ・第20師団通信隊:野瀬弘行大尉
・第20師団衛生隊:江本烈大佐 ・第20師団第1野戦病院:平賀強少佐
・第20師団第2野戦病院:中江皞三少佐 ・第20師団第4野戦病院:江田不二夫少佐
・第20師団防疫給水部:芦田二三男少佐 ・第20師団病馬廠:峯本文三郎大尉
 |
編成地:金沢 通称号/略称:討 所属軍:南方軍-印度支那駐屯軍 最終地:ハノイ 人員:
昭和13年)4月4日に第15・第17・第22・第23師団とともに編成された歩兵三個連隊編制師団である。
第21師団は、同年7月15日に編成完結すると北支那方面軍隷下で占領地の徐州の警備に当る。
昭和14年)2月の蘇北作戦や1941年(昭和16年)5月の中原会戦に参加した。
同年11月から北部仏印に転用され南方軍に編入される。隷下部隊から抽出した永野支隊が
第二次バターン半島攻略戦に参加、
師団は1943年(昭和18年)12月から印度支那駐屯軍隷下で北部仏印の警備に当る。
昭和20年)3月に明号作戦に参加し、同年8月にハノイで終戦を迎える。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 鷲津鈆平 中将 |
昭和13年7月- |
愛知県、昭和15年)9月、第4軍司令官となり、名古屋師管区司令官 |
| 田中久一 中将 |
昭和15年9月- |
兵庫県、中国大陸を転戦、戦犯指名を受け、同年10月9日に死刑判決 |
| 三国直福 中将 |
昭和18年3月 - |
- |
| 参謀長 |
- |
- |
| 千葉熊治 大佐 |
(昭和13年7月 |
- |
| 村田定雄 大佐 |
昭和15年3月 |
- |
| 小川泰三郎 大佐 |
(昭和16年10月 |
- |
| 宍戸清次郎 大佐 |
昭和20年1月 |
- |
高級副官:中島忠雄 中佐:1939年(昭和14年)8月1日 - 三根敏雄 中佐:1942年(昭和17年)8月1日 -
最終所属部隊
第21歩兵団:第21歩兵団司令部
・歩兵第62連隊(富山)
・歩兵第82連隊(富山
・歩兵第83連隊(金沢)
山砲兵第51連隊 第21師団通信隊 第21師団防疫給水部
工兵第21連隊 第21師団兵器勤務隊
輜重兵第21連隊 第21師団第1野戦病院 第21師団第2野戦病院
第21師団捜索隊 第21師団病馬廠
第21師団衛生隊
昭和16年:南方軍戦闘序列 昭和19年:第38軍隷下に移る

編成地:宇都宮 通称号/略称:原 所属軍:第23軍 最終地:バンコク
第22師団は、日中戦争勃発後の1938年(昭和13年)4月4日に、占領地の警備や治安維持を目的として、
第15・第17・第21・第23師団と共に編成された歩兵三個連隊制師団である。
編成は留守第14師団、補充は留守第2師団が担当した。
編成完結後中国大陸に派遣され中支那派遣軍隷下で武漢作戦に参戦し、その後第13軍隷下に移る。
第13軍の下では杭州の警備に当り、中国の第3戦区軍を相手に1940年(昭和15年)に江南作戦、
昭和16年)3月に太湖西方作戦や、浙東・皖浙で歴戦する。
昭和17年5月の浙贛作戦では衢県・広豊・広信を占領する。昭和18年に金華を占領し同地の警備に移る。
昭和19年2月に第23軍隷下に移ることが決まり香港に向かうが、移動中に歩兵第86連隊等を乗せた輸送船が
米軍の攻撃により撃沈される。香港に移った師団は大陸打通作戦の一環である湘桂作戦に従事する。
昭和20年から仏印に転用され明号作戦つづいてビルマ戦線に投入される。師団はタイの
バンコクで終戦を迎える。
師団の将兵には終戦後にベトミン軍に参加し対仏独立戦争で戦った者が多くいる。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 土橋一次 中将 |
昭和13年7月- |
鹿児島県、昭和18年)4月、予備役に編入 |
| 太田勝海 中将 |
昭和16年3月 |
- |
| 大城戸三治 中将 |
昭和17年3月- |
- |
| 磯田三郎 中将 |
昭和17年11月- |
昭和19年、南方軍遊撃隊司令官。昭和20年)1月、南方軍総司令部付 |
| 平田正判 中将 |
昭和19年1月 |
- |
| 参謀長 |
- |
- |
| 馬場英夫 大佐 |
昭和13年7月 |
- |
| 山脇正男 大佐 |
昭和15年3月 |
- |
| 宮本清一 少将 |
昭和18年1月 |
- |
| 堀田吉明 大佐 |
昭和18年12月 |
- |
兵器部長:羽佐田良吉 大佐:1940年(昭和15年)3月9日 -戸倉吉良 中佐:1942年(昭和17年)3月8日 -
隷下部隊
師団司令部
・第22歩兵団 第22歩兵団司令部
・歩兵第84連隊:深野時之助大佐
・歩兵第85連隊:能勢潤三大佐
・歩兵第86連隊:中川紀士郎大佐
・山砲兵第52連隊 ・工兵第22連隊 ・輜重兵第22連隊 ・騎兵第22大隊
・第22師団衛生隊 ・第22師団通信隊 ・第22師団兵器勤務隊 ・第22師団第1野戦病院
・第22師団第2野戦病院 ・第22師団病馬廠
師団には始め師団捜索隊が配備されていたが、昭和14年3月を以って騎兵第22大隊に改組され
上田巌中佐が大隊長に就任する。昭和18年11月24日を以って第22歩兵団は復員し各歩兵連隊は
師団直轄となる。
主な戦歴
日中戦争 杭州警備 大陸打通作戦で南寧を再占領 ビルマの戦い

編成地:熊本 通称号/略称:旭 所属軍:第14方面軍 最終地:ルソン島
昭和13年)4月に、第15・第17・第21・第22師団と共に、中国戦線の治安維持を目的に熊本で編成された
歩兵三個連隊編制師団である。
昭和14年)5月11日に満州と外蒙古の国境地帯であるノモンハンでソ連・モンゴルとの国境紛争が起こると、
日本側の主力部隊として実戦を経験することになった。
師団長の小松原道太郎中将は、関東軍の方針によって、まず師団の一部兵力からなる「東支隊」
(支隊長:第23師団捜索隊長の東八百蔵中佐)を編成して派遣した。7月初旬の総攻撃失敗で安岡支隊は
大打撃を受け、第23師団は1万1958名にも及ぶ死傷者を出した。悲劇の「小松原兵団」と呼ばれる。
太平洋戦争勃発後も第8国境守備隊と共に国境付近の警備を担任していた。
太平洋方面の戦局悪化から、1944年(昭和19年)になって師団の台湾派遣が決まった。台湾へ移動中にさらに
派遣先がフィリピンに変わり、同年12月にフィリピンのルソン島へ進出して第14方面軍隷下に加わった。
昭和20年)1月からのルソン島の戦いではリンガエン湾沿岸に配備され、上陸するアメリカ軍と交戦したが
3月頃から飢餓状態に陥り、ボコド陣地に後退して防御戦闘の最中に終戦を迎える。
ルソン島の戦闘に参加した将兵は現地補充を含め29,636名であったが、生還したのは5,128名に過ぎない。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 小松原道太郎中将 |
昭和137月 |
神奈川県、1940年1月に予備役に編入、同年10月に病死 |
| 井上政吉 中将 |
昭和14年11月 |
京都府、最後の陸軍戸山学校長として終戦 |
| 西原貫治 中将 |
昭和16年3月 |
広島県、第57軍司令官として鹿児島県財部で本土決戦に備えていた |
| 及川源七 中将 |
昭和17年11月 |
- |
| 西山福太郎 中将 |
昭和19年1月 |
- |
参謀長 高級副官
松田巌 大佐:昭和16年10月15日 - 花啓一 中佐:昭和15年)12月2日 -
高津利光 大佐:昭和17年8月1日 - 三好勇 少佐:
吉川浩 大佐:昭和19年3月1日 -
高津利光 大佐:昭和19年11月27日 -
最終所属部隊
歩兵第64連隊(熊本):中島正清大佐 第23師団通信隊:奥川弘毅大尉
歩兵第71連隊(鹿児島):二木栄蔵大佐 第23師団兵器勤務隊:本井秋太大尉
歩兵第72連隊(都城):中島嘉樹大佐 第23師団衛生隊:西田喜春大尉
捜索第23連隊:久保田尚平中佐 第23師団第1野戦病院:塩田浩政軍医大尉
野砲兵第17連隊:吉富徳三少将 第23師団第4野戦病院:花牟礼孝二郎軍医大尉
工兵第23連隊:水野捷海中佐 第23師団防疫給水部:谷口良碩軍医少佐
独立野砲兵第13大隊:宇田豊作少佐 第23師団病馬廠:西川春雄獣医大尉

編成地:満州国ハルピン 通称号/略称:山 所属軍:第32軍予備 軍 最終地:サイパン島-沖縄
昭和14年)10月に満州のハルビンで編成され第5軍隷下で国境警備に当る。
昭和19年)2月に歩兵第22・第32連隊、野砲兵第42連隊の各1個大隊と工兵第24連隊の1個中隊を主力とした
第7派遣隊を編成して、メレヨン島に派遣した。第7派遣隊は4月に無事にメレヨン島に上陸し、6月に
南洋第5支隊とともに 独立混成第50旅団に改編された。メレヨン島に連合軍の上陸は無かったが空襲は激しく、
さらには補給途絶による飢餓が著しく、守備隊の3/4は終戦までに死亡した。歩兵第89連隊の1個大隊も
第1派遣隊編成のために同様に抽出され、 最終的にサイパン島へと上陸。その後、第1派遣隊は
独立混成第47旅団に改編された。第24歩兵団司令部も、満州警備の 独立守備歩兵大隊3個を改編した
第9派遣隊の本部となり、ヤップ島に向かった。しかし、途中で輸送船が撃沈され、サイパン島に上陸した。
第9派遣隊の残存兵力は独立歩兵第318大隊に再編されて、これも独立混成第47旅団に編入され、
サイパンの戦いで玉砕した。昭和20年)4月にアメリカ軍が上陸し沖縄戦が始まると、第32軍の総予備として控え、
4月23日に戦闘加入し首里北西において米軍と交戦する。5月4日に総反撃に出たが、歩兵第32連隊第1大隊が
棚原高地を 占領した。以外には戦果を挙げられず、攻撃は失敗した。その後は後退しつつ防御したが、
6月初旬の段階で 師団固有の練度の高い人員は3000人以下に減少し、配属部隊を合わせて
師団兵力1万2千人だった。 6月20日に師団長の雨宮巽中将が自活自戦を指示して師団の組織的戦闘を
終え、 師団長・参謀長が自決した。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 黒岩義勝中将 |
昭和14年10月 |
高知県、予備役編入となり、昭和20年高知地区司令官に就任し終戦 |
| 根本博 中将 |
(昭和16年3月 |
福島県、昭和19年第3軍司令官、戦後台湾政府の対中共作戦に協力 |
| 雨宮巽 中将 |
昭和19年2月 |
沖縄戦で自決 |
歴代参謀長
吉武秀人 大佐:昭和16年)4月28日 -
白崎嘉明 中佐:昭和17年)2月9日 -
木谷美雄 大佐:昭和19年)5月16日 -(沖縄戦で自決)
最終所属部隊
歩兵第22連隊(松山):吉田勝大佐 第24師団通信隊:保科清一郎大尉
歩兵第32連隊(山形):北郷格郎大佐 第24師団防疫給水部:金井泰清少佐
歩兵第89連隊(旭川):金山均大佐 第24師団第1野戦病院:安井二郎少佐
捜索第24連隊:才田勇太郎少佐 第24師団第2野戦病院:小池勇助少佐
野砲兵第42連隊:西澤勇雄大佐 第24師団制毒隊:五十嵐正次郎大尉
工兵第24連隊:児玉昶光大佐 第24師団兵器勤務隊:田中信造大尉
輜重兵第24連隊:中村卯之助大佐 第24師団病馬廠:岩井吉五郎大尉

編成地:満州国東寧 通称号/略称:国 所属軍:第5軍 最終地:宮崎 小林
(昭和15年)7月に満州の東寧で編成され、林口に駐屯する。第5軍隷下で関東軍特種演習(関特演)に参加する。
昭和20年)3月に転用が決まり、本土決戦に備え宮崎県小林に移駐。連合軍と交戦することなく終戦を迎える。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 桑原四郎 中将 |
昭和15年8月 |
- |
| 赤柴八重蔵中将 |
昭和16年10月 |
新潟県、近衛第1師団長に発令。さらに第53軍司令官となり伊勢原で本土決戦に |
| 加藤怜三 中将 |
昭和18年10月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第14連隊(小倉):鎌浦留次大佐 第25師団通信隊:南口喜秋中尉
歩兵第40連隊(鳥取):愛甲立身大佐 第25師団兵器勤務隊:安田商一郎大尉
兵第70連隊(篠山):石川条吉大佐 第25師団衛生隊:河合好雄中佐
山砲兵第25連隊:原捷吉大佐 第25師団野戦病院:鳥山治正軍医少佐
工兵第25連隊:藤村忠明中佐
輜重兵第25連隊:新村理市大佐

編成地:華北 通称号/略称:泉 所属軍: 最終地:フィリピン レイテ
昭和12年)9月に満州の大同警備を目的に編成された。昭和13年)1月から駐蒙兵団隷下に編入される。
(昭和19年)7月にフィリピン戦線に転用され、乗船したヒ71船団で大損害を受けつつ、マニラに移駐する。
レイテ島の戦いに多号作戦の増援部隊として派遣されるが、輸送船団が揚陸途中で出航したため、
装備・物資の多くを失う。後続の補給船団も撃沈され、著しく戦力低下した状態で戦闘しなければならなくなった。
米軍と交戦し壊滅、師団長以下多数が戦死し、残存部隊はカンギポット山中で終戦を迎える。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
黒田重徳 中将 |
昭和14年8月- |
福岡県、、南方軍(総軍)の総参謀長、、第14方面軍司令官、A級戦犯 |
| |
矢野音三郎 中将 |
昭和16年6月- |
山口県、昭和17年)4月、陸軍公主嶺学校長、昭和18年)8月に予備役編入 |
| |
柴山兼四郎 中将 |
昭和17年4月 |
茨城県、陸軍次官、大本営兵站総監を兼務、戦犯容疑により拘留 |
| |
佐伯文郎 中将 |
昭和18年4月- |
宮城県、第2総軍により広島警備担任司令官に任命、戦犯容疑により逮捕 |
| |
山県栗花生 中将 |
昭和19年7月- |
山口県、レイテ決戦にて苦戦する中で戦死し、師団は壊滅した。 |
| |
栗栖猛夫 少将 |
昭和20年2月 |
山口県、第26師団長心得に就任。同年7月に戦死し陸軍中将 |
最終所属部隊
独立歩兵第11連隊(津):津田佃大佐 独立歩兵第12連隊(岐阜):
独立野砲兵第11連隊: 馬場喜重大佐 独立歩兵第13連隊(静岡):森岡信之丞大佐
輜重兵第26連隊:新村理市大佐 第26師団通信隊:内ヶ島芳男少佐
第26師団兵器勤務隊:山田清次郎大尉 第26師団野戦病院:武藤有一軍医少佐
第26師団病馬廠:吉田周一獣医少佐 工兵第26連隊:品川弥治中佐

編成地:北平 称号/略称:極 所属軍:第11軍-支那派遣軍 最終地:中国 江西省 南昌
日中戦争が勃発し支那駐屯軍が廃止された際、支那駐屯軍直轄部隊は支那駐屯混成旅団に改編され、
その後支那駐屯兵団と改称、さらに第27師団に改編された。
昭和13年)6月21日、第27師団の編制が下令され、同年7月4日の大陸命第133号により第11軍戦闘序列に編入、
7月25日に武漢作戦に投入される。作戦終了後は支那駐屯軍の衛戍地であった天津に戻り華北方面の警備
昭和18年)6月17日の大陸命第803号により満州に移駐、司令部を錦州に置き駐屯していたが、
師団は第12軍の支援を受け黄河を敵前渡河、5月9日には確山に至り、第一段の京漢陸路の打通に成功した。
打通成功後北進してきた第11軍部隊と合流し第二段の湘桂作戦に参加、第11軍が広西省方面に進攻した後は
第20軍隷下湖南省茶陵に在って、遂贛作戦では1945年(昭和20年)1月30日に江西省の遂川飛行場を占領する。
昭和20年)4月18日には再度支那派遣軍直轄師団となり広東から上海方面に向け移動中当時日本軍の
支配地域であった南昌に入ったところで終戦を迎える。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
冨永信政 中将 |
昭和15年12月- |
陸軍予科士官学校長、第19軍司令官、 アンボンで戦病死・陸軍大将 |
| |
原田熊吉 中将 |
昭和17年3月- |
大阪府、第55軍司令官 、戦後戦犯で絞首刑 |
| |
竹下義晴 中将 |
昭和17年11月- |
- |
| |
落合甚九郎少将 |
昭和19年5月 |
- |
| |
落合甚九郎中将 |
昭和19年6月 |
- |
参謀長:関根久太郎 大佐:1940年(昭和15年)10月23日 - 一色正雄 大佐:1944年(昭和19年)8月3日 - 終戦
最終所属部隊
支那駐屯歩兵第1連隊(佐倉):矢後孫二大佐 第27師団通信隊:鳳正文少佐
支那駐屯歩兵第2連隊(東京):井上進大佐 第27師団兵器勤務隊:鈴木浅之助中尉
支那駐屯歩兵第3連隊(甲府):森田庄作大佐 第27師団第1野戦病院:青柳良雄軍医少佐
山砲兵第27連隊:村上誠一大佐 第27師団第2野戦病院:紺谷信一軍医少佐
工兵第27連隊:橋本時夫中佐 第27師団第4野戦病院:林二郎軍医少佐
輜重兵第27連隊:原田不二太中佐

編成地:満州国 新京 通称号/略称:豊 所属軍:関東軍-第32軍 最終地:宮古島・石垣島方面
昭和15年)7月10日に関東軍直轄部隊として満州の新京で編成され、ハルピン・チチハルで警備に当り、
一貫して満州に駐屯していた。
昭和19年)頃から満州に駐留している部隊の南方への転用が始まる。第28師団の歩兵第36連隊は同年6月15日
に連合国軍がサイパンに上陸、絶対国防圏の要石であるサイパンの奪還のため派遣されるが、
サイパンの守備隊は玉砕し作戦中止となり師団へ復帰する。
師団主力は第32軍戦闘序列に編入、南西諸島に転用され、宮古島・石垣島方面の防衛を担当した。
この地域の部隊をまとめる「先島集団」が設けられ師団長は司令官に就任、連合国軍の先島諸島上陸に
備え態勢を整えていたが、連合国軍は宮古・石垣島を越え1945年(昭和20年)4月1日に直接沖縄本島に上陸し、
師団は交戦することなく終戦を迎える。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 石黒貞蔵 中将 |
昭和15年8月- |
第6軍司令官、第29軍司令官としてマレー半島に赴任し終戦を迎えた。 |
| 櫛淵?一 中将 |
昭和18年3月- |
東京都、第34軍司令官、終戦後シベリアに抑留 |
| 納見敏郎 中将 |
昭和20年1月 |
A級戦犯として納見の逮捕命令後、宮古島に渡り、同月13日に自決。 |
最終所属部隊
歩兵第3連隊(東京):衿土軍大佐 第28師団兵器修理所:藤本武輝大尉
歩兵第30連隊(高田):富沢国松大佐 第28師団病馬廠:保坂斯道獣医大尉
歩兵第36連隊(鯖江):田村権一大佐 第28師団第2野戦病院:三好祝二軍医大尉
騎兵第28連隊:上田巌大佐 第28師団第3野戦病院:横井忠男軍医大尉
山砲兵第28連隊:梶松二郎大佐 第28師団第4野戦病院:辻義春軍医少佐
兵第28連隊:外賀猶一大佐 第28師団防疫給水部:石塚政夫軍医少佐
輜重兵第28連隊:宮川正少佐 第28師団制毒訓練所:那須憲三少佐
第28師団通信隊:国武達雄少佐

編成地:名古屋 通称号/略称:雷 所属軍:関東軍-第31軍 最終地:グアム
1941年4月1日に新設され関東軍に編入し、戦略予備師団として遼陽に配備された。
1944年春、南方に転用され第31軍に編入。独立混成第48旅団と共に南部マリアナ地区集団を構成し、
グアム防衛に当たった。同年6月からアメリカ軍との戦闘を続けたが、7月28日に高品師団長が戦死し、
組織的な抵抗を終えた(グアムの戦い)。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 上村利道 中将 |
1941年4月- |
第5軍司令官、第36軍司令官として浦和にあって本土決戦に |
| 高品彪 中将 |
1943年10月 |
グアムの戦いにおいて米軍との激戦を続けたが、7月28日に戦死した |
最終所属部隊
歩兵第18連隊(豊橋):大橋彦四郎大佐 第29師団通信隊:須田保大尉
歩兵第38連隊(静岡):末長常太郎大佐 第29師団兵器勤務隊:亀井秀次中尉
歩兵第50連隊(松本):緒方敬志大佐 第29師団経理勤務部:水谷松男中佐
第29師団戦車隊:佐藤秀夫少佐 第29師団野戦病院:森本和雄中佐
第29師団輜重隊:洞下国吉中尉 第29師団防疫給水部:立村弘造少佐
第29師団海上輸送隊:藤井貞寿中佐

編成地:平壌 通称号/略称:豹 所属軍:第35軍 最終地:フィリピン・ミンダナオ島
1943年5月に新設された。1944年8月、南方に転用され第35軍に編入。フィリピン・ミンダナオ島守備を担当した。
レイテ島の戦いに投入され大きな損害を受け、さらにミンダナオ島の戦いでの
過酷な持久作戦を遂行し終戦を迎た
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 小林浅三郎 中将 |
1943年6月- |
兵庫県、防衛総参謀長に再任、支那派遣軍総参謀長に異動し南京で終戦 |
| 両角業作 中将 |
1944年3月- |
長野県、ミンダナオ島の戦いを遂行 |
最終所属部隊
歩兵第41連隊(福山):炭谷鷹義大佐 第30師団通信隊:村上一男少佐
歩兵第74連隊(咸興):根岸幹大佐 第30師団通信隊:村上一男少佐
歩兵第77連隊(平壌):新郷栄次大佐 第30師団衛生隊
捜索第30連隊:名波敏郎大佐 第30師団第1野戦病院:大重弥吉大尉
野砲兵第30連隊:大塚曻大佐 第30師団第2野戦病院
工兵第30連隊:大内維武大佐 第30師団第4野戦病院
輜重兵第30連隊:吉村繁次郎中佐 第30師団病馬廠:梶浦正市獣医大尉
第30師団防疫給水部:須賀木一軍医少佐
 |
編成地:タイ 通称号/略称:烈 所属軍:第15軍 最終地:ビルマ インパール
第31師団は、1943年(昭和18年)3月22日にタイのバンコクで、第18師団の川口支隊(歩兵第35旅団司令部及び
歩兵第124連隊)と、第13師団の歩兵第58連隊・第116師団の歩兵第138連隊・第40師団の山砲兵第40連隊を
基幹に編成され、直ちに第15軍戦闘序列に編入された。インパール作戦中に第15軍が
糧秣を供給しないことに抗議して独断で撤退したことで知られる。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 佐藤幸徳中将 |
昭和18年3月- |
山形県、インパール作戦において師団の独断退却 |
| 河田槌太郎中将 |
昭和19年7月 |
北海道、イラワジ会戦などで苦戦を強いられた。 |
| 歩兵団長 |
- |
- |
| 宮崎繁三郎少将 |
- |
岐阜県、陸軍中将任官、第31師団長代理、第54師団長 |
参謀長:加藤国治大佐
最終所属部隊
歩兵第58連隊(高田):稲毛譲大佐 山砲兵第31連隊:大矢部省三大佐
歩兵第124連隊(福岡):福沢定和大佐 工兵第31連隊:鈴木孝大佐
歩兵第138連隊(奈良):鳥飼恒男大佐 第31師団通信隊:西村七男少佐
輜重兵第31連隊:野中久治大佐

編成地:東京 通称号/略称:楓 所属軍:第12軍-14軍 最終地:ハルマヘラ島
日中戦争が泥沼化するなかで、占領地の警備や治安維持を目的として昭和14年2月に新設された師団の一つ
編成後第12軍隷下山西省に在って、ほかの治安師団と同様に1939年夏以降に行われたさまざまな
治安作戦に参加する。開戦後も第12軍隷下にあり山西省に駐屯していたが、1944年(昭和19年)4月に
フィリピン南部ミンダナオ島に駐屯することになり、第14軍に編入された。しかし、間もなく派遣先はハルマヘラ島
多数の兵員が海没するなどの損害を受けた。5月中旬にハルマヘラ島に上陸し、第2軍隷下連合国軍の上陸に備えた。
隣接するモロタイ島での戦闘が起きると一部を逆上陸部隊として派遣した。ハルマヘラ島には上陸が
無かったため、師団主力はハルマヘラ島の守備を固めつつ終戦を迎えた
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 木村兵太郎 中将 |
昭和14年3月- |
東京都、ビルマ方面軍司令官、大将、A級戦犯で絞首刑 |
| 井出鉄蔵 中将 |
昭和15年10月- |
- |
| 石井嘉穂 中将 |
昭和17年10月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第210連隊(甲府):松永英夫大佐 第32師団通信隊:加藤紫朗少佐
歩兵第211連隊(東京):三吉悌一中佐 第32師団兵器勤務隊:西村安一大尉
歩兵第212連隊(佐倉):土師正義中佐 第32師団衛生隊:木場茂大佐
野砲兵第32連隊:三田村佐一大佐 第32師団第1野戦病院:小菅俊平軍医少佐
工兵第32連隊:佐藤武志大佐 第32師団病馬廠:阿部国人獣医中尉
輜重兵第32連隊:中川千代吉大佐

編成地:仙台 通称号/略称:弓 所属軍:第15軍 最終地:ビルマ インパール
昭和14年)2月7日に新設された師団の一つ。宮城県仙台市で編成された。通称号の「弓」で知られる。
編成後、ただちに中国戦線に投入、第11軍戦闘序列に編入され湖北省に在って、ほかの治安師団と同様に
1939年夏以降に行われたさまざまな治安作戦に参加し、その後1941年4月に華北に転用され山西省に駐屯した。
太平洋戦争開戦後、第15軍戦闘序列に編入されビルマ攻略戦に参加、1942年1月にバンコクからビルマに向かう、
5月末には第15軍によりビルマのほぼ全域が占領された(第一次アキャブ作戦)。
昭和19年)3月には、師団は第15師団・第31師団とともにインパール作戦に参加した。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 甘粕重太郎 中将 |
昭和14年3月- |
山形県、駐蒙軍司令官、予備役に編入された。 |
| 桜井省三 中将 |
昭和16年1月- |
山口県、第28軍司令官 |
| 柳田元三 中将 |
昭和18年3月- |
長野県、旅順要塞司令官、関東州防衛司令官、ソ連に抑留 |
| 田中信男 少将 |
昭和19年5月- |
広島県、イラワジ会戦などに従軍 |
| 田中信男 中将 |
昭和19年6月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第213連隊(水戸):河原右丙大佐 第33師団通信隊:宮嶋清市少佐
歩兵第214連隊(宇都宮):林正直大佐 第33師団兵器勤務隊:五十嵐善一郎大尉
歩兵第215連隊(高崎):柄田節大佐 第33師団衛生隊:久世清蔵中佐
山砲兵第33連隊:龍福松中佐 第33師団第1野戦病院:阿部順一軍医少佐
工兵第33連隊:八木茂大佐 第33師団第2野戦病院:土井茂軍医少佐
輜重兵第33連隊:松木熊吉中佐 第33師団第2野戦病院:土井茂軍医少佐
第33師団病馬廠:高橋威彦獣医少佐
インパール作戦時
1.師団長:柳田元三(中将)→田中信男(着任時は少将のため、師団長心得中将昇進に伴い正式に着任する。)
2.歩兵団長:山本募(少将)
3.参謀長:田中鉄次郎(大佐
隷下部隊
1.歩兵第213連隊(右突進隊)(連隊長:温井親光(大佐))
2.歩兵第214連隊(中突進隊)(連隊長:作間喬宜(大佐))
3.歩兵第215連隊(左突進隊)(連隊長:笹原政彦(大佐))
4.山砲第33連隊(連隊長:福家政男(大佐))
5.工兵第33連隊(連隊長:八木茂(大佐))
6.輜重兵第33連隊(連隊長:松木熊吉(中佐))
9.歩兵第151連隊(連隊長:橋本熊五郎(大佐))(原隊:第53師団
10.歩兵第67連隊第1大隊(大隊長:瀬古三郎(大尉))(原隊:第15師団)
11.歩兵第154連隊第2大隊(大隊長:岩崎勝治(大尉))(原隊:第54師団(兵))

編成地:大阪 通称号/略称:椿 所属軍:第11軍-支那派遣軍 最終地:中国 九江
昭和14年)2月7日に新設された歩兵三個連隊編制師団の一つであり
編成後ただちに中国戦線に投入、第11軍戦闘序列に編入され武漢方面の警備に従事する。同年12月からは
南昌に移駐し同地の警備に従事する一方、1940年の宜昌作戦、翌1941年の錦江作戦などにも参戦する。
開戦後も第11軍隷下華中に在り占領地の警備や治安作戦に従事していたが、1944年(昭和19年)5月から
大陸打通作戦に参戦、湘桂作戦では長沙・岳麓山攻略などに従事する。
昭和20年)4月18日には支那派遣軍直轄部隊となり、南京方面に向けて移動中九江で終戦を迎える。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 関亀治 中将 |
昭和14年3月- |
兵庫県、第20軍司令官、予備役に編入後 |
| 大賀茂 中将 |
昭和15年12月- |
- |
| 秦彦三郎 中将 |
昭和17年10月- |
三重県、関東軍総参謀長、A級戦犯にてシベリア抑留 |
| 伴健雄 中将 |
昭和18年3月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第216連隊(大阪):石川明大佐 第34師団通信隊:西川浩大尉
歩兵第217連隊(大阪):木佐木清次大佐 第34師団第1野戦病院:高橋新吾軍医少佐
歩兵第218連隊(和歌山):沢多亮大佐 第37師団第2野戦病院:番場新一軍医少佐
第34師団工兵隊:森山正文大尉 第34師団病馬廠:倉田一良獣医大尉
第34師団輜重隊:森三丸大佐

編成地:東京 通称号/略称:東 所属軍:北支那方面軍-第12軍-第2軍 最終地:ニューギニア島
昭和14年2月7日に新設された師団の一つであり、編成後北支那方面軍隷下、黄河北岸の新郷に在って、
ほかの治安師団と同様に1939年夏以降に行われたさまざまな治安作戦に参加する。
開戦後も北支那方面軍隷下華北に在り占領地の警備や治安作戦に従事した。
昭和18年)、中国に駐屯する部隊の改編があり、この時に第35師団も乙師団で丙師団へ改編された。
第12軍に編入され、山東省方面の治安粛正の諸作戦に従事した。同年7月中旬から師団長は、
第59師団の歩兵第54旅団主力を指揮し、十八夏太行作戦に参加、省境付近の中共軍を掃討した。
昭和19年2月に南方への移動が決定され、配属砲兵隊として3月2日に満州の独立山砲兵第4連隊が師団に
編合れ、ハルマヘラ島の第2軍に編入された。当初には、第31軍所属として、マリアナに転用される予定であった
であったのだが、急遽第2軍に編入され、西部ニューギニアへと進出することになった。
師団主力は海軍艦艇で輸送され、ニューギニア島西端のソロンまでは到達できた。ソロンに進出後、
歩兵第220連隊を含む師団主力はソロン地区、歩兵第219連隊はヌンホル島、歩兵第221連隊はマノクワリ地区
に配置された。以後各部隊は、現地で連合軍の上陸に備え防衛体制の整備に着手した。
米軍は、同年5月27日にビアク島に上陸を開始した。この時師団は、歩兵第219連隊の第2大隊と歩兵第221連隊の
第2大隊を基幹として、約2,500名の将兵をビアク島に増員兵力へ派遣したが、全滅した。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 原田熊吉 中将 |
1940年5月- |
大阪府、第16軍司令官、第55軍司令官、戦後戦犯にて絞首刑 |
| 重田徳松 中将 |
1942年3月- |
千葉県、第52軍司令官、 |
| 坂西一良 中将 |
1943年2月- |
鳥取県、第20軍司令官 |
| 池田浚吉 中将 |
1944年3月- |
- |
最終所属部隊
歩兵第219連隊(甲府) 第35師団工兵隊:米山直一少佐
歩兵第221連隊(佐倉):鈴木友吉大佐 第35師団輜重隊:片倉春人少佐
歩兵第220連隊(東京):金井塚勇吉大佐 第35師団海上輸送隊:太郎田喜友中佐
独立山砲兵第4連隊:春山雄一大佐 第35師団野戦病院:兼島景徳軍医少佐
第35師団通信隊:若松軍吉少佐 第35師団病馬廠:佐久間忠大尉
第35師団衛生隊:草野昌蔵大佐

編成地:弘前 略称:雪 所属軍:第2軍 最終地:西部ニューギニア
昭和14年)2月7日に新設された師団の一つであり、編成後北支那方面軍・第1軍隷下、華北に在って、
ほかの治安師団と同様に1939年夏以降に行われたさまざまな治安作戦に参加する。
昭和18年)10月に南方移動を命じられ、同年11月5日に海洋編制師団へ改編、ニューギニアへ転用され第2軍に
昭和18年)10月に南方移動を命じられ、同年11月5日に海洋編制師団へ改編、ニューギニアへ転用され第2軍に
太平洋の戦局悪化に伴い、急遽南方戦線に投入された。上海から蘭印のハルマヘラを経由して、
西部ニューギニアのサルミ地区に上陸した。サルミに司令部を置き、同地で連合軍の上陸に備え防衛体制の
整備に着手した。その後、ビアク島に上陸した歩兵第222連隊を基幹として、ビアク支隊(支隊長:葛目直幸大佐)
が編成され、ビアク島の防衛を担当した。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 舞伝男 中将 |
1939年3月- |
- |
| 井関仭 中将 |
1940年8月- |
- |
| 岡本保之 中将 |
1943年2月- |
- |
| 田上八郎 中将 |
1943年10月 |
- |
最終所属部隊
兵第222連隊(弘前):葛目直幸大佐(ビアク島で玉砕)
歩兵第223連隊(秋田):吉野直靖大佐 第36師団通信隊:間瀬三郎少佐
歩兵第224連隊(秋田):松山宗右衛門大佐 第36師団兵器勤務隊:小枝八五郎少佐
第36師団戦車隊:藤村忠之少佐 第36師団野戦病院:細矢利次軍医大佐
第36師団輜重隊: 第36師団防疫給水部:斎藤恒友軍医少佐

編成地:熊本 通称号/略称:光/冬 所属軍:第1軍-第12軍-印度支那駐屯軍 最終地:タイ
日中戦争が泥沼化するなかで、占領地の警備や治安維持を目的として、1939年2月7日に新設された
三単位編制の治安師団の一つである。 大陸打通作戦で北京からバンコクまで踏破し、日本一歩いた軍隊と
言われている。開戦後も第1軍隷下にあり山西省に駐屯していたが、1944年(昭和19年)3月31日に
第12軍戦闘序列に編入され大陸打通作戦に参戦、4月17日に戦闘が始まった第一段の京漢作戦においては
4月23日河南省密県、4月30日には許昌を占領する。続いて同年7月17日には第11軍戦闘序列に編入、
第二段の湘桂作戦において9月29日に湖南省宝慶を占領、11月24日広西省南寧に至り、12月10日には
綏禄にて仏印方面から北上してきた第21師団の部隊と連絡し大陸打通を達成、12月19日印度支那駐屯軍
戦闘序列に編入される。印度支那駐屯軍(同年12月20日第38軍に改称)隷下タイ王国のナコーンナーヨック県
バーンナー近郊に駐屯して対イギリス戦に備えていたが、当地で終戦を迎え1946年(昭和21年)に復員した。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 平田健吉 中将 |
昭和14年3月- |
- |
| 安達二十三 中将 |
昭和15年8月- |
石川県、第18軍司令官、戦犯として終身刑を宣告後自決した |
| 長野祐一郎 中将 |
昭和16年10月 - |
島根県、第16軍司令官、橘丸事件の戦犯容疑で無罪 |
| 佐藤賢了 中将 |
昭和20年4月 |
石川県、最年少のA級戦犯で終身刑の判決 |
最終所属部隊
歩兵第225連隊(熊本):鎮目武治大佐 第37師団通信隊:丸田憲治郎少佐
歩兵第226連隊(都城):岡村文人大佐 第37師団第1野戦病院:陸哲之軍医少佐
歩兵第227連隊(鹿児島):河合自一大佐 第37師団第2野戦病院:岩崎豊次軍医大尉
山砲兵第37連隊:河野武夫中佐 第37師団第4野戦病院:阿部隣太郎獣医少佐
兵第37連隊:遠藤秀人中佐 第37師団防疫給水部:関三千夫軍医大尉
輜重兵第37連隊:米岡三郎大佐 第37師団病馬廠:阿部隣太郎獣医少佐

編成地:名古屋 通称号/略称:沼 所属軍:第21軍-南支那方面軍-第23軍-第16軍-第8方面軍
最終地:広東方面-香港-ジャワ島-ガダルカナル島-ニュージョージア島-ラバウル
昭和14年)6月30日に新設された歩兵三個連隊編制師団の一つであり、同時に第39師団・第40師団・第41師団
が新設された。また同年2月7日には第32師団・第33師団・第34師団・第35師団・第36師団・第37師団が新設された。
編成後、同年10月に華南に進駐、第21軍の指揮下に入り広東方面の警備に当たる一方、ほかの治安師団と
同様さまざまな治安作戦に参加した。昭和15年)2月9日、第21軍が廃止され、同時に編成された南支那方面軍に
に編入される。1941年(昭和16年)6月28日、南支那方面軍も廃止されると、新設の第23軍に編入され、
香港の戦いに参戦した。
昭和17年)1月4日、第16軍へ転属し、蘭印作戦に加わりジャワ島攻略などで激しい戦闘を行った。
さらに、ガダルカナル島の戦いに投入され大きな損害を受けた。ガダルカナル島撤退後に第8方面軍直轄となり、
隷下の歩兵第229連隊はニュージョージア島の戦いに参加する。
その後、戦力再建を進め、ラバウル防衛に従事しつつ終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 藤井洋治 中将 |
1939年10月- |
広島県、中部軍司令官、予備役に編入後、広島師管区司令官、第59軍司令官 |
| 佐野忠義 中将 |
1941年6月- |
静岡県、防衛総参謀長、第34軍司令官、1945年7月、仙台で戦病死 |
| 影佐禎昭 中将 |
1943年6月- |
広島県、中国政府から戦犯指名を受け、肺結核のため裁判に至らず |
最終所属部隊
歩兵第228連隊(名古屋):山口達春中佐 第38師団通信隊:集田貞雄少佐
歩兵第229連隊(岐阜):平田源次郎大佐 第38師団兵勤隊:佐藤光蔵少佐
混成第3連隊:遠藤健治大佐 第38師団衛生隊:仙田藤助少佐
山砲兵第38連隊:神吉武吉大佐 第38師団第1野戦病院:大畠良秀軍医中佐
工兵第38連隊:西村金三郎少将 第38師団第2野戦病院:坂野長夫軍医少佐
輜重兵第38連隊:幸田録郎中佐 第38師団病馬廠:土屋義弥獣医少佐

編成地:広島 通称号/略称:藤 所属軍:第11軍-第34軍-第30軍 最終地:中国 吉林省四平
昭和14年)6月30日に新設された歩兵三個連隊編制師団の一つであり、同時に第39師団・第40師団・第41師団
編成後、同年10月に華中に進駐、第11軍の指揮下に入り警備に当たる一方、ほかの治安師団と同様さまざまな
治安作戦に参加した。昭和15年)、宜昌作戦に参加し白河渡河戦闘で激戦を行った。同年11月には
漢水作戦に参加した。昭和16年)2月には予南作戦に参加、西部大洪山掃討作戦、江北作戦、第二次長沙作戦
参加した。その後、宜昌地区の警備に従事、現地で中国軍と対峙した。1944年(昭和19年)7月、第34軍に編入。
昭和20年)3月に老河口作戦に参加した。この作戦で師団の上級部隊である第34軍の任務は、第12軍の
河南方面作戦に策応するのだった。この作戦当時、湖北省一帯の日本軍占領地域の制空権は、連合国軍の手中
湖北省から上海方面に向け移動を開始した。満洲へ転進を開始した。この時捜索第39連隊が徒歩編制へ改編、
解散され師団の一部兵力とともに現地に残留した。これら残留部隊は、第68師団の残留部隊とともに
第132師団へ増強改編された。満洲に到着した師団主力は、7月30日付へ編成が発令された第30軍の戦闘序列に
編入され、吉林省四平に駐屯した。以後、現地でソ連軍の侵攻に備えて防禦陣地の構築などの防衛体制の整備
を行っていたが、ソ連軍と戦闘を交えることなく終戦を迎えた。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
村上啓作 中将 |
1939年10月- |
栃木県、第3軍の最後の司令官、戦後シベリア抑留収容所で病死 |
| |
澄田ライ四郎 中将 |
1941年9月- |
愛媛県、第1軍司令官 |
| |
佐々真之助 中将 |
1944年11月- |
- |
最終所属部隊
歩兵第231連隊(広島):福永勇吉大佐 輜重兵第39連隊:山田曻三大佐
歩兵第232連隊(浜田):山田正吉大佐 第39師団通信隊:大橋庸太郎大尉
歩兵第233連隊(山口):富永一大佐 第39師団兵器勤務隊:瀧沢勇雄少佐
野砲兵第39連隊:佐野芳蔵大佐 第39師団野戦病院:城島実軍医少佐
工兵第39連隊:今井洸中佐 第39師団病馬廠:井上繁義獣医大尉

編成地:善通寺 通称号/略称:鯨 所属軍:第11軍-第23軍-支那派遣軍 最終地:中国 南昌
昭和14年)6月30日に新設された歩兵三個連隊編制師団の一つであり、同時に第39師団・第40師団・第41師団
が新設された。また同年2月7日には第32師団・第33師団・第34師団・第35師団・第36師団・第37師団が新設された。
編成後、同年10月に第11軍指揮下に入り咸寧・武昌方面の警備に当たる一方、1940年(昭和15年)5月からの
宜昌作戦、1941年1月からの予南作戦、同年9月からの第一次長沙作戦、第二次長沙作戦に参加した。
昭和17年)4月18日にドーリットル空襲があり、爆撃したB-25が中国に着陸したことをきっかけに浙贛作戦が実施
参加した。1943年(昭和18年)2月には、江北殲滅作戦に参加。なお同年3月には山砲兵第40連隊を
山砲兵第31連隊として第31師団に転用し、以後砲兵力を欠いての作戦遂行を強いられることとなった。
昭和19年)4月から大陸打通作戦に参加、湘桂作戦にて6月10日に益陽を、7月9日に金蘭寺を攻略した。
その後更に南下し第23軍隷下華南・広東に移駐、広東(マカオ近辺)に展開して連合軍の中国南部上陸に
備えていたが、同年4月に連合軍が沖縄に上陸するなど戦局の変化により広東から上海方面に向け
移動を開始、支那派遣軍直轄師団となり、まだ日本軍の支配地域であった南昌に入ったところで終戦を迎える
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
天谷直次郎 中将 |
昭和14年10月- |
- |
| |
青木 成一 中将 |
昭和16年8月- |
- |
| |
宮川清三 中将 |
昭和19年8月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第234連隊(丸亀):西川俊元大佐 第40師団輜重隊:板橋勝少佐
歩兵第235連隊(徳島):堀内勝身大佐 第40師団通信隊:高岡欽一少佐
歩兵第236連隊(高知):小柴俊男大佐 第40師団野戦病院:福田義美軍医少佐
第40師団工兵隊:相徳定象少佐 第40師団病馬廠:中山辰己獣医少佐
 |
編成地:朝鮮/瀧山 通称号/略称:朝鮮/瀧山 所属軍:第1軍-第18軍 最終地:山西省-ニューギニア
昭和14年)6月30日に新設された歩兵三個連隊編制師団の一つであり、同時に第39師団・第40師団・第41師団
が新設された。また同年2月7日には第32師団・第33師団・第34師団・第35師団・第36師団・第37師団が新設された。
編成後、同年10月に華北に進駐、第1軍の指揮下に入り山西省方面の警備に当たる一方、ほかの治安師団と
同様さまざまな治安作戦に参加し、約3年間山西省を拠点に活動する。
昭和17年)11月に、師団は華北からニューギニアに転用されることとなり、第8方面軍隷下の第18軍に編入された。
先発隊の歩兵第239連隊が1943年2月下旬に、師団主力も同年5月に東部ニューギニアのウェワクに進出した。
しかし、その頃既に第51師団はラエ・サラモアの戦いに敗れ、続いてフィンシュハーフェンの戦いで第20師団も
大打撃を受け、第18軍は壊滅状態となっていた。
昭和19年)7月10日に、第41師団を主体とした残された第18軍の全勢力を以ってアイタペの戦いを挑むが功を
奏せず、以後アレキサンダー山系にこもり飢餓との戦いを続けた。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
田辺盛武 中将 |
昭和14年10月- |
第25軍司令官、戦犯容疑で死刑判決 |
| |
清水規矩 中将 |
昭和16年3月- |
福井県、第7方面軍参謀長を経て、第5軍司令官、シベリア抑留 |
| |
阿部平輔 中将 |
昭和17年7月- |
- |
| |
真野五郎 中将 |
昭和18年6月 |
- |
最終所属部隊
・第41歩兵団:青津喜久太郎少将
・歩兵第237連隊(水戸):奈良正彦少将 第41師団通信隊:長井角治少佐
・歩兵第238連隊(高崎):山口達春大佐 第41師団第1野戦病院:難藤正明軍医少佐
・歩兵第239連隊(宇都宮):越智鶴吉大佐 第41師団第2野戦病院:寺本巖軍医少佐
山砲兵第41連隊:大野斌夫大佐 第41師団第4野戦病院:中浜欣時軍医少佐
工兵第41連隊:加藤正中佐
輜重兵第41連隊:吉松篤大佐

編成地:仙台 通称号/略称:勲 所属軍:第27軍-第5方面軍 最終地:北海道 稚内
昭和18年)5月、軍令陸甲第45号下令により本土防衛強化のため第42師団、第43師団、第46師団、第47師団の
新設が命じられた。第42師団は、6月1日に留守第2師団と第62独立歩兵団を基幹に仙台で編成された。
編成後、当初は仙台に在り東部軍に属していたが、1944年3月16日に編成が発令された第27軍戦闘序列に
編入され、中千島守備を担った。1945年2月に第27軍が廃止となり、第5方面軍の直轄兵団に編入された。
北海道北部の稚内で本土決戦に備え、その準備を行なうと共にその地で警備任務に従事する中で戦闘を
交えることなく終戦を迎えた。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
寺倉正三 中将 |
1943年6月- |
岐阜県、第27軍司令官となり千島列島の防衛、東京防衛軍司令官 |
| |
佐野虎太 中将 |
1944年3月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第129連隊(若松):土持城大佐 第42師団編合
歩兵第130連隊(仙台):小川伊三雄大佐 独立戦車第5中隊:隅倉秋寿少佐
歩兵第158連隊(山形):浦野清治郎大佐 独立戦車第6中隊:塚越善三郎大尉
捜索第42連隊:佐藤国平中佐
野砲兵第12連隊:松川信正大佐 第42師団通信隊:金子善太郎少佐
工兵第42連隊:佐々木胞次郎中佐 第42師団兵器勤務隊:斎藤義雄少佐
輜重兵第42連隊:田悟直治中佐 第42師団第1野戦病院:藍沢太郎軍医大尉
第42師団第2野戦病院:桜田章軍医大尉
第42師団第3野戦病院:羽根田寛軍医大尉

編成地:名古屋 通称号/略称:誉 所属軍:第31軍 最終地:サイパン島
昭和18年5月、軍令陸甲第45号下令により本土防衛強化のため第42師団、第43師団、第46師団、第47師団の
新設が命じられた。第43師団は、6月10日に留守第3師団と第63独立歩兵団を基幹に名古屋で編成され、
中部軍に属した。1944年4月、第31軍に編入され、絶対国防圏の守備のためサイパン島へ派遣された。
同年6月15日、アメリカ軍の上陸を迎え、サイパン島の戦いに参加した。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 賀陽宮恒憲王中将 |
1943年6月- |
陸軍大学校長、軍事参議官 |
| 斎藤義次 中将 |
1944年4月- |
7月6日に洞窟内で井桁敬治少将、南雲忠一中将と共に自決した |
最終所属部隊
歩兵第118連隊(静岡):伊藤豪大佐
サイパン島に転進するため、第3530船団に乗船し横浜港を出港、一連の輸送船の沈没で
本連隊は連隊長以下2240名が死亡し、第3大隊長の大塚少佐が残存兵の指揮を執る
6月22日師団戦闘司令所が所在したチャチャで第3大隊が戦うも大塚大隊長以下ほとんどが戦死
6月26日 - タポチョ山に後退していた神田大尉以下27名が戦死、事実上の玉砕
歩兵第135連隊(名古屋):鈴木栄助大佐 第43師団兵器勤務隊:村瀬兼松大尉
歩兵第136連隊(岐阜):小川雪松大佐 第43師団経理勤務部:大川英夫中佐
第43師団通信隊:鷲津吉光大尉 第43師団野戦病院:深山一孝中佐
第43師団輜重隊:山本光男大尉

編成地:大阪 通称号/略称:橘 所属軍:第51軍 最終地:本土
昭和19年)4月4日に本土防衛強化のため、留守第4師団を基幹に大阪で編成された。
当初は中部軍隷下にあったが1945年(昭和20年)3月から関東平野に進出し、同年4月8日に新設された
第51軍戦闘序列に編入され、沿岸配備師団が防いでいるところに出撃し攻撃をかける機動打撃師団として、
本土決戦に備えるなかで終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 関原六 中将 |
昭和19年4月- |
- |
| 川並密 中将 |
昭和19年7月- |
茨城県、通信兵監に再任 |
| 谷口春治 中将 |
昭和20年3月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第92連隊(大阪):伊奈重誠大佐 第44師団兵器勤務隊
歩兵第93連隊(大阪):大沢勝二大佐 第44師団衛生隊
歩兵第94連隊(和歌山):工藤豊雄大佐 第44師団第1野戦病院
野砲兵第44連隊:高雄実大佐 第44師団第4野戦病院
工兵第44連隊:窪田英夫中佐 第44師団制毒隊
輜重兵第44連隊:金沢善治大佐 第44師団病馬廠
第44師団速射砲隊:鮫島良武少佐 第44師団通信隊:徳永貞少佐

編成地:熊本 通称号/略称:静 所属軍:西部軍 最終地:硫黄島-マレー半島
昭和18年)5月、本土防衛強化のため新設が命じられた。5月14日に留守第6師団と独立第66歩兵団を基幹に
熊本で編成され、西部軍に属した。1943年10月に南方への転出が命ぜられ、所属の歩兵第123連隊が
ジャワ島東部の小スンダ列島スンバワ島に上陸し、二ヶ月後には歩兵第147連隊がスンバワ島に上陸した。
残りの歩兵第145連隊は、輸送船の関係で進出することができず、1944年6月、硫黄島の小笠原兵団に
配属され硫黄島の戦いに参戦し全滅した。師団主力は、1945年4月、スンバワ島からマレー半島警備に
転用されたが、大きな戦闘を交えることもなく終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 萱嶋高 中将 |
1943年6月- |
宮崎県、留守第6師団長、退役後は宮崎市長 |
| 若松只一 中将 |
1943年10月- |
福島県、南方軍総参謀副長に、第2総軍参謀長、陸軍次官 |
| 国分新七郎 中将 |
1944年11月- |
- |
参謀長:新関栄作大佐 参謀:馬杉一雄中佐 山本立夫少佐 江見秀明少佐
最終所属部隊
歩兵第123連隊(熊本):中條豊馬大佐 第46師団輜重隊:有馬安成大尉
歩兵第147連隊(都城):西蓮寺元大佐 第46師団兵器勤務隊:阿万哲雄少佐
第46師団戦車隊:松永美尚少佐 第46師団経理勤務部:三ツ森文一主計中佐
第46師団通信隊:原田孫介大尉 第46師団野戦病院:田中平吉軍医大佐

編成地:弘前 通称号/略称:弾 所属軍:北方軍 最終地:済南
昭和18年)5月、本土防衛強化のため新設が命じられた。5月14日に留守第57師団と独立第67歩兵団を
基幹に弘前で編成され、北方軍に属した。昭和19年)11月、中国に動員され、華北での諸作戦に従事し、
終戦を済南で迎えた。戦後、一部の将兵が国共内戦に参加した。
第12派遣隊
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 大迫通貞 中将 |
1943年6月- |
- |
| 渡辺洋 中将 |
1944年10月- |
- |
参謀長:染矢半治郎大佐 参謀:曽我武雄中佐 高級副官:森田清之亟少佐
最終所属部隊
歩兵第91連隊(秋田):加藤正次大佐 第47師団防疫給水部:大橋常安軍医少佐
歩兵第105連隊(秋田):武信純一大佐 第47師団兵器勤務隊
歩兵第131連隊(弘前):重広三馬大佐 第47師団衛生隊
騎兵第47連隊:小野健大佐 第47師団第1野戦病院
山砲兵第47連隊:笹島太郎大佐 第47師団第2野戦病院
工兵第47連隊:阿部 大佐 第47師団第4野戦病院
輜重兵第47連隊:三田村正之助大佐 第47師団病馬廠
第47師団通信隊:赤松淳大尉
第12派遣隊
1944年6月13日、歩兵3個大隊、山砲兵1個大隊を基幹として第12派遣隊が編成され、南方戦線に派遣された。
その後、独立混成第58旅団に改編され、フィリピンのルソン島の戦いに参戦した。

編成地:海南島 通称号/略称:海 所属軍:第22軍-台湾軍-第14軍-第16軍-第19軍-第16軍
最終地:フィリピン-蘭印-ティモール島
日中戦争勃発後華中から華南を転戦し、第22軍隷下広東省に在った台湾混成旅団に、第6師団から転用された
歩兵第47連隊を加え編成された台湾軍の師団である。編成に先立ち第22軍は廃止され
南支那方面軍直轄から第23軍隷下を経て、1941年(昭和16年)8月12日に台湾軍隷下となり台湾に戻った。
昭和16年)11月6日に再び動員された。第48師団は第5師団とともに揚陸能力を備えた機械化師団
のうちの一つであり、極めて重要な存在だった。開戦後、まずは第14軍の主力としてフィリピンの攻略に従事した。
昭和17年1月に蘭印作戦のため第16軍戦闘序列に編入され、3月1日ジャワ島東部に上陸し、
3月7日スラバヤを攻略した。昭和18年)1月に第19軍隷下となるが、1945年(昭和20年)2月28日に第19軍が
廃止されたため、再び第16軍隷下となりティモール島で終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 中川広 中将 |
昭和15年12月- |
兵庫県、予備役編入 |
| 土橋勇逸 中将 |
昭和16年9月- |
佐賀県、印度支那駐屯軍司令官 、戦犯容疑で不起訴処分 |
| 山田国太郎 中将 |
昭和19年11月 |
- |
最終所属部隊
湾歩兵第1連隊(台北):恒岡小文吾大佐 第48師団通信隊:小池正次少佐
台湾歩兵第2連隊(台南):田中透少将 第48師団兵器勤務隊:興水忠治少佐
歩兵第47連隊(大分):徳弘保衛大佐 第48師団衛生隊:山本良三大佐
捜索第48連隊:住田英夫中佐 第48師団第1野戦病院:横尾正庸軍医少佐
山砲兵第48連隊:六反田壮吉大佐 第48師団第2野戦病院:原田純隆軍医少佐
工兵第48連隊:西本慶一少佐 輜重兵第48連隊:馬場和人大佐

編成地:京城 通称号/略称:狼 所属軍:南方軍-第33軍 最終地:ビルマ
昭和19年)1月、朝鮮半島の留守第20師団と独立第64歩兵団(司令部:奈良)を基幹に臨時に編成された。
兵員の約2割が朝鮮半島出身者であった。同年5月、南方軍戦闘序列に編入されビルマ派遣が決定された。
同年6月からシンガポール及びサイゴンへ出発するが、途中で2隻の輸送船が戦没し、約1,600名の将兵が失われた。
ビルマに進駐後、第33軍に歩兵第168連隊と山砲兵第49連隊第2大隊主力による吉田部隊が編入され、
ビルマルート遮断を目指した「断作戦」に参加した。また、歩兵第153連隊と山砲兵第49連隊第3大隊の
構成による林部隊は、エナンジャン油田(ビルマ南西部)北部での作戦に従事した。
さらに、第49師団はメイクテーラ奪回作戦を担ったが、作戦は失敗しビルマ南方に撤退。さらにシッタン川東岸に
において防御を実施する中で終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 竹原三郎 中将 |
1944年1月- |
熊本県、ビルマへ赴任。イラワジ会戦などで苦戦で終戦 |
参謀長:緒方捨次郎大佐 作戦参謀:的埜中郎中佐 情報参謀:淵熊市中佐
後方参謀:田口厳寛少佐 参謀:古賀俊次少佐 高級副官:杉浦栄次郎少佐
最終所属部隊
歩兵第106連隊(京城):斎藤敏雄少佐 山砲兵第49連隊:園田豊二中佐
歩兵第153連隊(京城):野田倭文雄中佐 工兵第49連隊:大原芳一少佐
歩兵第168連隊(京城):中尾策郎大佐 輜重兵第49連隊:大河原定大佐
騎兵第49連隊:田中和一郎大佐 第49師団通信隊:宮武金市少佐

編成地:台北 通称号/略称:蓬(ほう) 所属軍:台湾軍 最終地:台湾 高雄南方
昭和19年)5月、留守第48師団を基幹に編成され台湾軍に属した。所属の山砲兵第50連隊は、
留守山砲兵第48連隊補充隊を基幹に、南方へ移動中に輸送船の戦没などで台湾に留まっていた兵員により
編成されている。第50師団は、高雄南方においてアメリカ軍の上陸に備えていたが、戦闘を交えることなく終戦
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
石本貞直 中将 |
1944年5月- |
- |
参謀長:大石広海大佐 参謀:藤尾森生中佐 山田常少佐 高級副官:浦井博少佐
最終所属部隊
歩兵第301連隊(台北):奥中義男大佐 輜重兵第50連隊(鳳山):
歩兵第302連隊(台南):永野千秋大佐 第50師団通信隊:
歩兵第303連隊(鳳山): 第50師団兵器勤務隊:
捜索第50連隊(台中): 第50師団衛生隊:
山砲兵第50連隊(台北):田中次郎大佐 第50師団第1野戦病院:
工兵第50連隊(東港):宮本正三少佐 第50師団第4戦病院:

|
通称号/略称:基 編成地:宇都宮
大日本帝国陸軍の師団の一つ。茨城・栃木・群馬の三県を徴兵区とする常設師団として、
昭和15年)7月10日に留守第14師団を基幹に宇都宮で編成された。編成後当初は東部軍に所属し
宇都宮に在ったが、1941年(昭和16年)7月に関東軍特種演習参加のため満州へ派遣。
同年9月には華南に進出し第23軍に編入され、歩兵第66連隊基幹の荒木支隊が12月の香港の戦いに参戦する。
その後も第23軍隷下広東に駐屯していたが、1942年(昭和17年)11月にはニューギニア戦線に転用され
第18軍に編入、ラバウルに進出した。昭和18年)1月2日に東部ニューギニアのブナの日本軍が玉砕し、
師団は連合国軍の次の目標地であろうラエを守るべく2月28日にラバウルを出航した
しかし、3月2日・3日にダンピール海峡で連合軍の空襲を受け、輸送船8隻すべてと駆逐艦4隻が撃沈され
ダンピールの悲劇といわれる多大な犠牲を出した(ビスマルク海海戦)。その後小規模に分かれた
舟艇や駆逐艦による輸送により上陸した1個連隊ほどの兵員もラエ・サラモアの戦いに敗れ、
サラワケット越えを敢行しての撤退は悲惨を極め、さらに連合国軍の飛び石作戦に翻弄され飢餓との
戦いを続け、約16,000名の人員が終戦時には2,754名であった。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 上野勘一郎 中将 |
昭和15年9月- |
- |
| 李王垠 中将 |
昭和16年7月- |
初代大韓帝国皇帝高宗の第7男子、第1航空軍司令官、軍事参議官 |
| 中野英光 中将 |
昭和16年11月 |
- |
最終所属部隊
第51歩兵団::川久保鎮馬中将
・歩兵第66連隊(宇都宮):遠藤房俊大佐 第51師団通信隊:小泉茂大尉
・歩兵第102連隊(水戸):堀慶二郎大佐 第51師団兵器勤務隊:喜多川儀平中尉
・歩兵第115連隊(高崎):松井隆美大佐 第51師団衛生隊:小桜八太郎少佐
捜索第51連隊 第51師団第1野戦病院:谷口慶亮軍医少佐
野砲兵第14連隊:渡辺左之大佐 第51師団第2野戦病院:本間博軍医少佐
工兵第51連隊:安東英夫中佐 第51師団第3野戦病院:佐伯正之進軍医少佐
輜重兵第51連隊:江崎義雄大佐

編成地:金沢 通称号/略称:柏 所属軍:東部軍-第31軍 最終地:トラック島
昭和15年)8月から常設師団のうちの8個師団が満州に永久駐屯することになり、代替の常設師団として
同年7月10日に留守師団を基幹に編成された6個師団のひとつである
第52師団は、石川・富山・長野の三県を徴兵区とする常設師団として留守第9師団を基幹に金沢で編成された。
昭和20年)には補充任務等の管轄区域の軍政を担当する留守師団司令部は独立し金沢師管区司令部となった。
師団は編成後、当初は金沢に在り東部軍に属していたが、1944年(昭和19年)1月にトラック島へ派遣され、
翌月に新設の第31軍に編入された。その際、海洋師団編制に改編されている。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 草場辰巳 中将 |
1940年10月- |
滋賀県、関東防衛軍司令官、シベリア抑留、戦後自決 |
| 麦倉俊三郎 中将 |
1941年11月 |
栃木県、正式の第31軍司令官となり第52師団長事務取扱を兼務 |
| 麦倉俊三郎 中将 |
1945年1月- |
栃木県、正式の第31軍司令官となり第52師団長事務取扱を兼務 |
最終所属部隊
歩兵第69連隊(富山):柴野為亥知大佐 第52師団海上輸送隊:西村利央中佐
歩兵第107連隊(金沢):山中萬次郎大佐 第52師団通信隊:馬場義行少佐
歩兵第150連隊(松本):林田敬蔵大佐 第52師団経理勤務部:榊原茂大佐
第52師団戦車隊:佐藤恒哉少佐 第52師団兵器勤務隊:辻川初次郎少佐
第52師団輜重隊:大南斂大尉 第52師団野戦病院:杉田秀馬大佐

編成地:京都 通称号/略称:安 所属軍:南方軍予備 最終地:ビルマ シッタン川
昭和15年)8月から常設師団のうちの8個師団が満州に永久駐屯することになり、代替の常設師団として
留守師団を基幹にした師団の新設が進められることになった。
昭和16年)9月16日に留守第16師団を基幹に編成されたのが第53師団である。なお、第1師団分については
代替師団が編成されなかった。第53師団は京都で編成され、京都・滋賀・三重・福井の四府県を徴兵区とした
師団は編成後、当初は京都に在り中部軍に属していたが、1943年11月に動員され南方軍予備として派遣
昭和19年)1月からサイゴン、シンガポールなどに到着した。そして、インパール作戦の実施に伴いビルマに派遣
拉孟・騰越の戦い、イラワジ会戦に参加。シッタン川付近で英印軍との戦闘を交える中で終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 馬場正郎 中将 |
1941年10月- |
熊本県、第37軍司令官、BC級戦犯容疑絞首刑判決 |
| 河野悦次郎 中将 |
1943年9月 |
- |
| 武田馨 中将 |
1944年4月- |
滋賀県、教育総監部付、新設の高射兵監 |
| 林義秀 中将 |
1945年2月- |
和歌山、戦犯容疑で終身刑の判決を受けたが、1953年7月に釈放 |
最終所属部隊
歩兵第119連隊(敦賀):羽賀芳男大佐 第53師団兵器勤務隊:山本茂雄大尉
歩兵第128連隊(京都):菊地芳之助大佐 第53師団衛生隊:辻村正少佐
歩兵第151連隊(津):橋本熊五郎大佐 第1野戦病院:寺本嘉範少佐
捜索第53連隊:斎藤富雄少佐 第2野戦病院:板東保少佐
野砲兵第53連隊:横田武夫大佐 第4野戦病院:後下保少佐
工兵第53連隊:田中誠大佐 第53師団防疫給水部:小山田功少佐
第53師団病馬廠:宮本雄三郎大尉

編成地:姫路 通称号/略称:兵 所属軍:南方軍第16軍 最終地:ビルマ シッタン川
1940年7月10日に第51師団・第52師団・第54師団・第55師団・第56師団・第57師団の計6個師団が
がそれぞれ留守師団を基幹に編成された。翌年の1941年(昭和16年)9月16日に第53師団が留守第16師団を
基幹に編成されたが、第1師団分については除かれた。
第54師団は、兵庫・岡山・鳥取の三県を徴兵区とする常設師団として留守第10師団を基幹に姫路で編成された。
編成後、当初は姫路に在り中部軍に属していたが、1943年2月に動員され南方軍第16軍に編入された。
さらにビルマに派遣され緬甸方面軍の直轄部隊としてビルマ南西部に駐屯していたが、
昭和19年)1月、新設された第28軍に属した。1944年2月、第二次アキャブ作戦に参加し英印軍の堅い守りを
突破できず退却。インパール作戦の敗退により英印軍の圧迫を受け、1945年4月にイラワジ河を渡り
ペグー山系に退却し、さらにシッタン川向け後退し、シッタン川を渡河してまもなく終戦を迎えた。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
秋山義兌 中将 |
1940年8月- |
- |
| |
片村四八 中将 |
1941年8月- |
広島、第15軍司令官、第15軍は第18方面軍に編入されタイ |
| |
宮崎繁三郎 中将 |
1944年8月- |
岐阜県、ビルマの収容所 |
最終所属部隊
第54歩兵団 :歩兵団司令部:歩兵団長 木庭知時少将
歩兵第111連隊(姫路):矢木孝治大佐 第54師団通信隊:森下千代松少佐
歩兵第121連隊(鳥取):馬場進大佐 第54師団兵器勤務隊:瀧本武大尉
歩兵第154連隊(岡山):村山一馬大佐 第54師団衛生隊:岩田文三大佐
捜索第54連隊:古賀文夫少佐 第1野戦病院:山崎淳一少佐
野砲兵第54連隊:横田武夫大佐 第2野戦病院:須藤利一少佐
工兵第54連隊:大田智大佐 第4野戦病院:中間三次少佐
輜重兵第54連隊:太田貞次郎大佐 第54師団防疫給水部:菊地猛夫少佐

編成地:善通寺 通称号/略称:荘 所属軍:第15軍-第28軍 最終地:ビルマ-プノンペン
四国四県を徴兵区とする常設師団として、1940年7月10日に留守第11師団を基幹に善通寺で編成された。
編成後当初は善通寺に在り、中部軍に属していたが、師団主力は太平洋戦争開戦に伴い動員され、
第15軍に属しビルマの戦いに従軍した。第一次アキャブ作戦では多大な戦果を挙げた。
昭和19年)1月、新設された第28軍に属し第二次アキャブ作戦に参戦したが敗退。イラワジ河に後退し、
第38軍隷下となり仏印に移動。プノンペン付近で集結する中で終戦を迎えた。
南海支隊
昭和16年)11月15日、第55歩兵団司令部、歩兵第144連隊、山砲兵第55連隊第1大隊、第1野戦病院などにより
堀井富太郎少将を長とする南海支隊が編成された。支隊は開戦後、グアム島攻略、ラバウル攻略に従軍。
支隊は開戦後、グアム島攻略、ラバウル攻略に従軍。昭和17年)7月に始まったポートモレスビー作戦の担当となり、
第5師団から歩兵第41連隊と、マレー作戦に投入された独立工兵第15連隊が追加配属された。
昭和18年)11月、200名ほどの生存者が第55師団に復帰した。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 永見俊徳 中将 |
1940年8月- |
東京、予備役に編入後留守第55師団長、昭和18年召集解除 |
| 石本寅三 中将 |
1940年12月- |
兵庫県、1941年3月、現職で死去。 |
| 竹内寛 中将 |
1941年4月- |
岡山県、昭和18年)9月、予備役に編入、岡山市長(昭和19年~20年10月) |
| 古閑健 中将 |
1942年12月- |
- |
| 花谷正 中将 |
1943年10月- |
岡山県、第39軍参謀長に就任、第18方面軍参謀長として終戦 |
| 佐久間亮三中将 |
1945年7月- |
- |
最終所属部隊
歩兵第112連隊(丸亀):古谷朔郎大佐 第55師団通信隊:河村律三郎少佐
歩兵第143連隊(徳島):木村雄二郎大佐 第55師団衛生隊:内山万蔵中佐
歩兵第144連隊(高知):吉田章雄大佐 第55師団第1野戦病院:小野彰少佐
騎兵第55連隊:杉本泰雄大佐 第55師団第2野戦病院:瀧沢寿朗少佐
山砲兵第55連隊:井上義幸大佐 第55師団第4野戦病院:都甲元二少佐
工兵第55連隊:村山誠一中佐 第55師団病馬廠:宮沢正憲中尉
輜重兵第55連隊:八木達夫少佐 第55師団防疫給水部:藤岡勇少佐
第55師団兵器勤務隊:伊藤正雄大尉

編成地:久留米 通称号/略称:龍 所属軍:第25軍-第15軍 最終地:ビルマ-雲南省- タイ
昭和15年)8月から常設師団のうちの8個師団が満州に永久駐屯することになり、代替の常設師団として
留守師団を基幹にした師団の新設が進められることになった。第56師団は留守第12師団を母体に久留米で
編成され、福岡、佐賀、長崎の三県を徴兵区としていた。なお、その管轄区域は1941年から久留米師管区に
改称され、1945年(昭和20年)には、補充任務等の管轄区域の軍政を担当する
編成後、当初は久留米に在り西部軍に属していたが、師団主力は太平洋戦争開戦に伴い
1941年11月に動員され、第25軍に編入しマレー作戦を担当する予定であったが同作戦の早期達成により、
昭和17年)3月、第15軍に属しビルマの戦いに従軍。侵攻作戦とビルマルート(援蒋ルート)遮断に成功した。
1942年5月からビルマ北東部の中国雲南省との国境警備を担当。歩兵第113連隊の主力を拉孟に、
同連隊第3大隊を龍陵に、歩兵第148連隊を騰越に配置した。
昭和19年)1月、中国軍雲南遠征軍の攻撃を受け拉孟・騰越の戦いが始まるも敗退し、同年10月から
中国軍の総攻撃を受けビルマを南下し、さらにタイ領内に移動を進める中で終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 渡辺正夫 中将 |
1940年8月- |
大阪、沖縄の第32軍初代司令官、予備役編入後大阪師管区司令官 |
| 松山祐三 中将 |
1942年12月- |
青森県、、ビルマ戦線で苦戦を強いられた。終戦をタイ |
最終所属部隊
歩兵第113連隊(福岡):大須賀実大佐 第56師団通信隊:大石良市少佐
歩兵第146連隊(大村):今岡宗四郎大佐 第56師団兵器勤務隊:森友記大尉
歩兵第148連隊(久留米):相原無畏之輔大佐 第56師団衛生隊:原田万太郎少佐
捜索第56連隊(福岡):柳川明大佐 第56師団第1野戦病院:五十川秀夫少佐
野砲兵第56連隊(久留米):山崎周一郎大佐 第56師団第2野戦病院:三浦豊少佐
工兵第56連隊(久留米):山口稔夫少佐 第56師団第4野戦病院:長崎義雄少佐
輜重兵第56連隊(久留米):池田耕一大佐 第56師団病馬廠:馬場静雄大尉
第56師団防疫給水部:市村勢夫少佐

編成地:弘前 通称号/略称:奥 所属軍:第25軍-第15軍 最終地:ビルマ-雲南省-タイ
昭和15年)8月から常設師団のうちの8個師団が満州に永久駐屯することになり、代替の常設師団として
留守師団を基幹にした師団の新設が進められることになった。第56師団は留守第12師団を母体に久留米で
編成され、福岡、佐賀、長崎の三県を徴兵区としていた。なお、その管轄区域は1941年から久留米師管区に
改称され、1945年(昭和20年)には、補充任務等の管轄区域の軍政を担当する
編成後、当初は久留米に在り西部軍に属していたが、師団主力は太平洋戦争開戦に伴い
1941年11月に動員され、第25軍に編入しマレー作戦を担当する予定であったが同作戦の早期達成により、
昭和17年)3月、第15軍に属しビルマの戦いに従軍。侵攻作戦とビルマルート(援蒋ルート)遮断に成功した。
1942年5月からビルマ北東部の中国雲南省との国境警備を担当。歩兵第113連隊の主力を拉孟に、
同連隊第3大隊を龍陵に、歩兵第148連隊を騰越に配置した。
昭和19年)1月、中国軍雲南遠征軍の攻撃を受け拉孟・騰越の戦いが始まるも敗退し、同年10月から
中国軍の総攻撃を受けビルマを南下し、さらにタイ領内に移動を進める中で終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 渡辺正夫 中将 |
1940年8月- |
大阪、沖縄の第32軍初代司令官、予備役編入後大阪師管区司令官 |
| 松山祐三 中将 |
1942年12月- |
青森県、、ビルマ戦線で苦戦を強いられた。終戦をタイ |
最終所属部隊
歩兵第113連隊(福岡):大須賀実大佐 第56師団通信隊:大石良市少佐
歩兵第146連隊(大村):今岡宗四郎大佐 第56師団兵器勤務隊:森友記大尉
歩兵第148連隊(久留米):相原無畏之輔大佐 第56師団衛生隊:原田万太郎少佐
捜索第56連隊(福岡):柳川明大佐 第56師団第1野戦病院:五十川秀夫少佐
野砲兵第56連隊(久留米):山崎周一郎大佐 第56師団第2野戦病院:三浦豊少佐
工兵第56連隊(久留米):山口稔夫少佐 第56師団第4野戦病院:長崎義雄少佐
輜重兵第56連隊(久留米):池田耕一大佐 第56師団病馬廠:馬場静雄大尉
第56師団防疫給水部:市村勢夫少佐

編成地:中国湖北省、漢口 通称号/略称:広 所属軍: 最終地:
開戦後に中国に在った独立混成旅団を改編し、占領地の警備と治安維持を目的に編成された治安師団の
一つであり、独立混成第18旅団を改編して編成された。
前身である独立混成第18旅団は、復員した第106師団隷下の歩兵第136旅団の人員や装備を譲り受けていたので、
第58師団の補充業務は熊本師管区が担当した。師団の編制は、4つの独立歩兵大隊から成る
歩兵旅団(甲師団の歩兵旅団は2個連隊構成)を2つ持ち、砲兵力を欠いた丙師団である。
なお軍旗は連隊に下賜されるため、軍旗を持たない兵団である。
昭和17年)2月2日に漢口で編成された後、司令部を応城に置き、前身であった独立混成第18旅団の
任務を引き継ぎ応城付近の警備や治安維持に従事した。昭和19年)5月からは大陸打通作戦第二段の
湘桂作戦に参加、衡陽攻略作戦や桂林作戦などでは主力を勤め、作戦終了後は第11軍司令部の置かれた
柳州の北東側の桂林方面の警備を担当した。第58師団隷下の独立歩兵第94大隊は、第3師団と交代のため
一旦南下し4月13日に南寧に到着、5月26日まで確保した後南寧を放棄し5月29日には賓陽まで戻った。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 下野一霍 中将 |
1942年2月- |
東京、南方軍付、同軍兵站監、予備役編入 |
| 毛利末広 中将 |
1944年3月- |
- |
| 川俣雄人 中将 |
1945年3月 |
- |
最終所属部隊
・歩兵第51旅団:白浜重任少将
・独立歩兵第92大隊:松元実大尉 第58師団工兵隊:鈴木孝夫大尉
・独立歩兵第93大隊:平田友市少佐 第58師団輜重隊:和田喜代治少佐
・独立歩兵第94大隊:小林正道大尉 第58師団通信隊:狩谷伝次郎少佐
・独立歩兵第95大隊:稲垣陽大佐 第58師団野戦病院:魚住清軍医少佐
・歩兵第52旅団:藤本末夫大佐 第58師団病馬廠:前田甚蔵獣医大尉
・独立歩兵第96大隊:立川惣四郎大尉
・独立歩兵第106大隊:河野一馬大尉
・独立歩兵第107大隊:築島長作少佐
・独立歩兵第108大隊:山田善之輔大尉

編成地:中国山東省、斉南 通称号/略称:衣 所属軍:第34軍 最終地:朝鮮咸鏡南道咸興
開戦後に中国に在った独立混成旅団を改編し、占領地の警備と治安維持を目的に編成された治安師団の
一つであり、独立混成第10旅団を改編して編成された。
前身である独立混成第10旅団は、中国山東省済南(同省の首都)地区の警備や治安維持担当した。
第59師団の補充業務は東京師管区が担当した。師団の編制は、4つの独立歩兵大隊から成る歩兵旅団
を2つ持ち、砲兵力を欠いた丙師団である。
第59師団は、1942年(昭和17年)2月2日に済南で編成された後、司令部を済南に置き、前身であった
独立混成第10旅団の任務を引き継ぎ済南付近の警備や治安維持に従事した。
同年6月初旬、新泰、萊蕪県東方山地、次いで館陶県地区の討伐作戦に従事。
昭和18年)1月、軍直轄部隊と協同による討伐作戦では大王村(済南の北東)地区の中共軍を包囲急襲した。
昭和19年)1月下旬、河南作戦(一号作戦の第一期)が下令され、北支那方面軍も兵力を抽出したため、
師団の警備担任地域は山東全域および旧黄河下流地帯に拡大した。
昭和20年)3月、師団迫撃砲隊を編成し師団編合に編入された。 同年5月、師団全力による秀嶺作戦に
従事中に北朝鮮転用が発令され、同月30日関東軍隷下へ編入後、6月18日第34軍隷下に編入。
7月初旬から済南から鉄道輸送により朝鮮咸鏡南道咸興に到着し、陣地構築中に終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 柳川悌 中将 |
1942年4月- |
- |
| 細川忠康 中将 |
1943年3月- |
鳥取県、第43軍司令官 |
| 藤田茂 中将 |
1945年3月 |
- |
参謀長:武部松雄大佐 参謀:村上勇二少佐 参謀:谷垣迪男少佐 高級副官:伊藤久次郎少佐
最終所属部隊
・歩兵第53旅団(東京):上坂勝少将
・独立歩兵第41大隊(東京):栗木卓男大尉 第59師団迫撃砲隊:芳信雅之大尉
・独立歩兵第42大隊(佐倉):風神泰彦大尉 第59師団工兵隊:桑原実少佐
・独立歩兵第43大隊(佐倉):草野清少佐 第59師団通信隊:野口政喜少佐
・独立歩兵第44大隊(甲府):原口準三大尉 第59師団輜重隊:小池忠太郎少佐
・歩兵第54旅団(甲府):長島勤少将 第59師団野戦病院:森富士雄軍医少佐
・独立歩兵第45大隊(甲府):酒井利郎少佐 第59師団病馬廠:森磐次獣医大尉
・独立歩兵第109大隊(東京):坪井正佐大佐
・独立歩兵第110大隊(甲府):植野重利少佐
・独立歩兵第111大隊(佐倉):藤田宏大佐

|
編成地:華中 通称号/略称:矛 所属軍:第13軍 最終地:上海
1942年2月2日に、長江南部の警備を行っていた独立混成第11旅団を基幹に編成された。
編成後、前身であった独立混成第11旅団の任務を引き継ぎ上海から蘇州にかけての警備や治安維持に従事した。
昭和20年、連合国軍の上海への上陸に備え、その準備を行なうと共に治安警備に従事する中で終戦を迎えた。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
小林信男 中将 |
1942年4月- |
大阪府、第54軍司令官となり、愛知県新城に在って本土決戦 |
| |
落合松二郎 中将 |
1945年6月- |
- |
謀長:伊藤耕次郎中佐 参謀:泉祐順少佐 高級副官:前田正成中佐
最終所属部隊
・歩兵第55旅団(佐倉):南部外茂起少将
・独立歩兵第46大隊:大森勝一少佐 第60師団砲兵隊:戸谷悦雄大尉
・独立歩兵第47大隊:後藤学少佐 第60師団通信隊:森繁太少佐
・独立歩兵第48大隊:藤沢直助少佐 第60師団工兵隊:原岡逸郎大尉
・独立歩兵第49大隊:小沢千尋少佐 第60師団輜重隊:平田忠夫少佐
・歩兵第56旅団(佐倉):山口三郎少将 第60師団野戦病院:石原正己少佐
・独立歩兵第50大隊:青島武人大尉 第60師団病馬廠:陽田甚一大尉
・独立歩兵第112大隊:西垣正温少佐
・独立歩兵第113大隊:原武治少佐
・独立歩兵第114大隊:長藤丈夫少佐

編成地:東京 通称号/略称:鵄 所属軍: 最終地:上海
1943年3月、独立第61歩兵団を基幹に東京で編成された。編成後、南京からビルマ戦線に転用された
第15師団から任務を引き継ぐため南京に移動した。南京から蕪湖にかけての区域の警備に当たった。
上海に移動し連合国軍の上陸に備え、その準備を行なうと共に治安警備に従事する中で終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 田中勤 中将 |
1943年3月18日 - |
- |
参謀長:山下哲夫大佐 参謀:永田忠正中佐 高級副官:赤堀篤中佐
最終所属部隊
歩兵第101連隊(東京):野村懋大佐 第61師団工兵隊:清水達男大尉
歩兵第149連隊(甲府):岡村誠之大佐 第61師団輜重隊:小川福次郎少佐
歩兵第157連隊(佐倉):赤松貞雄大佐 第61師団野戦病院:高尾利弘大尉
第61師団迫撃砲隊:杉山重太郎少佐 第61師団病馬廠:小林芳治大尉
第61師団通信隊:松原常雄少佐

編成地:華北 通称号/略称:石 所属軍:第1軍-第32軍 最終地:山西省東部-沖縄本島
1943年5月、独立混成第4旅団と独立混成第6旅団の一部により山西省太原で編成された治安師団である。
編成後、第1軍に属し山西省東部の警備に当たった。1944年3月、大陸打通作戦の京漢作戦に参加した。
1944年8月、第62師団は沖縄に転用され第32軍に属した。1945年4月からアメリカ軍と嘉数の戦いなど
激戦を続けたが、ついに同年6月22日、沖縄本島南端の摩文仁において藤岡師団長が自決し戦闘を終えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 本郷義夫 中将 |
1943年6月- |
兵庫県、関東防衛軍司令官、第44軍司令官を務め、シベリア抑留 |
| 藤岡武雄 中将 |
1945年3月- |
東京都、沖縄戦に参加、1945年6月、撤退した摩文仁において自決 |
参謀長:上野貞臣大佐 参謀:北島之等之中佐 楠瀬梟師少佐 高級副官:原研介中佐
最終所属部隊
・歩兵第63旅団(敦賀):中島徳太郎中将
・独立歩兵第11大隊(敦賀):三浦日出四郎中佐 第62師団通信隊:砂川玄一郎大尉
・独立歩兵第12大隊(敦賀):賀谷与吉大佐 第62師団工兵隊:金木徳三郎少佐
・独立歩兵第13大隊(京都):原宗辰大佐 第62師団輜重隊:杉本秀義少佐
・独立歩兵第14大隊(京都):内山幸雄大尉 第62師団野戦病院:熊倉寛少佐
・歩兵第64旅団(京都):有川主一少将 第62師団病馬廠:小川昌美大尉
・独立歩兵第15大隊(京都):飯塚豊三郎少佐
・独立歩兵第21大隊(敦賀):西林鴻介大佐
・独立歩兵第22大隊(敦賀):磯崎璣大佐
・独立歩兵第23大隊(敦賀):山本重一少佐

編成地:華北 通称号/略称:陣 所属軍:第44軍 最終地:奉天東方
1943年5月、独立混成第15旅団と独立混成第6旅団の一部、日本本土で編成された部隊により華北で編成された
治安師団である。編成後、北支那方面軍に属し北京から保定方面の警備に当たった。
昭和19年)5月から大陸打通作戦の京漢作戦に参加した。
昭和20年6月、第63師団は満州に転用され第44軍に属し、通遼に駐屯した。同年8月のソ連軍進攻に伴い
奉天に退き、奉天東方の防御に当たる中、終戦を迎えた。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
野副昌徳 中将 |
1943年6月- |
- |
| |
岸川健一 中将 |
1945年3月- |
- |
参謀長:永井浩一大佐 参謀:大原晴海中佐 高級副官:林吾夫少佐
最終所属部隊
・歩兵第66旅団:下枝龍男少将
・独立歩兵第77大隊:石野武少佐
・独立歩兵第78大隊:小田二郎少佐
・独立歩兵第79大隊:矢萩留次郎少佐 第63師団迫撃砲隊:
・独立歩兵第137大隊:有馬敏雄大佐 第63師団通信隊:小島梅太郎大尉
・歩兵第67旅団:橋場帝次大佐 第63師団工兵隊:西沢彦義大尉
・独立歩兵第24大隊:上條保廣大佐 第63師団輜重隊:岩谷常男大尉
・独立歩兵第25大隊:福永勇吉大佐 第63師団野戦病院:大久保一郎少佐
・独立歩兵第80大隊:山川吉春少佐 第63師団病馬廠:東口力小大尉
・独立歩兵第81大隊:河野亨大尉

編成地:中華 通称号/略称:開 所属軍:第44軍 最終地:湖南省長沙
1943年5月、独立混成第12旅団と広島師管で編成された諸部隊により華中で編成された治安師団である。
同年7月10日に編成が完了し第20軍に属し、揚州、江北、鎮江、無錫方面の警備に当たった。
昭和19年)3月、湖南省長沙に移動し第11軍に編入され長沙の警備に当たった。
1944年10月、第20軍に編入され大陸打通作戦の一環である第二次湘桂作戦に参加した。
以後、華南で中国軍と交戦を続けたが、1945年(昭和20年)に入り華中に後退し、湖南省長沙で
防御準備を行っている中で終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 船引正之 中将 |
1943年6月- |
- |
参謀長:斎藤敏雄大佐 参謀:伊藤貞利中佐 高級副官:中尾音吉大尉
最終所属部隊
・歩兵第69旅団(広島):大岩実少将
・独立歩兵第51大隊:黒田儀一少佐
・独立歩兵第52大隊:桜井兵一大尉
・独立歩兵第53大隊:衛藤勇大尉
・独立歩兵第131大隊:香西裕少佐 第64師団通信隊:森繁太少佐
・歩兵第70旅団(山口):川勝郁郎少将 第64師団工兵隊:出射正大尉
・独立歩兵第54大隊:小林順一少佐 第64師団輜重隊:江藤新吾少佐
・独立歩兵第55大隊:梶尾政一少佐 第64師団野戦病院:大坪巽軍医少佐
・独立歩兵第132大隊:有馬典二少佐 第64師団病馬廠:正井夏雄獣医大尉
・独立歩兵第133大隊:桐谷幸昌少佐

編成地:安徽省廬州 通称号/略称:専 所属部隊:第13軍 最終地:安徽省廬州
1943年5月、独立混成第13旅団と名古屋師管で編成された諸部隊により安徽省廬州で編成された治安師団
第13軍に属し廬州方面の警備に当たった。同年9月、第17師団が徐州から南方に転用され、
第65師団が廬州に加えて徐州の警備を担当し、同地で終戦を迎えた。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
太田米雄 中将 |
1943年6月- |
- |
| |
坂口静夫 中将 |
1944年8月- |
熊本県、1945年3月予備役 |
| |
森茂樹 中将 |
1945年3月- |
- |
参謀長:折田貞重大佐 参謀:市川正中佐 高級副官:東義一少佐
最終所属部隊
・歩兵第71旅団(名古屋):大田熊太郎少将
・独立歩兵第56大隊:岡田功大尉
・独立歩兵第57大隊:星野輝夫大尉
・独立歩兵第58大隊:越本寿雄少佐 第65師団砲兵隊:花谷甫大尉
・独立歩兵第59大隊:村島英夫大尉 第65師団通信隊:前原正雄少佐
・歩兵第72旅団(名古屋):原田憲義少将 第65師団工兵隊:柿本早苗少佐
・独立歩兵第60大隊:南波留八少佐 第65師団輜重隊:久垣広文大尉
・独立歩兵第134大隊:藤本仁一大尉 第65師団第1野戦病院:進藤剛少佐
・独立歩兵第135大隊:高橋剛大尉 第65師団第2野戦病院:岩本正道少佐
・独立歩兵第136大隊:瀧本信愛少佐 第65師団病馬廠:太田代達夫大尉

編成地:台北 通称号/略称:敢 所属部隊: 最終地:台北
昭和19年)7月、台湾に駐屯していた独立混成第46旅団を基幹に、南方へ移動中に輸送船の戦没などで
台湾に留まっていた兵員により編成されている。所属の歩兵第249連隊には高砂族の人々も加えられていた。
第66師団は、台北、基隆方面でアメリカ軍の上陸に備えていたが、干戈を交えることなく終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 北川一夫 中将 |
1944年7月- |
- |
| 中島吉三郎 中将 |
1944年11月- |
- |
参謀長:鈴木君次大佐 参謀:南武正中佐 参謀:杉本保次少佐
最終所属部隊
歩兵第249連隊(台湾):高木環大佐 第66師団通信隊:藤岡孫市大尉
歩兵第304連隊(台湾):柳沢啓造大佐 第66師団兵器勤務隊:
歩兵第305連隊(台湾):青木功大佐 第66師団衛生隊:是永浩中佐
第66師団迫撃砲隊:八坂留吉少佐 第66師団第1野戦病院
第66師団速射砲隊: 第66師団第2野戦病院:
第66師団工兵隊: 第66師団病馬廠:
第66師団輜重兵隊:宮島福治大尉

編成地:江西省 九江 通称号/略称:檜 所属部隊:第20軍 最終地:中国 常寧
開戦後に中国に在った独立混成旅団を改編し、占領地の警備と治安維持を目的に編成した治安師団の一つ。
昭和17年)2月に華中で独立混成第14旅団を基幹に編成された。編成完了後、司令部を九江に置き、
前身であった独立混成第14旅団の任務を引き継ぎ九江付近の警備や治安維持に従事した。
1942年12月、大別山系の作戦、1943年(昭和18年)4月の江南殲滅作戦に参加。同年11月から
昭和19年)1月にかけて常徳殲滅作戦に参加し、漢寿を占領するなと戦果を挙げた。同年5月から大陸打通作戦の
一部である湘桂作戦に第11軍の直轄部隊として参加。衡陽攻略作戦に加わり、作戦終了後は衡陽の警備に従事
その後、第20軍に属し華南の中国軍と交戦した。
昭和20年)4月、華中方面防備のため常寧に移動し防備を固めていたが、その地で終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 中山惇 中将 |
1942年4月- |
- |
| 佐久間為人中将 |
1943年3月- |
- |
| 堤三樹男 中将 |
1944年7月- |
- |
参謀長:小合茂大佐 参謀:大場軍勝中佐 高級副官:山田誉六少佐
最終所属部隊
・歩兵第57旅団(大阪):黒瀬平一少将
・独立歩兵第61大隊:南部博之大尉 第68師団通信隊:三輪七郎少佐
・独立歩兵第62大隊:飯伏義盛少佐 第68師団工兵隊:北川三平少佐
・独立歩兵第63大隊:平松金松大尉 第68師団輜重隊:上山正敏中佐
・独立歩兵第64大隊:藤原稔少佐 第68師団野戦病院:森田清司軍医少佐
・歩兵第58旅団(和歌山):関根久太郎少将 第68師団病馬廠:御園生実三大尉
・独立歩兵第65大隊:横田忠広大尉
・独立歩兵第115大隊:安藤修道中佐
・独立歩兵第116大隊:麻生雄次郎大尉
・独立歩兵第117大隊:永里恒彦少佐

編成地:山西省 臨汾 通称号/略称:勝 所属部隊:第1軍 最終地:中国 上海近郊の嘉定
開戦後に中国に在った独立混成旅団を改編し、占領地の警備と治安維持を目的に編成した治安師団の一つ。
昭和17年)2月に独立混成第16旅団を基幹に編成された。独立混成第16旅団は、昭和15年)に第108師団が
復員した時、その人員・装備を引き継いでいるため、補充業務は弘前師管が担当した。
編成後、第1軍に属し、前身であった独立混成第16旅団の任務を引き継ぎ山西省中西部の警備や
治安維持に従事した。昭和18年)春に大行、同年秋に大岳の各作戦に参加。
昭和19年)3月、運城地区に移動し、同年6月、霊宝会戦に加わった。
昭和19年)5月から大陸打通作戦の一環である京漢作戦に参加
昭和20年)6月、上海近郊の嘉定に移動し防備を固めていたが、その地で終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 井上貞衛 中将 |
1942年4月- |
第14師団長、BC級戦犯指定死刑判決が終身刑に減刑で釈放された |
| 三浦忠次郎 中将 |
1943年10月 |
- |
参謀長:山本良一大佐 参謀:東富士雄少佐 高級副官:三明保真少佐
最終所属部隊
・歩兵第59旅団(弘前):伊黒清吾少将
・独立歩兵第82大隊:神保信彦中佐
・独立歩兵第83大隊:佐藤茂之大尉
・独立歩兵第84大隊:宮原九郎大尉 第69師団砲兵隊:内富佐市少佐
・独立歩兵第85大隊:西村勘治中佐 第69師団通信隊:難波一清少佐
・歩兵第60旅団(秋田):国司憲太郎少将 第69師団工兵隊:田浦清治郎少佐
・独立歩兵第86大隊:加藤鉦雄少佐 第69師団輜重隊:勝又繁雄中佐
・独立歩兵第118大隊:赤星正太少佐 第69師団野戦病院:松嶋次郎少佐
・独立歩兵第119大隊:進藤栄次郎中佐
・独立歩兵第120大隊:岡本一雄大尉

|
編成地:浙江省 寧波 通称号/略称:槍 所属部隊:第13軍-関東軍 最終地:嘉興方面~満州へ移動中
開戦後に中国に在った独立混成旅団を改編し、占領地の警備と治安維持を目的に編成した治安師団の一つ。
昭和17年)2月に独立混成第20旅団を基幹に、広島師管で編成された歩兵第62旅団を加えて編成された。
編成完了後、第13軍に属し、上海方面の警備や治安維持に従事した。4つの独立歩兵大隊から成る歩兵旅団
を2つ持ち、砲兵力を欠いた丙師団である。後に師団砲兵隊が所属した。
昭和17年)5月から浙贛作戦に参加。さらに、広徳、衢州、麗水、温州などでの作戦に従事した。
嘉興方面で防備を固めていたが、関東軍への転用が命じられ、満州に向けて出発した直後に終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 内田孝行 中将 |
1942年4月- |
- |
参謀長:中川俊二大佐 参謀:酒巻益次郎少佐 高級副官:西川理助中佐
最終所属部隊
・歩兵第61旅団(広島):今岡靖夫少将
・独立歩兵第102大隊:宍戸七郎大尉
・独立歩兵第103大隊:河野隆夫少佐
・独立歩兵第104大隊:海野鯱麻呂大尉
・独立歩兵第105大隊:大西粂蔵大尉 第70師団砲兵隊:望月淳一郎大尉
・歩兵第62旅団(広島):塘真策少将 第70師団通信隊:吉川義則大尉
・独立歩兵第121大隊:折田卓郎大尉 第70師団兵器勤務隊:北川永雪大尉
・独立歩兵第122大隊:藤江秋蔵大尉 第70師団工兵隊:日下康久少佐
・独立歩兵第123大隊:時広義人大尉 第70師団輜重隊:下川渉少佐
・独立歩兵第124大隊:田辺新之中佐 第70師団野戦病院:小森豊軍医少佐

編成地:満州 琿春 通称号/略称:命 所属部隊:関東軍-40軍 最終地:台湾
昭和17年)4月に琿春駐屯隊(歩兵第87連隊・第88連隊基幹)と第110師団所属の歩兵第140連隊を基幹に編成
同年6月編成完了後、関東軍に属し、満州東部のソ連国境付近の警備と防衛に従事した。
昭和19年2月、第71歩兵団司令部と歩兵大隊2個などを抽出して第5派遣隊を編成し、マリアナ諸島の
パガン島に送った。また、同時期に千島にも歩兵第140連隊の1個大隊を派遣した。師団主力も同年7月、
南方転用された第10師団に代わって満州北部のチャムスに移動し、南方転出に対応するための訓練を実施した。
昭和20年)1月、第10方面軍の第40軍に編入され「ガ号演習」の名で台湾に転用された。この転用に伴い、
第71歩兵団司令部と捜索第71連隊が廃止された。同年2月、台湾に到着後、
嘉義付近に布陣し連合国軍の侵攻に備えていたが、交戦することなく終戦を迎えた。
第5派遣隊
絶対国防圏の防衛強化のため、1944年2月の大陸令第948号に基づいて第71師団の隷下部隊から編成された。
第71歩兵団長の天羽馬八少将が派遣隊長となった。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 遠山登 中将 |
1942年4月- |
- |
参謀長:加藤守敏大佐 参謀:塚本政登士中佐 参謀:栗本栄三少佐 高級副官:上山義雄少佐
最終所属部隊
歩兵第87連隊(旭川):中村敏夫大佐 第71師団通信隊:保科年夫大尉
歩兵第88連隊(旭川):松浦龍一大佐 第71師団兵器勤務隊:野口求大尉
歩兵第140連隊(旭川):竹内主計中佐 第71師団第1野戦病院:
山砲兵第71連隊(旭川):石山虎夫大佐 第71師団制毒隊:石田林之助大尉
工兵第71連隊(旭川):佐藤久少佐 第71師団病馬廠:小田重夫大尉
輜重兵第71連隊:関広太中佐 第71師団防疫給水部:坂倉広海少佐

編成地:仙台 通称号/略称:伝 所属部隊:第11方面軍 最終地:日本本土
昭和19年)4月4日に留守第2師団を基幹に仙台で編成された。なお、この時点で内地に残っていた師団は、
前年の昭和18年5月14日に編成された師団のうちの、第43師団・第47師団・近衛第1師団の3個師団のみで
しかも第43師団は絶対国防圏の守備のためサイパンへの派遣が予定されていた。
師団は、当初東部軍の指揮下仙台に在ったが、翌1945年(昭和20年)2月1日に新設された第11方面軍戦闘
序列に編入され福島に移駐、機動打撃師団として関東或いは青森への増援を視野に
本土決戦に備えるなかで終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 大賀茂 中将 |
1944年4月- |
- |
| 重田徳松 中将 |
1944年7月- |
千葉県、第52軍司令官で千葉県佐倉で本土決戦に備え終戦 |
| 千葉熊治 中将 |
1944年4月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第134連隊(仙台):鈴木精一大佐 工兵第72連隊:山橋義明中佐
歩兵第152連隊(山形):山崎文一郎大佐 輜重兵第72連隊:小林正男少佐
歩兵第155連隊(若松):西岡貴一大佐 第72師団速射砲隊:城光寺崇夫少佐
野砲兵第72連隊:岩本東三中佐 第72師団通信隊:伊藤幸一少佐

編成地:名古屋 通称号/略称:怒 所属部隊:第13方面軍 最終地:本土
1944年7月、名古屋師管で編成され中部軍に編入。当初は知多半島から駿河湾にかけての地域の防衛を担当した。
のちに防衛担当区域は、豊橋南方から浜名湖までの区域に縮小され、師団司令部を名古屋から豊橋に移転した。
昭和20年)2月、新設された第13方面軍に編入した。本土決戦に備えている中で終戦を迎える
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
河田末三郎 中将 |
1944年7月 |
- |
参謀長:野々山秀美中佐 参謀:加藤元信少佐 参謀:堀部和夫少佐
最終所属部隊
歩兵第196連隊(名古屋):長谷川信哉大佐 第73師団通信隊:
歩兵第197連隊(静岡):手島治雄大佐 第73師団衛生隊:加藤光雄中佐
歩兵第198連隊(岐阜):吉川元大佐 第73師団第1野戦病院:飯島正章少佐
野砲兵第73連隊:野末一丸大佐 第73師団第4野戦病院:
工兵第73連隊:永沢正吾中佐 第73師団制毒隊:
輜重兵第73連隊:中川義弘中佐 第73師団兵器勤務隊:
第73師団速射砲隊:土屋嵓大尉 第73師団病馬廠:

編成地:旭川 通称号/略称:捻 所属部隊:第16方面軍 最終地:本土 九州 川内
1944年3月、旭川の第7師団が道東へ進出することに伴い、留守第7師団を基幹に編成され、5方面軍に
編入された。第77師団の担当区域は大雪山系より西側地域で、師団は勇払海岸に移動し陣地構築を行った。
昭和20年5月、九州に転用され第16方面軍に編入。当初は川内地域に駐屯し、
のち加治木に移り本土決戦に備えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 落合忠吉 中将 |
1944年4月- |
- |
| 中山政康 中将 |
1945年5月- |
- |
高級参謀:桑原勝雄中佐 高級副官:桜井平次郎少佐 兵器部長:藤田又八郎大佐
最終所属部隊
歩兵第98連隊(旭川):太田源助大佐 第77師団速射砲隊:新田次衛少佐
歩兵第99連隊(旭川):山口武臣大佐 第77師団通信隊:安田栄少佐
歩兵第100連隊(旭川):上原清二中佐 第77師団衛生隊:森清大尉
騎兵第77連隊(旭川):尾高三郎中佐 第77師団第1野戦病院:新川輝明大尉
山砲兵第77連隊(旭川):一柳恒市中佐 第77師団第4野戦病院:明石勝丈大尉
山砲兵第77連隊(旭川):一柳恒市中佐 第77師団制毒隊:間野清注意
輜重兵第77連隊(旭川):大野慶三少佐 第77師団兵器勤務隊:野村亮一中尉
第77師団編合
独立山砲兵第7連隊:田島昌治少佐 独立工兵第75大隊:石浜真琴少佐

編成地:朝鮮 羅南 通称号/略称:奏 所属部隊:第3軍 最終地:満州国境
ソ連に対する防衛強化のため、1945年2月、留守第19師団を基幹に、留守第20師団の一部を含めて編成された。
同年7月、関東軍隷下第3軍に編入され、朝鮮と満州国境に近い図們付近に移動し防禦を固めている最中、
ソ連軍の侵攻となった。所属の歩兵第291連隊第3大隊は大きな損害を受けたが、多数の部隊は本格的な戦闘を
交える以前に停戦となった。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
太田貞昌 中将 |
1945年2月- |
- |
参謀長:品部孝晴大佐 参謀:平田五郎中佐 参謀:浅野祐吾少佐 兵器部長:瀬尾善一大佐
最終所属部隊
歩兵第289連隊(羅南):松山圭助大佐 輜重兵第79連隊(鏡城):遠藤卓次少佐
歩兵第290連隊(会寧):今堀元貞大佐 第79師団通信隊:
歩兵第291連隊(羅南):杉山香也大佐 第79師団制毒隊:
騎兵第79連隊(羅南):稲波弘次少佐 第79師団兵器勤務隊:
山砲兵第79連隊(羅南):成川一郎中佐 第79師団病馬廠:
工兵第79連隊(会寧):本村太郎少佐

編成地:宇都宮 通称号/略称:納 所属部隊:第36軍 最終地:本土
昭和19年4月4日に、留守第51師団を基幹に宇都宮で編成された。同年7月21日に新設された第36軍戦闘序列
に編入され、機動打撃師団として本土決戦に備え、終戦を迎えた。
なお、自活のため営農活動もしており、秘匿号が納(のう)であったことから、農部隊と称された。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
古閑健 中将 |
昭和19年4月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第171連隊(宇都宮):今村重孝大佐 第81師団速射砲隊
歩兵第172連隊(水戸):桑利彦中佐 第81師団通信隊
歩兵第173連隊(高崎): 江口小一郎大佐 第81師団兵器勤務隊
野砲兵第81連隊:前田知玄大佐 第81師団衛生隊
工兵第81連隊:吉田利行大佐 第81師団第1野戦病院
輜重兵第81連隊:宮崎三郎大佐 第81師団第4野戦病院

編成地:姫路 通称号/略称:突 所属部隊:第53軍 最終地:小田原
昭和19年7月、留守第54師団を基幹に姫路で編成され中部軍に編入。同年末、沖縄から第9師団が台湾に
転出するため、その補充として第84師団を沖縄に派遣することが検討されたが、大本営は本土防衛を重視し
派遣を中止した。昭和20年)4月、第84師団は第53軍に属し小田原、沼津、国府津付近に展開し、本土決戦に備え
えて防禦を固めていたが、戦闘を交えることなく終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 小倉達次 中将 |
1944年7月- |
第131師団長の師団長として粤漢鉄道沿線の警備に当たった。 |
| 佐久間為人 中将 |
1945年2月- |
- |
参謀長:杉本和二郎大佐 参謀:田坂盛夫少佐 参謀:梶田倫正少佐
最終所属部隊
歩兵第199連隊(姫路):栗栖晉大佐 第84師団通信隊:小河原郁文大尉
歩兵第200連隊(姫路):川上芳雄大佐 第84師団兵器勤務隊
歩兵第201連隊(姫路):松本鹿太郎大佐 第84師団衛生隊
野砲兵第84連隊:川崎盛利大佐 第84師団第1野戦病院
工兵第84連隊:釜付敬二少佐 第84師団第4野戦病院
輜重兵第84連隊(堺):小林吉二大佐 第84師団制毒隊
第84師団速射砲隊:川崎平吾少佐 第84師団病馬廠

編成地:久留米 通称号/略称:積 所属部隊:第57軍 最終地:鹿児島 志布志
昭和19年)4月4日に留守第56師団を基幹に久留米で編成された。当初は西部軍の指揮下に在ったが、
翌1945年(昭和20年)4月8日には新設された第57軍戦闘序列に編入、鹿児島に在って志布志湾沿岸の
守備を担当、沿岸配備師団が防いでいるところに出撃し攻撃をかける機動打撃師団として本土決戦に備える
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 伊佐一男 中将 |
昭和19年4月- |
- |
| 芳仲和太郎 中将 |
昭和20年5月 |
- |
所属部隊
歩兵第187連隊(福岡):可西清二大佐 野砲兵第86連隊:佐川武彦中佐
歩兵第188連隊(大村):石井元良大佐 輜重兵第86連隊:瀬川孫兵衛大佐
歩兵第189連隊(久留米):山方知光大佐 第86師団通信隊
工兵第86連隊:有利正少佐
第86師団速射砲隊
以下同じ部署

編成地:樺太 通称号/略称:要 所属軍:第5方面軍 最終地:樺太 敷香町
1939年5月23日に南樺太の上敷香に樺太混成旅団が新設された。第7師団から抽出された歩兵1個大隊
(樺太歩兵第1大隊)と砲兵1個中隊(樺太山砲兵連隊第1中隊)が基幹戦力だった。
翌1940年末には歩兵第25連隊が札幌から移駐して、樺太歩兵第1大隊を吸収した。
1945年2月、本土決戦に備えて樺太にも師団の設置が図られ、樺太混成旅団を基幹に、歩兵第306連隊
と迫撃砲1個大隊を加えて、第88師団が編成された。師団は第5方面軍に編入された。
同年8月9日、国境近くの敷香町武意加の国境警察に加えられたソ連軍の砲撃により戦闘が始まった。
8月15日までは歩兵第125連隊の抵抗により陣地を死守した。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
峯木十一郎 中将 |
1945年3月 |
- |
参謀長:鈴木康大佐 参謀:筑紫富士雄中佐 高級副官:太田寿男中佐
最終所属部隊
歩兵第25連隊(札幌):山沢饒大佐 輜重兵第88連隊:小山国治少佐
歩兵第125連隊(旭川):小林与喜三大佐 第88師団通信隊:鈴木利孝大佐
歩兵第306連隊(旭川):高沢健児大佐 第88師団兵器勤務隊:萱沼広之中佐
山砲兵第88連隊:日野常蔵大佐 第88師団衛生隊:横山給八郎少佐
工兵第88連隊:東島時松少佐 第88師団病馬廠:遠藤清司獣医大尉

編成地:旭川 通称号/略称:摧(さい) 所属軍:第5方面軍 最終地:千島列島
昭和18年)8月、南千島の防衛のため歩兵2個大隊基幹の千島第3守備隊の編成が下令され、翌月に完結した。
昭和19年4月に千島第3守備隊司令部と歩兵第35連隊・歩兵第140連隊・独立山砲兵第3連隊の各1個大隊を
をもって、独立混成第8連隊(通称号:北部12608部隊)の編成が下令され、5月10日に小樽市で完結した。
1945年2月29日、独混第43旅団を混成第3旅団、独混第69旅団を混成第4旅団に改称し、第77歩兵団司令部とも
合流した第89師団の編成が下令された。3月27日に師団は編成完結し、第5方面軍に編入された。
師団主力は択捉島に駐屯し防禦を固め、師団の一部は色丹島に派遣された。
千島列島でのソ連軍との戦闘は終戦後、8月18日から開始された。本格的な戦闘は北千島の占守島で行われた
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 小川権之助 中将 |
1945年3月 |
- |
参謀長:森田利勝大佐 参謀:丸山武之中佐 経理部長:木村茂主計中佐
最終所属部隊
・混成第3旅団司令部(仙台):旅団長 志波信孝少将
・独立歩兵第294大隊:森田正少佐 ・独立歩兵第419大隊:三原録郎少佐
・独立歩兵第295大隊:小出貞治少佐 ・独立歩兵第420大隊:蘇武義美少佐
・独立歩兵第296大隊:重富広一少佐 ・混成第3旅団砲兵隊:広川礼順少佐
・独立歩兵第297大隊:村上進少佐 ・混成第3旅団工兵隊:平井雄三大尉
・混成第4旅団司令部(旭川):旅団長 土井定七少将
・独立歩兵第421大隊:佐藤政美大尉 ・混成第4旅団砲兵隊:鏡清次少佐
・独立歩兵第422大隊:松野直司少佐 ・混成第4旅団通信隊:
・独立歩兵第423大隊:田中耕治少佐 ・混成第4旅団作業隊:
・独立歩兵第460大隊:菊田義和少佐
・独立歩兵第461大隊:亀井源一大尉
第89師団通信隊:水野健作少佐 第89師団兵器勤務隊:
第89師団衛生隊:与倉守雄少佐 千島第3陸軍病院:跡部鉄郎軍医大佐

編成地:千島列島 通称号/略称:先 所属軍:第27軍- 最終地:千島列島 占守島
1944年4月、千島第1守備隊を基幹に編成され、第27軍に編入された。その担当区域は、千島列島の
占守島から捨子古丹島までで、師団主力は占守島、幌筵島に配置された。
千島列島でのソ連軍との戦闘は終戦後、8月18日から開始された。本格的な戦闘は占守島で行われ、守備隊は
ソ連軍に対して優勢であったが、第5方面軍の命令に従い21日に現地での停戦が最終的に成立し、
23日に武装解除された。(詳細は占守島の戦い参照)
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
堤不夾貴 中将 |
1944年4月 |
- |
参謀長:柳岡武大佐 参謀:角張清少佐 高級副官:山口定大佐 経理部長:木村重郎主計中佐
最終所属部隊
・歩兵第73旅団(旭川):杉野巌少将
・独立歩兵第282大隊:桜井平次郎少佐 ・独立歩兵第286大隊:桜井中佐
・独立歩兵第283大隊:竹下三代二少佐 ・独立歩兵第287大隊:得平操中佐
・独立歩兵第284大隊:野口谷五郎少佐 ・歩兵第73旅団通信隊:
・独立歩兵第285大隊:広江重郎大佐
・歩兵第74旅団(旭川):佐藤政治少将
・独立歩兵第288大隊:橋口俊成少佐 ・独立歩兵第292大隊:小川与之吉大尉
・独立歩兵第289大隊:山田徳蔵少佐 ・独立歩兵第293大隊:小川伊佐雄大佐
・独立歩兵第290大隊:吉野貞吾少佐 ・歩兵第74旅団通信隊:桃井亀蔵大尉
・独立歩兵第291大隊:林邦彦大尉
千島第1陸軍病院:朝枝淳一軍医中佐
戦車第11連隊:池田末男大佐 戦車第11連隊:池田末男大佐
独立戦車第2中隊:伊藤力雄大尉 第91師団通信隊:薄井善春少佐
第91師団兵器勤務隊:家永大次少佐 第91師団衛生隊:与倉守雄少佐
第91師団工兵隊:小針通少佐 第91師団防空隊:鈴木村治中佐
第91師団輜重隊:木村森茂大尉 第91師団速射砲隊:田口英男少佐
第91師団第1砲兵隊:加瀬谷陸夫中佐 第91師団第2砲兵隊:坂口元男中佐
第91師団第11対空無線隊:鈴木晋平軍曹

編成地:金沢 通称号/略称:決 所属軍:第36軍 最終地:千葉北部 九十九里浜
昭和19年)7月、留守第52師団を基幹に陸軍歩兵学校、陸軍野戦砲兵学校、陸軍工兵学校の教導連隊の
人員・馬匹を加えて編成され、第36軍に編入。第93師団は本土決戦において関東地方に配置することが予定
され、師団主力を御殿場に、歩兵第203連隊を千葉県北部に、歩兵第204連隊を松本に配置した。
その後、連合国軍の九十九里浜上陸に備えるため千葉県北部に移動したが、戦闘を交えることなく終戦を迎えた。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
末藤知文 中将 |
1944年7月 |
- |
| |
山本三男 中将 |
1945年3月 |
- |
参謀長:中村三郎大佐 参謀:篠田正治少佐 参謀:井内春二少佐 高級副官:長谷川良成中佐
最終所属部隊
歩兵第202連隊(富山):河合慎助大佐 工兵第93連隊:原亀治中佐
歩兵第203連隊(金沢):藤原忠次大佐 輜重兵第93連隊:白岩浩治少佐
歩兵第204連隊(富山):俵健次郎大佐 第93師団速射砲隊:神谷秀雄少佐
騎兵第93連隊:安高音吉大佐 第93師団通信隊:山下宗八少佐
山砲兵第93連隊:山口嘉良大佐 第93師団兵器勤務隊
その他

編成地:マレー半島 通称号/略称:威烈 所属軍:第29軍 最終地:マレー北部
昭和19年)10月、インパール作戦の失敗などによりビルマ戦線は崩壊寸前に陥る危機的な状況となった。
そのような中で、クアラルンプールに所在していた第12独立守備隊、第18独立守備隊などを基幹として
第94師団が編成され、第29軍に編入された。その担当区域はタイ南部からマレー北部にかけての地域であった。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
四手井綱正中将 |
1944年10月 |
京都、関東軍総参謀副長任地に向かう途中、台北の飛行機事故により殉職 |
| |
井上芳佐 中将 |
1945年5月 |
- |
参謀長:今村英次大佐 参謀:富永亀太郎中佐 参謀:福田重雄少佐
最終所属部隊
・第94歩兵団:青木一枝大佐
・歩兵第256連隊(大阪):羽生善良中佐
・歩兵第257連隊(大阪):乙守文策大佐
・歩兵第258連隊(大阪):山本勇大佐
野砲兵第94連隊:山澄邦太郎大佐 第94師団通信隊:
工兵第94連隊:笹良照中佐 第94師団衛生隊:今井秋三郎少佐
輜重兵第94連隊:松田正松大佐 第94師団防疫給水部:川原俊男軍医大尉

編成地:京城 通称号/略称:玄 所属軍:第58軍 最終地:済州島
太平洋戦争の末期に本土決戦準備のため急造された54個師団の一つであり、済州島の防備強化を目的に
編成された師団である。1945年2月10日、朝鮮龍山で留守第20・留守第30・留守第56師団を基幹に編成された。
編成完結後、済州島に上陸配置され、当地の防備を担当した。同年4月に第58軍戦闘序列に編入され
連合国軍の上陸に備えて防禦陣地の構築などを行っていたが、戦闘を交えることなく終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 飯沼守 中将 |
1945年2月 |
名古屋、昭和17年予備役より第96師団長となり済州島に赴任 |
| 玉田美郎 中将 |
1945年5月 |
昭和19年)-海上機動第2旅団長 |
参謀長:清水孝太郎大佐 参謀:八坂繁広中佐・小岩井光夫少佐
最終所属部隊
歩兵第292連隊(福岡):菅道教大佐 第96師団迫撃砲隊:進士正吉少佐
歩兵第293連隊(大村):越智鶴吉大佐 第96師団工兵隊:
歩兵第294連隊(大村):菊池安一大佐 第96師団通信隊:
第96師団野戦病院:

編成地:フィリピン・ミンダナオ島 通称号/略称:拠 所属部隊:第35軍 最終地:フィリピンタバオ北西山地
1944年6月、フィリピン、ミンダナオ島所在の独立混成第30旅団と、日本本土で編成された部隊により編成され、
第35軍に編入された。第100師団は独立混成第30旅団から任務を引き継ぎダバオに駐屯した。
昭和20年)4月17日、アメリカ軍がミンダナオ島西海岸のコタバトに上陸しタバオへ侵攻した。
優勢なアメリカ軍に圧迫され、師団はタバオ北西山地に退却し、自活をしながら終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 原田次郎 中将 |
1944年6月 |
- |
参謀長:服部宗一大佐 参謀:大野吉弘中佐 参謀:大和田浩少佐 高級副官:小川久吉少佐
最終所属部隊
・歩兵第75旅団(津):河添連少将
・独立歩兵第163大隊:志鶴林蔵大佐 ・独立歩兵第166大隊:内匠豊中佐
・独立歩兵第164大隊:田中徳実中佐 ・歩兵第75旅団通信隊:池田彰郎中尉
・独立歩兵第165大隊:多賀寛助中佐 ・歩兵第75旅団作業隊:高田敬三大尉
・歩兵第76旅団(静岡):栃木功少将
・独立歩兵第167大隊:吉山徳雄中佐 ・独立歩兵第353大隊:山田藤栄少佐
・独立歩兵第168大隊:片桐広一大佐 ・歩兵第76旅団通信隊:
・独立歩兵第352大隊:竹下兼雄少佐
第100師団作業隊: 第100師団輜重隊:中溝利雄少佐
第100師団砲兵隊:中井一雄少佐 第100師団野戦病院:清水清少佐
第100師団工兵隊:白井茂中佐 第100師団病馬廠:稲川善夫大尉
第100師団通信隊:猪瀬徳大尉 第100師団防疫給水部:伊藤武男少佐
 |
第101師団は昭和15年2月廃止

編成地:フィリピン ヴィサヤ諸島 通称号/略称:抜 所属部隊:第35軍 最終地:フィリピン セブ島
フィリピン、ビサヤ諸島において内地で仮編成した2個歩兵大隊、師団後方部隊などを編合して1944年7月編成
不明、レイテ島に渡りレイテ決戦に敗れ、セブ島で終戦を迎えた。
| 編成後 |
| 師団長は、着任と同時に司令部をセブ島セブに置き、歩兵旅団の主力をパナイ島とセブ島南部地区配備を部署し、 |
| 引き続き治安作戦と飛行場設定を命じた。同年8月初旬には、新設の第35軍戦闘序列に編入された。 |
| レイテ島の戦い |
| 10月中旬に米軍はレイテ湾のスルアン島に上陸、「捷一号作戦」が発動され第35軍司令官も「鈴号作戦」を令し、 |
| 師団から2個大隊をレイテ島へ急行させた。 |
| ビサヤ諸島の戦いと終戦 |
| 同島の戦局が悪化したため、12月下旬に師団長は島からの撤収を決心し、司令部員と一部兵力を連れ、 |
| 1945年1月にセブ島へ渡航した。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
福栄真平 中将 |
1944年6月 |
戦犯容疑で銃殺刑が執行された |
参謀長:和田俐大佐 参謀:渡辺英海大佐 丸山正寅中佐 有富重勝中佐 鈴木清中佐 金子正二少佐
副官:清水高蔵少佐
最終所属部隊
・歩兵第77旅団(熊本):河野毅中将
・独立歩兵第170大隊:戸塚良一中佐 ・独立歩兵第354大隊:堀久謙少佐
・独立歩兵第171大隊:田辺侃二中佐 ・歩兵第77旅団通信隊:中村秀大尉
・独立歩兵第172大隊:山口正一大佐 ・歩兵第77旅団作業隊:川田清中尉
・歩兵第78旅団(熊本):万城目武雄少将
・独立歩兵第169大隊:西村茂中佐 ・独立歩兵第355大隊:野瀬幸雄少佐
・独立歩兵第173大隊:大西精一中佐 ・歩兵第78旅団通信隊:四家肇中尉
・独立歩兵第174大隊:尾家刢大佐 ・歩兵第78旅団作業隊:小堀重次大尉
第102師団砲兵隊:斎藤正一少佐 第102師団野戦病院:
第102師団工兵隊:武田喜久雄少佐 第102師団病馬廠:山井忠獣医大尉
第102師団通信隊:山根一郎少佐 第102師団防疫給水部:鈴木政雄軍医少佐
第102師団輜重隊:正角竹次郎少佐

編成地:ルソン島 通称号/略称:駿 所属部隊:第14方面軍 最終地:ルソン島
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
村岡豊 中将 |
1944年6月 |
- |
参謀長:岡本孝行大佐
最終所属部隊
・歩兵第79旅団(熊本):荒木正二中将 ・独立歩兵第356大隊:瀧上良一少佐
・独立歩兵第175大隊:山下末吉少佐 ・歩兵第79旅団通信隊:
・独立歩兵第176大隊:杉木守大佐 ・歩兵第79旅団作業隊:
・独立歩兵第178大隊:松原勘一少佐
・歩兵第80旅団(熊本):湯口俊太郎少将 ・独立歩兵第357大隊:粂勇少佐
・独立歩兵第177大隊:坂巻隆次大佐 ・歩兵第80旅団通信隊:
・独立歩兵第179大隊:一瀬末松大佐 ・歩兵第80旅団作業隊:
・独立歩兵第180大隊:有園善行大佐
第103師団砲兵隊:羽田三蔵少佐 第103師団野戦病院:岩崎太郎少佐
第103師団工兵隊:竹内忠中佐 第103師団病馬廠:西喜久助中尉
第103師団通信隊:甲斐清一大尉 第103師団防疫給水部:大柴五八郎少佐
第103師団輜重隊:北原芳富少佐
師団に所属していた著名人
師団砲兵隊に所属し、将校としては数少ない生存者である故・山本七平が、第103師団での出来事を詳細に
記している(『一下級将校の見た帝国陸軍』など)。

編成地:大阪 通称号/略称:鳳 所属部隊:第23軍 最終地:広東省恵州
昭和13年)6月16日に留守第4師団の担当で編成された特設師団であり、中国大陸での作戦に従事した。
最初の三単位師団として編成された第26師団より後の編成であるが、第104師団は2個連隊構成の
歩兵旅団を2つ持つ甲編成の作戦師団として編成された。
編成完結とともに満州に派遣され、この時期張鼓峰事件が発生したため琿春方面に出動したが、8月11日に
停戦となり大連に帰還する。その後、9月19日に新設された第21軍戦闘序列に編入広東作戦に投入され、
10月12日に第18師団とともにバイアス湾から奇襲上陸し広東を攻略した。広東陥落後は従化付近に
駐屯し、警備と治安維持に従事する。
開戦後も第23軍隷下華南に在り、1944年(昭和19年)に大陸打通作戦が開始されると、第二段湘桂作戦に
参加し9月16日広東省肇慶を、11月4日広西省武宣を攻略、6日には象県を占領する。
粤漢作戦では1945年(昭和20年)1月15日広東省恵州を攻略、18日には海豊を占領する。
その後は海豊周辺に展開し連合国軍の中国南部上陸に備えていたが、連合国軍の
中国南部上陸は無く、同地で終戦を迎えた。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
三宅俊雄 中将 |
昭和13年6月- |
- |
| |
浜本喜三郎 中将 |
昭和13年11月- |
京都、北部軍司令官後予備役、、京都師管区司令官 |
| |
菰田康一 中将 |
昭和15年12月 |
- |
| |
鈴木貞次 中将 |
昭和17年8月- |
- |
| |
末藤知文 中将 |
昭和20年3月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第108連隊(大阪):青野三郎大佐 輜重兵第104連隊:門口元一中佐
歩兵第137連隊(大阪):藤本末夫大佐 第104師団通信隊:猪瀬徳大尉
歩兵第161連隊(和歌山):清水圓大佐 第104師団兵器勤務隊:福桝数一大尉
野砲兵第104連隊:横川止知少佐 第104師団野戦病院:福田一郎軍医少佐
工兵第104連隊:森立身少佐 第104師団病馬廠:福岡孝寿獣医少佐

編成地:ルソン島 通称号/略称:謹 所属部隊:第14方面軍 最終地:ルソン島
1944年6月、フィリピン、ルソン島南部に所在した独立混成第33旅団を基幹に編成され、第14方面軍の隷下
に入った。第105師団は独立混成第33旅団の担当地域を引き継ぎ、師団主力はルソン島ビコル半島地区、師団の
一部は歩兵第82旅団長河嶋修少将の河嶋支隊に属してラモン湾の防衛を担任した。
第105師団は、師団主力の本隊、河嶋兵団、野口兵団の3つに戦力を分割した状態で、ルソン島の
防衛にあたることになる。第105師団司令部は、この転進の指導のために参謀や副官の多くを歩兵第81旅団や
歩兵82旅団に派遣、配属していた。そのため第105師団司令部は要員の不足という問題に直面する。
昭和20年)1月9日、アメリカ軍がリンガエン湾に上陸し、第105師団主力はカガヤン付近の戦いで破れた後、
優勢なアメリカ軍に圧迫され山岳地帯に退却し、キアンガンの防衛を終戦まで行った。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
津田美武 中将 |
1944年6月 |
- |
参謀長:中沢勝三郎大佐
最終所属部隊
・歩兵第81旅団(広島):野口進少将
・独立歩兵第181大隊:黒宮隆文大佐 ・独立歩兵第185大隊:杉山欽次郎中佐
・独立歩兵第182大隊:木村忠孝少佐 ・歩兵第81旅団通信隊:
・独立歩兵第183大隊:牟田元次大佐 ・歩兵第81旅団作業隊:
・歩兵第82旅団(浜田):河嶋修少将
・独立歩兵第184大隊:二宮曻中佐 ・独立歩兵第359大隊:大藪富雄少佐
・独立歩兵第186大隊:沖田一夫大佐 ・歩兵第82旅団通信隊:
・独立歩兵第358大隊:笠間哲行少佐 ・歩兵第82旅団作業隊:
第105師団砲兵隊:漆谷英人少佐 第105師団野戦病院:遠藤信義少佐
第105師団工兵隊:落合鋠一大佐 第105師団病馬廠:吉田清作大尉
第105師団通信隊:鹿沼次郎大尉 第105師団防疫給水部:中嶋清博少佐
第105師団輜重隊:吉田泰助少佐

編成地:満州 通称号/略称:凪 所属部隊:関東軍→44軍 最終地:長春
太平洋戦争中期以降、多くの師団が満州から南方に転用されたため、1944年(昭和19年)5月16日に、
阿爾山(アルシャン)駐屯隊と独立混成第7連隊を基幹として第107師団が編成された。
昭和20年)8月9日のソ連対日参戦時には阿爾山南方に陣を構えていた。関東軍総司令部からの命令により、
8月12日に、600km南方の新京(しんきょう、現在の長春)方面へ撤退を開始した。
8月25日に、音徳爾西方でソ連軍と遭遇して戦闘となり、これを撃退した。驚いたソ連軍の要請により、
関東軍参謀が派遣され、2日間の捜索後に師団を発見して停戦命令が伝えられた。終戦後の戦闘で
1500名あまりが戦死、さらにその後のシベリア抑留により2000名あまりが死亡した。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
安部孝一 中将 |
昭和19年5月 |
宮城県、シベリア抑留 |
最終所属部隊
歩兵第90連隊(弘前):松村重夫大佐 輜重兵第107連隊:錦織喜八郎少佐
歩兵第177連隊(弘前):光本勝男大佐 第107師団挺進隊
歩兵第178連隊(秋田):堀尾茂光大佐 第107師団通信隊:畠中三次郎少佐
捜索第107連隊:進藤義彦少佐 第107師団兵器勤務隊
野砲兵第107連隊:角田文雄大佐 第107師団防疫給水部:佐久間栄枝軍医少佐
工兵第107連隊:永井清少佐 第107師団病馬廠

編成地:弘前・満州 通称号/略称:祐 所属部隊:第3方面軍 最終地:満州
第108師団は、1937年8月24日、留守第8師団の担当で新設された。昭和15年2月に廃止された。
昭和19年7月、満州の第9独立守備隊を基幹に再編成され、関東防衛軍の隷下に入り、満州と中国の
境界線付近 の警備等を担当した。1945年(昭和20年)7月、第3方面軍の直轄となり、翌月、ソ連軍の
侵攻に備えたが、本格的な戦闘となる前に終戦を迎えた。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
磐井虎二郎 中将 |
1944年7月 |
- |
参謀長:小堀晃大佐 参謀:酒井治隆中佐 高級副官:河野桂十郎少佐
最終所属部隊
歩兵第240連隊:中村赳大佐 第108師団通信隊
歩兵第241連隊:斎藤義夫大佐 第108師団工兵隊:佐々木行矩少佐
歩兵第242連隊:渡辺進大佐 第108師団輜重隊
騎兵第171連隊:井原清人少佐 第108師団衛生隊:赤川梅太郎中佐
野砲兵第108連隊 第108師団防疫給水部
第108師団挺進大隊

編成地:金沢・小笠原 通称号/略称:膽(たん) 所属部隊:第1軍→大本営 最終地:小笠原・硫黄島
昭和19年5月、父島要塞守備隊を基幹に再編成され、大本営直属の小笠原兵団(兵団長:栗林忠道・
第109師団長兼務)の隷下に入った。混成第1旅団を父島に、独立第2旅団を硫黄島に、混成第1連隊を
母島に配備しアメリカ軍からの侵攻に備えた。1945年(昭和20年)年2月16日からの硫黄島の戦いにおいて、
栗林師団長のもと激戦を続けたが、同年3月26日に硫黄島守備隊は全滅(玉砕)した。
その後、父島の混成第1旅団をもって第109師団を再編し、アメリカ軍の空襲を受けながら終戦まで守備を行った。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
栗林忠道 中将 |
1944年5月- |
長野県、昭和20年2月26日硫黄島にて戦死 陸海軍で最も若い陸軍大将 |
| |
立花芳夫 中将 |
1945年3月 |
愛媛県、軍事裁判で絞首刑判決(父島に駐留中に米軍捕虜を斬殺し人肉食)
硫黄島の109師団玉砕に伴い、混成第1旅団を第109師団に第109師団長 |
硫黄島戦前の構成
参謀長:堀静一 大佐 ⇒ 高石正 大佐 作戦参謀:中根兼次 中佐 情報参謀:西川猛雄 中佐
築城参謀:吉田紋三 少佐 後方参謀:山内保武 少佐 参謀:堀江芳孝 少佐 高級副官:小元久米治 少佐
所属部隊
・混成第1旅団:立花芳夫 少将
・独立歩兵第303大隊:安東九州男 少佐 ・混成第1旅団工兵隊:來代長平 大尉
・独立歩兵第308大隊:的場末男 少佐 ・独立歩兵第306大隊:吉岡直彦 大尉
・独立歩兵第304大隊:中北実 少佐 ・混成第1旅団通信隊
・混成第1旅団砲兵隊 ・独立歩兵第307大隊:加藤武宗 大尉
・独立歩兵第305大隊:工藤文雄 大尉 ・混成第1旅団野戦病院
・混成第2旅団:大須賀応少将 ⇒ 千田貞季少将 (5000人を父島より)
・独立歩兵第309大隊:粟津勝太郎 大尉 ・独立歩兵第311大隊:芦田元一大尉⇒ 辰己祭夫
・独立歩兵第314大隊:伯田義信 少佐 ・独立歩兵第312大隊:長田謙次郎 大尉
・独立歩兵第310大隊:岩谷為三郎 少佐 ・独立歩兵第313大隊:
・混成第2旅団砲兵隊:前田一雄 少佐 ・混成第2旅団工兵隊:大塚家一郎 中尉
・独立歩兵第312大隊:長田謙次郎 大尉 ・混成第2旅団通信隊:小園二三夫 大尉
・混成第2旅団野戦病院:野口巌 軍医大尉
第109師団砲兵隊 第109師団突撃中隊
第109師団高射砲隊:東庄太郎 少佐 第109師団工兵隊:前川陽治 少佐
第109師団迫撃砲隊 第109師団通信隊:森田豊吉 中尉
第109師団噴進砲中隊:横山義雄 大尉 第109師団警戒隊
第109師団野戦病院
小笠原兵団直轄
歩兵第145連隊(鹿児島):池田増雄 大佐(2700人) 戦車第26連隊:西竹一 中佐 (兵員600人)
重砲兵第9連隊:大坪四郎 中佐 混成第1連隊:政木均 大佐
独立混成第12連隊:坂田善市 大佐(南鳥島守備隊) 独立混成第17連隊:飯田雄亮 大佐
独立歩兵第274大隊:黒沢繁 大尉(母島守備隊) 独立歩兵第275大隊:竹中直二 少佐(兄島守備隊)
独立歩兵第276大隊:岩谷好 少佐(母島守備隊) 独立機関銃第1大隊:川南洸 大尉
独立機関銃第2大隊:川崎時雄 大尉 独立速射砲第8大隊:清水一 大尉
独立速射砲第9大隊:小久保蔵之助 少佐 独立機関銃第10大隊:松下久彦 少佐
独立速射砲第11大隊:野手保次 大尉 独立速射砲第12大隊:早内政雄 大尉
独立臼砲第20大隊:水足光男 大尉 中迫撃砲第2大隊:中尾猶助 少佐
中迫撃砲第3大隊:小林孝一郎 少佐 独立迫撃砲第1中隊
その他直轄部隊
船舶工兵第17連隊:相川順一郎 少佐 工兵第2中隊:武蔵野菊蔵 中尉
要塞建築勤務第5中隊:谷川純忠 中尉 野戦作井第21中隊:川中良夫 中尉
父島陸軍病院:柴田完 軍医中佐
硫黄島戦時の構成 終戦時の構成
参謀:堀江芳孝 少佐
所属部隊
独立歩兵第303大隊:安東九州男 少佐 父島陸軍病院:柴田完 軍医中佐
独立歩兵第304大隊:中北実 少佐 混成第1連隊:政木均 大佐
独立歩兵第305大隊:工藤文雄 大尉 独立混成第12連隊:坂田善市 大佐
独立歩兵第306大隊:吉岡直彦 大尉 独立混成第17連隊:飯田雄亮 大佐
独立歩兵第307大隊:加藤武宗 大尉 独立歩兵第274大隊:黒沢繁 大尉
独立歩兵第308大隊:的場末男 少佐 独立歩兵第275大隊:竹中直二 少佐
重砲兵第9連隊:大坪四郎 中佐 独立歩兵第276大隊:岩谷好 少佐
第109師団砲兵隊 船舶工兵第17連隊:相川順一郎 少佐
第109師団工兵隊:山本将八 大尉

編成地:姫路 通称号/略称:鷲 所属軍:第12軍 最終地:中国 洛陽
昭和13年)6月16日、姫路でに留守第10師団の担当で編成された特設師団である。北京付近の警備
開戦後も北支那方面軍隷下華北に在りこの方面のさまざまな作戦に参加した。1942年(昭和17年)5月には
歩兵第140連隊を第71師団に転用、歩兵3個連隊制師団に改編された。
昭和19年3月には、第12軍戦闘序列に編入大陸打通作戦第一段の京漢作戦に参加、洛陽を攻略し占領後警備
昭和20年)4月には、老河口作戦で飛行場破壊作戦に従事し、作戦終了後洛陽に戻り、同地で終戦を迎えた。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
桑木崇明 中将 |
1938年6月- |
石川県、(昭和14年)12月、予備役 |
| |
飯沼守 中将 |
1939年12月- |
愛知県、第96師団長となり済州島に赴任し終戦 |
| |
林芳太郎 中将 |
1942年8月- |
京都府、近衛第3師団長、東部軍管区付となり終戦 |
| |
木村経広 中将 |
1944年7月- |
- |
最終所属部隊
歩兵第110連隊(姫路):中村武男大佐 第110師団輜重隊:尾崎真三大尉
歩兵第139連隊(姫路):槇林太夫大佐 第110師団通信隊:野村豊大尉
歩兵第163連隊(松江):河野又四郎大佐 第110師団第1野戦病院:清水三郎軍医少佐
第110師団砲兵隊 第110師団第2野戦病院:島義仁軍医大尉
第110師団工兵隊:願念仙一大尉 第110師団病馬廠:清水保寛獣医大尉

編成地:善通寺 通称号/略称:市 所属軍:第3軍-58軍 最終地:済州島
昭和19年7月、綏陽において第9独立守備隊と南方に転用となった部隊の残留者により第111師団が編成され
第3軍に編入。編成後、満州東部の警備と治安維持に当る。昭和20年)4月、満州から朝鮮半島南部に転用され
第17方面軍隷下となり、第58軍が新設されると、その指揮下に編入された。同年5月、済州島に移動し、
合国軍の上陸に備えて防禦陣地の構築などを行っていたが、戦闘を交えることなく終戦を迎えた。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
岩崎民男 中将 |
1944年7月- |
- |
参謀長:芝田経一大佐 参謀:辛島泰善少佐 高級副官:飯田一三少佐
最終所属部隊
歩兵第243連隊(徳島):佐藤健吉大佐 第111師団砲兵隊:
歩兵第244連隊(高知):中山修大佐 第111師団工兵隊:
歩兵第245連隊(丸亀):坂口才平大佐 第111師団通信隊:
以下同様

編成地:満州 通称号/略称:公 所属軍:第3軍 最終地:満州東部 琿春
太平洋戦争中期以降、多くの師団が満州から南方に転用されたため、1944年(昭和19年)7月、琿春において
第111師団と同様に第9独立守備隊を基幹とし、宮古島に転用された第28師団の残留者が加わり第112師団が
編成され第3軍に編入。編成後、満州東部のソ連国境の南端の琿春、間島地区の警備と治安維持に当る。
昭和20年)8月9日、ソ連軍の侵攻(ソ連対日参戦)を受け、多くの犠牲を出しながら琿春の防衛に当たった。
8月17日、第1方面軍の命により停戦し、翌日に中村師団長、安木参謀長が自決した。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
中村次喜蔵 中将 |
1944年7月 |
自決- |
参謀長:安木亀二大佐 参謀:高杉覚中佐 副官:兼子兼治郎中佐
最終所属部隊
歩兵第246連隊(福岡):山本稜威大佐 第112師団工兵隊:
歩兵第247連隊(大村):西崎逸雄大佐 第112師団通信隊:尾形茂人大尉
歩兵第248連隊(久留米):広瀬利善大佐 第112師団挺進大隊:佐野隆夫少佐
野砲兵第112連隊:塚本清太郎少佐 第112師団輜重隊:竹内岱雲少佐

編成地:宇都宮/華北 通称号/略称:将 所属軍:第1軍 最終地:山西省臨汾
第114師団は、1937年10月12日、留守第14師団の担当で新設された。第10軍(司令官:柳川平助中将)隷下となり、
廃止:1939年(昭和14年)7月22日 編成地:宇都宮
太平洋戦争末期になると、華北に駐屯していた第26師団がフィリピン戦線に、第62師団が沖縄に転用されたため、
中国に在った独立歩兵旅団(独立混成旅団)を改編し、占領地の警備と治安維持を目的に編成した
治安師団の一つであり、1944年7月10日、軍令陸甲第79号下令により、編成が発令された。
第114師団は、華北の山西省臨汾運城において独立歩兵第3旅団の復帰人員と第69師団からの転属者などを
基幹に山西省臨汾で再編成された。編成後、第1軍に編入され、第69師団より臨汾周辺の警備を引き継いで、
山西省の治安粛正の各討伐作戦に従事した。昭和20年)8月9日にソ連が対日参戦に際して、平津地区転進を
令され、移動準備中に終戦を迎えた。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
中代豊治郎 少将 |
1944年7月- |
師団心得 |
| |
三浦三郎 中将 |
1944年10月- |
東京、 |
参謀長:高津康雄大佐 参謀:大田黒寿中佐 参謀:小林正孝少佐 高級副官:高橋慶太郎中佐
最終所属部隊
・歩兵第83旅団:青山清少将
・独立歩兵第199大隊:渋谷隆治大尉 ・独立歩兵第200大隊:阿部幸博大尉
・独立歩兵第201大隊:堺原元市大尉 ・独立歩兵第202大隊:小沢民部少佐
・歩兵第84旅団:松野尾勝明少将
・独立歩兵第381大隊:新庄繁樹大尉 ・独立歩兵第382大隊:田垣朝吉大尉
・独立歩兵第383大隊:鍵沢太郎少佐 ・独立歩兵第384大隊:佐波武郎大尉
第114師団通信隊:長峰春則少佐 第114師団砲兵隊:三瓶幸吉少佐
第114師団工兵隊:三瓶正次大尉 第114師団輜重隊:菅原大二郎大尉
第114師団野戦病院:熊谷俊夫少佐 第114師団病馬廠

編成地:中支 通称号/略称:北 所属軍::第12軍 最終地:河南省
太平洋戦争の末期後に華北に駐屯していた第26師団がフィリピン戦線に、第62師団が沖縄に転用されたため、
中国に在った独立歩兵旅団(独立混成旅団)を改編し、占領地の警備と治安維持を目的に編成した
治安師団の一つであり、昭和19年)7月10日、軍令陸甲第79号下令により、編成が発令された。
第115師団は、河南省で独立混成第7旅団を基幹に編成された。編成後、第12軍に編入され、黄河以南の
京漢線沿線の警備に当たった。
1945年3月、老河口作戦に参加した。老河口作戦後は河南省に戻り郾城で終戦を迎えた。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
杉浦英吉 中将 |
昭和19年7月 |
- |
最終所属部隊
・歩兵第85旅団:三宮満治少将
・独立歩兵第26大隊:高島義明大尉 ・独立歩兵第27大隊:藤本 格大尉
・独立歩兵第28大隊:桑原金一少佐 ・独立歩兵第29大隊:佐々木幸夫大尉
・歩兵第86旅団:樋口清登少将
・独立歩兵第30大隊:天野茂吉少佐 ・独立歩兵第385大隊:遠藤利雄大尉
・独立歩兵第386大隊:鈴木孝三郎少佐 ・独立歩兵第387大隊:今藤好雄少佐
第115師団輜重隊:斎藤忠一大尉 第115師団迫撃砲隊:吉田成行大尉
第115師団通信隊:福間耕次大尉 第115師団野戦病院:畠中正純軍医少佐

編成地:京都 通称号/略称:嵐 所属軍:第13軍→第20軍 最終地:湖南省衡陽
日中戦争勃発後の1938年(昭和13年)5月15日に京都で留守第16師団の担当で編成された特設師団である。
編成後、直ちに中支那派遣軍戦闘序列に編入中国戦線に派遣され華中に進出、歩兵4個大隊を基幹に
石原支隊が編成され武漢作戦に参戦した。武漢作戦後は華中での警備に当たり、中支那派遣軍廃止後
第13軍戦闘序列に編入された。太平洋戦争開戦後も第13軍隷下華中に在りこの方面のさまざまな作戦に参加
昭和19年)10月には第20軍戦闘序列に編入され、大陸打通作戦第二段湘桂作戦の衡陽攻略に参加、
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
清水喜重 中将 |
昭和13年5月- |
愛媛県、予備役で師団長 |
| |
篠原誠一郎 中将 |
昭和14年5月- |
- |
| |
武内俊二郎 中将 |
昭和16年10月- |
- |
| |
岩永汪 中将 |
昭和18年6月- |
- |
| |
菱田元四郎 中将 |
昭和20年3月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第109連隊(京都):瀧寺保三郎大佐 第116師団通信隊
歩兵第120連隊(福知山):児玉忠雄大佐 第116師団衛生隊:井村煕中佐
歩兵第133連隊(津):加川勝永大佐 第116師団第1野戦病院:小山倫夫軍医少佐
野砲兵第122連隊:安井清大佐 第116師団第2野戦病院:副島順造軍医少佐
工兵第116連隊:池田金太郎大佐 第116師団第4野戦病院:阿久津澄義軍医少佐
輜重兵第116連隊:南喜代彦大佐

編成地:河南省 新郷 通称号/略称:弘 所属軍:第44軍 最終地:吉林省
太平洋戦争の末期後に華北に駐屯していた第26師団がフィリピン戦線に、第62師団が沖縄に転用されたため、
中国に在った独立歩兵旅団(独立混成旅団)を改編し、占領地の警備と治安維持を目的に編成した
治安師団の一つであり、昭和19年)7月10日、軍令陸甲第79号下令により、編成が発令された。
第117師団は、河南省新郷で独立歩兵第14旅団を基幹に編成された。編成後、第12軍に編入され、
黄河以北の京漢線沿線の警備に当たっていた。
昭和20年)4月には老河口作戦に参加する予定であったが中止、関東軍第44軍戦闘序列に編入された。
桃南に駐屯していたところ、同年8月9日にソ連対日参戦となったため新京方面に向け後退中、終戦となり、
師団主力は吉林省公主嶺で武装解除された。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
鈴木啓久 中将 |
昭和19年7月 |
- |
最終所属部隊
・歩兵第87旅団:庄司巽少将
・独立歩兵第203大隊:中田卯三郎大尉 ・独立歩兵第204大隊:上古正樹大尉
・独立歩兵第205大隊:星野六蔵少佐 ・独立歩兵第206大隊:日野原松市少佐
・歩兵第88旅団:池田次郎少将
・独立歩兵第388大隊:遠間公佐久大尉 ・独立歩兵第389大隊:白戸憲吉郎少佐
・独立歩兵第390大隊:阿部庄司大尉 ・独立歩兵第391大隊:西元弥太郎大尉
第117師団迫撃砲隊:田岡貞一大尉 第117師団通信隊
第117師団工兵隊:佐久間成夫大尉 第117師団野戦病院:丹保司平軍医少佐
第117師団輜重隊:山中勇大尉 第117師団病馬廠

編成地:山西省 通称号/略称:恵 所属軍:駐蒙軍-第13軍 最終地:張家口
太平洋戦争の末期後に華北に駐屯していた第26師団がフィリピン戦線に、第62師団が沖縄に転用されたため、
中国に在った独立歩兵旅団(独立混成旅団)を改編し、占領地の警備と治安維持を目的に編成した治安師団の
一つであり、昭和19年)7月10日、軍令陸甲第79号下令により、編成が発令された。
第118師団は、1944年(昭和19年)7月に山西省大同で独立歩兵第9旅団を基幹として編成された。
編成後、駐蒙軍隷下に編入され、大同付近の警備に従事いたした。
(昭和20年)4月、上海方面防衛強化の為に第13軍の戦闘序列に編入され、華中に転進した。
同年8月9日にソ連が対日参戦すると、ソ連軍の侵攻を阻止するため北上、8月15日に張家口付近に達して終戦
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
内田銀之助 中将 |
昭和19年7月 |
- |
最終所属部隊
・歩兵第89旅団:岡博明少将
・独立歩兵第223大隊:士井政人少佐 ・独立歩兵第224大隊:米川忍大尉
・独立歩兵第225大隊:山重太郎少佐 ・独立歩兵第226大隊:家森清少佐
・歩兵第90旅団:福井浩太郎少将
・独立歩兵第392大隊:山川有夫大尉 ・独立歩兵第401大隊:須藤清二少佐
・独立歩兵第402大隊:春木屋幸市少佐 ・独立歩兵第403大隊:高橋鶴美大尉
第118師団砲兵隊:原欽平大尉 第118師団通信隊:泉館留八少佐
第118師団工兵隊:田中一博大尉 第118師団野戦病院:榊原美喜男軍医少佐
第118師団輜重隊:寅井徳郎少佐

編成地:黒竜江省 通称号/略称:宰 所属軍:第6軍-第4軍 最終地:ハイラル
太平洋戦争中期以降、多くの師団が満州から南方に転用されたため、1944年(昭和19年)10月11日に
ハイラルにおいて第8国境守備隊とフィリピン戦線に転用された第23師団の残留部隊を基幹として第119師団が
編成された。編成後、ハイラル方面の国境警備と治安維持に当る。師団は当初第6軍に属していたが、
1945年1月25日に第6軍が華中へ転用となり、第4軍に編入され、一貫してハイラルに駐屯した。
昭和19年)8月9日ソ連対日参戦と同時に後退し、追撃するソ連軍と交戦を続けている中で終戦を迎えた。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
塩沢清宣 中将 |
昭和19年10月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第253連隊(東京):三浦俊雄大佐 工兵第119連隊:石塚義治大佐
歩兵第254連隊(東京):長沢太郎大佐 輜重兵第119連隊:鈴木実少佐
歩兵第255連隊(市川):清水義虎大佐 第119師団挺進大隊
捜索第119連隊:田川泉大佐 第119師団通信隊
野砲兵第119連隊:石口茂大佐 第119師団制毒隊

編成地:黒竜江省 通称号/略称:宰 所属軍:第3軍-第17方面軍 最終地:京城
昭和19年7月、第12師団が満州から台湾に転用されたため、東寧において第12師団の残留者を基幹に
第120師団が編成された。同年12月末に編成が完了し第3軍に編入。満州東部の警備と治安維持に当る。
昭和20年)3月、満州から朝鮮半島南部に転用され、第17方面軍隷下となり、慶山に司令部を置き、
釜山、大邱方面の防衛を担当した。同年8月9日、ソ連軍の対日参戦(ソ連対日参戦)に伴い、
師団主力は京城に、歩兵第261連隊は平壌に移動したが、戦闘を交えることなく終戦を迎えた。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
柳川真一 中将 |
1944年11月 |
- |
参謀長:中西満洲次郎中佐 参謀:渋谷三千雄少佐
最終所属部隊
歩兵第259連隊(丸亀):本 繁久大佐 第120師団工兵隊:
歩兵第260連隊(徳島):橋本孝一大佐 第120師団通信隊:
歩兵第261連隊(高知):大西角一大佐 第120師団輜重隊:
第120師団砲兵隊:三原光雄少佐

|
編成地:浜江省 成高子 通称号/略称:栄光 所属軍:第58軍 最終地:済州島
太平洋戦争末期、多くの師団が満州から南方戦線と本土決戦準備に転用されたことに伴い、満州防備強化を
目的として1945年(昭和20年)1月16日に軍令陸甲下令により、師団の編成が発令された。
第121師団は、第28師団が満州から宮古島に転用されたため、浜江省成高子において第28師団の残留者を
基幹に騎兵第3旅団の騎砲兵第3連隊と同旅団輜重隊を加えて編成された。1945年3月30日に編成を完結後、
満州から朝鮮半島南部に転用され第58軍に編入された。同年6月、済州島に移動し同島東部で連合国軍の
上陸に備えて防禦陣地の構築などを行っていたが、戦闘を交えることなく終戦を迎えた。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
正井義人 中将 |
1945年1月 |
- |
参謀長:梅木留助大佐 参謀:加藤功中佐、市川英之進少佐
最終所属部隊
歩兵第262連隊(丸亀):中西熊太大佐 輜重兵第121連隊(善通寺):松田謹之助中佐
歩兵第263連隊(徳島):井野八郎大佐 第121師団通信隊
歩兵第264連隊(高知):森永清大佐 第121師団兵器勤務隊
野砲兵第121連隊(善通寺):今井建己大佐 第121師団病馬廠
工兵第121連隊(善通寺):佐藤今朝次郎少佐

編成地:牡丹江省/興隆 通称号/略称:舞鶴 所属軍:第1方面軍 最終地:牡丹江
太平洋戦争末期、多くの師団が満州から南方戦線と本土決戦準備に転用されたことに伴い、満州防備強化を
目的として1945年(昭和20年)1月16日に軍令陸甲下令により、編成が発令された。第122師団は、
第11師団が満州から四国に転用されたため、牡丹江省興隆において第11師団の残留者と第4国境守備隊を
基幹に編成された。同年3月30日に編成を完結し第1方面軍の直轄兵団に編入され牡丹江一帯で国境警備
同 年8月9日、ソ連対日参戦により侵攻してきたソ連軍と交戦し、8月17日に停戦命令を受領した。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
赤鹿理 中将 |
昭和20年1月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第265連隊(東京):出村耐造大佐 輜重兵第122連隊:田中剛一少佐
歩兵第266連隊(甲府):柏木求馬大佐 第122師団挺進大隊::
歩兵第267連隊(佐倉):杉村南平大佐 第122師団通信隊:
野砲兵第124連隊: 第122師団兵器勤務隊:
工兵第122連隊:渋谷勇雄少佐 第122師団病馬廠:

編成地:満州 通称号/略称:松風 所属軍:第4軍 最終地:満州
多くの師団が満州から南方戦線と本土決戦準備に転用されたことに伴い、満州防備強化を目的として
昭和20年)1月16日に軍令陸甲下令により、第121・第122・第123・第124・第125・第126・第127・第128師団の
個師団の編成が発令された。
第123師団は、1944年(昭和19年)10月にフィリピンへ転出した第1師団の残留者により編成された
独立混成第73旅団を基幹に、孫呉で編成された。同年3月30日に編成を完結し第4軍に編入され
孫呉一帯で満州北東部の国境警備に当る。1945年8月11日、アムール川を渡河しソ連軍が満州に侵攻した。
第123師団は独立混成第135旅団と共に、璦琿及び孫呉の陣地において防衛戦を遂行した。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
北沢貞治郎 中将 |
1945年1月 |
- |
参謀長:土田穣大佐 参謀:村木曠中佐
最終所属部隊
歩兵第268連隊(名古屋):山中高助大佐 工兵第123連隊:二階堂謙亮中佐
歩兵第269連隊(津):後藤三平大佐 輜重兵第123連隊:安部武雄少佐
歩兵第270連隊(岐阜):太田紀一大佐 第123師団挺進大隊 :
野砲兵第123連隊:町田賢助中佐 第123師団通信隊:

編成地:満州 通称号/略称:遠謀 所属軍:第5軍 最終地:牡丹江
多くの師団が満州から南方戦線と本土決戦準備に転用されたことに伴い、満州防備強化を目的として
昭和20年)1月16日に軍令陸甲下令により、第121・第122・第123・第124・第125・第126・第127・第128師団の
8個師団の編成が発令された。第124師団は、朝鮮半島へ転出した第111師団の残留者を基幹に編成され、
同年3月30日に編成を完結し第5軍に編入され、牡丹江正面の国境警備を担当した。
1945年8月9日、ソ連対日参戦に伴い、ソ連軍極東方面軍の奇襲攻撃を受けた。8月12日、第124師団主力が
陣を敷く穆陵西側にソ連軍の総攻撃を受けた。撤退命令が発令され敦化へ後退。8月23日に停戦が成立
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 椎名正健 中将 |
1945年1月 |
- |
参謀長:岩崎豊晴大佐 参謀:河野祐教少佐
最終所属部隊
歩兵第271連隊(仙台):安土武比古大佐 第124師団挺進大隊:
歩兵第272連隊(会津若松):石川英治大佐 第124師団通信隊:
歩兵第273連隊(山形):瀬尾浩大佐 第124師団工兵隊:
野砲兵第124連隊:瀧波幸助大佐 第124師団輜重隊:
第124師団兵器勤務隊

編成地:満州国 黒河省 通称号/略称:英機 所属軍:第30軍 最終地:吉林省通化
多くの師団が満州から南方戦線と本土決戦準備に転用されたことに伴い、満州防備強化を目的として
昭和20年)1月16日に軍令陸甲下令により、第121・第122・第123・第124・第125・第126・第127・第128師団の
8個師団の編成が発令された。第125師団は、第13国境守備隊(法別拉)と日本本土へ転出した第57師団の
残留者を基幹に満州黒河省神武屯・北門鎮一帯で編成された。同年3月30日に編成完結後、第4軍に編入され
黒竜江沿一帯で満州北部の国境警備を担当した。同年7月30日、第30軍戦闘序列に編入され、通化に移駐した。
師団主力は通化で対ソ戦に備えて防禦陣地の構築などを行っていたが、戦闘を交えることなく終戦を迎えた。
師団参謀長藤田実彦大佐は17日師団部隊長会同にて停戦を拒否し、一時部隊を離脱した。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
今利龍雄 中将 |
1945年1月 |
- |
参謀長:藤田実彦大佐 参謀:平田文一少佐
最終所属部隊
歩兵第275連隊(山口):瀬川正雄大佐 第125師団通信隊
歩兵第276連隊(浜田):岡野董大佐 第125師団兵器勤務隊
歩兵第388連隊(満洲):今田茂大佐(旧第149師団所属)
工兵第125連隊 輜重兵第125連隊 第125師団挺進大隊

編成地:満州 東安省 所属軍:第5軍 最終地:牡丹江
多くの師団が満州から南方戦線と本土決戦準備に転用されたことに伴い、満州防備強化を目的として
昭和20年)1月16日に軍令陸甲下令により、第121・第122・第123・第124・第125・第126・第127・第128師団の
編成が発令された。第126師団は、第12国境守備隊(廟嶺)と日本本土へ転出した第25師団の残留者を
基幹に満州東安省で編成され、第5軍に編入された。その担当は牡丹江正面の国境警備であった。
8月9日、ソ連対日参戦に伴い、ソ連軍極東方面軍の奇襲攻撃を受け、第124師団がソ連軍との激しい戦闘を
継続する中、牡丹江の防備を強化しソ連軍の攻撃を防ぎながら、牡丹江市街の在留邦人の脱出を助けた。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
野溝弐彦 少将 |
1945年1月- |
心得師団長 |
| |
野溝弐彦 中将 |
1945年3月- |
- |
参謀長:田中正司大佐 参謀:萩野重幸中佐
最終所属部隊
歩兵第277連隊(都城):山本義雄大佐 第126師団挺進大隊
歩兵第278連隊(熊本):山中肇大佐 第126師団通信隊
歩兵第279連隊(鹿児島):菊池永雄大佐 第126師団工兵隊
野砲兵第126連隊 第126師団輜重隊

編成地:満州 通称号/略称:英遇 所属軍:第3軍 最終地:満州東部
多くの師団が満州から南方戦線と本土決戦準備に転用されたことに伴い、満州防備強化を目的として
昭和20年)1月16日に軍令陸甲下令により、第121・第122・第123・第124・第125・第126・第127・第128師団の
編成が発令された。第127師団は、満州五家子に所在の第9国境守備隊を基幹に編成され、第3軍に編入された。
その担当は満州東部国境の警備・防衛であった。
1945年8月9日、ソ連対日参戦に伴いソ連軍の攻撃を受け、五家子に所在の歩兵第280連隊の一部、水流峰の
部隊は交戦し、8月19日頃まで持ちこたえていた。第127師団の部隊は本格的な戦闘を交えることなく停戦
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
古賀龍太郎 少将 |
1945年1月 |
心得師団長 |
| |
古賀龍太郎 中将 |
1945年3月 |
- |
参謀長:広瀬清大佐 参謀:境正男少佐
最終所属部隊
歩兵第280連隊(宇都宮):伊従秀夫大佐 第127師団通信隊
歩兵第281連隊(水戸):高畑洋平大佐 第127師団工兵隊
歩兵第282連隊(高崎):友枝敬一大佐 第127師団輜重隊
野砲兵第127連隊 第127師団兵器勤務隊
第 127師団挺進大隊 第127師団病馬廠

編成地:満州 通称号/略称:英武 所属軍:第3軍 最終地:牡丹省 羅子溝
多くの師団が満州から南方戦線と本土決戦準備に転用されたことに伴い、満州防備強化を目的として
昭和20年)1月16日に軍令陸甲下令により、第121・第122・第123・第124・第125・第126・第127・第128師団の
編成が発令された。第128師団は、朝鮮半島へ転出した第120師団の残留者を基幹に、第1国境守備隊、
第2国境守備隊、第11国境守備隊の一部を加えて編成され、4月10日に牡丹江省で編成を完了し第3軍に編入。
その後、独立混成第132旅団が指揮下に入り、第128師団主力は羅子溝付近に所在し、ソ連対日参戦を迎えた。
1945年8月13日から14日にかけて、ソ連軍は羅子溝の陣地に猛攻撃を加えた。第128師団は
支えきれず羅子溝西方の樺皮旬子の陣地に後退し、その地で停戦となった。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
水原義重 中将 |
1945年3月 - |
- |
参謀長:石橋忠雄大佐 参謀:下川久少佐
最終所属部隊
歩兵第283連隊(金沢):石丸繁雄大佐 第128師団挺進大隊
歩兵第284連隊(富山):松吉赳夫大佐 第128師団通信隊
歩兵第285連隊(富山):阿久刀川赳夫大佐 第128師団工兵隊
野砲兵第128連隊:勝又文雄少佐 第128師団輜重隊

編成地:広東省 通称号/略称:振武 所属軍:第23軍 最終地:広東省広州
昭和20年4月、独立混成第19旅団(湘桂作戦・粤漢作戦に参加した後華南に駐屯中)を二分割して基幹とし、
第129師団と第130師団が編成された。第129師団は編成後、第23軍の指揮下に入り、広州近郊に展開し
連合国軍の中国南部上陸に備えていたが、連合軍の中国南部上陸は無く広州近郊の淡水で終戦を迎える。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
鵜沢尚信 中将 |
昭和20年4月 |
- |
最終所属部隊
・歩兵第91旅団:谷肇少将
・独立歩兵第98大隊:三野春季少佐 ・独立歩兵第278大隊:鶴見和典少佐
・独立歩兵第279大隊:高井芳衛少佐 ・独立歩兵第280大隊:大神茂大尉
・歩兵第92旅団:平野儀一少将
・独立歩兵第100大隊:山内又兵衛中佐 ・独立歩兵第588大隊:中西義英少佐
・独立歩兵第589大隊:島村清次大尉 ・独立歩兵第590大隊:佐藤仁一郎大尉
第129師団砲兵隊:土橋武男中佐 第129師団兵器勤務隊:中川忠雄大尉
第129師団工兵隊:城戸口準大尉 第129師団野戦病院:清河宗吉軍医少佐
第129師団輜重隊:小西一夫大尉 第129師団病馬廠:中田竹三郎獣医大尉
第129師団通信隊:葛秀夫大尉 第129師団防疫給水部:岩崎与五郎軍医少佐

編成地:広東省 通称号/略称:鍾馗 所属軍:第23軍 最終地:広州近郊の番禹
昭和20年4月)、独立混成第19旅団(湘桂作戦・粤漢作戦に参加した後華南に駐屯中)の半数を基幹とし
編成された。なお、残る半分は第129師団の基幹となった。第130師団は編成後第23軍の指揮下に入り、
広州近郊に展開し連合国軍の中国南部上陸に備えていたが、上陸は無く広州近郊の番禹で終戦
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
近藤新八 中将 |
昭和20年4月 |
香川県、第37師団参謀長経て、台湾軍参謀長後第130師団長、戦後戦犯銃殺 |
最終所属部隊
・歩兵第93旅団:針谷逸郎少将
・独立歩兵第97大隊:三宮善人大尉 ・独立歩兵第99大隊:中原実大尉
・独立歩兵第100大隊:高谷瀧夫中佐 ・独立歩兵第277大隊:宮脇喜平次少佐
・歩兵第94旅団:小野修少将
・独立歩兵第281大隊:田中英二大尉 ・独立歩兵第620大隊:尾尻義馬少佐
・独立歩兵第621大隊:村重武一大尉 ・独立歩兵第622大隊:内田馨少佐
第130師団砲兵隊:宇宿達二大佐 第130師団兵器勤務隊:蔵丸等大尉
第130師団工兵隊:小形研三大尉 第130師団第1野戦病院:
第130師団輜重隊:佐瀬浅次郎少佐 第130師団第2野戦病院:
第130師団通信隊:菅原長利大尉 第130師団病馬廠:藤本範雄獣医大尉
第130師団防疫給水部:猪原貢軍医大佐

編成地:広東省 通称号/略称:秋水 所属軍:第23軍-支那派遣軍 最終地:上海方面移動中安慶
太平洋戦争末期、武漢地区の警備と治安維持を目的として1945年(昭和20年)2月1日軍令陸甲下令により、
第131師団・第132師団・第133師団の3個師団の編成が発令された。これら3個師団は、武漢方面に在った
部隊から兵力を抽出して設けられた師団である。師団の編制は、4個独立歩兵大隊から成る歩兵旅団を2個持ち、
砲兵を欠いた丙師団である。しかし、これら3個師団には、7月10日付けで師団砲兵隊が設けられた。
第131師団は、広東省で粤漢作戦で粤漢鉄道を占領した第40師団や第27師団などの残留部隊や
本隊追及隊などを基幹に編成された。編成後、第23軍の指揮下に入り粤漢鉄道沿線の警備に従事する。
その後、同年6月17日には支那派遣軍直轄部隊となり、警備地を独立歩兵第8旅団に譲って上海方面に
向けて移動中安慶で終戦を迎える。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
小倉達次 中将 |
1945年2月 |
佐賀県、留守第54師団長、第84師団長を経て第131師団長となる |
最終所属部隊
・歩兵第95旅団:岩本高次少将
・独立歩兵第591大隊:北原岩男少佐 ・独立歩兵第592大隊:財津子之吉少佐
・独立歩兵第593大隊:中井憲一少佐 ・独立歩兵第594大隊:田中真次郎少佐
・歩兵第96旅団:海福三千雄少将
・独立歩兵第595大隊:北村発卯麿中尉 ・独立歩兵第596大隊:井上良雄中尉
・独立歩兵第597大隊:糸原佐吉中尉 ・独立歩兵第598大隊:黒須政之助少佐
第131師団砲兵隊: 第131師団兵器勤務隊:小堀溪大尉
第131師団工兵隊:田岡正二大尉 第131師団野戦病院:郷田静夫軍医大尉
第131師団輜重隊: 第131師団通信隊:手塚郁夫大尉
第131師団病馬廠::佐々木恂次郎獣医大尉

編成地:湖北省 通称号/略称:振起 所属軍:第6方面軍 最終地:宜昌、当陽
太平洋戦争末期、武漢地区の警備と治安維持を目的として1945年(昭和20年)2月1日軍令陸甲下令により、
第131師団・第132師団・第133師団の3個師団の編成が発令された。これら3個師団は、武漢方面に在った
部隊から兵力を抽出して設けられた師団である。7月10日付けで師団砲兵隊が設けられた。
第132師団は、上海に転用された第39師団や、湘桂作戦のため南下した第68師団などの残留部隊を
基幹に編成された。編成後、第6方面軍の指揮下に入り、第39師団の任務を引き継ぎ、
宜昌、当陽方面の警備を担当し、その地で終戦を迎えた。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
柳川悌 中将 |
1945年2月 |
- |
参謀長:中森恒二大佐 参謀:高橋亮次郎中佐 高級副官:山中孝夫少佐
最終所属部隊
・歩兵第97旅団(大阪):梶浦銀次郎少将
・独立歩兵第599大隊:小坂田浩少佐 ・独立歩兵第600大隊:岩崎守大尉
・独立歩兵第601大隊:川崎陸雄少佐 ・独立歩兵第602大隊:原実大尉
・歩兵第98旅団(大阪):河村貞雄少将
・独立歩兵第603大隊:山内一大尉 ・独立歩兵第604大隊:小浜勇少佐
・独立歩兵第605大隊:日高博大尉 ・独立歩兵第606大隊:伊藤清少佐
第132師団砲兵隊: 第132師団兵器勤務隊:前原孝宣大尉
第132師団工兵隊:江口与四郎大尉 第132師団野戦病院:本多次郎少佐
第132師団輜重隊:有富正一大尉 第132師団病馬廠:井上繁蔵大尉
第 132師団通信隊:伊豆貝元貞中尉

編成地:広西省 桂州 通称号/略称:進撃 所属軍:第6軍 最終地:浙江省杭州
太平洋戦争末期、武漢地区の警備と治安維持を目的として1945年(昭和20年)2月1日軍令陸甲下令により、
第131師団・第132師団・第133師団の3個師団の編成が発令された。これら3個師団は、武漢方面に在った
部隊から兵力を抽出して設けられた師団である。7月10日付けで師団砲兵隊が設けられた。
第133師団は、満州に転用された第63師団や、後に杭州湾、満州へ転用された第70師団などからの
抽出部隊を基幹に桂州地区で編成された。編成後、第6軍の指揮下に入り、第70師団の任務を引き継ぎ、
寧波方面の治安警備を担当し、その地で終戦を迎えた。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
野地嘉平 中将 |
1945年3月 |
- |
参謀長:樋沢一治大佐 参謀:塩川辰己少佐
最終所属部隊
・歩兵第99旅団(熊本):城戸寛爾少将
・独立歩兵第607大隊:中村此君生大尉 ・独立歩兵第608大隊:水崎久雄大尉
・独立歩兵第609大隊:村木敏行大尉 ・独立歩兵第610大隊:鈴木正司大尉
・歩兵第100旅団(熊本):羽鳥長四郎少将
・独立歩兵第611大隊:三浦己之助大佐 ・独立歩兵第612大隊:山下孝雄大尉
・独立歩兵第613大隊:松井政一少佐 ・独立歩兵第614大隊:早木治文大尉
第133師団通信隊:霞堂哲生大尉 第133師団輜重隊:砂走孝大尉
第133師団工兵隊:高桑利道大尉 第133師団兵器勤務隊:横張利春中尉
第133師団野戦病院:星野宜士少佐 第133師団病馬廠:吉良幸逸大尉
第133師団砲兵隊:

編成地:満州 佳木斯 通称号/略称:勾玉 所属軍:関東軍管区 最終地:満州 富錦、佳木斯
昭和20年に入り、関東軍は南方へ兵力の過半数を引き抜かれていたが満州居留邦人15万名、在郷軍人25万名を
「根こそぎ動員」、さらに中国戦線から4個歩兵師団を戻してなんとか74万人の兵員を調達した。
さらに以前関東軍特種演習により本土から輸送させた戦車200輌、航空機200機、火砲1000門も健在であった。
同年7月、「根こそぎ動員」の際に第134師団は、第14国境守備隊、独立混成第78旅団、富錦駐屯隊を基幹に
佳木斯で編成された。同年8月9日のソ連対日参戦時に、第134師団は依蘭に所在していた。
ソ連軍が松花江沿いに進撃し、それに伴い第134師団主力は南に移動し方正南方に陣を敷いた。
富錦、佳木斯にあった部隊も戦闘を続けながら師団主力に合流したが、ほどなく停戦。武装解除となった。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
井関仭 中将 |
1945年7月 |
予備役- |
参謀長:末永光夫大佐
最終所属部隊
歩兵第365連隊(満州):岩田勝清中佐 第134師団通信隊:
歩兵第366連隊(満州):石山年秀中佐 第134師団兵器勤務隊:
歩兵第367連隊(満州):東野謹三大佐 第134師団病馬廠:
野砲兵第134連隊: 陸軍病院
工兵第134連隊: 関東第38(チャムス第1):長谷川重一軍医中佐
第134師団挺進大隊: 関東第90(チャムス第2):中野義雄軍医中佐
輜重兵第134連隊: 関東第91(興山):園田佐武郎軍医中佐
野砲兵第134連隊: 関東第92(富錦):河合武夫軍医中佐

編成地:満州 通称号/略称:真心 所属軍:第5軍 最終地:牡丹江
昭和20年)に入り7月、「根こそぎ動員」の際に第135師団は、第2国境守備隊(綏芬河)及び第4国境守備隊
(虎頭)の主力、第46兵站警備隊、独立混成第77旅団を基幹に編成され、第5軍に編入された。
同年8月9日のソ連対日参戦時に、第135師団は虎林から東安方面に所在していた。第5軍司令部は、
第135師団と第126師団に掖河まで退却を命令した。両師団は第124師団がソ連軍との激しい戦闘を
継続する中、牡丹江の防備を強化しソ連軍の攻撃を防ぎながら、牡丹江市街の在留邦人の脱出を助けた。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
人見与一 中将 |
1945年7月- |
予備役 |
参謀長:井上敬助大佐
最終所属部隊
歩兵第368連隊(満州):飯塚文二大佐 輜重兵第135連隊:
歩兵第369連隊(満州):中山亮輔大佐 第135師団挺進大隊:
歩兵第370連隊(満州):多喜弘中佐 第135師団通信隊
野砲兵第135連隊: 第135師団兵器勤務隊
兵第135連隊: 第135師団病馬廠

編成地:満州 通称号/略称:不抜 所属軍:第3方面軍 最終地:奉天
昭和20年)に入り7月、「根こそぎ動員」の際に第136師団は、満州で召集された邦人男子のみで編成された。
7月31日に海城で編成が完結したが、充足率は約6割で火砲も定数の半分程度という状況であった。
第3方面軍の直属として本渓で陣地構築を行った。同年8月9日のソ連対日参戦時には、
奉天で陣地構築を行っていたが、戦いを交えることなく停戦した。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
中山淳 中将 |
1945年7月 |
- |
参謀長:井上敬助大佐
最終所属部隊
歩兵第371連隊(満州):前田瑞穂大佐 野砲兵第136連隊
歩兵第373連隊(満州):河野桂十郎少佐 第136師団挺進大隊:
歩兵第372連隊(満州):重松光雄中佐 第136師団通信隊
野砲兵第136連隊: 第136師団兵器勤務隊

編成地:羅南師管区 通称号/略称:扶翼 所属軍: 最終地:満州 10000名
兵員の半数以上は訓練不足、日ソ中立条約違反を想定していなかった関東軍首脳部の混乱、物質不足
(砲弾は約1200発ほどで、航空部隊のほとんどが戦闘未経験者。また小銃が行き渡らない
10万名以上)のため事実上の戦力は30万名程度だったといわれている。
第137師団は、同年7月の「根こそぎ動員」の際に編成された師団の一つである。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
秋山義兌 中将 |
1945年7月 |
予備役将校 |
参謀長:三原七郎大佐
最終所属部隊
歩兵第374連隊(羅南):竹林凡夫大佐 工兵第137連隊(会寧):岳村柾少佐
歩兵第375連隊(羅南):船木健次郎大佐 輜重兵第137連隊(羅南):立間至少佐
歩兵第376連隊(会寧):林信行大佐 第137師団挺進大隊(羅南):北村忠光大尉
野砲兵第137連隊(羅南):大津山勝二少佐 第137師団通信隊(羅南):小原巌大尉

編成地:満州 吉林省 通称号/略称:不動 所属軍:第30軍 最終地:満州撫順 人員:20000
昭和20年7月、第135師団は「根こそぎ動員」の際に満州で召集された邦人男子を主体に吉林省で編成された。
第30軍に編入され、吉林付近に師団主力は所在した。しかし、師団の編成は完了しておらず、同年8月9日の
ソ連対日参戦時には総員2千名の規模であった。ソ連軍の侵攻を受け撫順に移動したが、
本格的な戦いを交える以前に停戦となり、8月19日に武装解除された。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 山本務 中将 |
1945年7月 |
- |
参謀長:佐藤貞二大佐
最終所属部隊
歩兵第377連隊(満州):須貝良民大佐 輜重兵第138連隊:
歩兵第378連隊(満州):赤尾今朝雄少佐 第138師団挺進大隊:
歩兵第379連隊(満州):加藤恒平少佐 第138師団通信隊
野砲兵第138連隊: 第138師団兵器勤務隊:
工兵第138連隊: 第138師団病馬廠:

編成地:満州 吉林省 通称号/略称:不屈 所属軍:第1方面軍 最終地:敦化
同年7月、第135師団は「根こそぎ動員」の際に満州で召集された邦人男子と、第77兵站警備隊、第79兵站警備隊、
第80兵站警備隊を基幹に吉林省で編成された。7月末に第139師団は編成が完了し第1方面軍に編入され、
敦化で陣地構築を実施した。同年8月9日のソ連対日参戦以後、敦化でソ連軍の侵攻に備えていたが
停戦となり、8月28日までに武装解除された。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 富永恭次中将 |
1945年7月- |
長崎県、陸軍次官、第4航空軍司令官、予備役から第139師団の師団長フィリピンから
台北へ逃亡で有名で「東條英機の腰巾着」と評判が悪い |
参謀長:松岡義一中佐
最終所属部隊
歩兵第380連隊(満州):大沢侃次郎大佐 輜重兵第139連隊:
歩兵第381連隊(満州):片山敬吉大佐 第139師団挺進大隊:
歩兵第382連隊(満州):遠藤三郎大佐 第139師団通信隊:
野砲兵第139連隊: 第139師団兵器勤務隊:
工兵第139連隊: 第139師団病馬廠

|
編成地:東京 通称号/略称:護東 所属軍:第1方面軍 最終地:湘南海岸
師団司令部は片瀬町(現藤沢市片瀬)におかれた。「相模湾防衛」を主任務とする第53軍の麾下に入り
湘南海岸から上陸する敵軍に対抗するために海岸線や付近の山林に多数の横穴陣地・トーチカを構築したが、
急遽編成されたため火力は乏しかった。稲村ヶ崎に残る横穴陣地
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 物部長鉾 中将 |
昭和20年4月 |
秋田県、輜重兵監に就任し、留守近衛第2師団長 |
最終所属部隊
歩兵第401連隊(東京):平沢喜一大佐(司令部:鎌倉山)
歩兵第402連隊(甲府):鈴木薫二大佐(司令部:千畳敷山)
歩兵第403連隊(佐倉):菅原甚吉中佐(司令部:藤沢市
歩兵第404連隊(溝ノ口):立花啓一大佐(司令部:御所見村(現:藤沢市御所見)
第140師団砲兵隊: 第140師団速射砲隊: 第140師団輜重隊: 第140師団通信隊

編成地:仙台 通称号/略称:護仙 所属軍:第11方面軍 最終地:宮城県黒川郡
第142師団は、仙台で編成され、第11方面軍の戦闘序列に編入された。宮城県黒川郡吉岡町に在って
仙台湾・石巻湾沿岸の防衛を任務とし、沿岸配備師団として防衛陣地構築等本土決戦に備えるなかで終戦
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
寺垣忠雄 中将 |
昭和20年4月 |
- |
| |
小泉恭次 中将 |
昭和20年8月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第405連隊(仙台):平沢喜一大佐 第142師団輜重隊
歩兵第406連隊(山形):太田軍蔵大佐 第142師団通信隊
歩兵第407連隊(若松):坂元宗治郎大佐 第142師団兵器勤務隊
歩兵第408連隊(仙台):鈴木忠大佐 第142師団野戦病院
第142師団速射砲隊:
第142師団噴進砲隊

編成地:名古屋 通称号/略称:護古 所属軍: 最終地:静岡県浜松市気賀
太平洋戦争の末期、1945年(昭和20年)1月20日に帝国陸海軍作戦計画大綱が策定された結果、
本土決戦に備えるべく急造が決定した54個師団の一つであり、本土決戦第一次兵備として
昭和20年)2月28日に編成された16個の沿岸配備師団の一つである。
| |
師団長名 |
補職日 |
備考 |
| |
鈴木貞次 中将 |
昭和20年4月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第409連隊(名古屋):丹羽篤郎大佐 第143師団速射砲隊:
歩兵第410連隊(静岡):松井利生大佐 第143師団噴進砲隊:
歩兵第411連隊(岐阜):森本辨三郎大佐 第143師団輜重隊:
歩兵第412連隊(津):笠原善修大佐 第143師団通信隊 その他

編成地:大阪 通称号/略称:護阪 所属軍: 最終地:和歌山県、潮岬 10000名
太平洋戦争の末期、1945年(昭和20年)1月20日に帝国陸海軍作戦計画大綱が策定された結果、
本土決戦に備えるべく急造が決定した54個師団の一つであり、本土決戦第一次兵備として
昭和20年2月28日に編成された16個の沿岸配備師団の一つである。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 高野直満 中将 |
昭和20年4月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第413連隊(大阪):百瀬保大佐 第144師団砲兵隊
歩兵第414連隊(和歌山):松尾謙三大佐 第144師団速射砲隊
歩兵第415連隊(大阪):白石通世大佐 第144師団輜重隊
歩兵第416連隊(和歌山):大野次郎大佐 第144師団通信隊
第144師団兵器勤務隊 第144師団野戦病院

編成地:大阪 通称号/略称:護阪 所属軍: 最終地:福岡県芦屋町 10000名
太平洋戦争の末期、1945年(昭和20年)1月20日に帝国陸海軍作戦計画大綱が策定された結果、
本土決戦に備えるべく急造が決定した54個師団の一つであり、本土決戦第一次兵備として
昭和20年2月28日に編成された16個の沿岸配備師団の一つである。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 小原一明 中将 |
昭和20年4月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第417連隊(広島):青山良政大佐 第145師団速射砲隊
歩兵第418連隊(浜田):黄葉収大佐 第145師団輜重隊
歩兵第419連隊(山口):森本誠四郎大佐 第145師団通信隊
歩兵第420連隊(広島):小川逸中佐 第145師団兵器勤務隊
第145師団噴進砲隊 第145師団野戦病院

編成地:熊本-鹿児島 通称号/略称:護南 所属軍: 最終地:鹿児島県大口 10000名
太平洋戦争の末期、1945年(昭和20年)1月20日に帝国陸海軍作戦計画大綱が策定された結果、
本土決戦に備えるべく急造が決定した54個師団の一つであり、本土決戦第一次兵備として
昭和20年2月28日に編成された16個の沿岸配備師団の一つである。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 坪島文雄 中将 |
昭和20年4月 |
- |
隷下部隊
歩兵第421連隊(熊本):渡辺美邦大佐 第146師団速射砲隊
歩兵第422連隊(都城):守田利一郎中佐 第146師団輜重隊
歩兵第423連隊(鹿児島):外園進大佐 第146師団通信隊
歩兵第424連隊(熊本):榊利徳中佐 第146師団兵器勤務隊
第146師団砲兵隊 第146師団野戦病院

編成地:旭川 通称号/略称:護北 所属軍: 最終地:千葉県茂原 10000名
太平洋戦争の末期、1945年(昭和20年)1月20日に帝国陸海軍作戦計画大綱が策定された結果、
本土決戦に備えるべく急造が決定した54個師団の一つであり、本土決戦第一次兵備として
昭和20年2月28日に編成された16個の沿岸配備師団の一つである。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 石川浩三郎 中将 |
昭和20年4月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第425連隊(旭川):山住伊織中佐 第147師団速射砲隊
歩兵第426連隊(旭川):田村禎一大佐 第147師団輜重隊
歩兵第427連隊(旭川):原子正雄大佐 第147師団通信隊
歩兵第428連隊(旭川):加藤武夫大佐 第147師団兵器勤務隊
第147師団砲兵隊 第147師団野戦病院

編成地:満州 通称号/略称:富嶽 所属軍: 最終地: 2000名
第148師団は、同年7月の「根こそぎ動員」の際に編成された師団の一つである。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 末光元広 中将 |
昭和20年7月 |
- |
参謀長:坂元眤大佐 参謀:丸岡茂雄中佐 参謀:岩佐義忠少佐 高級副官:高田登少佐
最終所属部隊
歩兵第383連隊(満洲):鈴元親三千大佐 輜重兵第148連隊
歩兵第384連隊(満洲):坂田英少佐 第148師団挺進大隊
歩兵第385連隊(満洲):加賀田作少佐 第148師団通信隊
野砲兵第148連隊 第148師団兵器勤務隊
工兵第148連隊 第148師団病馬廠

編成地:満州 通称号/略称:不撓 所属軍:第4軍 最終地:ハルビン
20年7月、第149師団は「根こそぎ動員」の際に第5国境守備隊、第6国境守備隊、第7国境守備隊を基幹に編成
第4軍に編入され、チチハルに所在し陣地構築を実施していた。同年8月9日のソ連対日参戦を受け、
第4軍司令部と共にハルビンに移動し、ソ連軍の侵攻に備えたが停戦となった。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 佐々木到一 中将 |
昭和20年7月 |
- |
参謀長:印南清大佐
最終所属部隊
歩兵第274連隊(広島):宮岸初次大佐 第149師団挺進大隊:露木甚助大尉
歩兵第386連隊(満州):近藤毅夫大佐 第149師団通信隊
歩兵第387連隊(満州):真方信雄少佐 第149師団兵器勤務隊
野砲兵第149連隊 第149師団病馬廠

|
成地:京城 通称号/略称:護朝 所属軍: 最終地:宇全羅南道 10000名
太平洋戦争の末期、1945年(昭和20年)1月20日に帝国陸海軍作戦計画大綱が策定された結果、
本土決戦に備えるべく急造が決定した54個師団の一つであり、本土決戦第一次兵備として
昭和20年)2月28日に編成された16個の沿岸配備師団の一つである。朝鮮半島の
全羅南道沿岸に配備された。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 三島義一郎 中将 |
昭和20年4月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第429連隊(姫路):曾我部元一大佐 第150師団噴進砲隊
歩兵第430連隊(姫路):粟屋発大佐 第150師団輜重隊
歩兵第431連隊(姫路):三村親厚大佐 第150師団通信隊
歩兵第432連隊(姫路):山崎孝三大佐 第150師団兵器勤務隊
第150師団速射砲隊 第150師団野戦病院 第150師団制毒隊

編成地:宇都宮 通称号/略称:護宇 所属軍: 最終地:茨城県水戸市沿岸 10000名
太平洋戦争の末期、1945年(昭和20年)1月20日に帝国陸海軍作戦計画大綱が策定された結果、
昭和20年)2月28日に編成された16個の沿岸配備師団の一つである。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 白銀義方 中将 |
昭和20年4月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第433連隊(宇都宮):米山靖正大佐 第151師団速射砲隊
歩兵第434連隊(水戸):遠藤典邦大佐 第151師団輜重隊
歩兵第435連隊(高崎):山本茂雄中佐 第151師団通信隊
歩兵第436連隊(宇都宮):宇野修一中佐 第151師団兵器勤務隊
第151師団噴進砲隊 第151師団野戦病院

編成地:金沢 通称号/略称:護沢 所属軍:第52軍 最終地:千葉 銚子
太平洋戦争の末期、1945年(昭和20年)1月20日に帝国陸海軍作戦計画大綱が策定された結果、
本土決戦に備えるべく急造が決定した54個師団の一つであり、本土決戦第一次兵備として
昭和20年)2月28日に編成された16個の沿岸配備師団の一つである。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 能崎清次 中将 |
昭和20年4月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第437連隊(富山):吉松秀孝中佐 第152師団速射砲隊
歩兵第438連隊(金沢):由谷弥市中佐 第152師団輜重隊
歩兵第439連隊(金沢):中村敏夫大佐 第152師団通信隊
歩兵第440連隊(富山):中野寿一中佐 第152師団兵器勤務隊
第152師団砲兵隊 第152師団野戦病院

編成地:京都 通称号/略称:護京 所属軍:第13方面軍 最終地:三重県伊勢市宇治山田
太平洋戦争の末期、1945年(昭和20年)1月20日に帝国陸海軍作戦計画大綱が策定された結果、
本土決戦に備えるべく急造が決定した54個師団の一つであり、本土決戦第一次兵備として
昭和20年)2月28日に編成された16個の沿岸配備師団の一つである。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 稲村豊二郎 中将 |
昭和20年4月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第441連隊(敦賀):松本昌次大佐 第153師団砲兵隊
歩兵第442連隊(京都):坂本嘉四郎大佐 第153師団速射砲隊
歩兵第443連隊(敦賀):山本信輝大佐 第153師団輜重隊
歩兵第444連隊(京都):西川正行大佐 第153師団通信隊
第153師団兵器勤務隊 第153師団野戦病院

編成地:広島 通称号/略称::護路 所属軍:第57軍 最終地:宮崎県 妻 10000名
太平洋戦争の末期、1945年(昭和20年)1月20日に帝国陸海軍作戦計画大綱が策定された結果、
本土決戦に備えるべく急造が決定した54個師団の一つであり、本土決戦第一次兵備として
昭和20年)2月28日に編成された16個の沿岸配備師団の一つである。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 毛利末広 中将 |
昭和20年4月 |
- |
| 二見秋三郎 少将 |
昭和20年7月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第445連隊(鳥取):堀龍市大佐 第154師団速射砲隊
歩兵第446連隊(鳥取):瀬野赳大佐 第154師団輜重隊
歩兵第447連隊(岡山):佐々木高一中佐 第154師団通信隊
歩兵第448連隊(岡山):永松亨一中佐 第154師団兵器勤務隊
第154師団砲兵隊 第154師団野戦病院

編成地:善通寺 善通寺 所属軍:第55軍 最終地:高知県香美郡・安芸郡
太平洋戦争の末期、1945年(昭和20年)1月20日に帝国陸海軍作戦計画大綱が策定された結果、
本土決戦に備えるべく急造が決定した54個師団の一つであり、本土決戦第一次兵備として
昭和20年)2月28日に編成された16個の沿岸配備師団の一つである。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 岩永汪 中将 |
昭和20年4月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第449連隊(丸亀):青山熊吉大佐 第155師団砲兵隊
歩兵第450連隊(徳島):下村肇大佐 第155師団輜重隊
歩兵第451連隊(高知):森田豊秋大佐 第155師団通信隊
歩兵第452連隊(丸亀):山本孝男中佐 第155師団兵器勤務隊
第155師団速射砲隊

編成地:久留米 通称号/略称:護西 所属軍:第57軍 最終地:宮崎県 本庄 10000名
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 樋口敬七郎 中将 |
昭和20年4月 |
開戦後、香港の戦いに参加、台湾軍参謀長、昭和20年3月、陸軍中将 |
最終所属部隊
歩兵第453連隊(福岡):成五一大佐 第156師団速射砲隊
歩兵第454連隊(大村):秋富勝次郎大佐 第156師団輜重隊
歩兵第455連隊(久留米):大江一二三大佐 第156師団通信隊
歩兵第456連隊(久留米):古賀恒大佐 第156師団兵器勤務隊
第156師団砲兵隊 第156師団野戦病院

編成地:弘前 通称号/略称:護弘 所属軍:第50軍 最終地:青森 三本木 10000名
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 宮下健一郎 中将 |
昭和20年4月 |
第32歩兵団長、中国で従軍し、昭和20年)3月、陸軍中将 |
最終所属部隊
歩兵第457連隊(弘前):伊藤晃中佐 第157師団速射砲隊
歩兵第458連隊(秋田):立川鴻一中佐 第157師団輜重隊
歩兵第459連隊(秋田):津川直志中佐 第157師団通信隊
歩兵第460連隊(弘前):本多菊治中佐 第157師団兵器勤務隊
第157師団噴進砲隊 第157師団野戦病院

編成地:満州 通称号/略称:不滅 所属軍:第11方面軍 最終地:
第158師団は上記の「根こそぎ動員」とは異なり、召集された満州在留邦人による編成ではなく、
満州に所在する教育訓練を終えた下士官候補隊、幹部候補生教育隊を基幹に編成が命ぜられた。
最終上級単位:第11方面軍
歴代師団長:未就任
最終所属部隊
歩兵第389連隊(満州) 歩兵第390連隊(満州) 歩兵第391連隊(満州)

編成地:平壌 通称号/略称:護鮮 所属軍:第17方面軍 最終地:全羅北道沿岸
太平洋戦争の末期、1945年(昭和20年)1月20日に帝国陸海軍作戦計画大綱が策定された結果、
本土決戦に備えるべく急造が決定した54個師団の一つであり、本土決戦第一次兵備として
昭和20年)2月28日に編成された16個の沿岸配備師団の一つである。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 山脇正雄 中将 |
昭和20年4月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第461連隊(広島):松田緩治中佐 第160師団噴進砲隊
歩兵第462連隊(浜田):村川正一大佐 第160師団輜重隊
歩兵第463連隊(山口):東長生大佐 第160師団通信隊
歩兵第464連隊(鳥取):菅野洋中佐 第160師団兵器勤務隊
第160師団速射砲隊 第160師団野戦病院

編成地:上海 通称号/略称:震天 所属軍:第13軍-支那派遣軍 最終地:南京
太平洋戦争末期の1945年(昭和20年)4月、軍令陸甲下令により、中国上海特別市において臨時編成された。
昭和19年)10月米軍がフィリピン方面へ来攻を開始、大本営は直ちに捷一号作戦を下令するとともに、
中国南部太平洋沿岸への来襲を予想し緊急戦備の実施に着手した。
師団編合部隊の大部は4月末頃までに完結し、同時に第13軍隷下に編入され上海南部郊外にて
警備ならびに陣地構築に従事した。同年6月策定の支那派遣軍の対米作戦計画大綱に、
師団は米軍の上海上陸に際し、主力が侵攻を拒止する間に予備兵力を以て反撃にあたるとされた。
同年8月9日にソ連対日参戦でソ連軍が満州へ侵攻すると、翌10日、支那派遣軍は兵力の手薄な蒙彊へ
増援する兵団として第118師団と第161師団派遣を決定した。
師団は13日から逐次上海を出発し、一部が鉄道輸送にて南京に到着した頃に終戦を迎えた
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 高橋茂寿慶 中将 |
昭和20年4月 |
- |
参謀長:小山達彦大佐 参謀:神谷正司中佐
最終所属部隊
・歩兵第101旅団(熊本):江口四郎少将
・独立歩兵第528大隊:宮崎幸男大尉 ・独立歩兵第476大隊:植田太郎大尉
・ 独立歩兵第475大隊:戸川春治少佐 ・独立歩兵第477大隊:仲田常行大尉
・歩兵第102旅団(熊本):石田寿少将
・独立歩兵第478大隊:大川戸辰蔵大尉 ・独立歩兵第479大隊:木藤重信大尉
・独立歩兵第480大隊:玉置文雄大尉 ・独立歩兵第481大隊:小城義雄大尉
第161師団砲兵隊:川口辰蔵少佐 第161師団第1野戦病院:落合為吉軍医少佐
第161師団工兵隊:白石兼一大尉 第161師団第2野戦病院:高橋昭軍医少佐
第161師団通信隊:田中七郎大尉 第161師団病馬廠:佐々木賢一獣医大尉
第161師団輜重隊:勝間田忠重少佐 第161師団防疫給水部:村田武雄軍医少佐
第161師団兵器勤務隊:楠木八重八大尉

編成地:東京 通称号/略称:武蔵 所属軍:第36軍 最終地:関東 20000名
太平洋戦争の末期、1945年(昭和20年)1月20日に帝国陸海軍作戦計画大綱が策定された結果、
本土決戦に備えるべく急造が決定した54個師団の一つであり、本土決戦第二次兵備として、
昭和20年)4月2日に編成された8個の機動打撃師団の一つである。第36軍戦闘序列に編入、
東京府国立に在って連合国軍の関東上陸作戦に備えていたが、連合国軍の関東上陸は
無く当地で終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 重信吉固 少将 |
昭和20年4月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第501連隊(東京):染谷満蔵大佐 第201師団機関砲隊:梶井勝美大尉
歩兵第502連隊(甲府):山下誠一中佐 第201師団工兵隊:高木博少佐
歩兵第503連隊(佐倉):岩瀬武司中佐 第201師団輜重隊:福瀬悦夫少佐
野砲兵第216連隊:勝沼静中佐 第201師団通信隊:高橋俊夫大尉
迫撃第216連隊:塩田一中佐 第201師団兵器勤務隊:
第201師団速射砲隊:浜田春生少佐 第201師団第4野戦病院:

編成地:仙台 通称号/略称:青葉 所属軍:第36軍 最終地:群馬県高崎 20000名
太平洋戦争の末期、1945年(昭和20年)1月20日に帝国陸海軍作戦計画大綱が策定された結果、
本土決戦に備えるべく急造が決定した54個師団の一つであり、本土決戦第二次兵備として、
昭和20年)4月2日に編成された8個の機動打撃師団の一つである。第36軍戦闘序列に編入、
群馬県高崎に在って連合国軍の関東上陸作戦に備えていたが、、連合国軍の関東上陸は
無く当地で終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 片倉衷 少将 |
昭和20年4月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第504連隊(仙台):菅野善吉中佐 第202師団機関砲隊:平田孝太郎大尉
歩兵第505連隊(若松):中山佐武郎中佐 第202師団工兵隊:宮瀬泰少佐
歩兵第506連隊(山形):工藤鉄太郎中佐 第202師団輜重隊:沢田熊衛少佐
野砲兵第202連隊:斎藤武少佐 第202師団通信隊:池田照彦少佐
迫撃第202連隊:楢崎五郎中佐 第202師団輜重隊:沢田熊衛少佐
第202師団速射砲隊:浜田信太郎少佐 第202師団通信隊:池田照彦少佐
第202師団兵器勤務隊:本田熊次大尉 第202師団第4野戦病院: 高橋伊一郎軍医少佐

編成地:広島 通称号/略称:安芸 所属軍:第55軍 最終地:高知 20000名
第205師団は、1945年(昭和20年)4月2日に広島で編成、第55軍戦闘序列に編入、高知に在って
連合国軍の四国上陸作戦に備えていたが、連合国軍の四国上陸は無く当地で終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 唐川安夫 中将 |
昭和20年4月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第507連隊(山口):石橋幸人中佐 第205師団機関砲隊:田村憲文大尉
歩兵第508連隊(鳥取):横山忠男中佐 第205師団工兵隊:大塚忠男少佐
歩兵第509連隊(岡山):足達謙三中佐 第205師団輜重隊:河済人也少佐
野砲兵第205連隊:小林繁大佐 第205師団通信隊:木村菊雄少佐
迫撃第205連隊:指宿三郎中佐 第205師団兵器勤務隊
第205師団速射砲隊:山県俊夫大尉 第205師団兵器勤務隊

編成地:熊本 通称号/略称:阿蘇 所属軍:第16方面軍 最終地:熊本人吉 20000名
第206師団は、1945年(昭和20年)4月2日に熊本県熊本で編成、第16方面軍戦闘序列に編入、
連合国軍の九州南部上陸作戦に備えていたが、連合国軍の九州南部上陸は無く当地で終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 岩切秀 中将 |
昭和20年4月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第510連隊(熊本):森園武夫中佐 第206師団機関砲隊:渡辺茂大尉
歩兵第511連隊(都城):山内俊太郎中佐 第206師団工兵隊:押川一美少佐
歩兵第512連隊(鹿児島):楠畑義則中佐 第206師団輜重隊:肝付兼武少佐
山砲兵第206連隊:田島昌治少佐 第206師団通信隊:永田秋雄少佐
迫撃第206連隊:岡本成雄中佐 第206師団兵器勤務隊
第206師団速射砲隊:内田修二少佐 第206師団第4野戦病院

編成地:金沢 通称号/略称:加越 所属軍:第36軍 最終地:石川県 津幡 20000名
第209師団は、1945年4月2日に石川県金沢で編成、第36軍戦闘序列に編入され終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 久米精一 少将 |
昭和20年4月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第513隊(金沢):安藤修道中佐 第209師団機関砲隊:富田七三郎大尉
歩兵第514連隊(富山):力石勝寿中佐 第209師団工兵隊:水野元二少佐
歩兵第515連隊(金沢):林司馬男中佐 第209師団輜重隊:宮下宗一少佐
山砲兵第209連隊:青木精一少佐 第209師団通信隊:山本良大尉
迫撃砲第209連隊:大江芳若中佐 第209師団兵器勤務隊
第209師団速射砲隊:大泉製正少佐 第209師団第4野戦病院

|
編成地:久留米 通称号/略称:菊池32601 所属軍:第16方面 最終地:宮崎都農 20000名
第212師団は、1945年4月2日に福岡県久留米で編成、第16方面軍戦闘序列に編入、宮崎県都農に在って
連合国軍の九州南部上陸作戦に備えていたが、連合国軍の宮崎都農の上陸は無く当地で終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 桜井徳太郎 少将 |
昭和20年4月 |
福岡、1943年8月、陸軍少将に進級、第55歩兵団長、ビルマ方面軍司令部付 |
最終所属部隊
歩兵第516連隊(久留米):金田高秋中佐 第212師団機関砲隊:西田応吉少佐
歩兵第517連隊(福岡):東昇中佐 第212師団工兵隊:押川一美少佐
歩兵第518連隊(大村):松倉民雄中佐 第212師団輜重隊:松永参郎少佐
山砲兵第212連隊(久留米) 第212師団通信隊:三砂安紀少佐
迫撃第212連隊(久留米):永田敏夫中佐 第212師団兵器勤務隊
第212師団速射砲隊:石田春暢少佐 第212師団野戦病院

編成地:宇都宮 通称号/略称:常盤 所属軍:第36軍 最終地:栃木県 宇都宮 20000名
第214師団は、1945年(昭和20年)4月2日に栃木県宇都宮で編成、第36軍戦闘序列に編入、連合国軍の
関東上陸作戦に備えていたが、連合国軍の関東上陸は無く当地で終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 山本募 中将 |
昭和20年4月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第519連隊(宇都宮):石井星一郎中佐 第214師団機関砲隊:坪井正庫大尉
歩兵第520連隊(水戸):河西敬次郎中佐 第214師団工兵隊:岡本隆邦少佐
歩兵第521連隊(高崎):鳥海宗雄中佐 第214師団輜重隊:臼田実雄少佐
野砲兵第214連隊:内野貞利少佐 第214師団通信隊:海老沢英夫大尉
迫撃第214連隊:桑田謹彰大佐 第214師団兵器勤務隊
第214師団速射砲隊:安楽辰夫大尉 第214師団第4野戦病院

編成地: 通称号/略称:比叡10521 所属軍:第16方面軍 最終地:熊本
第216師団は、1945年(昭和20年)4月2日に京都で編成され、第16方面軍直轄部隊として
作戦地の熊本に 配備中に終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 中野良次 中将 |
昭和20年4月 |
- |
最終所属部隊
歩兵第522連隊(京都):富田実中佐 第216師団機関砲隊:垣本政治少佐
歩兵第523連隊(敦賀):平井重文中佐 第216師団工兵隊
歩兵第524連隊(姫路):片岡太郎中佐 第216師団輜重隊:竹内一郎少佐
野砲兵第216連隊(京都):名川義人中佐 第216師団通信隊:富田義雄大尉
迫撃第216連隊(京都):幡川錬治大佐 第216師団兵器勤務隊
第216師団速射砲隊:大塚泰一大尉 第216師団第4野戦病院

|
(昭和20年)5月23日に行われた大本営の本土決戦に備えて行われた、3度目の師団増強である。
機動打撃師団8個、沿岸配備師団11個の計19個・独立混成旅団15個を新設したが、所属した歩兵連隊は
3個で、 第一次兵備の沿岸配備師団と較べても兵数・火力ともに劣っていた。また、計画された
兵器・人員の定数も充たされないままに終戦を迎えた。
機動打撃師団
| 第221師団 |
|
第222師団 |
| 通称号:「天龍」 |
|
通称号:「八甲」 |
| 編成地:長野/補充担任:長野師管区 |
|
編成地:弘前/補充担任:弘前師管区 |
| 師団長:永沢三郎中将 |
|
師団長:笠原嘉兵衛中将 |
| 最終上級部隊:第51軍 |
|
最終上級部隊:第11方面軍 |
| 最終位置:茨城県鹿島 |
|
最終位置:岩手県 |
| 歩兵第316連隊 |
|
歩兵第307連隊 |
| 歩兵第317連隊 |
|
歩兵第308連隊 |
| - |
|
歩兵第309連隊 |
| 第224師団 |
|
第225師団 |
| 通称号:「赤穂」 |
|
通称号:「金剛」 |
| 編成地:広島/補充担任:広島師管区 |
|
編成地:大阪/補充担任:大阪師管区 |
| 師団長:河村参郎中将 |
|
師団長:落合鼎五中将 |
| 最終上級部隊:第54軍 |
|
最終上級部隊:第15方面軍 |
| 最終位置:広島 |
|
最終位置:兵庫県龍野 |
| 歩兵第340連隊 |
|
歩兵第343連隊 |
| 歩兵第341連隊 |
|
歩兵第344連隊 |
| 歩兵第342連隊 |
|
歩兵第345連隊 |
| 第229師団 |
|
第230師団 |
| 通称号:「北越」 |
|
通称号:「総武」 |
| 編成地:金沢/補充担任:金沢師管区 |
|
編成地:東京/補充担任:東京師管区 |
| 師団長:石野芳男中将 |
|
師団長:中西貞喜中将 |
| 最終上級部隊:第13方面軍 |
|
最終上級部隊:第59軍 |
| 最終位置:石川県津幡 |
|
最終位置:岡山 |
| 歩兵第334連隊 |
|
歩兵第319連隊 |
| 歩兵第335連隊 |
|
歩兵第320連隊 |
| 第231師団 |
|
第234師団 |
| 通称号:「大国」 |
|
通称号:「利根」 |
| 編成地:広島/補充担任:広島師管区 |
|
編成地:東京/補充担任:東京師管区 |
| 師団長:村田孝生中将 |
|
師団長:永野亀一郎中将 |
| 最終上級部隊:第59軍 |
|
最終上級部隊:第52軍 |
| 最終位置:山口 |
|
最終位置:千葉県八日市場 |
| 歩兵第346連隊 |
|
歩兵第322連隊 |
| 歩兵第347連隊 |
|
歩兵第323連隊 |
| 歩兵第348連隊 |
|
歩兵第324連隊 |
沿岸配備師団
| 第303師団 |
|
第308師団 |
| 通称号:「高師」 |
|
通称号:「岩木」 |
| 編成地:名古屋/補充担任:名古屋師管区 |
|
編成地:弘前/補充担任:弘前師管区 |
| 師団長:石田栄熊中将 |
|
師団長:朝野寅四郎中将 |
| 最終上級部隊:第40軍 |
|
最終上級部隊:第40軍 |
| 最終位置:鹿児島県川内 |
|
最終位置:青森県野辺地 |
| 歩兵第337連隊 |
|
歩兵第310連隊 |
| 歩兵第338連隊 |
|
歩兵第311連隊 |
| 歩兵第339連隊 |
|
歩兵第312連隊 |
| 第312師団 |
|
第316師団 |
| 通称号:「千歳」 |
|
通称号:「山城」 |
| 編成地:久留米/補充担任:久留米師管区 |
|
編成地:京都/補充担任:京都師管区 |
| 師団長:多田保中将 |
|
師団長:柏徳中将 |
| 最終上級部隊:第56軍 |
|
最終上級部隊:第53軍 |
| 最終位置:佐賀県伊万里 |
|
最終位置:神奈川県伊勢原 |
| 歩兵第358連隊 |
|
歩兵第349連隊 |
| 歩兵第359連隊 |
|
歩兵第350連隊 |
| 歩兵第360連隊 |
|
歩兵第351連隊 |
| 第320師団 |
|
第321師団 |
| 通称号:「宣武」 |
|
通称号:「磯」 |
| 編成地:京城/補充担任:京城師管区 |
|
編成地:東京/補充担任:東京師管区 |
| 師団長:八隅錦三郎中将 |
|
師団長:矢崎勘十中将 |
| 最終上級部隊:第17方面軍 |
|
最終上級部隊:第12方面軍 |
| 最終位置:釜山 |
|
最終位置:伊豆大島 |
| 歩兵第361連隊 |
|
歩兵第325連隊 |
| 歩兵第362連隊 |
|
歩兵第326連隊 |
| 歩兵第363連隊 |
|
歩兵第327連隊 |
| 第322師団 |
|
第344師団 |
| 通称号:「磐梯」 |
|
通称号:「剣山」 |
| 編成地:仙台/補充担任:仙台師管区 |
|
編成地:善通寺/補充担任:善通寺師管区 |
| 師団長:深堀游亀中将 |
|
師団長:横田豊一郎中将 |
| 最終上級部隊:第11方面軍 |
|
最終上級部隊:第55軍 |
| 最終位置:宮城県大河原 |
|
最終位置:高知県宿毛 |
| 歩兵第313連隊 |
|
歩兵第352連隊 |
| 歩兵第314連隊 |
|
歩兵第353連隊 |
| 歩兵第315連隊 |
|
歩兵第354連隊 |
| |
第351師団 |
|
第354師団 |
| |
通称号:「赤城」 |
|
通称号:「武甲」 |
| |
編成地:宇都宮/補充担任:宇都宮師管区 |
|
編成地:東京/補充担任:東京師管区 |
| |
師団長:藤村謙中将 |
|
師団長:山口信一中将 |
| |
最終上級部隊:第56軍 |
|
最終上級部隊:東京湾兵団 |
| |
最終位置:福岡県福間 |
|
最終位置:千葉県丸山 |
| |
歩兵第328連隊 |
|
歩兵第331連隊 |
| |
歩兵第329連隊 |
|
歩兵第332連隊 |
| |
歩兵第330連隊 |
|
歩兵第333連隊 |
| 第355師団 |
|
独立混成旅団 |
|
独立混成旅団 |
| 通称号:「那智」 |
|
独立混成第113旅団 |
|
独立混成第114旅団 |
| 編成地:姫路/補充担任:姫路師管区 |
|
独立混成第115旅団 |
|
独立混成第116旅団 |
| 師団長:武田寿中将 |
|
独立混成第117旅団 |
|
独立混成第118旅団 |
| 最終上級部隊:第54軍 |
|
独立混成第119旅団 |
|
独立混成第120旅団 |
| 最終位置:姫路 |
|
独立混成第121旅団 |
|
独立混成第122旅団 |
| 歩兵第355連隊 |
|
独立混成第123旅団 |
|
独立混成第124旅団 |
| 歩兵第356連隊 |
|
独立混成第125旅団 |
|
独立混成第126旅団 |
| 歩兵第357連隊 |
|
独立混成第127旅団 |
|
|

|
編成地:満州 寧安 通称号/略称:拓 所属軍:第1方面軍-第36軍 最終地:栃木県 栃木市吹上
昭和17年)6月、第1戦車団を基幹に満州寧安で編成され、機甲軍に属した。満州東部国境付近に
配置され 教育錬成を実施し有事の際には第1方面軍に配備する計画であった。
次いで、所属の戦車第3連隊と師団防空隊は大陸打通作戦に加わった。
昭和20年)3月、本土決戦に備えるため、戦車第1師団は日本本土へ移動し、
第12方面軍第36軍に編入された。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 星野利元 中将 |
1942年9月1日 - |
新潟県、第50軍司令官となり青森で本土決戦 |
| 細見惟雄 中将 |
1945年6月15日 - |
長野県、昭和17年陸軍機甲整備学校長に就任 |
参謀長:清水馨大佐 参謀:樋口六之助少佐 高級副官:宮地育三中佐
機甲軍創設時の戦車第1師団所属部隊
・戦車第1旅団
・戦車第1連隊 ・戦車第5連隊
・戦車第2旅団
・戦車第3連隊 昭和19年 第11軍に転属 中支で終戦
・戦車第9連隊 第31軍第43師団に転属 サイパン、グアムで全滅
機動歩兵第1連隊 戦車第1師団防空隊 戦車第1師団輜重隊
機動砲兵第1連隊 戦車第1師団工兵隊
戦車第1師団速射砲隊 戦車第1師団整備隊
戦車第1師団捜索隊(戦車第26連隊に改編 第1軍第109師団に転属 昭和19年 硫黄島で全滅)
最終所属部隊
戦車第1連隊(福岡):中田吉穂大佐 戦車第5連隊(福岡):杉本守衛大佐
機動歩兵第1連隊(久留米):沢敏行大佐 機動砲兵第1連隊(福岡):神部英彦中佐
戦車第1師団速射砲隊:須山正規少佐 戦車第1師団工兵隊:安藤進少佐
戦車第1師団整備隊:鈴木宣少佐 戦車第1師団輜重隊:前野重弘中佐
戦車第1師団通信隊:森田一雄少佐

編成地:満州 勃利 通称号/略称:撃 所属軍:第14方面軍 最終地:ルソン島
昭和17年)6月 - 第2戦車団を基幹に満州勃利で編成され、機甲軍に属した。
昭和19年2月 所属の戦車第11連隊は第5方面軍第91師団に編入され北千島へ移動しソ連軍と占守島の戦い
昭和19年)7月 - 第14方面軍に編入されルソン島に移動、全滅した(フィリピンの戦い)。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 岡田資 中将 |
昭和17年9月 |
取県、その後第十三方面軍司令官兼東海軍管区司令官親補 |
| 岩仲義治 中将 |
昭和18年12月 |
- |
機甲軍創設時の戦車第2師団所属部隊
・戦車第3旅団
・戦車第6連隊 ・戦車第7連隊
・戦車第4旅団
・戦車第10連隊(連隊長:原田一夫中佐 九五式軽戦車(10輌)・装甲兵車(2輌)・自動貨車(4輌))
・戦車第11連隊(第5方面軍第91師団に転属、北千島へ移動)
機動歩兵第2連隊 機動砲兵第2連隊 戦車第2師団速射砲隊
戦車第2師団捜索隊 (第27戦車連隊へ改編、第10方面軍第32軍第24師団に転属、沖縄へ)
戦車第2師団防空隊 (第6方面軍第20軍に転属)
戦車第2師団工兵隊 (1945年1月、リンガエン湾に上陸した米軍に対して在留邦人を保護するため師団主力と
に共に敵を食い止めた。その後3月にはサラクサク峠で戦い、5月山中で全滅した。)
戦車第2師団整備隊 戦車第2師団輜重隊
最終所属部隊
・戦車第3旅団
戦車第6連隊 戦車第7連隊 戦車第10連隊
機動歩兵第2連隊 戦車第2師団工兵隊 患者収容隊
機動砲兵第2連隊 戦車第2師団整備隊
戦車第2師団速射砲隊 戦車第2師団輜重隊

編成地:内蒙古 包頭 通称号/略称:滝 所属軍:駐蒙軍-第12軍 最終地:
昭和17年)6月 - 駐蒙の騎兵集団を改編して中国戦線で編成された。北支那方面軍の駐蒙軍に属した。
昭和19年)4月 - 北支那方面軍の第12軍に編入された。大陸打通作戦に参加する。
昭和19年)7月 - 戦車第6旅団が湘桂作戦に参加する。昭和20年)3月 - 老河口作戦に参加する。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 西原一策中将 |
昭和17年12月 |
広島県、昭和16年 騎兵集団長・陸軍中将、昭和19年)1月- 陸軍機甲本部長 |
| 山路秀男中将 |
昭和19年1月 |
- |
所属部隊:創設時
・戦車第5旅団
・戦車第8連隊 : 昭和17年9月第8方面軍に転出、ラバウルへ
・戦車第12連隊: 昭和20年4月第17方面軍に転出、京城へ
・戦車第6旅団
・戦車第13連隊
・戦車第17連隊
機動歩兵第3連隊 機動砲兵第3連隊 戦車第3師団速射砲隊 戦車第3師団捜索隊
戦車第3師団防空隊 戦車第3師団工兵隊 戦車第3師団整備隊 戦車第3師団輜重隊
所属部隊:最終
・戦車第6旅団
・戦車第13連隊
・戦車第17連隊
機動歩兵第3連隊 機動砲兵第3連隊 戦車第3師団速射砲隊 戦車第3師団捜索隊
戦車第3師団防空隊 戦車第3師団工兵隊 戦車第3師団整備隊 戦車第3師団輜重隊

編成地:習志野 通称号/略称:鋼 所属軍:第36軍 最終地:千葉
昭和19年)7月 - 戦車、騎兵、野戦砲兵、工兵、輜重兵各学校教導部隊を基幹に師団編成
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 名倉栞 中将 |
昭和19年7月 |
東京、昭和16年第20軍参謀長 |
| 閑院宮春仁王少将 |
昭和20年8月 |
閑院宮載仁親王の第2王子 |
| 名倉栞 中将 |
昭和20年8月 |
- |
所属部隊
戦車第28連隊 戦車第29連隊 戦車第30連隊
戦車第4師団高射砲隊 戦車第4師団整備隊
戦車第4師団通信隊 戦車第4師団輜重隊
戦車第4師団機関砲隊(昭和20年4月編成)
 
|
編成地:東京 通称号/略称:晴 所属軍: 最終地:東京の久我山
1944年12月、主として京浜地方を主とする政治、経済、軍需の中枢を防衛するため編成された。B-29の日本
本土空襲に対応して、各地に展開した
1944年11月からのB-29による関東地区の軍事工場などに対する高々度精密爆撃に対しては、
九九式八糎高射砲では射撃高度が不足したため、三式12cm高射砲が導入された。
1945年5月に、司令部を代官山から上野の東京科学博物館本館(現国立科学博物館日本館)へ移転した。
1945年7月、東京の久我山高射砲陣地に五式十五糎高射砲が配備され、B-29の空襲に備えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 金岡? 中将 |
1944年12月 |
- |
参謀長:斎藤寿恵雄大佐 参謀:鈴木実次中佐 山本悦男少佐 倉橋一次少佐
高級副官:中元寛中佐 兵器部長:佐野四郎大佐
所属部隊
高射砲第111連隊(安行村):武田文雄大佐 独立高射砲第44大隊(大垣):隈本茂少佐
高射砲第112連隊(世田谷):大島知義中佐 独立高射砲第49大隊(福生):鈴木光太郎少佐
高射砲第113連隊(川崎):都築晋大佐 独立高射砲第50大隊:粟屋武少佐
高射砲第114連隊(月島):西野貞光大佐 野戦高射砲第95大隊(大宮):鈴木三七一少佐
高射砲第115連隊(市川):伏屋宏大佐 野戦高射砲第96大隊:
高射砲第116連隊(板橋):谷口正三郎大佐 機関砲第1大隊:西辻勝三少佐
高射砲第117連隊(横浜):樋口忠治中佐 機関砲第4大隊(川崎):高木学大尉
高射砲第118連隊(後楽園):栗田逞治中佐 独立機関砲第1大隊(四谷):桑田一少佐
高射砲第119連隊(市川):水野縫一少佐 照空第1連隊(八王子):池田赳夫大佐
独立高射砲第2大隊(立川):中野唯一少佐 独立照空第1大隊(上尾):中島良象少佐
独立高射砲第3大隊(国府台):栗田正忠中佐 第1要地気球隊:百田明福大尉
独立高射砲第4大隊(太田):渡辺正吾少佐 第101要地気球隊:佐藤正一大尉
臨時衛生隊:太田房吉軍医少佐
 
編成地:名古屋 通称号/略称:逐 所属軍: 最終地:名古屋 中心とする中部
1945年5月、主として名古屋地区を主とする政治、軍事、軍需の中枢を防衛するため編成され、司令部は
名古屋市昭和区鶴舞の名古屋市公会堂内に置かれた。新編の部隊は6月に編成を終え、主な工場地帯や
交通の要地に配置された。鉄道の防御強化が図られ、東海道線、関西線の主要河川鉄橋に
高射砲、機関砲を配備した。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 入江莞爾 少将 |
1945年5月 |
- |
参謀:内田久次中佐 参謀:串戸守雄中佐
所属部隊
高射砲第124連隊(愛知県上野):山田正樹中佐 野戦高射砲第97大隊
高射砲第125連隊(名古屋):大中正光中佐 機関砲第12大隊:飯川寅男少佐
独立高射砲第5大隊:津田惣一少佐 機関砲第106大隊:吉和清少佐
独立高射砲第12大隊(清水):三宅正雄中佐 独立照空第11大隊:中田一男大尉
独立高射砲第47大隊:大伴功少佐
 
編成地:大阪 通称号/略称:炸(さく) 所属軍: 最終地:関西 大阪、京都
1945年5月、主として阪神地区を主とする政治、軍事、軍需の中枢を防衛するため編成された。
阪神地区のほか、敦賀、宇部、高松、新居浜、吹田、枚方、京都などにも部隊を展開した。
7月には、空襲で焼け野原となった大阪、神戸の部隊の一部を、空襲を受けていない京都、広島に展開。
広島には派遣中隊の一部のみが到着した段階で原爆投下が行われた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 河合潔 少将 |
1945年5月 |
- |
参謀:森山元中佐 参謀:多羅尾光孝少佐 参謀:三品幸三郎少佐
所属部隊
高射砲第121連隊(大阪):樋口易信大佐
高射砲第122連隊(大阪北部):五峯作一大佐
高射砲第123連隊(神戸):山岡重孝中佐
独立高射砲第11大隊(尼崎):小木節三中佐 独立高射砲第22大隊:加藤恒太少佐
独立高射砲第13大隊(大阪):藤野毅一中佐 独立高射砲第45大隊:富田洋平少佐
機関砲第11大隊:前田俊夫少佐
 
編成地:小倉 通称号/略称:彗 所属軍:第57軍-第16方面軍 最終地:北九州地区
1945年5月、主として北九州地区を主とする政治、軍事、軍需の中枢を防衛するため編成された。
沖縄戦中はアメリカ軍の九州への空襲が頻繁となり、その防空戦闘に従事。5月に師団主力が都城付近に
移動し第57軍の指揮下に入り、第57軍高射砲隊(長:師団長)を編成し、南九州の飛行場、軍事施設等の
防空を実施するとともに野戦防空を準備した。
師団主力南進後、第4高射砲隊司令部は第16方面軍指揮下に入り、北九州地区の防空任務に従事した。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 伊藤範治 中将 |
1945年5月 |
- |
参謀長:寺尾征太露中佐 参謀:稲永一衛中佐 参謀:榎本健二郎少佐
高級副官:前原雪一少佐
所属部隊
・第4高射砲隊司令部(小倉):平向九十九少将
・高射砲第131連隊(八幡):刈谷春次大佐 ・高射砲第132連隊(小倉):飯塚国松大佐
・高射砲第133連隊(福岡):池辺栄弘中佐 ・高射砲第134連隊(長崎):力石静夫中佐
・高射砲第136連隊(都城):篠浦信一中佐 ・独立高射砲第21大隊(大牟田):伊都荘二少佐
・独立高射砲第23大隊:清宮正雄少佐 ・独立高射砲第24大隊:小川武夫少佐
・独立高射砲第43大隊:国友健次郎少佐 ・野戦高射砲第98大隊:高瀬源治少佐
・機関砲第5大隊 ・機関砲第21大隊:小林永知少佐
・独立照空第21大隊:菅吉雄大尉 ・第21要地気球隊:藤井武雄大尉
・第1機関砲教育隊:近藤義夫少佐
  |
編成地:札幌、帯広 通称号/略称:鏑(かぶら)1045 所属軍:第5方面軍 最終地:札幌
第1飛行集団司令部は1938年6月、東京で編成され内地の防衛を担当した。その後、司令部は岐阜へ移動し、
1942年に解隊した。1943年1月、第1飛行師団として再編成され、司令部を各務原に置き、内地の防衛を担当。
昭和19年)、北海道・千島列島の防衛担当となり、司令部を札幌に移動させ第5方面軍に属した。
その後、司令部を帯広に移動したが、終戦時は札幌に所在。
第1飛行集団長は記載しません
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 原田宇一郎 中将 |
1943年1月 |
滋賀県、昭和17年独立第20飛行団長、陸軍中将、第2航空軍司令官 |
| 佐藤正一 中将 |
1945年6月 |
- |
参謀長:成田貢大佐 参謀:高橋敏雄少佐 参謀:西村守雄少佐 高級副官:井上弘中佐
所属部隊 (第1飛行師団)
戦闘部隊
・第20飛行団:甘粕三郎大佐
・飛行第54戦隊(戦闘):竹田勇少佐 ・飛行第32戦隊(襲撃):岡村正義少佐
・第38独立飛行隊:小林実少佐
飛行場部隊
・第38航空地区司令部:鵜飼秀熊大佐 ・第39航空地区司令部:小川清水大佐
・第55飛行場大隊:河野宗少佐 ・第49飛行場大隊:久保田時蔵少佐
・第77飛行場大隊:神戸三夫少佐 ・第63飛行場大隊:坂東丈平大尉
・第83飛行場大隊:市島英雄少佐 ・第80飛行場大隊:寺沢憲三少佐
・第52航空地区司令部:楢木茂中佐
・第1飛行場大隊:原口作太郎少佐 ・第73飛行場大隊:工藤茂助少佐
・第2飛行場大隊:吉本勇太郎少佐 ・第178飛行場大隊:岩下栄吉少佐
・第12野戦飛行場設営隊:戸村丑末少佐 ・第21野戦飛行場設営隊:小林績少佐
通信関連部隊
第10航空通信連隊:古谷龍中佐 第11対空無線隊:藤井啓生大尉
第6航空特種通信隊:臼田玄次郎少佐 第12対空無線隊:渡辺淳大尉
第20航空情報隊:黒須三郎少佐 第1航空固定通信隊:江口宗三中佐
第20航空測量隊:高木利光少佐
整備・補給関連部隊
第119独立整備隊:渡辺三雄中尉 第6野戦航空修理廠:中原寛治大佐
第139独立整備隊:小田敬雄大尉 第6野戦航空補給廠:杉原清吉中佐
第150独立整備隊:平林光夫中尉 第11野戦気象隊:小林繁亀少佐
 
編成地:満州 通称号/略称:鷲 所属軍:第4航空軍-第3航空軍 最終地:ミンダナオ島
満州事変勃発以降の航空兵力増強のため、1931年(昭和6年)6月11日、関東軍飛行隊が平壌で編成された。
その後、新京を本拠地とし1935年12月2日に関東軍飛行集団、1937年8月2日に第2飛行集団とそれぞれ改称
そして、1942年(昭和17年)4月15日に第2飛行師団と改称し、満州での防空を担当した。
太平洋戦争後期に入りフィリピンの戦いに参戦のため、1944年5月にフィリピンに転用され第4航空軍隷下となった
第4飛行師団から所属航空機の移管を受けてレイテ島の戦いに参戦。アメリカ軍艦船や飛行場への攻撃、
船団護衛を担い、特攻機による攻撃なども行ったが、戦力が枯渇した。
1945年1月1日以降、第3航空軍の区処を受け、同年2月に第4航空軍の廃止に伴い第7飛行師団とともに
第3航空軍の隷下となった。同年3月下旬、司令部と残存飛行部隊はミンダナオ島に移動。
4月下旬、司令部はシンガポールに移り、5月17日に解散した。
第2飛行師団(太平洋戦争時)よりの師団長と所属部隊を記載する,
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 寺本熊市 中将 |
1942年4月 |
- |
| 河辺虎四郎 中将 |
1943年5月 |
富山県、陸軍航空総監部次長。参謀次長 |
| 下山琢磨 中将 |
1943年5月 |
福井県、第3飛行師団長、第5航空軍司令官に就任し京城で終戦 |
| 山瀬昌雄 中将 |
1943年9月 |
- |
| 木下勇 中将 |
1944年10月 |
福井県、、第55航空師団長。山梨県上空で搭乗機が墜落し戦死 |
| 寺田済一 中将 |
1944年11月 |
- |
参謀長:内田厚生大佐 参謀(作戦):野々垣四郎中佐 参謀(後方):鈴木清少佐
参謀(情報):伊藤禎三少佐 高級副官:上村三太夫中佐
所属部隊(1944年5月現在)
戦闘部隊
・第6飛行団司令部:小野門之助大佐
・飛行第32戦隊(軽爆):岡村正義少佐
・飛行第66戦隊(軽爆):佐藤辰男少佐
・飛行第70戦隊(戦闘):長縄勝己少佐
・第13飛行団司令部:江山六夫中佐
・飛行第65戦隊(襲撃):石原政雄中佐
・第28独立飛行隊(司偵)(温春):国枝治平中佐
飛行場部隊
・第6航空地区司令部
・第13航空地区司令部:細野光武中佐
・第26飛行場大隊 ・第37飛行場大隊 ・第86飛行場大隊

編成地:中国 南京 通称号/略称:隼 所属軍:第5航空軍 最終地:中国
航空兵団の関東軍編入に伴い、第3飛行集団は1939年9月に編成され、北中国における作戦を担った。
太平洋戦争開戦後、マレー作戦、蘭印作戦、ビルマの戦いに参戦。その後、中国に戻り南京に司令部を置いた。
1942年4月、第3飛行師団と改称。1944年2月、大陸打通作戦などに対応するため解散し、新たに第5航空軍が編成された。
第3飛行師団(太平洋戦争時)よりの師団長と所属部隊を記載する
| 師団長名 |
赴任年月 |
備考 |
| 菅原道大 中将 |
1942年4月 |
- |
| 中薗盛孝 中将 |
1942年7月 |
鹿児島、昭和18年)9月、搭乗機が広東上空で撃墜され戦死 |
| 下山琢磨 中将 |
1943年9月 |
福井県、第2飛行師団長、第5航空軍司令官に就任し京城で終戦 |
参謀長:参謀長:吉井宝一大佐 参謀(作戦):宮沢太郎中佐 参謀(情報):高田増実少佐
参謀(後方):浜田要少佐 兵器部長:平山清助大佐
最終所属部隊
戦闘部隊
・第1飛行団司令部(漢口):小林孝知大佐 ・飛行第90戦隊(軽爆):三木了中佐
・飛行第16戦隊(軽爆):甘粕三郎中佐 ・独立飛行第18中隊(司偵):青木秀夫少佐
・飛行第25戦隊(戦闘):坂川敏雄少佐 ・独立飛行第83中隊(軍偵):浜野宗房少佐
・飛行第44戦隊(偵察):福沢丈夫中佐 ・第8直協飛行隊
教導部隊
・第105教育飛行団司令部(北京):近藤三郎大佐
・第114教育飛行連隊(戦闘) ・第118教育飛行連隊(戦闘)
・第115教育飛行連隊(司偵)
飛行場部隊
第3航空地区司令部:高崎栄作中佐 第5航空地区司令部:山田与吉中佐
第16航空地区司令部:伊藤正一中佐
第18飛行場大隊(軽爆) 第31飛行場大隊(軽爆)
第57飛行場大隊(偵察) 第91飛行場大隊(軽爆)
第96飛行場大隊(重爆)
通信関連部隊
第15航空通信隊:吉村清中佐 第5航空固定通信隊
第6航空情報連隊:許斐専吉中佐 第5航空測量隊:我部俊雄大尉
支那派遣軍気象隊:太田鐸治中佐
整備・補給関連部隊
第15野戦航空廠 第23航空分廠
 
編成地:満州-フィリピン 通称号/略称:翼 所属軍: 最終地:
第4飛行集団は1942年2月に編成され満州の防衛を担当した。同年4月、第4飛行師団と改称。
太平洋戦争末にフィリピンに転じ、保有航空機のほとんどを第2飛行師団に移管し、基地管理の
任務に特化した師団となった。その後、地上での持久戦を継続して終戦を迎えた。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 下山琢磨 中将 |
1942年4月 |
福井県、第2飛行師団長、第5航空軍司令官に就任し京城で終戦 |
| 阪口芳太郎 中将 |
1943年5月 |
- |
| 木下勇 中将 |
1944年3月 |
福井県、、第55航空師団長。山梨県上空で搭乗機が墜落し戦死 |
| 三上喜三 中将 |
1944年10月 |
- |
参謀長:猿渡篤孝大佐 参謀:前島美佐男中佐 参謀:辻秀雄少佐 高級副官:瀧本美代治中佐
兵器部長:楠二郎中佐
最終所属部隊
戦闘部隊
独立飛行第52中隊(軍偵):手島丈夫少佐
飛行場部隊
第6航空地区司令部(ネグロス島):弓削伊三郎大佐
第10航空地区司令部(クラーク):江口清助大佐
第13航空地区司令部(ダバオ):細野光武中佐
第31航空地区司令部(カガヤン):清水茂中佐
第33航空地区司令部(リバ):戸根木亀之助大佐
第34航空地区司令部:新田正義大佐
第36航空地区司令部:若月金丸大佐
第8飛行場大隊:石黒寛少佐 第12飛行場大隊:井手継人少佐
第14飛行場大隊:島村吉太郎少佐 第26飛行場大隊:仲沢忠男少佐
第32飛行場大隊:渡辺敬少佐 第33飛行場大隊:平山彦助少佐
第31飛行場大隊:樋口次三郎少佐 第37飛行場大隊:牟田和惣少佐
第98飛行場大隊:荒木隆少佐 第99飛行場大隊:飯田英夫大尉
第102飛行場大隊:中川円二少佐 第103飛行場大隊:鈴木俊三少佐
第114飛行場大隊:南田多治郎少佐 第123飛行場大隊:小見山文蔵少佐
第124飛行場大隊:竹内馨少佐 第125飛行場大隊:天野順司少佐
第126飛行場大隊: 第127飛行場大隊:楠田武治少佐
第136飛行場大隊:加瀬良一大尉 第137飛行場大隊:星野喜松少佐
第150飛行場大隊:嘉瀬井正一大尉 第151飛行場大隊:斎藤武雄少佐
第152飛行場大隊:仲田礼治少佐 第153飛行場大隊:渡辺吉蔵少佐
第154飛行場大隊:山下武男少佐
第3野戦飛行場設定司令部(ダバオ):阿部修一大佐
第5野戦飛行場設定司令部:川本喜蔵大佐
第24野戦飛行場設営隊:興井作太郎少佐 第125野戦飛行場設営隊:戸田与右衛門少佐
第126野戦飛行場設営隊:高野佳雄少佐 第127野戦飛行場設営隊:安本晃少佐
第134野戦飛行場設営隊:奥村国三少佐 第135野戦飛行場設営隊:岩佐緑少佐
第138野戦飛行場設営隊:植田武男大尉 第140野戦飛行場設営隊:村上秀策少佐
通信関連部隊
第22野戦気象観測隊:佐野年久少佐
整備・補給関連部隊
第7野戦航空補給廠:武内与作少佐
 
編成地:ビルマ-仏印 通称号/略称:高 所属軍: 最終地:サイゴン
第5飛行集団は1940年12月に編成された。太平洋戦争開戦後、フィリピンの戦いに参戦。
その後、1942年、ビルマに転じ、同年4月、第5飛行師団と改称。ビルマの戦いの諸作戦に参加。ビルマにおける
戦況悪化に伴い、戦力を低下させた。1945年5月にはビルマから撤退し、プノンペンに司令部を移し、
部隊の一部はサイゴンに後退し終戦を迎えた。
使用機種:九七式重爆撃機・九七式軽爆撃機・九九式双発軽爆撃機・九七式戦闘機・一式戦闘機・
九七式司令部偵察機・一〇〇式司令部偵察機
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 小畑英良 中将 |
1942年4月 |
大阪、第3航空軍司令官、第31軍司令官となり、同年8月、グァム島で玉砕 |
| 田副登 中将 |
1943年5月 |
熊本、第8飛行団長後第5飛行師団長、航空総軍参謀長に就任し終戦 |
| 服部武士 中将 |
1944年12月 |
- |
参謀長:桑塚城大佐 参謀:緒方奨少佐 参謀:串岡周甫少佐 高級副官:斎藤照之助中佐
最終所属部隊
戦闘部隊
第4飛行団司令部:辻本隼三中佐
飛行第64戦隊(戦闘):宮辺英夫少佐 飛行第81戦隊(司偵):鈴木正雄少佐
飛行場部隊
第1航空地区司令部:塚本初雄大佐
第7航空地区司令部:伊藤稔中佐
第15飛行場大隊:斉藤武夫大尉 第17飛行場大隊:豊島幸三郎少佐
第19飛行場大隊:平井静少佐 第23飛行場大隊:岩持昌克大尉
第34飛行場大隊:大和勇三大尉 第52飛行場大隊:橋本政雄大尉
第75飛行場大隊:泉永二郎少佐 第78飛行場大隊:大宮司明少佐
第81飛行場大隊:時任早夫少佐 第82飛行場大隊:加藤美知雄少佐
第85飛行場大隊:古沢義四郎少佐 第90飛行場大隊:臼井喬少佐
第92飛行場大隊:熊谷芳己少佐 第94飛行場大隊:市川浩大尉
第7野戦飛行場設営隊:白川弘大尉 第8野戦飛行場設営隊:藤枝操大尉
高射砲第20連隊:野中侃中佐 野高第36大隊(乙):柳町平八郎少佐
通信関連部隊
第2航空情報連隊:来海民夫中佐
整備・補給関連部隊
独立自動車第35大隊
 
編成地:ラバウル-ニュ-ギニア 通称号/略称:洋 所属軍:第8方面軍 最終地:
1942年11月、南太平洋方面でのアメリカ軍航空兵力増強に対抗するため編成され第8方面軍隷下に編入した。
兵力は満州などの部隊から抽出され、ラバウルに司令部を置いた。東部ニューギニア方面での
航空戦、船団護衛を担当するが、次第に戦力が低下した。
昭和18年)4月、司令部をラバウルからニューギニア北東部のウェワク飛行場に移動。同年7月、
苦戦中の第6飛行師団を支援するため、第7飛行師団主力がニューギニアに移動し、司令部をブーツに置いた。
苦戦中の第6飛行師団を支援するため、第7飛行師団主力がニューギニアに移動し、司令部をブーツに置いた。
1943年8月17日から18日にかけ米第5空軍は、ウェワクおよびブーツの各飛行場を攻撃し、第6、第7飛行師団は
大打撃を受けた。同年10月、第7飛行師団はインドネシア、アンボンに後退した。
1944年3月26日、ウェワクからホーランディアに移動。4月22日、米陸軍第41歩兵師団などがホーランディアに
上陸を開始したため、基地部隊は多大な犠牲を払いながら山中を踏破しサルミに退却した。
師団は戦力を喪失したため、同年8月に解散した。
使用機種:九九式双発軽爆撃機・一式戦闘機・三式戦闘機・一〇〇式司令部偵察機・九九式軍偵察機
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 板花義一 中将 |
1942年11月 |
陸軍航空通信学校長を経て第2航空軍司令官、予備役編入 |
| 稲田正純 少将 |
1944年4月 |
昭和20年4月、陸軍中将、第16方面軍参謀長、戦犯容疑重労働7年 |
参謀長:徳永賢治大佐 参謀:岡本貞雄中佐 参謀:首藤忠男少佐 参謀:杉村良夫少佐
参謀:上田出少佐 高級副官:宮崎敏美中佐
所属部隊 (第1飛行師団)
戦闘部隊
独立飛行第83中隊(軍偵):宮永築大尉 飛行第10戦隊(司偵):下村兵一中佐
飛行第33戦隊(戦闘):福地勇雄少佐 飛行第34戦隊(軽爆):福地勇雄少佐
飛行第63戦隊(戦闘):原孫治少佐 飛行第208戦隊(軽爆):加島誠輝中佐
飛行第248戦隊(一式戦):黒田武文少佐 白城子陸軍飛行学校教導飛行団:森玉徳光大佐
飛行場部隊
白城子教導航空地区司令部:浅田宰中佐
第25飛行場大隊(重爆) 第47飛行場大隊(軽爆)
第48飛行場大隊(偵察) 第51飛行場大隊(戦闘
第209飛行場大隊(軽爆) 第5野戦飛行場設定隊
第6野戦飛行場設定隊 第10野戦飛行場設定隊
第11野戦飛行場設定隊
第12航空地区司令部:小原重蔵中佐
第21飛行場大隊(戦闘) 第22飛行場大隊(戦闘)

所在地:シンガポール 通称号/略称:襲 所属軍:第3航空軍-第4航空軍 最終地:インドネシア、アンボン
1943年(昭和18年)1月、シンガポールで編成され第3航空軍隷下に入った。当初の任務は、スマトラ島から
バンダ海にわたる区域の海洋哨戒、航空防衛、地上作戦協力などであった。
1943年6月20日、北オーストラリアダーウィンへの日本陸軍機初の空襲を実施。
1943年7月、ニューギニア島東岸で苦戦中の第6飛行師団を応援するため、主力がニューギニアに移動し、
司令部をブーツに置いた。この方面に二個飛行師団が配置されたことから、第4航空軍が創設されその隷下となる。
1943年8月17日から18日にかけ米第5空軍は、ウェワクおよびブーツの各飛行場を攻撃し、第6、第7飛行師団は
大打撃を受けた。同年10月、第7飛行師団はインドネシア、アンボンに後退した。
アンボンに移動してからジャワ島東方での船団護衛などに当たった。1945年2月、第4航空軍の廃止に伴い
第2飛行師団とともに第3航空軍の隷下となった。戦力の低下と本土決戦への対応のため、同年7月に解散した。
使用機種:百式重爆撃機・九九式双発軽爆撃機・一式戦闘機・二式複座戦闘機・一〇〇式司令部偵察機
九九式軍偵察機
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 須藤栄之助 中将 |
1943年1月 |
東京、防衛総軍司令部、第1総軍両軍本土決戦に備え両軍の総参謀長 |
| 白銀重二 中将 |
1945年2月 |
山口、、第9飛行師団長スマトラ島のパレンバン油田地帯の防衛に当たり終戦 |
参謀長:吉満末盛中佐 参謀(施設):東愛吉少佐 参謀(通信):辺見重孝少佐
参謀(後方):槇安之少佐 高級副官:白井日出雄中佐
最終所属部隊
戦闘部隊
独立飛行第73中隊(軍偵):春成兼正少佐 飛行第13戦隊(戦闘):町田久雄少佐
飛行第24戦隊(戦闘):庄司孝一少佐 飛行第208戦隊(軽爆):加島誠輝中佐
第9飛行団司令部:
飛行第61戦隊(重爆):堀川正三郎少佐
第3飛行団司令部:三宅友美大佐
独立飛行第70中隊(司偵):市川蔵康少佐 飛行第75戦隊(軽爆):土井勤中佐
飛行場部隊
第4航空地区司令部: 第9航空地区司令部:赤沢正之丞中佐
第32航空地区司令部:古閑武夫中佐
第5飛行場大隊: 第28飛行場大隊:武松哲夫大尉
第35飛行場大隊:小林貞一大尉 第68飛行場大隊:田中正夫大尉
第70飛行場大隊:佐藤秀雄大尉 第72飛行場大隊:阿部万治大尉
第107飛行場大隊:大参省一少佐 第108飛行場大隊:山岸長蔵少佐
第109飛行場大隊:水谷勇夫大尉 第113飛行場大隊:
第9飛行場大設定隊:川崎計三少佐
通信関連部隊
第9航空通信連隊:野辺常介少佐 第8航空情報連隊:松元朝雄少佐
第13野戦気象隊:中川勇少佐
整備・補給関連部隊
第21野戦航空修理廠:新保稔中佐 第21野戦航空補給廠:柳瀬良平少佐

所在地:東京-台北 通称号/略称:誠 所属軍:第6航空軍 最終地:沖縄特攻隊
1944年(昭和19年)6月10日、東京の第1航空軍司令部で司令部が編成され、同月中に台湾の台北へ移動した。
台湾および南西諸島の航空作戦を担当、台湾沖航空戦では海軍の指揮下で、来襲する
アメリカ空母機動部隊航空隊を邀撃した。
沖縄戦では第6航空軍とともに特攻を主体として戦った。内地から師団に配属された特攻隊は、台湾まで
到着することなく南九州で任務を受けて突入したものも少なくない。沖縄戦期間、突入した特攻隊は
延べ30個隊・245名を数えている。司令部通称号は「誠18901」。
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 山本健児 少将 |
1944年6月 |
高知、心得で昭和19年10月、陸軍中将に進み、第8飛行師団長に親補 |
| 山本健児 中将 |
1944年10月 |
- |
参謀長:岸本重一大佐 参謀長:岸本重一大佐 高級参謀:石川寛一中佐 参謀:川元浩中佐
参謀:西篤少佐 参謀:川野剛一少佐 高級副官:星光中佐
最終所属部隊
戦闘部隊
第9飛行団:柳本栄喜大佐
飛行第61戦隊(重爆):堀川正三郎少佐
第22飛行団:藤田隆中佐
飛行第17戦隊(三式戦):高田義郎少佐 飛行第19戦隊(三式戦):栗山深春大尉
第25飛行団:山崎武治中佐
飛行第8戦隊(軽爆):長屋義衛中佐 飛行第10戦隊(司偵):新沢勉中佐
飛行第13戦隊(戦闘):丸山公一少佐 飛行第20戦隊(一式戦):深見和雄少佐
飛行第21戦隊(戦闘):佐藤熈少佐 飛行第24戦隊(戦闘):庄司孝一少佐
飛行第29戦隊(二式戦):小野勇大尉 飛行第50戦隊(戦闘):河本幸喜少佐
飛行第58戦隊(重爆):中嶌隆弘少佐 飛行第105戦隊(三式戦):吉田長一郎少佐
飛行第108戦隊(輸送):古川日出夫中佐 飛行第204戦隊(戦闘):村上浩少佐
飛行第3戦隊(軽爆): 飛行第14戦隊(重爆):朝山小二郎中佐
飛行第26戦隊(一式戦):永田良平少佐 飛行第67戦隊(襲撃):佐藤辰男少佐
第206独立飛行隊(対潜):蓑毛松次中佐
独立飛行第23中隊(戦闘):大村信大尉 独立飛行第46中隊(対潜):
教導部隊
第3練成飛行隊(戦闘):杉本明少佐 第7教育飛行隊(戦闘):西島道助少佐
第8教育飛行隊(戦闘): 第10航空教育隊:丸山茂夫中佐
飛行場部隊
第38航空地区司令部:鵜飼秀熊大佐
第138飛行場大隊:山本信清大尉 第139飛行場大隊:金栗敏光少佐
第39航空地区司令部:小川清水大佐
第156飛行場大隊:田岡禎二大尉
第52航空地区司令部:楢木茂中佐
第187飛行場大隊:
第53航空地区司令部:大久保幸平中佐
第112飛行場大隊:酒井健一少佐 第188飛行場大隊
通信関連部隊
第16航空通信連隊:宇佐川武雄中佐 第16航空通信隊:玉井三郎少佐
第21航空通信隊:小鷲武雄中佐 第8航空特種通信隊:
第9航空測量隊: 第82対空無線隊:
整備・補給関連部隊
独立整備隊: 第5野戦航空修理廠:河村孝三郎大佐
第5野戦航空補給廠:柿原功中佐 第10野戦気象隊:肥佐多弁中佐
 
所在地:バレンバン 通称号/略称:翔 所属軍: 最終地:
1942年3月に日本軍が占領したスマトラ島北東部のパレンバン油田地帯の防衛のため、1943年12月に編成。
油田地帯の防衛にあたるとともに、イギリス海軍機動部隊作戦などに従事し終戦を迎えた。
使用機種:二式単座戦闘機・二式複座戦闘機・一式戦闘機・九九式襲撃機・一〇〇式司令部偵察機
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 鳥田隆一 中将 |
1943年12月 |
- |
| 橋本秀信 中将 |
1944年10月 |
- |
| 白銀重二 中将 |
1945年7月 |
山口、昭和19年、陸軍中将に進んだ、第7飛行師団長 |
参謀長:神笠武登中佐 兵器部長:海老原好中佐 経理部長:羽柴虎十郎主計中佐
最終所属部隊
戦闘部隊
飛行第87戦隊(戦闘):中野猪之八少佐 独立飛行第74中隊(司偵):湯地定三大尉
飛行場部隊
第8航空地区司令部:石原勘一郎大佐
第22航空地区司令部:村上儀太郎大佐
第46飛行場大隊:佐藤忠作少佐 第76飛行場大隊:目次忠夫少佐
第87飛行場大隊:渡辺政美少佐 第89飛行場大隊:八丁鶴夫少佐
通信関連部隊
第7航空情報連隊:岡村富雄中佐 第14航空情報連隊:権代良一中佐
第18航空情報隊:徳重房夫少佐

所在地:東京 通称号/略称:天翔 所属軍: 最終地:調布
昭和19年)3月、主として関東地区の防空のため編成され、司令部を調布飛行場に置いた。
1944年11月初頭からは来襲するB-29に体当たりを含めた迎撃にあたった(震天制空隊)。
1945年5月、司令部を竹橋に移転させ、第12方面軍司令部、高射第1師団との連絡の緊密化を図った。
使用機種:一式戦闘機・二式単座戦闘機・二式複座戦闘機・三式戦闘機
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 吉田喜八郎 少将 |
1944年3月 |
北海道、心得、昭和20年3月、陸軍中将に第13飛行師団長に親補南京で終戦 |
| 近藤兼利 中将 |
1945年3月 |
- |
参謀長:笹尾宏大佐 参謀:山本茂男少佐 参謀:栂博少佐 参謀:岩下徳治少佐
高級副官:吉田義倶少佐
最終所属部隊
戦闘部隊
飛行第18戦隊(三式戦):黒田武文少佐 飛行第23戦隊(一式戦):谷口正義少佐
飛行第53戦隊(二式複戦):児玉正人少佐 飛行第70戦隊(二式戦):坂戸篤行少佐
飛行場部隊
第46航空地区司令部(茨城):杉本健次郎大佐
第3飛行場大隊:堤袈裟市少佐 第6飛行場大隊:小林勝由少佐
第7飛行場大隊:沼沢広大尉 第43飛行場大隊(成増):石塚勇一郎少佐
第116飛行場大隊:伊藤敏少佐 第140飛行場大隊:弘兼久一少佐
第141飛行場大隊:野上正大尉 第244飛行場大隊:原田竹太郎大尉

所在地:大阪 通称号/略称:天鷲 所属軍:第15方面軍・第13方面軍 最終地:関西と中京
昭和19年7月、主として阪神地区の防空のため、第18飛行団を改編して編成され、司令部を大正飛行場に置いた。
防空に関して、主力は第15方面軍の、一部は第13方面軍の指揮を受け、関西と中京地区を担当した。
使用機種:三式戦闘機・四式戦闘機・五式戦闘機
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 北島熊男 少将 |
1944年7月 |
心得 |
| 北島熊男 中将 |
1945年4月 |
- |
参謀長:神崎清大佐 参謀:中本希生少佐 参謀:岡本信人少佐
参謀:野呂正男少佐 高級副官:吉原理郎中佐
最終所属部隊
戦闘部隊
第23飛行団司令部(小牧):二田原憲治郎大佐
飛行第5戦隊(五式戦):山下美明少佐 飛行第55戦隊(三式戦):小林賢二郎少佐
飛行第56戦隊(三式戦):古川治良少佐 飛行第246戦隊(四式戦):石川貫之少佐
飛行場部隊
第47航空地区司令部(小牧):外池弥中佐
第42飛行場大隊(小牧):目沢広吉少佐 第61飛行場大隊(浜松):鹿子木正任大尉
第62飛行場大隊(明野):岩添友次少佐 第143飛行場大隊(伊丹):久保喜栄少佐
第163飛行場大隊(清洲):福本利市少佐 第246飛行場大隊(大正):上野辰之助少佐

所在地:大阪 通称号/略称:天風 所属軍:第16方面軍 最終地:本土
昭和19年7月、主として北九州地区の防空のため、第19飛行団を改編して編成され、司令部を小月飛行場に
置いた。防空に関しては第16方面軍の指揮を受けた。1944年12月頃からは、来襲するB-29に対して体当たりを
行う「回天隊」(参照:震天制空隊)が組織され、迎撃を行った。
使用機種:二式複座戦闘機・三式戦闘機・四式戦闘機・一〇〇式司偵(改造機)
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 古屋健三 少将 |
1944年7月 |
心得 |
| 三好康之 少将 |
1944年9月 |
心得 |
| 土生秀治 少将 |
1945年5月 |
心得 |
参謀長:古川一治大佐 参謀:浜野宗房少佐 参謀:藤林伝吾少佐 高級副官:佐本団治中佐
最終所属部隊
戦闘部隊
飛行第4戦隊(二式複戦):町田久雄少佐 飛行第47戦隊(戦闘):奥田暢少佐
飛行第71戦隊(四式戦):綾部逸雄少佐
飛行場部隊
第51航空地区司令部:大藪直一郎中佐
第4飛行場大隊:福島勲少佐 第64飛行場大隊:
第65飛行場大隊:中尾秋男大尉 第193飛行場大隊:細田政喜大尉
第194飛行場大隊:裏出正雄大尉 第235飛行場大隊:宮本広大尉
第236飛行場大隊:山口留夫大尉 第248飛行場大隊:須鎗哲太少佐
通信関連部隊
第1航空通信司令部:三木勝一大佐
第18航空通信連隊:平山弥市中佐 第19航空通信連隊:野辺田義夫大佐

所在地:南京 通称号/略称:隼魁 所属軍: 最終地:
昭和20年)2月、南中国における作戦担当のため南京で編成され、漢口に司令部を置いた。
当初は広東方面の対上陸航空戦備、同作戦を担うこととなった。1945年5月、第5航空軍が朝鮮進出となり、
第5航空軍が担当していた中支方面三角地帯(上海、南京、杭州)の東西航空戦備も担当となり、
司令部を南京に移した。
使用機種:一式戦闘機・四式戦闘機・九九式襲撃機・九九式双発軽爆撃機・一〇〇式司偵
九八式直接協同偵察機
| 師団長名 |
補職日 |
備考 |
| 吉田喜八郎 中将 |
1945年3月 |
北海道、第10飛行師団長心得、(昭和20年)3月、陸軍中将 |
参謀長:堂薗勝二大佐 参謀:村岡長江中佐 参謀:前川国雄少佐
参謀:小松演少佐 兵器部長:井上静雄中佐
最終所属部隊
戦闘部隊
第1飛行団司令部:原田潔大佐
飛行第25戦隊(一式戦):金沢知彦少佐 飛行第48戦隊(一式戦):鏑木健夫少佐
飛行第85戦隊(四式戦):斎藤藤吾少佐
第2飛行団司令部:松本理教大佐
飛行第6戦隊(襲撃):広田一雄中佐 飛行第9戦隊(戦闘):平家輔少佐
第8飛行団司令部:弘中孫六大佐
飛行第16戦隊(軽爆):佐藤大六少佐 飛行第44戦隊(偵察):沢山義治少佐
飛行第82戦隊(司偵):奥村房夫少佐 飛行第90戦隊(軽爆):鈴木武男少佐
独立飛行第54中隊(直協):岡本良夫少佐
飛行場部隊
第5航空地区司令部:巨勢寛弼中佐 第16航空地区司令部:松本征夫大佐
第26航空地区司令部:清水勗大佐 第50航空地区司令部:光岡均中佐
第56航空地区司令部:飯島宇八大佐
第4飛行場大隊:福島勲少佐 第57飛行場大隊:滝本一正少佐
第58飛行場大隊:大西俊太大尉 第59飛行場大隊:飯島仲秋少佐
第60飛行場大隊:三宅升信少佐 第91飛行場大隊:
第96飛行場大隊:長通豊少佐 第104飛行場大隊:横山達少佐
第105飛行場大隊:城戸君蔵少佐 第106飛行場大隊:国岡完少佐
第129飛行場大隊:住友武寿少佐 第135飛行場大隊:中島藤吉少佐
第168飛行場大隊: 第184飛行場大隊:鈴木秀雄少佐
第186飛行場大隊:長岡英夫少佐 第217飛行場大隊:大高吉治大尉
第218飛行場大隊: 第219飛行場大隊:
第220飛行場大隊:中村進少佐
通信関連部隊
第5航空通信団司令部(南京):桜井徳三郎少将
第4航空通信連隊(南京):岩間行雄中佐 第14航空通信連隊(北京):讃岐武二中佐
第15航空通信連隊(漢口):宮村信幸大佐 第23航空通信連隊(広東):須藤三作中佐
第24航空通信連隊:栗栖信之中佐 第5航空固定通信隊:鷹羽泰治郎少佐
第5航空測量隊:我部俊雄少佐

|
所在地:宮崎 フィリピン 通称号/略称:鸞(らん)
大日本帝国陸軍の空挺部隊。挺進集団は既存の挺進団(挺進連隊・滑空歩兵連隊)などを掌握する師団に
準ずる部隊であり、旧日本軍の空挺部隊としては最大であった。集団としてまとまって運用される
機会は無く、分割されてフィリピンの戦いなどに参加した。
帝国陸軍における挺進集団(第1挺進集団)の軍隊符号はRD(1RD)、通称号(兵団文字符)は鸞(らん)。
編成後、第1挺進集団はさっそくルソン島の防衛に送られることになった。
先に動員されていた第2挺進団はすでにフィリピン方面に進出して、第4航空軍隷下で活動中だった
第1挺進集団長
塚田理喜智 少将(後に中将):1944年11月 - 終戦
第1挺進集団司令部
高級参謀:岡田安治 大佐 参謀:藤田幸次郎 少佐 高級副官:小林朝男 中佐
創設時の隷下部隊
第1挺進団司令部(帥9944):中村勇大佐
挺進第1連隊( ):山田秀男中佐 挺進第2連隊( ):大崎邦男中佐
第2挺進団司令部(威19040):徳永賢治大佐
挺進第3連隊(威9948):白井垣春少佐 挺進第4連隊(鸞9949):斉田治作少佐
第1挺進飛行団司令部( 19150):河島慶吾大佐
第1挺進飛行団通信隊(鸞19151):
挺進飛行第1戦隊(威9947):新原季人中佐 - 3個中隊で、定数は一〇〇式輸送機計27機ほか
挺進飛行第2戦隊(鸞19039):礪田侃少佐 - 同上。
滑空飛行第1戦隊(鸞19052):古林忠一少佐 - 2個中隊で、定数は九七式重爆撃機(曳航用)
計18機、ク8-II グライダー計36機ほか。
第101飛行場中隊( ):岡島大尉
第102飛行場中隊(帥19152): - 挺進飛行戦隊隷下にあった飛行場中隊を基幹に編成。
第103飛行場中隊( ): - 滑空飛行戦隊隷下にあった飛行場中隊の人員資材を基幹に編成。
滑空歩兵第1連隊(鸞19045):※急病のため南方出陣前に多田仁三少佐が着任。
滑空歩兵第2連隊(鸞19046):高屋三郎少佐
第1挺進戦車隊( ):田中賢一大尉 - 戦車中隊と自動車中隊から成る。後に歩兵中隊追加。
第1挺進機関砲隊(鸞19047):鈴木盛一大尉 - 九八式二十粍高射機関砲16門を有する。
第1挺進工兵隊(鸞19048):福本留一少佐 - 2個中隊。
第1挺進通信隊(鸞19044):坂上久義少佐 - 有線中隊と無線中隊から成る。
第1挺進整備隊( ):
 
立川陸軍航空整備学校
熊谷陸軍飛行学校 昭和20年)2月20日 第52航空師団に改編
陸軍航空通信学校 昭和20年)5月3日 - 水戸教導航空通信師団へ改編
下志津陸軍飛行学校 千葉市若松町にあった大日本帝国陸軍の教育機関のひとつである
昭和19年6月20日 - 下志津教導飛行師団に改編
明野陸軍飛行学校 現在の三重県伊勢市小俣町明野にあった大日本帝国陸軍の教育機関のひとつ
昭和19年)6月20日 - 明野教導飛行師団に改編
鉾田陸軍飛行学校 茨城県鹿島郡新宮村にあった大日本帝国陸軍の教育機関(軍学校)のひとつ
昭和19年)6月20日 - 鉾田教導飛行師団に改編
浜松陸軍飛行学校 浜松市にあった大日本帝国陸軍の教育機関
昭和19年)浜松教導飛行師団に改編
白城子陸軍飛行学校 満州白城子にあった大日本帝国陸軍の軍学校(実施学校)のひとつである
昭和19年)5月~6月 - 宇都宮に移転
7月13日 - 廃止され宇都宮教導飛行師団に改編

飛行場大隊
日本陸軍の部隊編制の一つで、航空機の整備・補給や飛行場の警備などの航空部隊の
後方支援を任務とした大隊のことである。
太平洋戦争が始まった1941年には、飛行場大隊は41個に増えていた。
太平洋戦争中も航空戦の激化に対応するために増強が進められ、1943年末には55個大隊、
1944年初めには140個大隊にまで達した。しかしながら、整備要員の養成が追いつかず、
また大隊単位での特定戦隊との提携運用も海上輸送力の関係で困難となったことから
1943年9月に任務の改正が行われ、整備機能が除かれることとなった。
編制
当初の計画では、大隊本部の下に整備中隊2個と警備中隊を置く約650名の編制とされ
第1整備中隊が提携関係にある飛行戦隊の支援を担当し、第2整備中隊はその他の航空部隊に
随時協力することが予定された。しかし、実際には1個の整備中隊しか持たないことが多かった。
警備中隊は歩兵中隊に準ずる編制だったが、初期には、小銃のほか少数の軽機関銃を
持つ程度の軽装備にとどまった。1943年9月以降、飛行場大隊から整備機能が除かれると、
整備中隊は補給中隊と名を変えた。他方、警備中隊は可能な限り武装が強化され、
20mm高射機関砲など若干の対空砲も装備するようになった。
 |
|
|