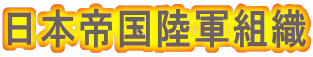陸軍創成期
帝国陸軍の起源は、明治維新後の明治4年に薩摩・長州・土佐から徴集され組織された
|

帝国陸軍建設の祖
大村益次郎 |
| 天皇直属の御親兵である。この兵力を背景にして廃藩置県を断行した。 |
| 御親兵はその後、近衛と改称された。 |
| その時点では士族が将兵の中心であったが、将来は徴兵制による軍備を目標としていた |
| この創成期の帝国陸軍では大村益次郎が兵部省兵部大輔として主に兵制の基礎を |
| 構築し、士族による軍制から徴兵制度による国民兵制への移行を目指した。 |
| 大村が暗殺されるとその後を山縣有朋が承継し、1874年(明治7年)1月に徴兵令を発布し |
| 同年4月に東京鎮台に初の徴兵による兵卒が入営した。 |
| プロイセン陸軍のメッケル参謀少佐が1885年(明治18年)に陸軍大学校教授として |
| 招請され、その助言を受けて1886年(明治19年)に大山巌らによる改革が進められた |
| 明治27年)の日清戦争開戦、明治38年)9月5日日露戦争開戦前に |
| 6月に総軍たる満州軍が編成され、総司令官には大山巌元帥陸軍大将が、 |
|
大日本帝国陸軍
| 大日本帝国陸軍は、1871年(明治4年)から1945年(昭和20年)まで日本(大日本帝国)に存在した陸軍である。 |
| 通称・呼称は日本陸軍・帝国陸軍・陸軍など。第二次世界大戦後の解体以降は「旧」を冠して旧日本陸軍・ |
| 旧帝国陸軍・旧陸軍とも称される。 |
|
|
|
| 概要 |
| 大日本帝国憲法制定前はその位置づけが未だ充分ではない点もあったが、憲法制定後は軍事大権に |
| ついては憲法上内閣から独立し、直接天皇の統帥権に属するものとされた。したがって、陸海軍の |
| 最高指揮官は大元帥たる天皇ただ一人であり、帝国陸軍については陸軍大臣(大臣)・参謀総長(総長)・ |
| 教育総監(総監)が天皇を除く最高位にあり、(直隷)、これらは陸軍三長官と呼称された。なお、三長官には |
| 陸軍大将ないし陸軍中将が任命されるため、役職自体は帝国陸軍の最高位といえど階級自体は |
| 必ずしも最高位の者がなるものではない |
| 三長官の補佐機関として、「省部」や「中央」と総称する陸軍省・参謀本部・教育総監部の3つの官衙(役所)が |
| 設けられており、陸軍大臣(陸軍省)が軍政・人事を、参謀総長(参謀本部)が軍令・作戦・動員を、教育総監 |
| (教育総監部)が教育をそれぞれ掌っていた。また、三機関の序列第2位の次席相当職として |
| 陸軍次官(次官、陸軍省)・参謀次長(次長、参謀本部)・教育総幹部本部長(本部長、教育総幹部)がある。 |
|
|
軍旗
組織
帝国陸軍の組織は、役所である官衙・部隊組織である軍隊・将兵を養成ないし再教育する学校
(実施学校・補充学校)と、これらのいずれにも属さない特務機関とに区分されていた
官衙
陸軍省(陸軍大臣)
参謀本部(参謀総長)
教育総監部(教育総監)
陸軍航空総監部(航空総監) - 第二次大戦末期に軍隊化
防衛総司令部(防衛総司令官) - 第二次大戦末期に軍隊化
・陸軍兵器行政本部(旧陸軍技術本部・陸軍兵器本部)・陸軍技術研究所・
・陸軍造兵廠・陸軍燃料本部・陸軍兵器補給廠・陸軍軍馬補充部・・・・・
・陸軍陸地測量部・陸軍中央気象部・陸軍運輸部・陸軍船舶司令部・・・・
・陸軍航空本部・陸軍航空技術研究所・陸軍航空審査部・陸軍航空工廠・陸軍航空輸送部
・陸軍機甲本部
・陸軍被服本廠・陸軍製絨廠・陸軍需品本廠・陸軍衛生材料本廠・・・・
・憲兵司令部・要塞司令部・連隊区司令部等
軍隊
部隊編制は主に総軍・方面軍・軍・師団・集団・旅団・団およびそれらを構成する連隊(聯隊)や
大隊を中心とする、歩兵部隊並びに砲兵部隊、騎兵部隊、工兵部隊、輜重兵部隊、機甲部隊、
航空部隊、空挺部隊、船舶部隊等の特科部隊からなる。
学校
・教育総監部管轄
・陸軍士官学校・陸軍予科士官学校・陸軍幼年学校・陸軍予備士官学校
・陸軍戸山学校・陸軍歩兵学校・陸軍科学学校・陸軍野戦砲兵学校・陸軍重砲兵・陸軍工兵学校
千葉陸軍高射学校・陸軍輜重兵学校・陸軍習志野学校・陸軍通信学校・陸軍少年通信兵学校
・陸軍省管轄
・陸軍憲兵学校・陸軍経理学校・陸軍軍医学校・陸軍獣医学校・陸軍法務訓練所・陸軍少年戦車兵学校
陸軍兵器学校・陸軍騎兵学校・千葉陸軍戦車学校・四平陸軍戦車学校・陸軍機甲整備学校
・参謀本部管轄
・陸軍大学校・陸軍中野学校
・航空総監部管轄
・陸軍航空士官学校・明野陸軍飛行学校・下志津陸軍飛行学校・浜松陸軍飛行学校
熊谷陸軍飛行学校・太刀洗陸軍飛行学校・白城子陸軍飛行学校・仙台陸軍飛行学校・・・・
特務機関
・元帥府・軍事参議院・侍従武官府・東宮武官・皇族王公族附武官・陸軍将校生徒試験委員
階級
元帥
陸軍大将 |
総軍(支那派遣軍・南方軍・関東軍・第1総軍・第2総軍・航空総軍)総司令官 |
| 大将 |
| 大将・中将 |
方面軍司令官 |
| 中将 |
軍司令官・航空軍司令官・師団長・戦車師団長・飛行師団長・高射師団長 |
| 少将 |
飛行団長 |
挺進集団長・旅団長・歩兵団長 |
| 大佐 |
挺進団長・歩兵連隊長 |
| 中佐 |
砲兵連隊長・騎兵連隊長・工兵連隊長・
輜重兵連隊長・戦車連隊長 |
| 少佐 |
挺進連隊長・滑空歩兵連隊長・捜索連隊長 ・飛行戦隊長・大隊長 |
| 大尉 |
飛行中隊長・独立飛行中隊長・中隊長 |
|
| 中尉 |
飛行小隊長・小隊長 |
| 少慰 |
飛行小隊長・小隊長 |
| 准尉 |
飛行分隊長 |
|
| 曹長 |
|
| 軍曹 |
分隊長 |
| 伍長 |
|
| 兵長 |
|
| 上等兵 |
|
| 一等兵 |
|
| 二等兵 |
|
肩章・襟章
| 将官 |
 |
 |
 |
 |
肩章 |
 |
 |
 |
 |
襟章 |
| 大元帥 |
大将 |
中将 |
少将 |
|
| 佐官 |
 |
 |
 |
|
肩章 |
 |
 |
 |
|
襟章 |
| 大佐 |
中佐 |
少佐 |
|
|
| 尉官 |
 |
 |
 |
 |
肩章 |
 |
 |
 |
 |
襟章 |
| 大尉 |
中尉 |
少尉 |
准尉 |
|
| |
 |
 |
 |
 |
同 |
| |
曹長 |
軍曹 |
伍長 |
兵長 |
|
| |
 |
 |
 |
|
同 |
| |
上等兵 |
一等兵 |
二等兵 |
|
|
肩章:
地質は緋絨(法務官のみ白絨)、縦長の着脱式で、基本的に下士官兵用の官給品は軟芯、将校准士官などの
私物は硬芯。線章・星章は、兵科将校准士官下士は金色金属、各部将校准士官下士相当官は銀色金属。
兵科卒の星章は黄絨、各部卒の星章は白絨
襟章:
階級章は肩章から襟章となる。明治45年制式の肩章をベースに形状のみの変更で、将校准士官は平行四辺形、
下士官兵は長方形(俗称「座布団」。のちには織出品も生産)。大きさは共通の縦18mm、横40mmとされた。
白絨の法務官/法務部将兵を除き、地質は緋絨。将校准士官襟章の星章の造型は昭和5年制式までの肩章で
使われていた立体型から、平型に変更された。1940年には兵長の階級が新設(伍長勤務上等兵は廃止)
されたのに伴い襟章も制定されている。
|
| 陸軍省 |
日本の第二次世界大戦以前の行政官庁各省の中の一つである。
大日本帝国陸軍の軍政機関。主任の大臣は陸軍大臣。
長は陸軍大臣で、陸軍大将または中将の親補職である。
歴代陸軍大臣一覧
| 成立・補職日 |
代 |
陸相 |
階級 |
内閣 |
|
| 明治18年 |
初代 |
大山巌 |
中将 |
第1次伊藤内閣 |
|
| 明治21年 |
2 |
大山巌 |
中将 |
黒田内閣 |
|
|
(以下昭和期) |
|
|
|
| 昭和6年 |
36 |
南次郎 |
大将 |
第2次若槻内閣 |
|
| 昭和7年 |
37.38 |
荒木貞夫 |
中将 |
犬養内閣 |
齋藤内閣 |
| 昭和9年 |
39.4 |
林銑十郎 |
大将 |
岡田内閣 |
|
| 昭和10年 |
41 |
川島義之 |
大将 |
岡田内閣 |
|
| 昭和11年 |
42 |
寺内寿一 |
大将 |
廣田内閣 |
|
| 昭和12年 |
43 |
中村孝太郎 |
中将 |
林内閣 |
|
| 昭和12年 |
44.45 |
杉山元 |
大将 |
第1次近衛内閣 |
|
| 昭和13~14年 |
46.47 |
板垣征四郎 |
中将 |
平沼内閣 |
|
| 昭和14~15年 |
48.49 |
畑俊六 |
大将 |
阿部内閣 |
近衛内閣 |
| 昭和16年 |
50.51.52
|
東條英機 |
大将 |
東條内閣 |
|
| 昭和19年 |
53 |
杉山元 |
元帥 |
小磯内閣 |
|
| 昭和20年 |
54 |
阿南惟幾 |
大将 |
鈴木貫太郎内閣 |
|
| 昭和20年 |
55 |
東久邇宮稔彦王 |
大将 |
東久邇宮内閣 |
|
|
56.57 |
下村定 |
大将 |
東久邇宮内閣.幣原内閣 |
|
歴代陸軍次官 一覧 (開戦後)
| 阿南惟幾中将 |
1939年10月14日 - 1941年4月10日 |
陸軍大臣。終戦後に割腹自刃) |
| 木村兵太郎中将 |
1941年4月10日 - 1943年3月11日 |
(太平洋戦争開戦時の陸軍次官、東京裁判で絞首刑) |
| 富永恭次中将 |
1943年3月11日 - 1944年8月30日 |
・ |
| 柴山兼四郎中将 |
1944年8月30日 - 1945年7月18日 |
・ |
| 若松只一中将 |
1945年7月18日 - 1945年11月1日 |
(在任中終戦。実質上「最後の陸軍次官」) |
| 原守中将 |
1945年11月1日 - 1945年11月30日 |
・ |
| 歴代軍務局長 |
| 山脇正隆 |
昭和13年12月29日 |
| 町尻量基 |
昭和14年1月31日 |
| 武藤章 |
昭和14年9月30日 |
| 佐藤賢了 |
昭和17年4月20日 |
| 真田穣一郎 |
昭和19年12月14日 |
| 吉積正雄 |
昭和20年3月27日 |
|
|
| 歴代人事局長 |
| 阿南惟幾 |
少将 |
昭和12年3月1日 |
| 飯沼守 |
少将 |
昭和13年11月9日 |
| 野田謙吾 |
少将 |
昭和14年10月2日 |
| 富永恭次 |
少将 |
昭和16年4月10日 |
| 富永恭次 |
中将 |
昭和18年3月11日(陸軍次官) |
| 岡田重一 |
少将 |
昭和19年7月28日 |
| 額田坦 |
少将 |
昭和20年2月1日 |
|
|
| 参謀本部 |
参謀本部は大日本帝国陸軍(明治36年までは海軍の軍令を統括した)の軍令を司った機関。
参謀総長(最終的な名称)を長として、作戦計画の立案等を職務とする。
歴代参謀総長(昭和期)
| 代・総長名 |
階級 |
就任 退任 |
次長 名 |
| 12.鈴木荘六 |
大将 |
1926年3月2日-1930年2月19日 |
金谷範三、南次郎、岡本連一郎 |
| 13.金谷範三 |
大将 |
1930年2月19日-1931年12月23日 |
岡本連一郎、二宮治重 |
| 14.閑院宮載仁親王 |
大将 |
1931年12月23日-1940年10月3日 |
二宮治重、真崎甚三郎、植田謙吉、杉山元 |
| 西尾寿造、今井清、多田駿、沢田 茂 |
| 15.杉山元 |
大将 |
1940年10月3日-1944年2月21日 |
沢田茂、塚田攻、田辺盛武、秦彦三郎 |
| 16.東條英機 |
大将 |
1944年2月21日-1944年7月14日 |
後宮淳(第一次長)、河辺虎四郎 |
| 17.梅津美治郎 |
大将 |
1944年7月18日-1945年11月30日 |
河辺虎四郎 |
参謀総長は、陸軍大臣・教育総監と並び「陸軍三長官」と呼ばれた。
廃止時の組織
内部部局
参謀総長(大将又は中将)
参謀次長(中将1名。昭和20年5月まで大本営兵站総監を兼ねた)
・総務部
・部長(中将又は少将。以下部長は全て同じ)
・総務課
・課長(大佐又は中佐。以下課長は全て同じ)
・副官
・庶務班(班長は中佐又は少佐。以下班長は全て同じ)
・電報班 ・主計官 ・軍医官
・教育課(第1課)
・課長:昭和18年3月から教育総監部第1課長の兼務
・第1部
・部長:大本営 兵站総監部参謀長を兼ねる
・作戦課(第2課)
・課長
・作戦班
・戦力班(昭和16年以前は兵站班)
・航空班(大正9年8月新設)
・戦争指導班(第1班。昭和12年12月新設)
・防衛班(昭和18年10月新設)
・編制動員課(第3課)
・課長:昭和20年4月から陸軍省軍務局軍事課長の兼務
・編制班 ・動員班 ・資材班
・第2部
・部長
・ロシア課(第5課)
・課長 ・軍備班 ・兵要地誌班 ・文書諜報班(第10班)
・欧米課(第6課)
・課長 ・米班 ・英班 ・仏班 ・独班 ・地図班 ・戦況班
・支那課(第7課)
・課長 ・支那班 ・兵要地誌班
・謀略課(第8課)
・課長 ・総括班(第4班) ・謀略班(第11班)
・第3部
・部長:大本営運輸通信長官を兼ねる
・鉄道船舶課(第10課。運輸課とも)
・課長
・通信課(第11課)
・課長
・本邦戦史編纂部(昭和17年3月23日支那事変史編纂委員会を改称)
・部長
一時期置かれた部局
この他、明治29年~昭和18年まで第4部が、明治32年から明治41年まで第5部が存在した。
・第4部
・部長
・内国戦史課(昭和11年戦史課へ統合)
・課長
・外国戦史課(昭和11年戦史課へ統合)
・課長
・戦史課(第12課。昭和11年6月5日発足)
・課長
・戦略戦術課(第13課。昭和11年8月新設。課長は戦史課長の兼任が多かった)
・課長
・第5部
・課長
外局
陸軍大学校
| 大日本帝国陸軍に設けられた参謀将校の養成機関、日本海軍には同じく海軍大学校が、現在の |
| 陸上自衛隊では指揮幕僚課程にそれぞれ相当する。 |
| 陸軍大学校は、1883年から1945年まで、今の港区北青山に設置され、参謀将校の育成や軍事研究などを |
| 主任務とした。64年間で3485人の卒業者を送り出した。略称は「陸大(りくだい)」。陸軍士官学校卒業者で、 |
| 隊附2年以上、30歳未満の大尉・中尉にのみ受験が許された。教育期間は通常、歩兵・騎兵が3年、 |
| 砲兵・工兵は2年。陸軍内の諸学校が教育総監部の管轄下に置かれたのに対し、陸大は参謀本部直轄の |
| 教育機関とされ、卒業生の人事も参謀本部が行った。 |
歴代校長
| 40.下村定 中将(1941年9月3日 -) |
|
41.岡部直三郎 中将(1942年10月8日 -) |
| 42.飯村穣 中将(1943年10月29日 -)再 |
|
43.(兼)秦彦三郎 中将(1944年3月22日 -) |
| 44.田中静壱 大将(1944年8月3日 -) |
|
45.賀陽宮恒憲王 中将(1945年3月9日 - |
陸軍中野学校
| 諜報や防諜、宣伝など秘密戦に関する教育や訓練を目的とした大日本帝国陸軍の軍学校 |
| (実施学校)。かつての所在地は東京都中野区中野4丁目付近で、校名の中野は |
| 地名に由来する。通称号は東部第33部隊。特殊勤務要員、後方勤務要員養成所 |
| 昭和15年には「陸軍中野学校」と改名し昭和16年には参謀本部直轄の軍学校へ転身する。 |
| その存在は陸軍内でも極秘とされていた。 |
| 学生は陸軍士官学校、陸軍予備士官学校、陸軍教導学校出身者から選抜された。 |
| 20年1月3日に中野学校に入校した第8期生150名のうち、90%以上は一般大学や高等専門学校の出身者で、 |
| 東京帝国大学出身者が最も多く、次いで拓殖大学、東京外国語大学、そして早稲田大学、慶應義塾大学、等 |
歴代校長
| 北島卓美 少将(1940年8月1日 -) |
|
(兼)田中隆吉 少将(1941年6月28日 -) |
| 川俣雄人 少将(1941年10月15日 -) |
|
山本敏 少将(1945年3月9日 - 閉校) |
陸地測量部
| 日本陸軍参謀本部の外局で国内外の地理、地形などの測量・管理等にあたった、現在の国土地理院の |
| 前身の一つである国家機関。 |
| 発足時には三角・地形・製図の三科及び修技所(後の国土交通大学校の元となる組織。 |
|
|
|
陸地測量部長
| 下田宣力 少将(昭和15年8月1日 -) |
|
小倉尚 少将昭和17年12月2日 - |
| 大前憲三郎 中将(昭和18年10月15日-) |
|
|
陸軍気象部
| 大日本帝国陸軍の機関の一つ。1938年(昭和13年)「陸軍気象部令」によって設置された。関東軍や南方軍等、 |
| 前線部隊に設置された気象部については「気象隊」の項目を参照されたい。 |
| 昭和10年)陸軍砲工学校内に設けられた気象部 |
|
|
|
陸軍気象部長
| 諌武鹿夫 大佐:昭和17年3月20日 - |
|
竹内善次 少将:昭和19年5月16日 - 昭和20年2月19日 |
|
| 教育総監 |
| 教育総監(きょういくそうかん)は、日本陸軍の教育を掌る役職で、その事務は教育総監部が行った。 |
| 陸軍における教育統轄機関であり、所轄学校や陸軍将校の試験、全部隊の教育を掌った。 |
| ただし、航空に関しては航空総監部が教育の大半を行い、参謀の養成は参謀本部が管掌した。 |
| 総監は陸軍中将以上をもって補職した。陸軍大臣・参謀総長と総称して陸軍三長官と呼ばれた。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歴代教育総監 (昭和期)
| 代 . 氏名 |
在職期間 |
|
歴代本部長 |
| 13.武藤信義 |
1927年8月26日 - |
|
川島義之 中将:1932年1月9日 - |
| 14.林銑十郎 |
1932年5月26日 - |
|
香椎浩平 中将:1932年5月26日 - |
| 15.真崎甚三郎 |
1934年1月23日 - |
|
林 桂 中将:1934年3月5日 - |
| 16.渡辺錠太郎 |
1935年7月16日 - |
|
中村孝太郎 中将:1935年12月2日 - |
| 17.西義一 |
1936年3月5日 - |
|
香月清司 中将:1937年3月1日 - |
| 18.杉山元 |
1936年8月1日 - |
|
安藤利吉 中将:1937年8月2日 - |
| 19.寺内寿一 |
1937年2月9日 - |
|
山脇正隆 中将:1938年7月15日 - |
| 20.畑俊六 |
1937年8月26日 - |
|
河辺正三 少将:1939年1月31日 - |
| 21.安藤利吉 |
1938年2月14日 - |
|
今村均 中将:1940年3月9日 - |
| 22.西尾寿造 |
1938年4月30日 - |
|
黒田重徳 中将:1941年7月1日 - |
| 代理 河辺正三 |
1939年9月12日 - |
|
清水規矩 中将:1942年7月1日 - |
| 23.山田乙三 |
1939年10月14日 - |
|
(扱)西原貫治 中将:1943年5月19日 - |
| 24.杉山元 |
1944年7月18日 - |
|
野田謙吾 中将:1943年10月1日 - |
| 代理 野田謙吾 |
1944年7月22日 - |
|
原守 中将:1945年4月7日 - |
| 25.畑俊六 |
1944年11月23日 - |
|
|
| 26.土肥原賢二 |
1945年4月7日 - |
|
|
| 27.下村定 |
1945年8月25日 - |
|
|
教育総監部の組織
| 設置当初の組織は、監軍部と同様に本部のほか騎兵監部・野戦砲兵監部・要塞砲兵監部・工兵監部・ |
| 輜重兵監部を置いた。明治33年3月から本部部長を参謀長と改称。明治40年10月9日野戦砲兵監部を |
| 野砲兵監部に、要塞砲兵監部を重砲兵監部と改称 |
| 明治41年12月参謀長を本部長と改称。本部に庶務・第1・第2の3課を置く。大正8年4月から野砲兵監部と |
| 重砲兵監部は統合され砲兵監部となる。昭和13年7月、本部に部制を採用し、第1部・第2部を置く。 |
| 昭和16年4月化兵監部と通信兵監部が新設。昭和20年)3月から高射兵監部が新設される。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
教育総監
本部部長 → 参謀長(1900.3.)→ 本部長(1908.12.)
第1部(1938.7.)→ 総務部(1941.4.)
第1部長(1938.7.)→ 総務部長(1941.4.)
庶務課(1908.12.)
第1課(1908.12.)
第2課(1908.12.)
第3課(1938.7.)
第2部(1938.7.)→ 廃止(1941.4.)
第2部長(1938.7.)→ 廃止(1941.4.)
第4課(1938.7.)→ 機甲本部(1941.4.)
第5課(1938.7.)→(化兵監部、1941.4.)
第6課(1938.7.)→(通信兵監部、1941.4.)
騎兵監 → 機甲本部(1941.4.)
野戦砲兵監 → 野砲兵監(1907.10.)→ (砲兵監、1919.4.)
要塞砲兵監 → 重砲兵監(1907.10.)→ (砲兵監、1919.4.)
砲兵監(1919.4.)
工兵監
輜重兵監
化兵監(1941.4.)
通信兵監(1941.4.)
高射兵監(1945.3.)
| 本部長 |
|
総務部 |
| 歴代本部長(日中戦争後) |
|
第1部長 |
|
神田正種 少将 |
1938年7月15日 - |
| 河辺正三 少将 |
1939年1月31日 - |
|
小林浅三郎 少将 |
1939年12月1日 - |
| 今村均 中将 |
1940年3月9日 - |
|
岡崎清三郎 少将 |
1940年12月2日 - |
| 黒田重徳 中将 |
1941年7月1日 - |
|
総務部長 |
| 清水規矩 中将 |
1942年7月1日 - |
|
岡崎清三郎 少将 |
1941年4月10日 - |
| 西原貫治 中将 |
1943年5月19日 - |
|
後藤光蔵 少将 |
1941年10月15日 - |
| 野田謙吾 中将 |
1943年10月1日 - |
|
小池龍二 少将 |
1945年2月20日 - |
| 原守 中将 |
1945年4月7日 - 8月22日 |
|
今井一二三 少将 |
1945年4月13日 - |
|
|
|
松村弘 少将 |
1945年8月22日 - |
| 砲兵監部 |
|
管轄学校
陸軍要塞砲兵射撃学校 → 陸軍野戦砲兵学校
現在の千葉県四街道市にあった旧日本陸軍の教育機関のひとつである。
学生の教育分野は甲種、乙種のほか観測、通信、馭法、情報など二十五種以上
陸軍重砲兵射撃学校 → 陸軍重砲兵学校
横須賀市にあった日本陸軍の軍学校(実施学校)のひとつである。
対象は砲兵大尉から砲兵科下士官まで、
陸軍防空学校
千葉市小仲台にあった日本陸軍の教育機関のひとつである。
高射砲術に関する高度な教育を行うための機関
|
| 砲兵監 |
| 井関隆昌 少将 |
1937年8月14日 - |
| 木本益雄 中将 |
1938年6月18日 - |
| 平田健吉 中将 |
1940年8月1日 - |
| 重田徳松 中将 |
1943年3月1日 - |
| 山室宗武 中将 |
1944年7月8日 - |
| 谷口春治 少将 |
1944年8月22日 - |
| 山室宗武 中将 |
1945年3月19日 - |
| 工兵監部 |
|
管轄学校
陸軍工兵学校
千葉県松戸市にあった旧陸軍の学校である
陸軍通信学校 → 通信兵監隷下へ
神奈川県相模原市にあった。
|
| 工兵監 |
| 牛島実常 中将 |
1937年3月1日 - |
| 桑原四郎 少将 |
1938年7月15日 - |
| 林柳三郎 中将 |
1940年8月1日 - |
| 服部暁太郎 中将 |
1942年4月15日 - |
| 河田末三郎 中将 |
1944年3月1日 - |
| (代)吉岡善四郎 少将 |
1944年7月8日 - |
| 岡善四郎 少将 |
1944年11月22日 - |
| 輜重兵監部 |
|
管轄学校
陸軍自動車学校
相模原市にあった日本陸軍の教育機関(軍学校)のひとつである。
憲兵を除く各兵科尉官、下士官学生に機甲車輌の整備に関する教育を実施した。
陸軍自動車学校歴代校長
武内俊二郎 大佐 1937年9月1日 井出鉄蔵 少将 1938年7月15日 -
(再)武内俊二郎 少将 1939年3月9日 -
落合忠吉 少将 1940年10月22日 -
陸軍機甲整備学校
落合忠吉 中将 1941年8月1日 - 細見惟雄 少将 1942年4月1日 -
長沼稔雄 少将 1943年12月27日 -
|
| 輜重兵監 |
| 武内俊二郎 少将 |
1940年10月22日 - |
| 柴山兼四郎 中将 |
1941年10月15日 - |
| 落合忠吉 中将 |
1942年4月1日 - |
| 物部長鉾 中将 |
1944年4月6日 - |
| (扱)中村肇 少将 |
1944年7月8日 - |
| 中村肇 少将 |
1944年11月22日 - |
| 落合忠吉 中将 |
1945年6月16日 - |
| 化兵監部 |
|
管轄学校
陸軍習志野学校
現千葉県習志野市泉町にあった帝国陸軍の化学兵器に関する
教育を行った軍学校の一つである。
新兵器の中には生物兵器・化学兵器も含まれていた。
歴代校長
青木重誠 少将 1941年3月1日 - 白銀義方 少将 1941年12月1日 -
小池龍二 少将 1944年2月7日 - 山崎武四 大佐 1945年2月20日 -
|
| 化兵監 |
| 町尻量基 中将 |
1941年4月10日 - |
| 西原貫治 中将 |
1942年11月10日 - |
| 白銀義方 少将 |
1944年2月7日 - |
| 宮本清一 少将 |
1944年12月11日 - |
| 通信兵監部 |
|
管轄学校
陸軍通信学校
日本陸軍の教育機関のひとつ。現在の神奈川県相模原市にあった。
歴代校長
酒井直次 少将(1940年12月2日 中村誠一 少将(1941年8月25日 -)
石川浩三郎 少将(1944年3月1日 -) 志甫勤一郎 少将(1944年11月22日 -)
陸軍少年通信兵学校
東京府北多摩郡東村山町にあった大日本帝国陸軍の教育機関ひとつである。
本校の目的は、通信関係の現役兵科下士官となる生徒に訓育、学科、術科の
教育を行うことであった。生徒は少年飛行兵召募試験合格者。
|
| 通信兵監 |
| 百武晴吉 中将 |
1941年4月10日 - |
| 川並密 中将 |
1942年12月1日 - |
| 石川浩三郎 中将 |
1944年11月22日 - |
| 川並密 中将 |
1945年3月19日 - |
| 高射兵監部 |
|
管轄学校
千葉陸軍高射学校
現在の千葉市小仲台にあった日本陸軍の教育機関のひとつである。
陸軍防空学校は、高射砲術に関する高度な教育を行うための機関として、
昭和13年4月に四街道の陸軍野戦砲兵学校内に
「陸軍防空学校創立準備室」
が組織され、同年8月に、小仲台において創設された。終戦時の名称は
「千葉陸軍高射学校」とである。通称は防空学校(ぼうくうがっこう)である。
|
| 高射兵監 |
| 武田馨 中将:1945年3月19日 - |
歴代校長
武田馨 少将 1940年12月2日 -
入江莞爾 少将 1942年5月4日 -
伊藤範治 少将 1944年8月22日 -
小池国英 中将 1945年4月1日 -
|
|
| 総監管轄学校 |
陸軍士官学校
| 明治7年)10月の陸軍士官学校条例により、12月市ヶ谷台に陸軍士官学校が開校され、 |
| 明治8年)2月第1期の士官生徒が入校した。いわゆる旧陸軍士官学校、ないしは旧陸士と呼ばれるものである。 |
| 昭和12年)に、陸軍士官学校本科は陸軍士官学校と改称され、陸軍士官学校予科は陸軍予科士官学校となる。 |
| 陸軍士官学校は座間に移転し、昭和天皇から相武台の名が与えられた。 |
| 昭和13年)に陸士本科の修学期間が1年8ヶ月に短縮され、更に1941年(昭和16年)に1年間に短縮される。 |
| なお、これらとは別に1939年(昭和14年)には甲種幹部候補生の教育機関として陸軍予備士官学校が置かれる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
士官学校の実情
| 陸大卒は天保銭組と呼ばれ[3] 、参謀や中央の要職を歴任するが、無天は余程の勲功でもない限り、 |
| その殆どは軍人としての生涯を部隊勤務で終わる。後者の場合は将官に進む割合はかなり低く、大佐から少佐、 |
| 人によっては大尉で予備役になるものもいた。 |
歴代校長
37.牛島満:昭和17年4月1日 38.山室宗武:昭和19年8月8日 39.北野憲造:昭和20年3月19日
|
陸軍予科士官学校
| 明治20年)に陸軍士官学校官制・陸軍幼年学校官制を制定しプロシア式の士官候補生制度が採用され、 |
| 士官候補者となる生徒(将校生徒)を養成する陸軍幼年学校が再設立された。 |
| 陸軍中央幼年学校本科が陸軍士官学校予科に、従来の陸軍士官学校が陸軍士官学校本科となる。 |
| 科の修学期間は4月1日に入校し、2年後の3月に卒業する。予科在学中は「将校生徒」と称し階級の指定はされず、 |
| 卒業時に士官候補生(階級は上等兵)となり、兵科及び原隊の指定がされる。 |
| 昭和12年)、生徒数の増加と広大な演習地確保のため、改正陸軍士官学校令(昭和12年勅令第110号)により |
| 陸軍士官学校本科は陸軍士官学校として市ヶ谷台から神奈川県座間町[2]に移転、同時に航空兵科将校の |
| 養成に特化した陸軍航空士官学校分校が埼玉県所沢町の陸軍所沢飛行場内[3]に設立されることが決まる。 |
| 予科士官学校に在校した生徒は、陸軍幼年学校の卒業生、満16歳から19歳までの採用試験合格者や |
| 同じく試験に合格した下士官などで、1941年から終戦時まで1万5000名もの生徒が学んでいた。 |
|
|
|
|
歴代校長
| 七田一郎 中将:1941年4月10日 - |
|
冨永信政 中将:1942年4月1日 - |
| 牧野四郎 少将:1942年12月22日 - |
|
中沢三夫 中将:1944年3月1日 - |
| 牟田口廉也 予備中将:1945年1月12日 - |
|
|
陸軍予備士官学校
下級将校の不足を補う為に1939年(昭和14年)以降に設置された、中等学校以上で軍事教練を
受け将校適任とみなされた甲種幹部候補生を、予備役将校に任用する為の教育機関である。
陸軍士官学校との違い
| 「陸軍予備士官学校ハ予備役将校ト為スベキ生徒ヲ教育スル所トス」と謳われていた。 |
| 「陸軍士官学校ハ各兵科(憲兵科ヲ除ク)将校及航空兵科将校ト為スベキ学生ヲ教育スル所トス」 |
| 背景には日中戦争の泥沼化など戦局の拡大で、死傷率の高い下級将校を戦時の間だけ一時的に増やす |
| 必要があった。しかし陸軍士官学校出身の現役将校を増員することには限度があり、その代用ともいえる |
| 予備役将校となるべき者の養成が陸軍予備士官学校創設の目的である。卒業者は見習士官を経て |
| 陸軍少尉に任官する点では陸軍士官学校と同じだが、少尉任官と同時に予備役に編入され、 |
| さらに同日招集されて(あくまでも人事の書類上の手続きである)陸軍予備少尉になる点が異なる。 |
| 昭和14年)8月に盛岡(歩兵科)、豊橋(歩兵科及び砲兵科)及び久留米(輜重兵科)に予備士官学校が設立される。 |
| 昭和15年)8月には関東軍幹部候補生隊が改編されて奉天陸軍予備士官学校が置かれる。 |
| 昭和16年)8月には奉天校が久留米第二陸軍予備士官学校となり、旧久留米校は久留米第一陸軍予備士官学校 |
| と改称し、盛岡校が前橋陸軍予備士官学校となる。1943年(昭和18年)8月、熊本陸軍予備士官学校を設置。 |
| 昭和20年)7月、熊本校を移転し津山陸軍予備士官学校と、豊橋第二校を移転し習志野陸軍予備士官学校とした。 |
|
|
各歴代校長
| 仙台陸軍予備士官学校 |
|
| 前橋陸軍予備士官学校 |
| 盛岡陸軍予備士官学校 |
| 阿部平輔 少将:1940年8月1日 - |
| 桜田武 少将:1941年7月13日 - |
| 前橋陸軍予備士官学校 |
| 野副昌徳 少将:1942年7月9日 - |
| 安部孝一 少将:1943年6月10日 - |
| 横田豊一郎 少将:1944年5月19日 - |
| 南部襄吉 予備役中将:1944年7月18日 - |
|
| (兼)高野直満 少将:1940年12月2日 - |
| (兼)岩切秀 少将:1942年8月1日 - |
| (兼)原田棟 大佐:1943年8月2日 - |
| 宮脇幸助 大佐:1945年2月12日 - |
| 豊橋第一陸軍予備士官学校 |
|
久留米第一陸軍予備士官学校 |
| 豊橋陸軍予備士官学校 |
久留米陸軍予備士官学校 |
| 古閑健 少将:1940年8月1日 - |
河根良賢 大佐:1939年8月1日 - |
| 小田健作 少将:1941年9月1日 - |
久留米第一陸軍予備士官学校 |
| 永沢三郎 少将:1943年3月1日 - |
中村次喜蔵 少将:1941年8月1日 - |
| 豊橋第一陸軍予備士官学校 |
人見秀三 少将:1943年3月1日 - |
| 永沢三郎 少将:1943年8月1日 - |
樋口敬七郎 少将:1943年10月29日 - |
| 早渕四郎 予備役中将:1944年7月18日 - |
野副昌徳 中将:1945年4月3日 - |
| 豊橋第二陸軍予備士官学校 |
|
久留米第二陸軍予備士官学校 |
| 豊橋第二陸軍予備士官学校 |
奉天陸軍予備士官学校 |
| 宮崎武之 大佐:1943年8月2日 - |
南部襄吉 少将:1939年8月1日 - |
| 島田恵之助 少将:1944年5月10日 - |
中村次喜蔵 大佐:1940年12月2日 - |
| 習志野陸軍予備士官学校 |
久留米第二陸軍予備士官学校 |
| 島田恵之助 少将:1945年7月 - |
八木節太郎 大佐:1941年8月1日 - |
| |
|
橋本定寿 大佐:1942年9月 - |
| |
|
宮下秀次 大佐:1943年12月15日 - |
陸軍幼年学校
| 幼年時から幹部将校候補を純粋培養するために設けられた陸軍の全寮制の教育機関。 |
| 旧制中学1年から旧制中学2年修了程度に受験資格を与えた。 |
| 明治20年)陸軍士官学校官制、陸軍幼年学校官制が制定され再度設立された。明治22年)6月、陸軍幼年学校 |
| 官制を廃止し陸軍幼年学校条例が制定された。 |
| 東京に陸軍中央幼年学校、東京、仙台、名古屋、大阪、広島、熊本に陸軍地方幼年学校が設立された。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陸軍砲工学校
| 大日本帝国陸軍の教育機関の一つ。明治22年5月に設置され、当初は砲兵科・工兵科将校の専門教育を目的 |
| としたが、昭和14年から憲兵科を除く全兵科将校の入学が可能となった。昭和16年8月陸軍科学学校に改組された。 |
| 昭和16年8月1日を以って陸軍科学学校と改称し、昭和19年10月31日に閉鎖された |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陸軍戸山学校 東京都新宿区
| 東京都新宿区戸山にあった日本陸軍の歩兵戦技(射撃、銃剣術、剣術など)、体育、歩兵部隊の戦術、軍楽の |
| 教官育成とその研究を行う軍学校(実施学校)である。歩兵戦技、体育の教官育成と研究 |
| この学校で、旧日本陸軍の射撃、銃剣術、短剣術、軍刀操法(両手軍刀術・片手軍刀術)などの歩兵戦技が制定 |
| 軍刀操法は居合道流派の戸山流となって、現在は民間団体で稽古されている。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陸軍歩兵学校 千葉県千葉市天台1丁目
歩兵の実施学校としてもっぱら歩兵戦闘法及研究とその普及に任じ軍練成上きわめて重要な使命を
遂行する陸軍の教育機関だった。通称は歩兵学校(ほへいがっこう)である。
|
| 兵科部 |
兵科部 (大日本帝国陸軍)
| 兵科、狭義には、陸軍・海軍軍人に割り当てられた職務区分のうち、主に直接的な戦闘を担当する職務区分。 |
| 広義には、直接的な戦闘を担当する戦闘職務以外の後方職務(各部と呼称されることが多い。)をも含んで |
| 用いられることや、戦闘を担当する職務以外を含めて細分化された特技職(兵種と呼称されることが多い。) |
| を指すこともある。そのため、単に「兵科」といっても多様な用いられ方をする。 |
| 大日本帝国陸軍では、当初は様々な兵科区分が置かれる。明治7年11月8日に改定された |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.参謀科
| 参謀とは、軍隊などの軍事組織において高級指揮官の幕僚として、作戦・用兵などに関して計画・指導にあたる将校の役職。 |
| 旧日本海軍では、軍令部総長が長を務める軍令部を筆頭に、部隊では参謀部は艦隊や戦隊などに設置された。 |
旧日本陸軍では、参謀総長(陸軍三長官)が長を務める参謀本部を筆頭に、部隊では参謀部は旅団以上に設置された
| 種類 |
人事・行政(参謀) |
情報(参謀) |
作戦(参謀) |
後方(参謀) |
|
計画(参謀) |
通信(参謀) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.憲兵
| 憲兵(けんぺい)とは、大日本帝国陸軍において陸軍大臣の管轄に属し、主として軍事警察を掌り、 |
| 兼て行政警察、司法警察も掌る兵科区分の一種。 |
配置編制
| 全国の憲兵の頂点に憲兵司令官が置かれた。憲兵の部隊は、一般の部隊のように連隊・大隊・中隊・小隊の |
| 編制を採らず、各地に配置される憲兵隊が基本単位となっていた。憲兵隊の下に、警察署に相当する憲兵分隊 |
| (分隊と呼称されるが数十名の人員が居る)があり、憲兵分隊の下に憲兵分遣隊がある。 |
歴代憲兵司令官
| 28.豊島房太郎 中将:1940年8月1日 - |
|
29.田中静壱 中将:1940年9月28日 - |
| 30.中村明人 中将:1941年10月15日 - |
|
31.加藤泊治郎 少将:1943年1月4日 - |
| 32.大木繁 中将:1943年8月26日 - |
|
33.大城戸三治 中将:1944年10月14日 - |
| 34.飯村穣 中将:1945年8月20日 - 1945年11月1日 |
|
|
3.騎兵
| 兵種の一つで、馬に乗って戦う兵士である。 |
| 騎兵は乗馬移動による相対的に高い機動力・衝撃力を誇り、戦術的に重要な兵種と考えられてきた。 |
| 戦場で戦うことの出来る軍馬を用いる騎兵は一般に歩兵と比較して高コストである。 |
| 日本による騎兵は鎌倉時代より始まるが、明治以後では「日本騎兵の父」と呼ばれた”秋山好古”が有名で |
| 日露戦争においては、馬格で劣る日本馬で、機関銃の装備など、当時世界最強と謳われたロシアの |
| コサック騎兵に勝つため、数々の工夫をなした。昭和16年)には、歩兵科の流れを汲む戦車兵と統合されて |
| 機甲兵となり、兵種としての騎兵は消滅した。騎兵の多くは、西竹一に代表されるように戦車部隊の |
| 要員となっていった。もっとも、機甲兵となってからも、主に中国戦線での運用を目的として少数の乗馬騎兵が存続した。 |
| 少数の乗馬騎兵が存続した。 |
|
|
|
|
|
|
4.砲兵
陸上戦闘を行う兵科の1つであり、火砲による支援攻撃を担っている。
5.工兵
| 陸軍における戦闘支援兵科の一種であり、歩兵、砲兵、騎兵に並ぶ四大兵科の一つである。 |
| 戦闘においては実際に戦う歩兵・戦車・砲兵部隊だけでなく、土木建築などの技術に特化した部隊が求められる。 |
| 敵の防禦陣地や自然障礙の破壊、野戦築城や道路の建設、爆破工作、塹壕掘り、地雷原敷設などの能力を持つ。 |
| 通常、各師団は、400 人から1,000人程度で編成される工兵大隊または工兵連隊などの工兵部隊を保有している。 |
| 旅団や連隊が各自の工兵中隊を持っていることもある。師団に属する工兵部隊のように敵の攻撃に晒されながら |
| 爆破・建設などの作業を行うものを戦闘工兵、後方における架橋・兵站整備などを任務とするものは建設工兵と呼ぶ。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.輜重兵
| 輜重兵(しちょうへい)とは、兵站を主に担当する日本陸軍の後方支援兵科の一種。 |
| 戦闘行動の上で兵站業務は極めて重要であり、輜重兵とはこの兵站業務を専門とする兵士である。 |
| 水食料・武器弾薬・各種資材など様々な物資を第一線部隊に輸送して、同部隊の戦闘力を |
| 維持増進することが主任務であり、貨物自動車(トラック)などの大型車両を保有するが、武装は自衛に |
| 限定されるため比較的軽装備である。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
各部
定色
日本陸軍では、兵科部毎に定められた色を「定色」という。
| 兵科 |
歩兵 - 兵科色は血を表す緋色。 |
| 騎兵 - 兵科色は大地の植物を表す萌黄色 |
| 砲兵 - 兵科色は火薬の煙を表す山吹色 |
| 工兵 - 兵科色は土を表す鳶色 |
| 輜重兵 - 兵科色は藍色 |
| 憲兵 - 兵科色は何ものにも染まらない黒色。 |
| 航空兵 - 兵科色は大空を表す淡紺青色 |
| 各部 |
技術部 - 定色は山吹色 |
| 法務部 - 定色は白色 |
| 経理部 - 定色は銀茶色(薄紫色)。 |
| 軍楽部 - 定色は紺青色。 |
| 衛生部 - 定色は深緑色。 |
| 獣医部 - 定色は紫色。 |
兵力
| 開戦時だと日本陸軍212万(師団×51、独立混成師団×21、国境警備隊×13、飛行集団×4、留守師団×11) |
| 米陸軍170万3千(歩兵師団×27、機甲師団×2、騎兵師団×2)ですから、1:0.8です。 |
| 日本陸軍兵力のピークは45年で595万(軍属込みで640万。『近代戦争史概説 資料集』より)に対し、 |
| 米陸軍は45年3月末の時点で829万1336 |
| 大東亜戦争(開戦当初) |
| 陸軍総兵力(万人) |
日 : 210万 |
|
米 : 152万 |
| 航空機(百機) |
日 : 48 機 |
|
米 : 122 機 |
| <兵員の比較> |
| 日本 陸軍290万人 海軍 68万人 |
|
米国 陸軍699万人 海軍221万人 |
| <航空機の比較> |
| 日本 陸軍 2,000機 海軍 7,100機 |
|
米国 陸軍45,900機 海軍20,000機 |
| <軍艦の比較> |
| 日本 1,400,000t |
|
米国 2,800,000t |
|
| 外局等 |
陸軍築城部
明治30年9月15日設置。永田町1丁目1番地、皇居お堀端の今の最高裁判所の位置にあつた。
陸軍兵器廠
明治30年9月15日設置。昭和15年4月1日陸軍兵器本部に改編統合。
兵器・弾薬・機材などの補給、要塞の備砲工事を担当した。
陸軍運輸部
明治37年4月1日設置、陸軍の船舶および鉄道輸送を担当した。
| 運輸部長 |
| 上月良夫 中将:1940年3月9日 - ※兼第1船舶輸送司令官(- 1940年6月8日)・兼船舶輸送司令官 |
| 佐伯文郎 少将:1940年9月28日 - ※兼船舶輸送司令官(- 1942年7月9日)・兼船舶司令官 |
| 鈴木宗作 中将:1943年4月8日 - ※兼船舶司令官 |
| 佐伯文郎 中将:1944年7月28日 - ※兼船舶司令官 |
陸軍航空本部
大正4年1月30日設置の陸軍航空部が前身。大正14年4月28日改編
| 航空本部長 |
| 東久邇宮稔彦王 中将:1937年8月2日 - |
| (以下、1938年6月18日から1945年4月18日まで陸軍航空総監が本部長を兼任。) |
| 寺本熊市 中将:1945年4月18日 - 8月15日 |
| (兼)河辺正三 大将:1945年8月16日 - 11月30日 |
| 歴代本部次長(航空総監部次長兼任) |
| 菅原道大 中将:1944年3月27日 - 7月18日 |
| 河辺虎四郎 中将:1944年8月8日 - 1945年4月7日 |
陸軍造兵廠
| りくぐんぞうへいしょう)は、大日本帝国陸軍の機関の一つ。 |
| (大正12年)3月29日に創設された[1]。小銃・弾薬・火砲等の製造から馬具や軍刀に至るまで、 |
| 国内4箇所の工廠と2箇所の兵器製造所に於いて製造にあたった。 |
| 第8代長官小須田勝造中将の時に、陸軍兵器廠に統合された |
| 今までの工廠にあたる格で東京第一・東京第二・相模・名古屋・大阪・仁川・南満に置かれた。 |
| 東京第一の場合、正式には「東京第一陸軍造兵廠」と称した。 |
| 歴代長官 |
| 永持源次 中将:1936年(昭和11年)8月1日 - |
| 小須田勝造 中将:1938年(昭和13年)12月10日 - 1940年(昭和15年)4月1日(陸軍兵器廠に統合) |
| 陸軍造兵廠東京工廠(東京第1陸軍造兵廠) |
|
・精器製造所 ・銃砲製造所 ・火具製造所 |
| 陸軍造兵廠火工廠(東京第2陸軍造兵廠) |
|
・岩鼻製造所 ・忠海製造所 ・曽根製造所 ・板橋製造所 ・宇治製造所 |
| 陸軍造兵廠名古屋工廠(名古屋陸軍造兵廠) |
|
・鳥居松製造所 ・熱田製造所 ・高蔵製造所 ・立川製造所 |
| 陸軍造兵廠大阪工廠(大阪陸軍造兵廠) |
|
・大阪工廠研究所 ・弾丸製造所 ,・管製造所 ・鉄材製造所 ・火薬製造所
・火砲製造所 ・播磨製造所
|
| 陸軍造兵廠小倉工廠(小倉陸軍造兵廠) |
|
・砲弾製造所 ・砲具製造所 ・平壌製造所 |
| 陸軍造兵廠南満工廠(南満陸軍造兵廠) |
船舶司令部
| 大日本帝国陸軍の部隊の一つ。戦時における陸軍の船舶輸送を担当した。司令部が統括した船舶部隊は |
| 通称「暁部隊」と呼ばれた。昭和17年7月、船舶輸送司令部を軍司令部と同格の組織である船舶司令部 |
| に改編した。また、船舶部隊の改編も行われ、第1船舶輸送司令部(大本営直轄船舶の輸送 |
| 内地・台湾・朝鮮方面)、第2船舶輸送司令部(中国方面の輸送)、第3船舶輸送司令部(南方方面の輸送) |
| を編成し、さらに上陸作戦部隊を統一した組織として船舶兵団を新設した。 |
陸軍兵器本部
日本陸軍の兵器製造と補給を統括する機関で、陸軍省の外局である。
昭和15年)4月1日、陸軍兵器廠と陸軍造兵廠を統合し新組織の陸軍兵器廠とした。
| 歴代本部長 |
所属組織 |
| 斎藤弥平太 中将:1940年4月1日 - |
次長 |
| 小須田勝造 中将:1942年7月1日 - 10月15日 |
小須田勝造 中将:1940年4月1日 - 1942年7月1日 |
|
企画部長 |
| 東京第1陸軍造兵廠 |
長野祐一郎 少将:1940年4月1日 - |
第1製造所 第2製造所
第3製造所 東京第1造兵廠研究所 |
酒井康 中将:1941年3月1日 - |
| 東京第2陸軍造兵廠 |
総務部長 |
板橋製造所 宇治製造所
東京第2造兵廠研究所
|
伴健雄 少将:1940年4月1日 - 国武三千雄 少将:1941年3月1日 -
国武三千雄 少将:1941年3月1日 -
|
| 相模陸軍造兵廠 |
作業部長 |
| 第1製造所 |
長谷川治良 少将:1940年4月1日 - |
| 名古屋陸軍造兵廠 |
補給部長 |
| 鳥居松製造所 |
吉田嘉猷 少将:1940年4月1日 - |
| 大阪陸軍造兵廠 |
技術部長 |
第1製造所 第4製造所 播磨製造所
枚方製造所 |
相馬癸八郎 少将:1940年4月1日 - |
| 会計部長 |
| 小倉陸軍造兵廠 |
前川敬悦 少将:1940年4月1日 - |
| 第1製造所 |
|
| 仁川陸軍造兵廠 |
|
名古屋陸軍兵器補給廠 |
|
広島陸軍兵器補給廠 |
|
南満陸軍兵器補給廠(奉天) |
| 南満陸軍造兵廠(奉天) |
|
小倉陸軍兵器補給廠 |
|
大阪陸軍兵器補給廠 |
|
台湾陸軍兵器補給廠(台北) |
| 東京陸軍兵器補給廠 |
|
千葉陸軍兵器補給廠 |
|
岡山陸軍兵器補給廠 |
|
平壌陸軍兵器補給廠 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陸軍兵器行政本部
| 日本陸軍の兵器について、製造・補給、研究開発・試験、教育を一元的に統括する機関で、陸軍省の外局 |
| 陸軍省兵器局、陸軍技術本部の総務部・第1部から第3部、陸軍兵器本部を統合し、陸軍兵器行政本部を新設 |
| 陸軍兵器学校を隷下とし、さらに、陸軍兵器廠内の造兵廠・補給廠、技術本部内の第1から第9研究所を |
| 独立させ兵器行政本部長の直属とした。本部長は陸軍大臣に隷した。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 歴代本部長 |
所属組織 |
| 小須田勝造 中将:1942年10月15日 - |
総務部長 |
| (兼)木村兵太郎 中将:1943年3月11日 - |
菅晴次 中将:1942年10月15日 - |
| 菅晴次 中将:1944年8月30日 - |
伊藤鈴嗣 少将:1944年8月30日 - |
| |
技術部長 |
| |
小池国英 中将:1942年10月15日 - |
| |
本部長事務取扱:1945年4月1日 - |
| 補給部長 |
造兵部長 |
| 平野凞 少将:1942年10月15日 - |
長谷川治良 中将:1942年10月15日 - |
| 権藤恕 少将:1945年5月23日 - |
武田信男 少将:1943年12月27日 - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陸軍兵器学校
現在の神奈川県相模原市にあった日本陸軍の教育機関のひとつである。
昭和15年)8月1日、工科学校21期生の時代に陸軍兵器学校に改称され、7期生の時代に終戦を迎える。
兵器学校長
椎名正健 少将:1940年8月1日 - 宮川清三 少将:1941年7月13日 -
永野叢人 少将:1942年12月1日 - 辻演武 少将:1945年1月20日 - 閉校
陸軍燃料本部 軍馬補充部
昭和19年3月11日設置。
陸軍陸運部 陸軍恤兵部
昭和20年6月16日設置 長は恤兵監で人事局恩賞課長の兼務。出征兵士への慰問に関する業務。
|
| 陸軍航空総監部 |
航空総監は陸軍航空部隊の教育を掌り、航空関連軍学校を管轄した。
航空総監部の幹部は何れも陸軍航空本部の幹部を兼務した。
昭和20年4月本土決戦に備え隷下学校を部隊に改編した事に伴い航空総監部も航空総軍に改編された。
航空総監部の組織
| 航空総監 航空本部長を兼任 |
航空総監部次長 |
| 東條英機 中将 |
昭和13年6月18日 - 昭和15年7月22日 |
|
| 山下奉文 中将 |
昭和15年7月22日 - 昭和16年6月9日 |
菅原道大 中将 |
| 鈴木率道 中将 |
昭和15年12月10日 - 昭和16年6月9日 代理 |
河辺虎四郎 中将 |
| 土肥原賢二 大将 |
昭和16年6月9日 - 昭和18年5月1日 |
|
| 安田武雄 中将 |
昭和18年5月1日 - 昭和19年3月28日 |
|
| 後宮 淳大将 |
昭和19年3月28日 - 昭和19年7月18日 |
|
| 菅原道大中将 |
昭和19年7月18日 - 昭和19年12月26日 |
|
| 阿南惟幾 大将 |
昭和19年12月26日 - 昭和20年4月7日 |
|
| 寺本熊市中将 |
昭和20年4月7日 - 昭和20年4月18日 代理 |
|
| 航空総監部総務部長 |
|
航空総監部教育部長 |
| 鈴木率道 少将 |
昭和13年12月10日 - |
|
安倍定 少将 |
昭和13年12月10日 - |
| 河辺虎四郎 中将 |
昭和16年12月1日 - |
|
鈴木率道 中将 |
昭和15年3月4日 - |
| 遠藤三郎 中将 |
昭和18年5月1日 - |
|
寺田済一 少将 |
昭和15年12月3日 -昭和18年5月 |
| 橋本秀信 少将 |
昭和18年11月1日 - |
|
|
|
| 寺田済一 少将 |
昭和19年3月12日 - |
|
|
|
| 河辺虎四郎 中将 |
昭和19年8月30日 - |
|
|
|
| 田副登 中将 |
昭和19年12月26日 - |
|
|
|
管下学校
陸軍航空士官学校
昭和12年10月設置の陸軍士官学校分校が前身で、昭和13年12月に設置された。昭和期に存在した
日本陸軍の航空兵科、現役将校を養成する教育機関(軍学校)である。
陸軍航空士官学校を卒業し、航空兵科将校となった者は陸軍航空士官学校を卒業し、
航空兵科将校となった者は士官候補生出身者約4200名と、少尉候補学生出身者約2000名の計約6200名である
| 歴代校長 |
| 寺倉正三 少将:1939年7月1日 - |
|
木下敏 中将:1941年9月15日 - |
| 遠藤三郎 中将:1942年12月22日 - |
|
菅原道大 中将:1943年5月1日 - |
| 徳川好敏 中将:1944年3月28日 - |
|
|
東京陸軍航空学校
| 昭和12年10月創立。昭和18年陸軍少年飛行兵学校と大津陸軍少年飛行兵学校に分離。 |
| 本校の目的は、14歳から16歳の生徒に少年飛行兵となるため一年間の教育を行うことであった。 |
| その後、操縦の実技訓練は熊谷陸軍飛行学校で、技術の訓練は陸軍航空技術学校で実施した。 |
| 通信はのちに水戸陸軍飛行学校で教育されることとなった。 |
| 生徒数の増加に伴い、1942年10月、大津分校を設置した。その後も生徒数は増加したため、 |
| 1943年4月、大津校を大津陸軍少年飛行兵学校として独立させ、同月、校名を陸軍少年飛行兵学校と改名。 |
| 同年10月に大分教育隊を設置し、1944年5月、大分陸軍少年飛行兵学校に昇格させた。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 歴代校長 |
| 東京陸軍航空学校 |
|
陸軍少年飛行兵学校 |
| 河原利明 少将:1939年8月1日 - |
|
高田利貞 少将:1943年4月15日 - |
| 高橋常吉 少将:1940年12月2日 - |
|
坂井武 大佐:1944年7月14日 - |
| 三木吉之助 大佐:1941年10月15日 - 1943年4月15日 |
|
戸田剛 中佐:1945年6月1日 - |
下志津陸軍飛行学校
大正13年5月陸軍航空学校下志津分校が独立したもの。昭和19年6月下志津教導飛行師団に改編。
千葉県千葉市若葉区若松町
歴代校長
| 菅原道大 中将:1939年12月1日 - |
|
下野一霍 少将:1940年8月1日 - |
| 秋山豊次 少将:1942年4月1日 - |
|
白銀重二 少将:1943年9月20日 - |
| 服部武士 少将:1944年2月9日 - |
|
片倉衷 少将:1944年12月26日 - |
| 古屋健三 少将:1945年4月15日 -1945年7月16日 |
|
|
明野陸軍飛行学校 三重県伊勢市小俣町明野
大正13年5月陸軍航空学校明野分校が独立したもの。昭和19年6月明野教導飛行師団に改編。
歴代校長
| 小畑英良 少将:1938年7月15日 - |
|
今川一策 少将:1945年3月1日 - |
| 板花義一 少将:1940年9月24日 - |
|
青木武三 少将:1945年5月16日 - |
| 青木武三 大佐:1942年12月1日 - |
|
服部武士 少将:1944年2月9日 - |
| 今川一策 大佐:1944年10月12日 - |
|
松村黄次郎 大佐:1945年7月18日 - |
浜松陸軍飛行学校 静岡県浜松市西区西山町(航空自衛隊浜松基地)
昭和8年8月飛行第7連隊練習部を基幹に創設。昭和19年6月浜松教導飛行師団と三方原教導飛行団に改編。
歴代校長
| 寺本熊市 少将:1939年8月1日 - |
|
山本健児 少将:1943年1月29日 - |
| 儀峨徹二 中将:1940年8月1日 - |
|
川上清志 少将:1944年6月10日 - |
| 須藤栄之助 少将:1941年10月15日 - |
|
星駒太郎 少将:1944年11月27日 -1945年8月6日 |
熊谷陸軍飛行学校 埼玉県熊谷市拾六間(航空自衛隊熊谷基地)
昭和10年8月開校。太刀洗・白城子・宇都宮の各飛行学校は本校から分離独立した。昭和20年2月第52航空師団へ改編。
歴代校長
| 岩下新太郎 少将:1938年12月10日 - |
|
平田勝治 少将:1943年12月11日 - |
| 本郷義夫 少将:1940年12月2日 - |
|
加藤敏雄 少将:1944年10月21日 -1945年2月20日 |
| 松岡勝蔵 少将:1943年6月10日 - |
|
|
太刀洗陸軍飛行学校 福岡県三井郡大刀洗村
昭和14年7月に熊谷陸軍飛行学校から独立。昭和20年2月第51航空師団へ吸収改編
昭和18年4月創設。昭和20年4月第4航空教育団へ改編。
歴代校長
| 松岡勝蔵 少将:1940年10月1日 - |
|
小沢武夫 少将:1944年6月20日 - |
| 近藤兼利 少将:1943年6月10日 - |
|
下田竜栄門 少将:1944年12月1日 - 1945年2月20日 |
白城子陸軍飛行学校 満州白城子 宇都宮に移転
昭和14年7月に熊谷陸軍飛行学校から独立。昭和19年6月宇都宮に移転し宇都宮教導飛行師団に改編。
歴代校長
| 宝蔵寺久雄 少将:1939年7月1日 - |
|
山瀬昌雄 少将:1942年2月20日 - |
| 安倍定 少将:1940年3月5日 - |
|
小沢武夫 少将:1943年9月11日 - 1944年6月13日 |
| 原田宇一郎 少将:1941年7月17日 - |
|
/ |
宇都宮陸軍飛行学校
昭和15年7月に熊谷陸軍飛行学校から独立、昭和19年10月10日熊谷陸軍飛行学校に編入され同校分校になる。
歴代校長
| 尾関一郎 少将:1940年10月1日 - 1943年3月1日 |
|
加藤敏雄 大佐:1943年3月1日 - 1944年10月21日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岐阜陸軍飛行学校 岐阜県各務原市
歴代校長
| 神谷正男 大佐:1940年8月1日 - |
|
下田竜栄門 少将:1942年6月1日 - |
| 欠:1943年1月3日 - 4月1日廃止 |
|
/ |
鉾田陸軍飛行学校 茨城県鹿島郡新宮村(現:鉾田市)
昭和15年12月開校。昭和19年6月鉾田教導飛行師団へ改編。
歴代校長
| 柴田信一 少将:1940年12月2日 - |
|
今西六郎 少将:1943年10月18日 - |
| 藤塚止戈夫 少将:1942年12月1日 - |
|
高品朋 少将:1945年5月3日 - |
陸軍航空技術学校
昭和10年8月、所沢陸軍飛行学校から機関科が独立して創立。昭和19年10月廃校。
所沢陸軍航空整備学校
昭和13年7月陸軍航空整備学校として創設。昭和18年4月所沢陸軍航空整備学校に改称、昭和20年2月第3航空教育団に改編。
歴代校長
| 中富秀夫 少将:1939年8月1日 - |
|
三上喜三 中将:1943年8月2日 - |
| 加藤尹義 少将:1942年6月1日 - |
|
平田勝治 中将:1944年10月21日 - 1945年2月20日 |
岐阜陸軍航空整備学校 現:航空自衛隊・岐阜基地
昭和18年4月創設。昭和20年4月第4航空教育団へ改編
歴代校長
| 田中誠三 少将:1943年8月2日 - |
|
谷内誠一 大佐:1944年8月1日 - 1945年2月20日 |
陸軍航空通信学校 茨城県東茨城郡吉田村(水戸市)
昭和15年8月開校。昭和20年5月水戸教導航空通信師団へ改編。航空関係通信についての
調査・研究・試験を行うことであった
歴代校長
| 藤田朋 中将:1940年8月1日 - |
|
板花義一 中将:1944年5月10日 - |
| 藤沢繁三 少将:1941年10月15日 - |
|
田中友道 中将:1944年8月8日 - |
| 安達三朗 大佐:1943年8月3日 - |
|
/ |
立川陸軍航空整備学校 東京府立川市
本校の目的は、学生に火器の装備を含む航空兵器の整備・補給に関する教育、整備補給に関する
調査・研究、整備用兵器・資材の研究試験などである。
昭和16年開校。昭和19年6月立川教導航空整備師団に改編。
歴代校長
| 加藤尹義 少将:1943年8月2日 - |
|
山口槌夫 少将:1945年2月20日 - |
| 仁村俊 少将:1944年6月20日 - |
|
・ |
大分陸軍少年飛行兵学校 大分県大分市 駄の原字野中
昭和18年10月東京陸軍少年飛行兵学校大分教育隊として設立し、昭和19年5月に独立する。
歴代校長
| 金岡正忠 大佐:1944年5月15日 - |
|
三宅央 大佐:1945年7月5日 - |
大津陸軍少年飛行兵学校 滋賀県大津市別所
昭和17年10月東京陸軍航空学校大津分校として設置し、昭和18年4月独立。
歴代校長
| 三木吉之助 大佐:1943年4月15日 - |
|
狩野弘 中佐:1945年6月1日 - |
| 簗瀬真琴 少将:1944年3月6日 - |
|
・ |
|
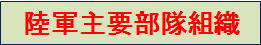 |
| 日中戦争以前に組織された総軍に相当する軍は、日露戦争における満州軍のみであった。 |
| 昭和14年9月12日に支那派遣軍が、昭和16年11月6日には南方軍が編成され、太平洋戦争開戦時には |
| 2つの総軍が存在した。また内地などにあった軍司令部を広域防衛(防空のこと)の見地から指揮する |
| 防衛総司令部がこれに類した。1945年(昭和20年)4月7日には防衛総司令部を廃し、本土決戦を担当する |
|
| 日本陸軍組織単位 |
1.総軍
| 日中戦争以前に組織された総軍に相当する軍は、日露戦争における満州軍のみであった。 |
| 昭和14年)9月12日に支那派遣軍が、1941年(昭和16年)11月6日には南方軍が編成され、 |
| 太平洋戦争開戦時には2つの総軍が存在した。また内地などにあった軍司令部を広域防衛(防空のこと)の見地から |
| 指揮する防衛総司令部がこれに類した。 |
| 昭和20年)4月7日には防衛総司令部を廃し、本土決戦を担当する |
・第1総軍(1SA) ・第2総軍(2SA) ・航空総軍(FSA)
2.方面軍 軍隊符号ではHA
| 大日本帝国陸軍における軍として、日中戦争開戦以前には朝鮮軍・台湾軍・関東軍・支那駐屯軍の4軍があったが、 |
| 方面軍と称するものは置かれたことは無かった。 |
| 昭和12年)7月7日に盧溝橋事件が勃発し、8月31日に支那駐屯軍が第1軍に改編されると共に、華北西部を |
| 作戦地域とする第2軍も設けられ、それらを統括する部隊として編成された北支那方面軍が大日本帝国陸軍における |
| 最初の方面軍である。その後、同年11月7日に中支那方面軍が、昭和15年2月9日には南支那方面軍が置かれたが、 |
| 太平洋戦争開戦以前に廃止され、太平洋戦争開戦時に方面軍と称するものは北支那方面軍のみであった。 |
| しかし戦争の激化と共に方面軍は増設され、終戦時は17個が存在した。また、さらに方面軍より上の、 |
| 最大の陸軍部隊の単位としての総軍も編成された。陸軍大将または中将が司令官として親補された。 |
| 各方面軍と軍の詳細説明参照 |
3.軍 軍隊符号 A
| 大日本帝国陸軍では、軍団という単位が用いられなかったため、軍は師団の上という位置づけであった。 |
| 日中戦争開戦以前の平時の内地における部隊組織は師団のみであり、海外領土の駐留部隊を管轄する単位として |
| 朝鮮軍・台湾軍・関東軍・支那駐屯軍の4軍がおかれていた。有事の際には作戦の都度その作戦に応じた規模の |
| 軍が編成された。これらの軍は、数個の師団およびその他の直轄部隊によって編成されていた。 |
| また、日中戦争開戦後、陸軍の大拡充に伴って多数の軍が設置されたことから、これら軍の上級部隊として |
| 軍集団に近い方面軍が設置された。軍の長は司令官(軍司令官)と称し主に陸軍中将が親補された。軍隊符号はA。 |
| 各方面軍と軍の詳細説明参照 |
4.師団
| 軍隊の部隊単位のひとつ。旅団より大きく、軍団より小さい。師団は、主たる作戦単位であるとともに |
| 地域的または期間的に独立して、一正面の作戦を遂行する能力を保有する最小の戦略単位とされることが多い。 |
| 後方支援部隊などの諸兵科を連合した6,000人から20,000人程度の兵員規模の作戦基本部隊である |
| 各師団の詳細説明参照 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.旅団
| 大日本帝国陸軍では、鎮台時代から戦時には鎮台から旅団を臨時編成して戦地に派遣していた(西南戦争など)。 |
| 後に師団制が採られるに至り、旅団は師団内旅団タイプとして位置づけられるに至った。 |
| この旅団は主に師団に属する歩兵旅団が主流で大半を占める。長は旅団長で少将が就任する。 |
| ただし、師団と異なり参謀長や参謀は置かれず、旅団長の補佐や旅団司令部の実務は旅団副官が行った。 |
| 師団には2個の歩兵旅団が属し、旅団には2個歩兵連隊が属した。 |
| 師団が出動するほどではない場合には砲兵部隊や騎兵部隊、工兵部隊などを配属し混成旅団として派遣した。 |
| 昭和9年に「独立混成旅団」が創設され、支那事変以降は占領地の治安維持を主目的に約100個ほど編成された。 |
| 師団内旅団タイプと独立混成旅団タイプの中間的な旅団も太平洋戦争(大東亜戦争)期には出現した。 |
| 各旅団の下には連隊が存在せずに、多くの独立混成旅団のように独立歩兵大隊から構成される |
| 旅団と連隊の構成等の詳細説明参照 |
6.連隊
| 幕末の江戸幕府による軍制改革の中で、連隊という編制も導入された。幕府陸軍の歩兵隊では、 |
| 2個大隊をもって1個連隊とする建前がとられており、最終的に8個連隊が編成された。 |
| 大日本帝国陸軍では、連隊(聯隊)は鎮台時代から置かれた。1874年(明治7年)1月に近衛歩兵連隊が |
| 編成されたのが最初である。 |
| 以降、各鎮台にも歩兵連隊が編成された。帝国陸軍の連隊はその管轄地域(連隊区)の徴兵によって |
| 充足されたることから「郷土連隊」としての意識が高かった。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
連隊の種類
歩兵連隊 騎兵連隊 捜索連隊 砲兵連隊 野砲兵連隊 山砲兵連隊 重砲兵連隊
野戦重砲兵連隊 工兵連隊 輜重兵連隊 戦車連隊 航空部隊 空挺部隊
7.大隊
陸軍編制上の戦術単位の一つ。連隊の下位で、中隊の上位。通常は、単一の兵科によって編成する。
隊長は中佐か少佐。2から6個程度の中隊から編成される。
8.中隊
軍隊の部隊編成の単位で、小隊の上、大隊の下に位置する。一般的には歩兵なら約200人(4個小隊相当)、
砲兵では4門か6門だが、兵科、装備、時代によって規模はさまざまである。
9.小隊
軍隊の編成において中隊より下位で分隊より上位の部隊。小隊は、概ね2個から4個の分隊
|
| 昭和16年初頭主要兵団配備表 |
| 地域 |
|
軍名 |
師団名 |
混成旅団名 |
独立歩兵団 |
独立守備隊 |
国境守備隊 |
内地
台湾 |
|
東部軍 |
2・51・52 |
(G) |
61・62 |
|
|
| |
中部軍 |
16・54 |
|
63・.64 |
|
|
| |
西部軍 |
55・56 |
|
65・66 |
|
|
| |
北部軍 |
7・57 |
樺 |
67 |
|
|
| |
台湾軍 |
|
|
|
|
|
| 朝鮮 |
|
朝鮮軍 |
19・20 |
|
|
|
|
満州 関
東
軍
|
|
第3軍 |
8・9・12 |
|
|
4 |
1.2.10.11 |
| |
第4軍 |
19・20 |
|
|
8 |
5.6.7.13 |
| |
第5軍 |
11・24・25 |
|
|
6 |
3.4.12 |
| |
第6軍 |
14・23 |
|
|
|
8 |
| |
直属 |
10・28 |
|
|
1.2.3 |
9 |
| |
|
|
|
|
5.7.9 |
|
支那
支
那
派
遺
軍
印度支那 |
北支那方面軍 |
駐蒙軍 |
26 |
2 |
|
|
|
| 第1軍 |
36.37.41 |
3.4.9.16 |
|
|
|
| 第12軍 |
21.32 |
5.6.10 |
|
|
|
| 直属 |
27.35 |
1.7.8 |
|
|
|
|
110 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
第11軍 |
3.4.6.13 |
14.18.20 |
|
|
|
| |
|
33.34.39 |
|
|
|
|
| |
|
40 |
|
|
|
|
| |
第13軍 |
15.17.22 |
11.12.13 |
|
|
|
| |
|
116 |
17 |
|
|
|
| |
南支那
方面軍
印度支那 派遺軍 |
G.18.38 |
19 |
|
|
|
| 48.104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大本営直属 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
| 大戦間の陸軍部隊の配置の推移表 |
| 時期別 |
対ソ連 |
対中国 |
本土 |
対英国 |
対米国 |
総計 |
| 開戦当時 |
満州・朝鮮 |
中国 |
本土・台湾 |
南方進攻 |
・ |
51ケ 師団 |
| 昭和16年12月~ |
14ケ師団27% |
23ケ師団45% |
4ケ師団8% |
10ケ師団 20% |
・ |
・ |
|
76.9万人34% |
61.5万人27% |
51.2万 22% |
39.4万 17% |
・ |
227万人 |
| ガ島反攻の直前 |
17ケ師団27% |
27ケ師団44% |
6ケ師団10% |
ビルマ・マレー |
比島・豪北 |
61ケ師団 |
|
78万 35% |
63万 28% |
40万 18% |
8ケ師団13% |
3ケ師団5% |
249万人 |
| 昭和17年8月 |
航空67中隊 |
航空8中隊 |
航空16中隊 |
航空61中隊 |
・ |
航空152中隊 |
|
44% |
5% |
11% |
40% |
・ |
・ |
|
16ケ師団26% |
24ケ師団39% |
6ケ師団10% |
8ケ師団13% |
7ケ師団12% |
61ケ師団 |
| ガ島撤退直前 |
・ |
・ |
・ |
・ |
+南東方面 |
・ |
|
航空68中隊 |
航空15中隊 |
航空37中隊 |
航空37中隊 |
航空13中隊 |
航空184 |
| 昭和18年1月 |
37% |
8% |
20% |
20% |
7% |
・ |
| 絶対国防圏 |
19ヶ師団26% |
25ヶ師団34% |
8ヶ師団11% |
11ヶ師団15% |
10ヶ師団14% |
73ヶ師団 |
|
航空16ヶ戦隊 |
航空4ヶ戦隊 |
航空11ヶ戦隊 |
航空14ヶ戦隊 |
航空10ヶ戦隊 |
航空60ヶ戦隊 |
| 昭和18年1月 |
29% |
7% |
20% |
25% |
19% |
・ |
| マリアナ海戦当時 |
14ヶ師団16% |
23ヶ師団27% |
12ヶ師団14% |
13ヶ師団15% |
10ヶ師団14% |
86ヶ師団 |
|
・ |
・ |
・ |
・ |
中部太平洋 |
・ |
| 昭和19年6月 |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
| 比島決戦当時 |
8ヶ師団8% |
26ヶ師団26% |
12ヶ師団12% |
14ヶ師団14% |
39ヶ師団40% |
99ヶ師団 |
| 昭和19年10月 |
・ |
・ |
・ |
・ |
台湾・沖縄 |
・ |
|
・ |
・ |
・ |
・ |
南朝鮮・千島 |
・ |
| 沖縄戦 |
8ヶ師団7% |
31ヶ師団25% |
23ヶ師団19% |
15ヶ師団12% |
46ヶ師団37% |
123ヶ師団 |
|
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
|
・ |
・ |
・ |
・ |
上同じ |
・ |
| 終戦当時 |
満州 |
・ |
千島・台湾朝鮮 |
|
台湾・朝鮮 |
173ヶ師団 |
|
22ヶ師団13% |
25ヶ師団14% |
73ヶ師団42% |
14ヶ師団 8% |
39ヶ師団 23% |
|
66.4万 12% |
105万 20% |
288.2万 53% |
玉砕部隊等を含む) |
|
547万人 |
|
・ |
・ |
・ |
82.5万人 15% |
|
・ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和18年末の日本陸軍部隊の概況
| 関東軍 |
第1方面軍(8ヶ師団基幹)第3方面軍(4ヶ師団)他計15ヶ師団 |
| 第2航空軍(2ヶ飛行師団基幹) |
| 支那派遺軍 |
北支那方面軍(9ヶ師団基幹)第11・第13・第23軍他計24同 |
| 第3飛行師団 |
| 南方軍 |
ビルマ方面軍(第15・その他、計7ヶ師団) |
| 第16軍(2ヶ混成旅団)・第25軍 (2ヶ師団)他計12ヶ師団 |
| 第3航空軍(2ヶ飛行師団基幹) |
| 第2方面軍 |
(第2・第19軍他、計4ヶ師団)・・・・・・・・豪北方面 |
| 第8方面軍 |
(第17・第18軍他、計6ヶ師団)・・・・・・・ソロモン・東部ニューギニア |
| 第4飛行師団 |
| 第14軍(1ヶ師団基幹)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 比島 |
| 防衛総司令部・・・・・・・・・・・・ 東部軍・中部軍・西部軍・北方軍他計6ヶ師団 |
| 朝鮮軍 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2ヶ師団基幹) |
| 台湾軍 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (警備部隊・防空隊・補充隊等のみ) |
| 第1航空軍 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (3ヶ飛行師団基幹) |
|
合計 70ヶ師団、9ヶ飛行師団 |
|
陸軍戦闘序列概要(昭和19年後期)
| 大本営 |
|
南方軍寺内寿一 元帥 (マニラ・サイゴン) |
|
|
ビルマ方面軍 (ラングーン) |
|
|
第15軍 |
(第15・31・33 師団) |
|
|
第33軍 |
(第18・56 師団) |
| |
|
第28軍 |
(第2・54・55師団) |
|
|
第2方面軍(セレベス) |
|
|
第2軍 |
(第35・36師団) |
| |
|
第28軍 |
(第5・46・48師団) |
|
|
第7方面軍(シンガポール) |
|
|
第16軍 |
(第27・28独立混成旅団) |
| |
|
第25軍 |
(第2近衛・4師団 |
|
|
第29軍 |
(第94師団・第95独混旅団) |
|
|
第14方面軍 (マニラ) |
|
|
第35軍 |
(第16・30・100・102師団、第54独混旅団) |
|
|
直轄 |
第1・8・10・19・23・26・103・105師団、第2戦車師団 |
|
|
|
第55・58・61独立混成旅団・第68旅団 |
|
|
第18軍 (北部ニューギニア) |
第20・41・51師団 |
|
|
第37軍 (ボルネオ守備軍) |
第56・71独立混成旅団 |
|
|
第38軍 (インドシナ駐屯軍) |
第21・37師団 |
|
|
第39軍 (タイ国駐屯軍 ) |
第29独立混成旅団 |
|
|
第3航空軍 (シンガポール) |
第5・9飛行師団 |
|
|
第4航空軍 (マニラ) |
第2・4・7飛行師団、第1挺進集団 |
|
支那派遺方面 畑 俊六 元帥のち岡村大将(南京) |
|
|
北支那方面軍 (北京) |
|
|
第1軍 |
(第69・114師団、第3独立混成旅団、第10・14独立歩兵旅団) |
|
|
第12軍 |
(第110・115・117師団、第3戦車師団、第4騎兵旅団) |
|
|
駐蒙軍 |
(第118師団、第2独立混成旅団) |
|
|
直轄 |
(第59・63師団、第1・5・8・9独立混成旅団、第1・2独立歩兵旅団 |
|
|
第6方面軍 (漢口) |
|
|
第11軍 |
(第3・13・34・40・58師団) |
| |
|
第20軍 |
(第27・64・68・116師団) |
|
|
第23軍 |
(第22・104師団、第19・20・23独立混成旅団、第5・7・11・12独立歩兵旅団) |
|
|
直轄 |
第37師団 |
|
|
第13軍(上海) |
(第60・61・65・70師団、第62独立混成旅団、第6独立歩兵旅団 |
|
|
第5航空軍(南京) |
|
|
第5方面軍(北部軍) |
|
|
第27軍 |
(42・91師団、第43・69独立混成旅団、海上旅団) |
|
|
直轄 |
第7師団、第1飛行師団 |
|
|
第8方面軍(ラバウル) |
|
|
第17軍 |
(第6師団、第38独立混成旅団、南海守備隊) |
|
|
直轄 |
第17・38師団、第65旅団、第39・40独立混成旅団 |
|
|
第10方面軍 (台湾) |
|
|
第32軍 |
(第9・24・28・62師団、第44・45・59・60・64独立混成旅団) |
|
|
直轄 |
第12・50・66師団、第8飛行師団 |
|
|
第31軍 (中部太平洋) |
|
|
トラック地区 |
第52師団、第51・52独立混成旅団、 |
|
|
北部マリアナ地区 |
第43師団、第47独立混成旅団 |
|
|
南部マリアナ地区 |
第29師団、第48独立混成旅団 |
|
|
小笠原兵団 |
(109師団) |
|
|
防衛総司令部(本土 |
|
|
第36軍 浦和 |
:第81・93師団、第4戦車師団 |
| |
|
第6航空軍 |
(第10・11・12飛行師団) |
|
|
東部軍 |
(第1・3近衛師団、第72師団) |
| |
|
中部軍 |
第44・84師団) |
|
|
西部軍 |
(第86師団) |
|
関東軍 (満州) |
関東軍 (満州) |
|
|
第1方面軍 |
|
|
第3軍 |
(第111・112・120師団) |
| |
|
第5軍 |
(第11・25師団) |
|
|
直轄 |
第1戦車師団、第1独立戦車旅団 |
|
|
第3方面軍 |
|
|
第4軍 |
(第57師団、第73独立混成旅団) |
| |
|
第6軍 |
(第119師団) |
|
|
直轄 |
第107師団 |
|
|
関東防衛軍 直轄 (第71師団) |
|
|
第2航空軍 |
|
朝鮮軍(のち第17方面軍) |
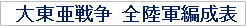
| 支那派遣軍 |
|
開戦期 |
|
中期 |
|
終戦 |
|
開戦期 |
|
中期 |
|
終戦 |
|
北支那方面軍 |
|
北支那方面 |
|
北支那方面 |
|
第1軍 |
|
第1軍 |
|
第1軍 |
|
第12軍 |
|
第12軍 |
|
第12軍 |
|
駐蒙軍 |
|
駐蒙軍 |
|
駐蒙軍 |
|
第11軍 |
|
第11軍 |
|
第11軍 |
|
第13軍 |
|
第13軍 |
|
第13軍 |
|
第23軍 |
|
第23軍 |
|
第23軍 |
|
|
|
第6方面軍 |
|
第6方面軍 |
|
|
|
第5航空軍 |
|
|
|
|
|
第20軍 |
|
第20軍 |
|
|
|
第34軍 |
|
|
|
|
|
|
|
第6軍 |
|
|
|
|
|
第43軍 |
|
|
|
|
|
香港占領地総督 |
| 南方軍 |
|
開戦期 |
|
中期 |
|
終戦 |
|
第15軍 |
|
第15軍 |
|
第15軍 |
|
第25軍 |
|
第25軍 |
|
第25軍 |
|
第16軍 |
|
第16軍 |
|
第16軍 |
|
第14軍 |
|
|
|
|
|
|
|
緬甸方面軍 |
|
緬甸方面軍 |
|
|
|
第28軍 |
|
第28軍 |
|
|
|
第33軍 |
|
第33軍 |
|
|
|
第7方面軍 |
|
第7方面軍 |
|
|
|
第29軍 |
|
第29軍 |
|
|
|
ボルネオ守備軍 |
|
|
|
|
|
第37軍 |
|
第37軍 |
|
|
|
印度支那駐屯軍 |
|
|
|
|
|
泰国駐屯軍 |
|
|
|
|
|
第38軍 |
|
第38軍 |
|
|
|
第39軍 |
|
|
|
|
|
第3航空軍 |
|
第3航空軍 |
|
|
|
|
|
第4航空軍 |
|
|
|
|
|
第35軍 |
|
|
|
|
|
第41軍 |
|
|
|
|
|
第14軍方面軍 |
|
|
|
|
|
第18軍方面軍 |
|
|
|
|
|
第2軍 |
|
|
|
|
|
第18軍 |
|
|
|
|
|
パラオ地区集団 |
| 関東軍 |
|
開戦期 |
|
中期 |
|
終戦 |
|
第3軍 |
|
第3軍 |
|
第3軍 |
|
第4軍 |
|
第4軍 |
|
第4軍 |
|
第5軍 |
|
第5軍 |
|
第5軍 |
|
第6軍 |
|
第6軍 支那派遣軍へ移動 |
|
第20軍 |
|
第20軍 支那派遣軍へ移動 |
|
関東防衛軍 |
|
関東防衛軍 |
|
|
|
航空兵団 |
|
|
|
|
|
|
|
第1方面軍 |
|
第1方面軍 |
|
|
|
第2軍 南方軍へ移動 |
|
|
|
第2方面軍 |
|
|
|
|
|
第3方面軍 |
|
第3方面軍 |
|
|
|
第2航空軍 |
|
|
|
|
|
機甲軍 |
|
|
|
|
|
|
|
第30軍 |
|
|
|
|
|
第44軍 |
|
|
|
|
|
第17方面 |
|
|
|
|
|
第58軍 |
|
|
|
|
|
第34軍 |
|
|
|
| |